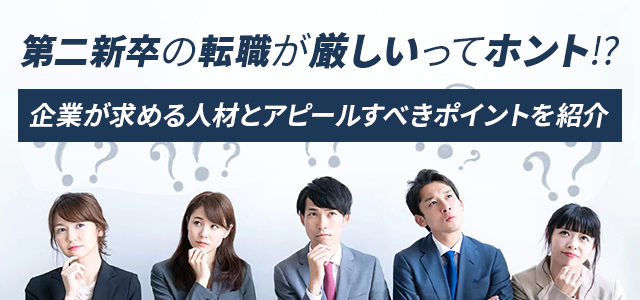転職市場では、第二新卒者に対して「スキルが不十分」「すぐに辞めるのでは」とマイナスなイメージを抱いている企業があります。
そのため、転職したい第二新卒者のなかには「転職に失敗したらどうしよう」と転職できるのか不安に考える方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、下記について解説します。
あまり不安に思わず、積極的に行動してみることを推奨します。 実際の転職活動や情報収集には転職サイトやエージェントの活用が便利なので、ぜひ積極的に使っていきましょう。
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
公開求人数
73.2万件
非公開求人数
30.7万件 |
【初めて転職する方向け】20万件以上の中からピッタリの企業が見つかる。 |
|
★ 4.6
|
非公開 |
【未経験歓迎求人が豊富】大手企業からベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
公開求人数
18.8万件
非公開求人数
非公開 |
【年収500万以上向け】レジュメ登録だけで自分の市場価値がわかる |
|
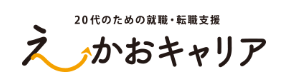 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
非公開求人
多数 |
【入社後の定着率97%】どんな仕事が向いているのか分からない方におすすめ |
|
 doda
doda
★ 4.0
|
公開求人数
26.7万件
非公開求人数
1.8万件 |
【圧倒的な顧客満足度】未経験でチャレンジしたい方におすすめ |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
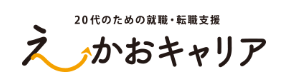 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 doda
doda
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
★ 4.6
|
|
・初めての転職でしたが、マンツーマンでサポートしてくれました。
・未経験でも挑戦できる求人を多く紹介してくれました。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
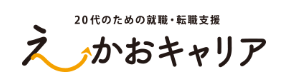 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
|
・自分一人で転職活動をしていたら、なかなか入れない企業への内定が決まりました。
・自分でもびっくりするくらいすぐに内定をもらえました! |
|
 doda doda
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
関連記事:20代転職サイトおすすめ比較ランキング!前半後半や女性向けも解説
関連記事:第二新卒におすすめ転職エージェント22選を徹底比較|失敗しない選び方を解説
第二新卒の転職が難しいといわれる6つの理由
転職活動をおこなう第二新卒者のなかには、選考が順調に進まず気落ちする方もいるのではないでしょうか。
転職市場において、第二新卒者がスムーズに内定を得るのは「難しい」といわれるケースがあり、その理由を把握しておくと何らかの対策が打てるようになります。
ここからは「第二新卒者の転職が難しい」といわれる6つの理由を詳しく説明します。
1.転職先からすぐに辞めると思われる
第二新卒者の転職が難しいといわれる1つ目の理由に「早期で退職する可能性」を企業が不安視する点が挙げられます。
もっとも、第二新卒者には若さや活力といった魅力があるものの前職での経歴が浅いため、採用担当者に「自社でもすぐに辞めるかもしれない」と思われるケースがあります。
なかでも前職を1年たらずで退職している方であれば、仕事における忍耐力を疑われる可能性もあるでしょう。
第二新卒者を採用したところですぐに辞められては、企業が採用にかけた費用や時間、労力が無駄になってしまいます。そのため「すぐに辞めるかも」と思われる第二新卒者は、採用に至りづらい厳しい現実があるのです。
2.実務経験が条件を満たしていないケースがある
第二新卒者の転職が難しい2つ目の理由は「実務経験が企業の採用条件を満たしていない」からです。
第二新卒者の応募窓口となるキャリア採用では、多くの場合「未経験者OK」や「経験者優遇」のように、企業の求める人材がひと目でわかるフレーズが付いています。
もし、前述のような条件であれば、第二新卒者の人柄やスキルに魅力がある限りスムーズな転職が見込めるでしょう。
しかし「経験者優遇」や「○○経験3年以上」と記載されている場合、前職で多少の業務経験があっても「第二新卒者=経験不足」と判断されるケースがあるのです。
実際に、第二新卒者の実務経験が募集要項の年数に達していない場合、応募しても門前払いされる可能性があります。経験の浅い第二新卒者にとって、実務経験を求められる求人では転職活動を難しく感じるかもしれません。
3.ビジネスマナーが不十分の可能性がある
第二新卒者の転職が難しいといわれる3つ目の理由に「ビジネスマナーが不十分」が挙げられます。
社会人である以上、第二新卒者にはビジネスで使う礼儀作法や丁寧な電話応対、誤字脱字のないメール作成といったスキルが求められます。
社会経験が短いとはいえ、ビジネスマナーが身に付いていて当然と考える企業は少なくありません。
もし、採用した第二新卒者に基本マナーが備わっていない場合、企業はビジネスマナーの教育コストを負担する必要が出てくるでしょう。
そこにかかる手間や労力を考慮すると、企業としてはビジネスマナーが不十分な人材の採用を見送るといっても過言ではありません。
採用担当者は、第二新卒者が提出する応募書類の誤字脱字や面接時の対話力、お辞儀や所作といった細部までチェックしています。そのため、ビジネスマナーが不十分な点が見受けられる人物の場合、選考が進みづらいのは仕方がないかもしれません。
4.一般のキャリア採用ではスキル不足になる
第二新卒者の転職が難しい理由の4つ目には「キャリア採用内ではスキルが未熟」が挙げられます。
第二新卒者の応募窓口は「キャリア採用」ですが、ここでは企業の即戦力となる人材を募集しているケースが多いものです。
そのようなスキルの高い人材が溢れるなかで、職歴3年程度の第二新卒者が競うとなれば、圧倒的な経験値と技術力を保有していない限り内定を勝ち取りづらいといえます。
採用担当者からも、第二新卒者というだけで「即戦力にならない」と思われてしまうでしょう。第二新卒者はどうしても他の求職者より劣って見えるため、採用に至らないと考えられます。
5.業界未経験者だと企業側に負担がかかる
第二新卒者の転職が難しいとされる5つ目の理由は「業界未経験だと企業側に負担がかかる」点にあります。
第二新卒者のなかには、未経験業種への転職を希望する方もいるでしょう。
しかし、企業が業界未経験の第二新卒者を採用すると、即戦力としての見込みを断つ以外に、業界の知識をゼロから教え込むための教育コストを負うことになるのです。
そのような状況に対して、メリットを感じられない企業は多いといえます。
採用担当者が「業界経験者を優先したい」と思うのは当然であるため、第二新卒者が未経験業界を希望する場合、転職活動の難航は避けられないと思っておくのがよいかもしれません。
6.求人数が少ない
近年では第二新卒を歓迎する企業が増えているものの、新卒採用や経験者採用に比べると求人数が少ないと感じられるでしょう。新卒採用で人材が充足している、経験者採用ではスキルに長けた即戦力を採用したいなどの事情があって、第二新卒を対象とした採用活動を検討しない企業もあるからです。
企業によっては、第二新卒者に新卒採用枠への応募を認めていたり、若さを評価して経験者採用の対象としていたりします。
応募したい企業がある際は、第二新卒での応募が可能かどうか、募集要項をよく確認し、掲載されていない場合は問い合わせてみるとよいでしょう。
第二新卒に特化した転職エージェントを利用し、第二新卒者が応募できる企業を教えてもらうのもひとつの方法です。
第二新卒を歓迎する企業の特徴は?
- 新卒採用で十分な人材を確保できなかった
- 市場拡大のため、若い人材を獲得したい
株式会社マイナビが新卒採用を実施した企業を対象としておこなった調査によると、採用充足率、つまり募集人数に対する実際の内定者数の割合は、2024年卒で75.8%となっています。すなわち、約25%の企業が「新卒採用で十分な人数の人材を確保できなかった」と感じているようです。
引用元:2024年卒企業新卒内定状況調査|マイナビキャリアリサーチLab
このような企業は若手人材の獲得を必要としており、第二新卒者の採用にも積極的だと考えられます。
また、市場拡大が続いている業界では、長期的に働ける人材の確保・育成が課題のひとつです。具体的には、以下のような業界が該当します。
- IT・Web業界
- EC業界
- Web広告業界
- 電子部品・半導体業界
- 運輸業界
- 医療業界
- Webエンタメ業界
第二新卒に対して企業が期待することとは?
第二新卒者は企業から忍耐力やスキルを不安に思われる一方、期待されている一面があるのも事実です。
ここからは、企業が第二新卒者に期待している点を詳しく紹介していきます。
関連記事:【未経験OK】第二新卒歓迎の求人の探し方・転職成功のコツを解説
向上心をもって自発性な行動がとれる
第二新卒者は年齢こそ新卒と差がないものの、社会経験があるため仕事の学び方を知っています。新卒同等のフレッシュさを備えながら、いち早く業務を習得しようとする前向きな姿勢は、第二新卒者だからこそもっている要素といえるでしょう。
そのような向上心や自発性は企業に新しい風を吹かせる可能性があるため、企業の採用担当者は、第二新卒者の目に見えるやる気と行動力を期待しているといえます。
企業への適応力がある
採用担当者が第二新卒者に期待することには、社風や職場環境に対する適応力が挙げられます。第二新卒者は社会経験が短い点でマイナスにとらえられる一方「前職に染まっていない」と言い換えれば魅力的な人材にもなり得ます。
第二新卒者が応募するキャリア採用では、どんなにスキルが高い人材であっても、企業の雰囲気をつかんで馴染む力がなければ円滑に業務を進められません。
その点、前職のカラーに染まっていない第二新卒者であれば、新しいやり方でも柔軟に取り込めるため、周囲との関係性も築きやすいといえます。
企業への適応力の有無は仕事をするうえで重要なポイントであるため、企業が第二新卒者に期待している可能性が高いでしょう。
教育コストがかからない
たいていの企業は、第二新卒者に対する教育コストの削減を期待しています。前職の内容にもよりますが、第二新卒者であれば「お世話になっております」「今後ともよろしくお願いいたします」といったビジネス上のコミュニケーションスキルを備えているものです。
その他、電話応対や名刺交換といった社会人に求められる最低限のマナーも理解しているといえるでしょう。
このようなマナーの有無は、同年代である新卒との大きな違いでもあり、企業が重視するポイントです。
第二新卒者であれば、入社後、必要な業務指導のみで企業へ馴染めるケースが多いため、採用担当者から教育コストがかからない面で期待されているでしょう。
即戦力になる可能性がある
企業は、第二新卒者が将来的に即戦力として活躍してくれることに期待しています。第二新卒者には、まだ開花していない内に秘めた能力やポテンシャルがあり、その大きさは計り知れません。
スキルや経験値の少なさから転職後すぐにパフォーマンスを発揮するのはできないかもしれませんが、将来的な可能性が評価されて採用に至るケースは多いでしょう。
第二新卒の転職が難しい人に共通する5つの特徴
ここからは、第二新卒の転職が難しい人と、成功する人でそれぞれ共通する特徴について解説します。第二新卒の転職はあなたが思う以上に転職難易度は高い傾向にあります。
第二新卒で納得する企業への転職を成功させるためにも、自分が難しい人に該当するのか確認しましょう。第二新卒の転職が難しい人の特徴は下記のとおりです。
転職理由が明確でない人
というのも、転職する明確な理由がないと面接官が納得できる返答をするのは難しいからです。面接官が納得できる理由を伝えるには、自己分析を行い転職する目的を明確にする必要があります。
自己分析では、自分のスキルや経験、興味関心、価値観、キャリア目標などを客観的に見つめ直し、どんな仕事に転職したいのか明確にします。また、現職を転職する理由の深掘りも重要です。
退職理由と転職理由が明確になれば、面接官からの質問に対して論理的に回答できます。第二新卒の転職で苦労する人は、自己分析が足りていない可能性が考えられます。
自己分析は時間がかかりますが、第二新卒の転職を成功するためには重要なステップです。自分の強みや目標を把握し、転職先とのマッチングや志望動機の説明に活かしましょう。
前職の退職理由がネガティブな人
前職の退職理由がネガティブな人も、第二新卒の転職が難しい人に該当します。その理由は、転職先の企業からの評価や信頼を得ることが難しくなるからです。
前職の退職理由がネガティブな場合でも、その経験をポジティブに捉えることが重要です。企業としては、物事を後ろ向きに考える人より、前向きにとらえる人と働きたいと思うでしょう。転職先への説明や面接での回答においては、前職での学びや成長、新たなチャレンジを求める姿勢をアピールすることが大切です。
たとえば、人間関係のトラブルがあった場合、コミュニケーションや協調性の重要性を学んだと言えます。給与不満や業務の過重負荷があった場合には、自己管理や仕事の効率化の重要性を学んだと言えるでしょう。
前職のネガティブな退職理由をポジティブに捉え、成長や目標達成への意欲をアピールすることは、第二新卒の転職を成功させるために重要な要素です。
ビジネスマナーが欠落している人
ビジネスマナーとは、職場での適切な言動や態度、コミュニケーションスキルなどを指します。ビジネスマナーが欠落している人は、職場での円滑な人間関係の構築や業務遂行において問題が生じる可能性があると考えられるでしょう。
第二新卒の場合、スキルや経験が豊富なわけではないため、ビジネスマナーや熱意といった部分でアピールする必要があります。企業側が第二新卒に求めることは、社会人としての基盤です。つまり、業務の研修にすぐ移れるような、ビジネスマナーです。
そのため、ビジネスマナーが欠落している人は、第二新卒の転職が難しいと言えるでしょう。仮にビジネスマナーが欠落している人は、いままでの行動を振り返り、直す努力をする必要があります。
自身のキャリアの発展や職場での評価を高めるために、ビジネスマナーの重要性を理解し、積極的に取り組んでいきましょう。
人間関係だけがつらい人
転職の面接で退職理由を聞かれたときに、人間関係にトラブルがあったと伝えると「自社で同じことがあったらすぐ辞めるの?」と思われてしまうでしょう。
ただし、人間関係の問題に対策を講じた場合は、高評価に繋がる可能性があります。なぜなら、解決するために行動を起こす力があると判断できるからです。
第二新卒の転職において、人間関係がつらいと感じている人は多くいます。しかし、企業側からすると「転職前にやれることはあるのではないか」と思うはずです。人間関係がつらくて転職したい場合は、やれるだけの対策をしてから検討する必要があります。
たとえば、人事異動で環境を変えたり、考え方や捉え方を変えたりなど、自主的に改善する姿勢が大切です。
社会人として成長するためにも、つらい状況をどうすれば乗り越えられるのか考えることが大事です。人間関係の問題に改善策を行って現状が変わらない場合は、転職へと進めましょう。
仕事内容だけが嫌な人
仕事内容だけが嫌な人も、第二新卒の転職が難しい特徴に該当します。人間関係だけがつらいと同様に、転職前にできる対策がないか考えることが大切です。
たとえば、人事異動でジョブチェンジの提案をすることがあげられます。また、第二新卒は社会人経験が少ないため、仕事内容に慣れていないだけの場合も考えられるでしょう。
改善策を考えるには、現状の不満や嫌悪感の具体的な要素を明確に把握する必要があります。仕事内容が嫌だと思う具体的な要素を洗い出さなくては、同じ状況を繰り返す可能性があります。
さらに、辞め癖がつき短期間で再転職を続けると、企業から「就業する意欲がない」と判断されるため、転職する難易度があがってしまいます。
仕事内容だけが嫌な人は、まず自分でできる対策を実践することが大切です。どうしても嫌だった場合は、理由を明確にしてから転職を進めましょう。
第二新卒の転職活動が成功する人に共通する5つの特徴
続いては、第二新卒の転職が成功する人の特徴についてみていきましょう。共通する特徴は下記のとおりです。
志望企業に入社したい理由が明確にある
志望企業に対する明確な理由を持つことは、転職活動を効果的に進めるうえで重要な要素です。
入社したい明確な理由があると、キャリアビジョンや希望条件に合致する企業を選べます。また、企業から「志望理由を教えてください」といった質問に対して、情熱や意欲を伝えることができ、魅力的な候補者として評価される可能性が高まります。
第二新卒で入社する理由を明確にするには、自己分析やキャリア設計を行うことが必要です。自分の価値観や適性、興味関心を把握し、合致する業界・職種・企業を選ぶことが成功に近づきます。企業の特徴や価値観、事業内容などを調査し、自身のキャリアやスキルにどのように貢献できるかを考えることも大切です。
企業側としても、入社意欲が高い転職者を採用する傾向があるため、入社したい明確な理由を伝えられれば、第二新卒の転職活動を成功させられるでしょう。
将来像のイメージを描けている
なぜなら、企業は入社後の活躍に期待しており、将来像がある人は達成するために努力できると考えられるからです。
たとえば「20代で年収1,000万円稼ぎたい」人と「安定した給与がもらえればいいかな」と考える人がいた場合、企業側からして努力してくれる可能性が高いのはどちらでしょうか。
将来像のイメージを描けている人の方が、入社後に努力してくれると思う企業がほとんどです。将来像のイメージを持つことは、転職を成功させる要素のひとつと言えるでしょう。
ただし、将来像をイメージするときは、転職先で達成できる目標にするのがポイントです。将来像があっても転職先で達成できなければ「他社でよくない?」と思われてしまいます。
第二新卒の転職活動を成功させるには、志望先の企業で達成できる将来像のイメージを描くようにしましょう。
企業が求める人物像を把握している
転職先の企業が求める人物像を把握することは、自身の適性や魅力をアピールするうえで重要な要素です。
企業が求める人物像を把握するには、企業研究が欠かせません。企業のホームページや採用情報、社員インタビューなどを通じて、会社のビジョンや価値観、求める人物像を理解しましょう。また、業界の動向や競合他社の状況も調査し、自分の強みやスキルが企業にとってどのような価値を持つのかを考えることも重要です。
企業が求める人物像に合致する自分の特徴を明確にし、アピールすることで高評価に繋がるでしょう。
また、企業が求める人物像を把握すれば、企業の求める人物像に合致するエピソードや経験を具体的にあげ、自分の魅力や適性をアピールできます。
企業が求める人物像に対する自分の適合度を高めるために、事前の準備や面接の練習等を行いましょう。
前職の経験を活かしている
前職で培ったスキルや経験を転職先で活かすことは、アピールポイントを高めるうえで重要な要素です。
前職の経験を活かすには、これまでのスキルや経験を客観的に評価しましょう。前職で得た知識やスキル、実績などを整理し、強みや専門性を把握することが重要です。また、前職での成功体験やプロジェクトの成果なども振り返り、具体的なエピソードとしてアピールできるように準備します。
前職の経験を活かすには、転職先が求めるスキルや経験を把握するのも重要です。転職先の企業や業界のニーズや課題を理解し、自分の経験がどのように活かせるのか考えましょう。前職での経験を通じて培ったスキルや知識をアピールすれば、自分の価値を高められます。
前職の経験を活かして転職活動をすることは、転職を成功に近づけるための要素のひとつです。企業としても、1から教育をするのと5から教育するのでは、かかるコストが違います。企業側としては、少ないコストで即戦力として活動してもらうことが理想的です。
そのため、前職の経験を活かしている人は、第二新卒の転職で成功しやすいと言えるでしょう。
仕事に対する熱意を持っている
企業側が第二新卒に求めることは、スキルや経験ではなく、仕事に対する熱意です。
第二新卒の中でも、自信が持てるスキルや経験があれば、アピールできる材料となります。しかし、企業は第二新卒の社会人経験が少ないことを理解しています。自信がないスキルや経験をアピールしても、高評価に繋げるのは困難です。第二新卒にしかない仕事への熱量をアピールすることが、転職を成功させるポイントに繋がるでしょう。
仕事に対する熱意を持つには、興味や関心がある領域を明確にし、達成したい将来のビジョンを決めます。自分の興味や関心に基づいて仕事を選べば、やりがいや充実感を見つけられるでしょう。
熱意を持って仕事へ取り組む姿勢は、自己成長やスキルの向上、新たなチャレンジへの積極性を高めます。また、企業側からも仕事に真剣に取り組む姿勢を評価され、求められる人材としての価値が高まるでしょう。
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
公開求人数
73.2万件
非公開求人数
30.7万件 |
【初めて転職する方向け】20万件以上の中からピッタリの企業が見つかる。 |
|
★ 4.6
|
非公開 |
【未経験歓迎求人が豊富】大手企業からベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
公開求人数
18.8万件
非公開求人数
非公開 |
【年収500万以上向け】レジュメ登録だけで自分の市場価値がわかる |
|
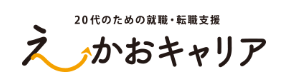 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
非公開求人
多数 |
【入社後の定着率97%】どんな仕事が向いているのか分からない方におすすめ |
|
 doda
doda
★ 4.0
|
公開求人数
26.7万件
非公開求人数
1.8万件 |
【圧倒的な顧客満足度】未経験でチャレンジしたい方におすすめ |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
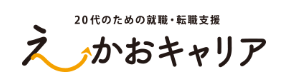 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 doda
doda
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
★ 4.6
|
|
・初めての転職でしたが、マンツーマンでサポートしてくれました。
・未経験でも挑戦できる求人を多く紹介してくれました。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
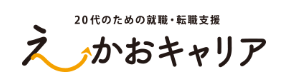 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
|
・自分一人で転職活動をしていたら、なかなか入れない企業への内定が決まりました。
・自分でもびっくりするくらいすぐに内定をもらえました! |
|
 doda doda
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
第二新卒の転職を成功させるためにすべき7つのこと
第二新卒の転職を成功させるためにすべきことは、下記のとおりです。
- 応募企業について研究する
- 徹底的に自己分析する
- 希望条件に優先順位を立てる
- 中長期的なキャリアを明確にしている
- 転職理由をポジティブに置き換える
- 退職理由と志望動機に一貫性を持たせる
- 転職エージェントを利用する
第二新卒で転職を成功させるには、上記の一つひとつが必要です。後悔しない転職活動にするためにも、ぜひ参考にしてください。
応募企業について研究する
応募企業のビジョンや事業内容、文化、価値観などを把握することで、会社理解の深さをアピールできます。
応募企業について研究するには、公式ホームページやWebサイト、採用情報などを活用しましょう。また、企業のニュースや取り組み、社員インタビューなども調査して、最新の動向をチェックすることで、自分が挑戦したい環境があるか否か判断できます。
応募企業の研究は、志望理由を具体的に説明するうえでも役立ちます。企業のビジョンや価値観と自分のスキル・経験・価値観をマッチさせることで、明確な志望理由を作成できるでしょう。
転職したい企業の研究には時間と努力が必要ですが、得られる情報は転職活動を成功に導くために有益です。自分のキャリア目標や成長の方向性に合致する企業を見つけ、その企業に対して戦略的なアプローチをすることで、内定獲得の可能性を高められます。
徹底的に自己分析する
自己分析で価値観や経験、キャリア目標を明確にすれば、適切な転職先を選択できるだけでなく、アピールポイントを決めることができます。
自己分析をするには、強みやスキル、経験を客観的に評価する必要があります。なぜなら、自分は頑張ったと思っていても、周囲からは当たり前と思われる可能性があるからです。客観的な評価が難しい場合は、友人やキャリアアドバイザーへの相談を推奨します。
第三者からフィードバックを受けることで、自分の魅力や成長ポイントを客観的に知ることができます。転職エージェントからの専門的アドバイスは、より深い自己理解ができるでしょう。
自己分析は転職活動を成功させるための基盤です。自分の強みや魅力、キャリア目標を明確にし、それにもとづいた転職先の選択やアピールを行うことで、第二新卒の転職活動を成功に導けるでしょう。
希望条件に優先順位を立てる
転職先を選ぶ際、自身のキャリアビジョンやライフスタイル、働き方などに合致する条件を明確にし、その中で優先順位をつけることで、あなたにとって最適な転職先を見つけられます。
希望条件に優先順位を立てるには、重要視する要素を洗い出しましょう。たとえば、給与・待遇、職種・業界、勤務地、キャリアパス、ワークライフバランスなど、転職先に求める条件を具体的に考えます。これらの要素は人それぞれ異なるため、自分自身が何を重視しているのかを明確にすることが重要です。
次に、自身のキャリア目標や長期的なビジョンとの整合性を考えましょう。どの要素が自身の成長や目標達成にとって重要なのかを判断し、それにもとづいて優先順位をつけます。たとえば、将来的なキャリアの発展を重視するのであれば、キャリアパスや成長機会が豊富な企業を優先するといいでしょう。
ただし、希望条件に優先順位をつけるときは、柔軟性も重要です。場合によっては、予想外の選択肢やチャンスが現れるケースもあるため、固定観念にとらわれずに選択肢を検討する柔軟性も持ちましょう。
中長期的なキャリアを明確にしている
キャリアビジョンを明確にすると、適切な企業選びができます。間違った企業選びをしてしまうと転職後「思った企業じゃなかった」と後悔する可能性があり、早期離職に繋がる場合もあるでしょう。
転職後に後悔しながら働くことは、転職成功とは言えません。転職活動は、入社するまでではなく、転職後に納得して働けるかも大切です。そのため、第二新卒で転職する場合、中長期的なキャリアを考慮しながら企業選びをする必要があります。
また、明確なキャリアビジョンを示すことで、企業側に対しても将来の成長意欲や貢献度をアピールできます。
中長期的なキャリアビジョンを明確にし、その目標に向かって努力を重ねることで、第二新卒の転職活動を成功に導けるでしょう。
転職理由をポジティブに置き換える
企業側は、自社に貢献してくれる可能性が高い人材を求めます。
基本的に「成長したい」「新しい業界に挑戦したい」といったポジティブな転職理由は、前向きに捉えてもらえます。一方「人間関係がつらい」「思った事業内容ではなかった」といったネガティブな転職理由は、面接担当者が自社に悪影響を与える可能性があると考えるため、不採用になるケースがほとんどでしょう。
企業に「採用したら貢献してくれるかもしれない」と思ってもらうには、転職理由をポジティブに置き換えることが大切です。
ポジティブな転職理由は、転職先企業に対して、自身の成長意欲やキャリアビジョン、貢献度をアピールできます。転職理由をポジティブに置き換え、自身の魅力を最大限に活かして転職活動を進めましょう。
退職理由と志望動機に一貫性を持たせる
企業は、候補者がなぜ転職を考えているのかを理解し、転職後のモチベーションや結果に繋がるかを判断します。また、退職理由と志望動機が一貫していないと、志望度が低いと思われ、採用されない可能性が高いです。
第二新卒の転職活動を成功させるには、退職理由と志望動機に一貫性を持たせ、誠実さや真摯さをアピールすることが大切です。一貫性を持たせたメッセージは、企業に対して信頼性を高め、転職活動を成功させるための重要な要素となるでしょう。
転職エージェントを利用する
転職エージェントは近年の転職市場に関する情報を網羅しており、これまでの経験から成功するための方法を理解しています。また、転職活動に必要な準備を手伝ってくれるため、スムーズに進められるでしょう。
- キャリアプランの相談
- 求人紹介
- 履歴書や職務経歴書の添削
- 面接対策
- 退職手続のサポート
転職エージェントを利用すれば、上記のサポートを受けられます。
ただし、担当キャリアアドバイザーの質が悪いと、転職がスムーズに進まない可能性があります。転職エージェントを利用する場合は、Webサイトや口コミなどを参考にして、信頼できる企業を選ぶことが重要です。
第二新卒の転職活動を成功させるには、キャリアアドバイザーとのコミュニケーションを通じて、自分の理想的な職場環境やキャリアプランを詳しく話すことが重要です。
第二新卒での転職は、決して簡単ではありません。しかし、転職エージェントを有効活用できれば、納得する活動に近づけるため、積極的に利用しましょう。
第二新卒におすすめの転職エージェント
第二新卒が転職を成功させるためには、転職エージェントのサポートを受けるのが得策です。なかでも、第二新卒に特化したサービスを提供しているエージェントや、第二新卒の転職支援実績が豊富なエージェントに登録すれば、内定獲得の道が拓けるでしょう。
この章では、第二新卒におすすめの転職エージェントを紹介します。それぞれのサービスを把握して、自身に合うエージェントを活用してください。
リクルートエージェント

- リクルートエージェントにしかない非公開求人が多数
- 「職務経歴書エディター」機能で簡単に職務経歴書が作れる
- 様々な転職セミナーやイベントに参加できる
「リクルートエージェント」は、業界最大手の転職エージェントで、他社を圧倒する豊富な求人数が特徴です。
豊富な転職成功データをもとにした、質の高い書類添削や面接対策も魅力のひとつです。
各業界に精通したキャリアアドバイザーが転職に受かるための方法を詳しく丁寧に教えてくれます。
- 初めての転職で進め方が分からない方
- どんな業界・職種に転職するか決まっていない方
- 自分の将来のためにスキルや経験が身につく会社で働きたい方
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | リクルートエージェント |
| 運営会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ |
| 公開求人数 | 740,943件 (未経験歓迎:113,606件) |
| 非公開求人数 | 293,340件 |
| 対応地域 | 東京、名古屋、大阪、福岡など全国/海外 |
| 公式サイト | https://www.r-agent.com/ |
- 自分に合う求人が見つかった
- めんどくさい手続きを代行してくれる
- 書類の添削や面接対策をしてくれる
マイナビ転職エージェント

- 大手企業からベンチャー企業まで幅広い求人を保有
- サポート期間に制限がなく納得がいくまで転職活動を続けられる
- 業界ごとにキャリアアドバイザーがサポート
「マイナビ転職エージェント」は、20代から高い支持を得ている転職エージェントです。
目先の結果だけではなく、5年、10年先を見据えたカウンセリングをおこなうなど、充実したサポート体制と高い内定率に定評があります。
- 年収アップしたい方
- 職場環境を改善したい方
- キャリアプランを相談したい方
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | マイナビ転職エージェント |
| 運営会社 | 株式会社マイナビ |
| 求人数 | 非公開 |
| 対応地域 | 東京、名古屋、大阪、福岡など全国/海外 |
| 公式サイト | https://mynavi-agent.jp/ |
- 求人情報が見やすく使いやすい
- 求人情報の内容以上の情報を知ることができる
- サポートが手厚く親身に対応してくれる
ビズリーチ

- レジュメ登録で自分の市場価値が分かる
- 自分のペースで転職活動を進められる
- 3人に2人が年収アップを実現
「ビズリーチ」はレジュメ登録をするだけで、企業や転職エージェントからスカウトが届きます。
届くスカウトで自分の市場価値が把握できるため、今すぐ転職したい方はもちろん、転職する予定がない方にもおすすめです。
- 転職できるか自分の市場価値を確かめたい方
- 自分でサポートしてくれるキャリアアドバイザーを選びたい方
- 今すぐ転職する予定がない方
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | ビズリーチ |
| 運営会社 | 株式会社ビズリーチ |
| 公開求人数 | 182,980件 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 対応地域 | 東京、名古屋、大阪、福岡など全国/海外 |
| 公式サイト | https://www.bizreach.jp/ |
| 参考ページ | ビズリーチの使い方・利用するメリット ビズリーチのハイクラス会員とは? ビズリーチに登録できない!審査落ちする理由 ビズリーチの登録が今の会社にばれるって本当? ビズリーチは20代でも利用できる? ビズリーチは30代でも転職可能? ビズリーチを40代が利用するべき理由とは? 【50代の転職】ビズリーチの現実に迫る! ビズリーチを利用した看護師の口コミは? |
- 高年収の求人情報が豊富
- 自分の市場価値を理解できた
- 自分でエージェントを選べる
第二新卒の転職活動における注意点
ここまで解説してきたように、第二新卒の転職は決して難しいわけではありません。ただし、いくつかの注意点を意識しないと、転職の成功が遠のいてしまう可能性があります。
以下に紹介するポイントを念頭に置き、転職活動に取り組みましょう。
新卒の就活とは違うことを理解する
たとえば、新卒の就活は活動開始時期がある程度定まっているのに対し、第二新卒の転職活動はいつでも始められます。また、相手が大学生である新卒採用とは異なり、第二新卒者にはビジネスマナーや社会人としての振る舞いが求められるのは言うまでもありません。
さらに、「第二新卒採用」と明示されている求人は新卒採用ほど多くなく、求人の選択肢の少なさを感じやすいのも異なる点です。
このように、第二新卒の転職活動と新卒の就職活動の違いを理解し、第二新卒に合った転職活動の進め方を取り入れるのが成功のポイントといえます。
第二新卒に特化した転職エージェントを利用すれば、具体的なノウハウを教えてもらえるでしょう。
転職先が決まってから退職する
企業は第二新卒者に対して、「忍耐力がないのではないか」「採用してもすぐに辞めるのでは?」といったイメージを抱いています。もし、転職先が決まらないまま退職すると、ブランク期間が生じてしまい、企業へのマイナスイメージを増幅することにもつながりかねません。
転職活動には計画的に取り組み、空白期間をつくらないように注意しましょう。ただし、激務やセクハラ・パワハラなどに悩まされて、心身ともに追いつめられているような方は、この限りではありません。
転職に適した時期を考える
第二新卒者は、経験・スキルの面において、5年以上のキャリアがある人材よりも劣ってしまう可能性があります。転職を有利に進めたいのであれば、ひとつでも多くの実績を積んでから転職を検討するのが賢明です。
たとえば、現在プロジェクトの一員として携わっている仕事があれば、プロジェクトが終結してから転職したほうが、応募先企業へのアピールポイントを増やせます。現在の仕事の状況を振り返り、転職に有利になるかどうかの観点もふまえて、転職時期を考えてみてください。
なお、一般的に、3月〜5月は新卒者の採用・研修で人事担当者が多忙な時期であるため、第二新卒の転職には不利になりやすいといわれています。少しでも成功率を上げたいのであれば、この時期は避けたほうがよいでしょう。
長く働けそうな会社に転職する
もちろん、実際に働いてみないとわからない部分もありますが、自己分析と企業研究である程度の予測を立てることは可能です。
まずは自己分析に取り組み、自身が達成感を覚えるポイントや現職への不満点、これらを表す具体的なエピソード、5年後・10年後のキャリアプランを考えてみてください。次に企業研究を実施し、やりがいを感じられそうか、不満点を解消できそうか、理想のキャリアを実現できそうかを判断します。
企業研究は、以下のような方法でおこなうと効果的です。
- 転職サイトの企業情報をみる
- 企業の公式サイトをみる
- OB・OGを訪問する
- 転職エージェントで企業情報を共有してもらう
- 会社四季報を読む
- 口コミ・評判サイトで調べる
大手企業への転職は難しい可能性あり
なかには、第二新卒で大手企業への転職を希望する方もいるでしょう。しかし、第二新卒で大手企業に採用されるのは難しいかもしれません。この理由は、大手企業はその知名度の高さゆえ、新卒採用で若手人材を十分に獲得できているケースが多いからです。
前述したように、第二新卒の採用に積極的な企業の特徴として、新卒採用で若手社員を確保できなかった、市場拡大のために若い人材の獲得が急がれているなどが挙げられます。この傾向をふまえると、第二新卒の採用は、おもに中小企業やベンチャー企業、スタートアップ企業で多いと予測でき、大手企業への転職のハードルは高いと考えられるのです。
ただし、可能性はゼロではありません。大手企業でも第二新卒の採用を実施しているところはあるため、決して後ろ向きにとらえずに、内定獲得に向けて転職活動に取り組んでください。
第二新卒の転職先選びで重視すべきポイント
第二新卒者は、入社3年以内という早期に離職を検討しているため、次の勤め先では長く働けるよう、転職先選びには慎重になるべきです。
企業の事業内容や将来性、職場の雰囲気を事前に把握し、長く働く姿をイメージできるかどうかを判断してみてください。それぞれのポイントについて解説します。
事業内容に興味がもてるか
とくに、現職の退職理由が「仕事内容に不満がある」「会社の製品・サービスに興味がもてない」という方は、興味をもてる会社に転職したほうが、納得感をもって仕事に取り組めるでしょう。
なお、第二新卒の転職では、未経験の業界・職種で採用される可能性も十分に考えられます。もちろん、現職と関連性のある仕事のほうが転職成功率は高いといえますが、あまり範囲を限定せず、自身がやりがいをもって働ける仕事に挑戦するのもひとつの方法です。
会社や職種に将来性があるか
大卒の第二新卒に該当する25歳前後の方は、60歳の定年退職まであと35年もの期間があります。この先キャリアチェンジしないのであれば、35年の月日を転職先の企業や仕事で過ごすことになるため、将来性のある会社・職種を選択するのが大切です。
たとえば、IT業界や介護業界の需要は、将来的にも上昇傾向にあると予想されています。反対に、AI技術の進化により、一般事務や銀行員、警備員の仕事はなくなる可能性が高いといわれています。
第二新卒のタイミングで将来性のある仕事に就くことは、安定的な収入確保や長期的なキャリア形成の視点からも、重視すべき要素のひとつでしょう。
職場の雰囲気はよいか
職場の雰囲気も、第二新卒の転職で重視したいポイントです。とくに、現職で人間関係に悩まされている方は、職場の雰囲気を事前に把握できると、安心して入社の日を迎えられるでしょう。
キャリアアドバイザー、もしくは企業を担当するリクルーティングアドバイザーは、企業と頻繁にやり取りしており、職場の雰囲気をつかんでいるはずです。
なかには、実際に職場を訪問した担当者や、過去にそのエージェントを通じて入社した社員がいて、詳しい情報を共有してもらえるエージェントもあるかもしれません。
また、企業の口コミ・評判サイトを調べると、実際に在籍経験がある人の企業への評価を把握できます。
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
公開求人数
73.2万件
非公開求人数
30.7万件 |
【初めて転職する方向け】20万件以上の中からピッタリの企業が見つかる。 |
|
★ 4.6
|
非公開 |
【未経験歓迎求人が豊富】大手企業からベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
公開求人数
18.8万件
非公開求人数
非公開 |
【年収500万以上向け】レジュメ登録だけで自分の市場価値がわかる |
|
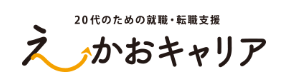 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
非公開求人
多数 |
【入社後の定着率97%】どんな仕事が向いているのか分からない方におすすめ |
|
 doda
doda
★ 4.0
|
公開求人数
26.7万件
非公開求人数
1.8万件 |
【圧倒的な顧客満足度】未経験でチャレンジしたい方におすすめ |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
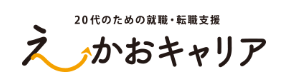 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 doda
doda
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
★ 4.6
|
|
・初めての転職でしたが、マンツーマンでサポートしてくれました。
・未経験でも挑戦できる求人を多く紹介してくれました。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
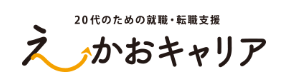 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
|
・自分一人で転職活動をしていたら、なかなか入れない企業への内定が決まりました。
・自分でもびっくりするくらいすぐに内定をもらえました! |
|
 doda doda
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
第二新卒の転職でよくある質問
第二新卒の転職でよくある質問は下記のとおりです。
第二新卒は何年目まで?「第二新卒」の定義は?
そもそも「第二新卒」とは、専門学校や大学を卒業後、企業に就職して2~3年経過した転職志願者をいいます。具体的な年齢は出身校によってさまざまですが、高卒であれば21歳前後、大学卒であれば25歳前後の人を指します。
いずれにしても、一度は「就職」の社会経験を経て転職活動する人物が該当し、通常の中途採用のなかでも「第二新卒」とグルーピングされ別枠で考えられます。
その他、転職市場には「既卒」と呼ばれる分類もありますが、これは卒業後の就職経験が一度もない人を指す言葉のため第二新卒者とは異なるものとして区別されます。
【参考記事】若年者雇用を取り巻く現状|厚生労働省
3年以内に離職する人の割合は?
厚生労働省が雇用保険の加入届をもとに集計した結果によると、大卒で正社員として入社してから3年以内に離職した人の割合は、以下のように推移しているようです。
引用元:新規学卒者の離職状況|厚生労働省
これはいわゆる「3年3割」と呼ばれる問題で、せっかく採用して教育した新入社員のうち、3割が3年以内に退職することは、企業にとって解決すべき課題のひとつとなっています。
3年以内に離職した人材がすぐに転職しているとは限りませんが、おおむね第二新卒者の割合もこのとおりだと予想できるでしょう。
第二新卒に多い転職理由は?
第二新卒者は、入社前に思い描いていた理想と入社後の現実にギャップを感じて、転職を決意する人が多いようです。
本調査は大卒で入社した3年目〜6年目の社会人を対象として実施されたものです。
引用元:若者にとって望ましい初期キャリアとは ~調査結果からみる“3年3割離職”の実情~(2018年)|公益社団法人全国求人情報協会
ミスマッチのない就職を叶えるには、徹底した自己分析と企業研究が肝心です。第二新卒の転職では同じ後悔を繰り返さないように、入念な下準備をしたうえで選考に臨みましょう。
転職エージェントを利用すると、自己分析や企業研究のサポートが受けられるため、入社後のギャップを最小限に抑えられるはずです。
新卒と第二新卒はどっちが有利ですか?
難易度はどちらも同じです。ただし、新卒と第二新卒では判断基準が異なるため、それぞれのポイントを理解しておく必要があるでしょう。
退職してから転職活動してもいいですか?
問題ありません。しかし、安定した収入がなくなるといったリスクがあるため、注意が必要でしょう。
関連記事:仕事を辞めてから転職活動をするメリット・デメリットや注意点を徹底解説
第二新卒で大手企業への転職は難しいですか?
難しいですが、可能です。本記事で解説した、転職でやるべき行動を妥協せずに実施すれば、転職できる可能性は高まるでしょう。
完全未経験の職種に転職することはできますか?
できます。完全未経験の職種の場合、転職理由が重要になるため、企業に納得してもらえる内容にしましょう。
第二新卒の女性は不利ですか?
女性だからといって、第二新卒の転職活動で不利になることはないでしょう。
ただし、出産後も仕事を続けていきたい方は、産休・育休の取得実績が多いか、子育てに理解が得られやすいかどうかにも目を向けてみてください。
新卒採用で受けた企業に応募できますか?
新卒採用で受けた企業に、第二新卒の転職活動で再び応募することは可能です。
数年前に「不採用」の結果を受けてからこれまで努力してきたことや、以前に比べて成長できた点、現職で得られたスキルなどをアピールしましょう。
第二新卒の転職を安心しておこなうには転職エージェントを活用しよう!
第二新卒者が転職を試みた場合、その経験値の低さから「内定をもらうのは難しい」と思いやすいですが、自身を戦略的にアピールすればスムーズな転職が可能になります。
そのためには、事前の企業研究や自己分析をきちんとおこない、採用担当者から好印象を獲得することが大切です。
もし、自己分析が苦手、自身のアピールポイントが見つからないと思う場合は、転職エージェントに相談するとポイントを教えてもらえる可能性があります。
自身の経歴もエージェントが丁寧にヒアリングしてくれるため、企業にアピールすべき強みを見つけるヒントが得られるでしょう。また、エージェントはさまざまな業種に精通しているため、自身が希望する求人とも結び付けてくれるはずです。
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
公開求人数
73.2万件
非公開求人数
30.7万件 |
【初めて転職する方向け】20万件以上の中からピッタリの企業が見つかる。 |
|
★ 4.6
|
非公開 |
【未経験歓迎求人が豊富】大手企業からベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
公開求人数
18.8万件
非公開求人数
非公開 |
【年収500万以上向け】レジュメ登録だけで自分の市場価値がわかる |
|
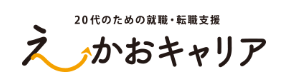 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
非公開求人
多数 |
【入社後の定着率97%】どんな仕事が向いているのか分からない方におすすめ |
|
 doda
doda
★ 4.0
|
公開求人数
26.7万件
非公開求人数
1.8万件 |
【圧倒的な顧客満足度】未経験でチャレンジしたい方におすすめ |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
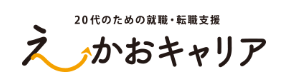 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 doda
doda
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
★ 4.6
|
|
・初めての転職でしたが、マンツーマンでサポートしてくれました。
・未経験でも挑戦できる求人を多く紹介してくれました。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
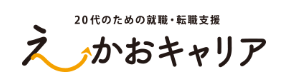 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
|
・自分一人で転職活動をしていたら、なかなか入れない企業への内定が決まりました。
・自分でもびっくりするくらいすぐに内定をもらえました! |
|
 doda doda
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
【参考記事】若年者雇用を取り巻く現状|厚生労働省