「第二新卒は門前払いされる?」
といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
結論、第二新卒は需要があるため大手企業や優良企業に転職できる可能性は十分にあります。なぜなら、ポテンシャル採用を取り入れている企業が多いからです。
ただし、自分に合った企業を選ばないと、転職してからミスマッチだと気づき早期離職につながるかもしれません。
そこで本記事では、第二新卒におすすめの大手企業一覧や優良企業の見極め方、転職を成功させるためのポイントなどを詳しく解説します。
転職エージェント5社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
公開求人数
51.6万件
非公開求人数
41.4万件
|
【初めて転職する方向け】20万件以上の中からピッタリの企業が見つかる。
|
|
|
★ 4.6
|
非公開
|
【未経験歓迎求人が豊富】大手企業からベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。
|
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
公開求人数
14.8万件
非公開求人数
非公開
|
【年収500万以上向け】レジュメ登録だけで自分の市場価値がわかる
|
|
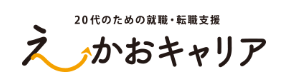 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
非公開求人
多数 |
【入社後の定着率97%】どんな仕事が向いているのか分からない方におすすめ
|
|
|
doda
★ 4.0
|
公開求人数
25.7万件
非公開求人数
2.2万件
|
【圧倒的な顧客満足度】未経験でチャレンジしたい方におすすめ
|
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
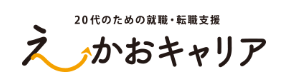 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
doda
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
|
★ 4.6
|
|
・初めての転職でしたが、マンツーマンでサポートしてくれました。
・未経験でも挑戦できる求人を多く紹介してくれました。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
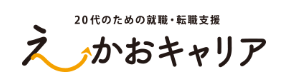 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
|
・自分一人で転職活動をしていたら、なかなか入れない企業への内定が決まりました。
・自分でもびっくりするくらいすぐに内定をもらえました! |
|
 doda doda
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
関連記事:第二新卒におすすめ転職エージェント22選を徹底比較|失敗しない選び方を解説
目次
第二新卒の転職は門前払いされる?
第二新卒は需要があるため転職できる可能性は十分にあります。
なぜ、第二新卒の転職は門前払いされるイメージがついているのか、以下解説します。
採用を懸念する企業もある
すべての企業が第二新卒を受け入れているわけではありません。
企業によっては以下のリスクを考慮して第二新卒枠を採用していないこともあります。
- 短期間での退職リスク
- スキルや経験不足
- キャリアの方向性が不明確
- モチベーションの継続性への懸念
- 企業文化や仕事のミスマッチ
第二新卒とは、新卒で入社した後、短期間(1〜3年以内)で退職し、再び転職活動を行う若手社会人を指します。
一度短期間で退職したことがきっかけで企業側としては「また退職するのではないか」と1歩マイナスなイメージを持っている可能性があります。
また実務経験がある一方で、スキルや業務経験が不足している場合があり即戦力を求める企業にとっては、採用をためらう要因のひとつとなるでしょう。
第二新卒は、自己分析を行うことで企業の求める人物像にマッチしているか、採用担当者が納得できる退職理由や入社した際のキャリアプランなど詳細かつ簡潔にアピールすることが重要です。
第二新卒の需要は高まっている
第二新卒は新卒と比較して多少の社会経験を持っていることから、ポテンシャル採用として受けいれることが多い傾向にあります。
以下は企業や採用担当社視点で、第二新卒を採用するメリットとなります。
- 前職の特色に染まりきっていない
- 新卒と比べて教育コストがかからない
- 長期的な活躍が期待できる
- 新卒採用で十分な人材を確保できなかった
- 市場拡大のため、若い人材を獲得したい
すなわち、約25%の企業が「新卒採用で十分な人数の人材を確保できなかった」と感じているようです。
引用元:2024年卒企業新卒内定状況調査|マイナビキャリアリサーチLab
また日本の労働市場においては、少子化や人材不足の影響もあり企業がより柔軟に若手人材を受け入れる姿勢を持つようにもなっています。
【業界別】門前払いしない第二新卒におすすめの大手企業
第二新卒の転職で「大手企業に転職したい」と思っている方も多いでしょう。しかし、大手企業といっても業界・職種ごとに採用難易度が異なるため、それぞれ調べる必要があります。
そこで、dodaの「転職人気企業ランキング2023」に掲載されている、総合ランキング上位100位の企業の中から、第二新卒を募集・歓迎している大企業を以下に紹介します。企業選びの参考にしてください。
関連記事:第二新卒でも転職できるおすすめの大手企業を業界別に徹底解説
コンサルティング
コンサルティング業界に該当する企業は、以下のとおりです。
- コンサルティング
-
- リクルートホールディングス
- アクセンチュア
- 野村総合研究所
コンサルティング業界は、第二新卒の転職の中でも難度が高くなるため、社会人1年目での転職は難しいかもしれません。企業によっては、社会人1年目でも業績を求められる可能性があります。
ただし、上記で紹介した企業のうち、第二新卒者の応募要件について、アクセンチュアは「半年以上4年未満の社会人経験」、野村総合研究所は「職務経験3年未満」としており、社会人経験が浅い方の受け入れ体制が整っていると予想できます。
SIer
SIer業界でのランクインは、NTTデータのみでした。
- SIer
-
NTTデータ
おもに顧客の課題を解決することを目的に、サーバーやデータベースの構築などをおこないます。NTTデータは、第二新卒を含めた若年層の採用にも力を入れている傾向があります。
ただし、第二新卒で転職する場合は、アプリケーション開発の経験などIT業界に携わった経験が必要になるかもしれません。
SaaS
SaaS業界に該当する企業は、以下のとおりです。
- SaaS・Web
-
- 楽天
- アマゾンジャパン
- ヤフー
- 日本アイ・ビー・エム
- サイボウズ
- KDDI
楽天やアマゾンジャパン、ヤフーが代表的なSaaS企業ですね。
SaaS企業はIT業界の中でも人気があり、競争率が高い傾向があります。
IT企業は成果主義を採用している企業が多いため、自分自身のポテンシャルをうまくアピールできれば、学歴に関係なく採用されます。
金融
金融業界に該当する企業は、以下のとおりです。
- 金融
-
- 日本銀行
- 三井住友銀行
- 東京海上日動火災保険
金融に関する知識が重要になりつつあります。実際、小学校・中学校・高等学校の学習指導要領には金融教育が盛り込まれており、金融リテラシーの向上が目指されています。
金融業界の需要は高騰しており、第二新卒で転職を目指す方もいるでしょう。金融業界は人手不足の傾向もあるため、転職の難易度はそれほど高くないと予想できます。
金融に関する知識は、将来のライフプランの実現や、自身の生活の質の向上にも役立つので、仕事を進めながら勉強できるのは大きなメリットになるでしょう。
総合商社
総合商社に該当する企業は、以下のとおりです。
- 総合商社
-
- 三菱商事
- 伊藤忠商事
- 三井物産
- 丸紅
- 住友商事
総合商社は、安定感のある企業が多く、福利厚生が充実していることから学生から社会人まで入社を目指す方が多い業界です。
コミュニケーション力が重視される傾向があり、国内外の取引企業を相手に気負わず会話・交渉できる方に向いている業界です。とくに、語学が得意な方は能力を発揮しやすいでしょう。
インフラ
インフラ業界に該当する企業は、以下のとおりです。
- インフラ
-
- 東日本電信電話(NTT東日本)
- 西日本電信電話(NTT西日本)
- 東日本旅客鉄道(JR東日本)
- 西日本旅客鉄道(JR西日本)
- 九州旅客鉄道(JR九州)
- 全日本空輸(ANA)
- 日本航空(JAL)
- 九州電力
インフラ業界は、競争率が高く、書類選考の時点で候補者が大幅に絞られる可能性があるので、入念な事前準備が欠かせません。
インフラ業界は、世の中の状況に応じて募集人数が上下する傾向があるため、採用情報を見逃さないようにしましょう。
メーカー
メーカー業界に該当する企業は、以下のとおりです。
- メーカー
-
- トヨタ自動車
- 本田技研工業
- 日産自動車
- デンソー
- ソニー
- パナソニック
- 日本電気(NEC)
- キヤノン
- シャープ
- 日立製作所
- 東芝
- 富士通
- 東京エレクトロン
- 村田製作所
- 京セラ
- IHI
- 富士フイルム
- 未来工業
- アイリスオーヤマ
- バンダイ
- キリンホールディングス
- アサヒビール
- 明治
- 日清食品
- カゴメ
- 資生堂
- AGC
dodaの調査結果からみても、メーカー業界はとくに人気があります。
また、第二新卒を歓迎している企業も多く、メーカー業界に挑戦できる可能性は大いにあるでしょう。
ただし、企業によっては、採用の難易度が高くなるので、書類・面接選考対策は欠かせません。
サービス
サービス業界に該当する企業は、以下のとおりです。
- サービス
-
- オリエンタルランド
- JTB
サービス業界の求人は多岐にわたるため、第二新卒でも転職しやすいのが特徴です。
デスクワークを想定して応募すると、入社後にギャップを感じるかもしれません。
サービス業界への転職は、3年・5年・10年後のキャリアビジョンを描いたうえで検討しましょう。
門前払いしない第二新卒におすすめな企業の特徴5つ
キャリアアドバイザー経験のある筆者は、いままで第二新卒の方から数多くの転職相談を受けてきました。
ここでは、その際におすすめしてきた企業の特徴を紹介します。
おすすめできる理由についても詳しく解説するので、第二新卒で転職を考えている場合は、ぜひ参考にしてください。
通年採用している大手企業
第二新卒で転職を考えている方の中には、「大手とベンチャーどっちがいいのかな?」と悩んでいる方もいるでしょう。
なぜなら、大手企業は倒産する可能性が低く、福利厚生や各種制度が整備されていたり、経験できる業務の規模が大きかったりするからです。くわえて、通年採用を実施している企業であれば、気になるポジションがオープンになった段階ですぐに応募できます。
ベンチャー企業は、制度がまだ整っていないケースが多く、中には安定した生活が送れるか確証をもてない企業もあるでしょう。その点、大手企業ではほとんどの場合、安定した収入が得られます。
また、大手企業は事業の規模が大きいため、第二新卒のうちから、ビッグプロジェクトに関われることもあります。
一方、第二新卒で「とにかく成長したい」「20代のうちは残業問わず仕事に打ち込みたい」方は、ベンチャー企業への転職がおすすめです。
ベンチャー企業に転職する明確な理由がなく、規模で迷っている場合は、大手企業のほうがいいでしょう。
関連記事:第二新卒で大手は無理?内定獲得のコツやおすすめのエージェントを紹介
「未経験OK」の企業
未経験者を歓迎している企業も、第二新卒におすすめです。採用活動をおこなう企業の中には、未経験可としている場合と、していない場合があります。
未経験採用をしている企業は、求人票に「未経験可」のような文言が見られます。未経験者を積極採用している企業は、人材不足である可能性が高いため、第二新卒でも転職できる可能性が高くなるはずです。
ただし、未経験可の企業に応募するときは、事前に企業の研修制度を確認してください。研修が整っていない場合、転職後すぐに実務に移り、仕事の全体像がわからないまま取り組む可能性があります。
また、企業によっては、就業経験を問わず、卒業後3年程度までは新卒採用に応募できることもあります。その場合は、新卒で入社した同期とともに一定期間研修を受けることになるため、未経験であっても問題ないでしょう。
転職してから基本的なノウハウを身につけたい方は、研修制度も確認するようにしましょう。
転職してから基本的なノウハウを身につけたい方は、研修制度も確認するようにしましょう。
成長を続けているベンチャー企業
企業の規模には、大手・中小・ベンチャー企業が存在しており、人それぞれ向いている規模の企業があるはずです。
たとえば、ベンチャー企業に向いている第二新卒の特徴としては、以下があげられます。
- 成長意欲が高い人
- 主体的に取り組める人
- 若いうちはワークライフバランスよりもスキルアップを重視したい人
- 裁量権をもちたい人
- 経営を学びたい人
- 実力に応じて昇給する環境を望む人
- 20代で管理職に就きたい人
ベンチャー企業は多くの経験が積める一方、多忙な毎日になると予測されます。とくに、急成長中のベンチャー企業では、ルーティンワークで日々が過ぎるようなことはなく、新しい挑戦をする毎日になるでしょう。
若いうちから多様な挑戦ができるため、営業力や論理的思考力、交渉力など、様々なビジネススキルを身につけることができます。
ベンチャー企業には、大手や中小企業にはない魅力があります。
離職率が低い企業
離職率が低いことも、第二新卒におすすめな企業の特徴です。離職率が高い企業は、社内で何からの問題が起きている可能性が考えられます。
たとえば、上司のハラスメントや人間関係のストレス、求人票とは違う業務内容などがあげられます。このような内情が求人広告に掲載されることはないため、働いてみないと判断は難しいでしょう。
しかし、離職率を見れば、応募前にある程度の予想ができるかもしれません。働きやすい環境であれば、社員が離職せずに「長く働きたい」と思うはずだからです。
離職率が高い理由を公表していない企業には注意が必要です。
もし、企業の離職率が求人票に記載されていないときは、「就職四季報」やインターネット検索で調べたり、転職エージェントに聞いたり、面接時に質問したりすることをおすすめします。
離職率が低い企業の目安は、10%以下であることを覚えておきましょう。
いままでの経験を活かせる企業
いままでの経験が活かせる業種・職種の企業に応募すると、採用の可能性を高められるメリットがあるうえ、年収アップも実現できるかもしれません。
第二新卒は、スキルや経験・実績が少ないため、転職で年収が上がりづらい傾向があります。なぜなら、企業は自社に貢献してくれる可能性が高い人材を採用するケースが多く、そのような人材に対して高い年収を提示するからです。
そこで、経験したことが活かせる業界・職種・企業に転職すれば、すぐに貢献できる可能性が高く、年収も上げられる可能性があります。
第二新卒の転職で年収を上げたい場合は、自分のスキルや経験が活かせる企業を選びましょう。
第二新卒が門前払いになりやすい企業の特徴
企業によっては第二新卒採用を受け入れていない場合もあります。
以下では、第二新卒が門前払いになりやすい企業はどんな特徴なのか解説します。
第二新卒の採用経験がない
企業がこれまでに第二新卒の採用を行った経験がない場合、門前払いになってしまうでしょう。
第二新卒は新卒と中途採用の中間に位置する存在であり、企業によっては採用フローや評価基準が明確に定めてないことや、第二新卒のニーズを認識していない場合があります。
新卒採用しか募集していない
新卒採用しか募集していない企業は、毎年新卒学生を対象に一括採用する方法や入社後に新卒社員をゼロから育成するなど独自の研修プログラムを持っている可能性があります。
また年度ごとの計画に基づいた採用スケジュールに従っていることから、年度途中での採用や計画外の採用に対応できず、第二新卒を募集していない場合も考えられます。
とくに大企業や歴史のある伝統的な企業は上記のような傾向が見られます。
門前払いになりやすい会社の特徴として、新卒社員を自社文化に合わせた長期的な育成方針を持っているため、社会経験のある第二新卒や中途採用の必要性を感じていない企業が挙げられます。
第二新卒を門前払いしない転職におすすめの業界7選
ここからは第二新卒におすすめの業界を、厳選して7つ紹介します。
転職したい業界が決まっていない人は、ぜひ参考にしてください。
- IT業界
- コンサルティング業界
- 機械業界
- 製造業界(メーカー)
- インフラ業界
- 金融業界
- サービス業界
IT業界
高い専門性を身につけたい、キャリアアップを目指したいという方に、IT業界はおすすめです。
コロナ禍で著しく成長しましたが、人手不足が深刻な業界でもあるため第二新卒への求人が多い傾向にあります。担当する業種にもよりますが、WebマーケティングやプログラミングなどのITスキルが身に付くのも魅力のひとつです。
エンジニアは人手不足が顕著なので、重宝されやすいでしょう。専門性が高まれば、ITマネジメントやコンサルタントなど、さまざまなキャリアアップが可能です。
コンサルティング業界
コンサルティングとは、企業が抱えている問題や悩みを専門的な観点から診断し、解決に導く仕事です。経営面はもちろん、社内システムや人材管理などさまざまな知識が求められます。
結果が求められる仕事のため、やりがいを持って働けるのが特徴です。
時期によっては激務になりやすい業界ですが、評価次第では高収入も狙えます。今までの自分の経験や知識を活かしたい人や、人の役に立ちたい人におすすめです。
機械業界
機械業界も第二新卒におすすめの業界です。とくに家電製品や建設、自動車など工業系の業界は、20代の採用活動が活発なので採用されやすい傾向にあります。
機械業界は副業OKな企業も多いため、収入を上げたいと考えている方にもおすすめです。
製造業界(メーカー)
製造業界は未経験者歓迎の求人が多いので、経験のない第二新卒でも応募しやすいのが特徴です。
他の業界に比べ、製造業界は一人で仕事をすることも多いため、黙々と作業をしたい方や、一つひとつの作業を丁寧にこなすことが好きな方にもおすすめできます。
製造業は専門的な技術を習得しやすく、企業の中で自分の居場所を作りやすいのも魅力です。
インフラ業界
インフラ業界とは、ガスや水道、鉄道など生活に欠かせないサービスを提供する企業のことです。インフラ業界は給与が安定しており、倒産のリスクが少ない傾向にあります。
金融業界
社会貢献や政治経済に興味がある方は、銀行や証券会社などの金融業界がおすすめです。銀行は営業時間がきっちりと決まっているため、ワークライフバランスを重視しながら働けます。
基本的に4年生大学を卒業している人を採用していることから、高卒の第二新卒の方の転職は難しい可能性があります。
サービス業界
接客や販売、飲食などのサービス業界も第二新卒におすすめの業界です。未経験歓迎の求人も多いため、比較的チャレンジしやすい業界といえます。
人に喜びや笑顔を与える仕事なので、人のためになることがしたい方や仕事にやりがいを感じたい方におすすめです。
門前払いされる第二新卒の特徴
第二新卒は新卒採用と中途採用の中間に位置し、企業側からの期待と現実のギャップが生まれやすいポジションです。
いくら新卒より需要が高いとはいえ、社会経験を生かさずに転職すると長期的な転職活動が続いてしまう可能性があります。
以下では、門前払いされる第二新卒の特徴について詳しく解説します。
前職を短期離職している
門前払いされる第二新卒の特徴として、前職を短期離職している方があげられます。
また、企業は新たな社員を採用する際、教育・育成コストを考慮する傾向にあり、短期離職されてしまうと新人育成に費やした時間が無駄になってしまう恐れもあります。
結果的に、短期離職の経験がある第二新卒は企業から敬遠されやすく、門前払いされてしまいます。
企業に信頼を与えるためにも、短期離職に至った背景を振り返り自己分析を徹底的行いましょう。
面接や志望動機では短期離職で学んだこと具体的に説明し、新しい会社で長期的に成長していきたいという強い意欲を伝えることが大切です。
転職理由があいまい
転職活動において、転職理由が明確であることは重要です。
結果、信頼することが難しく門前払いされるリスクが高まってしまうでしょう。
転職理由を明確にするには、転職するにあたって短期的・長期的なキャリア目標を考えることや、新しい環境で挑戦したいことや成長したいという前向きな理由をアピールすることが重要です。
ビジネスマナーが身に付いていない
企業は、短期間での就業経験があったとしても第二新卒に対して基礎的なスキルやマナーを持っている人材を求めています。
なぜなら企業は、教育や研修のコストを抑えようと採用に対して慎重になるためです。
とくに面接時に正しい言葉遣いや態度ができない場合、能力やスキルに関わらず社会人としての素養に欠けるとマイナスな印象抱いてしまいます。
上記の理由によりビジネスマナーが身についていない第二新卒は、選考段階で不利になることが多いため、面接対策するなど事前準備が必要です。
第二新卒が自分に合う企業を探す3つのコツ
第二新卒が自分に合う企業を探すコツは、以下のとおりです。
- 求人サイトを複数利用する
- 他社に転職した同僚・先輩に相談する
- 転職エージェントを活用する
転職サイトを複数利用する
第二新卒が自分に合う企業を探すには、転職サイトを複数利用しましょう。
転職サイトには、さまざまな業界・職種の求人が掲載されており、自分に合う企業を探せます。サイトによって保有されている求人の特徴は異なるため、複数のサイトに登録することで転職の選択肢を増やせることがメリットです。
たとえば、転職求人サイトのdodaでは、24万8,321件(2023年9月現在)の求人が保有されています。さらに、「詳しい条件で求人を検索する」というシステムを活用すれば、この中から条件に合う求人をピンポイントで見つけることが可能です。
dodaでは以下のような項目で求人を検索することができます。
- 職種
- 勤務地・路線・駅
- 業種
- 雇用形態
- 希望年収
【参考記事】求人情報を詳細条件から探す|doda
ほかの転職サイトでも簡単に求人を絞り込めるため、複数サイトを併用すれば、自分の希望条件にマッチする企業の選択肢を増やせるはずです。
他社に転職した同僚・先輩に相談する
他社に転職した同僚・先輩に相談するのも、第二新卒で自分に合う企業を探すコツです。
転職経験がある同僚・先輩は、自社から転職できそうな企業の特徴や方法を把握している可能性があります。あなたが希望する業界・職種に転職している場合は、実体験をもとに明確なアドバイスを聞けるかもしれません。
また、転職だけでなく、退職するときのポイントなども教えくれるでしょう。
関連記事:第二新卒の転職相談先おすすめ4選|よくある悩みやリアルな相談内容も紹介
転職エージェントを活用する
第二新卒で自分に合う企業が見つからない場合は、転職エージェントの活用をとくにおすすめします。なぜなら、多くの転職エージェントは独自の非公開求人を保有しているからです。
非公開求人には、有名大手企業や優良ベンチャー企業の求人が含まれていることもあり、好条件の仕事に出会える可能性もあります。
また、転職エージェントによって保有している非公開求人は異なるため、複数のエージェントを活用するのがおすすめです。転職エージェントを併用すれば、多くの公開・非公開求人と出会え、より自身のチャンスを広げられるでしょう。
さらに、転職エージェント経由で企業に応募する場合、書類選考や面接における内定を取るためのコツも教えてもらえるので、転職成功の可能性を高められるはずです。履歴書・職務経歴書の添削や面接対策、企業の内情の共有などのさまざまなサポートによって、理想の転職を叶えられるように導いてくれるでしょう。
関連記事:第二新卒が転職エージェントを利用するメリット5選|おすすめのエージェントや選び方とは?
第二新卒での転職で門前払いしない企業を見極める9つのポイント
「次に転職するなら優良企業」と考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、大手企業なら必ずしも優良企業とは限りません。
希望の働き方を実現するためには、応募する企業のあり方が理想とミスマッチでないことが大切です。ここからは、優良企業の特徴を9つ紹介します。
- 給与体系は業務形態と見合っているか
- 残業時間は短めか
- 福利厚生が充実しているか
- 有休取得率が高いか
- 社内の雰囲気はいいか
- 離職率が低いか
- 従業員数は増加しているか
- 評価・表彰制度が充実しているか
- 求人票の採用人数が多すぎないか
給与体系は業務形態と見合っているか
優良企業は給与体系が業務内容に見合っている、または水準よりも高いのが特徴です。優良企業は、事業で得た利益を積極的に従業員に還元するため、他社よりも給与水準が高い傾向にあります。
また、どんな企業であっても基本給は最低賃金以上支給するのが義務ですが、なかには違法な給与額を設定している企業も少なくありません。
残業時間は短めか
優良企業は、従業員の残業時間が短いところが多いです。サービス残業はもってのほかですが、残業代が全額支給されていたとしても残業時間が多すぎる場合は注意しましょう。
また、みなし残業制を取り入れている企業の場合は、実際どの程度残業があるのかを面接や転職エージェントを介して確認しておくと安心できます。
福利厚生が充実しているか
優良企業は、福利厚生が充実していることが多いです。福利厚生には、雇用保険や健康保険などの法律で定められている福利厚生以外に、会社が独自で定めている法定外福利厚生があります。
法定外福利厚生は住宅手当や社員食堂、フィットネスジムの利用など、会社によってさまざまです。
法律で定められている以外の福利厚生がある企業は、従業員を大切にする優良企業だといえるでしょう。
有休取得率が高いか
年間休日数も大切ですが、有休取得率にも注目しましょう。
優良企業ではワークライフバランスが重視されている傾向にあるため、有休取得率が高くなりやすいのが特徴です。なかには、従業員の有休取得率が100%近い会社もあるほどです。
では、どの程度の取得率なら有休取得率が高いといえるのでしょうか。
厚生労働省が調査した「令和3年就労条件総合調査」の結果を見ると、有休を取得した日数は10.1日、取得率は56.6%となっています。
そのため、この数値以上の有休取得日数・有休取得率であれば、有休が取りやすいと考えられるでしょう。ちなみに、法律で年間5日は有休取得が義務付けられています。
【参考記事】令和3年就労条件総合調査『労働時間制度』|厚生労働省
【参考記事】年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
社内の雰囲気はいいか
社内の雰囲気は、働きやすい環境という面で重要なポイントです。面接や社内見学の際、チェックしておきましょう。
暗かったり異常な緊張感があったりする会社は居心地が悪いことが多いため、避けたほうが無難です。
離職率が低いか
働きやすい環境が整っている優良企業は、離職率が低い傾向にあります。会社に対して不満が少ないので、長く勤める社員が多いのも特徴です。
3年後離職率が30%以上と離職率が高い企業は、人間関係や働く環境、業務量など何かに問題がある可能性が高いと考えられます。
離職率が高い企業は、求人票に離職率を記載しないことがほとんどです。
離職率が記載されていない場合は転職エージェントを通して聞いたり、就活情報誌に記載されていたりするので確認してみましょう。
従業員数は増加しているか
年々従業員数が増加し、企業規模が拡大している企業は優良企業である可能性が高いといえます。
評価・表彰制度が充実しているか
従業員の評価・表彰制度が充実している会社は、優良企業であることが多いです。優良企業は従業員のことを大切にしているため、仕事に対して正当な評価をしてくれる傾向にあります。
求人票の採用人数が多すぎないか
従業員数に対し、採用人数が多すぎる会社は注意が必要です。その場合、入社後すぐ退職することを考えて人を多めに採用している可能性があります。
大量に人を採用しないといけないほど退職者が多いとも考えられるので、採用人数もチェックしておきましょう。
第二新卒が転職で門前払いされないための対策
第二新卒が転職で門前払いされないための対策は、以下のとおりです。
- 自己分析をする
- 転職する時期を見極める
- 業界・企業研究を入念におこなう
- 資格を取得する・スキルを磨く
- 応募書類は企業に合わせて作りこむ
- 面接対策をしっかりおこなう
- 複数社を並行して受ける
- 転職エージェントを利用する
詳しい方法について解説していきます。一つひとつのステップを実践し、転職を成功させましょう。
自己分析をする
転職活動で欠かせないのが、自己分析です。自己分析では、志望する業界・職種を決め、自己アピールをするために過去の経験を振り返っていきます。
ほかの求職者に負けない強みをアピールすることは、志望先に自身の魅力を伝えるために大切です。また、譲れない条件を明確にすれば、転職活動の軸が定まり、入社後のミスマッチを回避することにつながるでしょう。
あらためて自分自身を深掘りすることで、価値観やモノの見方が把握でき、自己PRや希望条件の輪郭をクリアにできるはずです。
自己分析は、いまの自分の価値観を再確認するためにも重要です。過去・現在・未来を分析し、なぜ転職したいのか、転職によって何か叶えたいのかを明確にしましょう。
関連記事:第二新卒の転職には自己分析が重要な理由とポイントを解説
転職する時期を見極める
すぐに転職先が決まるとは限らないため、転職する時期を見極めることが重要です。
また、転職活動は在職中におこない、転職先が決まってから退職するのがおすすめです。先に退職してしまうと、転職先が決まらずに後悔する可能性もあります。
志望する業界・職種への転職を成功させるには、余裕をもって行動することが大切です。第二新卒で大手・優良企業への転職を希望する場合は、転職する時期を見極めましょう。
関連記事:第二新卒の転職にかかる期間とは?有利な時期や失敗しないためのポイントを解説
関連記事:新卒入社後からの転職におすすめのタイミングは?転職を成功させるコツや転職時の注意点を解説
業界・企業研究を入念におこなう
面接で質問に答えられなかったり、一貫性のない回答をしてしまったりすると、「志望意欲が低い」とみなされるかもしれません。業界・企業研究を十分におこなっていれば、その業界・企業ではないといけない理由を説得力をもって説明できるでしょう。
志望する業界・企業にしかない志望理由を作るには、「経営理念×ビジネスモデル」のように、掛け算をするのがポイントです。
効果的な志望理由を考えるためには、入念な業界・企業研究が欠かせません。また、徹底的な業界・企業研究ができれていれば、転職後のミスマッチも予防できるでしょう。
資格を取得する・スキルを磨く
資格をもっていると有利になる業界・職種への転職を考えているのであれば、転職活動前に資格を取得するのがおすすめです。
資格は、特定の知識を有していることの証明となるため、即戦力になり得ることをアピールできます。また、資格を取得していることで、収入が上がる可能性もあります。
第二新卒の方で、資格取得を悩んでいる場合は、以下のような資格取得に挑戦してみるのも選択肢のひとつです。
- ITパスポート
-
ITに関する基本的な知識を有していることを証明する国家資格
- MOS(マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト)
-
Word・Excel・PowerPointなど、マイクロソフト社製のオフィスソフトを使いこなせるスキルを有することを証明する資格
- 日商簿記3級以上
-
企業の経営活動や財政状況の把握に欠かせない簿記の技能・知識の程度を測る資格
- 宅地建物取引士
-
不動産取引の専門家で、不動産売買や賃貸契約の場において設置が義務付けられており、おもに不動産業界で需要が高い国家資格
- TOEIC750点以上
-
自分の英語力を測るための試験。大手・優良企業に転職する場合は、TOEIC750点以上が必須要件とされることも
- 基本情報技術者試験
-
情報処理技術に関する基礎的な知識・技能を有していることを証明する国家資格
応募書類は企業に合わせて作りこむ
それぞれの企業に合わせて応募書類を作り込むことは、選考を通過するための大切なポイントのひとつです。
大手・優良企業は競争率が高いため、よくある志望動機・自己PRは目に留まりにくくなります。
履歴書・職務経歴書を作成するときは、求められているスキルに焦点を当てて経歴を記載したり、その企業の募集要項に合わせて応募書類を作成したりするのがおすすめです。
関連記事:第二新卒が転職する時の志望動機の書き方|注意点と例文も紹介
第二新卒の転職理由とは?履歴書の書き方や面接時の回答方法のコツも解説
面接対策をしっかりおこなう
第二新卒の面接では、新卒採用で問われた内容とは異なる質問を聞かれます。具体的には、以下のような質問があげられます。
- 転職理由
- 退職理由
- 志望理由
- 別の業界・職種を選択した理由
- 転職後の将来像(3年後・5年後・10年後・20年後)
- 転職できる時期
退職理由と志望動機に矛盾があると、面接官に対してあまり良い印象を与えられません。なぜなら、退職理由と志望動機に一貫性がないと、「嘘をついているのではないか」と疑われるからです。
企業は第二新卒に対して素直さや謙虚さを求めているため、本心を聞きたいと考えています。内定を得たいからといって嘘の説明をすると悪い印象を与えかねません。面接で聞かれた質問には、正直に答えましょう。
また、当たり障りのない「模範解答」だと、人柄や人間性が伝わりません。
事前に転職を決意した理由を自分の言葉で明確に伝えられるように準備しておきましょう。
面接時のビジネスマナーや立ち居振る舞いも、新卒時より厳しく見られています。受け答えだけに集中せず、身だしなみや行動にも注意を払うことが大切です。
複数社を並行して受ける
応募する企業を1社に絞れば集中して採用試験に臨める反面、不採用になったら一からやり直しになるで、転職活動が長引く可能性があります。
とくに、大手企業は競争率が高いため、内定獲得率を上げるためにも複数社を並行して応募するのがおすすめです。
しかし、業界・職種関係なく手当たり次第に受けると、それぞれの企業に合わせた書類・面接対策が必要になります。
転職エージェントを利用する
大手・優良企業に転職を考えているなら、転職エージェントを利用するのがおすすめです。
転職エージェントは、非公開求人を多数保有しているのに加え、応募書類の添削や面接対策などのサポートも無料で提供してくれます。具体的に実施しているサポートは、以下のとおりです。
- 現状のヒアリング
- 転職市場や応募先企業の情報共有
- 求人紹介・選定
- 履歴書や職務経歴書の作成・添削
- 面接の日程調整
- 面接対策
- 選考後のフィードバック
- 内定後の年収・条件交渉
- 入社手続きのサポート
「できるだけ効率的に転職活動を進めたい」「一人で転職活動ができるか不安」という第二新卒は、転職エージェントの活用がおすすめです。
いくつかの転職エージェントを併用すれば、より充実したサポートが受けられます。複数の転職エージェントを併用するメリットについては、以下の記事を参照ください。
第二新卒におすすめの転職サービス5つ
第二新卒で大手企業への転職を考えている方は、転職エージェントを利用するのがおすすめです。転職エージェントを利用すれば企業に関する有益な情報を入手しやすくなるので、失敗を減らせます。
また、転職エージェントでは、たくさんの転職希望者を見てきた転職のプロがサポートしてくれるのも特徴です。
自分に合った企業の選定から、応募書類の添削、面接対策、入社の手続きまで徹底的にサポートしてくれるので、転職活動が初めての第二新卒でも安心です。
ここからは、とくにおすすめの転職エージェントを5社紹介していきます。
ハタラクティブ

ハタラクティブは第二新卒、既卒、フリーターなど20代の若手世代に特化している転職エージェントです。
とくにエンジニアや医療領域を中心とした、未経験歓迎の求人を多く取り揃えています。
ハタラクティブの大きな特徴は、登録してから内定までの早さにあります。
登録してから1ヵ月以内で内定をもらっている方が多く、さらに就職成功率は80%以上というのだから驚きです。
【参考記事】ハタラクティブ
そのため、できるだけ早く転職活動を終わらせたいと考えている方にもおすすめの転職エージェントといえるでしょう。
また、20代向けの転職エージェントということもあり、利用者には転職活動が初めての方が多いため丁寧なサポートをおこなっているのもハタラクティブの魅力です。
些細な心配事もキャリアアドバイザーに相談できるので、「はじめての転職活動なので不安」と感じている方はハタラクティブを利用してみてください。
関連記事:ハタラクティブの評判・口コミを徹底解説【やばい・やめとけ?】
就職カレッジ

就職カレッジは独自の就職支援制度がある、20代向けの転職エージェントです。
就職カレッジには就活生向け・転職者向けなど、複数の研修制度が準備されており、研修を終了すればジェイックが厳選した企業20社の採用試験をが書類選考なしで受けられるようになります。
学歴や職歴ではなく、人柄を重視した企業の求人を多数取り扱っているので、「学歴に自信がない」「その業界は未経験なので心配」という方でも安心です。
また、就職カレッジで転職した方の定着率は90%以上と転職エージェントのなかでも高水準を誇り、働きやすい企業の求人のみを取り扱っていることがわかります。
【参考記事】就職カレッジ®の実績|ジェイック
長く勤められる職場を探している方には、ぴったりの転職エージェントです。
キャリアスタート

キャリアスタートは、若い世代の転職サポートに特化した転職エージェントです。
キャリアスタートには第二新卒向けの好待遇求人が充実しており、大手企業や有名企業へ転職が成功した実績も多数あるので、安心してサポートを受けられます。
企業への調査やインタビューなども徹底しておこなわれているため、入社してからのギャップや失敗を回避できるでしょう。
キャリアスタートのサポートによる転職で年収がアップした人は83%、転職後の定着率は92%と、高い実績を誇っています。
【関連記事】第二新卒・既卒事業|キャリアスタート
理想の働き方がある方や年収を今よりもアップしたいと考えている方にもおすすめです。
また、キャリアスタートで扱っている求人は関東圏に集中しているので、関東圏に在住している方や上京を考えている方にも最適です。
家賃補助や寮がある求人の紹介や初期費用が不要な住居の相談、関東での生活費に関する相談まで、一見転職とは関係ないことまで親身になってくれるのも嬉しいポイントです。
DYM就職

DYM就職は、20代から30代前半の若手向け転職エージェントです。
第二新卒をはじめとし、既卒やフリーター、ニートの方の転職活動までサポートしています。
DYM就職では、書類選考なしで面接から選考を受けられる求人も多数保有しているので、学歴や職歴に自信がない方にもおすすめです。
DYM就職は研修制度が充実している企業の求人を多く保有しているのも特徴です。「社会人経験が少ないから、自分のビジネスマナーに自信がない」「スキルが足りないかも」という方でも、研修を受けられるので不安を解消できます。
企業選定から内定後のフォローまではもちろん、入社後もサポートを受けられるので安心です。
働きながら転職活動をしたい方は、退職手続きなどのサポートも受けられます。
第二新卒エージェントneo

第二新卒エージェントneoは、20代の既卒(高卒・中卒含む)やフリーター支援に特化している転職エージェントです。
大手の転職エージェントと比較するとそこまで求人数は多くありませんが、第二新卒エージェントneoで取り扱っている求人は質が高いのが特徴です。
なぜかというと、キャリアアドバイザーが実際に訪問し、独自に設けた基準をクリアしている企業のみ第二新卒エージェントneoに求人を掲載できる仕組みになっているからです。
そのため、実際の職場の雰囲気もわかりやすく、「思っていたのと違った」というミスマッチを防げるのもポイントです。
応募書類の添削や面接対策はもちろんですが、未経験の職種や業界への転職を考えている場合、その業界の知識をレクチャーしてもらえるのも第二新卒エージェントneoならではの魅力です。
未経験歓迎の求人も多く取り扱っているので、新しい業界にキャリアアップしたいと考えている方におすすめです。
|
転職するか悩んでいる方へ |
|---|
 |
転職エージェントを利用する際の流れ
ここからは、利用する転職エージェントを選んでから実際に入社するまでの流れについて解説します。
- 公式サイトから登録する
- キャリアアドバイザーによる面談を受ける
- 求人を紹介してもらう
- 応募書類の添削・面接対策をおこなう
- 面接を受ける
- 入社手続きや退職準備をおこなう
転職エージェントを利用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
1.公式サイトから登録する
まずは、利用したい転職エージェントの公式サイトから登録しましょう。
転職エージェントは求人サイトとは違い、登録しないと求人紹介や転職サポートなどのサービスを受けられません。
申し込みフォームから氏名や希望勤務地、職種などを入力し申し込みます。ほとんどの転職エージェントはWebで情報を入力するだけで登録完了です。
スムーズに転職活動を進めたいなら、3~5社ほど転職エージェントを登録しておきましょう。
2.キャリアアドバイザーによる面談を受ける
転職エージェントに登録後、数日から1週間程度経った頃に、メール、または電話で連絡が届きます。
面談日を調整し、キャリアアドバイザーによる面談が実施されます。
面談は、転職エージェントのオフィスや電話、オンラインなどで実施されます。これまでのキャリアを棚卸しされたり、転職の目的や希望条件を確認されたりして、これからおこなう転職活動のスケジュールを大まかに設定していきます。
4.求人を紹介してもらう
面談で転職先の希望条件を伝えると、求める内容に合った求人を紹介してもらえます。
また、転職エージェントは企業を直接訪問し、取材調査しているケースもあり、業界の最新動向や特徴、企業の風土、職場の雰囲気などの「生」の情報を共有してもらえることもあります。
企業の福利厚生や残業時間なども転職エージェントを経由して確認できるので、自分の希望や適性と合っているかを確認しながら、応募する企業を決めていきましょう。
4.応募書類の添削・面接対策をおこなう
応募する企業を決めたら、必要な書類を準備しましょう。
転職エージェントを経由して応募する場合、担当のキャリアアドバイザーが企業に求職者の情報や書類の送付をおこない、応募手続きを進めるのが一般的です。
転職エージェントでは、採用担当者の目に留まる職務経歴書や応募書類の書き方を丁寧にレクチャーしてもらえます。また、面接対策を受けられるのも転職エージェントの魅力です。
身だしなみや振る舞いはもちろん、応募先の企業の特徴や質問の傾向なども教えてもらえるので、十分に準備したうえで面接に臨めます。
5.面接を受ける
書類選考に通ったら、次のステップは面接です。
キャリアアドバイザーが面接日の調整をおこなってくれるので、面接の準備に専念できるのもうれしいポイントです。
6.入社手続きや退職準備をおこなう
内定を獲得したら、入社日を調整したり、退職の手続きをしたりして、転職に向けて準備を進めていきます。
希望の入社日を担当のキャリアアドバイザーに伝えれば、企業へ交渉してくれるので安心です。
年収や待遇など、直接企業に伝えにくいことの交渉まで転職エージェントが代行してくれるので、気になることがあればキャリアアドバイザーに相談しましょう。
また、円満退職に向けた手続きについてのアドバイスも受けられます。
第二新卒が転職活動をするときの注意点5つ
転職活動をするうえで、第二新卒ならではの注意点があります。転職活動に失敗しないためにも、以下で紹介する5つの点に注意して進めていきましょう。
大手企業=優良・ホワイト企業とは限らない
大手企業だからといって、優良企業・ホワイト企業とは限りません。前述したとおり、大手企業にはデメリットも存在します。
仕事内容や社内の雰囲気、勤務形態はそれぞれの企業によって異なるため、有名な企業とはいえ働きやすさが保証されているわけではありません。
そのため、企業のネームバリューだけに注目して転職活動をするのではなく、「自分の理想が叶うかどうか」を重視して企業を選ぶことが大切です。
転職先が決まるまで退職しない
現在勤めている会社を退職するのは、内定が決まってからがおすすめです。転職活動は3ヵ月ほどかかるといわれています。
場合によってはそれ以上に長引く可能性もあるので、退職してから転職活動をすると経済面での不安から、希望と異なる転職先を選んでしまう恐れがあります。
また、無職の期間が長いと、採用試験の際に不信感を持たれてしまうこともあります。
後悔しないためにも、突発的な考えで退職しないよう気を付けましょう。
年収が高い企業の倍率は高くなりやすい
当然ですが、年収が高い企業はその分人気が高く、採用試験の倍率も高くなりやすいです。
倍率が高いと内定獲得の難易度も上がってしまうので、年収の高い企業に絞って転職活動をしている場合、長期化する可能性が高くなります。
希望年収との折り合いをつけるのは難しいですが、どうしても譲れない条件以外はこだわりすぎないことが大切です。どれだけ収入があれば満足か必要な生活費などを確認しながら、しっかり考えて応募する企業を選ぶようにしましょう。
新卒の頃と同じ感覚で転職活動をしない
第二新卒と新卒では、企業側の採用基準が異なるのが特徴です。第二新卒は少なからず社会人としての経験があるため、採用試験の際にビジネスマナーもしっかりチェックされる傾向にあります。
また、企業のいいところだけしか捉えられていないような受け答えや応募書類は、第二新卒だと甘いとみなされてしまうこともあります。
そのため、企業研究は念入りにおこない、いい部分だけでなく大変な部分も理解したうえで応募書類を作成したり面接の受け答えを考えたりすることが大切です。
前職の退職理由を人のせい・会社のせいにしない
第二新卒に対する定番の質問に「前職の退職理由」がありますが、そこで前職の会社の不満や人間関係のせいだと伝えることはやめましょう。
たとえ本当のことであっても、採用担当者としては「また同じような理由でやめてしまうのでは?」と思ってしまいます。
そのため、前職の退職理由はネガティブなまま伝えず、「より専門的な知識を身につけたい」など前向きなポイントに焦点を当てて答えるようにしましょう。
門前払いされるか不安な第二新卒によくある質問
ここからは、第二新卒で転職する方からよくある質問について回答していきます。
1.第二新卒におすすめな企業の選び方は?
第二新卒におすすめの企業を選ぶポイントは、以下の2つです。
大手企業に限らず、以下のポイントにマッチしていれば、大きく失敗することはないでしょう。
成長企業を選ぶ
成長企業とは大手企業だけでなく中小企業やベンチャー企業の中でも、利益や事業規模が年々拡大し続けている企業のことです。成長企業は一人ひとりの目的意識が高い傾向にあります。
優良企業を選ぶ
自分の希望の働き方がある場合は、優良企業を選ぶのがおすすめです。
ただ、経営が安定している大手企業だからといって、実際に働きやすいかどうかは別問題です。給与や休日数、福利厚生、残業時間などは必ずチェックしておきましょう。
2.同じ会社で3年経験を積んでから転職するほうが有利って本当?
大手企業が募集要項に「就業経験3年」と定めている場合も多いため、大手企業への転職を目指す場合は、就業経験が3年あるほうが有利な傾向にあります。
そのため、確実に大手企業へ転職したいと考えている場合は、最低でも3年就業経験を積んでおくのがおすすめです。
ただし、すべての企業が就業経験を求めているわけではないので、「3年働いていないと絶対に無理」というわけではありません。
第二新卒で人気の大手企業へ転職するのはライバルも多いため、少しでも有利に進められるよう、転職するタイミングは考えるようにしましょう。
関連記事:新卒2年目の転職で「甘え」と思われないケースは?転職時の注意点や甘えと思われず成功させるポイントなどを解説
関連記事:新卒入社3年目での転職は早い?転職するべきかどうか判断するポイントを解説
3.第二新卒から大手企業への転職は難しい?
第二新卒が大手企業へ転職することは、難しいことではありません。少子高齢化の影響により若い働き手が不足しているため、第二新卒を採用する大手企業は増えています。
第二新卒は教育コストを削減できるなど、企業側にとってもメリットが多いので、新卒入社後の2〜3年後に大手企業への転職を目指すのはおすすめといえます。
とはいえ、大手企業となると応募者も多いのに加えて求人数も少ないため、しっかりと対策して採用試験に望むことが大切です。
4.第二新卒から大手企業の総合職へ転職はできる?
ハードルは高いですが、不可能ではありません。
とはいえ、個人の能力や、前職での経験によって転職できるかどうかの可能性は異なるでしょう。
関連記事:第二新卒で大手総合職に転職するポイントやおすすめの企業一覧を解説
5.第二新卒で優良企業に転職するには?
求人票に記載されている「給与」「福利厚生」「残業時間」などに注目してみましょう。
優良企業の場合、水準より高め、あるいは業務内容に見合った給与が設定されており、残業時間は少ない傾向にあります。
また、法律で定められている以外の福利厚生が充実している企業は、従業員を大切にしている事が多いです。
面接や社内見学などの際に、実際の社内の雰囲気が良いかも確認しておくと優良企業かどうかの判断材料になるでしょう。
まとめ|第二新卒での転職は門前払いしない企業選びが重要
本記事では第二新卒におすすめの企業や、転職を成功させるためのポイントなどについて解説しました。
あまりいい印象でなかった第二新卒は、働き手の不足や教育コストの観点からポジティブな印象へ変化しています。
それにより、大手企業でも積極的に第二新卒を採用する割合が増えてきているのが現状です。
とはいえ、大手企業は第二新卒の求人数も少なく人気も高いため、第二新卒で大手企業へ転職するのは容易ではありません。
転職のプロである転職エージェントを利用して、少しでも転職の成功率をアップさせるのがおすすめです。転職エージェントではプロのサポートが受けられるので、転職活動が初めての第二新卒でも安心して進められます。
今回紹介した内容を参考に、転職エージェントを利用して大手企業への転職を成功させてください。
転職エージェント5社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
公開求人数
51.6万件
非公開求人数
41.4万件
|
【初めて転職する方向け】20万件以上の中からピッタリの企業が見つかる。
|
|
|
★ 4.6
|
非公開
|
【未経験歓迎求人が豊富】大手企業からベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。
|
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
公開求人数
14.8万件
非公開求人数
非公開
|
【年収500万以上向け】レジュメ登録だけで自分の市場価値がわかる
|
|
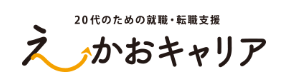 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
非公開求人
多数 |
【入社後の定着率97%】どんな仕事が向いているのか分からない方におすすめ
|
|
|
doda
★ 4.0
|
公開求人数
25.7万件
非公開求人数
2.2万件
|
【圧倒的な顧客満足度】未経験でチャレンジしたい方におすすめ
|
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
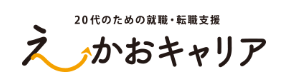 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
doda
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 4.8
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
|
★ 4.6
|
|
・初めての転職でしたが、マンツーマンでサポートしてくれました。
・未経験でも挑戦できる求人を多く紹介してくれました。 |
|
 ビズリーチ ビズリーチ
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
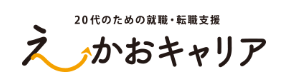 えーかおキャリア えーかおキャリア
★ 4.2
|
|
・自分一人で転職活動をしていたら、なかなか入れない企業への内定が決まりました。
・自分でもびっくりするくらいすぐに内定をもらえました! |
|
 doda doda
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |








