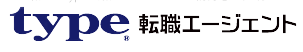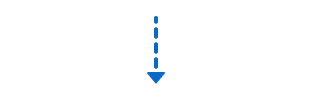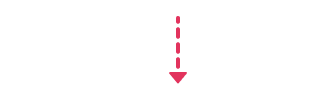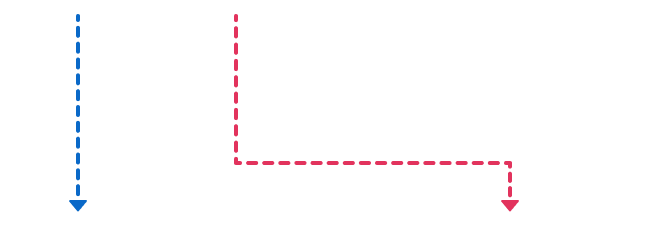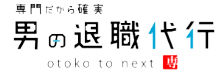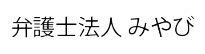「退職代行を利用したいけど、失敗したらどうしよう」と不安になっていませんか?
退職代行の失敗を防ぐには、代行業者選びが重要になります。一言で「退職代行」といっても、運営元は3つにわけられ、それぞれ対応できる業務範囲が異なるからです。
運営元ごとの退職代行業者の特徴を把握し、自分の状況に対応してもらえるところを選ぶと、失敗するリスクを減らせるでしょう。
※クリックで該当箇所にスキップします
あわせて読みたい⇒退職代行おすすめランキング23選|サービス内容や料金・評判を比較【最新版】
人気の退職代行サービスを徹底比較し、2024年で本当におすすめできる退職代行を紹介しています。
今すぐ1位の退職代行サービスを知りたい方は以下のボタンからチェックしてください。
| サービス | 料金 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
限定価格
24,800円 |
【当サイト限定価格24,800円】転職のフォローもある退職代行。有給休暇の無料申請や引っ越しなどの幅広いサポートを受けられる。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
19,800円 |
労働組合運営なので条件交渉もできる最もおすすめな退職代行。即日退職可能で会社とのやり取りも不要でスピード退社できる。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
24,000円 |
【退職代行実績10,000件以上】即日対応も可能な退職代行。最も安価で顧客満足度96%の安心安全なサービス。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
19,800円 |
退職相談実績30,000件以上で24時間LINE相談対応。有給消化やアフターフォローのサービスも充実。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
27,000円 |
人材紹介会社と提携の転職フォロー体制も万全。退職が全て完了するまで追加料金なしでサポートを受けられる。 |
| サービス | 相談方法 | 後払い・返金保証 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
転職フォローもあり
|
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
追加料金一切なし
|
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
| サービス | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
・自分ではできない退職成功率100%のJobsに任せて良かったです!
・限界状態の中、丁寧な対応に救われました。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
・サポートやフォローの対応が素早く、丁寧なサービスでした。
・利用方法もシンプルでわかりやすかったです。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
・後払いだったので、安心して利用できました。
・思い残しもなくスッキリとした退職ができました。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
・パワハラの恐怖の中でも丁寧なサポートで退職できました。
・スピード、親切さ、交渉などの全ての対応に満足でした。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
・うつ病気味だったけど即日退職できて、ニコイチに救われました。
・行きたくなかったから当日にお願いしました。 |
今の仕事をやめたいけど、
次の一歩が不安なあなたへ。
多くの人が、退職前に次の職場を決めることで、経済的にも精神的にも安心して新しいスタートを切っています。
次こそは…
- 人間関係が良好な職場で働きたい
- 頑張りを正当に評価してくれる職場で働きたい
- 残業や休日出社のないホワイトな職場で働きたい
このような思いの方は、転職エージェントに無料相談して、あなたにピッタリの求人を提案してもらうのがおすすめです。有益なアドバイスがもらえるだけでなく、履歴書作成から面接対策まで転職活動を完全無料でサポート。ストレスフリーな環境からの再スタートを目指せます。
転職エージェント5社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
公開求人数
58.3万件
非公開求人数
41.6万件
|
【圧倒的な求人数と転職支援実績】初めての転職なら登録すべきエージェント。
|
|
|
★ 4.6
|
非公開
|
【20~30代向け】有名大手企業からベンチャー企業まで幅広い求人を保有。
|
|
|
★ 4.5
|
公開求人数
14.9万件
非公開求人数
非公開
|
【転職者の1/3が年収アップ】レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。
|
|
|
★ 4.2
|
公開求人数
24.7万件
非公開求人数
2.4万件
|
【登録者数は業界最大級の約750万人】実績ノウハウをもとにしたマンツーマンサポート。
|
|
|
★ 4.0
|
公開求人数
1.3万件
非公開求人数
2.2万件
|
【年収アップ率71%】1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川)で転職する方におすすめ。
|
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
|
・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。
・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |
|
|
★ 4.6
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
|
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
|
★ 4.2
|
|
・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。
・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |
|
|
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
・関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
目次
退職代行での失敗例
退職代行での失敗例には、「交渉してもらえなかった」「書類が届かなかった」などがあげられます。
退職できなかった
退職代行を利用するからには退職したいと思うのは当然ですが、まれに退職できないケースも存在します。
たとえば、退職代行のサービスが不十分であり、退職の意思だけを代弁され放置されてしまった場合などです。
このようなケースでは、退職の手続きは終わっておらず、退職ではなく無断欠勤扱いとなっている可能性も否定できません。また、退職の手続きをしに出社するよう求められることもあり得ます。
出社した際に引き止めにあってしまうと、断り切れずに辞められないケースもあるでしょう。
退職代行に関して続報というか報告
— 星村奏音@猫メイド (@hoshimura___) December 22, 2022
結果から言えば金ドブに捨てただけになりました。
基本受け身で退職意志を伝えるだけであとは放置。何か特に連絡がある訳でもなくただただ“言えば終わり”だそうで。
全代行に言えるかは分からないけれど、男の退職代行に関してはおすすめ出来ないし
職場から連絡がきた
上司や同僚とこれ以上話したくなくて退職代行を利用したのに、職場から連絡がくるケースもあります。
退職代行を利用する方のなかには、「一切の連絡を絶ちたい」と思っている方もいるでしょう。しかし、退職の手続きや備品の返却について、あるいは今後の引き継ぎの相談などで連絡が入るケースは少なくありません。
自分の業務を引き継ぐ後任者から、資料の保管場所や業務の進捗状況の連絡がくる場合も考えられます。
「頻繁に連絡がくるのは避けたい」「スムーズに退職したい」際には、あらかじめ資料や業務内容をまとめておくと、結果的に職場からの連絡を防ぐ対策となるでしょう。
退職代行使っているのに、会社から電話・SMSでの連絡きたわ…
— 毛蝸牛@野槌庵 (@kema1ma1) January 23, 2023
「直接連絡取り合った方が楽だよね?」ってSMSできたから、「こちらはお金を払って退職代行を依頼しており、契約上の問題もありますので、退職代行からの返答次第で連絡を取り合うか決めさせて頂きます」と連絡しといた。
『退職代行の実行日、会社からの電話が鳴りやまない。無視して良い?』
— ひろし@退職代行の体験談を発信中 (@hiroshi_5963_) June 18, 2023
無視しても良いです。やりとりは退職代行業者を通じて行いましょう。
退職代行からの連絡はあるので、スマホの電源は落とさないようにして下さい。
残業代や有給消化の交渉ができなかった
「残業代や有給休暇を取得したかったのに、交渉できなかった」という失敗例もあります。
民間企業が運営する退職代行の場合、職場との交渉権をもっていません。そのため、仮に「残業代がほしい」という要望を伝えてもらったとしても、職場から「認められません」といわれてしまうと、それ以上の交渉はできないことになっています。
交渉できないゆえに、「残業代をもらえない」「有給消化ができない」「退職金を減らされた」といった不利な条件で退職しないためにも、退職代行業者は慎重に選ぶことが大切です。
あと残業代を払ってもらえないとか有給取れないとか精神的・肉体的に病気になりそうな状態だったら退職代行使わず弁護士に相談(弁護士のやってる退職代行っぽいサービスも可)をした方がお得だから…!会社都合退職になったり損害賠償や慰謝料も貰えるから…!相談先探すのFF外の人でも私手伝うし…!
— 舞姫 (@s_myhime) July 23, 2019
退職代行は、やっぱり弁護士がいい。
— ゆたちん@運の話は運のいい人には理解不能 (@yutachinthe1st) January 7, 2020
弁護士以外が有給消化とかの交渉できない、という情報は正しいようだ。
しかも辞める会社からさらに脅しが来ても、弁護士以外は対応できないみたい。
費用はさほど変わらないので、退職代行する方は弁護士を勧めます。
退職後に必要な書類が届かなかった
退職後に、離職票などの必要な書類をなかなか送ってもらえないパターンもあります。
「とりあえず退職できれば…」と思う方もいるかもしれませんが、離職票がなければ失業手当の受給などが困難になります。
また、源泉徴収票を受け取れなければ、正確な年収や所得税額、保険料控除などがわからず、転職先での年末調整や確定申告の際に苦労しかねません。
交渉可能な退職代行であれば、退職後の書類についてもサポートしてもらえる業者もあるため、事前に確認しておきましょう。
職場辞める時に退職代行会社を使い、無事に辞められたんだど…
— ☆ちづるるる(ゝω∂)-・*’* (@DesuyoChan) July 1, 2023
退職代行会社って入金するまですごく親切で、入金すると連絡疎遠になって不安だった。しかもLINEだけの連絡だし…
辞めたい時って心理状態も不安定の事が多いから、これから代行会社使う方は気をつけて下さいね!
#退職代行#会社辞めたい
即日の対応をしてもらえなかった
「即日対応可能!」としている退職代行も多く見受けられますが、全てのケースで即日対応ができ、即日で退職できるわけではありません。
たとえば、正社員の場合は、原則2週間前に退職の意向を伝えなければならないと民法で定められています(民法第627条1項)。
そのため、退職代行では退職の意向を伝えた翌日から2週間以上、有給休暇を利用する、あるいは欠勤対応にすることで、実質「即日退職」とするケースが多い傾向です。
一方、契約社員や派遣社員など、雇用期間が定められている契約を結んでいる場合は、原則、期間の満了まで退職することはできません。
即日退職をするためには、1年を超える契約期間であり、かつ契約の初日から1年以上経過している場合や、「やむを得ない理由がある」などの条件を満たす必要があります(民法第628条、労働基準法附則第137条)。
やっば、人柱になるつもりで退職代行使ってみたけどやり取り遅いクセに走り出し早すぎてちゃんと共有した情報で話し合ってるのか不安になってくる
— 犬太郎 配信とか (@dogtarodog) August 4, 2021
退職代行診断チャート
あなたに合う退職代行が見つかる!
辞めづらい
辞めづらい
仕事をしたくない...
解消するには?
失敗しないために知っておきたい退職代行の基礎知識
退職代行は、業者によって「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3つの運営元にわかれており、それぞれ業務内容が異なります。
退職代行で失敗しないためには、退職代行業者選びがカギになるため、確認して自分の目的にあう業者に依頼しましょう。
民間企業の退職代行サービス
一般企業が運営している退職代行サービスの業務内容は、「退職の意思伝達の代行」です。
依頼すると、退職代行業者から職場へ「〇〇さんが退職の意思を示しています」と伝えてもらえます。とはいえ、交渉はできない決まりとなっているため、職場から「退職は容認できません」と拒否されてしまうと、それ以上の返答はできません。
仮に言い返したり交渉したりしてしまうと、弁護士以外が対応してはならない法的行為を無資格者がおこなったこととなり、「非弁行為」という違法行為に該当してしまいます(弁護士法第72条)。
「労働組合」の退職代行サービス
労働組合が運営している退職代行サービスでは、退職の意思伝達のほか、「交渉」もおこなってもらえます。
弁護士ではないのに交渉ができる理由は、労働組合は「団体交渉権」という権利をもっているからです。
団体交渉権
労働者の自主的団体(通常は労働組合)が労働者の生活を守るため、労働条件その他の労働関係につき、使用者または使用者団体と交渉を行う権利。
引用元:団体交渉権とは?|コトバンク
たとえば、退職の意思表示に対して、職場から「認められません」と拒否された場合でも、「労働者には退職の自由があり、申し入れる権利がありますよ」といった具合に交渉してもらえます。
なお、残業代の請求なども交渉してもらえる可能性はあるものの、訴訟に発展した際に、労働組合の退職代行では対応できません。法的な手続きについては、弁護士に改めて依頼する必要があることを理解しておきましょう。
「弁護士」の退職代行サービス
3つの運営元のうち、業務範囲が最も広いのが、弁護士が運営している退職代行サービスです。弁護士の退職代行では、以下の業務に対応してもらえます。
- 退職の意思の伝達
- 退職に関する交渉
- 有給休暇の交渉
- 離職票・源泉徴収票の請求
- 残業代・未払い給与・退職金などの請求
- 損害賠償などの法律業務
「退職を認めてもらえない」ケースのほか、「書類を送ってもらえない」場合や、「これまでのパワハラに対する慰謝料を請求したい」といった場合には、弁護士の退職代行であれば、心強いサポートを受けられるでしょう。
| サービス | 料金 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
限定価格
24,800円 |
【当サイト限定価格24,800円】転職のフォローもある退職代行。有給休暇の無料申請や引っ越しなどの幅広いサポートを受けられる。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
19,800円 |
労働組合運営なので条件交渉もできる最もおすすめな退職代行。即日退職可能で会社とのやり取りも不要でスピード退社できる。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
24,000円 |
【退職代行実績10,000件以上】即日対応も可能な退職代行。最も安価で顧客満足度96%の安心安全なサービス。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
19,800円 |
退職相談実績30,000件以上で24時間LINE相談対応。有給消化やアフターフォローのサービスも充実。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
27,000円 |
人材紹介会社と提携の転職フォロー体制も万全。退職が全て完了するまで追加料金なしでサポートを受けられる。 |
| サービス | 相談方法 | 後払い・返金保証 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
転職フォローもあり
|
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
追加料金一切なし
|
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
| サービス | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
・自分ではできない退職成功率100%のJobsに任せて良かったです!
・限界状態の中、丁寧な対応に救われました。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
・サポートやフォローの対応が素早く、丁寧なサービスでした。
・利用方法もシンプルでわかりやすかったです。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
・後払いだったので、安心して利用できました。
・思い残しもなくスッキリとした退職ができました。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
・パワハラの恐怖の中でも丁寧なサポートで退職できました。
・スピード、親切さ、交渉などの全ての対応に満足でした。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
・うつ病気味だったけど即日退職できて、ニコイチに救われました。
・行きたくなかったから当日にお願いしました。 |
失敗しないための退職代行の選び方
自分に合う退職代行を選ぶ際には、費用やサービス内容、「交渉することになりそうかどうか」などの面から考えてみると、失敗や後悔をするリスクを減らせるはずです。
自分の状況に対応してもらえる代行業者を選ぶ
自分の目的に対応してもらえる代行業者を選びましょう。
たとえば、「辞めたいけど引き止められそう」といった場合には、交渉に進展する可能性が考えられます。交渉できる退職代行は、労働組合や弁護士が運営している業者に限られており、民間企業が運営する退職代行ではできません。
同じように、「未払い給与も支払ってほしい」という場合、会社が交渉に応じず訴訟に発展しそうなケースでは、弁護士が運営している退職代行に依頼したほうが賢明です。
このように、自分の目的によって対応できる代行業者が限られてくるため、意図に合ったところを選ばなければ、「業務の対象外」となり、対応してもらえません。その結果、失敗したと感じてしまうでしょう。
トラブルや訴訟などの問題が起きる可能性がある場合はとくに、「交渉ができる」「請求ができる」など考えられる状況に対応してもらえる代行業者を選ぶことが大切です。
サービス内容から選ぶ
サービス内容から選ぶのも、ひとつの方法です。
退職代行では、「24時間対応」や「オンラインのみでやりとりが完結」「後払いができる」など、さまざまなサービスが展開されています。
日中に連絡をとるのが難しい方や、深夜まで勤務が入っている方などは、24時間対応している退職代行を選ぶと連絡をとりやすく、便利に利用できるでしょう。
人とのコミュニケーションが苦手な方にとっては、オンラインで完結できれば、臆せず安心して相談できるかもしれません。
費用から選ぶ
費用を基準に選ぶこともできます。
各退職代行によって詳細な金額は異なりますが、おおよその相場では、以下のようになっています。
- 民間企業 … 約2万円~3万円
- 労働組合 … 約2.5万円~3万円
- 法律事務所 … 約5万円~
「それなら、できるだけ最安のところがいい」と思うかもしれませんが、安さだけで選んでしまうのはおすすめできません。なぜなら、追加費用やサービス内容によっても金額は変動するからです。
本来退職は、自分で意思を伝えて手続きをすると費用はかかりません。費用は気になるところですが、あわせて業務範囲や追加費用の有無、代行業者の評判なども確認してから選ぶようにしましょう。
退職代行を利用する前に確認すべき注意点
退職代行は、利用者にとって「出社せずに退職できる」メリットがありますが、リスクもあります。利用する前に確認しておきましょう。
職場からの連絡を完全に絶つことは難しい
職場からの連絡を完全にシャットアウトするのは難しいことを心得ておきましょう。
「出社せずに辞めたい」「上司に会わずに辞めたい」と思うかもしれませんが、退職するためには、どうしても事務手続きが必要です。
また、退職にあたり、上司は業務をほかの社員に割り振ったり、後任者を選出したりしなければなりません。そのため、進捗状況を把握するために連絡してくるケースも少なくありません。
連絡がくるのが嫌な場合は、事前に引き継ぎ書を作成しておき、業務の進捗状況や資料の保管場所などを記載しておくのが有効といえます。
それでも、手続きの連絡は入ることがあります。退職するまでは、職場と完全には連絡を絶ち切れない点は踏まえておきましょう。
公務員は退職代行サービスを利用できない可能性がある
公務員の場合、退職代行を利用できない可能性があります。
なぜなら、雇用に関する法制度や手続きが一般企業とは異なるためです。
一般企業では、「退職の意思を示した日から2週間経過すると退職できる」と民法で定められていますが、公務員は国家公務員法や地方公務員法などの規定に従わなければなりません。
公務員の規定では、第三者による退職が原則不可能となっており、「任命権者による同意と手続き」が必要になります。
そのため、退職代行の介入が難しく、民間企業や労働組合が運営している退職代行では、公務員をサービスの対象外としているところもあります。
最低限の「引き継ぎ」はしておくのが無難
最低限の引き継ぎはしておきましょう。
引き継ぎせずに辞めたいと考える方もいるかもしれませんが、かえって上司や後任者から頻繁に連絡がきてしまう可能性があります。
引き継ぎ書や資料のデータ一覧などを作成しておけば、上司や後任者から連絡がくるのを防ぐことにもつながるはずです。
退職代行のおすすめ人気ランキング比較一覧
退職代行サービスのおすすめ比較ランキングは以下の通りです。
各サービスの特徴や料金について比較してありますので、ぜひ参考にしてみてください。(左右にスクロールできます。)

| サービス | リンク | 口コミ・評判 | 料金 | ポイント | 後払い対応 | 返金保証(全額) | 転職フォロー | 弁護士監修 | 支払い方法 | 相談方法 | 対応時間 | 運営元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 口コミを見る |
24,800円〜
|
条件交渉やアフターフォローなどのサービスが充実
|
クレジットカード
銀行振込
コンビニ決済
Paidy
|
LINE
メール
電話
|
24時間対応可能
|
株式会社アレス
|
||||||
| 詳細 | 口コミを見る |
19,800円
|
迷ったらココ!労働組合運営で即時退職もできる退職代行サービス
|
 |
クレジットカード
銀行振込
|
LINE
電話
|
24時間対応可能
|
東京労働経済組合
|
|||||
| 詳細 | 口コミを見る |
24,000円
|
退職代行実績10,000件以上で即日対応も可能な退職代行サービス
|
クレジットカード
銀行振込
|
LINE
|
24時間対応可能
|
株式会社5core
|
||||||
| 詳細 | 口コミを見る |
19,800円
|
すべての連絡やサポートがLINEのみで完結。
|
クレジットカード
銀行振込
Apple Pay,Google Pay
|
LINE
|
24時間対応可能
|
株式会社warabe
|
||||||
| 詳細 | 口コミを見る |
27,000円
|
人材紹介会社と提携の転職フォロー体制も万全
|
 |
クレジットカード
銀行振込
PayPay
Apple Pay,Google Pay
|
LINE
メール
電話
|
電話のみ7:00~23:30
|
株式会社ニコイチ
|
|||||
| 詳細 | 口コミを見る |
19,800円
|
有給消化や退職後のサポートが充実していて労働組合運営
|
 |
クレジットカード
銀行振込
Apple Pay,Google Pay
|
LINE
|
24時間対応可能
|
株式会社アニマルバンク
|
|||||
| 詳細 | 口コミを見る |
24,000円
|
完全後払い制で利用できる退職代行サービス
|
 |
 |
クレジットカード
|
LINE
電話
|
24時間対応可能
|
株式会社25H
|
||||
| 詳細 | 口コミを見る |
アルバイト/パート
19,800円 正社員/派遣/契約社員 26,800円 |
男性向けで日本退職代行協会JRAAの特級認定を取得しているサービス
|
クレジットカード
銀行振込
コンビニ決済
キャリア決済
楽天ペイ
PayPay
Paidy
|
LINE
メール
|
24時間対応可能
|
合同労働組合
退職代行toNEXTユニオン |
||||||
| 詳細 | 口コミを見る |
アルバイト/パート
19,800円 正社員/派遣/契約社員 29,800円 |
女性向けで日本退職代行協会JRAAの特級認定を取得しているサービス
|
クレジットカード
銀行振込
コンビニ決済
キャリア決済
楽天ペイ
PayPay
Paidy
|
LINE
メール
|
24時間対応可能
|
合同労働組合
退職代行toNEXTユニオン |
||||||
| 詳細 | 口コミを見る |
着手金
55,000円 |
弁護士が運営していて法的業務も対応可能
|
 |
 |
銀行振込
|
LINE
メール
|
24時間対応可能
|
弁護士法人みやび
|
失敗しないおすすめの退職代行サービス3選
おすすめの退職代行サービスを3つ紹介します。
退職代行Jobs

退職代行Jobsは、民間企業が運営している退職代行サービスです。
運営元は民間企業ですが、労働組合と提携しているため、交渉にも対応してもらえます。
また、顧問弁護士の監修のもと、サービスが運営されているため、非弁行為の心配がなく、安心して依頼できるでしょう。
労働組合費がかかりますが、追加費用がかからない点もメリットです。
| 運営元の種類 | 労働組合と提携/顧問弁護士監修 |
| 料金 | 2万7,000円→当サイト限定価格2万6,000円 + 労働組合費2,000円(税込) |
| 交渉権 | あり |
| 24時間対応 | あり |
| 相談方法 | LINE・メール・電話 |
| 公式ホームページ | https://jobs1.jp/ |
退職代行ガーディアン
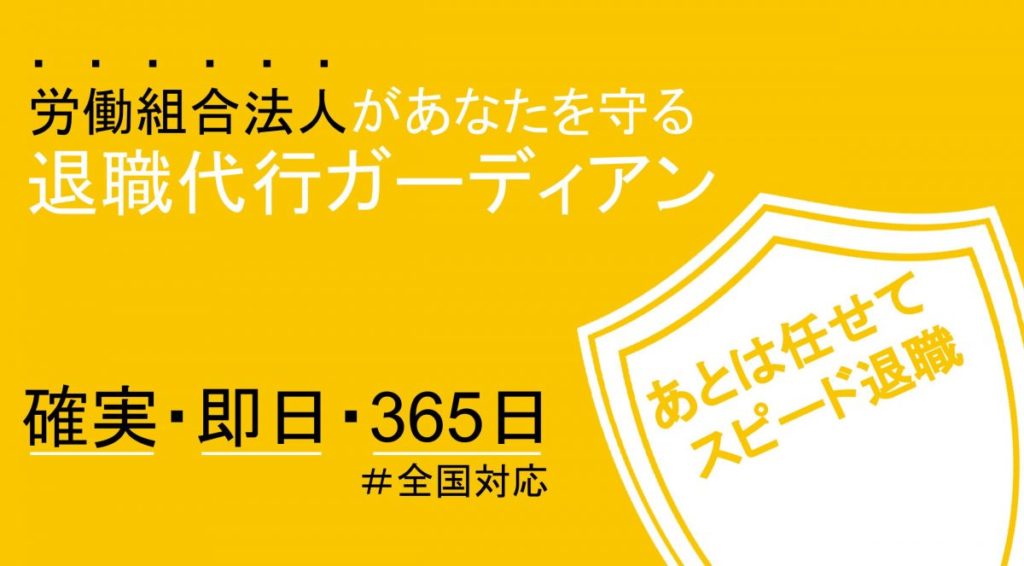
退職代行ガーディアンは、労働組合が運営している退職代行サービスです。
団体交渉権を有しているため、退職に関する交渉にも対応してもらえます。
また、雇用形態に関わらず一律料金であり、追加費用がかからないところも魅力です。
全国対応であり、相談から退職までスマートフォン1台で完結できるため、都市部だけでなく地方在住の方にも使いやすいサービスといえるでしょう。
| 運営元の種類 | 労働組合 |
| 料金 | 2万9,800円(税込) |
| 交渉権 | あり |
| 24時間対応 | あり |
| 相談方法 | LINE・電話 |
| 公式ホームページ | https://taisyokudaiko.jp/ |
退職代行OITOMA

退職代行OITOMAは、株式会社5coreが運営している退職代行サービスです。
労働組合が運営している退職代行の中でも、費用水準が低いという特徴があるので、「退職代行を使ったことがなくて不安...」という方も比較的気軽に利用を進めることができます。
また、追加料金もなく、退職完了まで無制限で相談・サポートしてもらえるため、安心してサービスを利用できるでしょう。
まとめ
退職代行で失敗しないためには、「退職代行選び」が重要です。
自分の目的に合った対応をしてもらえるか、サービス内容・費用などに納得できるかをよく確認してから選びましょう。
「失敗したくない」「不安が大きい」という方は、最初に無料相談をしてみるのもおすすめです。
スタッフの対応などもわかるため、自分に合うかどうかの判断基準にもできるでしょう。
| サービス | 料金 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
限定価格
24,800円 |
【当サイト限定価格24,800円】転職のフォローもある退職代行。有給休暇の無料申請や引っ越しなどの幅広いサポートを受けられる。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
19,800円 |
労働組合運営なので条件交渉もできる最もおすすめな退職代行。即日退職可能で会社とのやり取りも不要でスピード退社できる。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
24,000円 |
【退職代行実績10,000件以上】即日対応も可能な退職代行。最も安価で顧客満足度96%の安心安全なサービス。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
19,800円 |
退職相談実績30,000件以上で24時間LINE相談対応。有給消化やアフターフォローのサービスも充実。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
27,000円 |
人材紹介会社と提携の転職フォロー体制も万全。退職が全て完了するまで追加料金なしでサポートを受けられる。 |
| サービス | 相談方法 | 後払い・返金保証 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
転職フォローもあり
|
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
追加料金一切なし
|
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
| サービス | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
・自分ではできない退職成功率100%のJobsに任せて良かったです!
・限界状態の中、丁寧な対応に救われました。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
・サポートやフォローの対応が素早く、丁寧なサービスでした。
・利用方法もシンプルでわかりやすかったです。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
・後払いだったので、安心して利用できました。
・思い残しもなくスッキリとした退職ができました。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
・パワハラの恐怖の中でも丁寧なサポートで退職できました。
・スピード、親切さ、交渉などの全ての対応に満足でした。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
・うつ病気味だったけど即日退職できて、ニコイチに救われました。
・行きたくなかったから当日にお願いしました。 |
今の仕事をやめたいけど、
次の一歩が不安なあなたへ。
多くの人が、退職前に次の職場を決めることで、経済的にも精神的にも安心して新しいスタートを切っています。
次こそは…
- 人間関係が良好な職場で働きたい
- 頑張りを正当に評価してくれる職場で働きたい
- 残業や休日出社のないホワイトな職場で働きたい
このような思いの方は、転職エージェントに無料相談して、あなたにピッタリの求人を提案してもらうのがおすすめです。有益なアドバイスがもらえるだけでなく、履歴書作成から面接対策まで転職活動を完全無料でサポート。ストレスフリーな環境からの再スタートを目指せます。
転職エージェント5社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
公開求人数
58.3万件
非公開求人数
41.6万件
|
【圧倒的な求人数と転職支援実績】初めての転職なら登録すべきエージェント。
|
|
|
★ 4.6
|
非公開
|
【20~30代向け】有名大手企業からベンチャー企業まで幅広い求人を保有。
|
|
|
★ 4.5
|
公開求人数
14.9万件
非公開求人数
非公開
|
【転職者の1/3が年収アップ】レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。
|
|
|
★ 4.2
|
公開求人数
24.7万件
非公開求人数
2.4万件
|
【登録者数は業界最大級の約750万人】実績ノウハウをもとにしたマンツーマンサポート。
|
|
|
★ 4.0
|
公開求人数
1.3万件
非公開求人数
2.2万件
|
【年収アップ率71%】1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川)で転職する方におすすめ。
|
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
|
・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。
・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |
|
|
★ 4.6
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
|
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
|
★ 4.2
|
|
・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。
・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |
|
|
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
・関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |