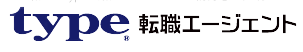現在民間企業で働いている方の中には、公務員への転職を志している方もいるでしょう。
公務員には福利厚生の充実や安定した給与などの良いイメージがあり、中には「給料を上げたい」「リストラの不安をなくしたい」などの理由で目指す方もいるかもしれません。
しかし、民間企業から公務員への転職は簡単ではありません。公務員への転職には、メリットと同時にデメリットがあることも知っておくべきでしょう。
この記事では、民間企業から公務員への転職について、両者の違いや公務員への転職のメリット・デメリットのほか、志望動機を考えるうえでのポイントや注意点などを解説します。
転職エージェント5社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 5.0
|
公開求人数
14.9万件
非公開求人数
非公開
|
転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。
|
|
|
★ 4.8
|
公開求人数
58.3万件
非公開求人数
41.6万件
|
まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。
|
|
|
★ 4.6
|
非公開
|
人材大手マイナビが運営する転職エージェント。特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。
|
|
|
★ 4.2
|
公開求人数
24.7万件
非公開求人数
2.4万件
|
新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。
|
|
|
★ 4.0
|
公開求人数
1.3万件
非公開求人数
2.2万件
|
1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川)に絞って質の高い求人情報を提供しているエージェント。企業との間に太いパイプがあり、年収アップ率はなんと71%。
|
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 5.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 5.0
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
|
★ 4.8
|
|
・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。
・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |
|
|
★ 4.6
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
|
★ 4.2
|
|
・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。
・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |
|
|
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
・関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
占い感覚の無料キャリアカウンセリング実施中
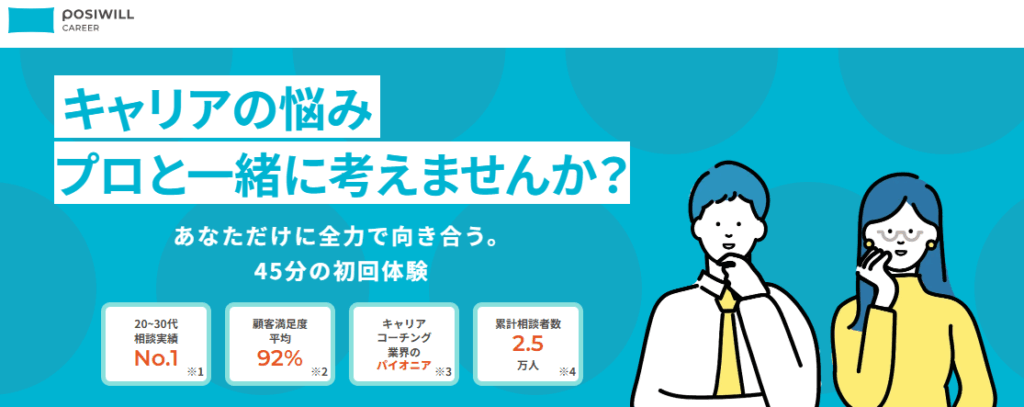
- 転職以外の選択肢も気になる、やりたいことがわからない方大歓迎
- どんな仕事の悩みもキャリアのプロに相談OK
- 『自己分析』や『適職診断』が好評
- 転職をすすめられる心配やしつこい電話もなし
- 「転職しないほうがいいかも」と気付く人も続出中
関連記事:公務員への転職におすすめの転職エージェント7選|選び方と使いこなすコツも解説
目次
民間企業から公務員への転職はできる?
結論からいうと、民間企業から公務員への転職は可能です。国家公務員を例に挙げると、2021年度経験者採用試験では198人の方が新たに採用されています。
公務員に転職するためには、国や地方自治体で実施される試験に合格しなければいけません。民間企業の転職とは違い、一斉に採用試験が実施されるため、受験申込締め切り日や試験日などのスケジュールはあらかじめ決められていることがほとんどです。
公務員に転職する方法には、大きく分けて通常の公務員試験である「一般受験」と、社会人からの転職を受け入れる「社会人経験者採用受験」の2種類があります。
社会人向けの枠が設けられているため、民間企業から公務員への転職は可能であるといえますが、募集職種によっては応募できる年齢が決められていることもあるようです。
たとえば、国家公務員の院卒者試験・大卒程度試験では、国家総合職や国家一般職、外務省専門職員、法務省専門職員などの受験資格を30歳未満としています。
対して、経済産業省で2022年度に実施されている課長補佐級・係長級を対象とした中途採用試験では、年齢制限は設けられていません。
地方公務員の場合は、自治体によって年齢制限が異なります。
北海道職員採用では、大卒程度を対象としたA区分では年齢制限を30歳以下、社会人を対象としたC区分では31~59歳としています。大阪府職員採用試験では大学卒程度行政職の受験資格を22~25歳、社会人等の行政職では49歳までとしており、自治体や職種によって大きく異なるようです。
年齢や経験に応じて、大卒程度区分の採用試験か、または民間企業での経験を活かせる社会人経験者採用試験か、どちらを受験するか決めるといいでしょう。
【参考記事】
国家公務員 経験者採用試験|人事院 ※最終合格者数の合計から採用人数を算出
国家公務員採用試験の概要 -院卒者試験・大卒程度試験-|人事院
2022年度選考採用情報|財務省
A区分(一般行政(第1回)・教育行政(第1回)・総合土木(専門試験口述型)(第1回)・普及職員(農業)(専門試験口述型)(第1回))|北海道
C区分|北海道
令和5年度大阪府職員採用試験実施予定|大阪府
民間企業と公務員の違いとは?
民間企業と公務員では、「雇用の安定性」と「利益の追求」の面に主な違いがあります。
日本国憲法では、公務員は「全体の奉仕者」と位置づけられ(日本国憲法第15条第2項)、国や地方自治体に所属して業務を遂行します。国や地方自治体が破綻して公務員がリストラされるような事態はほとんど起こり得ないため、安定して働ける仕事だといえるでしょう。
一方、民間企業の場合、企業の平均寿命は30年というのが通説で、実際2021年に倒産した企業の平均寿命は23.8年となっています。22歳で入社した人が45歳になったときに会社が倒産してしまうと考えれば、民間企業の不安定さがわかるはずです。
【参考記事】倒産企業の平均寿命23.8年 3年ぶりに上昇【2021年】|東京商工リサーチ
倒産や業績不振を回避するために、民間企業では業績を上げて利益を追求する必要があります。社員一人ひとりが利益を生み出す意識をもって業務に取り組むことは、公務員との大きな違いでしょう。
対して、公務員は営利ではなく公共への奉仕を目的としています。国や地域のために働くという使命感をもって、業務に取り組むのが特徴です。
民間企業から公務員へ転職するメリットとデメリット
民間企業から公務員への転職を考える際、メリットばかりに目を向けがちですが、デメリットも存在します。
デメリットを把握しないまま公務員に転職すると、「こんなはずではなかった」と後悔してしまうかもしれません。民間企業から公務員に転職するメリット・デメリットを理解したうえで、慎重に転職を判断しましょう。
民間企業から公務員へ転職するメリット
最初に民間企業から公務員に転職する際のメリットについて紹介します。メリットは大きく分けて以下の3つがあります。
- 将来設計がしやすい
- 地域や国のために仕事ができる
- 退職金が多い
将来設計がしやすい
公務員は国や地方自治体に所属するため、倒産がなく、リストラされる可能性が低い職業です。雇用や給与が安定しているので、将来設計を立てやすいメリットがあります。
たとえば、公務員は収入が安定していて、年功序列で年齢とともに昇給していくため、早期にマイホームを購入しやすいでしょう。公務員は返済能力や信用力が高いとみなされるので、金融機関からの借り入れもしやすい傾向にあります。
また、地方公務員であれば転勤の心配はほとんどなく、希望の地域に根差して生活できることもメリットです。
また、福利厚生が充実していることも特徴で、特に育児のための制度は民間企業よりも手厚いといえるでしょう。育児休業は子どもが3歳になるまで取得できるうえ、子どもが未就学の間は短時間勤務が認められています。子どもを育てながら就業できる制度が整っているため、女性でも将来設計を立てやすいことも公務員の魅力といえます。
【参考記事】育児のための主な制度概要【常勤職員用】|人事院
地域や国のために仕事ができる
公務員には売上目標や営業ノルマがなく、公共への奉仕を意識して仕事に取り組みます。国や地域で暮らしている人たちのために仕事ができるのは、公務員ならではの魅力でしょう。
一方、民間企業の使命は、売上を伸ばしたりマーケットを拡大したりして、自社の利益を追求することです。
「地域の発展のため」などの経営理念があったとしても、業績不振に陥ると従業員の給与に直結するので、企業を発展させることを常に意識する必要があります。
公務員は利益を追い続けるのではなく、社会貢献のために力を尽くしたい方に向いている仕事といえます。
退職金が多い
国や地方自治体の業務に従事する公務員には、退職金支給額の面でもメリットがあります。
民間企業、国家公務員、地方公務員の定年退職金の平均金額は以下のとおりです。なお、民間企業の調査結果に合わせて、2018年の調査結果を用いて比較しました。
| 定年退職時の勤務先 | 定年退職金の平均額(2018年) |
| 民間企業 | 1,983万円 |
| 国家公務員 | 2,068万 |
| 地方公務員 | 2,213万7,000円 |
【参考記事】
第44表 学歴・職種、勤続年数階級、企業規模別定年退職者1人平均退職給付額(2018年)|e-Stat政府統計の総合窓口 ※企業規模計「大学・大学院卒(管理・事務・技術職)」の給付額
退職手当の支給状況(2018年度)|内閣官房内閣人事局 ※常勤職員の定年退職手当金額
第15表 団体区分別,職員区分別,退職事由別,年齢別退職者数及び退職手当額|平成30年 地方公務員給与の実態|総務省 ※「25年以上勤務 定年退職・その他」の全職員の平均手当額
それぞれの退職金平均額を比較すると、民間企業の退職金平均金額が2,000万円に満たないのに対し、国家公務員・地方公務員の退職金平均額はいずれも2,000万円を超えています。
特に、地方公務員と民間企業の間には約230万円もの差があり、公務員は退職金の面でも民間企業より恵まれているといえそうです。
くわえて、公務員の退職金支給は国家公務員退職手当法、または地方自治体の条例などで定められているため、今後退職金の減額があったとしても、退職金制度がなくなる可能性は低いでしょう。
民間企業から公務員へ転職するデメリット
メリットだけを見ていると、民間企業から公務員への転職には利点が多いように感じますが、公務員へ転職することにはデメリットもあります。
民間から公務員へ転職する3つのデメリットについて紹介していきます。
予想以上に業務は過酷
前述したように、公務員は福利厚生が充実しているうえ、有給取得などの制度が整っています。
2019年度の調査によると、民間企業の年間有給平均取得日数が10.1日であったのに対し、国家公務員の平均取得日数は14.9日、地方公務員は11.7日でした。
このような背景もあり、「民間企業と比較して残業もなく、定時で帰宅できるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、実際は公務員でも残業はあります。仕事の内容によって業務の多忙さは異なりますが、深夜まで残業が続くケースも珍しくはないようです。
人事院が公表している国家公務員の残業に関する調査結果によると、他府省の影響で残業が発生しやすい「他律部署」においては、全体の13.6%の方が月間残業時間の上限を超えて残業していることがわかりました。ひと月100時間未満の上限時間を超えている方は7.2%で、本府省に限定すると13.8%にも上ります。
さらに、実際に残業した時間に対して、満額の残業代が支払われないことも起こり得るようです。株式会社ワークライフ・バランスがおこなった調査によると、「残業代が正しく支払われていない」と回答した国家公務員は28.2%で、残業代なしのサービス残業を強いられている方もいることがわかります。
また、2019年度に公表された地方公務員の残業時間に関する調査によると、地方公務員の時間外勤務数は月平均11.9時間、本庁に限定すると月平均14時間となっています。残業時間が月45時間を超えている方の割合は4.8%、100時間以上の方は0.3%でした。
このように、転職前に想像していた以上に公務員の業務は過酷である可能性があります。公務員だからといって「定時に帰れる」「残業代は全額もらえる」というわけではないことは、転職前に理解しておくべきでしょう。
【参考記事】
地方公務員における働き方改革に係る状況 ~令和元年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要~|総務省
第3章 良好な勤務環境の整備 1 長時間労働の是正(2021年度)|人事院
【プレスリリース】【コロナ禍における中央省庁の残業代支払い実態調査】 全額支払い指示後もなお3割が残業代を正しく支払われていないことが判明 残業代を最も正確に支払っていないのは「財務省」「厚生労働省」|株式会社ワーク・ライフバランス
年功序列の昇進・昇給制度が民間より根強い
最近では、年功序列を廃止して能力に応じた昇進・昇給の評価制度に切り替える企業も徐々に増えてきているようです。仕事ぶりや成果が評価され、若くして役職に就くなど、若い世代のやりがいにもつながっているでしょう。
一方、公務員の給料は号級制で定められており、年功序列の評価制度が根強く残っているようです。2022年には内閣人事局と人事院の若手職員が年功序列による昇進制度の廃止を含む提言を政府に提出しました。
年功序列の評価制度は長く勤めるほど年収がアップし、役職も上がっていくため、将来設計がしやすいメリットがあります。一方、どれだけ能力が高くても年齢が若いと給与が上がらず、モチベーションの低下につながる可能性もあるでしょう。
公務員に転職すると、年功序列の評価制度にストレスを感じることがあるかもしれません。若くても能力を発揮し、成果をあげ、出世していきたいという願望が強い方は、公務員よりも民間企業で働くほうが合っているといえます。
給与が前職よりも下がる可能性もある
現在勤務している企業によっては、公務員に転職すると給与が前職よりも下がるケースもあり得ます。
それでも、「国や地域のために仕事をしたい」という強い信念があれば問題ないかもしれません。しかし、収入アップに期待して転職を考えているのであれば、ケースによっては考え直す必要があるでしょう。
国家公務員の平均年収は673万円、地方公務員の平均年収は643万円です。もちろんこの金額は平均値なので、実際はもっと少なかったり高かったりする可能性もあります。
あくまでもひとつの目安として、現在の年収と比較してみるといいでしょう。
【参考記事】
令和3年国家公務員給与等実態調査報告書|人事院…①
期末・勤勉手当(ボーナス)|国家公務員の給与(令和4年版)|内閣官房内閣人事局…② ※国家公務員の年収は、①の「平均給与月額×12ヵ月分」と②の「期末・勤勉手当(ボーナス)」の数値をもとに算出
第5表 職種別職員の平均給与額|令和3年 地方公務員給与の実態|総務省 ※地方公務員の年収は、「給与月額合計×12ヵ月分」と「期末手当」「勤勉手当」を合計して算出
転職エージェント5社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 5.0
|
公開求人数
14.9万件
非公開求人数
非公開
|
転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。
|
|
|
★ 4.8
|
公開求人数
58.3万件
非公開求人数
41.6万件
|
まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。
|
|
|
★ 4.6
|
非公開
|
人材大手マイナビが運営する転職エージェント。特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。
|
|
|
★ 4.2
|
公開求人数
24.7万件
非公開求人数
2.4万件
|
新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。
|
|
|
★ 4.0
|
公開求人数
1.3万件
非公開求人数
2.2万件
|
1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川)に絞って質の高い求人情報を提供しているエージェント。企業との間に太いパイプがあり、年収アップ率はなんと71%。
|
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 5.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 5.0
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
|
★ 4.8
|
|
・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。
・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |
|
|
★ 4.6
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
|
★ 4.2
|
|
・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。
・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |
|
|
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
・関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
占い感覚の無料キャリアカウンセリング実施中
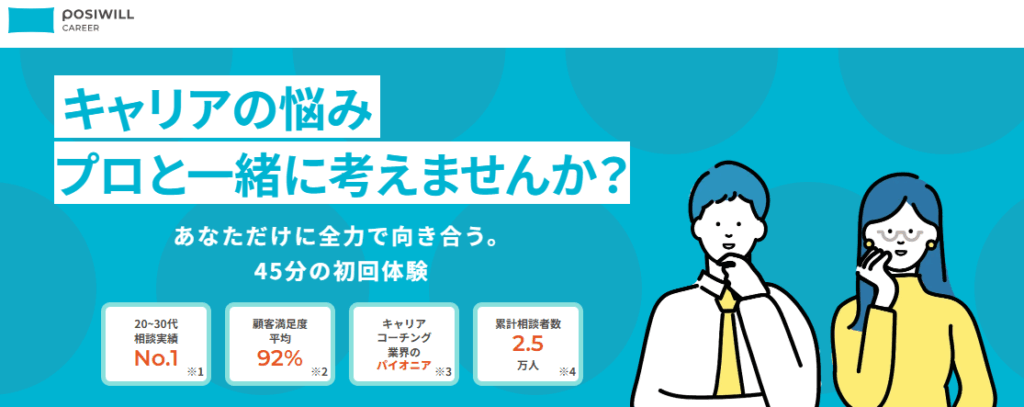
- 転職以外の選択肢も気になる、やりたいことがわからない方大歓迎
- どんな仕事の悩みもキャリアのプロに相談OK
- 『自己分析』や『適職診断』が好評
- 転職をすすめられる心配やしつこい電話もなし
- 「転職しないほうがいいかも」と気付く人も続出中
民間から公務員へ転職する方法
メリット・デメリットをしっかり理解したうえで、民間企業から公務員へ転職したいと決断した場合、避けて通れないのが公務員試験です。
公務員試験は筆記試験だけでなく、民間企業への転職と同じように面接もあります。また、職種によっては適性検査の一環として体力測定がおこなわれることもあるようです。
公務員試験の流れとしては、試験に合格すると「採用候補者名簿」に登録され、その中から志望府省の面接を経て採用されたり、成績優秀者順に内定が決まったりするのが一般的です。係長級以上の採用試験の場合には、第1次~第3次試験まであり、筆記試験、論文、グループ討議、面接を経て内定となるケースもあります。
民間企業から民間企業への転職であれば、書類選考と面接で採用されるかどうかを判断されるため、一般教養を試される筆記試験があるケースはほとんどありません。
筆記試験の準備を確実にしておかなければ合格できないため、その準備に時間を割く必要があることが公務員への転職の特徴です。
なお、公務員へ転職する際には、一般受験枠と社会人経験者採用枠の2種類があります。採用枠によって申し込み期間が定められているため、人事院や地方自治体の採用情報を十分に確認しましょう。
【参考記事】国家公務員試験採用情報NAVI|人事院
一般受験枠で受験する
一般受験枠とは、院卒者、または大卒程度の方を対象とした公務員試験のことです。一般受験枠は筆記試験の難度が高く、大学卒業程度の学力が要求されます。
公務員試験の筆記試験は内定者を絞り込むための試験であるため、ここでかなりの人数が落とされます。たとえば、2021年に実施された国家公務員試験では、総合職試験の合格率は院卒者で約40%、大卒程度で約9%、一般職の大卒程度の合格率は約27%、高卒者は約24%でした。
なお、国家公務員試験の場合、試験のあとに志望府省での面接があり、試験合格者の中からさらに採用者が絞り込まれることになります。
受験先によって異なりますが、具体的には以下のような内容で試験がおこなわれます。
【国家公務員(行政区分)】
| 総合職 | 一般職 | |
| 年齢制限 | 【院卒】30歳未満 【大卒程度】21歳以上30歳未満 |
21歳以上30歳未満 |
| 申し込み方法 | インターネット | インターネット |
| 試験内容 | 【第1次試験】基礎能力試験/専門試験 【第2次試験】専門試験(記述式)/政策課題討議試験/人物試験/英語試験 ※法務区分以外の区分の場合 |
【第1次試験】基礎能力試験/専門試験/一般論文試験 【第2次試験】人物試験 |
| 採用スケジュール | 【春試験】 ・受付:3月頃 ・第1次試験:4月頃 ・第2次試験:5月頃 ・最終合格者発表:6月頃 |
・受付:3~4月頃 ・第1次試験:6月頃 ・第2次試験:7月頃 ・最終合格者発表:8月頃 ・官庁訪問、面接を経て採用 |
【参考記事】
国家公務員試験ガイド2023 総合職|人事院
国家公務員試験ガイド2023 一般職|人事院
国家公務員採用 総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)受験案内|人事院
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)「教養区分」受験案内|人事院
【地方公務員(行政) ※東京都・大阪府の例】
| 東京都Ⅰ類B採用 | 大阪府職員 | |
| 年齢制限 | 22歳以上29歳以下 | 22歳以上25歳以下 ※入庁年3月31日時点の年齢 |
| 申し込み方法 | インターネット | インターネット |
| 試験内容 | 【第1次試験】一般教養/論文/専門試験 【第2次試験】個別面接 |
【第1次試験】SPI3/エントリーシート 【第2次試験】論文/個別面接 【第3次試験】個別面接/グループワーク |
| 採用スケジュール | ・受付:3~4月頃 ・第1次試験:4月頃 ・第2次試験:6~7月頃 ・最終合格者発表:7月頃 ・任命権者による面談:8月頃 ・採用内定:10月上旬 ※一般方式の場合 |
・受付:3~4月頃 ・第1次試験:5月頃 ・第2次試験:6月頃 ・第3次試験:7~8月頃 ・最終合格者発表:8月頃 ・大阪府各機関からの請求に応じて、採用者決定 |
【参考記事】
東京都職員Ⅰ類B採用試験案内(令和5年度)|東京都
大阪府職員採用案内|大阪府
国家公務員・地方公務員のいずれにおいても、筆記試験に合格すると、論文試験や面接による人物試験に進むのが通常です。面接については個別面接が主流ですが、集団討論のケースもあるので、事前に受験要項をしっかり確認しましょう。
【参考記事】
2 国家公務員採用総合職・一般職(大卒程度・高卒者)試験等の実施状況|令和3年度 年次報告書|人事院
社会人経験者採用枠で受験する
一般受験枠と社会人経験者採用枠での受験では、試験内容が大きく異なります。
社会人経験者採用枠は、係長級以上など、民間企業で経験を積んできた方を対象としているのが一般的です。そのため、民間企業で培ってきた専門スキルやコミュニケーションスキル、マネジメントスキルなどの能力面を見極めることを目的として、面接が重視されると考えられます。
社会人経験者採用枠の試験内容は、以下のとおりです。
【国家公務員】
| 係長級以上 | |
| 年齢制限 | なし |
| 申し込み方法 | インターネット |
| 試験内容 | 【第1次試験】基礎能力試験/経験論文試験 【第2次試験】政策課題討議試験/人物試験 【第3次試験】職種によって実施 |
| 採用スケジュール | ・受付:7~8月頃 ・第1次試験:10月頃 ・第2次試験:11~12月頃 ・第3次試験:職種によって実施 ・最終合格者発表:12月頃 ・採用予定府省の面接を経て採用 |
【参考記事】国家公務員 経験者採用試験|人事院
【地方公務員 ※東京都・大阪府の例】
| 東京都キャリア活用採用 | 大阪府職員 行政【35~49歳以下】 | |
| 年齢制限 | 59歳まで | 35歳以上49歳以下 ※入庁年3月31日時点の年齢 ※別途26歳以上34歳以下の募集あり |
| 申し込み方法 | インターネット | インターネット |
| 試験内容 | 【第1次試験】書類選考/教養試験/論文/専門試験 【第2次試験】個別面接 【第3次試験】個別面接 【課長代理級職選考】個別面接 |
【第1次試験】SPI3/論文
【第2次試験】個別面接/グループワーク |
| 採用スケジュール | ・受付:6月頃 ・第1次試験:8月頃 ・第2次試験:10月頃 ・第3次試験:11月頃 ・最終合格者発表:12月頃 ・課長代理級職選考:12月頃 ・結果発表:12月頃 |
・受付:7月頃 ・第1次試験:8月頃 ・第2次試験:10月頃 ・最終合格者発表:11月頃 ・大阪府各機関からの請求に応じて、採用者決定 |
【参考記事】
東京都職員キャリア活用採用選考案内(2022年度)|東京都
令和4年度大阪府職員採用試験〔行政(社会人等:35-49)〕試験案内|大阪府
社会人経験者採用では、面接による人物試験が2次試験、3次試験と二度以上おこなわれることもあります。社会人経験者枠で受験する際には、筆記試験・論文試験の準備とともに、面接対策も十分におこないましょう。
民間から公務員へ転職するのはなぜ難しいのか
一般的に、民間企業から公務員へ転職するのは難しいといわれています。民間企業から公務員へ転職するためのハードルを3つ確認していきましょう。
筆記試験と面接に備える時間の確保が難しい
理由のひとつ目には、公務員に転職するためには試験対策をしなければならず、時間の確保が難しいことが挙げられます。仕事のかたわらで計画的かつ根気強く試験準備に取り組むことは、困難といえるでしょう。
終業後、疲れている中で毎日2時間勉強したり、休日は一日かけて試験準備に臨んだりと、どんなに仕事で忙しくても試験対策のための時間を捻出しなければいけません。
特に、仕事内容が重労働であったり、休日出勤があるほど忙しかったりすると、準備時間の確保はさらに厳しくなるでしょう。
まずは、どのように試験対策の時間を捻出できるか、仕事のスケジュールとあわせて合格までの計画を立ててみてください。計画が立ったら、最後まで成し遂げる強い覚悟と熱意も必要です。
筆記試験の範囲が広い
公務員試験の筆記試験は出題範囲が広く、受験先によっては教養科目・専門科目の両方について勉強しておかなければいけません。以下が一般的な試験内容です。
上記の全ての範囲を短期間で身につけることは困難といえます。対策としておすすめなのは、過去問を使って効率良く勉強したり、予備校を活用したりする方法です。
目安として過去5年分の問題を解けば、問題のレベルや自身の弱点が見えてくるはずです。そのうえで重要だと考えられる単元を優先して復習していけば、効率的に知識を身につけられるでしょう。
また、公務員試験受験用の予備校に通えば、指導を受けながら筆記試験の準備を進められます。オンラインレッスンや解説動画なども利用すると、隙間時間でも有効に試験対策を進められるでしょう。
合格に必要な点数は受験先によって異なりますが、一般的には教養科目で6割以上、専門科目で7割以上の正解が必要だといわれています。仕事との両立は容易ではありませんが、苦手部分に的を絞って、確実に点数を獲得できるように勉強を進めましょう。
試験に年齢制限が設けられている場合がある
民間企業から公務員への転職が難しいとされる背景には、試験に年齢制限が設けられていることも影響しています。
たとえば、国家公務員の院卒者・大卒程度試験は年齢制限が30歳未満となっているため、30歳を過ぎると社会人経験者枠で受験することになります。
地方公務員の年齢制限は地方自治体によってさまざまで、前述した東京都の例では、大卒程度枠の年齢制限は29歳、キャリア活用採用の年齢制限は59歳までです。
一方、大阪府の例では大卒程度者の採用は25歳まで、行政職の中途採用は49歳までとなっています。年齢制限は地域によって異なるため、自身が希望する地方自治体の募集要項をよく確認してください。
ただし、社会人経験者枠での採用は常時求人があるわけではないため、倍率が高くなりやすいことは覚えておきましょう。
以下の表は、2022年度の社会人経験者枠と一般受験枠の倍率を比較したものです。
| 社会人経験者枠 | 一般受験枠 | |
| 札幌市一般事務(行政コース) | 23.2倍 | 3.9倍 |
| 福岡市行政(一般) | 24.4倍 | 8.3倍 |
| 千葉市事務行政 | 21.4倍 | 4.8倍 |
【参考記事】
試験実施状況|社会人経験者の部|札幌市
試験実施状況|大学の部、保健師|札幌市
令和4年度 福岡市職員(社会人経験者)採用選考実施状況|福岡市
上級、消防吏員A、獣医師、保健師採用試験等に関するお知らせ|福岡市
令和4年度 上級、資格免許職(上級相当)/民間企業等職務経験者|千葉市
上記の表で比較すると、社会人経験者枠の採用がいかに狭き門であるか理解できるでしょう。
民間企業から公務員への転職が厳しいといわれる理由には、採用枠が少なく競争率が高いことも関係しているといえそうです。
【面接対策】公務員への転職に成功するためには志望動機が重要
筆記試験の対策ができたら、同時に論文や面接対策もしていきましょう。重要なのは、「これまでの職歴を公務員に転職してどう活かしていくのか」という点を明確にすることです。
この章では、面接対策のポイントと注意点をそれぞれ紹介します。
志望動機を考える際のポイント
志望動機は面接時に必ず聞かれる質問です。
公務員に転職したい本音の理由が「安定した職業に就きたい」だったとしても、それを正直に話したところで倍率の高い公務員試験では採用されない可能性が高いでしょう。
面接官は応募者が「この部署でどれだけ活躍してくれるのか」「どれだけの良い影響を周囲に与えてくれるのか」といった要素を見ています。志望動機を考える際には、「応募部署でなぜ働きたいのか」「応募部署でどのように活躍できるのか」「国民や地域のためにどのようなことをしたいのか」という点を柱に、「公共への貢献」を意識して組み立ててください。
民間企業で働いた経験があると、学生時代よりも志望動機を考えやすいはずです。これまでの経験や培ったスキルをもとにして、希望する公務員職との具体的なつながりをアピールするといいでしょう。
また、応募先の職種や地方自治体の情報をくまなく調べ、自治体が掲げる「まちの将来像」や教育理念、応募職種の求める人物像などに関連した志望動機を作ることも大切なポイントです。特に、地方自治体の公務員試験を受ける方は「この自治体を希望する動機」は必ず質問されるため、納得できる理由を用意しておいてください。
退職理由を志望動機にするのはNG
民間企業から公務員への転職だけでなく、転職全般に当てはまることですが、退職理由を志望動機にするのはおすすめできません。
たとえば、「人間関係が良くない職場環境なので、より働きやすいところで仕事がしたいと思った」と志望動機を語っても、面接官にはまったく好意的に受け止めてもらえないでしょう。むしろ、「この部署でも人間関係でトラブルを起こし、また辞めるのではないか」とマイナスのアピールになってしまいます。
また、「現在勤めている企業は残業が多いので、定時で帰れる公務員になりたい」といった志望動機も、福利厚生や条件面ばかり見ているとマイナスなイメージを与えてしまう可能性があります。
前述したように、本音で志望理由を述べるのではなく、「公務員としてどのように活躍できるのか」に着目して志望動機を考えることが大切です。
民間から公務員に転職する際の手続きや年金
民間企業から公務員への転職が決まった際に、どのような手続きが必要なのか疑問に感じる方もいるでしょう。
通常は内定時に指示されたとおりに準備すれば問題ないため、自身で用意することはほとんどありませんが、以下のふたつの項目については忘れずに確認しておいてください。
源泉徴収票をもらっておく
年度途中で退職すると、退職するタイミングで現在の勤務先から源泉徴収票が発行されます。受け取った源泉徴収票は大切に保管し、転職先の国・または地方自治体に提出してください。
源泉徴収票は、通常退職から1ヵ月以内に郵便で送られてきます。もし郵送されてこなかった場合でも、源泉徴収票の発行は法律で事業主に義務づけられている(所得税法第226条)ものなので、退職した勤務先に依頼すれば応じてもらえるはずです。
年金手帳は大切に保管
民間企業に勤めている間は年金手帳が発行されていましたが、公務員については基礎年金番号通知書だけしか発行されないため、年金手帳を提出する必要はありません。
ただし、入職手続きの際に基礎年金番号の提出を求められるため、年金手帳をなくさないように注意してください。年金手帳は個人情報が記載されているものなので、手続き後も大切に保管しておきましょう。
民間から公務員への転職活動におすすめの転職エージェント
この項目では、民間企業から公務員への転職活動時、利用がおすすめの転職エージェントをご紹介します。
リクルートエージェント

「リクルートエージェント」は、さまざまな業種・職種など幅広い求人を多く保有する転職エージェントです。
また、職務経歴書作成ツールや面接対策セミナーなど、支援サポートが充実しているため「初めての転職活動でどのように動けばいいのか分からない」といった不安を感じる方であっても安心して利用できるでしょう。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | リクルートエージェント |
| 運営会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ |
| 公開求人数 | 581,372件 |
| 非公開求人数 | 443,015件 |
| 対応地域 | 東京・名古屋・大阪・福岡など全国/海外 |
| 公式サイト | https://www.r-agent.com/ |
- 自分に合う求人が見つかった
- めんどくさい手続きを代行してくれる
- 書類の添削や面接対策をしてくれる
口コミをもっと知りたい方はこちら
関連記事:【独自調査】リクルートエージェントの評判はひどい?口コミから実情を調査
マイナビエージェント

「マイナビエージェント」は、求人紹介から内定までを一貫して支援してくれる転職エージェントです。これまで培ってきた転職ノウハウをもとに、一人ひとり専任制でサポートしてくれます。
求職者がもっている強みや価値観をヒアリングなどを通して引き出し、企業情報とかけ合わせたうえで、あなたの特性に合った求人を紹介してくれるでしょう。また、仕事が忙しく面談の時間が取れない場合でも、夜間や土曜日の相談することが可能です。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | マイナビエージェント |
| 運営会社 | 株式会社マイナビ |
| 求人数 | 非公開 |
| 対応地域 | 東京、名古屋、大阪、福岡など全国/海外 |
| 公式サイト | https://mynavi-agent.jp/ |
- 求人情報が見やすく使いやすい
- 求人情報の内容以上の情報を知ることができる
- サポートが手厚く親身に対応してくれる
doda

「doda」は、「転職サイト」「転職エージェント」「スカウト」の3つのサービスを同時に利用できる転職支援サービスです。
dodaでは転職イベントも多く、採用担当者と直接話せる機会が多いため、「転職先が求めるニーズ」「自分の市場価値」についても知れるのは大きなメリットでしょう。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | doda |
| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
| 公開求人数 | 248,625件 |
| 非公開求人数 | 28,425件 |
| 対応地域 | 東京、名古屋、大阪、福岡など全国 |
| 公式サイト | https://doda.jp/ |
- 内定獲得までサポートしてくれた
- 親身に話を聞いてもらえた
- 面接対策がしっかりしている
まとめ
公務員は倒産やリストラのリスクが少なく、福利厚生や退職金などが充実しているメリットがあります。くわえて給与が安定していて将来設計が立てやすいことも、公務員の魅力のひとつです。
ただし、公務員に転職するためには公務員試験を突破する必要があり、忙しい中で準備に時間を割くことは簡単ではないでしょう。
公務員試験の準備中に挫折したり、転職後に後悔したりしないように、「公務員として社会に貢献したい」と強い覚悟をもって転職活動に臨んでください。
転職エージェント5社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 5.0
|
公開求人数
14.9万件
非公開求人数
非公開
|
転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。
|
|
|
★ 4.8
|
公開求人数
58.3万件
非公開求人数
41.6万件
|
まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。
|
|
|
★ 4.6
|
非公開
|
人材大手マイナビが運営する転職エージェント。特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。
|
|
|
★ 4.2
|
公開求人数
24.7万件
非公開求人数
2.4万件
|
新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。
|
|
|
★ 4.0
|
公開求人数
1.3万件
非公開求人数
2.2万件
|
1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川)に絞って質の高い求人情報を提供しているエージェント。企業との間に太いパイプがあり、年収アップ率はなんと71%。
|
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 5.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 5.0
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
|
★ 4.8
|
|
・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。
・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |
|
|
★ 4.6
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
|
★ 4.2
|
|
・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。
・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |
|
|
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
・関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
占い感覚の無料キャリアカウンセリング実施中
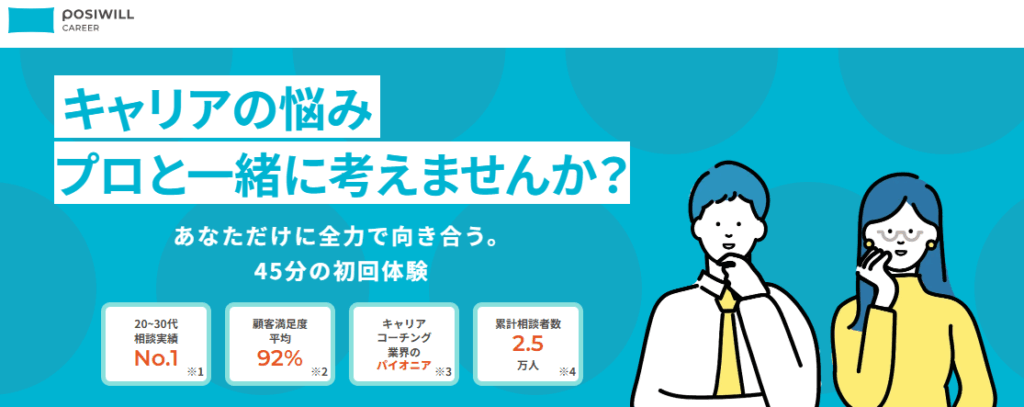
- 転職以外の選択肢も気になる、やりたいことがわからない方大歓迎
- どんな仕事の悩みもキャリアのプロに相談OK
- 『自己分析』や『適職診断』が好評
- 転職をすすめられる心配やしつこい電話もなし
- 「転職しないほうがいいかも」と気付く人も続出中