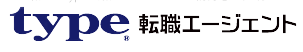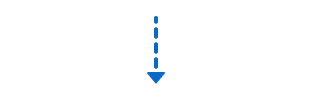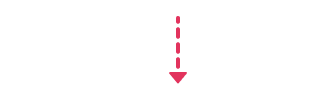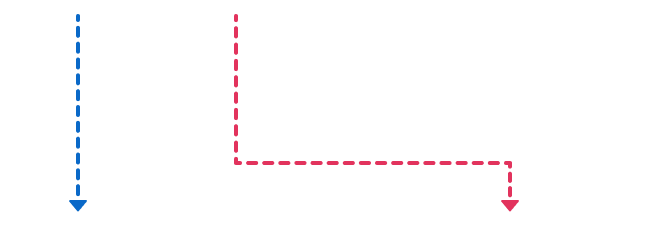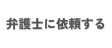退職代行を利用する際の「引き継ぎ」について、気になる方も多いのではないでしょうか。
「絶対、引き継ぎしたくない」と思う方もいれば、「出社したくないけど、引き継ぎしないと周りに迷惑がかかるから」と、迷っている方もいるでしょう。
退職代行を利用すると、引き継ぎなしでも退職できます。
とはいえ、就業規則などで引き継ぎについての定めがある場合には、引き継ぎをしなければトラブルを招いてしまうおそれがあるため注意が必要です。
この記事では、退職代行を利用した際の引き継ぎについて、引き継いだほうが良いケースや、引き継ぎをしないリスク、スムーズな退職を目指すポイントを紹介します。
※クリックで該当箇所にスキップします。
人気の退職代行サービスを徹底比較し、2025年で本当におすすめできる退職代行を紹介しています。
今すぐ1位の退職代行サービスを知りたい方は以下のボタンからチェックしてください。
| サービス | 料金 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
限定価格
24,800円 |
【当サイト限定価格24,800円】転職のフォローもある退職代行。有給休暇の無料申請や引っ越しなどの幅広いサポートを受けられる。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
19,800円 |
労働組合運営なので条件交渉もできる最もおすすめな退職代行。即日退職可能で会社とのやり取りも不要でスピード退社できる。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
24,000円 |
【退職代行実績10,000件以上】即日対応も可能な退職代行。最も安価で顧客満足度96%の安心安全なサービス。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
19,800円 |
退職相談実績30,000件以上で24時間LINE相談対応。有給消化やアフターフォローのサービスも充実。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
27,000円 |
人材紹介会社と提携の転職フォロー体制も万全。退職が全て完了するまで追加料金なしでサポートを受けられる。 |
| サービス | 相談方法 | 後払い・返金保証 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
転職フォローもあり
|
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
追加料金一切なし
|
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
| サービス | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
・自分ではできない退職成功率100%のJobsに任せて良かったです!
・限界状態の中、丁寧な対応に救われました。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
・サポートやフォローの対応が素早く、丁寧なサービスでした。
・利用方法もシンプルでわかりやすかったです。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
・後払いだったので、安心して利用できました。
・思い残しもなくスッキリとした退職ができました。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
・パワハラの恐怖の中でも丁寧なサポートで退職できました。
・スピード、親切さ、交渉などの全ての対応に満足でした。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
・うつ病気味だったけど即日退職できて、ニコイチに救われました。
・行きたくなかったから当日にお願いしました。 |
今の仕事をやめたいけど、
次の一歩が不安なあなたへ。
多くの人が、退職前に次の職場を決めることで、経済的にも精神的にも安心して新しいスタートを切っています。
次こそは…
- 人間関係が良好な職場で働きたい
- 頑張りを正当に評価してくれる職場で働きたい
- 残業や休日出社のないホワイトな職場で働きたい
このような思いの方は、転職エージェントに無料相談して、あなたにピッタリの求人を提案してもらうのがおすすめです。有益なアドバイスがもらえるだけでなく、履歴書作成から面接対策まで転職活動を完全無料でサポート。ストレスフリーな環境からの再スタートを目指せます。
転職エージェント5社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
公開求人数
58.3万件
非公開求人数
41.6万件
|
【圧倒的な求人数と転職支援実績】初めての転職なら登録すべきエージェント。
|
|
|
★ 4.6
|
非公開
|
【20~30代向け】有名大手企業からベンチャー企業まで幅広い求人を保有。
|
|
|
★ 4.5
|
公開求人数
14.9万件
非公開求人数
非公開
|
【転職者の1/3が年収アップ】レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。
|
|
|
★ 4.2
|
公開求人数
24.7万件
非公開求人数
2.4万件
|
【登録者数は業界最大級の約750万人】実績ノウハウをもとにしたマンツーマンサポート。
|
|
|
★ 4.0
|
公開求人数
1.3万件
非公開求人数
2.2万件
|
【年収アップ率71%】1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川)で転職する方におすすめ。
|
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
|
・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。
・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |
|
|
★ 4.6
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
|
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
|
★ 4.2
|
|
・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。
・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |
|
|
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
・関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |
目次
退職代行を利用すると引き継ぎなしでも退職できる
退職代行を利用すると、引き継ぎなしでも退職できます。厳密にいうと、退職代行の利用にかかわらず、引き継ぎなしでも退職は可能です。
なぜなら、無期雇用の労働者(正社員など)は「いつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から2週間を経過することによって、雇用契約は終了する」と民法で定められているからです。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法 第627条第1項|e-Gov法令検索
民法では、退職の申し入れがいつでもできることや申入れから契約終了の効果が発生する期間は定められている一方、「引き継ぎ」についての明記はされていません。
つまり、業務の引き継ぎに関して法律上の明確な定めはないといえます。そのため、引き継ぎをしないまま退職しても、法律上は問題ありません。
ただ、企業の就業規則などで退職時の引き継ぎを義務としているケースや、「〇〇だけでも引き継ぎしてもらえないか?」と依頼されるケースもあります。
このようなケースでは、かたくなに引き継ぎを拒否するのではなく、引き継ぎをおこなったほうが良いといえるでしょう。
退職までに引き継ぎをしたほうが良いケース
法律上は引き継ぎについて特に定めはありませんが、企業や後任者にとっては、引き継ぎは重要なものです。以下のケースではとくに、引き継ぎをおこなうようにしましょう。
- 就業規則で引き継ぎが定められている場合
- 会社に大きな損失が出そうな場合
就業規則で引き継ぎが定められている場合
勤めている企業の就業規則にて、退職時の引き継ぎが義務づけられている場合は、就業規則にしたがって引き継ぎをしたほうが良いでしょう。
就業規則のなかには、退職金を満額受け取る要件のひとつとして、引き継ぎを義務づけているケースもあります。
退職金の支給の有無や金額などの要件は、企業側が自由に決められるため、仮に引き継ぎをしなかった場合、退職金が減額されるおそれがあります。
損をしないためにも、引き継ぎについての記載はないか、あらかじめ就業規則を確認しておきましょう。
会社に大きな損失が出そうな場合
引き継ぎをしないことが原因で会社に損失が出そうな場合は、退職前に引き継ぎをしたほうが良いでしょう。なぜなら、企業から損害賠償などを求められる可能性もあるからです。
たとえば、自分が重要なプロジェクトを任されていた場合、適切な引き継ぎがおこなわれなかったために、業務の遂行に大幅な遅れが生じ、企業が損害を被る可能性はゼロではありません。
また、担当の取引先があるケースなどでも、取引先との引き継ぎがおこなわれなかったために信用を失い、取引がなくなってしまう可能性も考えられます。
そのため、企業に損失が出る可能性がある場合には、できる限り引き継ぎをするのが望ましいといえるでしょう。
業界のプロがあなたの悩み解決します!
ストレスを感じる
不安を感じる
給付金をもらいたい
公務員?
引き継ぎなしで退職代行を利用した場合に考えられるリスク・トラブル
引き継ぎなしで退職する際に考えられるリスクやトラブルは、以下のとおりです。
- 会社や顧客から連絡がくる可能性がある
- 損害賠償請求や懲戒解雇扱いされる可能性も否定できない
- 退職金が減額される可能性がある
会社や顧客から連絡がくる可能性がある
引き継ぎをせずに退職すると、会社や顧客、あるいは後任者から連絡がくる可能性があります。また、連絡がつかない場合には、上司などが自宅まで訪問してくるケースも考えられます。
連絡をしてくる目的には「引きとめたい」「業務内容の確認をしたい」「資料の保管場所を教えてほしい」など、さまざまな理由が考えられますが、対応するのが苦痛な場合は面談、電話といった方法は避け、メール等で最低限の連絡事項のみ伝えるといった方法も一つです。
損害賠償請求や懲戒解雇扱いされる可能性も否定できない
引き継ぎをしなかったことで企業に損失がでた場合、損失を理由に、損害賠償を求められる、もしくは懲戒解雇扱いされてしまうおそれも否定できません。
企業の損害は、重要な業務やポジションに携わっている方であればあるほど、大きくなりがちです。
懲戒解雇とするには就業規則等の懲戒解雇事由に該当している必要があるため、このようなケースは稀ではあるものの、万が一「懲戒解雇」として処理されてしまうと、今後の転職なども不利になってしまいかねないため、可能な限り引き継ぎをおこなっておくことをおすすめします。
退職金が減額される可能性がある
退職金が減額されるリスクもあります。
たとえば、就業規則に「引き継ぎをせずに退職する際は退職金が減額となる」といった旨が記載されているケースでは、減額されてしまうかもしれません。
「減額になっても構わない」と、自分が納得して退職するのであれば問題ありませんが、「満額受け取りたい」と思う場合には、引き継ぎをしたほうが良いでしょう。
引き継ぎなしで退職する際は、就業規則の退職金支給条件に引き継ぎについて記載がないか確認しておきましょう。
できる限りスムーズに退職するポイント
引き継ぎをしない場合、上司や顧客、後任者などから連絡がきたり、退職金が減額されるリスクがあったりするため、円満退職を実現させることは難しいかもしれません。
しかし、少しでも自分ができる対策をしておくことで、できる限りスムーズな退職が目指せます。ポイントを3つ紹介します。
自分の業務はできる限り完遂させておく
自分の業務は、できる限り完遂させておきましょう。
中途半端なまま退職してしまうと、上司や後任者は業務の進捗状況などがつかめず、その分、時間をロスしてしまいかねません。
その結果、業務が大幅に遅れて企業が不利益を被り、トラブルに発展する可能性も考えられます。
退職するまでの間に業務をできるだけ完遂させておくと、企業側は進捗状況を確認する手間や心配がなく、話もスムーズに進みやすくなるでしょう。
退職代行を利用する場合、翌日から出勤しないケースも少なくないため、大きなプロジェクトに携わっている場合や、会社の損失につながる業務をしている場合はとくに、可能な限り業務を完遂させておきましょう。
あらかじめ引き継ぎ書を作成しておく
引き継ぎ書を作成しておくのもポイントです。
簡易的なものであっても、作成しておくとリスク回避につながります。
引き継ぎ書には、以下のような項目を記載しましょう。
- 業務関係者の氏名や連絡先
- 取引先とのアポイントの状況
- 業務の進捗状況・スケジュール
- 業務フローや具体的な手順
- 業務に関する書類や資料の保管場所 など
明確な引き継ぎ書があれば、上司から電話がかかってきたり、引き継ぎのために出社を迫られたりする可能性が低くなり、精神的負担も軽くなるでしょう。
退職代行業者から交渉してもらう
引き継ぎ書の作成を含め、どうしても引き継ぎをしたくない方は、退職代行業者から交渉してもらうのも、ひとつの方法です。
退職代行業者に、「引き継ぎなしで退職したい」旨を伝え、退職代行業者から企業へ交渉してもらいましょう。
「引き継ぎなしでの退職」に了承を得られれば、引き継ぎをする必要はなく、企業から「引き継ぎのために出社して」といわれることもありません。
退職代行を利用する前に「運営元」をよく確認しておきましょう。
| サービス | 料金 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
限定価格
24,800円 |
【当サイト限定価格24,800円】転職のフォローもある退職代行。有給休暇の無料申請や引っ越しなどの幅広いサポートを受けられる。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
19,800円 |
労働組合運営なので条件交渉もできる最もおすすめな退職代行。即日退職可能で会社とのやり取りも不要でスピード退社できる。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
24,000円 |
【退職代行実績10,000件以上】即日対応も可能な退職代行。最も安価で顧客満足度96%の安心安全なサービス。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
19,800円 |
退職相談実績30,000件以上で24時間LINE相談対応。有給消化やアフターフォローのサービスも充実。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
27,000円 |
人材紹介会社と提携の転職フォロー体制も万全。退職が全て完了するまで追加料金なしでサポートを受けられる。 |
| サービス | 相談方法 | 後払い・返金保証 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
転職フォローもあり
|
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
追加料金一切なし
|
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
| サービス | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
・自分ではできない退職成功率100%のJobsに任せて良かったです!
・限界状態の中、丁寧な対応に救われました。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
・サポートやフォローの対応が素早く、丁寧なサービスでした。
・利用方法もシンプルでわかりやすかったです。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
・後払いだったので、安心して利用できました。
・思い残しもなくスッキリとした退職ができました。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
・パワハラの恐怖の中でも丁寧なサポートで退職できました。
・スピード、親切さ、交渉などの全ての対応に満足でした。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
・うつ病気味だったけど即日退職できて、ニコイチに救われました。
・行きたくなかったから当日にお願いしました。 |
おすすめの退職代行サービス
おすすめの退職代行サービスを3社紹介します。
退職代行Jobs

退職代行Jobsは、株式会社アレスが運営している退職代行サービスです。
運営元は民間企業ですが、労働組合と提携しているため、企業との交渉もおこなってもらえる特徴があります。
たとえば、有給休暇の取得や退職日についての交渉をしてもらえるため、引き継ぎをしたくない場合も、その旨を伝えると対応してもらえるでしょう。
また、退職後の転職支援や、退職が完了するまで期間無制限でのフォローなども受けられ、サポート体制が整っています。
| 運営元の種類 | 労働組合と提携/顧問弁護士監修 |
| 料金 | 2万7,000円→当サイト限定価格2万6,000円+ 労働組合費2,000円(税込) |
| 交渉権 | あり |
| 24時間対応 | あり |
| 相談方法 | LINE・メール・電話< |
| 公式ホームページ | https://jobs1.jp/ |
退職代行ガーディアン
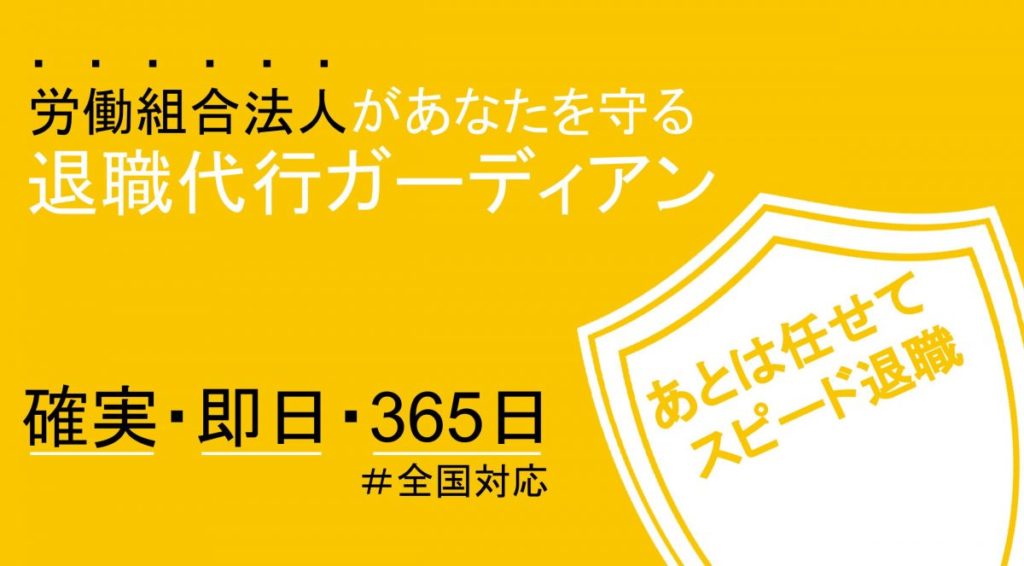
退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合が運営している退職代行サービスです。
労働組合が運営しており、有給休暇や退職金などの交渉をしてもらえます。引き継ぎなしでの退職交渉にも対応してもらえるでしょう。
また、相談から退職までをスマートフォン1台で完結できる手軽さも魅力のひとつです。日中に仕事がある場合、なかなか連絡はとりづらいものです。
LINEであれば、自分の都合の良いときに相談ができます。
| 運営元の種類 | 労働組合 |
| 料金 | 2万9,800円(税込) |
| 交渉権 | あり |
| 24時間対応 | 不明 |
| 相談方法 | LINE・電話 |
| 公式ホームページ | https://taisyokudaiko.jp/ |
退職代行OITOMA

退職代行OITOMAは、株式会社5coreが運営している退職代行サービスです。
労働組合が運営している退職代行の中でも、費用水準が低いという特徴があるので、「退職代行を使ったことがなくて不安...」という方も比較的気軽に利用を進めることができます。
また、追加料金もなく、退職完了まで無制限で相談・サポートしてもらえるため、安心してサービスを利用できるでしょう。
まとめ
退職代行利用の有無にかかわらず、引き継ぎせずに退職することは可能です。
とはいえ、自分が担っている業務をキリの良いところまで終わらせておくなど、最低限のマナーを守って退職しなければ、自身の信用も失ってしまいかねません。
そのため、極力引き継ぎをするほうが無難であるといえるでしょう。
どうしても出社したくない場合は、「引き継ぎ書」の作成がおすすめです。明確に引き継ぎの内容がわかれば、トラブルやリスクの軽減につながります。
引き継ぎ書の作成も困難な場合には、退職代行への相談を検討してみましょう。交渉が可能な退職代行業者であれば、代わりに交渉してもらえるため、気持ちも楽になるのではないでしょうか。
| サービス | 料金 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
限定価格
24,800円 |
【当サイト限定価格24,800円】転職のフォローもある退職代行。有給休暇の無料申請や引っ越しなどの幅広いサポートを受けられる。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
19,800円 |
労働組合運営なので条件交渉もできる最もおすすめな退職代行。即日退職可能で会社とのやり取りも不要でスピード退社できる。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
24,000円 |
【退職代行実績10,000件以上】即日対応も可能な退職代行。最も安価で顧客満足度96%の安心安全なサービス。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
19,800円 |
退職相談実績30,000件以上で24時間LINE相談対応。有給消化やアフターフォローのサービスも充実。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
27,000円 |
人材紹介会社と提携の転職フォロー体制も万全。退職が全て完了するまで追加料金なしでサポートを受けられる。 |
| サービス | 相談方法 | 後払い・返金保証 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
転職フォローもあり
|
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
追加料金一切なし
|
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
後払いOK
全額返金保証あり
|
| サービス | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
 退職代行Jobs 退職代行Jobs
★ 4.9
|
|
・自分ではできない退職成功率100%のJobsに任せて良かったです!
・限界状態の中、丁寧な対応に救われました。 |
|
 退職代行ガーディアン 退職代行ガーディアン
★ 4.7
|
|
・サポートやフォローの対応が素早く、丁寧なサービスでした。
・利用方法もシンプルでわかりやすかったです。 |
|
 退職代行OITOMA 退職代行OITOMA
★ 4.5
|
|
・後払いだったので、安心して利用できました。
・思い残しもなくスッキリとした退職ができました。 |
|
 退職代行トリケシ 退職代行トリケシ
★ 4.2
|
|
・パワハラの恐怖の中でも丁寧なサポートで退職できました。
・スピード、親切さ、交渉などの全ての対応に満足でした。 |
|
 退職代行ニコイチ 退職代行ニコイチ
★ 4.0
|
|
・うつ病気味だったけど即日退職できて、ニコイチに救われました。
・行きたくなかったから当日にお願いしました。 |
今の仕事をやめたいけど、
次の一歩が不安なあなたへ。
多くの人が、退職前に次の職場を決めることで、経済的にも精神的にも安心して新しいスタートを切っています。
次こそは…
- 人間関係が良好な職場で働きたい
- 頑張りを正当に評価してくれる職場で働きたい
- 残業や休日出社のないホワイトな職場で働きたい
このような思いの方は、転職エージェントに無料相談して、あなたにピッタリの求人を提案してもらうのがおすすめです。有益なアドバイスがもらえるだけでなく、履歴書作成から面接対策まで転職活動を完全無料でサポート。ストレスフリーな環境からの再スタートを目指せます。
転職エージェント5社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
公開求人数
58.3万件
非公開求人数
41.6万件
|
【圧倒的な求人数と転職支援実績】初めての転職なら登録すべきエージェント。
|
|
|
★ 4.6
|
非公開
|
【20~30代向け】有名大手企業からベンチャー企業まで幅広い求人を保有。
|
|
|
★ 4.5
|
公開求人数
14.9万件
非公開求人数
非公開
|
【転職者の1/3が年収アップ】レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。
|
|
|
★ 4.2
|
公開求人数
24.7万件
非公開求人数
2.4万件
|
【登録者数は業界最大級の約750万人】実績ノウハウをもとにしたマンツーマンサポート。
|
|
|
★ 4.0
|
公開求人数
1.3万件
非公開求人数
2.2万件
|
【年収アップ率71%】1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川)で転職する方におすすめ。
|
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.6
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.2
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
|
★ 4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
|
★ 4.8
|
|
・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。
・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |
|
|
★ 4.6
|
|
・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
|
|
★ 4.5
|
|
・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
|
|
★ 4.2
|
|
・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。
・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |
|
|
★ 4.0
|
|
・サイトがシンプルな作りで見やすい。
・関東圏で、すぐに転職をしたいと考えているような人には向いているかなと思いました。 |