仕事が原因で適応障害となった場合、転職せざるを得ない状況になるケースは少なくありません。
ストレスの原因となった職場から離れられることはありがたい一方で、次の仕事は見つかるのか、見つかったとして上手くやっていけるのか不安ですよね。
実際、適応障害が不利に働いて転職活動が上手くいかない、新しい職場で適応障害を再発してしまうという方も少なくありません。
再発リスク、職場の理解、向いている仕事選び……心配は尽きないものです。
しかし、きちんとした準備をして転職活動に臨めば、あなたに適した職場が見つけられます。
この記事では、まず適応障害を発症する理由や仕事における症状、発症した場合の対応について解説します。
後半では、適応障害の方でも負担が少ない仕事や転職を成功させるポイント、おすすめの転職支援サービスについて解説します。
※前半の内容は、まだ病院で診断を受けてない方向けです。既に医師から適応障害と診断されている方は、適応障害の方に負担が少ない仕事から、読み進めることをおすすめします。
適応障害による不安は大きいかもしれませんが、あなたのペースでよいので、転職活動を進めていきましょう。
おすすめのサービス4社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 5.0 | 公開求人数 約4,000件 | 【一都三県にお住まいで障害者手帳をお持ちの方向け】業種や合理的配慮・在宅勤務の可否など詳細な絞り込みも可能。 | |
★ 4.8 | 公開求人数 約1,400件 | 【障害者手帳をお持ちの方向け】面接対策や書類添削など手厚いサポートが人気。 | |
★ 4.7 | 公開求人数 約1,600件 | 【全国対応!】大手ならではのサポートで大手・優良企業・正社員求人を多数保有 | |
★ 4.6 | 公開求人数 約2,000件 | 【一都三県・大阪にお住まいで障害者手帳をお持ちの方向け】手に職をつけて安定的に働ける。 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 5.0 | 20代 30代 40代 50代 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 | |
★ 4.8 | 20代 30代 40代 50代 | 首都圏 名古屋 大阪 兵庫 福岡 札幌 仙台 その他 | |
★ 4.7 | 20代 30代 40代 50代 | 首都圏 名古屋 大阪 兵庫 福岡 札幌 仙台 その他 | |
★ 4.6 | 20代 30代 40代 50代 | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 5.0 | ・発達障害を自覚し、不安もありましたが様々なサポートを受け働いています。 ・精神疾患について理解してもらえ、失敗しない会社選びについてアドバイスをもらえました。 | ||
★ 4.8 | ・これまでの経験を活かした求人を提案していただき、具体的な仕事内容まで詳しく説明してくれたので安心して応募できました。丁寧なサポートで、自分に合った職場を見つけることができました。 ・転職活動を進めていく中で、自身を失った時も、スタッフさんが丁寧に求人の選定から面接対策、応募後のフォローまで一貫してサポートしてくれたので、前向きに活動を続けられました。 | ||
★ 4.7 | 自分一人での転職活動であれば、仕事のイメージが湧かずエントリーをしていなかっただろうと思います。企業情報だけでなく仕事内容も細かく紹介していただいたことが意欲に繋がり、最終的に2社から内定をいただき、今の会社に入社しました。 | ||
★ 4.6 | ・肉体的な負担が少ない仕事内容の求人が豊富だったので魅力的でした。 ・障害者雇用バンクのエージェントが面接試験に合格するコツをいくつも伝授してくれた |
目次
適応障害を発症してしまう原因と仕事での症状

病院に行ったわけではないけど、もしかして適応障害なのかなと不安に感じている方もいるかと思います。
まずは、適応障害を発症してしまう原因と仕事での症状について、確認していきましょう。
適応障害はストレスとなる状況や出来事が原因で発症する
そもそも適応障害とはどういった精神疾患なのか、厚生労働省は以下のように説明しています。
日常生活の中で、何かのストレスが原因となって心身のバランスが崩れて社会生活に支障が生じたもの。原因が明確でそれに対して過剰な反応が起こった状態をいう。
引用元:適応障害|e-ヘルスネット
要するに、適応障害とは何かしらストレスとなる状況や出来事があるために、普段通りに生活することができない状態といえます。
通常、ストレスを感じれば、誰しも少なからず気分が沈んだり、イライラしたりするものです。
ですが、適応障害の場合、ストレスに釣り合わないほどの重度な症状が現れます。
ただし、適応障害はストレスとなる状況や出来事がはっきりしているため、その原因から離れてしまえば、特別な治療をせずとも症状が改善する場合もあります。
適応障害が引き起こす症状
適応障害を発症した場合、心身や行動に以下のような変化を引き起こします。
- 心身面
不安感、抑うつ気分、焦燥感、集中力や判断力の低下、目まい、動悸、不眠、偏頭痛、手足の震えなど
- 行動面
無断欠勤、暴飲暴食、自殺行為、口論、危険運転、ケンカ、破壊行為など
適応障害では、上記のような症状が、原因となった出来事が起きてから1ヶ月以内に発症し、影響を受けなくなってから6ヶ月以上は症状が続かないとされています。
精神疾患による労災請求は年々増加中
職場のストレスが原因で精神疾患を発症し、労災として認定されるケースも年々増加しています。
.png)
実際、厚生労働省が毎年公表している「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」では、労災の請求件数・支給決定件数ともに年々増加しています。
令和5年度に発表した報告書によると、精神障害による労災請求件数が過去最多の2,683件に達し、支給決定件数も710件と過去最高の数値になりました。これは、「職場環境が精神的に健康でないケースが増えている」ことを示唆しています。
このように、精神疾患は誰にでも起こり得る問題となっており、適応障害も決して特別なケースではありません。「自分だけが弱い」と思い込まず、状況を客観的に見ることが、次の一歩につながります。
適応障害での転職前にできること
適応障害と医師から診断され、その原因が職場にあった場合、これからどうすればよいのだろうと不安が募りますよね。
働くことが難しくなったからといって、仕事を辞める以外に選択肢がないわけではありません。
会社や家族、担当医などと話し合いつつ、自身の状況に合わせて、解決策を探っていくべきでしょう。
業務量を調整する
ストレスの原因が長時間労働や勤務形態にある、と考えられる場合には、業務量を調整してもらうことから始めるとよいでしょう。
仕事が原因で適応障害になったからといって、休職や転職が症状の改善につながるとは限りません。
むしろ、仕事復帰へのプレッシャーが余計にかかってしまい、より自分を追い込む結果になってしまうことも…。
適応障害は人によって症状が異なり、また、日によって波もあります。
職場に余裕があるなら、様子をみて業務量を調整できないか相談してみてください。
休職する
症状の度合いによっては、医師から休職を促される場合もあります。
休職制度は法律で定められた制度ではないため、運用の状況は会社によってマチマチです。
しかし、制度がなかったとしても、休職扱いにしてくれる場合もありますので、まずは上司や人事などに相談してみてください。
休職期間中は、まずしっかりと心身を休めることに努めましょう。休職することになったのは、決してあなたが弱いからなんて理由ではありません。
むしろ、仕事に対して真摯に向き合ったからであり、自分自身のことをしっかりとねぎらってあげてください。
とはいえ、休職できる期間にも限りがあります。
復職できる状態まで回復せず、仕事を辞めざるを得ないことも十分考えられるので、転職活動の準備をする・利用できる生活支援制度を調べるなどの対策をしておきましょう。
今の仕事を辞めて転職する
業務量の調整や休職などの手段では、状況の改善が見込めないのであれば、今の仕事を辞めて転職することを考えたほうがよいでしょう。
これまで散々足を引っ張ってしまったのに、なんの貢献もできずに辞めるのは申し訳ない、と感じる方もいるかもしれません。
しかし、無理をして働いても、あなたの状況が悪化するばかり。結局はあなたも会社も得をしない状況に陥ってしまうでしょう。
また、会社を辞めようにも引き留められてしまう場合もあります。そうした場合は、退職代行(できれば弁護士が行っているもの)を利用してみることをおすすめします。
ただし、転職することで適応障害が一時的に改善したとしても、再発しないとは限りません。
あなたがストレスを感じる原因となっていた状況や出来事はなんなのか、どういった職場・仕事で働きたいのかを見極めないと、再発のリスクは避けられないでしょう。
おすすめのサービス4社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 5.0 | 公開求人数 約4,000件 | 【一都三県にお住まいで障害者手帳をお持ちの方向け】業種や合理的配慮・在宅勤務の可否など詳細な絞り込みも可能。 | |
★ 4.8 | 公開求人数 約1,400件 | 【障害者手帳をお持ちの方向け】面接対策や書類添削など手厚いサポートが人気。 | |
★ 4.7 | 公開求人数 約1,600件 | 【全国対応!】大手ならではのサポートで大手・優良企業・正社員求人を多数保有 | |
★ 4.6 | 公開求人数 約2,000件 | 【一都三県・大阪にお住まいで障害者手帳をお持ちの方向け】手に職をつけて安定的に働ける。 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 5.0 | 20代 30代 40代 50代 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 | |
★ 4.8 | 20代 30代 40代 50代 | 首都圏 名古屋 大阪 兵庫 福岡 札幌 仙台 その他 | |
★ 4.7 | 20代 30代 40代 50代 | 首都圏 名古屋 大阪 兵庫 福岡 札幌 仙台 その他 | |
★ 4.6 | 20代 30代 40代 50代 | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 5.0 | ・発達障害を自覚し、不安もありましたが様々なサポートを受け働いています。 ・精神疾患について理解してもらえ、失敗しない会社選びについてアドバイスをもらえました。 | ||
★ 4.8 | ・これまでの経験を活かした求人を提案していただき、具体的な仕事内容まで詳しく説明してくれたので安心して応募できました。丁寧なサポートで、自分に合った職場を見つけることができました。 ・転職活動を進めていく中で、自身を失った時も、スタッフさんが丁寧に求人の選定から面接対策、応募後のフォローまで一貫してサポートしてくれたので、前向きに活動を続けられました。 | ||
★ 4.7 | 自分一人での転職活動であれば、仕事のイメージが湧かずエントリーをしていなかっただろうと思います。企業情報だけでなく仕事内容も細かく紹介していただいたことが意欲に繋がり、最終的に2社から内定をいただき、今の会社に入社しました。 | ||
★ 4.6 | ・肉体的な負担が少ない仕事内容の求人が豊富だったので魅力的でした。 ・障害者雇用バンクのエージェントが面接試験に合格するコツをいくつも伝授してくれた |
適応障害での転職を成功させるポイント5つ
適応障害を抱えながらの転職活動は、不安なことも多いですよね。
この項目では、適応障害での転職を成功させるために重要なポイントを解説します。
まずは治療に励む
早く治さなきゃと焦る気持ちもわかりますが、症状の改善が見られないうちに転職活動をすべきではありません。適応障害と診断を受けた人の中で、4割を超える人が5年後にはうつ病などに病名が変更されると言われています。
適応障害はより重い病気を発症する前段階の状態ともいえ、今のうちに治療できたかどうかで、あなたの将来が大きく変わります。
適応障害を乗り越えるためにも、まずは治療に励みましょう。
適応障害の発症原因を認識する
転職活動に臨む前に適応障害を発症した原因が何であったのか、しっかりと自身でわかるようにしておきましょう。
適応障害のような精神疾患は、一度発症すると簡単には治りません。ストレスの原因から離れることで、症状の改善が見られたとしても一時的なもの。
完治していなければ、新しい職場でまた同じような状況・出来事に遭遇した場合、再発する可能性は高いといえます。
そのため、再発のリスクを抑えたいのであれば、何にストレスを感じていたのか認識し、そうした状況や出来事に関わらないようにすべきでしょう。
転職希望先の企業・業界について詳しく調べる
転職先選びで失敗しないためには、求人応募を考えている企業や業界について、念入りに調べておくことも大切です。
転職サイト等にある企業の情報は、人を採用するために載せているもの。そのため、企業の良い部分しか書かれていません。
実際の評判を知るためには、Openworkや転職会議などの口コミサイトやSNSを利用して情報収集したほうがよいでしょう。
また、業界全体の傾向も把握しておくべきです。業界全体が停滞しているような状況であれば、転職後にかなりの苦労を強いられるかもしれません。
適応障害であることは隠さないほうがよい
適応障害であると知られたら、採用されないと思うかもしれないですが、できれば隠さないで転職活動することをおすすめします。
というのも、適応障害であることを隠してしまうと、周りの人と同じような働き方を求められます。
仮に適応障害の影響で、スムーズに仕事をこなせなかったら、周囲からの評価は大きく下がってしまうでしょう。
あなた自身も、仕事ができない自分に嫌気が差し、そうしたストレスが原因となって、より適応障害を重症にしてしまうかもしれません。
適応障害だと明かすことで、採用を見送る会社もあるかと思います。ですが、適応障害だと知ったうえでも、採用してくれる会社のほうが働きやすいのではないでしょうか。
適応障害に関して理解のある会社を選ぶ
適応障害に理解がある会社であれば確実に働きやすいですが、どうやって探せばよいかわからないですよね。
探し方の一つとしては、前述のように自分が適応障害であると伝えることでしょう。
適応障害だと聞いてもなお、採用してくれるのであれば、理解があると考えられます。
また、過去もしくは現在に適応障害の人が在籍していたことがあるか、確認してみるのも良いかもしれません。
どのような対応をしているかわかれば、理解があるかどうかの参考になるはずです。
その他には、人材紹介会社や就労移行支援を利用して転職活動をするのもよいでしょう。
適応障害の方に負担が少ない仕事

適応障害を発症する原因は人それぞれ異なります。そのため、負担が少ない仕事というのも、人それぞれに異なるといえます。
この項目で紹介するのはあくまでも一例です。色々な職種・業種があるので、自分がやりたいこと、得意なこと、できる業務などを考慮した上で仕事を探しましょう。
下記の記事では、適応障害の方の職場探しのポイントや注意点をまとめています。ぜひご覧になって、職場探しや落ち着いて働ける職場環境の参考にしてください。

残業や休日出勤があまりない仕事
仕事が激務であったために適応障害を発症した場合、残業や休日出勤などが少ない仕事を選ぶのが良いかもしれません。
- 事務職
- 経理職
- コールセンター
- 製造業 など
上記で挙げたような仕事は、基本的に同じルーティンで業務を行うため、慣れてさえしまえば、仕事による負担はそれほど感じなくなるでしょう。
リモートワークでも働ける仕事
職場の人間関係が原因で適応障害を発症した人の中には、リモートワーク可能な仕事だったらやれそうと考えている方もいるかもしれません。
- WEBライター/校正
- エンジニア/プログラマー
- データ入力
- 翻訳
- デザイナー など
ただ、リモートワークだからといって、会社の人とコミュニケーションを取る必要がないわけではありません。
しかし、チャットやメール、電話など、面と向かってコミュニケーションをしなくてもよいだけでも、だいぶ気が楽なはずです。
転勤や海外出張が少ない仕事
適応障害は転勤や海外出張など、慣れない土地での生活を強いられるような場合にも発症します。
新しい環境に慣れてしまえば、症状は改善するかもしれませんが、難しい人もいるでしょう。
であれば、転勤や海外出張が少ない仕事を選ぶのがよいと考えられます。
- 不動産デベロッパー(土地開発事業者)
- プログラマー/エンジニア
- バックオフィス系の職種
また、規模がそれほど大きくない会社や限定正社員の求人を探してみても良いかもしれません。
適応障害の方におすすめの転職方法

普通の体調ならまだしも、適応障害を抱えながらの転職活動はどうすればと、お悩みの人も多いかもしれません。
この項目では、適応障害の方に適した転職活動方法をおすすめします。
ハローワークの利用
適応障害であることをオープンにして転職活動を行う場合、ある程度は数を重視して求人応募しなくてはならないでしょう。
となれば、求人を多数保有しているハローワークの利用がおすすめです。
ハローワークでは求人紹介を受けられるだけでなく、就業相談も受けられます。
就業相談では、自己分析の手伝いや履歴書の添削、面接対策など、さまざまなサポートが受けられるため、自身が抱える不安を解消しながら、転職活動に臨むことができます。
また、ハローワークには障害者専用の窓口もあるため、適応障害の症状がひどい場合は、そちらも利用してみるとよいかもしれません。
適応障害の人におすすめの転職エージェントの利用
転職活動では求人サイトだけでなく、転職エージェントを利用するのも一つの手です。
転職エージェントとは、専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを元に、あなたに合った求人を紹介してくれる転職支援サービスです。自分で求人を探したり、面接日程の調整をしたりする手間が減らせるため、転職活動にかかる負担を軽減できます。
さらに、アドバイザーが履歴書の添削や面接練習なども行ってくれるので、二人三脚で就職・転職活動を行えます。
さまざまな人材紹介会社が転職エージェントを行っており、中には障害者の転職支援を専門に扱っているエージェントもあります。
大手企業から中小企業まで、さまざまな転職エージェントに登録し、あなたにきちんと向き合ってくれるキャリアアドバイザーがいるサービスを利用しましょう。
以下の関連ページでは、適応障害の方におすすめの転職エージェントをさらに詳しくまとめています。ぜひ参考にして、安心して働ける職場への内定を獲得してください。

LITALICO仕事ナビ│障がい者専門の就職支援エージェント

求人数:4,000件以上
公式サイト:https://snabi.jp/
- 一都三県で利用可能
- 障害者雇用求人は約4,000件以上と業界最大級
- 15年以上の障害者支援実績に基づく丁寧なサポート
LITALICO仕事ナビは、障害者雇用専門の転職支援サービスで、業界でも最大級の約4,000件以上の公開求人を保有しています。
日本全国に求人があり、障害者手帳をお持ちの一都三県(東京、埼玉、千葉、神奈川)の方が登録すると、個別で転職サポートをしてもらえます。
業種や合理的配慮・在宅勤務の可否など詳細な絞り込みも可能なため、自分自身の興味のある求人を見つけやすいでしょう。また、非公開求人を紹介してもらえる場合もあります。
利用料金は完全無料で、専任のアドバイザーが就職までを徹底サポートしてくれます。15年以上の障害者支援実績に基づく、一人ひとりに合ったサポートを提供してくれるので、内定に最短でたどり着けるでしょう。
- 一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)に居住中の方
- 都心の求人を探したい方
- 障害者手帳をお持ちの方
- 20~30代で障害者雇用でキャリアアップして働きたい方
- 20~30代ではじめての障害者雇用枠で挑戦したい方
| サービス名 | LITALICO仕事ナビ |
| 運営会社 | 株式会社LITALICO |
| 公開求人数 | 約4,000件以上 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 正社員として働けるまでの期間 | 確認中 |
| 研修制度 | なし |
| 対応地域 | 一都三県 |
| 公式サイト | https://snabi.jp/ |
LITALICO仕事ナビの良い口コミ・評判
障害に対して理解のあるキャリアドバイザーが相談に乗ってくれたおかげで、転職活動への不安が解消されました。


担当者が丁寧に親切に対応してくださいました。求人数も多く、様々なジャンルのお仕事が検索できるところが良い所だなと思いました。
LITALICO仕事ナビの悪い口コミ・評判


連絡が少し遅いように感じました。アドバイザーを変えて解決しましたが、すぐに仕事を見つけたかったので、連絡があまりに帰ってこなかったのは残念でした。
LITALICO仕事ナビの担当者からのコメント


LITALICO仕事ナビは業界最大級の障害者枠の求人を保有しています。 登録は簡単なのでまずは無料で面談しましょう!
内定獲得までアドバイザーがサポートします。
関連記事:LITALICO仕事ナビの評判|登録前に知っておきたい注意点やメリットを徹底解説
dodaチャレンジ | 全国対応・適応障害専門のアドバイザー在籍


- 全国で利用可能
- 適応障害専門のアドバイザーが在籍
- 障害者の転職支援実績が豊富
- 入社後の定着率が高い
dodaチャレンジは、障害者の転職支援実績No.1を誇る転職エージェントです。全国対応であり、カウンセリングの満足度も95%(※1)と高く、質の高いサービスで好評を得ています。
登録すると、障害特性別の専任アドバイザーが配慮してほしい事項をもとに、希望を叶える求人を紹介してくれます。多くの支援実績で蓄積されたノウハウをもとに、適応障害の方の転職活動に関して的確なアドバイスを受けられます。
また、自己分析や企業研究などのサポートが充実していることからも、入社後の定着率が高いです。
そのため、入社後のミスマッチを防止したいと考えている人にdodaチャレンジはおすすめです。
(※1)dodaチャレンジの公式サイトより
関連記事:dodaチャレンジの評判は?メリット・デメリットや利用する流れまで徹底解説
就労移行支援を利用する
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つで、就労希望の障害のある方に対し、さまざまなサポートを行っています。就労に必要な知識や能力を身につけるための訓練や企業インターン、就職活動のサポート、就職後の定着支援など、多くの役立つサービスが受けられます。
就労移行支援を行っている事業所は、全国に3,000ヶ所以上あります。
参考:社会福祉施設等調査の概況|厚生労働省
施設のある場所は、お住まいの県庁または市区町村ホームページから探すか、運営する企業のホームページより探せます。
下記では安心したサポート・実績を残しており、特におすすめできる就労移行支援事業所を厳選して2つお教えします。
welbe(ウェルビー)


- 一般企業のオフィスを再現したセンターで、実務を想定しながらトレーニングできる
- 「栄養バランスが取れたランチの提供」などを通じ、生活サイクルを整えるサポートを提供してくれる
- 就職後は、定着支援に向けて「利用者・企業」の双方にサポートを提供してくれる
welbe(ウェルビー)は、各地域の障害者就職においてトップクラスの実績をあげている就労移行支援事業所です。
2025年5月現在で全国に121センターを構えており、就職者が累計8,480人います。半年定着率は91.0%と高水準を記録(2022年10月~2023年9月)しており、2018年から2023年までの長期で見ても、常に約90%の定着率を維持しています。このことから、求職者への高水準の支援、および求職者にマッチした企業の紹介がされていることがわかります。
就職を目指す方に向けて「社会人基礎力」「実践力」「持続力」の3つの力を身につけられるカリキュラムが用意されています。パソコン訓練やベーシックトレーニング(軽作業)など、就職先で長く働けるスキルが習得でき、一般企業のオフィスを再現したセンターで「働く」ことをイメージしながらトレーニングできます。
利用者の体調などを考慮し通所日数や時間を調整しつつ、正しい生活リズムが整うような配慮も行ってくれます。健康面を考慮し、栄養バランスが取れたランチを提供してくれる点も嬉しいポイントです。
就職後は、利用者へのフォローだけでなく、企業に対し「利用者との接し方」「配慮方法」などに関するアドバイスを提供しています。そのため、企業も利用者への正しいコミュニケーション方法がわかり、結果的に利用者本人の定着率アップにつながっています。
デイゴー求人ナビ・就労支援ナビ

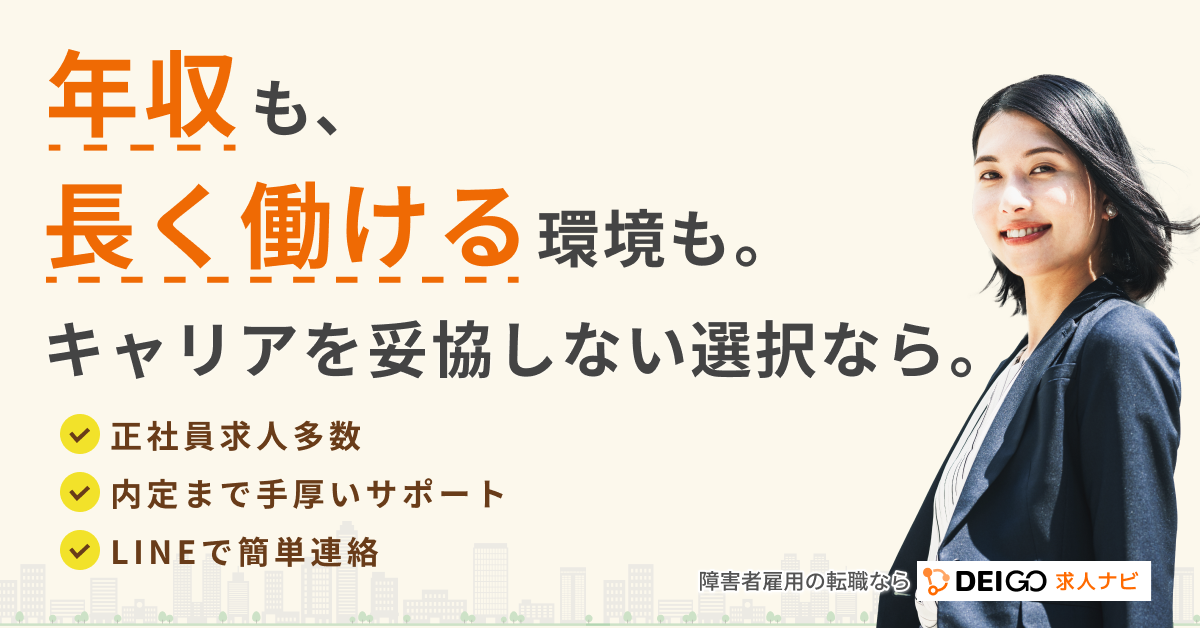
- 就労移行支援を含め、障害者が活用できる施設や障害者雇用枠の求人を幅広く紹介している
- 介護・障害福祉事業で培った専門知識をもとに信用性の高い施設の情報を提供してくれる
- おすすめの就労移行支援を地域別でまとめている
デイゴー求人ナビは、「就労移行支援・障害者雇用の求人・就労継続支援」の3つを紹介してくれるナビサイトです。
2024年9月にサービスが開始され、精神障害や知的障害、身体障害を持っている方向けの求人を紹介してもらうことができます。人材紹介サービスの経験と障害福祉事業所のノウハウを持った専任のキャリアパートナーが、利用者の特性やスキル、経験に合わせたマッチングを行ってくれるので安心です。
入社後の健康・心理状態などのヒアリングを行っているなど、就労後のサポートも充実しています。障害雇用の求人も紹介しているため、将来的に一般企業で働きたい人にとっても使いやすいでしょう。
運営会社は、介護・障害福祉士事業者向けに経営改善サービスなどを展開しているため、障害者の働き方に関する知見が豊富です。こうした豊富な知見を活かし、全国から質の高い就労移行支援を紹介してもらえるでしょう。
各地域別でおすすめの就労移行支援の事業所一覧も紹介しているため、自宅近くの施設を探す際に活用しましょう。
関連記事:デイゴー求人ナビの評判は?メリットやデメリット・特徴を口コミとともに解説
【まとめ】適応障害でも転職成功できる
適応障害により、多くの変化が起きている中での転職は、かなりの不安があるかと思います。
しかし、焦って転職活動を始めても、良い結果には繋がらないでしょう。
まずは、焦らず治療に専念することが第一です。症状が良くなってないのにも関わらず、無理をすれば、うつ病などのより重度な精神疾患を発症するかもしれません。
適応障害を発症した原因を突き止めることも大切です。原因さえわかっていれば、再発のリスクを下げられます。
また、転職活動では適応障害であることを隠さないほうがよいでしょう。
確かに公表すれば採用の面で不利になるかもしれませんが、隠してしまうと上手くできない理由を理解されないまま働くことになり、かなりつらいはずです。
適応障害であることをわかった上で、採用してくれた会社のほうが働きやすいのではないでしょうか。
適応障害での転職活動には、自身で求人サイトを利用して探す以外にも、以下のような方法があります。
自分の力だけで転職活動を進めていくのが不安な人は、ぜひとも利用してみてください。
おすすめのサービス4社
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 5.0 | 公開求人数 約4,000件 | 【一都三県にお住まいで障害者手帳をお持ちの方向け】業種や合理的配慮・在宅勤務の可否など詳細な絞り込みも可能。 | |
★ 4.8 | 公開求人数 約1,400件 | 【障害者手帳をお持ちの方向け】面接対策や書類添削など手厚いサポートが人気。 | |
★ 4.7 | 公開求人数 約1,600件 | 【全国対応!】大手ならではのサポートで大手・優良企業・正社員求人を多数保有 | |
 ★ 4.6 | 公開求人数 約2,000件 | 【一都三県・大阪にお住まいで障害者手帳をお持ちの方向け】手に職をつけて安定的に働ける。 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 5.0 | 20代 30代 40代 50代 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 | |
★ 4.8 | 20代 30代 40代 50代 | 首都圏 名古屋 大阪 兵庫 福岡 札幌 仙台 その他 | |
★ 4.7 | 20代 30代 40代 50代 | 首都圏 名古屋 大阪 兵庫 福岡 札幌 仙台 その他 | |
 ★ 4.6 | 20代 30代 40代 50代 | 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
★ 5.0 | ・発達障害を自覚し、不安もありましたが様々なサポートを受け働いています。 ・精神疾患について理解してもらえ、失敗しない会社選びについてアドバイスをもらえました。 | ||
★ 4.8 | ・これまでの経験を活かした求人を提案していただき、具体的な仕事内容まで詳しく説明してくれたので安心して応募できました。丁寧なサポートで、自分に合った職場を見つけることができました。 ・転職活動を進めていく中で、自身を失った時も、スタッフさんが丁寧に求人の選定から面接対策、応募後のフォローまで一貫してサポートしてくれたので、前向きに活動を続けられました。 | ||
★ 4.7 | 自分一人での転職活動であれば、仕事のイメージが湧かずエントリーをしていなかっただろうと思います。企業情報だけでなく仕事内容も細かく紹介していただいたことが意欲に繋がり、最終的に2社から内定をいただき、今の会社に入社しました。 | ||
 ★ 4.6 | ・肉体的な負担が少ない仕事内容の求人が豊富だったので魅力的でした。 ・障害者雇用バンクのエージェントが面接試験に合格するコツをいくつも伝授してくれた |
