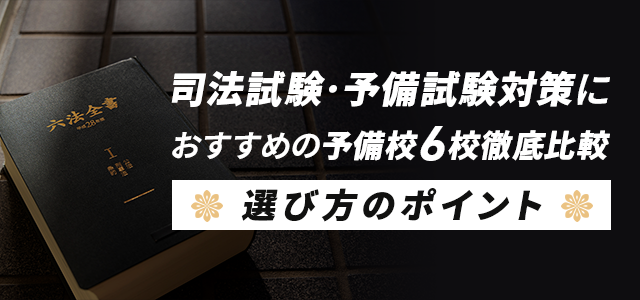司法試験・予備試験は難易度が高く出題範囲も膨大なので予備校の利用は不可欠です。
とはいえ予備試験対策講座を展開する予備校は多数あり、それぞれに特色があり、どの口座を選ぶのか悩んでいる方も多いでしょう。
そこでこの記事では講座選びのポイントを紹介したうえで、予備試験受験生から人気の高いおすすめの予備校6校の特徴を解説します。予備校選びの参考にしてください。
| 予備校名 | 特徴 |
|---|---|
| アガルートアカデミー | 令和7年の司法試験合格者は618名で、アガルート生の合格者占有率は39.1%という司法試験で高い実績を有している。 司法試験備試験合格者50%OFF |
| STUDYing | 「スキマ時間で合格」を掲げたオンライン型資格予備校。短期合格者の学習法を体系化し、能力を最大限に引き出し最短時間で知識を習得できるのが魅力。 |
| 資格スクエア | 「新世代の学習法」を提唱するオンライン型資格予備校。独自の学習メソッドとITをかけあわせた学習法は多くのメディアで取り上げられている。 |
| 伊藤塾 | 2021年予備試験ルートからの合格者のうち88.8%(5人に4人)が伊藤塾の受講生。司法試験合格者1,421名のうち1,137名が伊藤塾を何らかの形で利用する老舗予備校。 |
| LEC東京リーガルマインド | 1993年~2019年累積で5,182名と多数の司法試験合格者を輩出。受験指導歴は40年以上と長期にわたって受験指導を行ってきた実績を有する。 |
| 辰巳法律研究所 | 答練講座の人気が根強いことから、答練を含めて何らかの形で辰巳法律研究所を利用して合格した人が多いと予想される。 |
- 司法試験予備校9選おすすめ人気ランキング
- アガルートアカデミー:司法試験に合格すると受講料が全額返金!
- STUDYing:オンラインスマホ学習に特化。圧倒的コスパが特徴!
- 資格スクエア:脳科学とAIで学習を最適化!質の高い学習環境を求めている方におすすめ
- 伊藤塾:充実したカリキュラムと手厚いサポートで確実な合格を実現!
- LEC東京リーガル:全国展開の校舎と多彩な講師から選べる学習スタイル
- 資格の学校TAC:長年のノウハウを活かした教育を受けたいならここ!
- BEXA:必要な講座だけをピンポイントで選んで苦手を克服!
- 加藤ゼミナール:効率的な学習サポートを受けながら合格したい方はここ!
- 辰已法律研究所:模試の質がとにかく高い!質×金額のバランスの良さが特徴伝統の実力派予備校
- 司法試験・予備試験対策で予備校を利用するべき?
- 予備試験対策として予備校を選ぶときのポイント
- 料金は約50~120万円が相場。安いだけで選ぶのは危険。
- 司法試験・予備試験の合格率
- 司法試験・予備試験合格までに必要な学習時間
- 司法試験の受験資格を得る方法は2つ
- 最短何年で司法試験に合格可能?
- 予備試験に最短1年で合格する際のスケジュール
- 司法試験を受験するうえで注意しておきたいこと
- 2025年の予備試験・司法試験の日程
- 司法試験予備校に関するよくある質問
- まとめ
司法試験予備校9選おすすめ人気ランキング
「司法試験の勉強を始めたいけど、予備校ってたくさんあって、どこが自分に合っているのか分からない…」
予備校選びは、これから長い期間の勉強を共にする大切なパートナー選びと同じ。合格への道のりを大きく左右する、とても重要な選択ですよね。
そこでここからはおすすめの司法試験予備校をランキング形式で紹介します。
それぞれの予備校の強みや特徴を比較しながら、あなたの学習スタイルや目標にピッタリ合う場所を見つけるための参考にしてください。気になる予備校が見つかったら、ぜひ資料請求や無料体験講座で、その質を自分の目で確かめてみましょう。
アガルートアカデミー:司法試験に合格すると受講料が全額返金!
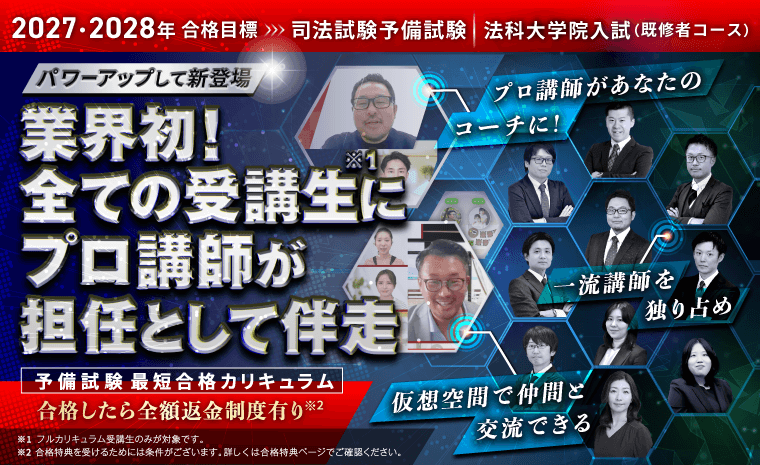
アガルートアカデミーは、最短ルートでの司法試験合格を本気で目指すすべての方におすすめです。オンライン講座のみなので、仕事と勉強を両立したい社会人や、在学中の合格を狙う大学生、そして独学の学習効率に限界を感じている方に最適なサービスといえます。
アガルートの講座料金は、初学者向けの主要講座【2028・2029年合格目標】予備試験最短合格カリキュラムは1,298,000円(税込)と、決して安価ではありません。しかし、特筆すべきは合格時の大きなリターンです。司法試験に合格すると、支払った受講料が全額返金されます(※適用条件あり)。
「司法試験対策講座|【2029年4月入学目標】法科大学院入試・法曹コース最短合格カリキュラム(スタンダード)」では「業界最強の網羅性」と「大学受験並みの個別対策」を実現。最大の特徴は、個別の法科大学院入試の過去問解説講座において22校もの対策が可能(選択式)である点です。
また、独学で不安になりがちなサポート体制も充実しています。受講生はKIKERUKUNを通じて、いつでも講師に質問することができます。さらに手厚いサポートを求める方には、プロ講師による個別指導や定期カウンセリングで学習進捗を徹底管理する「マネージメントオプション(有料)」も用意されており、学習の継続を強力に後押ししてくれます。
オンライン専門のため校舎がなく、対面での講義や自習室を利用したい方には不向きな点がデメリットとして挙げられます。しかし、令和7年司法試験において合格者占有率39.1%(合格者618名)という圧倒的な実績が、その指導の質の高さを証明しています。本気で合格を目指すなら、これ以上ない投資となるでしょう。
- 令和7年司法試験の合格者占有率39.1%という圧倒的な実績
- 合格時の「受講料全額返金+お祝い金」制度でモチベーションアップ
- オンラインに最適化された質の高い講義とフルカラーテキストで効率的に学習可能
| 予備校名 | アガルートアカデミー |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アガルート |
| 講座料金の目安 | 予備試験最短合格カリキュラム ライト:998,800円(税込) フル:1,298,000円(税込) |
| 学習形式 | オンライン講義(スマホ・PC・タブレット対応) |
| 教材 | フルカラーテキスト、デジタルブック、論証集など |
| 学習サポート | オンライン質問制度、マネージメントオプション(有料)など |
| 合格特典 | 司法試験合格で受講料全額返金+お祝い金(条件あり) |
| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/ |
STUDYing:オンラインスマホ学習に特化。圧倒的コスパが特徴!

STUDYingは、とにかく費用を抑え、お持ちのスマートフォンやタブレットで効率的に学習を進めたい方におすすめです。学習を始めるハードルを下げたい学生の方や、コストを重視する社会人の方に選ばれています。
最大の魅力は、他社を圧倒するほどの低価格な料金設定です。司法試験合格に必要なインプットから論文対策まで一貫して学べる主要コースが10万円台から受講可能で、そのコストパフォーマンスの高さが際立っています。
学習システムは、忙しい方がスキマ時間で勉強できるようスマホでの利用に最適化されています。AIが自動で最適な復習問題を提案する機能や、日々の学習タスクを明確にする「学習フロー」機能が搭載されており、迷うことなく効率的に知識を定着させられます。
学習の進捗状況がグラフで可視化されるレポート機能や、匿名の勉強仲間と繋がれる機能も、独学になりがちなオンライン学習のモチベーションを維持するのに役立ちます。
一方で、冊子版のテキストは別料金であり、講師への直接質問も有料チケット制のため、手厚い個別サポートを求める方には物足りなさを感じるかもしれません。しかし、この価格で司法試験合格を目指せる学習環境が手に入るのは大きな利点です。費用を抑えつつ、自分のペースで効率よく学びたい方にとって、最適な選択肢の一つといえるでしょう。
- 主要コースが10万円台からと、業界トップクラスの圧倒的な低価格
- スマホ一つで完結でき、AIによる問題復習など効率的な学習機能が豊富
- 学習レポートや勉強仲間機能で、独学でもモチベーションを維持しやすい
| 予備校名 | STUDYing |
|---|---|
| 運営会社 | KIYOラーニング株式会社 |
| 講座料金の目安 | 予備試験合格コース(総合):159,500円(税込) |
| 学習形式 | オンライン講義(スマホ・PC・タブレット対応) |
| 教材 | ビデオ講座、WEBテキスト、AI問題復習、スマート問題集など |
| 学習サポート | 学習レポート機能、勉強仲間機能、質問チケット制度(有料)など |
| 合格特典 | 合格お祝い金制度(最大10万円・条件あり) |
| 公式サイト | https://studying.jp/ |
資格スクエア:脳科学とAIで学習を最適化!質の高い学習環境を求めている方におすすめ
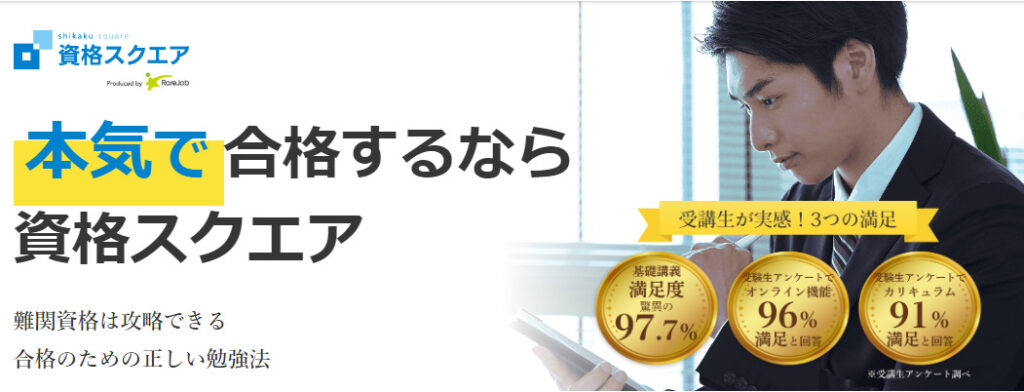
資格スクエアは、科学的根拠に基づいた効率的な学習方法を求める方に、特におすすめです。単なる暗記に頼らず、ロジカルに学習を進めたい社会人や学生、また従来の勉強法に限界を感じている方に最適な選択肢といえます。
料金は主要講座である「予備試験 合格フルパッケージ」が40万円台からとなっており、機能性の高いオンライン予備校の中では比較的バランスの取れた価格設定です。予備試験の合格で受講料が全額返金される制度もあり、コストを抑えつつ質の高い学習環境を求める方にとって魅力的なプランです。
最大の特徴は「脳科学」に基づいた独自の学習メソッドです。試験日から逆算して設計されたカリキュラムや、記憶の定着を促す「ワンクリック復習機能」が搭載されており、学習の無駄を徹底的に排除します。さらに、AIが本試験の出題を予測する「未来問」や、AIによる論文添削機能は、学習の効率を飛躍的に高めてくれます。
オンラインでの質問は24時間いつでも可能で、学習の疑問点をすぐに解消できる環境が整っています。IT技術を駆使したこれらのユニークな機能が、学習の継続を強力にサポートし、独学の不安を取り除いてくれます。
一方で、その独自性の高い学習システムは、より伝統的でオーソドックスな指導を好む方には合わない可能性も考えられます。しかし、科学的なアプローチで最短ルートを切り拓きたい方にとって、資格スクエアの提供するAI機能と効率的なカリキュラムは、他にはない強力な武器となるでしょう。
- 脳科学に基づき、記憶の定着まで考慮された効率的なカリキュラム
- AIによる出題予測「未来問」や論文添削など、独自の学習ツールが豊富
- 合格時の全額返金制度があり、コストと機能のバランスが取れている
| 予備校名 | 資格スクエア |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社レアジョブ |
| 講座料金の目安 | 予備試験 合格フルパッケージ:437,800円(税込)~ |
| 学習形式 | オンライン講義(スマホ・PC・タブレット対応) |
| 教材 | オンラインテキスト、ビデオ講座、AI機能(未来問など) |
| 学習サポート | オンライン質問機能、ワンクリック復習機能など |
| 合格特典 | 予備試験合格で受講料全額返金制度(条件あり) |
| 公式サイト | https://www.shikaku-square.com/ |
伊藤塾:充実したカリキュラムと手厚いサポートで確実な合格を実現!

伊藤塾は、司法試験合格のために確立された学習法を求めるすべての方におすすめです。網羅性の高いカリキュラムと手厚いサポート体制の下で着実に力をつけたい大学生や、安心して学習に専念したい社会人の方にとって、これ以上ない選択肢となるでしょう。
講座料金は、主要な入門講座で100万円を超え、他の予備校と比較しても高価格帯に位置します。しかし、これは単なる費用ではなく、長年の指導で培われた質の高い講義、圧倒的な情報量を誇るオリジナルテキスト、そして万全のサポート体制すべてを含んだ「合格への投資」と捉えることができます。
講義や教材の質の高さは、伊藤塾が「王道」といわれる所以です。伊藤真塾長をはじめとする経験豊富な講師陣は、法律の面白さや奥深さから伝え、受験生を惹きつけます。長年改訂を重ねてきたオリジナルテキストは、試験合格に必要な情報が網羅されており、多くの合格者が「テキストだけで十分だった」と語るほど、絶大な信頼を得ています。
学習を継続するためのサポート体制も盤石です。専門のカウンセラーや合格者チューターが学習面・精神面の両方から支え、独学の不安を解消します。東京や大阪など全国に校舎があるため、対面での相談やライブ講義への参加も可能で、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境が整っています。
デメリットとしては、その圧倒的な情報量ゆえに、一度遅れを取ると消化不良に陥る可能性がある点や、費用の負担が大きい点が挙げられます。
とはいえ、令和6年(2024年)司法試験では、最終合格者1,781名中1,287名が有料講座受講生という実績が、その指導の確かさを何よりも証明しています。確実な合格を目指すならば、最も信頼できる道しるべとなるでしょう。
- 長年の伝統と、司法試験合格者の多くを輩出してきた圧倒的な実績
- 情報が網羅された質の高いオリジナルテキストと、実力派講師陣による講義
- カウンセラーや校舎など、学習を継続するための手厚いサポート体制
| 予備校名 | 伊藤塾 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社法学館 |
| 講座料金の目安 | 司法試験入門講座:約120万円~ |
| 学習形式 | 校舎でのライブ講義、オンライン講義(ウェブキャスト) |
| 教材 | オリジナルテキスト(合格セレクション等)、論文マスターなど |
| 学習サポート | カウンセリング制度、合格者チューター、校舎利用、質問制度 |
| 合格実績 | 2024年司法試験合格者のうち1,287名が有料講座受講生 |
| 公式サイト | https://www.itojuku.co.jp/ |
LEC東京リーガル:全国展開の校舎と多彩な講師から選べる学習スタイル

LEC東京リーガルマインドは、自分に合った講師から直接指導を受けたい方や、お住まいの地域で通学できる環境を求める方におすすめです。全国に校舎を持つ大手ならではの安心感と、講師を選べる柔軟性を両立したい方に最適な予備校といえます。
料金は、主要な初学者向けコース「予備試験 1年スマート合格コース」が約70万円台からと、伊藤塾などの大手予備校の中では比較的、検討しやすい価格設定です。この価格で、長年の指導ノウハウが詰まったカリキュラムと、全国規模のサポート体制を利用できるのは大きな魅力です。
LECの最大の特徴は、実績豊富な講師陣の中から自分に合う講師を選んで、一貫した指導を受けられる「講師選択制」にあります。熱意あふれるライブ講義が魅力の講師や、色分けを駆使して分かりやすさを追求する講師など、多彩な指導スタイルのプロが在籍。もちろん、校舎での生講義だけでなく、オンラインでの受講も可能です。
学習の継続を支える環境もLECの強みです。全国40校以上の校舎には自習室が完備され、学習に集中できるほか、窓口で直接相談することもできます。地方にお住まいの方でも、都市部の受験生と同じ質の高いサポートを受けられる安心感は、他のオンライン特化型予備校にはない大きなメリットです。
どの講師が良いか、選択肢が多いために迷ってしまう可能性がある点はデメリットかもしれません。とはいえ、長年の指導実績に裏打ちされた教材の質の高さと、全国を網羅するサポート体制は、どんな学習環境の方にとっても心強い味方です。自分に合った先生と二人三脚で、着実に合格を目指したい方にぴったりの予備校です。
- 全国に展開する校舎で、通学や自習室の利用、直接相談が可能
- 個性豊かな実力派講師陣から、自分に合った講師を選択できる
- 大手ならではの安心感と、比較的リーズナブルな価格設定のバランス
| 予備校名 | LEC東京リーガルマインド |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社東京リーガルマインド |
| 講座料金の目安 | 予備試験 1年スマート合格コース:約70万円~ |
| 学習形式 | 校舎でのライブ講義、オンライン講義、Zoom講義 |
| 教材 | オリジナルテキスト、過去問集、答練など |
| 学習サポート | 全国校舎の利用(自習室・相談)、講師選択制、質問制度 |
| 合格実績 | 1993年~2024年の入門講座出身の司法試験合格者数 5,365名 |
| 公式サイト | https://www.lec-jp.com/ |
資格の学校TAC:長年のノウハウを活かした教育を受けたいならここ!

資格の学校TACは、大手資格予備校ならではの安定した学習環境で、堅実に学びたい方におすすめです。特に公認会計士など他の難関資格の学習経験がある社会人や、全国の校舎で対面サポートを受けたい方に選ばれています。
TACの魅力は、他の難関資格指導で培われた社会人教育のノウハウです。初学者向けの「予備試験本科生」コースは、法律知識ゼロから段階的に実力を養成する堅実なカリキュラムが組まれており、特に働きながら学習する社会人受験生への配慮が豊富です。料金はWeb通信講座で約60万円台からと、校舎を持つ大手予備校の中ではLECと並び、比較的検討しやすい価格帯にあります。
講義は、丁寧で分かりやすい指導に定評のある実力派講師陣が担当します。長年の受験指導で磨かれた教材作成のノウハウも強みで、図解や具体例を豊富に取り入れたオリジナルテキストは、初学者でも直感的に理解しやすいように工夫されています。
学習を継続するためのサポート体制も、全国に校舎を持つ大手ならではの強みです。講義を行う教室とは別に個別ブースの自習室が用意されており、集中できる環境を確保できます。また、担任講師制度や質問コーナーなど、オンラインだけでは難しい、きめ細やかな対面サポートを受けられる点も大きな安心材料です。
司法試験の分野では、伊藤塾やアガルートといった専門予備校に比べると、合格者数の規模では一歩譲る面もあります。しかし、社会人受験生に対する深い理解と、全国規模の安定したサポート体制は、他にはない魅力です。着実に一歩ずつ合格への階段を上りたい方にとって、信頼できるパートナーとなるでしょう。
- 公認会計士など他の難関資格で培われた、社会人教育の豊富なノウハウ
- 全国の校舎に完備された自習室や、担任講師による対面サポート
- 丁寧な指導に定評のある講師陣と、分かりやすさを重視したオリジナル教材
| 予備校名 | 資格の学校TAC |
|---|---|
| 運営会社 | TAC株式会社 |
| 講座料金の目安 | 予備試験本科生(Web通信):約64万円~ |
| 学習形式 | 校舎での教室講座、個別DVD講座、Web通信講座 |
| 教材 | オリジナルテキスト、論文答案練習会、過去問題集など |
| 学習サポート | 全国校舎の利用(自習室・質問コーナー)、担任講師制度 |
| 割引制度 | 他資格合格者割引、再受講割引、大学生協割引など |
| 公式サイト | https://www.tac-school.co.jp/ |
BEXA:必要な講座だけをピンポイントで選んで苦手を克服!
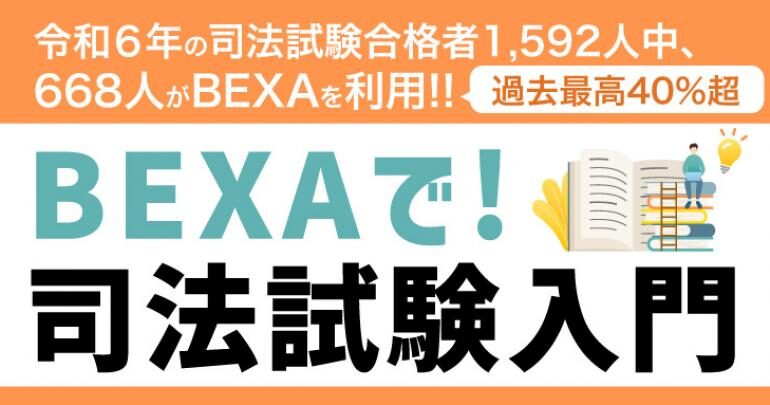
BEXAは、自分の学習状況に合わせて、必要な講座だけを自由に選びたい方に最適なプラットフォームです。特に、苦手科目を集中的に克服したい学習経験者や、他の予備校の講座を補強したい方、独学で有名講師の視点を取り入れたい方におすすめできます。
BEXAの最大の特徴は、総合コースだけでなく、さまざまな講師が提供する多種多様な「単科講座」を1科目から購入できる点にあります。料金は数千円の単発講座から数万円の科目別パックまで幅広く、自分の予算と目的に合わせて無駄なくカリキュラムを組めるため、究極のコストパフォーマンスを実現できます。
さまざまな予備校で人気を博した実力派講師が多数在籍しており、自分と相性の良い講師の講義を科目ごとに選べるのも大きな魅力です。例えば、「憲法はこの先生、民法はあの先生」といった形で、最高の講師陣で自分だけのドリームチームを編成することができます。教材はPDFで提供されることが多く、オンラインでの学習に最適化されています。
大手予備校のような手厚い担任制度はありませんが、その圧倒的な自由度が、かえって学習の継続を後押しします。高額なコース契約のプレッシャーなく、自分のペースで必要な分だけ学べるため、忙しい社会人でも精神的な負担が少なく、学習を続けやすい環境です。
一方で、どの講座をどう組み合わせれば良いか、ある程度の知識がないと判断が難しい点はデメリットといえます。完全な初学者がゼロから始める場合は、道筋が示されている他の予備校の方が安心かもしれません。しかし、自分の弱点を正確に把握している方にとって、BEXAは最高の武器を最適な価格で手に入れられる、非常に強力な学習ツールとなるでしょう。
- 必要な科目・講座だけを個別に購入できる、自由度の高いマーケット形式
- さまざまな予備校で実績のある、多彩な実力派講師陣から講義を選べる
- 自分の弱点補強やセカンドオピニオンとして、無駄なく柔軟に利用可能
| 予備校名 | BEXA |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社BEXA |
| 講座料金の目安 | 単科講座:1,000円~ / セットプラン:約10万円~ |
| 学習形式 | オンライン講義(買い切り・ダウンロード形式が中心) |
| 教材 | 各講師が作成するオリジナル教材(PDF形式など) |
| 学習サポート | 講座ごとの質問制度(講師による)、個別指導プラン(有料) |
| 特徴 | 必要な講座を自由に組み合わせる「アラカルト形式」 |
| 公式サイト | https://bexa.jp/ |
加藤ゼミナール:効率的な学習サポートを受けながら合格したい方はここ!

加藤ゼミナールは、試験合格というゴールから逆算し、最短距離での到達を目指す方におすすめです。特に、学習範囲の広さに圧倒されている方や、より密度の高いインプットを求める学習経験者、そして回り道をせずに効率よく学びたい方に最適な選択肢といえます。
加藤ゼミナールの最大の特徴は、創設者である加藤喬講師自身の合格経験にもとづき、試験合格に不要な情報を徹底的に削ぎ落とした「超効率カリキュラム」にあります。料金は初学者向けコースで約60万円台からと、オンライン予備校の中でもコストパフォーマンスを意識した設定です。合格時の返金制度も用意されています。
講義と教材の質の高さ、特にその「凝縮度」には定評があります。加藤講師が一貫して担当する講義は、論理的で分かりやすいと評判です。また、教材は重要箇所がAランク・Bランクなどで明確にランク付けされており、学習の優先順位が一目瞭然です。特に、知識をコンパクトに集約した「総まくり講座」のテキストは、多くの受験生から絶大な支持を得ています。
オンライン専門校として、学習サポートも効率化されています。受講生はいつでもオンラインで質問することができ、学習上の疑問を迅速に解決できます。学習量をあえて絞り込んでいるため、多忙な社会人や学生でも「これだけやればいい」という安心感を持って、学習を継続しやすい環境です。
デメリットとしては、情報量を絞っている分、人によっては「本当にこれだけで足りるのか」と不安に感じる可能性がある点です。また、オンライン完結のため、校舎での対面指導を求める方には向きません。しかし、試験を知り尽くした講師の指し示すルートを信じ、一直線にゴールを目指したい方にとって、加藤ゼミナールは最もシャープで信頼できる羅針盤となるでしょう。
- 合格者である創設者が全監修。無駄を徹底的に省いた超効率カリキュラム
- 重要度がランク付けされ、知識が凝縮された質の高いオリジナル教材
- オンラインに特化し、コストを抑えつつ質の高い講義を提供
| 予備校名 | 加藤ゼミナール |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社加藤ゼミナール |
| 講座料金の目安 | 予備試験 全くの初学者向けコース:約66万円~ |
| 学習形式 | オンライン講義(ストリーミング形式) |
| 教材 | オリジナルテキスト(ランク付けあり)、論証集など |
| 学習サポート | オンライン質問システム、合格返金制度 |
| 特徴 | 創設者・加藤喬講師による一貫指導と超効率主義 |
| 公式サイト | https://kato-seminar.jp/ |
辰已法律研究所:模試の質がとにかく高い!質×金額のバランスの良さが特徴伝統の実力派予備校
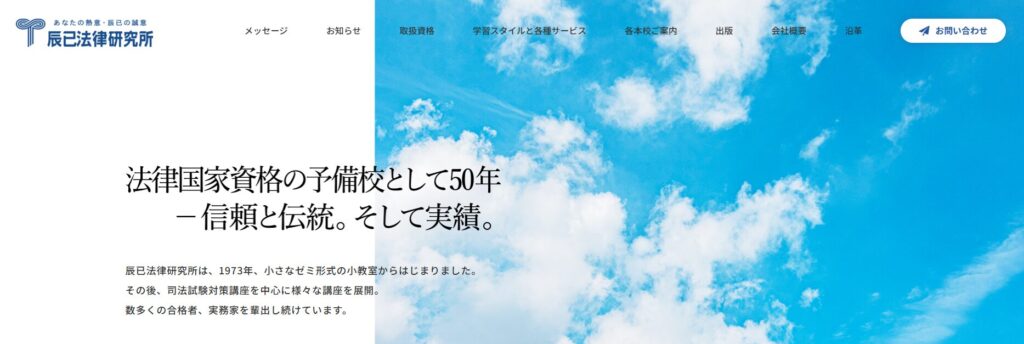
辰已法律研究所は、講義で得た知識を、答案作成という形でアウトプットする訓練を徹底的に積みたい方におすすめです。特に、論文式試験の得点力向上を目指す学習経験者や、本番さながらの緊張感で実力を試したい方に最適な予備校といえます。
辰已法律研究所の最大の強みは、なんといっても「答練・模試」の質の高さにあります。長年の指導実績にもとづき、本試験の出題傾向を徹底分析して作られるオリジナル問題は、多くの受験生から「本番に最も近い」と絶大な信頼を寄せられています。他の予備校に通う受験生も、辰已の模試だけは受験する、というのは有名な話です。
もちろん、インプット講座も充実しています。初学者向けのコースは、まず基礎知識を固め、そこからスムーズに答練へと移行できるように設計されています。料金は、論文と短答の対策をフルで学べるパックで約40万円からと、答練の質の高さを考えると非常にバランスの取れた価格設定です。
東京や大阪にある校舎では、生講義の熱気を体感できるだけでなく、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境があります。定期的に開催される答練と、それに対する丁寧な添削指導のサイクルは、自分の現在地を正確に把握し、学習のモチベーションを維持するのに非常に効果的です。
デメリットとしては、答練中心のカリキュラムは、人によっては常に試験を受けているようなプレッシャーを感じるかもしれません。また、全国に校舎を持つLECやTACに比べると、校舎の数は限られます。しかし、本番で確実に得点できる「答案作成能力」を徹底的に鍛え上げたいと考えるならば、辰已法律研究所に勝る選択肢はないでしょう。
- 本番に最も近いと評判の、質の高い「スタンダード論文答練」や「全国公開模試」
- 答練と解説講義のサイクルで、実践的な答案作成能力を徹底的に鍛えられる
- 長年の指導実績に裏打ちされた、伝統と信頼のあるカリキュラム
| 予備校名 | 辰巳法律研究所 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社辰已法律研究所 |
| 講座料金の目安 | 予備試験 論文+短答フルパック:約40万円~ |
| 学習形式 | 校舎でのライブ講義、オンライン講義 |
| 教材 | オリジナルテキスト、スタンダード論文答練、全国公開模試など |
| 学習サポート | 校舎利用、添削指導、奨学生制度 |
| 特徴 | 司法試験予備校界で随一と評される答練・模試のクオリティ |
| 公式サイト | https://www.tatsumi.co.jp/ |
司法試験・予備試験対策で予備校を利用するべき?
司法試験・予備試験を突破するためには、そもそも予備校の利用は必要なのでしょうか?合格率や学習時間を紹介しながら、予備校を利用するべきか否かについて解説します。
司法試験・予備試験の合格率
まずは司法試験・予備試験の合格率を確認しましょう。2021年予備試験の結果は以下のとおりです。
- 短答式:受験者数11,717名、うち合格者は2,723名
- 論文式:受験者数2,633名、うち合格者は479名
- 口述:受験者数476名、うち合格者は467名
受験者数11,717名のうち最終合格者は467名なので、合格率は約3.9%という結果です。例年も最終的な合格率は4%前後で推移しており、難易度が非常に高い試験であることが分かります。
司法試験・予備試験合格までに必要な学習時間
予備試験合格に必要な学習時間は、一般に3,000時間~1万時間と言われています。初学者なのか学習経験者なのか、学習環境はどうかといった要素に左右されるため個人差が大きく、一律ではありません。しかし膨大な時間が必要であることは確かだといえます。
独学で勉強すると非効率
独学で合格できる可能性はゼロではないですが、予備校の講座を利用した場合と比べてどこが重要論点なのかが分かりにくいため、とにかく時間をかけて幅広く学習しなければなりません。
しかし予備試験の範囲を網羅するには非常に多くの時間が必要となり、また受講生は試験対策のプロではないため論点がずれてしまう可能性もあります。仮に合格できたとしても非効率です。
予備校を活用して効率よく学習することが重要
合格率の低さや学習にかかる時間を考慮すると、独学ではなく予備校を利用して受験対策をするのが現実的な方法です。
各予備校が研究した受験ノウハウを教えてもらうことで膨大な受験範囲の中から合格に必要な部分だけを効率よく学ぶことができます。
予備試験対策として予備校を選ぶときのポイント
司法試験・予備試験対策を展開している予備校は多数あるため、どの予備校を選ぶべきか迷ってしまう人は多いでしょう。以下で予備校選びのポイントを挙げます。予備校を比較する際の検討材料としてください。
ライフスタイルや自分の重視する点にあった受講方法を選ぼう
あなたは、どんな風に勉強を進めたいですか?司法試験予備校の学び方には、大きく分けて「通学講座」と「通信講座」の2種類があります。自分の生活スタイルや性格に合った方を選びましょう。
- 決まった時間、決まった場所で集中して勉強したい
- 先生にその場で直接質問したい
- 一緒に頑張る仲間が欲しい
通学講座は、学校のように校舎へ通うスタイルです。強制力があるので、「一人だとついサボってしまう…」という方でも学習を続けやすいのがメリット。同じ目標を持つ仲間と出会えるのも心強い点です。
- 部活やアルバイト、仕事などで忙しい
- 自分のペースで勉強を進めたい
- 近くに校舎がない
通信講座は、スマートフォンやパソコンを使い、いつでもどこでも講義を受けられるのが通信講座の強みです。通学時間がかからないので、移動中のスキマ時間も有効活用できます。最近の司法試験予備校はオンラインに力を入れており、通信でも質の高い講義を受けられるのが一般的です。
受講料は「総額」と「保証」で選ぶ
予備校選びで最も気になるのが、やはり「お金」の問題だと思います。料金を比較する際は、単純な表示価格だけでなく、「結局、トータルでいくらかかるのか(総額)」と「もしもの時のための保証制度」という2つの視点を持つことが非常に重要です。
予備校によっては、基本料金とは別に、答練(答案練習会)や公開模試、法改正に対応した追加テキストなどが別料金になっている場合があります。「安いと思って申し込んだのに、後から追加費用がどんどんかさんでしまった…」という失敗をしないためにも、入学前に「合格までに必要な費用は、総額でいくらですか?」としっかり確認しましょう。
受講料の相場は10万円~150万円。講座内容に注意。
予備試験対策にかかる費用の相場は、おおよそ10万円~150万円と非常に幅広いです。この価格差は、講座に含まれるサービス内容の違いから生まれます。
例えば、10万円前後の安い講座は、講義動画が見られるだけで、質問対応や答案の添削といったサポートが一切付いていない場合があります。一方で、100万円を超えるような高価格帯の講座は、専属のカウンセラーが付いたり、何度でも質問や添削が受けられたりと、合格まで手厚くサポートしてくれるのが一般的です。
「安さ」だけで選んでしまうと、結局サポートが足りずに別の講座を買い足すことになり、かえって高くついてしまう可能性もあります。料金と、それに含まれる講義時間、サポート内容、教材の質などを総合的に比較し、ご自身の学習スタイルや予算に最も合った「コストパフォーマンスの良い」講座を選ぶようにしましょう。
合格保証や返金保証のある予備校・通信講座を選ぶ
「もし試験に合格できなかったら、高いお金が無駄になってしまうかも…」と不安に感じる方もいるでしょう。そんな時は、「合格保証」や「返金保証」といった制度がある司法試験予備校を選ぶと安心です。
これは、「もし目標の試験に合格できなかった場合、受講料の一部または全額を返金しますよ」「翌年の講座を無料で受講できますよ」といった、予備校からの約束のようなものです。
この制度がある予備校は、それだけ講座内容や合格実績に自信を持っている証拠ともいえます。ただし、「出席率〇%以上」といった適用条件が定められている場合がほとんどなので、契約する前に必ず細かい条件を確認するようにしましょう。
合格実績も予備校を選ぶ際の1つの目安
その予備校から、実際にどれくらいの人が合格しているかを示す「合格実績」も、信頼性をはかる重要なチェックポイントです。たくさんの合格者を輩出している予備校は、それだけ質の高いカリキュラムやサポート体制が整っている可能性が高いといえます。
ただし、数字を見るときには少し注意が必要です。ただ単に「合格者数〇〇名!」という大きな数字だけでなく、「合格率」もあわせて確認しましょう。
例えば、1000人の受講生の中から100人合格する(合格率10%)予備校と、100人の受講生の中から20人合格する(合格率20%)予備校では、後者の方が合格への期待値が高いと判断できます。いつの試験のデータなのかも確認し、最新の情報を参考にすることが大切です。
無料講座で講師の質が高いかチェックしよう
予備校選びで意外と見落としがちなのが、「講師との相性」です。どれだけ評判の良い先生でも、話し方や説明の仕方が自分に合わなければ、内容を理解するのは難しくなってしまいます。
そこで活用したいのが「無料の体験講座」です。多くの司法試験予備校では、実際の講義を無料で体験できる機会を設けています。洋服を買う前に試着をするように、まずは講義を「お試し」で受けてみましょう。
- 説明は分かりやすいか?
- 話すスピードは聞き取りやすいか?
- 聞いていて飽きないか、面白いか?
- 「この先生から学びたい!」と心から思えるか?
といった点をチェックし、あなたが「分かりやすい!」と直感的に思える先生を見つけることが、合格への近道になります。
初学者~学習経験者まで自分のレベルに合った講座を選ぶ
あなたは、法律の勉強をするのは初めてですか?それとも、大学などで少し学んだ経験がありますか?
司法試験予備校の講座は、受講生のレベルに合わせてさまざまなコースが用意されています。
- 初学者(法律の勉強が初めての人)
法律の「ほ」の字も知らないという方は、「入門コース」や「初学者向けコース」を選びましょう。法律用語の解説から丁寧に教えてくれるので、知識ゼロからでも安心してスタートできます。 - 学習経験者(少し勉強したことがある人)
大学の法学部などで基礎を学んだことがある方は、基礎知識の説明はそこそこに、問題演習や応用論点に力を入れたコースがおすすめです。自分の苦手な科目だけを選んで受講できる単科講座を利用するのも良いでしょう。
自分のレベルに合わない講座を選ぶと、簡単すぎて時間がもったいなかったり、逆に難しすぎてついていけなくなったりします。自分の現在地をしっかり把握し、最適なコースを選ぶことが重要です。
料金は約50~120万円が相場。安いだけで選ぶのは危険。
司法試験予備校を選ぶ上で、料金は誰もが気になるポイントだと思います。予備試験合格までを目指すコースの場合、料金の相場はおおよそ50万円~120万円程度です。
もちろん、できるだけ費用を抑えたい気持ちは分かりますが、「安いから」という理由だけで決めてしまうのは非常に危険です。
なぜなら、極端に安い予備校は、
- 質問できる回数が限られているなど、サポート体制が不十分
- 教材の内容が古く、最新の試験傾向に対応していない
- 合格実績がほとんどない
といったケースがあるからです。せっかく勉強を始めても、これでは合格が遠のいてしまいます。
「安物買いの銭失い」にならないよう、料金とサポート内容、教材の質のバランスが取れているか、総合的に判断するようにしましょう。
司法試験・予備試験の合格率
司法試験やその予備試験が「最難関の試験」と言われるのは、なぜなのでしょうか。その理由の一つが、合格率の低さにあります。実際のデータをもとに、その厳しい現実と、その中に隠された重要なポイントを分かりやすく解説します。
まず、司法試験の受験資格を得るためのルートの一つである「予備試験」の合格率は、毎年多くの受験生を驚かせます。令和6年(2024年)の予備試験の最終合格率は、なんと約3.6%でした。これは、100人が挑戦しても、合格できるのは3人か4人という計算になり、まさに「超」がつくほどの狭き門なのです。
では、この予備試験を突破した人や、法科大学院(ロースクール)を卒業した人が挑戦する最終関門、「司法試験」の合格率はどうでしょうか。令和6年(2024年)の司法試験全体の合格率は約42.1%です。この数字だけ見ると「意外と高い?」と思うかもしれませんが、ここには大きなポイントが隠されています。
それは、受験資格のルートによって、合格率が全く異なるという事実です。法科大学院(ロースクール)卒業者の合格率が約34.8%であるのに対し、予備試験合格者の合格率は、なんと約92.8%にも達します。この差は一目瞭然で、司法試験の受験者のうち、予備試験合格者は、ずば抜けて高い合格率を誇っているのです。
この事実は、「予備試験に合格する力があれば、司法試験の合格は目前に迫る」ということを力強く証明しています。司法試験・予備試験は、数字の上でも非常に厳しい試験ですが、この高い壁を乗り越えるためには、質の高い教材を使い、正しい方向で学習を続けることが不可欠です。
だからこそ、多くの受験生が合格への最短ルートをナビゲートしてくれる「司法試験予備校」というパートナーを選んでいます。
| 予備校名 | 特徴 |
|---|---|
| アガルートアカデミー | 令和7年の司法試験合格者は618名で、アガルート生の合格者占有率は39.1%という司法試験で高い実績を有している。 司法試験備試験合格者50%OFF |
| STUDYing | 「スキマ時間で合格」を掲げたオンライン型資格予備校。短期合格者の学習法を体系化し、能力を最大限に引き出し最短時間で知識を習得できるのが魅力。 |
| 資格スクエア | 「新世代の学習法」を提唱するオンライン型資格予備校。独自の学習メソッドとITをかけあわせた学習法は多くのメディアで取り上げられている。 |
| 伊藤塾 | 2021年予備試験ルートからの合格者のうち88.8%(5人に4人)が伊藤塾の受講生。司法試験合格者1,421名のうち1,137名が伊藤塾を何らかの形で利用する老舗予備校。 |
| LEC東京リーガルマインド | 1993年~2019年累積で5,182名と多数の司法試験合格者を輩出。受験指導歴は40年以上と長期にわたって受験指導を行ってきた実績を有する。 |
| 辰巳法律研究所 | 答練講座の人気が根強いことから、答練を含めて何らかの形で辰巳法律研究所を利用して合格した人が多いと予想される。 |
司法試験・予備試験合格までに必要な学習時間
「弁護士や裁判官になるには、一体どれくらい勉強すればいいんだろう?」と、果てしない道のりを想像して不安に思うかもしれません。
一般的に、司法試験・予備試験の合格に必要とされる学習時間は、3,000時間~8,000時間と言われています。
これは、毎日3時間みっちり勉強したとしても、3年~7年以上かかる計算です。この途方もない学習時間を、あなたはどのように乗り越えますか?ここでは、合格への道を効率的に進むための考え方について解説します。
独学で勉強すると非効率
「予備校は高いから、本屋さんで参考書を買って自分で頑張ろう」と考える方もいるかもしれません。しかし、司法試験の学習範囲は、まるで広大な海のようなもの。独学という船で、コンパスも海図も持たずにゴールを目指すのは、非常に困難で非効率だといえます。
- 何から手をつければいいか分からない
膨大な法律の中から、試験に出る重要なポイントを自力で見つけ出すのは至難の業です。勉強の順番を間違えると、遠回りになってしまいます。
- 分からないことを解決できない
難しい法律の壁にぶつかった時、質問できる相手がいません。一つの疑問を解決するために何時間も悩んでしまい、勉強がストップしてしまうこともあります。 - モチベーションを維持しにくい
一人きりでの挑戦は、孤独との戦いです。励まし合う仲間や、ペースを管理してくれる人がいないため、「今日は疲れたからやめておこう…」と、くじけやすくなってしまいます。 - 最新の試験情報が手に入らない
法律は頻繁に改正されますし、試験の傾向も毎年変わります。独学では、そうした重要な変化に気づくのが遅れてしまう危険性があります。
こうした理由から、多くの受験生は独学ではなく、予備校を活用することを選んでいます。
予備校を活用して効率よく学習することが重要
前述した3,000~8,000時間という膨大な時間を、最短ルートでゴールするために最も有効な手段が、司法試験予備校の活用です。予備校は、いわば合格への道を照らしてくれるナビゲーションシステムのような存在です。
- 合格までの最短カリキュラムがある
予備校には、長年のノウハウが詰まった「合格するためのカリキュラム」があります。「ここが試験に出る!」という要点をプロの講師が教えてくれるので、無駄な勉強をせず、効率的に知識を身につけられます。 - いつでも質問できる環境がある
分からないことがあれば、すぐに講師に質問できます。一人で何時間も悩む必要がなく、スピーディーに学習を進めることが可能です。 - 勉強を続けやすい仕組みが整っている
決まった日時に講義があったり、定期的にテストが行われたりするため、学習のペースを保ちやすくなります。同じ目標を持つライバルや仲間の存在も、大きな刺激になるでしょう。
司法試験・予備試験は、正しい努力を、正しい方向で、継続できた人が合格する試験です。予備校をうまく活用することが、その一番の近道といえます。
受講料が納得して払える額か確認する
予備校が効率的だと分かっても、やはり気になるのは高額な受講料です。「この金額を払う価値があるのかな?」と不安になるのは当然のこと。
この費用は、単なる「出費」ではなく、「自分の夢を叶えるための投資」と考えることが大切です。弁護士や検察官といった、社会で活躍する未来の自分への投資と捉えましょう。
ただし、金額の高さだけで予備校の価値を決めるのは早計です。料金の中に、どのようなサービスが含まれているのかをしっかり確認しましょう。
- 質問は無制限にできるか?
- 論文の添削は何度でも受けられるか?
- 学習の悩み相談(カウンセリング)はあるか?
こうしたサポート体制と料金を見比べて、「このサポート内容なら、この金額を払う価値がある」とあなた自身が心から納得できるかが最も重要です。ご家族ともよく相談し、自分にとって最高の投資となる予備校を選びましょう。
司法試験の受験資格を得る方法は2つ
司法試験は、誰でもすぐに受けられる試験ではありません。例えるなら、ラスボスに挑戦するための「特別な挑戦権」が必要な、特別な試験なのです。この挑戦権を手に入れるための公式なルートは、大きく分けて2つあります。
どちらの道を選ぶかによって、学習期間や費用が大きく変わってきます。あなたがどちらのルートに向いているのか、それぞれの特徴をしっかりと理解しておきましょう。
1.法科大学院(ロースクール)を修了する
一つ目は、大学を卒業した後に、「法科大学院(ロースクール)」という法律の専門家を育てるための大学院に進学し、そこを卒業(修了)する方法です。これは、学校の勉強を順に進めていく、いわば「王道」のルートといえます。
- 2年コース(既修者):大学の法学部などで、すでに法律を学んだ人向けのコースです。
- 3年コース(未修者):法学部以外の出身者など、法律を初めて本格的に学ぶ人向けのコースです。
大学を卒業後、さらに2年か3年、専門的な環境で仲間と切磋琢磨しながらじっくりと学び、司法試験の受験資格を得ます。時間はかかりますが、着実にステップアップしていきたい人に向いている方法です。
2.予備試験に合格する
二つ目は、「予備試験」という特別な試験に合格する方法です。これは、法科大学院を卒業するのと同等以上の力があることを証明し、司法試験の受験資格を得るための、いわば「飛び級」や「ワープ」が可能なルートです。
この予備試験の最大の特徴は、年齢や学歴、国籍などの受験資格が一切ないことです。大学生はもちろん、高校生や社会人でも、誰でも挑戦することができます。
もしこの試験に合格できれば、法科大学院に通う必要がなくなるため、時間も学費も大幅に節約できます。大学在学中に合格すれば、卒業後すぐに司法試験に挑戦することも可能です。
ただし、その分、予備試験自体の難易度は非常に高く、合格率は毎年わずか3~4%という超難関です。この狭き門を突破するために、ほとんどの受験生が、合格への最短ルートを知り尽くした「司法試験予備校」を活用しています。
| 予備校名 | 特徴 |
|---|---|
| アガルートアカデミー | 令和7年の司法試験合格者は618名で、アガルート生の合格者占有率は39.1%という司法試験で高い実績を有している。 司法試験備試験合格者50%OFF |
| STUDYing | 「スキマ時間で合格」を掲げたオンライン型資格予備校。短期合格者の学習法を体系化し、能力を最大限に引き出し最短時間で知識を習得できるのが魅力。 |
| 資格スクエア | 「新世代の学習法」を提唱するオンライン型資格予備校。独自の学習メソッドとITをかけあわせた学習法は多くのメディアで取り上げられている。 |
| 伊藤塾 | 2021年予備試験ルートからの合格者のうち88.8%(5人に4人)が伊藤塾の受講生。司法試験合格者1,421名のうち1,137名が伊藤塾を何らかの形で利用する老舗予備校。 |
| LEC東京リーガルマインド | 1993年~2019年累積で5,182名と多数の司法試験合格者を輩出。受験指導歴は40年以上と長期にわたって受験指導を行ってきた実績を有する。 |
| 辰巳法律研究所 | 答練講座の人気が根強いことから、答練を含めて何らかの形で辰巳法律研究所を利用して合格した人が多いと予想される。 |
最短何年で司法試験に合格可能?
「できるだけ早く弁護士や裁判官になりたい!」と考えたとき、どのくらいの時間がかかるのかは、とても気になりますよね。
司法試験の合格を目指す道には、大きく分けて「予備試験ルート」と「法科大学院(ロースクール)ルート」の2種類があり、どちらを選ぶかによって、最短で合格できるまでの期間が大きく変わります。それぞれのルートについて、詳しく見ていきましょう。
予備試験の場合
予備試験ルートは、司法試験合格への「ワープルート」や「飛び級」のようなイメージです。このルートの最大の特徴は、大学在学中など、早い段階で司法試験の受験資格を得られる可能性があることです。
予備試験には年齢や学歴などの受験資格がないため、例えば大学1年生から予備校などで本格的に勉強を始め、大学2年生や3年生で予備試験に見事合格できれば、翌年の司法試験に挑戦できます。うまくいけば、大学卒業と同時に司法試験合格者になることも可能です。勉強開始から2~3年での司法試験合格も夢ではありません。
ただし、このルートの最大の壁は、予備試験そのものの合格率が約3~4%と、非常に低いことです。この超難関を突破するためには、質の高い教材を使い、効率的な学習計画を立ててくれる予備校をうまく活用することが、最短合格を実現するためのカギとなります。
法科大学院の場合
法科大学院(ロースクール)ルートは、大学で法律の基礎を学んだ後、さらに専門的な大学院でじっくりと実力を養う、王道で着実なルートといえます。
このルートでは、まず大学を4年間で卒業し、その後、法科大学院に2年間(法律を学んだ人向けのコース)または3年間(法律を学んだことのない人向けのコース)通うことで、司法試験の受験資格が得られます。つまり、大学入学から最短でも6年(大学4年+大学院2年)の期間がかかる計算になります。
予備試験ルートに比べると時間はかかりますが、同じ目標を持つ仲間と議論を重ねながら、体系的に法律を深く学べるという大きなメリットがあります。最近では、大学の学部と法科大学院が連携して、大学を3年で早期卒業し、合計5年で司法試験の受験資格を得られる「法曹コース」という制度もできており、期間を少し短縮することも可能になっています。
司法試験にチャレンジできるのは5回まで
合格までの期間だけでなく、もう一つ知っておかなければならない重要なルールがあります。それは、司法試験は「何度でも受けられるわけではない」ということです。
現在のルールでは、司法試験の受験資格を得てから「5年以内に5回まで」しかチャレンジすることができません。
これは、ゲームのライフが5つしかないようなもので、非常に厳しい制限です。さらに注意が必要なのは、「5年以内」という期間の縛りです。たとえ受験回数が1回や2回しかなくても、最初に受験資格を得てから5年が経過してしまうと、その時点で受験資格を失ってしまいます。
このルールがあるため、「とりあえずお試しで受けてみよう」という考え方は通用しません。一回一回の受験が非常に貴重なのです。だからこそ、最初の挑戦から合格できるよう、予備校などを活用して万全の準備を整え、自分の実力に自信を持ってから本番に臨むことが何よりも大切になります。
予備試験に最短1年で合格する際のスケジュール
「予備試験に1年で合格する」というのは、非常に高い目標ですが、決して不可能な夢ではありません。実際に、毎年多くの合格者が予備校の1年合格カリキュラムなどを活用し、この目標を達成しています。
ただし、そのためには、1年間のすべてを勉強に捧げるくらいの覚悟と、綿密な学習計画が不可欠です。ここでは、多くの予備校が採用しているモデルケースをもとに、1年合格を達成するための具体的なスケジュールを紹介します。
【学習開始~年末】基礎固め期:とにかくインプット!
予備試験の試験は夏から始まるため、前年の夏(7月~8月)から学習をスタートします。最初の約半年間は、法律の知識ゼロの状態から、合格に必要なすべての科目の土台を急ピッチで作り上げる、最も重要な期間です。
- 予備校の基礎講座(入門講座)を、毎日数コマのハイペースで受講。
- 講義を聞く「インプット」と、その範囲の簡単な問題を解く「アウトプット」を必ずセットで行い、知識を定着させる。
- 憲法・民法・刑法などの主要科目から始め、年末までに行政法や商法、民事・刑事訴訟法といった全科目の基礎講義を一通り聴き終えるのが目標。
この時期は、まるで家の土台をものすごいスピードで作っていくイメージです。大変ですが、ここでの頑張りが後半に大きく影響します。
【年明け~7月】短答集中期:過去問を解きまくる!
年が明けると、7月に行われる「短答式試験(マークシート形式の試験)」に向けて、一気にギアを上げていきます。基礎講座で学んだ知識を、得点力に直接結びつけるための期間です。
- 短答式試験の過去問をとにかく繰り返し解きます。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを基礎講座のテキストに戻って徹底的に復習。
- 予備校の短答模試などを活用し、時間配分や現在の自分の実力を正確に把握。
この時期から、9月にある「論文式試験」も見据え、論文の基本的な書き方を学び始めます。
家の土台の上に、柱や壁を頑丈に組み立てていくイメージです。知識をより正確なものに仕上げていきます。
【7月~9月】論文集中期:書く練習に全力を注ぐ!
短答式試験が終わったら、自己採点をしてすぐに論文式試験の対策に切り替えます。この約2ヶ月間は、人生で最も勉強するといっても過言ではない、論文対策だけに集中する期間です。
- 論文式試験の過去問を、時間を計って解く実践的なトレーニングを毎日続ける。
- 予備校の答練(答案練習会)に参加し、プロの講師から自分の答案に赤ペンで添削指導を受け、合格できる答案の書き方を体に叩き込む。
家の内装やインテリアを整え、誰が見ても「住みたい!」と思える完璧な家を完成させるイメージです。知識を「使える武器」に変える最後の仕上げです。
【9月~1月】口述対策期:面接の準備!
論文式試験を終え、合格発表(12月頃)を待つ間も、勉強は続きます。最終関門である「口述試験(面接形式の試験)」に備える期間です。
- これまでの知識を総復習し、条文などを正確に口に出して説明できるかを確認。
- 予備校が実施する口述模試に参加し、面接官役の講師からの鋭い質問に答える練習を重ね、本番の雰囲気に慣れておく。
この非常にハードなスケジュールを1年間やり遂げるのは、並大抵のことではありません。しかし、合格までの最短ルートを知り尽くした予備校のカリキュラムを信じて走り抜けば、1年合格は現実的な目標となります。この厳しい計画を管理し、実行する上で、予備校というペースメーカーの存在が不可欠なのです。
| 予備校名 | 特徴 |
|---|---|
| アガルートアカデミー | 令和7年の司法試験合格者は618名で、アガルート生の合格者占有率は39.1%という司法試験で高い実績を有している。 司法試験備試験合格者50%OFF |
| STUDYing | 「スキマ時間で合格」を掲げたオンライン型資格予備校。短期合格者の学習法を体系化し、能力を最大限に引き出し最短時間で知識を習得できるのが魅力。 |
| 資格スクエア | 「新世代の学習法」を提唱するオンライン型資格予備校。独自の学習メソッドとITをかけあわせた学習法は多くのメディアで取り上げられている。 |
| 伊藤塾 | 2021年予備試験ルートからの合格者のうち88.8%(5人に4人)が伊藤塾の受講生。司法試験合格者1,421名のうち1,137名が伊藤塾を何らかの形で利用する老舗予備校。 |
| LEC東京リーガルマインド | 1993年~2019年累積で5,182名と多数の司法試験合格者を輩出。受験指導歴は40年以上と長期にわたって受験指導を行ってきた実績を有する。 |
| 辰巳法律研究所 | 答練講座の人気が根強いことから、答練を含めて何らかの形で辰巳法律研究所を利用して合格した人が多いと予想される。 |
司法試験を受験するうえで注意しておきたいこと
司法試験は、ただがむしゃらに勉強時間を積み重ねるだけでは、合格するのが難しい試験です。合格というゴールに最短でたどり着くためには、避けて通れない「落とし穴」や、絶対に意識しておくべきポイントが存在します。
ここでは、司法試験の勉強を始める前に、必ず心に留めておきたい3つの注意点について解説します。
全教科網羅しておく
司法試験の勉強は、まるでたくさんの科目(キャラクター)で戦うチーム戦のようなものです。一つの科目でも極端に苦手な「穴」があると、チーム全体が負けてしまう、非常に厳しいルールになっています。
司法試験には、一科目でも基準点を大きく下回ると、他の科目がどんなに高得点でも不合格になる「足切り(最低ライン)」という制度が存在します。例えば、民法が満点でも、刑法が赤点ならその時点でアウト、ということです。そのため、「この科目は苦手だから後回しにしよう」「出題数が少ないから捨ててしまおう」といった「捨て科目」を作ることは、絶対に避けましょう。
すべての科目をバランス良く、効率的に学習するためには、どの科目にどれくらいの時間をかければ良いか、戦略的に計画を立てる必要があります。予備校のカリキュラムは、まさに全科目を網羅し、苦手を作らせないように設計されています。
論文試験対策を十分におこなう
司法試験の合否を分ける最大のカギは、「論文式試験」にあるといっても過言ではありません。この試験は、ただ法律の知識を覚えているかを問うものではなく、その知識を使って、目の前の事件(問題文)をどう解決に導くか、あなたの「思考力」と「表現力」を試す試験です。
料理に例えるなら、法律知識は「食材」です。論文式試験は、その食材を使って、時間内に、採点者を納得させられる美味しい「料理(答案)」を作れるかどうかを問われています。どれだけ高級な食材を持っていても、調理の仕方を知らなければ、美味しい料理は作れません。
この「答案作成能力」は、一人で本を読むだけではなかなか身につきません。予備校などを活用し、合格者の答案と自分の答案を比較したり、プロの講師から直接添削指導を受けたりすることで、初めて「合格できる答案」の書き方が分かってくるのです。
独学での合格はかなり厳しい
ここまで説明した「全科目を網羅すること」「論文対策を十分におこなうこと」という2つのポイントを踏まえると、この試験に独学で合格することがいかに厳しいかが分かるはずです。
もちろん、予備校を使わずに合格する人がいないわけではありません。しかし、それは宝くじの1等に当たるような確率だと考えるべきです。膨大な試験範囲の中から重要な論点を自力で見つけ出し、誰の助けも借りずに論文の書き方をマスターし、高いモチベーションを何年も維持し続けるのは、現実的とは言えません。
時間は有限です。そして、司法試験には「5年で5回まで」という受験制限もあります。あなたの貴重な時間とチャンスを無駄にしないためにも、合格のノウハウを知り尽くした「司法試験予備校」というプロの力を借りることが、結果的に最も確実で、賢明な選択となるのです。
2025年の予備試験・司法試験の日程
司法試験や予備試験の合格という高い山を登るためには、まず「いつ山頂にたどり着くのか(=試験日はいつか)」というゴールを正確に知ることが大切です。試験日から逆算して学習計画を立てることが、合格への着実な第一歩となります。
ここでは、2025年(令和7年)に実施された(または、これから実施される)試験の具体的な日程をご紹介します。来年以降の受験を考えている方も、年間のスケジュール感を掴むための目安として、ぜひ参考にしてください。
予備試験の日程
予備試験は、3つのステージを順番にクリアしていく、まるでRPGのような試験です。「短答式」「論文式」「口述式」という3つの試験をすべて突破して、初めて最終合格となります。半年以上にわたる長丁場の試験なので、全体像をしっかり把握しておきましょう。
- 出願期間:2025年2月24日(月)~ 3月7日(金)
- 第1ステージ:短答式試験:2025年7月13日(日)
- 第2ステージ:論文式試験:2025年9月6日(土)、7日(日)
- 最終ステージ:口述試験:2026年1月24日(土)、25日(日)
まず7月の短答式試験に合格した人だけが、約2ヶ月後に行われる論文式試験に進むことができます。そして、論文式試験にも合格した人が、翌年の1月に行われる最終面接のような口述試験に臨む、という流れです。
司法試験の日程
司法試験は、年に一度、夏に実施される最終決戦です。予備試験合格者と法科大学院(ロースクール)卒業者が、同じ日に同じ問題で競い合います。試験は4日間にわたって行われ、知識だけでなく、集中力や体力も求められる非常にタフな試験です。
- 出願期間:2025年3月26日(水)~ 4月8日(火)
- 試験日:2025年7月9日(水)、10日(木)、12日(土)、13日(日)の4日間
試験日は毎年ほぼ同じ時期に設定されています。
試験合格というゴールに向かって、いつから何を始め、どの時期にどのレベルに達しているべきか。司法試験予備校は、長年のデータに基づいて最適な学習スケジュールを組んでくれます。試験日から逆算して計画的に勉強を進めることが、合格の可能性を大きく高める鍵となるのです。
司法試験予備校に関するよくある質問
ここでは、司法試験予備校に関するよくある質問を紹介します。司法試験予備校に対して抱いている疑問や懸念点を払拭しておきましょう。
司法試験の予備校に行くべきタイミングは?
「法曹になろう」と決意した時が最適なタイミングですが、一般的には早いほど有利です。
大学1・2年生から始めると、長期コースで無理なく学習できます。大学3年生以上や社会人向けにも、短期集中コースやオンライン講座が用意されており、いつからでも挑戦は可能です。自分の状況に合ったコースを選びましょう。
司法試験の予備校にかかる費用は?
予備試験合格までを目指すコースの費用相場は、50万円~130万円程度です。
高額ですが、これには講義、教材、手厚いサポートの全てが含まれており、合格への「未来への投資」と言えます。多くの予備校では月々の分割払いが可能なので、一度に大きなお金がなくても、計画的に支払うことができます。
まとめ
予備試験は非常に難易度の高い試験なので予備校の利用は必須です。各予備校で学習の進め方やフォロー体制など全く異なるため、自分が重視したいポイントを中心に比較検討しましょう。
| 予備校名 | 特徴 |
|---|---|
| アガルートアカデミー | 令和7年の司法試験合格者は618名で、アガルート生の合格者占有率は39.1%という司法試験で高い実績を有している。 司法試験備試験合格者50%OFF |
| STUDYing | 「スキマ時間で合格」を掲げたオンライン型資格予備校。短期合格者の学習法を体系化し、能力を最大限に引き出し最短時間で知識を習得できるのが魅力。 |
| 資格スクエア | 「新世代の学習法」を提唱するオンライン型資格予備校。独自の学習メソッドとITをかけあわせた学習法は多くのメディアで取り上げられている。 |
| 伊藤塾 | 2021年予備試験ルートからの合格者のうち88.8%(5人に4人)が伊藤塾の受講生。司法試験合格者1,421名のうち1,137名が伊藤塾を何らかの形で利用する老舗予備校。 |
| LEC東京リーガルマインド | 1993年~2019年累積で5,182名と多数の司法試験合格者を輩出。受験指導歴は40年以上と長期にわたって受験指導を行ってきた実績を有する。 |
| 辰巳法律研究所 | 答練講座の人気が根強いことから、答練を含めて何らかの形で辰巳法律研究所を利用して合格した人が多いと予想される。 |