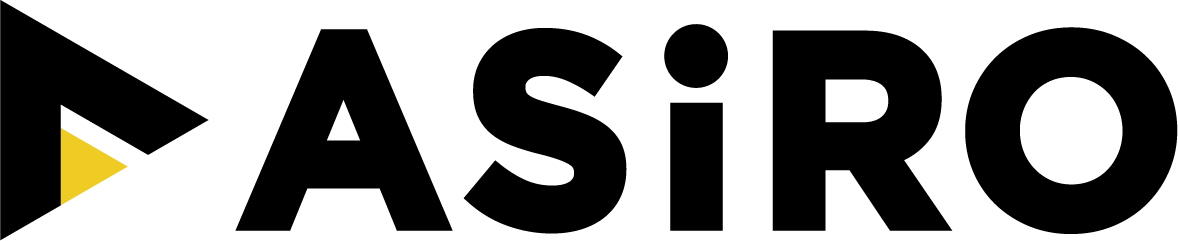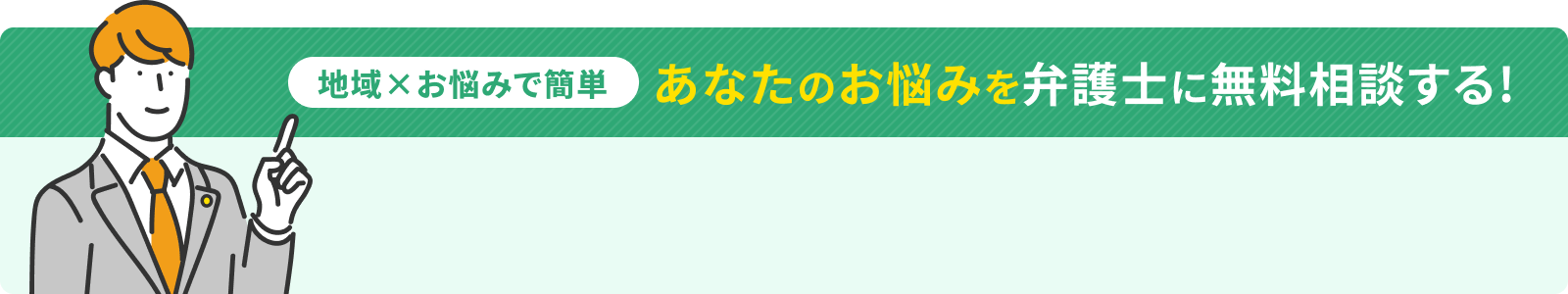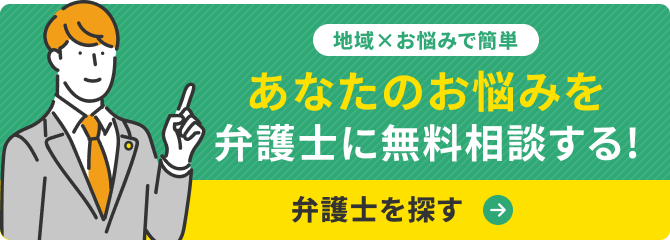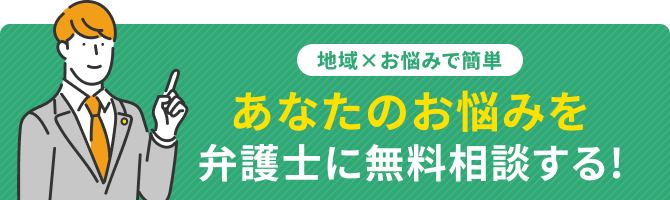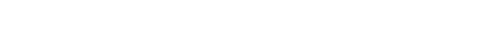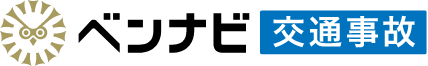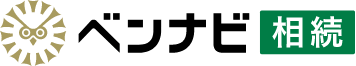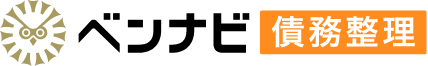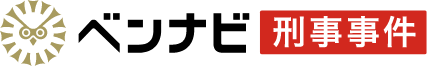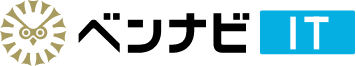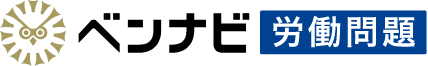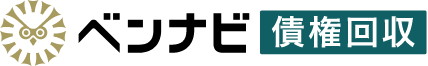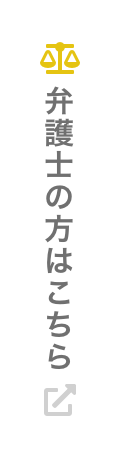損害賠償請求は弁護士なしでもおこなうことができますが、本人だけで対応するのは非常に大変です。
適切な対応ができないと、本来であれば獲得できるはずの損害賠償金が受け取れなくなるおそれもあります。
弁護士に依頼すると着手金や報酬金などの弁護士費用がかかるものの、弁護士の選び方などを工夫すれば安く抑えられる可能性があります。
さまざまなルートで弁護士を探し、合理的な費用で依頼できる弁護士を選びましょう。
本記事では、弁護士なしで損害賠償を請求する方法やデメリット、弁護士に依頼するメリットや、弁護士費用を安く抑える方法などを解説します。
解決したい
減らしたい
相談内容を選択してください
獲得したい
揉めている
弁護士をしてほしい
相談できる
親族と揉めている
対策をしたい
請求したい
されてしまった
訴えたい
払ってもらえない
分からない
お金を取り戻したい
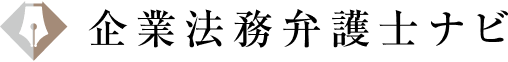
企業法務に
実績のある弁護士が
経営課題を解決
労働者・従業員側のご相談はベンナビ労働問題で受け付けています。
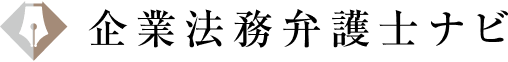
企業法務に
実績のある弁護士が
経営課題を解決
損害賠償請求は弁護士なしでも可能だが、失敗するリスクがある
まず、損害賠償請求は自力でおこなうことも可能です。
ただし、損害賠償請求では、証拠などを準備したうえで的確な主張を展開する必要があります。
法律知識や交渉経験のない素人では適切に対応できず、なかなか相手方が応じてくれずに交渉が難航したり、相手方に交渉の主導権を握られて不利な条件で合意したりする場合もあります。
また、直接交渉では解決が難しい場合は訴訟などの法的手段に移行することもあり、その際に手続きを有利に進めるためには法律に関する知識が必要となります。
素人が自力で対応しようとすると失敗するリスクが高まるため、損害賠償請求をおこないたい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
初回相談無料の法律事務所も多くあるので、まずは一度相談してみましょう。
損害賠償請求ができるケースの例
損害賠償請求は、さまざまなトラブルが起きた際におこなうことができます。
以下に挙げているのは、損害賠償請求ができるケースの一例です。
- 債務不履行に基づく損害賠償請求
- 不法行為に基づく損害賠償請求
- 使用者責任に基づく損害賠償請求
- 工作物責任に基づく損害賠償請求
- 製造物責任に基づく損害賠償請求
ここでは、それぞれのケースについて解説します。
債務不履行に基づく損害賠償請求
「債務不履行」とは、契約をして決めた義務を果たさないことをいいます。
たとえば業務委託契約の場合、受託者は委託者のために何らかの業務をおこない、委託者は受託者に業務の対価として報酬を支払います。
業務を遂行することは受託者の義務、報酬を支払うことは委託者の義務です。
受託者が業務を遂行する義務を怠れば、委託者は業務が停滞することにより損害を被ります。
この損害につき、委託者は受託者に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です(民法415条1項)。
また、受託者が業務を遂行したにもかかわらず委託者が報酬を支払わなければ、受託者は本来受け取れるはずだった報酬を利用できない損害を被ります。
この場合、受託者は委託者に対して、債務不履行に基づく損害賠償(遅延損害金)を請求できます。
不法行為に基づく損害賠償請求
「不法行為」とは、故意・過失により、他人の権利や法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせる行為のことです(民法709条)。
不法行為の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できます。
たとえば、以下のような場合には不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
- 知的財産権(特許権・商標権・著作権など)を侵害された場合
- 交通事故の被害に遭った場合
- 配偶者が不貞行為をした場合
- インターネット上で誹謗中傷を受けた場合 など
使用者責任に基づく損害賠償請求
「使用者責任」とは、被用者が事業執行の際に第三者に加えた損害について、使用者が負う責任のことです(民法715条)。
被用者の選任・事業の監督について相当の注意をしたことや、相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを証明しなければ、使用者は使用者責任を免れません。
また、使用者の代わりに事業を監督する者も使用者責任を負います。
たとえば、以下のような場合には使用者責任に基づく損害賠償請求が可能です。
- 他社の従業員が、その会社の業務の一環として、自社のコンテンツを盗用した場合
- 上司のパワハラによって精神疾患を患った場合
- 医師の過失によって医療ミスが発生した場合(医療機関が使用者責任を負う) など
工作物責任に基づく損害賠償請求
「工作物責任」とは、土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって生じた損害につき、その工作物の占有者または所有者が負う責任のことです(民法717条)。
原則として占有者が工作物責任を負いますが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、所有者が工作物責任を負います。
所有者の工作物責任は、過失を要件としない「無過失責任」とされています。
また、竹木の植栽・支持に瑕疵がある場合にも、竹木の占有者・所有者が工作物責任を負います。
たとえば、以下のような場合には工作物責任に基づく損害賠償請求が可能です。
- 道路を通行していたところ、建物に備え付けられた看板が落下してきてけがをした場合
- 私立学校の運動設備を用いて運動していたところ、設備が破損してけがをした場合 など
※国公立学校の場合は、国家賠償責任が問題となる
製造物責任に基づく損害賠償請求
「製造物責任」とは、引き渡した製造物の欠陥によって生じた損害につき、製造業者などが負う責任のことです(製造物責任法3条)。
なお、欠陥があった製造物が壊れただけの場合は製造物責任の対象外で、それ以外の損害が生じたことが必要です。
製造物責任の免責要件は、通常の不法行為よりも非常に厳しくなっています。
以下のいずれかの事実を証明しなければ、製造業者などは製造物責任を免れることができません(製造物責任法4条)。
1.開発危険の抗弁
免責事由のひとつである「開発危険の抗弁」とは、以下のようなことを指します。
- 「製造物を引き渡したときにおける科学または技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識できなかった」ということを主張立証すること
2.部品製造業者の抗弁
もうひとつの免責事由である「部品製造業者の抗弁」とは、以下のようなことを指します。
- 「当該製造物がほかの製造物の部品または原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該ほかの製造物の製造業者がおこなった設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつその欠陥が生じたことにつき過失がない」ということを主張立証すること
たとえば、以下のような場合には製造物責任に基づく損害賠償請求が可能です。
- ノートパソコンのバッテリーが発火して火災が生じ、自宅の一部が燃えた場合
- 石鹸の中に表示されていないアレルギー物質が含まれており、使用したところアナフィラキシーショックを発症した場合 など
弁護士なしで損害賠償請求をする方法
損害賠償請求は、弁護士なしでもおこなうことができます。
弁護士なしで損害賠償を請求する際は、以下のような方法でおこないます。
- 相手方に連絡する(内容証明郵便の送付・直接交渉など)
- 民事調停を申し立てる
- ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する
- 本人訴訟を提起する
1.相手方に連絡する(内容証明郵便の送付・直接交渉など)
法的手段などに移行することなく相手方との話し合いがまとまれば、早期に損害賠償金を受け取ることができます。
損害賠償請求をおこなうにあたっては、まず相手方と連絡をとる必要があります。
メールなどでメッセージを送るという方法もありますが、正式な請求であることを明確化しておくためにも内容証明郵便で請求書を送付するのがよいでしょう。
内容証明郵便による請求書の送付には、消滅時効の完成が6ヵ月間猶予されるという効果もあります(民法150条1項)。
請求書の送付などによって相手方と連絡をとったら、損害賠償請求の交渉を始めましょう。
相手方との間で条件を提示し合い、状況に応じて歩み寄ったりして合意を目指します。
無事に交渉が成立した場合は、合意内容を和解合意書(示談書)にまとめて締結したのち、合意内容に従って損害賠償金が支払われて終了となります。
2.民事調停を申し立てる
弁護士に依頼せずに損害賠償請求する際には、民事調停を利用するのも有効です。
民事調停とは、簡易裁判所で実施される紛争解決手続きです。
調停委員による仲介のもと、当事者間で話し合って紛争解決を模索します。
民事調停では、客観的な立場にある調停委員が、紛争解決に向けた意見調整などのサポートをしてくれます。
代理人の弁護士がいない状況では、調停委員のサポートが大きな助けとなるでしょう。
ただし、調停委員はあくまでも中立的な立場にあり、弁護士とは違って自分の味方として動いてくれるわけではないという点には注意しましょう。
3.ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する
客観的な立場から紛争解決をサポートしてもらいたい場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)の利用も効果的です。
ADRとは、裁判所以外の第三者機関が取り扱う紛争解決手続きです。
ADRの手続きは、特定の事件の種類に特化されていることが多く、専門的な紛争解決サポートを受けられるというメリットがあります。
以下に挙げるのは、ADRの一例です。
- 交通事故ADR:公益財団法人交通事故紛争処理センター、公益財団法人日弁連交通事故相談センター
- 医療ADR:医療ADR|日本弁護士連合会
- 金融ADR:金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)|金融庁
4.本人訴訟を提起する
示談交渉・民事調停・ADRによる紛争解決は、相手方の協力がなければ成立しません。
相手方との間で歩み寄りの余地がない場合は、裁判所に訴訟を提起する必要があります。
弁護士を代理人とせず、本人が自ら裁判手続きをおこなうことを「本人訴訟」といいます。
弁護士費用をかけたくないなどの理由から、本人訴訟を選択する方も一定数います。
特に少額の損害賠償請求の場合、弁護士に依頼すると費用倒れになることが多いため、本人訴訟が選択されやすい傾向にあります。
なお、60万円以下の請求であれば、審理が原則1回で迅速に終結する「少額訴訟」を利用でき、本人訴訟を考えている方は少額訴訟も検討しましょう。
【参考元】少額訴訟|裁判所
弁護士なしで損害賠償請求をすることのデメリット
弁護士なしで損害賠償請求をおこなうのは、実際のところ非常に大変です。
特に以下のデメリットには注意が必要で、懸念がある場合は弁護士への依頼をご検討ください。
- 法的に適切な主張・立証をするのが難しい
- 損害賠償金の請求漏れが生じやすい
- 請求に必要な書類を準備する手間がかかる
- 調停・ADR・訴訟などの手続きを正確におこなうのが難しい
法的に適切な主張・立証をするのが難しい
損害賠償請求を成功させるためには、法的な根拠に基づいて主張をすることが大切です。
もし交渉不成立となって損害賠償請求訴訟に発展した場合は、裁判所にて証拠を用いて主張立証しなければなりません。
適切に主張立証をおこなうためには法的な観点からの検討が必要になりますが、弁護士の力を借りることなく自分で適切に判断するのは非常に困難です。
主張立証に不備があった場合には、損害賠償請求が認められないおそれもあり、納得のいかない結果となってしまうこともあります。
損害賠償金の請求漏れが生じやすい
たとえば、不法行為などによる損害賠償請求の場合、請求できる項目はひとつではなく、具体的な事情に応じてさまざまなものが請求可能です。
交通事故トラブルであれば、被害状況に応じて以下のようなものが請求可能です。
- 治療費
- 通院交通費
- 装具・器具の購入費
- 付添費用
- 介護費用
- 入院雑費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
- 葬儀費用
- 後遺障害逸失利益
- 死亡逸失利益
- 車の修理費(買替費用)
- 車の評価損
- 休車損害 など
損害賠償請求する際は、被害者側に生じた損害を漏れなく集計する必要があります。
しかし、初めて直面したトラブルについて、損害を漏れなく把握・算出することは非常に難しいでしょう。
素人では請求漏れに気付かないまま損害賠償請求の手続きを進めてしまい、本来よりも低額な賠償金を受け取ることになるおそれがあります。
請求に必要な書類を準備する手間がかかる
損害賠償請求にあたっては、主張の根拠となる資料を揃えて提示しなければなりません。
民事調停やADRを利用する際には申立書や関連書類、訴訟提起する際には訴状などの作成が必要です。
損害賠償請求の手続きが不慣れな方にとって、これらの資料を全て準備するのは非常に大変な作業です。
適切な資料を準備できていないと解決が長引くことになりますし、賠償金額にも影響するおそれもあります。
民事調停・ADR・訴訟などの手続きを正確におこなうのが難しい
民事調停・ADR・訴訟などの手続きは専門性が高く、一般の方は戸惑う部分も多いでしょう。
自分でルールなどを調べながら、これらの手続きについて適切に対応するのは大きな負担となります。
場合によっては、不適切な対応をしてしまったりして調停委員・ADR委員・裁判官などの心証を害し、不利な立場に置かれることになるおそれもあります。
損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット
損害賠償請求は弁護士なしでも可能ですが、自力でおこなうとリスク・デメリットが多くあるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
ここでは、損害賠償請求を弁護士に依頼する主なメリットについて解説します。
正確な賠償金を算出してくれる
弁護士に依頼すれば、依頼内容を把握したうえで正確な賠償金を計算してくれます。
賠償金額は損害の程度や内容などによって大きく変わりますが、弁護士ならこれまでの解決事例や過去の判例などを参考にしながら、根拠のある金額を算出してくれます。
相手方の提示額に対しても妥当かどうか客観的に判断してくれて、もし低額な賠償金を提示されている場合は反論してもらうことで獲得金額の増額が期待できます。
交渉や裁判などの請求対応を一任できる
弁護士なら、トラブル相手とのやり取りを一任することができます。
相手との交渉が決裂して訴訟などに移行する場合でも、弁護士は依頼者の代理人としてそのまま裁判手続きに対応してくれます。
民事調停・ADR・訴訟などでの必要書類の収集のほか、損害賠償請求を有利に進めるための情報収集も進めてくれるなど、弁護士は依頼者の利益のために尽力してくれます。
弁護士に依頼することで請求手続きにかかる精神的負担が大きく減りますし、特に交通事故などでけがを負っている場合は治療に集中できるというのも大きなメリットです。
トラブルなくスムーズな賠償金の獲得が望める
弁護士に依頼した場合、自力で対応するよりもスムーズな賠償金の獲得が期待できます。
当事者同士で交渉しようとすると、お互い感情的になってトラブルに発展したり、なかなか落としどころが見つからずに交渉が難航したりすることもあります。
弁護士なら、法的視点から冷静に交渉を進めてくれるほか、相手方と主張が対立している場合は妥当な落としどころを見極めてくれるなど、相手の出方に応じて臨機応変な対応が望めます。
なかには弁護士に対応を代わってもらうことで相手側がプレッシャーを感じ、これまでの態度が変わってすんなり請求に応じてくれることもあります。
解決したい
減らしたい
相談内容を選択してください
獲得したい
揉めている
弁護士をしてほしい
相談できる
親族と揉めている
対策をしたい
請求したい
されてしまった
訴えたい
払ってもらえない
分からない
お金を取り戻したい
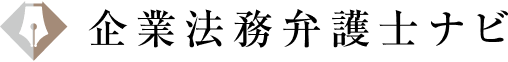
企業法務に
実績のある弁護士が
経営課題を解決
労働者・従業員側のご相談はベンナビ労働問題で受け付けています。
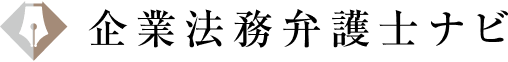
企業法務に
実績のある弁護士が
経営課題を解決
損害賠償請求を弁護士に依頼する場合の費用相場・内訳
弁護士への依頼を考えている方の中には、弁護士費用がどれだけかかるのか気になっている方もいるでしょう。
ここでは、損害賠償請求でかかる弁護士費用の内訳や相場について解説します。
弁護士費用の内訳
弁護士費用の内訳としては、主に以下のようなものがあります。
| 項目 | 概要 |
| 相談料 | 弁護士に法律相談する際に支払う費用 |
| 着手金 | 弁護士に案件対応を依頼する際に支払う費用 ※依頼が失敗に終わった場合も原則返金されない |
| 報酬金(成功報酬) | 弁護士の介入によって問題が解決した場合に発生する費用 ※問題解決しなかった場合は発生しない |
| 日当 | 弁護士が案件対応のために事務所外に出張した場合に発生する費用 |
| 実費 | 弁護士が案件対応の際に実際にかかった費用 |
弁護士費用の相場
弁護士に損害賠償請求を依頼する場合、弁護士費用の相場は以下のとおりです。
| 項目 | 相場 |
| 相談料 | 30分あたり5,000円~1万円程度 ※初回相談無料の法律事務所もある |
| 着手金 | 依頼者の請求金額によって異なる |
| 報酬金(成功報酬) | 依頼後の獲得金額によって異なる |
| 日当 | ・半日出張の場合:3万円~5万円程度 ・1日出張の場合:5万円~10万円程度 |
| 実費 | 弁護士の対応内容によって異なる |
着手金や報酬金の相場は以下のとおりで、かつて用いられていた「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」という報酬基準を参考にしています。
| 経済的利益の額 | 着手金相場 |
| 300万円以下 | 経済的利益の8% |
| 300万円超3,000万円以下 | 経済的利益の5%+9万円 |
| 3,000万円超3億円以下 | 経済的利益の3%+69万円 |
| 3億円超 | 経済的利益の2%+369万円 |
| 経済的利益の額 | 報酬金相場 |
| 300万円以下 | 経済的利益の16% |
| 300万円超3,000万円以下 | 経済的利益の10%+18万円 |
| 3,000万円超3億円以下 | 経済的利益の6%+138万円 |
| 3億円超 | 経済的利益の4%+783万円 |
ただし、実際のところは法律事務所によっても料金体系・金額設定は異なります。
あくまでも上記の金額は参考程度に留めて、正確な金額を知りたい方は直接事務所にご確認ください。
弁護士費用の負担を抑えながら弁護士に依頼する方法
損害賠償請求を弁護士なしでおこなうのは非常に大変であるため、可能であれば弁護士に依頼することが望ましいです。
弁護士費用について懸念がある方は、費用負担を抑えながら弁護士に依頼するためにも、以下のような方法を検討しましょう。
- 無料法律相談を利用する
- 複数の弁護士に相談して、見積もりを比較する
- 着手金を後払い・分割払いにしてもらう
- 着手金と報酬金の配分を交渉する
- 法テラスの民事法律扶助制度を利用する
無料法律相談を利用する
弁護士との法律相談では相談料がかかりますが、なかには初回無料相談を実施しているところもあります。
少しでも弁護士費用を抑えたい場合は、無料法律相談に対応している法律事務所に絞って依頼先を探すのが有効です。
なお、弁護士との無料法律相談は依頼するか否かにかかわらず利用できるため、弁護士への依頼を悩んでいる方も気軽に相談してみることをおすすめします。
当社が運営する弁護士ポータルサイト「ベンナビ」では、各分野に強い全国の弁護士を掲載しており、初回相談無料の法律事務所も多くあります。
相談内容・相談地域を選択するだけで対応可能な弁護士を一括検索できますので、弁護士との相談を検討している方はぜひご利用ください。
複数の弁護士に相談して、見積もりを比較する
具体的に弁護士費用がいくらかかるのかは、依頼する弁護士によっても変わります。
少しでも弁護士費用を抑えたい場合は、複数の弁護士に相談して見積もりを出してもらい、どこが安いのか比較してみるのがよいでしょう。
その際も、ベンナビなどの弁護士ポータルサイトを利用すれば、検索結果から何人かの弁護士をリストアップして電話やメールで直接問い合わせることで、複数の弁護士をスムーズに比較できるためおすすめです。
着手金を後払い・分割払いにしてもらう
弁護士に損害賠償請求を依頼する際には、着手金を支払う必要があります。
着手金は依頼時に一括払いするのが原則ですが、弁護士に相談すれば後払いや分割払いを認めてもらえることもあります。
すぐにまとまったお金を準備できない方は、経済的な事情で着手金を一括で支払うのが難しいことを説明して、後払いや分割払いをお願いできないか交渉してみましょう。
【関連記事】弁護士に支払う着手金の後払いは可能? 弁護士費用が支払えない場合の対処法
着手金と報酬金の配分を交渉する
成功率が高いと思われる損害賠償請求のケースでは、弁護士に相談すれば着手金と報酬金の配分を変えてもらえる可能性もあります。
報酬金を増額する代わりに着手金を減額してもらえれば、依頼時の経済的負担は減ります。
着手金と報酬金の配分変更に応じるかどうかは弁護士の方針によっても異なりますが、どうしても支払いが難しい場合は相談してみましょう。
法テラスの民事法律扶助制度を利用する
法テラス(日本司法支援センター)とは、法律トラブルの解決をサポートしてくれる公的機関のことです。
法テラスでは「民事法律扶助制度」として、弁護士による30分×3回の無料法律相談や、弁護士費用の立替払いなどのサポートを提供しています。
弁護士費用の立替払いを利用した場合は、法テラスへ毎月5,000円~1万円ほど返済していく必要がありますが、通常の弁護士費用よりも安く済むケースも多くあります。
ただし、民事法律扶助制度には収入基準や資産基準などの利用要件が設けられており、詳しくは「民事法律扶助業務|法テラス」をご確認ください。
法テラスの利用を希望する方は、「お近くの法テラス(地方事務所一覧)|法テラス」から近くの地方事務所にご相談ください。
なお、法テラスの契約弁護士を自分で探して相談すれば、その弁護士を通じて法テラスの利用を申し込むことも可能です。
ベンナビでは法テラスの契約弁護士も多数掲載しており、電話やメールで直接問い合わせることができるので、法テラスの利用を検討している方は一度ご確認ください。
さいごに|損害賠償請求を考えているなら、まずはベンナビで無料相談を
損害賠償請求を弁護士なしでおこなうことはできますが、適切に対応するのは非常に大変です。
弁護士なら、代理人として相手方とのやり取りを一任できますし、法律知識や交渉ノウハウを活かして迅速かつ適切な額の賠償金獲得が望めます。
法律事務所によっては後払いや分割払いなどに対応しているところもあるため、現在手持ちがなくて依頼を悩んでいる方も、まずは無料相談などを利用してみましょう。
ベンナビなら、各分野に強い全国の弁護士を掲載しており、相談内容や相談地域から対応可能な弁護士を一括検索できます。
初回相談無料・着手金0円・後払い対応・分割払い対応などの法律事務所も多くあるので、損害賠償請求を考えている方は一度ご利用ください。
解決したい
減らしたい
相談内容を選択してください
獲得したい
揉めている
弁護士をしてほしい
相談できる
親族と揉めている
対策をしたい
請求したい
されてしまった
訴えたい
払ってもらえない
分からない
お金を取り戻したい
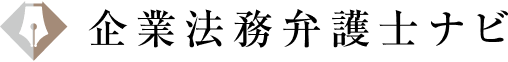
企業法務に
実績のある弁護士が
経営課題を解決
労働者・従業員側のご相談はベンナビ労働問題で受け付けています。
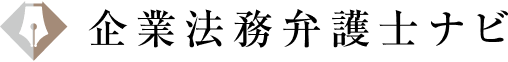
企業法務に
実績のある弁護士が
経営課題を解決