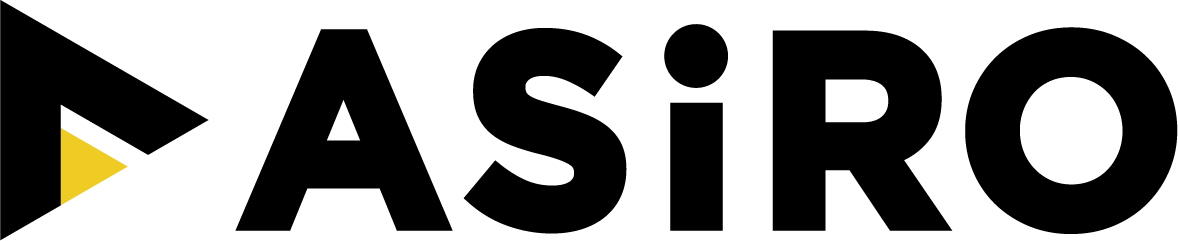固定資産税の金額等から考えると、借地代をもう少し減額してほしいと考えている方も多いのではないでしょうか。
借地契約は20年〜30年続くのが前提の契約です。その当時の時価や経済状況などを考慮して決めた借地代が変更されていない場合、今の相場では不相当な金額で設定されていることもあるでしょう。
ただ、いざ借地代を減額したいと考えたとしても、どうやって請求すればいいのかわからない方も多いと思います。
本記事では、借地代の減額方法や正しい計算方法についてわかりやすく解説していきます。
不動産業界の法務について弁護士を探す 電話相談・オンライン相談可・初回面談無料 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
借地代の減額請求ができる場合とは
借地代の減額請求は、どんな場合でも請求できるわけではなく、ある一定の条件下でのみ認められます。
まずは、借地代の減額ができるのはどんな場合なのかについて解説していきます。
相場よりも高いというだけでは減額してもらえない
借地代は、法律でその金額が決まっているわけではなく、当事者同士の話し合いで決めるものなので、貸主が減額に応じるのであれば、借地代が相場よりも高いという理由だけで減額してもらうことも可能ではあります。
しかし、最初に契約するときに、「今後20年〜30年経過して相場が変わる可能性はあるが、借地代は契約当時の相場に基づいて決める」という意味合いで、お互い合意のうえ借地代を決めたはずです。
そのため、後になってから借地代が今の相場より高いという理由だけで減額の請求をすることは、法的には簡単に認められない請求となるのです。
減額請求が認められる要件とは
借地代の減額請求が認められるための要件は、借地借家法で定められています。
第11条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課(※1)の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動(※2)により、又は近傍類似(※3)の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
※1固定資産税・都市計画税など
※2物価指数、通貨供給量、労働賃金指数など
※3同種の業態で比較する必要があるため、たとえば飲食店と賃貸アパートなどは比較の対象にはなりません。
バブル崩壊やリーマンショックなど、経済事情が大きく変動した場合や、固定資産税や都市計画税などの税金・時価の変動などにより、借地代が、周りの土地と比較して高いと認められれば、減額請求は認められることになります。
特約があっても減額請求ができる場合もある
契約の際に、「たとえ今後消費者物価指数が低下したとしても、賃料の減額は認められない」という特約を結ぶことがあるかもしれません。
しかし、この特約を結んでいたとしても、要件を満たせば減額請求をできることが、最高裁判所の判例で認められています(最高裁平成16年6月29日第三小法廷判決)。
つまり、借地借家法第11条は、当事者の合意内容に左右されず、強制的に適用される強行法規なので、第11条第1項に定められている通り、一定期間増額をしない旨の特約は認められるが、それ以外の特約は認められない、としたのです。
借地借家法は、取引において弱い立場にある消費者を守る規定なので、消費者が不利になるような特約は、法的には認められないのです。
どれくらい減額できる?借地代の計算方法
借地代の減額請求をすると、どれくらい減額できるのでしょうか。
借地代の相場は、固定資産税や都市計画税の2倍~3倍といわれていますが、正確に計算するためには、不動産鑑定士が使う計算方法で算出する必要があります。
借地代を計算する方法は、全部で4つあります。
- 差額分配法
- 利回り法
- スライド法
- 賃貸事例比較法
ここでは、それぞれの計算方法をくわしく解説していきます。
差額配分法
差額配分法では、「現在の借地代」と「適正な借地代」の差額を基準にして借地代を算出します。
【差額分配法】
- 現在の借地代+(適正な借地代-現在の借地代)×差額の配分率
「差額の配分率」は、以下の要素を考慮して決定します。
【差額の配分率を決める際の考慮要素】
- 契約した期間や、残りの契約期間
- 契約から現在までの経緯や事情の変化(ex.経済事情が大幅に変化した)
- 貸主、借主双方の近隣地域の発展に対する貢献度 など
差額の配分率はおおむね1/2〜1/3ほどで設定されることが多いです。
【具体例】
・現在の借地代:150万円(年間)
・適正な借地代:100万円(年間)
・配分率が1/2
【計算式】
・150万円+(100万円-150万円)✕1/2=125万円
・借地代:125万円(年間)・減額できた金額:25万円
利回り法
利回り法とは、契約当時に想定していた利回りや賃金改定時の利回りを、今の土地価格で計算したらどうなるのかを基準にして借地代を算出する計算方法です。
【利回り法】
- 基礎価格(※1) ×継続賃料利回り(※2) + 必要経費(※3)
※1 「基礎価格」とは、現在の土地の評価額(地価)のことで、「底地価格」を用いて計算します。
- 底地価格=更地価格-路線価で定められた借地権割合
「低値価格」とは・・・借地権が設定されている土地の価格
「更地価格」とは・・・借地権が設定されていない場合の土地の価格
「路線価」とは・・・路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額
※2「継続賃料利回り」とは、契約当時に想定していた利回りのことを指します。
- 継続賃料利回り(※3)=(現在の借地代 - 必要経費) / 契約当時の土地の評価額
※3必要経費とは、固定資産税や維持管理費など、不動産を維持するうえで必要になる経費のことを指します。
【具体例】
・基礎価格(土地の評価額):3,000万円
・継続賃料利回り:3%
・必要経費:25万円
【計算式】
・3,000万円✕3%+25万円=115万円
・地代:115万円(年間)
スライド法
スライド法とは、物価や地価の変動、所得水準の変動、その時の経済事情の変動に合わせて、借地代も変動させる算出方法のことです。
【スライド法】
- (現在の借地代-契約当時設定した必要経費)×変動率+現在の必要経費
【具体例】
・現在の借地代:120万円(年間)
・契約当時設定した必要経費:20万円
・物価変動率:0.8倍程度
・現在の必要経費:25万円
【計算式】
・(120万円-20万円)×0.8+25万円=105万円(年間)
・借地代:105万円(年間)
・減額できた金額:15万円
賃貸事例比較法
賃貸事例比較法とは、近隣地域やその周辺地域の借地代と比較することで、適正な借地代を算出する方法です。
おもに新規の借地代を求める際に利用されますが、近隣地域において、それぞれの契約内容や契約から現在に至るまでの経緯、契約当初の賃料などを調査することは非常に難しく、何十年も昔のことなので覚えていないというケースはほとんどでしょう。
また、各契約でそれぞれ特殊事情がある場合には、単純に比較することが難しいケースも存在するため、比較対象になる事例を見つけ出すことが困難である場合もあるでしょう。
【具体例】
・対象となる土地:130平方メートル
・近隣の借地代
①40平方メートル:60万円(年間)
②100平方メートル:130万円(年間)
③160平方メートル:200万円(年間)
【計算方法】
・まず、それぞれの契約で1平方メートルあたりの金額を算出します。
①60÷40=15,000円
②130÷100=13,000円
③200÷160=12,500円
・次に、①〜③の1平方メートルあたりの平均額を算出します。
(15,000+13,000+12,500)÷3=13,500円
・最後に、今回の対象となる土地の価額を算出します。
13,500円×130平方メートル=1,755,000円(年間)
借地代の算出は複雑!専門家に相談がおすすめ
4つのうちどの計算方法を使うかについて、明確なルールは存在しません。
そのため、貸主と借主がお互い納得できるものを選択することになります。
あえてどれか一つを選択しなくても、複数の方法を組み合わせて算出することも可能です。
ただ、実際の借地代の算出は、さまざまな事情を考慮しておこなうため非常に複雑になりやすく、最終的には金額の部分で揉めてしまうことがよくあります。
どうやって計算したらいいのか、揉めてしまった場合どうやって妥協点を見つければいいのかなど、何か疑問点があれば弁護士に相談することをおすすめします。
実際に借地代の減額請求をおこなう手順
ここからは、借地代の減額請求をおこなう際の、具体的な手順について確認していきましょう。
まずは貸主と交渉
まずは、貸主に着地代の減額を申し出てみましょう。
できれば、先ほどの4つの計算方法で計算した具体的な金額や、自分の経済状況を考慮するとどうしても今の金額では支払いが厳しいなどの事情もあわせて伝えるようにすると、貸主としても減額に応じてくれやすくなります。
もし交渉に応じてもらえたら、新たに契約書や覚書などの書面を取り交わしておくと、あとあとトラブルになるのを避けることができるでしょう。
応じてもらえなければ調停申し立て
交渉で話し合いがまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てて、調停委員にお互いの主張をまとめてもらいます。
ただし、調停はあくまでも当事者の話し合いが前提の手続きなので、お互いが主張を全く譲らない場合には、調停は不成立となってしまうでしょう。
なお、地代の減額請求については、訴訟の前に必ず調停を起こさなければならないという、「調停前置主義」という原則があるので、調停を経ずに訴訟を起こすことはできません。
調停が不成立なら訴訟提起
調停でも話し合いがまとまらない場合には、訴訟を起こし、減額をするべきかどうか、減額するのであればいくらが妥当かについて、裁判所に具体的な決定をしてもらいます。
契約書や不動産の鑑定評価書などの証拠資料、お互いの言い分をもとに裁判所が判断しますが、裁判となると、判決が出るまでにかなりの手間や時間がかかってしまいます。
そのため、できれば調停の段階まででお互いで妥協点を見つけるのがいいでしょう。
借地代の減額請求に関するFAQ
最後に、借地代の減額請求に関するよくある質問に回答します。
交渉で決まった賃料はいつから適用されますか?
交渉で着地代を減額できた場合、多くの場合、その交渉の際にいつから減額された賃料で支払いをするのかも一緒に決めることになるので、それに従って支払いをするのが通常です。
また、減額交渉で決まった金額が適用されるのは、減額する旨が記載された書面を受け取った日に効果が発生するとされています。
口頭で減額を認めてもらった場合には交渉が成立した日、別途減額に関する覚書などを作成した場合には、書面に署名押印をした日となります。
減額交渉中の賃料はいくらになりますか?
借地借家法では、借地代について以下のような規定があります。
第32条
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
つまり、裁判で借地代の減額を争った場合には、少なくとも裁判が確定するまでは、今まで通りの賃料を支払う必要があります。
裁判で減額が認められた場合には貸主に対して、差額分や利息の支払いを求めることができます。
交渉や和解で合意した場合には、合意で決定した月から減額した金額で支払うことになります。
地主ともめて、地代の受け取りを拒否されています。どうすればよいでしょうか?
借地代の減額交渉で揉めた場合、借主が借地代を支払っても、貸主が受け取ってくれないケースがあります。
このままだと支払いをしていないことになってしまい、債務不履行責任で契約を解除されてしまうおそれがあります。
この場合、借主は借地代を供託所(法務局)に供託することで、支払いをしたのと同じ法的な効果を得ることができ、契約を解除されてしまうことを避けることができます。
なお、供託する金額は、今まで支払ってきた借地代と同額の金額が必要である点に、注意が必要です。
まとめ|借地代の減額請求の前に、まずは専門家に相談を!
借地代の減額交渉を成功させるポイントは、さまざまな計算方法を用いて適正な借地代を算出することと、減額してほしい理由を丁寧に説明することです。
それでも交渉に応じてくれない場合には、調停や訴訟などまで検討する必要がありますが、減額に関する証拠資料の収集や、適正な借地代の計算には法律的な知識や入念な調査が必要です。
裁判手続きに不慣れな方であれば、こちらの主張したいことをうまく主張できず、こちらに不利な結果になってしまう可能性があります。
交渉を確実に成功させるためには、できるだけ早い段階から弁護士に相談することが重要です。
貸主に減額の請求をする前に、計算方法や今後の進め方について、まずは専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
不動産業界の法務について弁護士を探す 電話相談・オンライン相談可・初回面談無料 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
こちらの記事も参考に>>不動産の実際のトラブルで困ったら|弁護士が事例と共に解決!【不動産トラブルの解説室】