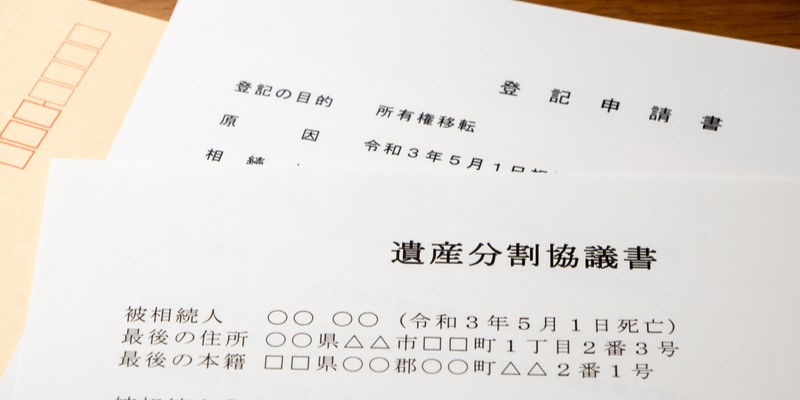相続手続きをおこなう方の中には、遺産分割に関わる手続きの期限について不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
遺産分割に関わる手続きでは、期限が定められているものもあります。
期限を超過してしまうと、相続に関する重要な手続きができなくなってしまい、トラブルに発展してしまうこともあるでしょう。
そのため、遺産分割をおこなう際は、各手続きの期限について把握しておくことが重要です。
本記事では、遺産分割協議などの相続手続きの期限や、相続手続きを正しく進める方法について解説します。
遺産分割協議には期限はない
相続手続きのうち遺産分割協議については、法律上の期限は定められていません。
ただし、相続トラブルなどを避けるためにも遺産分割協議は速やかにおこなう必要があり、なかには「実質的な期限は10年」などと言われることもあります。
ここでは、遺産分割協議の期限や、対応が遅れた場合のリスクなどを解説します。
遺産分割協議の期限が10年といわれる理由
遺産分割協議の期限が10年と言われる背景として、2021年の民法改正によって「遺産分割協議で特別受益や寄与分を主張できる期限は相続開始から10年以内」と定められたことが大きな理由としてあります。
- 特別受益:被相続人から生前贈与・遺贈・死因贈与などを受けて得た利益
- 寄与分:被相続人の財産維持・増加などの貢献をした相続人について、法定相続分以上の相続が受けられる制度
特別受益や寄与分は公平な相続を実現するために設けられており、相続開始から10年が経つとこれらの主張はできなくなります。
不公平な相続となって余計なトラブルを生まないためにも、できるだけ速やかに遺産分割協議をおこないましょう。
遺産分割協議を10ヵ月以内におこなわなかった場合のリスク
相続税の申告手続き・納税手続きには「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内」という期限が設けられています(相続税法第27条1項)。
10ヵ月経っても遺産分割協議が済んでいない場合、加算税や延滞税などのペナルティが課せられるほか、相続税の特例や控除制度を利用できなくなるおそれもあります。
遺産分割協議を3年以内におこなわなかった場合のリスク
被相続人から不動産を相続する場合は、相続登記という名義変更の手続きが必要です。
相続登記には「自己のために相続の開始があったことを知り、相続による不動産の取得を知った日から3年以内」という期限が設けられています(不動産登記法第76条の2)。
3年経っても遺産分割協議が済んでいない場合、罰則として10万円以下の過料が科されるおそれがあります。
遺産相続手続きの期限一覧
遺産分割協議自体には、特に期限は定められていません。
ただし、遺産分割に関する各手続きには、それぞれ期限が定められています。
- 【3ヵ月以内】相続放棄・限定承認の申し立て
- 【4ヵ月以内】準確定申告
- 【10ヵ月以内】相続税の申告・納付
- 【1年以内】遺留分侵害額請求
- 【3年以内】相続登記
- 【5年以内・10年以内】預金・株式に関する権利
- 【10年以内】特別受益・寄与分の主張
ここでは、それぞれの手続きの期限を解説します。
【3ヵ月以内】相続放棄・限定承認の申し立て
相続放棄は「相続開始を知ったときから3ヵ月」を経過するまでにおこなう必要があります(民法第915条)。
相続放棄とは、相続権を放棄することです。
たとえば、被相続人の相続財産について、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合は、相続権を放棄したほうが経済的負担を減らせるでしょう。
相続をする際は、相続財産調査で被相続人の財産を明確にして、まずは相続を承認するのか放棄するのかを十分に検討する必要があります。
期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなり、被相続人の相続財産に多額の借金があった場合でも相続されてしまうので注意しましょう。
なお、やむを得ない理由のため熟慮期間内に相続放棄の判断ができない場合にかぎって、相続放棄の期間を延長できます。
たとえば、被相続人の財産調査に時間がかかっている場合や、相続人が所在不明で連絡を取るのに時間が必要な場合などは、期間の延長が認められる可能性があります。
延長される期間は裁判所の判断によって異なりますが、通常は1ヵ月~3ヵ月程度でしょう。
【4ヵ月以内】準確定申告
準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内」です(所得税法第124条・第125条)。
準確定申告とは、亡くなった人の生前の所得に関する確定申告を、代わりに相続人が申告することです。
準確定申告が必要かどうかを確かめる際は、被相続人に確定申告の義務があるかを確認しましょう。
具体的には、被相続人が以下のようなケースにあてはまっていれば確定申告が必要になります。
- 事業所得や不動産所得などの収入がある
- 2,000万円以上の収入がある
- 複数の会社から収入がある
- 公的年金による400万円以上の収入がある
- 給与や退職金以外で20万円以上の収入がある
場合によっては、準確定申告をおこなうことで還付金を得られる可能性があります。
なお、申告期限に遅れてしまうと追徴税が課される可能性があるため注意しましょう。
【10ヵ月以内】相続税の申告・納付
相続税の申告・納付期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内」です(相続税法第27条1項)。
期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分で計算した暫定的な相続税を支払う必要があります。
その場合、相続税の金額を抑えられる特例や控除制度は利用できなくなるでしょう。
「3年以内の分割見込書」を提出すれば、のちに協議がまとまった際に特例控除の還付を受けることは可能ですが、請求に手間がかかったり相続税額が増加したりするなどのデメリットがあります。
そのため、できるだけ10ヵ月の期限内に遺産分割協議を完了し、確定した相続税を申告・納付できるとよいでしょう。
【1年以内】遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求の期限は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年」です(民法第1048条)。
遺留分侵害額請求とは、遺産分割協議や遺言書により本来受け取るべき遺留分を受け取れなかった相続人が、その侵害分を取り戻すために請求することです。
しかし、遺留分侵害額請求権の時効は1年です。
なお、遺留分の侵害について知らない場合でも、相続開始から10年が経過すると権利行使できなくなります。
自身の相続分を確保するためにも、遺留分が侵害されていないかを早めに確認し、遺留分が侵害されたと知った際はすぐに適切な法的アドバイスを求めることが重要です。
【3年以内】相続登記
相続登記の期限は「自己のために相続の開始があったことを知り、相続による不動産の取得を知った日から3年以内」です(不動産登記法第76条の2)。
これまで相続登記には期限が設けられていませんでしたが、法改正によって2024年4月1日から義務化され、期限を遅れた場合の罰則なども設けられています。
【5年以内・10年以内】預金・株式に関する権利
相続財産のうち預金は5年または10年、株式は5年で権利が消滅してしまう可能性があります(民法第166条1項)。
もし相続財産の中に預金や株式などがある場合は、銀行預金の払い戻しの請求や株主の名義変更などの対応を権利が消滅する前に済ませておきましょう。
【10年以内】特別受益・寄与分の主張
特別受益や寄与分は「相続開始のときから10年以内」に主張する必要があります(民法第904条の3)。
もし相続人の中に特別受益を受けた人がいる場合は、相続財産の額と合算して相続分を決めます。
なお、期限満了6ヵ月の間に遺産分割できないやむを得ない事由があり、この事由が消滅したときから6ヵ月以内に家庭裁判所へ遺産分割調停や審判を請求した場合には、特別受益や寄与分の主張ができます。
遺産分割協議の手続きの流れ
ここでは、遺産分割協議の手続きの流れについて解説します。
- 相続人調査・相続財産調査をおこなう
- 相続人全員で遺産分割協議をおこなう
- 遺産分割協議書を作成する
- 遺産分割調停・遺産分割審判に移行する(協議不成立の場合)
1.相続人調査・相続財産調査をおこなう
まずは、法定相続人や相続分などを正確に把握しましょう。
法定相続人は民法により定められており、通常は配偶者や子ども、親などの血縁者が該当します。
相続分も法律で定められた割合により算出されるため、まずは「誰がどの程度の割合を相続するのか」を把握しておきましょう。
相続財産については、現金・預金・不動産・株式・貴重品など、さまざまな種類があります。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産がある場合もあるでしょう。
相続財産の状況によって遺産分割協議の方向性は大きく異なるため、相続人が継承する全ての財産を詳細にリストアップして、あとからトラブルが起きないようにしましょう。
2.相続人全員で遺産分割協議をおこなう
相続財産などが確定したら、法定相続人で遺産分割協議をおこないます。
基本的には、法定相続分を基準にして決めるのが一般的です。
ただし、相続人が合意すれば法定相続分と異なる割合で相続しても問題ありません。
遺産分割協議は、公平かつ公正におこなう必要があります。
ときには協議に時間を要しますが、それぞれの相続人の希望やニーズを尊重しながら進めていくことが重要です。
3.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまった際は、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
自力で作成することも可能ですが、素人では記載漏れなどが生じてのちのちトラブルに発展する可能性もあるため、相続問題が得意な弁護士などに依頼することをおすすめします。
4.遺産分割調停・遺産分割審判に移行する(協議不成立の場合)
もし遺産分割協議が難航して合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもひとつの手段です。
遺産分割調停では、中立的な立場である調停委員が間に入って、公平な問題解決を図ります。
親族同士では冷静な話し合いができないこともあるため、相続に関する専門家を入れて話し合いをすることで解決につながるでしょう。
もし遺産分割調停でも解決しない場合は、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では、各相続人の主張や証拠などをもとに、裁判所が遺産分割の内容を決定します。
遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット
遺産分割をおこなう際、弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 遺産分割協議や裁判手続きなどを代行してくれる
- 相続人や相続財産を正確に調査してくれる
- 不備なく正確な遺産分割協議書を作成してくれる
- 状況に適した相続方法をアドバイスしてくれる
- 遺産の使い込みなどの相続トラブルも解決してくれる
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
遺産分割協議や裁判手続きなどを代行してくれる
弁護士なら、相続人との交渉や裁判手続きなども任せられます。
相続問題では相続人同士が感情的になりやすいため、なかなか話し合いが解決に向かわないことも多いでしょう。
中立的な立場から交渉を進められる弁護士がいれば、冷静な判断のもとで話し合いができます。
また、相続問題が得意な弁護士であれば適切な解決策を示してくれるため、遺産分割をスムーズかつ穏便におこなえるでしょう。
相続人や相続財産を正確に調査してくれる
弁護士であれば相続人調査や相続財産調査を一任できます。
専門的な知識や経験が必要になる調査なので、不慣れな人がおこなうと時間と労力が多くかかってしまうでしょう。
弁護士は、適切な法的手段を用いて相続人の特定や遺産の評価をおこないます。
各相続人の負担も軽減されますし、遺産調査を正確におこなえれば公正な遺産分割が望めます。
不備なく正確な遺産分割協議書を作成してくれる
遺産分割協議が完了したら、あとからトラブルにならないように遺産分割協議書を作成する必要があります。
ただし、不備なく適切な遺産分割協議書を作成するには、ある程度の法的知識が必要です。
遺産分割協議書には、相続財産の内容や価値・各相続人が受け取る財産の詳細・相続人全員の署名や押印などが必要になります。
もし遺産分割協議書に不備などがあれば、法務局や金融機関でも受け付けてもらえず、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどができないでしょう。
法律問題を扱う弁護士が作成することで、不備が発生する心配はありません。
トラブル回避やスムーズな相続のために、遺産分割協議書の作成は弁護士に依頼するとよいでしょう。
状況に適した相続方法をアドバイスしてくれる
弁護士に相談すれば、自身に合った相続の方法をアドバイスしてもらえます。
たとえば、相続では法定相続・遺産分割協議による相続・遺言書による相続など、さまざまな方法があります。
弁護士に相談すると、経済的・税制的なメリットなどを踏まえながら、最適な相続方法を提案してくれるでしょう。
遺産の使い込みなどの相続トラブルも解決してくれる
ほかの相続人によって遺産が不適切に使い込まれてしまった場合などは、弁護士に依頼することで取り戻せる可能性があります。
弁護士に依頼すると、被相続人の預貯金取引履歴を取得して状況を調査します。
不適切な使い込みが判明した場合は返還請求をして、使い込んだ金額を取り返す手続きをおこないます。
もし相手が返還に応じない場合には、訴訟手続きも可能です。
弁護士に依頼することで、このような相続人同士では解決しづらいトラブルなども早期解決できるでしょう。
遺産分割協議を弁護士に依頼する場合の費用相場
遺産分割協議を弁護士に依頼する際、かかる費用相場は以下のとおりです。
なお、事務所によって金額設定にはバラつきがあるため、正確な金額を知りたい方は直接事務所に確認しましょう。
- 相談料|1時間あたり5,000円~1万円程度
- 着手金|20万円~30万円程度
- 報酬金|経済的利益によって異なる
- 実費|依頼状況によって異なる
- 日当|1日あたり5万円程度
ここでは、それぞれの費用について解説します。
相談料|1時間あたり5,000円~1万円程度
相談料の相場は、1時間あたり5,000円~1万円程度です。
相談料とは、弁護士に遺産分割などについて法律相談する際にかかる費用です。
なかには初回相談料無料という法律事務所もあります。
着手金|20万円~30万円程度
着手金の相場は20万円~30万円程度です。
着手金とは、弁護士が遺産分割手続きなどの業務をおこなう際にかかる費用です。
着手する業務の内容や、遺産額の大きさなどによって金額が異なることもあります。
報酬金|経済的利益によって異なる
報酬金とは、遺産分割協議などを依頼して問題解決したときに支払う費用です。
報酬金の金額は、弁護士に依頼したことで得られた経済的利益に応じて算出されます。
たとえば「得られた経済的利益が300万円・成功報酬は経済的利益の16%」という場合、報酬金として48万円を支払うことになります。
ただし、成功の定義や報酬金の算出方法などは法律事務所ごとに異なるため、依頼前によく確認しておきましょう。
実費|依頼状況によって異なる
実費は、弁護士が依頼を遂行するうえで発生する費用です。
たとえば、交通費・郵送費・印紙代などが含まれます。
特に調停を申し立てた場合は裁判所までの交通費や印紙代などがかかるため、費用が高くなりやすいでしょう。
日当|1日あたり5万円程度
日当の相場は、1日あたり5万円程度です。
日当とは、弁護士が事務所を離れて出張する場合に支払う費用です。
たとえば、遠隔地にある不動産を確認する場合や、ほかの相続人と面談をする場合などに発生します。
基本的に弁護士が出張しなければ発生しないため、0円になるケースもあるでしょう。
さいごに|スムーズに解決したいなら弁護士への依頼がおすすめ!
速やかに遺産分割の手続きを進めないと、税金の申告・納税が遅れて延滞税が課されたり、登記手続きが遅れて10万円の過料が課されたりするなどのリスクがあります。
遺産分割の手続きをスムーズに済ませたいなら、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士なら相続状況に適した対応策をアドバイスしてくれるほか、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成・裁判手続きなど、相続で必要な手続きの大部分を代行してくれます。
当社が運営する「ベンナビ相続」では相続問題が得意な全国の弁護士を掲載しており、初回相談無料の事務所なども多くあるため、一度相談してみることをおすすめします。