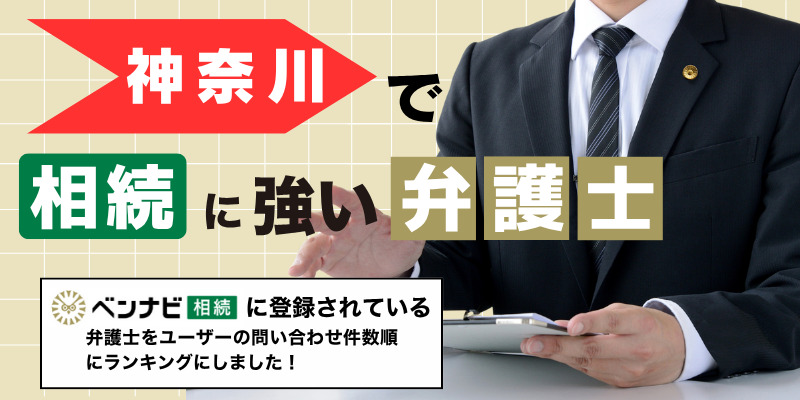「相続人同士の仲が良いとは言えず、遺産相続トラブルに発展しないか心配だ」
「実際にどんな遺産相続トラブルが起こる可能性があるか知っておきたい」
遺産相続でトラブルとなり、その解決のためにたいへんな負担が強いられたり、不利益を被ってしまったりするケースは少なくありません。
そのため実際にどんな遺産相続トラブルが発生するかチェックし、備えておきたいと考えるのは当然です。
本記事では、よくある遺産トラブル事例10選とそれぞれの対処方法、遺産相続トラブルを迅速に解決するためのポイントについて解説しました。
本記事を読むことで、多くの遺産トラブルを予防し、万が一トラブルになってもより適切な対応ができるようになります。
遺産相続トラブルの件数|2022年の受付件数は1万2,981件
裁判所がまとめた統計によると、2022年に全国の家庭裁判所が受け付けた遺産分割関係事件の件数は1万2,981件です。
約半数にあたる5,729件は調停が成立していますが、約3割の3,791件は調停が成立せず裁判官による審判が下されています。
また4,542件は1年以上の審理期間を要しているなど、トラブルが長期化することも珍しくありません。
遺産相続トラブルの約3割が1,000万円以下の遺産相続で起きている
次に家庭裁判所が受け付けた遺産分割関係事件の統計から、相続遺産の価格別による割合をみていきましょう。
相続遺産の価格別では約3割が1,000万円以下、約4割が1,000万円超5,000万円以下でした。
一方で遺産額が1億円を超える遺産分割関係事件は、全体の1割以下となっています。
こういった統計をみても、遺産分割トラブルがお金持ちだけの問題でないことがわかるでしょう。
よくある遺産相続トラブル事例10選|トラブルごとの対処法も!
次に、よくある遺産相続トラブルを紹介します。
トラブルごとの対処法もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
1.遺言書の内容が著しく偏っている
よくある遺産相続トラブルのひとつが、遺言書の内容が著しく偏っているケースです。
財産の相続方法は、遺言書によってある程度決めることができます。
しかし遺言書の内容が、一部の相続人のみ優遇されるような著しく不公平なものだった場合に、遺産相続トラブルが起こりやすいのです。
遺言書に関するトラブルへの対処法
遺言書に関するトラブルを解決するためには、遺留分侵害額を請求したり、遺言の無効を主張したりする方法があります。
まずは、遺留分侵害額の請求ができないかを検討しましょう。
遺留分とは相続遺産において、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限の取り分のことです。
遺留分は相続財産の半分が割り当てられ、兄弟姉妹以外の法定相続人で分け合います。
たとえば法定相続人が被相続人の子ども3人のみであれば、それぞれ相続遺産の1/2×1/3=1/6が遺留分として認められるのです。
遺留分は、たとえ遺言であっても侵害されることは許されません。
特定の人物に全財産を相続させるといったように、遺言書の内容が遺留分侵害にあたる場合は、遺留分の支払いを請求することができます。
遺留分侵害額を請求する際は、まず当事者間でおこなうケースが一般的です。
それでもなお、相手方が応じようとしなければ、裁判所に対して遺留分侵害請求調停を申し立て、解決をはかります。
また、遺言そのものの効力に疑義がある場合は、遺言無効確認の調停を申し立て、遺言無効を主張するのもひとつの方法です。
たとえば、以下のようなケースでは遺言が無効になる可能性があります。
- 内容が不明瞭で、複数の意味に読み取れる
- 認知症などで、遺言能力がない状態の被相続人が作成した
- 被相続人がほかの誰かにそそのかされて書かされた疑いがある
- 遺言書の日付がないか、日付が特定できない形式で書かれている
なお相続人全員が合意することで、遺言書と異なる内容での遺産分割が可能です。
相続人全員の合意が得られない場合は、遺言無効確認の調停を検討しましょう。調停が不成立となった場合は、訴訟で解決を目指すことになります。
2.相続財産の内容が不透明である
相続財産の内容が不透明な場合も、「財産の一部が隠されているのでないか」と疑義が起こり、遺産相続トラブルが発生しやすいので注意してください。
相続財産を正確に把握できていない状態だと、このようなトラブルにより相続人同士の争いにつながる可能性が高くなります。
相続財産の範囲についてのトラブルの対処法
被相続人が亡くなってしまう前に財産目録を作成しておくことで、相続財産の範囲に関するトラブルを避けられます。
相続人全員が全ての相続財産を把握できていれば、隠し財産の疑義が生じるのを予防できます。
被相続人自身が所有財産の存在を忘れてしまっているケースもあるので、相続人同士でも確認し合いながら財産目録を作成するようにしましょう。
具体的には、以下のような財産を所有している場合は目録に記載しておくことをおすすめします。
- 土地
- 有価証券
- 銀行預金
- 自動車・家財・貴金属などの動産
- 住宅ローン・未払いの税金などマイナスの財産
財産目録にはマイナスの財産も明記しておくと、よりトラブルを回避しやすくなります。
3.相続財産に不動産が含まれている
相続財産に不動産が含まれている場合も、トラブルが生じやすい傾向があるので注意しておきましょう。
不動産は現金や預貯金などと違って、簡単に分割することができません。そのため相続人間で公平に分割するのが難しく、トラブルに発展しやすいのです。
また遺産分割に大きな影響を与える不動産の評価方法でもめたり、不動産を売却するか否かでもめたりすることもあります。
>不動産相続でよくあるトラブルについて詳しく知る
不動産相続のトラブルへの対処法
不動産相続のトラブルを避けるためには、分割方法を正しく使い分けることが大切です。
不動産の分割方法には主に以下の3つがあるので、それぞれのメリット・デメリットをしっかりと押さえておきましょう。
| 分割方法 | メリット | デメリット | |
| 現物分割 | 不動産をそのままの形で分割すること | 相続手続きが比較的簡単 | ● 公平に相続するのが難しい ● 分割(分筆)によって資産価値が下がる可能性がある ● 土地の面積だけでは公平に分割できない |
| 換価分割 | 不動産を現金化して相続人間で分割する | 分割が容易で不平等が生じにくい | ● 不動産が相続人の手元から離れる ● 手間と経費がかかるうえ、税金が発生する可能性もある ● 価値が低いときに売ると経済的に損をすることもある |
| 代償分割 | 特定の相続人が不動産を取得し、ほかの相続人に対価(代償金)を支払う | ● 公平に分割しやすい ● 不動産を相続人の手元に残せる | ● 不動産の評価方法で争いになることがある ● 代償する側に十分なお金がないと選べない ● 代償金が支払われないことがある |
上記のほか、相続人同士で不動産を共有する方法がありますが、遺産相続ではあまりおすすめできません。
共有した相続人全員の合意がないと、活用も売却もできず柔軟性にかけるなどデメリットが多いからです。
不動産による遺産相続のトラブルを避けるためには、相続人同士で上記のうちどの分割方法がよいか話し合う必要があります。
相続人だけで決めるのが難しい場合は、弁護士などの専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。
弁護士であれば、相続人の事情を把握したうえで、どの方法が適切か提案してくれるでしょう。
次に不動産の評価方法でトラブルになった場合は、どうしたらよいでしょうか。
解決策としては不動産鑑定を依頼して適正価格を算出したり、平均値をとって譲り合ったりする方法があげられます。
不動産を売却するか否かで争いがおきた場合、売却するとどのくらい利益がでるかシミュレーションしてみるのも手です。正確な金額が分かれば、どうするのがよいか判断しやすくなるでしょう。
これらの内容についても、相続人間で判断するのが難しい場合、弁護士に仲介してもらうのがおすすめです。
4.相続人同士が疎遠になっている
相続人同士が疎遠になっている場合も、遺産相続トラブルが発生する原因のひとつです。
相続人同士が疎遠で遠くに住んでいたりすれば、そもそも全員が集まるのは難しいこともあるでしょう。
長年連絡をとっておらず、連絡先さえわからないこともあるかもしれません。
疎遠な相続人間の遺産相続トラブルへの対処法
遺産分割協議は、相続人全員が集まって合意しなければ無効となってしまいます。
疎遠になっている相続人についても、必ず連絡先を取り遺産分割協議に参加してもらう必要があるのです。
ただ、遺産分割協議では、必ずしも全員が1ヵ所に集まっておこなう必要はありません。
集まれない相続人については、手紙やメール、電話などでやりとりしてまとまった内容を伝え、合意を得ることも可能です。
相続人の居所が分からず相続人だけで調べるのが難しい場合は、弁護士に調査を依頼することもできます。
5.前妻の子どもなど想定していない相続人が見つかる
よくある遺産相続トラブルのひとつが、想定していない相続人が見つかったケースです。
たとえば、被相続人の前妻の子どもや認知された子どもがいた場合などが挙げられます。
新たな相続人が現れると一人ひとりの相続分は減ってしまうため、相続人のなかから不満の声があがることも少なくありません。
想定していない相続人とのトラブルへの対処法
想定していない相続人が見つかった場合は、できるだけ早く連絡を取りましょう。
相続人になっていることを伝え、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
ただし面識のない相続人と短い期間で信頼関係を築き、互いを尊重しながら遺産分割協議をするのは簡単ではありません。
この場合も、弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。
弁護士であれば、法的な観点から公正に遺産を分割できるような提案をしてくれるでしょう。
6.一部の相続人に介護の負担が偏っていた
一部の相続人に介護の負担が偏っていた場合も、遺産相続トラブルが起こりがちです。
長年にわたり被相続人を介護してきた相続人が、介護をしなかったほかの相続人より「多く遺産を相続させて欲しい」と考えることがあります。
実際、被相続人が所有する財産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合は、「寄与分」として法定相続分を超える財産を相続できます。
しかし、単に介護を続けていたことを理由に、寄与分が認められるケースはほとんどありません。
仕事を辞めて家業を無償で手助けした、ヘルパーを雇わず自分だけで介護をやり切ったなど、「特別な寄与」が認められる根拠が必要になるのです。
寄与分に関するトラブルへの対処法
寄与分に関するトラブルが生じた際は、相続分の上乗せが妥当かどうかを検討しましょう。
特別の寄与と認められるような事実があり、問題の早期収束を望むのであれば、ある程度の上乗せを妥協するのも選択肢のひとつです。
相続人同士の意見が折り合わない場合は、調停や裁判で争うことになります。
7.一部の相続人に多額の生前贈与がおこなわれた
被相続人が生前に、特定の相続人にのみ多額の贈与をしていた場合も、遺産相続トラブルに発展するケースが多くなっています。
生前贈与を受けていない相続人が、不公平に感じるためです。
生前贈与による遺産相続トラブルへの対処法
生前贈与が原因でトラブルが発生した場合は、「特別受益の持ち戻し」ができないかを検討しましょう。
特別受益の持ち戻しとは、生前贈与をはじめとした遺産の前渡し分を、遺産分割の計算に含める方法のことです。
生前贈与で得したように見える状態が解消されるため、遺産分割がスムーズに進む可能性があります。
特別受益の持ち戻しをおこなうかどうかは、まず遺産分割協議で合意形成を図りましょう。
生前贈与を受けた相続人が合意しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになるでしょう。
8.一部の相続人による相続財産の使い込みがある
相続財産を整理していくなかで、一部の相続人による使い込みが発覚することもあります。
よくあるのが、被相続人の財産管理を任されていた相続人が、自分のために預貯金を使い込むケースです。
使い込まれた財産を取り戻すことは難しいため、どのように取り扱うのかで揉め事が起こる可能性があります。
相続財産の使い込みトラブルへの対処法
相続財産の使い込みトラブルが起きたときは、まず、使い込みの事実が本当にあったかどうかを確認しましょう。
被相続人からの指示があったり、被相続人のために使われていたりと、使い込みとはいえない事情があるかもしれません。
使い込みが明らかな場合や本人が使い込みを認めている場合は、使い込んだ金額を遺産分割の計算に含めることができます。
当該相続人の相続分から使い込んだ金額を差し引くことで、公平性を確保するわけです。
使い込みが明らかであるのに本人が認めないときは、調停や訴訟によって争うことになります。
9.相続人のひとりが相続財産を管理していた
特定の相続人が相続財産を管理していた場合も、トラブルが起きやすいので注意してください。
その相続人が相続財産の開示を拒否したり、使い込みが疑うべき根拠があったりすることがあります。
反対に被相続人の財産を被相続人の医療費などのために使っただけなのに、使い込みを疑われるケースも少なくありません。
相続財産の管理に関するトラブルの対処法
相続財産を管理していた相続人の使い込みが発覚した場合は、前項で述べたように使い込んだ金額を含んで遺産分割する方法があります。
使い込みが明らかな証拠があるのに本人が認めない場合は、調停や訴訟などで争うことになるでしょう。
一方で適切に相続財産を管理していたのに使い込みを疑われた場合、証拠の資料を用意して濡れ衣であることを証明することが必要です。
たとえば被相続人の医療費や介護などの記録、領収証、契約書などがあげられます。また使い込みを疑われないようにするために、生前からそれらの資料を保管しておくことも有効です。
10.被相続人が同族会社の経営者だった
被相続人が同族会社の経営者で、遺言を残さず亡くなってしまった場合も、遺産相続トラブルが起きやすくなっています。自社株の配分を、遺産分割協議で決めなくてはならないからです。
後継者である相続人が自社株を全て相続した場合、ほかの相続人の不満を招き相続争いが起きてしまうことがあります。
しかし遺産分割協議が長引くと、会社へ悪影響が生じる可能性があるため、なるべく早く解決しなくてはなりません。
同族会社関連の遺産相続トラブルへの対処法
最も有効な予防策は、被相続人がきちんと遺言で財産の配分を決めておくことです。
たとえば自社株は後継者へ引き継ぎ、ほかの相続人には代わりに自社株以外の財産を多めに相続させます。こうすることで、遺産相続トラブルを未然に防げるでしょう。
遺言書がない場合、自社株を引き継いだ後継者が、ほかの相続人に代償金を支払うなどの対応を検討し、早期解決を目指しましょう。
遺産相続トラブルを迅速に解決するための5つのポイント
次に、遺産相続トラブルを迅速に解決するためのポイントを紹介します。
1.トラブルを見極め適切な対処法を選ぶ
遺産相続トラブルを解決するためにはトラブルの原因を見極め、適切な対処法を選ぶことが大切です。
遺産相続トラブルの解決方法は多岐にわたります。
寄与分を受け取ることで解決するケース、代償金を支払うことで解決するケースなど最終的な着地点はさまざまです。
そのため、トラブルの内容に応じた最善の方法を選択することがなによりも重要といえます。
もし自分たちだけで対処法が見つからない場合、相続人同士で争いになってしまう前に弁護士へ相談するのがおすすめです。
相続問題を得意とする弁護士であれば、法律の知識などに基づき、もっとも適切な解決策を提案してくれるでしょう。
2.冷静な話し合いを心掛けるようにする
冷静な話し合いを心掛けることも、遺産相続トラブルの早期解決に欠かせないポイントです。
感情が高ぶり、論理的な話し合いができなくなると、トラブルがより深刻になる可能性もあります。
まずは相手の心情をできる限り理解し、尊重することが重要です。
一見身勝手にみえる主張をする相続人も、被相続人の介護のために身を捧げてきたなど、「ほかの相続人より多くの財産を相続したい」と考える背景があるのかもしれません。
各相続人の意見が折り合わないときでも、相手の視点に立って話し合いを進めることが、スムーズな問題解決につながります。
3.なるべく関係ない人を出席させない
遺産相続の話し合いには、相続に関係ない人物をなるべく出席させないようにしましょう。
たとえば相続人の配偶者など、相続人としての権利をもたない第三者が遺産分割協議に出席することがあります。
この場合、相続人の配偶者も相続人本人を通じて、遺産相続の利害関係に間接的な関係がないとはいえません。
そのため無関係な方が増えれば増えるほど、利害関係が複雑化して遺産分割協議がまとまりにくくなるのです。
相続権をもたない第三者は、そもそも遺産分割協議に参加するべきではありません。
4.ある程度妥協することを心がける
遺産相続トラブルを起こさないためには、ある程度妥協する柔軟な姿勢も重要です。
全ての相続人が心から満足できる、完全な分割方法を探し出すのは簡単ではありません。
不動産のような分割しにくい相続遺産があるのに、「1円も損したくない」といった頑なな姿勢では、遺産分割協議で合意するのは困難です。
相続人全員が、それぞれ少しずつ妥協することで、遺産分割協議を円滑に進めることができます。
反対に相続人が誰も妥協せず協議が長引けば、特例制度を活用できず相続税が高くなるなどデメリットも生じてしまうのです。
5.できる限り早く専門家に相談をする
遺産相続トラブルに直面した際は、できる限り早く専門家に相談するようにしましょう。
法律の知識がなければ、法律の観点からみて適切な遺産の分割方法や割合を判断するのは困難です。
法定相続分などに則った遺産分割の方法を提案することで、ほかの相続人も納得しやすくなります。
また利害の対立する相続人だけでは、感情的にならず話し合いをすすめるのは難しいかもしれません。
弁護士が間に入ることで専門知識をもつ第三者の意見も参考にでき、冷静に話し合いをすすめられる可能性が高まります。
なお遺産分割協議に関わる専門家として、弁護士以外に司法書士などを思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし遺産相続トラブルが発生している際に、相談先として最適なのは弁護士です。
弁護士のみ、相続人間の紛争が起きた際の仲裁や解決をする法律的な権限を有しています。
遺産相続トラブルの解決を弁護士に相談・依頼する4つのメリット
遺産相続トラブルの解決を弁護士に相談・依頼するメリットは以下の4つです。
- 法律に則った解決方法を教えてもらえる
- ほかの相続人と直接交渉をせずに済む
- 交渉を有利に進められる可能性が高い
- 調停や訴訟に移行しても対応を任せられる
トラブルを複雑化・長期化させないためにも、弁護士に依頼するメリットを正しく理解し、有効に活用しましょう。
1.法律に則った解決方法を教えてもらえる
弁護士に相談・依頼すれば、法律に則った解決方法を提示してもらえます。
相続手続きは、法律に従って進めるのが大前提です。
法律に則った正しい解決方法が分かれば、ほかの相続人からの理不尽な主張に対しても毅然とした対応をとることができるでしょう。
2.ほかの相続人と直接交渉をせずに済む
ほかの相続人と直接交渉せずに済む点も、弁護士を頼るメリットのひとつです。
各相続人は近しい間柄であるケースも多く、遺産相続トラブルで対立することは精神的な負担になります。
なんでも言い合える仲だからこそ、感情が高ぶり、冷静に話し合えなくなることもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、ほかの相続人と直接対峙することなく、遺産分割協議を進められます。
弁護士に介入してもらうことで、相手も感情的にならず冷静に協議をすすめてくれるケースも少なくありません。その結果、協議をスムーズに進めやすくなるのです。
3.交渉を有利に進められる可能性が高い
交渉をより有利に進められる可能性が高くなる点も、弁護士に依頼するメリットです。
弁護士は法的な知識・経験を豊富に持ち合わせているうえ、交渉のプロでもあります。
相手が不適切な主張をしてきた場合でも、法律に基づいて反論することが可能です。
たとえば遺留分や特別受益など、法律の知識がなければわからない権利についても、弁護士に交渉を任せれば適切に主張してくれます。
4.調停や訴訟に移行しても対応を任せられる
弁護士であれば、調停や訴訟に移行しても対応を任せられます。
当事者間での話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟などに移行して争わなければなりません。
しかし、調停や訴訟を申し立てるには書類作成など煩雑な手続きをしなくてはならないうえに、自分の主張を適切に立証する必要もあります。
弁護士に依頼すれば、これらの手続きや検討を全て代行してもらうことができるのです。
調停や訴訟の場で適切に主張を展開することもでき、有利にすすめられる可能性も高まります。
遺産相続トラブルを防ぐために知っておくべき相続の基礎知識
ここからは、遺産相続トラブルを防ぐために知っておくべき相続の基礎知識を解説します。
ここであげる知識がなければ、遺産分割協議で適切な主張をするのは困難です。遺産分割協議をおこなう前に、チェックしておきましょう。
法定相続人とは|故人の財産を相続できる、民法で定められた相続人のこと
法定相続人とは個人の財産を相続できる、民法で定められた相続人のことです。
遺産分割では遺言書の内容が優先されますが、遺言書がなければ法定相続人が集まり協議することになります。
法定相続人となるのは、配偶者と血族です。配偶者は常に法定相続人となり、血族は以下にあげる順位のなかで最も順位の高い方が法定相続人となります。
- 第1順位:子ども・孫などの直系卑属
- 第2順位:親・祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹・甥姪などの傍系血族
最も高い相続順位の方が複数いる場合は、その全員が法定相続人になります。たとえば配偶者のほか子どもが2人いれば、配偶者とその子ども2人が法定相続人となるのです。
被相続人が亡くなる前に子どもが亡くなっていた場合は、子どもの子ども(=孫)が代わりに法定相続人となります。
法定相続分とは|民法で定められた各相続人の相続割合のこと
法定相続分とは、民法で定められている各相続人の相続割合のことです。
配偶者がいない場合は、最も高い相続順位が全ての財産を相続することになり、該当者が複数人いる場合は均等に分割します。
被相続人に配偶者がいる場合の法定相続分は、以下のとおりです。
- 配偶者と子どもが法定相続人である場合:配偶者と子どもが2分の1ずつ
- 配偶者と親が法定相続人である場合:配偶者3分の2・親3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人である場合:配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
たとえば配偶者と子ども2人がいるケースで考えてみましょう。
この場合の法定相続分は配偶者が2分の1で、残りの2分の1を2人の子どもが均等に分ける(4分の1ずつ分ける)のです。
なお、必ずしも法定相続分のとおりに相続しなくてはならないわけではありません。
遺言や遺産分割協議で、独自の相続割合を設定することも可能です。
遺産分割協議とは|相続財産の分け方について相続人同士で話し合う手続きのこと
遺産分割協議は、相続財産の分け方を相続人同士で話し合う手続きのことです。
法定相続人全員が参加し、遺産分割方法を細かく決めていきます。
1人でも協議に参加していなければ、話し合った内容は無効になるので注意してください。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成するケースが一般的です。
だれがどの遺産を相続するかを明記し、相続人全員が署名・押印します。
相続人全員の合意を得られれば、遺産分割協議をやり直すことも可能です。
遺産相続トラブルに関する3つの注意点
ここからは、遺産相続トラブルに関する注意点を解説します。
取り返しのつかない事態に陥らないようにするためにも、最低限の知識はしっかりと身につけておきましょう。
遺産相続トラブルが長引くと相続税の申告・納付に影響が生じる
遺産相続トラブルが長引くと、相続税の申告・納付に影響が生じることもあるので注意してください。
相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
納税が遅れると、加算税や延滞税が課されたり、節税につながる特例が利用できなくなったりします。
相続人全員が協議に参加できる日を調整するには時間がかかるうえ、話し合いがスムーズにまとまらないこともあるでしょう。
遺産分割協議の実施期限はありませんが、できるだけ早く済ませ、相続税の申告・納付をおこなうことが大切です。
もし10ヵ月以内に申告・納付できない場合は、暫定的に法定相続分で申告し、後日修正することでペナルティを避けられます。
なお遺産分割協議が終了していないと、小規模宅地などの特例を適用することができないので注意してください。
遺産分割協議が終了していなくても特例を活用したい場合は、あわせて「申告後3年以内の分割見込書」を提出し、あとから還付請求をします。
このように手続きをすることで、申告期限後3年以内なら、特例を適用できず納め過ぎていた金額の還付をあとから受けることができるのです。
無理やり協議を進めるとあとから無効を主張されるおそれがある
無理やり遺産分割協議を進めると、あとから無効を主張されるおそれもあります。
以下のようなケースにおいては、遺産分割協議が無効となることを覚えておきましょう。
- 相続人全員が参加していなかった
- 意思能力を欠く相続人が参加していた
- 親子の両方が相続人である場合に、親が子の代理人として参加していた
- 協議内容が公序良俗に反する
遺産分割協議を法的に有効なものとするためには、相続人全員の参加が必須です。
認知症などを患い、意思能力を欠く者がいた場合は後見人に参加してもらわなければなりません。
相続人に未成年が含まれる場合は、親が代理人として出席します。
ただし、親も相続人に含まれているケースでは、親と子の利益が相反するため、親が子の代理人になることはできません。
そのため、家庭裁判所に対して、「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
安易に不動産を共有名義にすると将来的にトラブルになる可能性がある
遺産相続において安易に不動産を共有分割して、共有名義とするのはおすすめできません。
不動産の共有分割にはデメリットが多く、将来的にトラブルとなる可能性があるからです。
たとえば共有名義にすると、不動産を売却したり賃貸したりしたくても相続人単独では実行できません。
共有名義とした結果、不動産を適切に活用しづらくなってしまうのです。売却や賃貸のほか、大規模な修繕や建て替えなども単独では実行できません。
また、相続人のうち1人が自分の持ち分だけ、勝手に売ってしまうというトラブルも多いです。
ある日突然、自分の知らない方と不動産を共有することになるといった事態もあり得ます。
これまでスムーズにおこなえていた不動産の税負担なども、第三者が絡むことで困難になるかもしれません。
遺産分割協議において不動産の取り扱いに困った場合、弁護士のような専門家にアドバイスを求めることを強くおすすめします。
さいごに|遺産相続トラブルが起きたら弁護士に早めに相談を!
遺産相続トラブルに巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
遺産相続には、さまざまな法律が関係しているため、法的な知識のない個人が自力で対応しようとしても、トラブルの複雑化・長期化を招いてしまうかもしれません。
弁護士に依頼すれば、複雑な書類作成なども全て任せられます。
ほかの相続人との交渉も代行してもらえるので、近しい親類と争っている場合は精神的な負担を大きく抑えられるはずです。
法律事務所によっては無料相談をおこなっていることもあるので、まずは気軽に問い合せてみることをおすすめします。