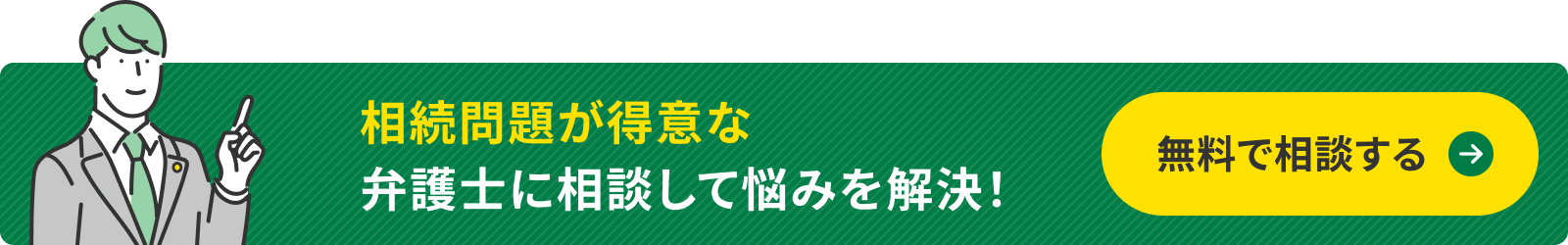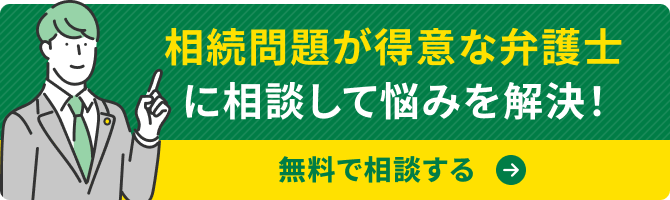親族が亡くなり、相続人で遺産分割をおこなわなければならないものの、面倒で長らく放置しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
あまりに長く放っておいてしまうと、以下のように心配になる方もいるでしょう。
- 「遺産分割に時効はあるのだろうか?」
- 「このまま放っておいたらさすがにマズイのでは?」
しかし、遺産分割自体には時効はありません。
そのため、いつおこなっても構わないのです。
とはいえ、あまりに長い時間、放っておくのはおすすめできません。
なぜなら、いくつかの相続手続きには時効があり、知らない間に時効が成立することで、不利益を被る可能性があるからです。
本記事では、遺産相続に関連する時効や遺産分割を放置し続けることのリスク、遺産分割のやり直しはできるのかどうか、などについて解説します。
遺産分割に時効はない
遺産分割自体に時効はありません。
なぜなら、遺産を相続する権利そのものには、時効が存在しないからです。
このため、被相続人が亡くなってから何年経過していても、遺産分割協議はおこなうことができます。
また、家庭裁判所への遺産分割調停の申立ても受け付けてもらえます。
遺産を相続する権利を失うことがないため、遺産はいつでも分けられるのです。
なお、2023年4月の民法改正により、相続が開始されてから10年経過すると、特別利益や寄与分の主張ができなくなる制度が設けられました。
依然として、遺産分割に時効はないものの、特別受益や寄与分を主張したい場合には、10年以内に遺産分割をおこなう必要があります。
ただし、遺産相続には時効がある
遺産分割に時効はありませんが、遺産相続に関する一部の手続きには、時効が存在します。
たとえば、遺産を相続しないための手続きである相続放棄は、相続開始から3ヵ月以内という時効が定められています。
そのため、もし被相続人の相続財産に借金があり、相続放棄を希望しても、3ヵ月を経過してしまうと、その借金を相続しなければならなくなります。
このように、遺産相続の手続きの中には、時効を迎えることで相続人が不利益を被るケースがあります。
遺産分割するタイミングは自由ですが、相続に関する手続きについては、時効を正確に抑えておき、早めに対応することが重要です。
遺産相続に関連する時効一覧
遺産相続に関連する手続きの時効は、それぞれ以下のように定めされています。
| 相続放棄 | 3ヵ月 |
|---|---|
| 遺留分侵害額請求権 | 1年 |
| 遺留分が侵害されていることを知らなかった場合は10年 | |
| 遺産分割請求権 | 時効はなし |
| 相続回復請求権 | 5年 |
| 知らなかった場合は20年 | |
| 相続税申告 | 5年 |
| 悪意があると判断された場合は7年 | |
| 贈与税申告 | 6年 |
| 悪意があると判断された場合は7年 | |
| 債務(債権) | 5年 |
| 相続登記 | 時効はなし※ |
| 準確定申告 | 5年 |
| 保険金請求 | 3年 |
| 遺産の取得時効 | 20年 |
※不動産の相続登記については法改正により、3年以内の相続登記が義務化されています。思わぬ不利益を被らないためにも、それぞれの相続手続きについて、どのくらいの時効が定められているのか、詳しくみていきましょう。
1.相続放棄|3ヵ月で時効
相続放棄とは、プラスもマイナスも含めたあらゆる遺産の相続を放棄することをいいます。
特に被相続人が多額の負債を残して亡くなったケースや、ほかの相続人と一切関わりたくない場合に有効な手続きといえます。
ただし、相続放棄をするには、相続開始を知ったときから原則として、3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述の申立てをおこなわなければなりません。
なぜなら、3ヵ月以内に相続放棄の申述を申し立てなければ、自動的に「単純承認」という相続方法を選択したとみなされるからです。
単純承認が成立すると、マイナス分を含む全ての遺産を相続することになり、多額の負債を抱える可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、相続開始後は3ヵ月の熟慮期間のうちに相続に関する手続きを開始すべきです。
2.遺留分侵害額請求権|1年で時効(例外として10年)
遺留分侵害額請求権とは、遺言による遺贈や生前贈与によって不公平な遺産分割がおこなわれ、遺留分に相当する金額すら受け取っていない場合に、侵害額の支払いを請求できる権利です。
主に被相続人の配偶者や子ども、親などの相続人がこの権利を持っています。
この遺留分侵害額請求権は、被相続人が亡くなったこと、さらに遺贈や生前贈与があったことを知ってから、1年以内に行使しなければなりません。
1年を過ぎてしまうと時効を迎えてしまうからです。
なお、例外として遺留分が侵害されていることを知らなかった場合には、10年経過後に時効を迎えます。
遺留分を請求する際には、遺留分侵害額請求をおこなう意思を伝えます。
口頭で請求してもかまいませんが、あとで争いにならないよう、証拠が残る配達証明付き内容証明郵便を利用するのが望ましいでしょう。
3.遺産分割請求権|時効はなし
遺産分割請求権は、自分に遺産を分割するよう主張する権利です。
この権利には、行使の期限が設けられていません。
そのため、遺産分割請求権自体に時効はありません。
ただし、遺産分割をおこなわずに財産の共有状態が長く続くと、のちに相続人同士のトラブルの原因になります。
たとえば、財産の売却や処分するためには共有者全員の同意が必要です。
また、共有状態が続くうちに相続人が亡くなり、権利関係が複雑化する可能性なども考えられます。
遺産分割請求権はいつでも行使できますが、財産の共有状態が長期間続くことによるデメリットも考慮し、早めに分割を検討する必要があるといえるでしょう。
4.相続回復請求権|5年で時効(例外として20年)
相続回復請求権とは、相続人でない方が相続人のふりをして遺産を取得したために、自分の相続権が侵害されている場合に行使できる権利です。
この権利を行使することで、本来の相続人が遺産を取り返すことができます。
相続回復請求権の時効は5年です。
また例外として、相続権の侵害がおこっていることを知らなかった場合には、20年で時効を迎えます。(民法884条)
5.相続税申告|5年で時効(例外として7年)
相続税は、一定以上の金額を相続した場合に発生する税金です。
相続税の申告および納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
この期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが発生します。
相続税には時効があり、申告期限の翌日から5年を経過すると、納税義務がなくなります。
そのため、延滞税などのペナルティを受ける期間は申告・納税期限の翌日から5年間ということになります。
ただし、例外として悪意のあるケースでは、7年という時効が適用される場合があります。
たとえば、遺産を相続したことを知りながら、意図的に申告しなかったり、虚偽の申告をおこなったりした場合です。
この場合、相続税の時効期間は、通常の5年から7年に延長されます。
相続税の申告・納税は、適切な手続きを期限内におこなうことが大切です。
6.贈与税申告|6年で時効(例外として7年)
贈与税は、生前贈与によって年間で合計110万円以上の財産を受け取った際に課される税金です。
贈与税の申告および納税の期限は、贈与を受けた翌年の3月15日までと定められています。
この期限を過ぎたり、申告漏れなどがあった場合には、国税局や税務署から追徴課税などのペナルティを受ける可能性があります。
ただし、贈与税にも時効が定められており、申告期限の翌日を起算日として、通常は6年間で納税義務が消滅します。
しかし、納税義務があることを知りながら、申告しないなどの不正行為があった場合には、時効が7年間に延長されます。
贈与は、与える側と受け取る側の合意によって成立するため、贈与を受け取ったことを知らなかったという主張は通用しません。
被相続人から年間110万円を超える財産を受け取った場合には、期限内に必ず申告するようにしましょう。
7.債務(債権)|5年で時効
債務(債権)の消滅時効は、債権者が権利を行使できることを知ってから5年です。
たとえば、被相続人が借金を長期間支払わずにいたり、相続人が債務を相続したあとに借金を支払わなかったりして、その支払い期日から5年が経過すれば、消滅時効によって債務は消滅します。
ただし、5年が経過すれば自動的に債務が消滅するわけではありません。
債権者に対して、消滅時効を援用する旨を通知する必要があります。
通知方法に決まりはありませんが、時効の援用をしたという証拠を残すためにも、配達証明付きの内容証明郵便の利用をおすすめします。
8.相続登記|時効はなし
相続登記とは、土地や建物などの所有者が亡くなった場合に、相続により所有者が変更されたことを登記簿に登録する手続きです。
相続登記には時効がありませんが、登記が完了していない状態では、第三者に対して相続した権利を主張できない場合があります。
また、 2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されています。
そのため、不動産を相続した場合、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を完了させなければなりません。
期限内に相続登記をおこなわなかった場合、 10万円以下の過料が発生する可能性があるため、注意しましょう。
【関連記事】自分でできる相続登記|必要書類や申請書・相続関係図の作り方まとめ
9.準確定申告|5年で時効
準確定申告とは、被相続人が生前に所得税の納税義務があった場合に、その相続人が代わりに確定申告をおこなう手続きです。
通常の確定申告とは異なり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告手続きを完了しなければなりません。
この期限を過ぎた場合には、加算税や延滞税が課される可能性があるため、注意しましょう。
なお、準確定申告における税金の徴収権に時効があり、申告期限の翌日から5年で消滅します。
この期間内に税務署が徴収に関する対応をしない場合には、納税義務がなくなります。
10.保険金請求の時効|3年で時効
生命保険などの保険金は、被相続人が亡くなってから自動的に支払われるわけではなく、相続人などが保険会社に請求手続きをおこなう必要があります。
保険金請求の基本的な時効期間は、保険会社の種類や契約条件によって異なりますが、被相続人が亡くなってから3年以内としている保険会社が多いです。
ただし、保険契約や保険会社の規定によって、時効が延長される場合や、例外的に請求が受け付けられる場合もあります。
被相続人が保険に加入していることが判明した場合には、3年以内に請求手続きをおこなうことが重要です。
11.遺産の取得時効|20年で時効
土地や不動産など、分割すべき遺産であるにもかかわらず、特定の相続人が占有している場合、その占有が20年以上にわたるのであれば、取得時効が成立します。
そのため、遺産分割の対象とはならない可能性があります。
取得時効については、民法第162条1項で次のように定められています。
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
ここでいう「所有の意思」とは、それが「自分のものだと確信する」ということです。
その遺産が当然自分のものであり、分割すべき遺産であるとは思いもよらないと考えている状態を指します。
取得時効を主張できる例としては、親が祖父母の残した家に20年以上住み続けているケースなどが挙げられます。
この家は祖父母の遺産であり、本来ならば遺産分割の対象です。
しかし、親が亡くなれば、その事実を知らない子どもは当然相続します。
親の兄弟から、家は祖父母の遺産であり分割することを主張されても、取得時効が成立しているため、子どもは応じなくてよいのです。
この例のように、取得時効は数次相続が起こった際に援用できる可能性のあるものです。
一般的な相続では、「所有の意思」が認められないため、発生しえません。
遺産分割のやり直しはできる?
ここで見てきたとおり、遺産分割の手続きには、さまざまな時効があります。
では、遺産分割のやり直しはいつでもできるのでしょうか。
結論からいうと、遺産分割のやり直しは可能です。
時効がないからできる
遺産分割の手続きのうち、遺産分割請求権には時効がありません。
このため、遺産分割のやり直しを主張すること自体はいつでも可能です。
ただし、遺産分割協議は通常、相続人全員の合意によって成立します。
そのため、基本的には遺産分割は一度で完了すべきものであり、やり直しは例外的な対応とされています。
したがって、遺産分割をやり直すためには、一定の条件を満たす必要があります。
遺産分割のやり直しをする条件
遺産分割は次のようなケースでやり直すことができます。
遺産分割後に新たな財産が見つかる
遺産分割協議を経て遺産分割をしたあとに、新たな財産が見つかった場合は、必ず遺産分割をおこないます。
しかし、初めからやり直す必要はなく、新たに見つかった分についてのみ協議をおこない、分割すれば問題ありません。
相続人全員がやり直しに合意している
相続人全員が遺産分割協議のやり直しに合意すれば、もう一度遺産分割をおこなえます。
ただし、合意は全員分必要で、ひとりでも反対している方がいれば、できません。
また、遺産分割協議をやり直すなら、必ず遺産分割協議書も作り直します。
さらに、以前作成した遺産分割協議書の破棄も忘れずにおこなうことも大切です。
誤った内容で相続手続きを進めてしまえば、さらなるトラブルが起こる可能性があるためです。
遺産分割協議が無効と認められた
遺産分割協議が無効となる場合もやり直すことができます。
たとえば、遺産分割協議は次のようなケースで無効となります。
- あとになって新たな相続人の存在が発覚するなど、遺産分割協議に参加していない相続人がいた
- 相続人ではない方が遺産分割協議に参加していた
- 相続人の中に認知症で判断能力のない方がいた相続人の中に未成年がいるにもかかわらず、法定代理人を立てていなかった
遺産分割協議に詐欺や脅迫があった
次のような場合は遺産分割協議を取り消し、協議のやり直しを求めることができます。
- 詐欺があった
- 脅迫があった
- 大きな誤解をしていた
これらの場合には、相続人全員の合意がなくても協議の取り消しを主張できます。
なお、取消権には時効があり、詐欺や脅迫などがあったことを知った日から5年、遺産分割協議が成立した日から20年経過すると取消権は消滅します。
そのため、遺産分割協議に詐欺や脅迫があった場合には、早めに手続きを進めましょう。
遺産分割をやり直すときの注意点
遺産分割をやり直す際は、以下の点に注意しましょう。
第三者の権利を侵害することはできない
遺産分割をやり直すことになっても、相続人以外の第三者の権利を侵害することはできません。
たとえば、先に作成した遺産分割協議書をもって、すでに不動産を売却してしまっていた場合、売却先から該当不動産を取り戻すことはできません。
遺産分割をやり直すといっても、全てを無効にして初めからやり直せるわけではないので注意しましょう。
不動産取得税・登録免許税が発生してしまう
遺産に不動産が含まれる場合は、遺産分割のやり直しによって不動産取得税や登録免許税がかかる可能性があります。
所有者が変更となれば、贈与または売買とみなされるため、不動産取得税がかかります。
また、相続登記のやり直しによって、登録免許税がもう一度かかります。
遺産分割をやり直せば税負担が倍増しかねないため、どうしてもやり直したい場合は、あらかじめ税理士に税額を確認のうえ、おこなったほうがよいでしょう。
贈与税や所得税が新たに発生する可能性がある
遺産分割のやり直しによって、当初とは別の方が遺産を相続すれば、贈与や売買とみなされるため、二重に課税される可能性があります。
その結果、相続税とは別に贈与税や所得税が発生し、本来支払う必要のなかった税金まで支払う必要が生じるのです。
遺産分割の時効に関するよくある質問
最後に、遺産分割の時効に関してよくある質問について、みていきましょう。
遺産相続の時効は何年ですか?
遺産相続の時効は、遺産相続の際に請求する権利の種類や状況によって異なります。
主な時効の期限は、以下のとおりです。
| 相続放棄 | 3ヵ月 |
|---|---|
| 遺留分侵害額請求権 | 1年 |
| 遺留分が侵害されていることを知らなかった場合は10年 | |
| 遺産分割請求権 | 時効はなし |
| 相続回復請求権 | 5年 |
| 知らなかった場合は20年 | |
| 相続税申告 | 5年 |
| 悪意があると判断された場合は7年 | |
| 贈与税申告 | 6年 |
| 悪意があると判断された場合は7年 | |
| 債務(債権) | 5年 |
| 相続登記 | 時効はなし※ |
| 準確定申告 | 5年 |
| 保険金請求 | 3年 |
| 遺産の取得時効 | 20年 |
※不動産の相続登記については法改正により、3年以内の相続登記が義務化されています。ただし、具体的な状況やケースによって、異なる場合もあります。ですので、時効に関して不明点がある場合には、弁護士などに相談したほうがよいでしょう。
相続してから10年後の遺産分割はどうなりますか?
相続してから10年が経過した場合の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなります。
これは、2023年4月の民法改正により定めされた規定です。
遺産分割そのものは引き続き可能であり、法定相続分または指定相続分に基づいて分割がおこなわれます。
なお、10年経過後であっても、相続人全員が合意すれば、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割をおこなうことは可能です。
遺産分割を放置したらどうなりますか?
遺産分割を放置すると、相続人は相続財産を自由に扱うことができません。
そのため、相続財産を売却したり、預貯金を引き出したりすることができなくなります。
また、相続放棄の期限は相続の開始を知った日から3ヵ月、相続税の申告期限(時効)は相続の開始から10ヵ月と定められています。
このため、遺産分割を放置したまま時効や期限を迎えると、借金を相続したり、追徴課税や延滞税を課せられる可能性があります。
これらの損失を防ぐためにも、遺産分割は放置せずに、早めに誰が何を相続するのか決めることが重要です。
まとめ
遺産分割自体に時効はありません。
だからといって、いつまでも遺産分割をおこなわなければ、知らない間にほかの相続手続きの時効が成立してしまい、思わぬ不利益を被る可能性があります。
そのため、できるだけ早めに遺産分割の手続きを進めるのが賢明です。
時効のある手続きにはどのようなものがあるかを知り、計画的に遺産分割をおこないましょう。
なお、わからないことがあったり、相続人同士での話し合いがまとまらなかったりして、遺産分割が進まない場合には、早めに弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士の協力によって、すぐに解決できる問題もあるからです。
遺産相続で思わぬ不利益を被らないためにも、遺産分割をはじめとした相続手続きは、早めに着手しましょう。