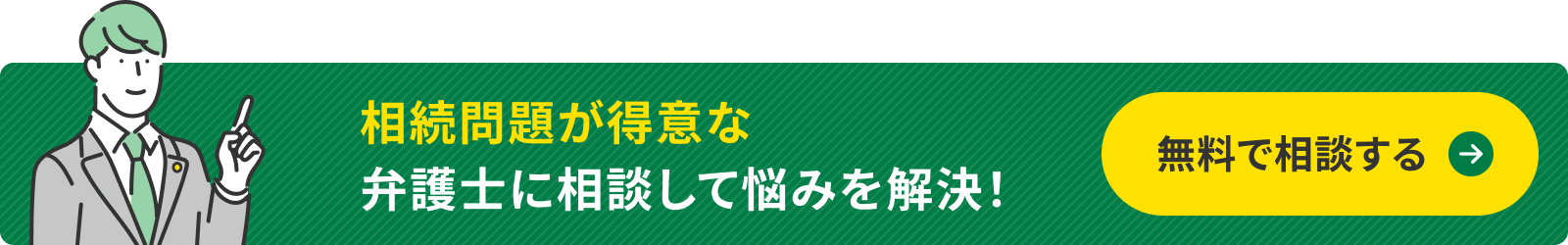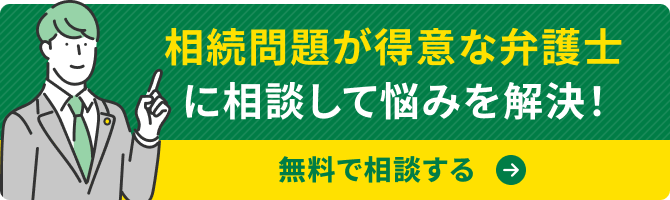「親の相続が開始してはじめて借金の存在が判明した」というような場合、生前に財産を贈与されていても相続放棄はできるのでしょうか?
「親の財産を一度受け取ったなら、借金の返済義務なども引き継がなければならない」と思う方もいるかもしれません。
しかし、結論からいうと、生前贈与を受けていても相続放棄は可能です。
ただし、被相続人の債権者に生前贈与の取り消しを請求されたり、生前贈与に対して相続税が課税されたりする可能性があります。
本記事では、生前贈与後の相続放棄について注意すべき点や、手続きの流れなどについて解説します。
また、生前贈与や相続放棄以外に効果的な相続方法なども触れますので、参考にしてみてください。
生前贈与や相続放棄をする際の基礎知識
ここでは、生前贈与や相続放棄がどのようなものなのかを解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、自身が存命中に財産を家族などに贈与することを指します。
生前贈与の対象になるのは現金や預金だけでなく、不動産(家や土地など)や株式などが贈与されることもあります。
生前贈与をおこなう際は、贈与契約にもとづいて贈与契約書を作成する方法のほか、口頭だけで済ませることも可能です。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の資産も負債も一切相続しないことを指します。
相続放棄をおこなうと「はじめから相続人ではなかった」という扱いになり、遺産分割協議などの相続手続きにも参加できなくなります。
なお、相続放棄をおこなうには家庭裁判所に申述して許可を得る必要があり、手続きには期限なども設けられています。
生前贈与を受けても相続放棄をすることは可能
生前贈与を受けたあとに相続が発生しても、相続放棄することは可能です。
相続放棄ができなくなるケースとしては「すでに相続財産を処分した場合」や「期限内に相続放棄の申述書などを提出しなかった場合」などがあります(民法第915条、921条)。
相続財産の一部を処分してしまった場合は「単純承認をしたもの」とみなされてしまい、相続放棄はできません。
また、相続放棄では「自分が相続人になったことを知ったときから原則3ヵ月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
生前贈与を受けたあとに相続放棄をする場合の注意点
生前贈与後に相続放棄をおこなう場合、以下のような点に注意しましょう。
詐害行為取消権を行使されて生前贈与が取り消されるおそれがある
生前贈与によって被相続人の財産を譲り受けておきながら相続放棄によって被相続人の債務の引き受けを免れる場合、被相続人の債権者からみると不公平に感じることもあるでしょう。
特に、生前贈与の時点で被相続人が債務超過などの状況にあることを知りながら、生前贈与を受けた可能性がある場合はなおさらです。
このように、被相続人の債権者にとって不公平な生前贈与がおこなわれた場合、債権者は生前贈与の取り消しを求めることができ、これを「詐害行為取消権」(民法第424条第1項)といいます。
たとえば「被相続人である父親に借金があり、債権者が被相続人の唯一の財産である不動産について強制執行を予定していた」というケースを想定して考えてみましょう。
父親が不動産を守るため、推定相続人である息子に対して不動産を生前贈与して名義変更をしてしまった場合、債権者としては差し押さえる財産がなくなってしまいます。
相続によって息子が父親の債務などを引き継いだ場合は、債権者は息子に対して返済を請求できるでしょう。
しかし、息子が借金を受け継がずに相続放棄をおこなった場合、被相続人の不動産から債権回収しようとしていた債権者は不当に害されます。
債権者が、生前贈与を受けた息子に対して詐害行為取消訴訟を提起して勝訴すれば、生前贈与は否定されて息子は不動産を返さなければなりません。
このような場合、相続放棄をしているため債務の返済は免れることができますが、生前贈与を取り消された息子は不動産を手放すことにはなります。
相続財産に持ち戻しされて相続税が発生する可能性がある
生前贈与後の相続放棄で注意すべきものとして「相続税」があります。
「相続放棄をして相続財産を引き継いでいないのだから相続税は発生しない」と思う方もいるかもしれません。
しかし、相続放棄をした場合でも、生前贈与については相続財産に持ち戻しされて相続税がかかることもあります。
相続税が発生するケースとしては、以下のようなものがあります。
生前贈与が相続開始前3年以内~7年以内におこなわれた場合
被相続人の死亡前に相続人に対してなされた生前贈与のうち、死亡時からさかのぼって3年分~7年分のものについては相続税の課税対象となります。
これまでの生前贈与加算の期間は「相続開始前3年以内」でしたが、2023年の税制改正によって順次「7年以内」に変更されています。
なお、以下のように一定の経過措置が設けられています。
| 相続が発生した時期 | 生前贈与加算の対象 |
|---|---|
| 2026年12月まで | 現行法どおり3年分が加算 |
| 2027年1月から同年12月まで | 最長4年分が加算 |
| 2028年1月から同年12月まで | 最長5年分が加算 |
| 2029年1月から同年12月まで | 最長6年分が加算 |
| 2030年1月から同年12月まで | 最長7年分が加算 |
| 2031年1月以降 | 7年間が生前贈与加算対象 |
このように、今後は7年間の生前贈与額の合計が相続税の基礎控除額を超える場合、たとえ相続放棄をしたとしても相続税の支払い義務が発生します。
相続時精算課税制度を利用した場合
相続時精算課税制度とは「合計2,500万円までの生前贈与について贈与税が非課税になる」という制度です。
相続時精算課税制度は贈与税対策にはなりますが、相続発生時には相続税によって精算されるため相続税対策にはなりません。
なお、こちらも2023年に税制改正がおこなわれて「年110万円までの基礎控除枠」が新たに追加されました。
これは「年110万円までの贈与については贈与税も相続税もかからない」というものです。
税制改正によって税負担は軽くなりましたが、控除額を超えている場合は相続税を支払うことになります。
相続放棄の手続きには期限があって取り消しできない
相続放棄には「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」という期限が定められています(民法第915条1項)。
やむを得ない事情などで期限内の手続きが難しい場合は「期間伸長」を申し立てることも可能ですが、申立書などを準備する必要があるうえ、必ずしも認められるわけではありません。
なお、基本的に相続放棄の取り消しは認められないため、本当に相続放棄してもよいかどうか考えたうえで迅速に手続きをおこないましょう。
生前贈与後に相続放棄をする際の手続きの流れ
生前贈与後に相続放棄をおこなう場合、基本的には以下のような流れで手続きを進めます。
- 生前贈与を受ける
- 相続が発生する
- 被相続人の遺言書を確認する
- 相続財産調査・相続人調査をおこなう
- 相続放棄の必要書類を集めて家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所から届いた照会書に記入して返送する
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
ケースにもよりますが、家庭裁判所に必要書類を提出して照会書が届くまでに2週間程度、照会書を返送して相続放棄申述受理通知書が届くまでに1週間~10日程度かかるのが一般的です。
生前贈与や相続放棄以外に効果的な相続方法
生前贈与を受けたあとに相続放棄をした場合でも、相続税などが課税される可能性があります。
また、生前贈与は債権者によって取り消されてしまう可能性もあります。
被相続人に債務がある場合、相続人への負担を抑えて相続するためには以下のような方法が有効です。
相続人が限定承認をおこなう
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという方法です。
この方法であれば、債務を清算したあとに資産が残れば、相続人同士で分配できます。
ただし、限定承認の場合は相続人全員の同意を得たうえでおこなわなければいけません。
生前に債務整理をおこなう
生前に被相続人自身が債務整理をおこなうことも有効です。
主な債務整理の方法としては以下のようなものがあります。
- 任意整理:債権者と話し合って返済期間の延長や月々の返済額の減額などを目指す方法
- 個人再生:裁判所を介して最大90%まで借金を減額させる方法
- 自己破産:裁判所を介して借金の返済義務を免除してもらう方法
できるだけ相続人に債務を引き継がせたくないのであれば、生前に借金問題を解決しておくべきでしょう。
生前贈与や相続放棄に関するよくある質問
ここでは、生前贈与や相続放棄に関するよくある質問について解説します。
生前贈与を受けていても相続放棄はできる?
生前贈与を受けていても相続放棄は可能です。
ただし、相続放棄の期限を過ぎてしまうと認めてもらえないため、速やかに手続きを済ませましょう。
生前贈与は相続に影響する?
生前贈与は相続税対策として有効で、早いうちに済ませて相続財産を減らしておくことで相続税を軽減できる可能性があります。
ただし、タイミングを誤ると相続財産に持ち戻しされたりして十分な節税効果が望めない場合もあります。
親が生きている間に相続放棄はできる?
相続開始前の段階で相続放棄することはできません。
生前贈与を受け取りたくない場合はどうすればよい?
生前贈与は贈与者と受贈者が合意した場合に成立するものであるため、贈与者に「受け取りたくない」という意思表示をすれば受け取らずに済みます。
相続放棄後に遺留分侵害額請求されることはある?
相続放棄をおこなうと「はじめから相続人ではなかった」という扱いになるため、基本的に相続放棄後に遺留分侵害額請求されるようなことはありません。
ただし、相続開始直前に高額な生前贈与を受けた場合や、遺留分権利者に損害が生じることを知りながら生前贈与を受けた場合などは、遺留分侵害額請求される可能性があります。
まとめ
生前贈与を受けていても、相続放棄によって債務などの承継を避けることは可能です。
ただし、債権者によって生前贈与の取り消しを請求されたり、相続放棄をしていても相続税が課税されたりする可能性もあるため注意が必要です。
相続財産に債務が含まれる場合、資産を相続しつつできるだけ債務を引き継がないためには、生前贈与のほかにも限定承認や生前の債務整理などの方法があります。
専門家である弁護士に相談し、自身のケースに合った方法を選びましょう。