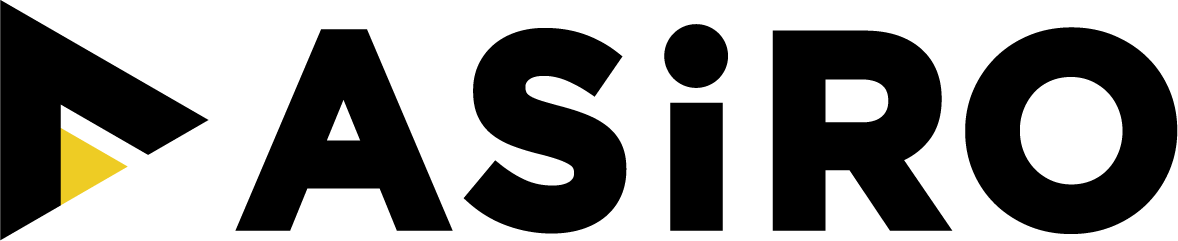兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分に満たない遺産しか相続できなかった方は、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求をおこないましょう。
不足額に相当する金銭の支払いを受けられる可能性があります。
遺留分の計算方法は民法で定められており、実際の計算は複雑になることがあります。
正確な遺留分額を知りたい方は、弁護士にご相談ください。
本記事では、遺留分侵害額の計算方法・計算例・請求手続きなどを解説します。
遺留分とは
「遺留分」とは、相続できる遺産の最低保障額です。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分未満の遺産しか取得できなかった相続人は、財産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」をおこなうことができます。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。
具体的には、以下のいずれかに該当する者のうち、相続権を有するものに遺留分が認められます。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の子の代襲相続人(被相続人の孫、ひ孫など)
- 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
これに対して、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人(被相続人の甥・姪)、相続人でない者(被相続人の元配偶者・内縁者・いとこなど)には遺留分が認められません。
遺留分侵害額請求について
遺留分に満たない財産しか取得できなかった相続人は、被相続人の財産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」をおこなうことができます(民法1046条1項)。
遺留分侵害額請求をすると、遺留分額と実際の財産の取得額の差額につき、相手方から金銭の支払いを受けられます。
ただし、遺留分侵害額請求権には消滅時効がある点に注意が必要です。
以下のいずれかの期間が経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます(民法1048条)。
- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年
- 相続開始の時から10年
遺留分が侵害されている可能性がある場合は、上記の期間内に内容証明郵便の送付や訴訟の提起などをおこない、消滅時効の完成を阻止しましょう。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額は、以下の手順で計算します。
- 基礎財産を調査・集計する
- 遺留分割合を求める
- 遺留分額を計算する
- 遺留分額と実際の取得額の差額を求める
基礎財産を調査・集計する
まずは、遺留分計算の基礎となる財産を調査し、その金額を集計します。
遺留分の基礎財産に含まれるもの、および基礎財産から控除するものは以下のとおりです(民法1043条、1044条)。
<基礎財産に含まれるもの>
①相続財産(原則として、被相続人が死亡時に有した一切の財産)
②遺贈された財産(遺言によって贈与された財産)
③生前贈与された財産のうち、以下のいずれかに該当するもの
(a)相続人に対して相続開始前10年以内に贈与された財産であって、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として贈与されたもの)
(b)相続人以外の者に対して相続開始前1年以内に贈与された財産
<基礎財産から控除するもの>
④被相続人が死亡時に負っていた債務の全額
遺留分割合を求める
次に、遺留分権利者の遺留分割合を求めます。
遺留分割合は、以下の要領で計算します。
①直系尊属のみが相続人である場合
法定相続分の3分の1
②①以外の場合
法定相続分の2分の1
(例1)被相続人の両親のみが相続人である場合
父・母の遺留分割合は6分の1(=2分の1×3分の1)
(例2)被相続人の配偶者と子2人が相続人である場合
配偶者の遺留分割合は4分の1(=2分の1×2分の1)
子の遺留分割合は各8分の1(=4分の1×2分の1)
遺留分額を計算する
基礎財産額と遺留分割合を計算したら、両者を掛け合わせて遺留分額を計算します。
遺留分額=基礎財産額×遺留分割合
(例)基礎財産額が3,000万円、遺留分割合が4分の1の場合
遺留分額は750万円(=3,000万円×4分の1)
遺留分額と実際の取得額の差額を求める
最後に、遺留分侵害額を計算します。
遺留分侵害額は、遺留分額と実際の財産の取得額の差額です。
遺留分侵害額=遺留分額-実際の財産の取得額※
※実際の財産の取得額=取得した基礎財産額-相続した債務額
(例)遺留分額が750万円、取得した基礎財産額が300万円の場合(債務の相続はなし)
遺留分侵害額は450万円(=750万円-300万円)
相続人の構成別|遺留分侵害額の計算例
これまで解説した計算方法に沿って、相続人の構成が異なる以下の設例を用いて、実際に遺留分侵害額を計算してみましょう。
- 相続人が配偶者のみ
- 相続人が配偶者と子2人
- 相続人が配偶者と両親
- 相続人が配偶者と兄弟2人
相続人が配偶者のみ
<設例①>
- 相続人は配偶者Aのみ
- 被相続人が死亡時に有した財産は3,000万円(債務はなし)
- Aは被相続人から、相続発生の5年前に、生計の資本として600万円の贈与を受けた
- 被相続人は、愛人Bに対して相続財産のすべてを遺贈する旨の遺言を残した
設例①において、遺留分の基礎財産額は3,600万円(=遺贈3,000万円+生前贈与600万円)です。
相続人は配偶者Aしかいないため、配偶者Aの法定相続分は1(=100%)です。
したがって、遺留分割合は2分の1となるため、Aの遺留分額は1,800万円(=3,600万円×2分の1)です。
Aは生前贈与として500万円を取得しているので、Aの遺留分侵害額は1,300万円となります。
AはBに対して、1,300万円の支払いを請求できます。
相続人が配偶者と子2人
<設例②>
- 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
- 被相続人が死亡時に有した財産は3,000万円(債務はなし)
- Aは被相続人から、相続発生の5年前に、生計の資本として600万円の贈与を受けた
- 被相続人は、子Bに対して相続財産のすべてを相続させる旨の遺言を残した
設例②において、遺留分の基礎財産額は3,600万円(=相続財産3,000万円+生前贈与600万円)です。
相続人は配偶者A・子B・子Cの3人であるため、Aの法定相続分は2分の1、B・Cの法定相続分は各4分の1です。
遺留分割合は法定相続分の2分の1であるため、Aの遺留分割合は4分の1、B・Cの遺留分割合は各8分の1です。
基礎財産額に遺留分割合を掛けると、Aの遺留分額は900万円(=3,600万円×4分の1)、B・Cの遺留分額は各450万円(=3,600万円×8分の1)となります。
基礎財産のうち、実際に取得できた財産の額はAが600万円、Bが3,000万円、Cが0円です。
これと遺留分額を比較すると、Aの遺留分侵害額は300万円(=900万円-600万円)、Cの遺留分侵害額は450万円(=450万円-0円)となります。
AはBに対して300万円、CはBに対して450万円の支払いを請求できます。
相続人が配偶者と両親
<設例③>
- 相続人は配偶者A、父B、母Cの3人
- 被相続人が死亡時に有した財産は3,000万円(債務はなし)
- Aは被相続人から、相続発生の5年前に、生計の資本として600万円の贈与を受けた
- 被相続人は、父Bと母Cに対して、相続財産を半分ずつ(1,500万円ずつ)相続させる旨の遺言を残した
設例③において、遺留分の基礎財産額は3,600万円(=相続財産3,000万円+生前贈与600万円)です。
相続人は配偶者A・父B・母Cの3人であるため、Aの法定相続分は3分の2、B・Cの法定相続分は各6分の1です。
遺留分割合は法定相続分の2分の1であるため、Aの遺留分割合は3分の1、B・Cの遺留分割合は各12分の1です。
基礎財産額に遺留分割合を掛けると、Aの遺留分額は1,200万円(=3,600万円×3分の1)、B・Cの遺留分額は各300万円(=3,600万円×12分の1)となります。
基礎財産のうち、実際に取得できた財産の額はAが600万円、Bが1,500万円、Cが1,500万円です。
これと遺留分額を比較すると、Aの遺留分侵害額は600万円(=1,200万円-600万円)となります。
後述のとおり、受遺者が複数いる場合は、価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担します。
BとCの相続割合は半分ずつなので、Aは、BとCに対して各300万円(計600万円)の支払いを請求できます。
相続人が配偶者と兄弟2人
<設例④>
- 相続人は配偶者A、弟B、妹Cの3人
- 被相続人が死亡時に有した財産は3,000万円(債務はなし)
- Aは被相続人から、相続発生の5年前に、生計の資本として600万円の贈与を受けた
- 被相続人は、妹Cに対して相続財産のすべてを相続させる旨の遺言を残した
設例④において、遺留分の基礎財産額は3,600万円(=相続財産3,000万円+生前贈与600万円)です。
相続人は配偶者A・弟B・妹Cの3人であるため、Aの法定相続分は4分の3、B・Cの法定相続分は各8分の1です。
もっとも、兄弟姉妹は遺留分権利者ではないため、Aの遺留分割合は2分の1、B・Cの遺留分割合は0となります。
基礎財産額に遺留分割合を掛けると、Aの遺留分額は1,800万円(=3,600万円×2分の1)、B・Cの遺留分額は各0円となります。
基礎財産のうち、実際に取得できた財産の額はAが600万円、Bが0円、Cが3,000万円です。
これと遺留分額を比較すると、Aの遺留分侵害額は1,200万円(=1,800万円-600万円)、Bの遺留分侵害額は0円となります。
AはCに対して1,200万円の支払いを請求できます。
遺留分侵害額を負担する者の順位・負担額
遺留分侵害額は、被相続人の財産を多く取得した者が負担します。
遺留分侵害額の負担順位については、民法によって以下のルールが定められています(民法1047条)。
- 負担額は遺留分を超える金額が限度
- 受遺者が受贈者よりも先に負担する
- 後に贈与を受けた者から順に負担する
- 受遺者または同時の受贈者が複数の場合|価額の割合に応じて負担する
- 遺留分侵害額の負担者が無資力の場合|他の人には請求できない
負担額は遺留分を超える金額が限度
一部の相続人の遺留分が侵害されている場合、他の相続人が負担する遺留分侵害額は、自らの遺留分を超える金額が上限となります。
たとえば、相続人Aの遺留分侵害額が300万円を、相続人Bが最初に負担しなければならないとします。
仮にBが取得した基礎財産額が500万円で、Bの遺留分額が300万円だとすると、遺留分を超える金額は200万円です。
この場合、BはAに対して200万円を支払えば足り、Aは残りの100万円を次順位の負担者に請求することになります。
受遺者が受贈者よりも先に負担する
受遺者(遺言による贈与を受けた人)と受贈者(贈与契約に基づく贈与を受けた人)が両方いる場合は、受遺者が受贈者よりも先に遺留分侵害額を負担します。
たとえば相続人Aの遺留分が侵害されているケースで、Bが遺贈を受け、Cが生前贈与を受けていたとします。
この場合、まずBがAの遺留分侵害額を負担し、残額があればCが負担することになります。
後に贈与を受けた者から順に負担する
被相続人から贈与を受けた人が複数いる場合は、後に贈与を受けた者から順に遺留分侵害額を負担します。
たとえば相続人Aの遺留分が侵害されているケースで、Bが2022年9月1日に生前贈与を受け、Cが2022年8月31日に生前贈与を受けていたとします。
この場合、まずBがAの遺留分侵害額を負担し、残額があればCが負担することになります。
受遺者または同時の受贈者が複数の場合|価額の割合に応じて負担する
受遺者が複数いる場合、または同時に贈与を受けた受贈者が複数いる場合には、遺贈・贈与の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担します。
たとえば相続人Aの遺留分が侵害されているケースで、遺言によりBが1,000万円、Cが500万円の遺贈を受けたとします。
この場合、BとCは2対1の割合で、Aの遺留分侵害額を負担します。
また、Bが1,000万円、Cが500万円の生前贈与を同時に受けた場合も、同様に遺留分侵害額の負担割合は2対1となります。
遺留分侵害額の負担者が無資力の場合|他の人には請求できない
受遺者または受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰するとされています(民法1047条4項)。
つまり、受遺者または受贈者にお金がないことによって回収できなかった遺留分侵害額は、次順位以降の負担者に対して請求できないということです。
たとえば相続人Aの遺留分侵害額が300万円で、Bが2022年9月1日に生前贈与を受け、Cが2022年8月31日に生前贈与を受けていたとします。
この場合、BがCよりも先に、Aの遺留分侵害額を負担します。
Bの取得した基礎財産額が、Bの遺留分額を300万円以上上回っていれば、Aの遺留分侵害額は全額Bの負担となります。
仮に上記のケースにおいて、Bが遺留分侵害額を支払えずに自己破産したとします。
この場合、AはBから遺留分侵害額を回収できなくなりますが、回収不能額をCに請求することはできません。
受贈者であるBの無資力によって生じた損失は、遺留分権利者であるAの負担となるからです。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額請求をおこなう際の手続きは、主に協議・調停・訴訟の3通りです。
まずは協議による解決を試み、不調に終われば調停・訴訟の順に手続きが移行します。
①協議
遺留分権利者と負担者の間で、遺留分侵害額の精算について話し合います。
合意が調えば書面を締結し、その内容に従って遺留分侵害額を精算します。
②家庭裁判所の調停
調停委員の仲介の下で、家庭裁判所において遺留分侵害額の精算方法を話し合います。
合意が調えば調停調書が作成され、その内容に従って遺留分侵害額を精算します。
【参考】遺留分侵害額の請求調停|裁判所
③遺留分侵害額請求訴訟
裁判所に訴訟を提起して、遺留分侵害額の支払いを命じる判決を求めます。
遺留分侵害額請求権を、証拠に基づき立証することが必要です。
いずれの手続きによる場合も、弁護士へのご依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すれば、適正な遺留分侵害額を計算した上で、法的根拠に基づいてその金額を請求できます。
遺留分侵害額請求の弁護士費用の目安
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する際には、弁護士費用がかかります。
弁護士費用の大部分を占めるのは、依頼時に支払う「着手金」と、金銭を回収できたときに支払う「報酬金」です。
「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考にした、遺留分侵害額請求の着手金・報酬金の目安額を紹介します(いずれも税込)。
実際の弁護士費用は、各弁護士へ個別にご確認ください。
<遺留分侵害額請求の着手金額の目安>
| 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の額の8.8% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の額の5.5%+9万9000円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額の3.3%+75万円9000円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の額の2.2%+405万9000円 |
※着手金の最低額は11万円
※経済的利益の額は、請求額(請求された額)の時価相当額
<遺留分侵害額請求の報酬金額の目安>
| 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の額の17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の額の11%+19万8000円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額の6.6%+151万8000円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の額の4.4%+811万8000円 |
※経済的利益の額は、獲得額(支払額の減額分)の時価相当額
遺留分問題について弁護士に相談するなら「ベンナビ相続」
「ベンナビ相続」には、遺産相続事件を豊富に取り扱う弁護士が多数登録されています。
地域や相談内容に応じて、弁護士をスムーズに検索可能です。
無料相談ができる弁護士も多数登録されており、電話やメールで直接問い合わせることができます。
遺留分侵害額請求を依頼する弁護士をお探しの方は、「ベンナビ相続」をご利用ください。