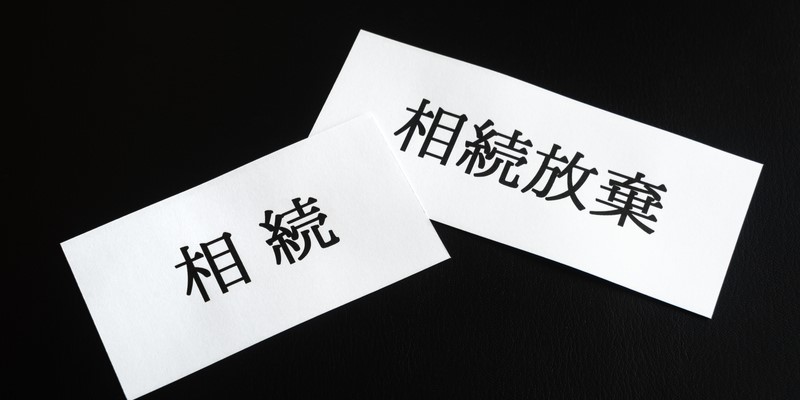相続放棄の費用を知って、誰に依頼するか、自分でやったほうがよいのか判断したいという方も多いのではないでしょうか。
相続放棄をしたいと考えているものの、経済的に余裕があるわけでもない方も少なくありません。
できるだけ費用はかけずに済ませたいと考えるのは当然です。
ただし、相続放棄の費用に関しては注意点も多くあります。
相続放棄について迅速に解決するためにも、なるべく早い段階で専門家に相談するのがおすすめです。
本記事では、相続放棄にかかる費用相場、相続放棄をする際に費用以外で気をつけるべきポイントについて解説します。
相続放棄にかかる費用相場|自力の場合と専門家に依頼する場合
相続放棄にかかるおもな費用相場は、以下のとおりです。
| 相続放棄の手続き方法 | 費用相場 |
| 自分でおこなう場合 | 約3,000円〜5,000円 |
| 司法書士に依頼する場合 | 約3万円〜5万円 |
| 弁護士に依頼する場合 | 約5万円〜10万円 |
こちらでは、手続き方法ごとの相続放棄の費用相場についてそれぞれ解説していきます。
相続放棄を自分でおこなう場合の費用|3,000円~5,000円程度
相続放棄を自分でおこなう場合の費用内訳は、以下のとおりです。
| 必要書類 | 費用 |
| 相続放棄申述書に添付する印紙 | 800円 |
| 郵便切手 | 470円 |
| 相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
| 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
| 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 被相続人の戸籍附票(または住民票除票) | 300円 |
相続放棄の費用は、裁判所によって異なります。
そのため、亡くなられた方の最終居住地の裁判所にあらかじめ問い合わせてみるとよいでしょう。
また、相続放棄の理由や方法によっても費用が変わる場合があります。
たとえば、ご自身と亡くなられた方が別の場所に住んでいた場合、必要な書類を取得したり送付したりするために、交通費や郵送料がかかります。
さらに、ご自身と被相続人との関係によっては、多くの書類が必要になることもあります。
その場合、書類の準備だけで数千円の出費が発生する可能性があるでしょう。
相続放棄は一度しかできません。
書類に不備や漏れがあると、相続放棄が認められないこともあります。
また、死亡時などの相続開始を知ったときから3か月以内に裁判所に手続きをする必要があり、スケジュール管理も大切です。
ご自身で手続きをする場合は、注意深く書類を確認することが重要です。
相続放棄を司法書士に依頼する場合の費用|3万~5万円程度
相続放棄を司法書士に依頼する場合の費用内訳は、以下のとおりです。
| 相談料 | 0〜5,000円/60分 |
| 申述書作成のための実費 | 3,000〜5,000円 |
| 書面作成代行手数料 | 3万円〜5万円 |
相続放棄の手続きは、書類の作成や提出が必要ですが、司法書士に依頼することで効率的に進めることができます。
司法書士は、戸籍謄本などの必要な書類を取得し、相続放棄申述書の作成や提出を代行してくれます。
これにより、手続きにかかる時間や手間を大幅に減らすことができるでしょう。
司法書士の報酬は、事務所によって異なります。
依頼を検討する場合は、事前に見積もりを取っておくのがおすすめです。
相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用|5万円~10万円程度
相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用内訳は、以下のとおりです。
| 相談料 | 0〜1万円/60分 |
| 申述書作成のための実費 | 3,000~5,000円 |
| 代理手数料 | 5万円〜10万円 |
相続放棄をする場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、相続放棄の申し立てから回答書の作成・提出まで、全ての手続きを代理でおこなってくれます。
回答書は、相続放棄が認められるかどうかに影響する重要な書類です。
自分で作成すると、ミスや不備があると相続放棄が無効になる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、回答書の内容も適切に記載してもらえるので、安心して相続放棄を依頼することができるでしょう。
ただし、裁判所や相続放棄の事情によっては、回答書が本人宛に送られてくることもあります。
その場合でも、弁護士に記載方法を教えてもらって、回答書を提出すれば問題ありません。
相続放棄は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべき?
「弁護士と司法書士、どっちに依頼したほうがいいの?」と悩む方もいるかもしれません。
相続放棄の手続きは、司法書士の業務範囲に制限がかかっています。
したがって、相続放棄の手続きを依頼する際には、ご自身の状況に応じて弁護士と司法書士のどちらに依頼するかを慎重に検討することが大切です。
ここでは、相続放棄は弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきなのかについてそれぞれ解説します。
弁護士に依頼するのが向いている人
相続放棄について弁護士に依頼するのが向いている人は、以下のとおりです。
- 債権者対応も任せたい
- 相続放棄をするべきか迷っている
- 相続財産清算人選任申し立ても依頼したい
- 費用がかかっても手続きを完全に一任したい
相続手続きは、遺産分割協議や遺言書の作成など、さまざまな法的な問題を含む複雑なプロセスです。
そのため、自分でおこなうのは大変な場合が多く、相続人間の対立や紛争の原因になることもあります。
そうしたリスクを回避するためには、相続手続きの専門家である弁護士に依頼することが最善の方法です。
また、相続放棄をしなければならない多くのケースは、債権者から相続人のところに請求がきた場合です。
このときに、債権者対応なども任せられるのは弁護士しかいません。
弁護士は、相続手続きの流れや必要な書類などをわかりやすく説明し、適切なアドバイスや代理業務をおこなってくれます。
また、弁護士は相続人間の利害調整や交渉、裁判などのトラブル解決もサポートしてくれます。
相続手続きに関する不安や悩みを抱えている方、時間や労力を節約したい方、相続トラブルを未然に防ぎたい方は、弁護士に相談するとよいでしょう。
司法書士に依頼するのが向いている人
相続放棄について司法書士に依頼するのが向いている人は、以下のとおりです。
- 少しでも費用を節約したい
- 相続財産調査も依頼したい
相続放棄の手続きにおいて、書類作成や提出のサポートが必要な場合は、司法書士に依頼すると費用対効果が高いでしょう。
司法書士は書類に関する専門知識をもち、相続放棄に必要な書類の準備や手続きをスムーズにおこなえます。
相続人間のトラブルがなく、相続財産が複雑でない場合など、問題なく解決できそうなときは司法書士を利用するのがおすすめです。
相続放棄を弁護士に相談・依頼する4つのメリット
相続放棄は、一定の要件を満たさないと無効になる可能性があります。
そのため、相続放棄を考えている方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すると、手続きの正確さやスピードが向上し、トラブルを回避できる可能性が高まります。
自分で手続きする場合と比べて、どちらがよりよい選択か判断するとよいでしょう。
ここでは、相続放棄を弁護士に相談・依頼するメリット4つをそれぞれ解説します。
1.相続放棄が適しているかのアドバイスをもらえる
相続放棄をするかどうかは、相続人にとって重要な決断です。
相続放棄をすれば、被相続人の財産だけでなく、借金も相続しなくて済みますが、一度相続放棄をしたら取り消すことはできません。
そのため、相続放棄をする前には、被相続人の財産や借金の全体像を把握する必要があります。
しかし、相続人は期限内に決断しなければならず、感情的になってしまうこともあります。
そこで、弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。
弁護士は、客観的な立場から相続放棄が最善の選択かどうかを判断してくれます。
また、相続放棄以外の選択肢も提示してくれます。
たとえば、単純承認や限定承認という方法もあります。
単純承認は、財産と借金を全て受け取ることで、財産の価値が借金を上回る場合に有利です。
限定承認は、財産の範囲内で借金を支払うことで、負債の責任を限定することができます。
弁護士は、これらの方法のメリットやデメリットを説明してくれます。
弁護士に相談することで、ご自身にとって最適な相続方法を見つけることができるでしょう。
2.相続放棄手続きで失敗する可能性が低い
相続放棄の手続きは容易ではありません。
多くの人は相続放棄の意味や方法を十分に理解しておらず、知らず知らずのうちに相続財産を承認してしまうことがあります。
たとえば、被相続人の財産を自分のものとして使ったり、契約や名義を変更したりすると、相続放棄ができなくなるおそれがあります(みなし単純承認)。
また、遺産分割協議に同意することも相続財産の承認とみなされることもあるでしょう。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、書類に不備があると却下されてしまいます。
このとき、一度却下されるとやり直しはできませんので、注意が必要です。
さらに、家庭裁判所から送られてくる相続放棄照会書にも正確に回答しなければなりません。
そのため、相続放棄は弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士は相続放棄の要件を確認し、不備のない書類を作成してくれます。
弁護士に依頼することで、安心して相続放棄ができるでしょう。
3.ほかの相続人とのトラブルを回避できる
相続放棄の手続きや効果について正しく理解している人は少なく、知らず知らずのうちに相続放棄ができなくなるリスクがあります。
被相続人の財産を自分のものとして扱うと、相続を受け入れたことになりますが、これは銀行口座からお金を引き出すことだけでなく、遺産建物の取り壊しなども含まれます。
また、遺産分割協議に同意することも相続を受け入れたことになるので、慎重に判断する必要があります。
自分だけが相続放棄をすると、被相続人の借金は他の相続人に分配され、ほかの相続人の負担が増える可能性があるでしょう。
そのため、他の相続人から反対されることも考えられます。
親族間での争いは感情的になりやすく、スムーズに解決できない場合も多くあります。
弁護士に依頼すれば、ほかの相続人に対しても適切な説明をしてもらえ、協力して相続放棄をするなどの方法を検討し、話し合いを進めてもらえます。
4.債権者の対応もしてもらえる
相続放棄をおこなうと、被相続人の借金を負わなくても済みますが、手続きが終わるまでのあいだは債権者からの請求に直面する可能性があります。
そのような場合は、相続放棄を弁護士に依頼し、合わせて債権者対応も依頼するのがおすすめです。
そうすれば、弁護士が貸金業者などに「受任通知」を送り、債権者とのやり取りを全て代行してくれます。
依頼後は債権者との対応に煩わされることがなくなり、精神的な負担が大きく減るでしょう。
相続放棄の費用が高くなる3つのケース
次のようなケースの場合、相続放棄の費用が高くなる可能性もあります。
- 相続放棄の期限を過ぎている
- 相続財産清算人の申し立てもする
- 相続財産の調査も依頼する
こちらでは、相続放棄の費用が高くなるケースを3つそれぞれ解説します。
1.相続放棄の熟慮期間を過ぎている場合
相続放棄の手続きをおこなう際には、熟慮期間の期限を守ることが重要です。
期限を過ぎてしまうと、相続放棄の理由や事情を書いた「上申書」を提出する必要があり、そのぶん手数料が加算されます。
相続放棄の期限は、「相続開始の事実を知った日から3ヵ月以内」と法律で定められていますが(民法第915条)、期限を過ぎてしまっても、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
2.相続財産清算人の申し立てもする場合
相続放棄をした場合でも、相続財産の管理義務が消えるわけではありません。
相続放棄によって相続人となった方が相続財産を引き継ぐまでの間、相続放棄をした方は引き続き財産の管理する必要があります。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
しかし、法定相続人が1人しかいない場合で相続放棄をした場合や、法定相続人の全員が相続放棄をした場合は、誰も相続財産を引き継ぐことができません。
このような場合は、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう必要があるでしょう。
相続財産清算人は、荒れ果てた空き家を整備したり、売却したりするなど、相続財産の保全や処分などをおこなうことができます。
なお、相続放棄と相続財産清算人選任の申し立てを同時に依頼する場合は、費用が増額されます。
3.相続財産の調査も依頼する場合
相続放棄の手続きだけでなく、相続財産の調査も依頼する場合は、別途費用が必要になります。
相続放棄を検討する際には、銀行預金や株式、土地や建物などの相続財産の状況を知りたいと思うことも多いでしょう。
相続放棄の手続きに加えて、相続財産の調査もおこなうと費用が増額されます。
相続放棄の依頼費用を安く済ませる5つの方法
相続放棄の依頼費用を安く済ませるには、以下の方法を検討するのがおすすめです。
- ほかの親族の相続放棄もまとめて依頼する
- 法テラスを利用する
- 弁護士保険に加入しておく
こちらでは、相続放棄の費用を安く済ませる方法5つをそれぞれ解説します。
1.複数の事務所から見積もりを取って比較する
弁護士費用の相場は、事件の種類や内容、弁護士の実績や評判などによって大きく変わります。
インターネットで調べても、一概に正しいといえる情報を見つけることは難しいものです。
弁護士費用が適正かどうかを判断するためには、複数の弁護士に見積もりを依頼することがおすすめです。
2〜3人以上の弁護士から見積もりを取ることで、弁護士費用の相場をある程度把握することができます。
ただし、弁護士費用だけでなく、弁護士のスキルや対応なども考慮して、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。
2.ほかの相続人の相続放棄もまとめて依頼する
相続放棄をする場合、同じ相続順位にある相続人は一緒に手続きをおこなうことができます。
相続放棄の手続きには専門家の協力が必要ですが、専門家によって料金は異なります。
兄弟姉妹全員が相続放棄を希望するなら、1人ずつ依頼するよりも、まとめて依頼するほうが料金を抑えることができるでしょう。
3.法律事務所などの無料相談を有効活用する
「初回の相談料無料」と謳っている法律事務所は数多く存在します。
相談できる時間は「30分まで」「1時間まで」などと限られていることが多く、居住地や相談したい内容などによっては条件が設けられている場合もあります。
無料で利用できるのは相談だけで、弁護士に問題や事件の解決を依頼する場合は、依頼する際に着手金が必要になります。
相談と依頼は別物として考えておく必要がありますので注意が必要です。
ですが、相談するだけでも専門家の視点から解決方法やアドバイスをもらえるため、自分が何をすべきかがはっきりとわかるでしょう。
無料相談を上手に活用すれば、いくつかの法律事務所に相談したあとで、着手金や報酬金を比べることもできます。
弁護士との相性を確かめることができるのも利点といえるでしょう。
相続放棄の無料相談をするならベンナビ相続がおすすめ!
相続問題に関する専門的なアドバイスを必要とする方は、「ベンナビ相続」というポータルサイトの利用がおすすめです。
ここでは、日本全国の相続問題に強い弁護士を地域や無料相談の有無などの条件で検索できます。
相続問題は複雑でデリケートなものですから、信頼できる弁護士に相談することが大切です。
ベンナビ相続は、そんな相続問題に対応できる弁護士を見つけるための便利なWebサイトです。
4.法テラスの民事法律扶助業務を利用する
法テラスは、法的トラブルに直面した人々に対して、専門家の支援を提供する国の機関です。
法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士・司法書士に依頼する際の費用を立て替えてもらえます。
しかし、この制度を利用するには収入および資産に関する一定の要件が必要です。
そのため、詳しくは法テラスの公式サイトを確認してください。
5.加入している弁護士費用保険を利用する
相続トラブルなどの法的問題に対処するためには、弁護士のサポートが必要です。
しかし、弁護士に依頼すると高額な費用がかかることが多く、気軽に相談できないと感じる方もいるでしょう。
そのような場合は、弁護士保険を利用すると便利です。
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際に必要となる弁護士費用を補償する保険のことです。
保険料も月額数百円から数千円程度のため、加入しやすくなっています。
弁護士保険に加入しておけば、着手金や報酬金などの費用を心配せずに、弁護士に相談や依頼ができるでしょう。
相続トラブルだけでなく、離婚や近隣トラブル、子どものいじめ問題など、幅広い分野で活用できます。
法的問題に巻き込まれたときに安心できるように、弁護士保険に加入しておくのもおすすめです。
相続放棄をする際に費用以外で気を付けるべき3つのポイント
相続放棄は、相続人が相続財産を受け取らないことを意思表示することです。
相続放棄は、一度おこなうと取り消すことができないため、慎重に判断する必要があります。
ここでは、相続放棄をする際に費用以外で気をつけるべきポイント3つをそれぞれ解説します。
1.相続財産を勝手に処分しないようにする
相続放棄を希望する方は、相続財産を勝手に処分しないようにしましょう。
無断で処分をした場合、その財産に対する相続の意思があると判断され、相続放棄が不可能になります。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続財産の処分は、無意識におこなってしまうこともありますが、法律の知識がなくても処分をした場合は相続放棄ができなくなることに注意しましょう。
ただし、葬儀費用などの一部の財産については処分が認められています。
もし「処分」の範囲について不明な点があれば、弁護士に相談するのがおすすめです。
2.現に占有している不動産の管理義務は残る
相続放棄を選択した場合でも、相続財産の一部を現に占有している場合は、その財産の管理義務が発生します。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
そのため、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を適切に保護する必要があります。
たとえば、親の名義である実家に住んでいた場合、親が亡くなったあとに相続放棄をしても、実家の管理義務は免れません。
3.一度受理された相続放棄は基本的には取り消しができない
相続放棄は、一度受理されてしまうと原則として取り消すことができません。
相続放棄後に財産が見つかることもありますが、そのような場合に「相続放棄を撤回したい」と申し出たとしても、法律上認められないのです。
そのため、相続放棄は財産の状況を十分に把握し、確実にしてから決めるのが賢明といえます。
さいごに|相続放棄をするなら一度弁護士に相談してみよう!
相続放棄をする場合には、弁護士にサポートしてもらうのが賢明です。
相続放棄をすれば、ご自身は負債を引き受けなくて済みますが、その代わりにほかの人が相続することになります。
たとえば、被相続人の子どもたちが相続放棄をしたら、被相続人の両親や兄弟(子どもたちにとってはおじ・おば)が法定相続人となります。
このように、予想外の相続関係が生じると、相続問題が複雑化し、相続トラブルに発展する可能性が高まります。
相続トラブルに巻き込まれたとき、対処できるのは弁護士だけです。
弁護士であれば、相続放棄の妥当性を法的な根拠で主張してくれます。
費用は必要ですが、時間や労力、手間を節約できるだけでなく、万一の相続トラブルにも対応してくれる安心感が得られます。
これは、大きなメリットといえるでしょう。
そして、弁護士を探す方法のひとつに「ベンナビ相続」の活用があります。
ベンナビ相続は、相続問題を解決するために、専門的な知識と経験をもつ弁護士を紹介するポータルサイトです。
全国各地の相続問題に強い弁護士が登録されており、自宅や職場から近い弁護士を簡単に検索することが可能です。
地域や相続問題の種類などの条件によって、ご自身に合った弁護士を探せます。
さらに、平日の昼間に相談できない方のために夜間・休日の相談や、オンラインでの相談も可能な法律事務所もあります。
相続放棄が発生した場合には、なるべく早めに弁護士へ相談することをおすすめします。