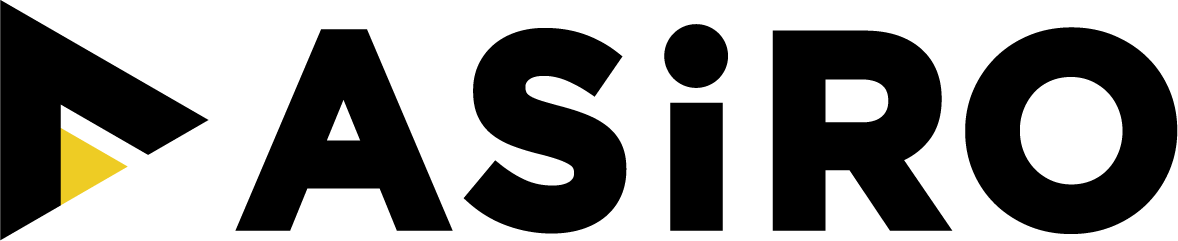相続が発生した際に、亡くなった方に借金が見つかった場合や、相続財産のなかに管理がたいへんな不動産がある場合、相続放棄を考える方は少なくありません。
しかし、相続放棄するとどうなるのか、いつまでにどんな手続きが必要なのか、損することはないのかなど、わからないことも多いのではないでしょうか。
本記事では、相続放棄の効果・方法・注意点など、基本的な知識を紹介します。
また、相続放棄するかどうかを適切に判断するためのポイントについても解説していきます。
相続放棄とは?被相続人の資産・負債を一切引き継がない手続きのこと
相続放棄とは、財産を相続する権利をもっているものの、それを一切引き継がずに放棄することをいいます。
相続をすると、相続人は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。
なお、相続において被相続人とは、亡くなって財産を残す方のことを指します。
反対に、相続人とは、残された財産を引き継ぐ方のことを指します。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多いケースでは、相続放棄をすることが多いでしょう。
相続放棄をするには、家庭裁判所に必要な書類を提出しなければなりません。
相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなって自分が相続人となったことを知った時から3ヵ月以内におこなう必要があり、被相続人の財産を調査するのが困難な場合も少なくないため、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
このあと、相続放棄を選択するほうがいいケースや手続きの流れなどについて、詳しく説明していきます。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続放棄を選択するほうがよい3つのケース
財産を相続せずに、相続放棄を選択するほうがよい3つのケースを紹介します。
1.プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いと考えられる場合
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いと考えられる場合には、相続放棄を選択するとよいでしょう。
プラスの財産とは、現金や預貯金、不動産や車、株式などの有価証券をはじめとする資産を指します。
マイナスの財産とは、クレジットカードの残債や住宅ローンをはじめ、友人に対する借金なども含めて、負債となるものです。
被相続人が多額のマイナスの財産を残して亡くなった場合、同時に引き継いだプラスの財産から返済したとしても、返しきれないようなケースがあります。
そのようなときは、相続放棄するとよいでしょう。
相続放棄が完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
相続放棄が受理されたことを証明する「相続放棄申述受理証明書」は、自動的に交付されないため、別途家庭裁判所に申請する必要があります。
金銭を借りている先である債権者に、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提示すれば、相続放棄したことが伝わり、借金の返済を請求されなくなるのが通常です。
もし何度も請求が来て不安に感じたら、弁護士などに相談しましょう。
2.相続財産が不要な空き家や山林などの場合
空き家や山林などを相続しなければならない場合、相続放棄が適している可能性があります。
自分にとって不要な不動産だったとしても、相続すると固定資産税がかかります。
2024年4月から相続登記の義務化がスタートしたため、相続登記の申請も必要です。
また、使わないからと管理せずに放置するわけにもいきません。
もしも管理しなければ、雑草や倒壊のおそれについて近隣住民から苦情を言われるなどの可能性があります。
さらに、管理をおろそかにしていたことが原因で他人に損害を与えた場合には、損害賠償を請求される可能性もあります。
利用価値の有無だけでなく、空き家や山林などは、放置することにもリスクがあると認識し、相続するかどうかを慎重に検討するべきです。
なお、2023年4月から、相続した不要な土地を国に引き渡すことができる、相続土地国庫帰属制度が開始されました。
この制度を使えば相続放棄をしなくてよい可能性があります。
ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するには要件があり、別途手続きが必要であるため、専門家に相談して判断しましょう。
3.相続人同士の関係が悪く、相続に関わりたくない場合
相続人が複数いる場合、全員で遺産分割協議をおこなわなければなりません。
相続放棄しなければ、自分も遺産分割協議に参加する必要があります。
ほかの相続人との関係性が悪く、話し合いへの参加を避けたい場合も相続放棄が選択肢となります。
相続放棄はほかの相続人から許諾を得る必要はなく、それぞれの相続人が個別で手続きできます。
ただし、相続放棄を選択すると、プラスの財産も一切受け取れなくなります。
遺産分割協議への参加が面倒と感じる程度であれば、相続放棄せず、代理人として弁護士に参加してもらう方法を検討するとよいでしょう。
また、協議は対面だけでなく、電話やメールでも可能です。
そのため、相続人同士の関係が悪く、相続に関わりたくない場合でも、相続放棄をすべきかどうかは慎重に考えたほうがよいでしょう。
相続放棄をする際の流れ|相続放棄申述受理通知書の受け取りまで
ここからは、相続放棄をする際の流れについて説明していきます。
1.相続人と相続財産を調査する
まずは、相続人を確定させなければなりません。
そして、亡くなった方の財産を調べ、相続財産を明らかにする必要があります。
相続人になれる方の範囲と順位は、民法で定められています。
民法の規定にしたがって相続する権利を持つ方を、法定相続人といいます。
法定相続人を確定するため、亡くなった方の戸籍謄本などを入手しましょう。
戸籍謄本は、相続放棄を申述する際などに必要となるため、必要になったらすぐに持ち出せる場所で保管することをおすすめします。
また、亡くなった方の財産を調査することも重要です。
プラスの財産とマイナスの財産がどれくらいあるのかを把握できなければ、相続するのか相続放棄するのかを適切に選ぶことが難しくなります。
2.相続放棄に必要な書類を用意する
財産調査の結果、相続放棄をすると決めたら、家庭裁判所に対して相続放棄を申述しましょう。
手続きに必要な書類を用意する必要があります。
必要書類は、誰が申述するかによって異なります。
誰が申述人である場合にも、次の書類は共通して必要です。
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
これに加え、申述人の立場ごとに次の書類も必要です。
被相続人の配偶者が申述人であるケース
- 被相続人の死亡について記載がある戸籍謄本
被相続人の子どもまたはその代襲相続人(孫など)が申述人であるケース
- 被相続人の死亡について記載がある戸籍謄本
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡について記載されている戸籍謄本
被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が申述人であるケース
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の子どもやその代襲相続人で死亡している方がいる場合、その方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 自分より下の代の直系尊属で死亡している方がいる場合、その方の死亡について記載がある戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹または甥・姪が申述人であるケース
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の子どもやその代襲相続人で死亡している方がいる場合、その方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡について記載がある戸籍謄本
- 甥・姪の場合、被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の死亡について記載がある戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人の立場ごとに必要となる戸籍謄本
3.家庭裁判所に相続放棄を申述する
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票除票または戸籍附票によって調査します。
被相続人の最後の住所地はわかるが、管轄の家庭裁判所がわからないというときは、裁判所のホームページで調べることができます。
相続放棄申述書などの書類は郵送で提出できます。
直接持ち込むと、記載漏れや印鑑の押し忘れなど、小さなミスをその場でチェックしてもらえる可能性があります。
申述期限が迫っているときは、直接持ち込んで、より確実に手続きを進めるとよいでしょう。
申述する際は、申述人一人につき800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手が必要です。
必要な郵便切手の内訳は申述先の家庭裁判所で確認できます。
4.家庭裁判所から届いた照会書に回答する
申述すれば相続放棄が終わるわけではありません。
提出した書類に不備がなければ、家庭裁判所から相続放棄照会書が送付されるため、これに回答して返送する必要があります。
相続放棄照会書とは、相続放棄に関する質問事項が記載された書面です。
相続の開始を知ったのはいつか、相続財産を処分したことがあるかといった質問事項が記載されています。
相続放棄照会書は、通常、相続放棄の申述をしてから1~2週間程度で届きます。
相続放棄の申述をした後は、家庭裁判所からの郵便物がないか入念に確認することをおすすめします。
照会書の内容を確認したら、質問に正確に回答して、家庭裁判所へ返送しましょう。
5.家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が郵送される
相続放棄照会書を返送したら、とくに問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。
この通知書を受け取れば、相続放棄の手続きは完了します。
相続放棄申述受理通知書が送付されるのは1回限りです。
再発行されないため、紛失しないよう気をつけましょう。
相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、別途家庭裁判所に申請する必要があります。
自動的に郵送されることはないため注意が必要です。
相続放棄申述受理証明書が必要となる状況としては、不動産の相続登記をする際などに、相続放棄をしたことを証明する書類を提出しなければならないケースが挙げられます。
なお、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されている相続放棄申述受理通知書であれば、相続登記の際に使用できるとされています。
相続放棄ができなくなってしまう3つのケースに注意しよう
相続放棄をしようとしている方が、相続人の財産を処分したり、隠したりすると、相続放棄できなくなるので注意しなければなりません。
ほかにも相続放棄ができなくなってしまうことがあり、ここでは3つのケースについて説明します。
1.被相続人の財産を処分してしまった場合
相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまった場合、原則として、単純承認したものとみなされ、相続放棄は認められません。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことです。
プラスの財産のなかから現金や預貯金を使い込んでしまうようなケースだけでなく、被相続人が住んでいた部屋に残っていた遺品を処分するだけでも、単純承認したものとみなされる可能性があります。
また、実家が老朽化していたために取り壊した場合も、単純承認したものとみなされる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、プラスの財産にもマイナスの財産にも手をつけず、基本的には全てをそのままにしておくよう、気をつけましょう。
なお、相続放棄の申述が却下されてしまったときは、不服申立てができます。
ただし、申立て期間があるため、注意が必要です。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
2.3ヵ月間の熟慮期間を過ぎてしまった場合
相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内です。
相続開始を知った日は、相続人によって異なります。
被相続人の配偶者や子どもは、亡くなったことをその日のうちに知ることが多いと考えられるため、被相続人が亡くなった日から3ヵ月となるのが通常でしょう。
一方で、被相続人と疎遠になっている場合は、時間が経ってから亡くなったことを知るケースもあるでしょう。
3ヵ月の期間が経過すると、原則として相続放棄はできません。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
3.相続放棄後に財産を隠匿・消費した場合
相続放棄の手続きをしたあとであっても、財産を隠匿・消費してはいけません。
相続放棄したにもかかわらず、このような行為をおこなった場合、相続放棄は無効になり、単純承認したものとみなされます。
単純承認したものとみなされれば、マイナスの財産があった場合は、借金の返済を請求される可能性があります。
現金や預金だけでなく、宝石・美術品・家具・衣服なども、ものによっては財産的価値があるため、相続放棄をした場合、被相続人の自宅から勝手に持ち帰ったり廃棄したりしてはいけません。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続放棄を検討している人が知っておくべき4つの注意点
相続放棄を検討するにあたって知っておくべき注意点について紹介します。
1.一度受理された相続放棄は撤回できない
たとえ相続放棄の期限である、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内であっても、一度受理された相続放棄は、民法第919条により撤回できません。
相続放棄したあとに、被相続人に多額のプラスの財産が見つかったとしても、相続放棄の撤回はできないため、原則としてそれを引き継ぐことはできません。
また、相続手続きが面倒だったために相続放棄をしたけれど気が変わったという場合も、もちろん撤回は不可能です。
被相続人に負債があるからといって、すぐに相続放棄を選択するのではなく、調査を十分おこなってから相続放棄をするとよいでしょう。
なお、以下のような場合には、例外的に相続放棄の取消しが可能です。
- 未成年者が親権者に無断で相続放棄をした
- 詐欺または強迫によって相続放棄をした
- 錯誤によって相続放棄をした
2.祭祀財産は相続放棄の対象にはならない
墓や仏壇は祭祀財産に分類され、相続財産には含まれないため、相続放棄をしても、墓や仏壇を放棄することにはなりません。
祭祀財産とは、祖先を祀るための財産の総称で、民法第897条には、系譜・祭具・墳墓の3つが規定されています。
系譜は、家系図をはじめ、祖先からの家系を示すもののことを指します。
祭具は、祭祀や礼拝に用いる器具で、仏壇・神棚・位牌などです。
墳墓は、墓石や墓地、埋棺を指します。
祭祀財産は、祭祀主宰者が引き継ぐことになります。
祭祀主宰者は、被相続人の指定によって決まります。
指定がない場合には慣習で決まり、慣習が明らかでない場合には家庭裁判所の審判で決まります。
なお、墓を手放したい場合には、いわゆる「墓じまい」をすることになります。
墓じまいの際には、遺骨を取り出したうえ、墓石を撤去して区画を霊園・墓地に返還する必要があります。
墓じまいにかかる費用は数十万円以上になることもあるため、費用についても十分に検討するとよいでしょう。
3.放棄後に財産の保存が必要な場合がある
相続放棄をしても、相続財産である不動産などの保存をしなければならない場合もあります。
たとえば、ほかに相続人がいない場合に相続放棄をしたとき、その財産を現に占有している方はこれを保存しなければなりません。
現に占有しているとは、事実上財産を支配している状態のことです。
具体的には被相続人の自宅で暮らしている相続人などは、現に自宅を占有している状態になるため、相続放棄をしても自宅を保存しなければなりません。
一方、被相続人の自宅に住んでいない場合には、現に自宅を占有しているとはいえないため、相続放棄をしたあとの保存義務はありません。
4.相続放棄の場合は代襲相続が発生しない
相続放棄には、代襲相続が発生しないという特徴があります。
代襲相続とは、本来相続人となるべき方が一定の理由で相続できない場合に、その子どもが代わりに相続人になることです。
典型的なパターンとして、子どもが親よりも先に死亡しているケースがあります。
親が亡くなれば、本来は子どもが相続人になります。
しかし、子どもがすでに死亡していると、子どもは相続人になれません。
このようなときは、子どもの子ども、つまり被相続人にとっての孫が相続人となります。
同じように、子どもに相続欠格や相続廃除があった場合は代襲相続が発生し、孫が相続人になります。
このとき、孫のことを代襲相続人と呼び、すでに亡くなっている子どもを被代襲者と呼びます。
相続放棄では代襲相続が発生しないため、子どもが相続放棄をしても、その子どもが代襲相続人となることはありません。
たとえば、親にプラスの財産が多くあった場合などには、自分ではなく、自分の子どもつまり親からみた孫に相続させたいと考える方もいるでしょう。
しかし、相続放棄をして、代襲相続を実現することはできません。
相続放棄に関するよくある質問
相続放棄に関して、よくある質問とその答えを見てみましょう。
Q.相続人全員が相続放棄をすると相続財産はどうなる?
全ての相続人が相続放棄をすると、相続財産は最終的に国のものになります。
相続放棄をすると、通常、相続の権利は次に相続人となるべき方に移りますが、全員が相続放棄をすると、相続人がいなくなります。
相続人がいなくなった場合、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、本当に相続人がいないかを調査します。
相続人が存在しないことが確定した場合、債権者への支払いなどがなされ、相続財産は清算されます。
最終的に残った財産は国庫に帰属することになります。
Q.相続財産から葬儀費用を支払った場合でも相続放棄はできる?
葬儀費用が社会通念上相当といえる範囲内であれば、相続財産から葬儀費用を支払ったとしても相続放棄できる可能性が高いといえます。
しかし、葬儀費用が不相当に多額な場合などには、単純承認とみなされ相続放棄できない可能性があります。
Q.相続放棄をすると死亡保険金や遺族年金も受け取れなくなる?
生命保険の死亡保険金は、受取人が被相続人とされている場合を除き、受取人固有の財産として相続財産とはなりません。
遺族年金も相続財産ではなく、受給者である遺族固有の財産です。
そのため、これらについては、受取人に指定されている方や受給者であれば、相続放棄をしても受け取れます。
Q.相続放棄と事実上の相続放棄の違いは何か?
相続放棄と似たような手段として、事実上の相続放棄があります。
財産放棄、遺産放棄などと呼ばれることもありますが、いずれも法律上の用語ではありません。
事実上の相続放棄にはいくつかの方法がありますが、たとえば、遺産分割協議において、ほかの相続人に対し、自分は財産を放棄すると伝え、自分の取得する分をゼロとする方法があります。
相続放棄と異なり、家庭裁判所で手続きをする必要はありません。
ただし、事実上の相続放棄をしても、相続人という立場は失われません。
事実上の相続放棄をしても、マイナスの財産の相続を免れることはできないため、注意が必要です。
マイナスの財産を相続したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることを検討しましょう。
さいごに|相続放棄によって被相続人の負債を背負わないでよくなる!
相続放棄すると、被相続人のマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなります。
一方で、プラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
相続放棄をすべきかどうか迷っているなら、無料相談を活用して弁護士に相談しましょう。
相続放棄には期限があります。
少しでも早い相談が、後悔のない決断につながります。
相続について弁護士に相談したい場合は、相続問題を得意とする法律事務所が多数登録しているポータルサイト「ベンナビ相続」を、ぜひ活用してください。
自分に合う弁護士がきっと見つかります。