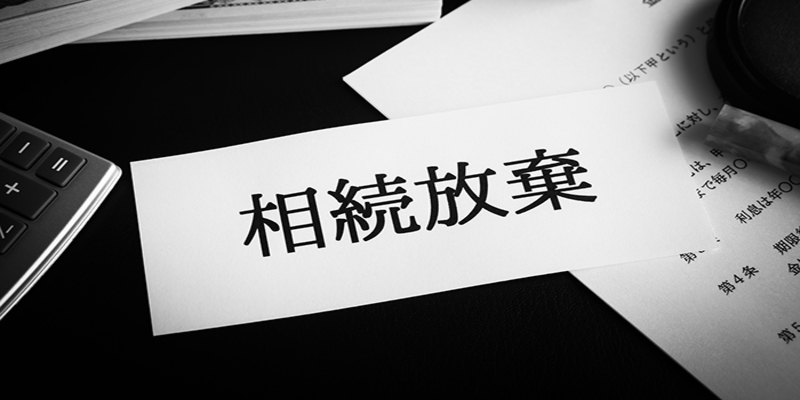親が亡くなると、通常、子どもは遺産を相続します。
しかし、もしその遺産に多額の借金があると発覚したら、どうすればよいのでしょうか。
代わりに支払わなければならないのでしょうか。
実は、親の借金を引き継がずに済む方法があります。
その方法とは、「相続放棄」です。
相続放棄をすれば、全ての相続財産を手放すことになるため、親の借金を返済する義務を免れることができます。
本記事では、親の借金を相続しない相続放棄について、注意すべきデメリットや手続きの流れを解説します。
また、親の借金を相続してしまった場合の対処法についても紹介しますので、参考にしてください。
相続の際に親の借金が見つかり、どうすれば借金を相続せずに済むかわからず悩んでいませんか。
結論からいうと、親の借金は相続放棄で回避できます。しかし、相続放棄は財産調査のうえで判断しないと損をする可能性もあるので、一度弁護士へ相談するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 相続放棄をすべきかどうか判断できる
- 相続放棄以外の方法に関してもアドバイスがもらえる
- 依頼した場合、借金を相続しないための手続きをサポートしてもらえる
ベンナビ相続では、相続放棄を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
親の借金を子どもが相続する義務はある?
亡くなった親に借金がある場合、何もしなければ子どもに引き継がれます。
では、親の借金を子どもが相続する義務はあるのでしょうか。
まずは相続する際の、親の借金の取り扱いについてみていきましょう。
親の借金は「相続人」が相続する義務がある
親の借金は「相続人」が相続する義務を負います。
日本の民法では、配偶者は常に相続人、子どもは第1順位の相続人として、相続財産を引き継ぐことになります。
ここでいう相続財産とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て含めたものを指します。
したがって、亡くなった親の借金は何もしなければ、配偶者やその子どもが相続人として引き継ぐのです。
亡くなった親が生前に負っていた借金の支払い義務は、相続人が相続することになります。
借金は「法定相続分」で分割される
亡くなった親の借金は、基本的に「法定相続分」で分割されます。
法定相続分とは、相続人の取り分を表す目安となる割合です。
複数の相続人がいる場合、この法定相続分をもとに借金が分割されることになります。
具体的な割合は、亡くなった親と相続人との続柄で決定されます。
たとえば、配偶者とふたりの子どもを持つ被相続人が、借金200万円を残して亡くなった場合を考えてみましょう。
この場合、法定相続分(配偶者:2分の1、子ども:4分の1ずつ)に基づいて、配偶者が100万円、子どもがそれぞれ50万円を相続し、借金の返済義務を負います。
なお、相続人全員の話し合いで合意した場合、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分ける必要はありません。
別の方法や割合で分割することもできるでしょう。
親の借金は相続放棄で回避できる
親の借金を相続したとしても、相続放棄することで借金の返済義務がなくなります。
ここでは、相続放棄とはどのような手続きなのか、詳しくみていきましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人としての立場そのものを放棄する法的な行為です(民法第939条)。
相続放棄をした相続人は、相続する権利を完全に失うため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も一切相続できなくなります。
相続放棄をすることで、相続人としての地位を失うため、親の借金を引き継ぐ義務を免れることができるのです。
相続放棄をしたら親の借金は誰が支払う?
では、相続放棄をした場合、親の借金は誰が支払うのでしょうか。
相続放棄をしたとしても、親の借金自体が消えるわけではありません。
借金自体はそのまま残り続け、返済義務は次順位の相続人に引き継がれることになります。
たとえば、父親が亡くなり、配偶者である妻と、長男、長女の3人が総額2,000万円の借金を相続したケースをみていきましょう。
法定相続分によって分けられた各相続人の借金は、以下のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 | 相続される借金額 |
|---|---|---|
| 妻(配偶者) | 2分の1 | 1,000万円 |
| 長男(子ども) | 4分の1 | 500万円 |
| 長女(子ども) | 4分の1 | 500万円 |
ここで、配偶者である妻が相続放棄をしたとしましょう。
すると、次順位の相続人に借金が引き継がれるため、ほかの相続人の借金の負担額が増えることになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 相続される借金額 |
|---|---|---|
| 妻(配偶者) | なし | なし |
| 長男(子ども) | 2分の1 | 1,000万円 |
| 長女(子ども) | 2分の1 | 1,000万円 |
このため、相続放棄することを次順位の相続人に事前に連絡しておかないと、トラブルになる可能性があるのです。
なお、相続人全員が相続放棄した場合は、父親の借金の連帯保証人になっていた方が借金の支払い義務を負います。
また、連帯保証人がいなかった場合には、裁判所によって相続財産管理人が選任され、プラスの財産を換金したうえで、債権者に借金を返済します。
親の借金を相続放棄した場合のデメリット
親の借金を相続放棄することには、借金を返済する義務がなくなるなどのメリットがある一方で、以下のようなデメリットが存在します。
プラスの財産も相続できなくなる
親からの遺産を相続する場合、借金などの負債だけではなく、預貯金や不動産などの資産を合わせて承継します。
その結果、負債を差し引いてもプラスの財産が残るケースがあります。
しかし、相続放棄をすると、相続人としての立場を失うため、このプラスの財産を受け取る権利も放棄することになります。
そのため、相続放棄を検討する際には、相続できる額から借金を引いた金額がプラスになる可能性があるかを十分に確認し、相続放棄の必要性を判断することが大切です。
ほかの相続人が借金を取り立てられる
相続放棄をすると、次順位の相続人に借金の相続権が移ります。
しかし、裁判所が次順位の相続人に相続放棄があったことを通知する仕組みはありません。
そのため、借金の取立てを受けて初めて、自分が借金の相続人になっていたことを知るケースもあります。
相続放棄をする前には、ほかの相続人に迷惑をかけないように、自分が相続放棄をする予定であることを、事前に相続人に伝えておくことが望ましいでしょう。
やり直しや撤回ができない
相続放棄は、一度手続きをおこなうと基本的にやり直しや撤回ができません。
そのため、相続放棄をしたあとに、高額な財産が見つかった場合でも、相続することはできず、資産の相続をあきらめるしかありません。
相続放棄を検討する際には、遺産をしっかりと調査し、本当に相続放棄すべきか慎重に判断することが重要です。
親の借金を相続放棄する手続きの流れ
親の借金を相続放棄する際の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 被相続人の財産を調査する
- 相続放棄に必要な書類を用意する
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 家庭裁判所から届く照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
では、手続きの各ステップについて詳しくみていきましょう。
1.被相続人の財産を調査する
相続放棄を検討する際には、はじめに被相続人の財産を調査します。
相続する財産はあるのか、またプラスの財産とマイナスの財産を差し引いて、その差額のどちらが多いかなどを把握します。
預貯金の通帳やクレジットカード会社から届いた督促状などを集め、財産の全体像を把握し、相続放棄するかどうかを慎重に判断しましょう。
2.相続放棄に必要な書類を用意する
被相続人の財産を調査した結果、相続放棄したほうがよいと判断した場合には、以下の書類を準備します。
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
- 被相続人の戸籍附票または住民票の除票
- 収入印紙(ひとり800円)
- 切手
なお、申立人と被相続人との関係により、必要書類が追加される場合があります。
自分にとって必要な書類がわからない場合は、家庭裁判所に確認するか、弁護士に相談するとよいでしょう。
3.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
必要書類が揃ったら、家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。
必要書類の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
なお、必要書類は、直接持参するほか、郵送で提出することも可能です。
4.家庭裁判所から届く照会書に回答する
相続放棄の申立てが受理されると、家庭裁判所から「照会書」という質問状が送付されます。
これは、相続放棄が本人の意思であることを確認するためのものです。
記載された質問に正直に回答し、速やかに家庭裁判所に返送しましょう。
5.相続放棄申述受理通知書を受け取る
照会書の回答に問題がなければ、相続放棄が承認されます。
承認されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されるため、受け取りましょう。
この通知書は、相続放棄の手続きが完了したことを知らせる重要な書類であり、債権者への相続放棄の証明などに使用できます。
通知書を受け取ることができたら、相続放棄の手続きは完了です。
親の借金を相続放棄できないケース
親の借金を相続放棄したくてもできないケースが存在します。
以下のいずれかに該当する場合には、相続放棄ができないため、注意しましょう。
法定単純承認が認められる
法定単純承認が認められた場合、親の借金を相続放棄できなくなります。
法定単純承認とは、相続人が相続財産を使用したり処分したりすると、相続放棄が認められなくなる制度です。
この制度は借金にも当てはまり、相続放棄の手続きが完了する前に、借金の一部を返済した場合に、単純承認が成立する可能性があります。
そのため、相続放棄の手続き中は借金の返済を断るとともに、相続財産には一切手を付けないよう注意しましょう。
熟慮期間を過ぎている
相続放棄の手続きには、相続の開始を知った日から3ヵ月の熟慮期間が設けられています。
この期間内に手続きをおこなわないと、相続人が単純承認したとみなされるため、相続放棄ができなくなります。
もし、3ヵ月以内に相続放棄の手続きを完了させることが難しい場合は、家庭裁判所に延長を申し立てることを忘れないようにしましょう。
親の借金を相続してしまった場合の対処法
相続放棄の期限を過ぎてしまったなど相続放棄できないケースに該当し、親の借金を相続してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
結論としては、債務整理を検討するのがおすすめです。
債務整理の種類によっては、借金を免除することができるからです。
債務整理には、以下の3つの方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
ここでは、上記それぞれの債務整理の方法について確認していきます。
1.任意整理|債権者と交渉し、利息分や遅延損害金をカットしてもらう
借金額が大きくないケースや返済期間を延ばしてもらえば完済できそうなケースでは、債務整理のなかでも任意整理がおすすめです。
任意整理は、借金返済について債権者と直接交渉します。
相続した借金について、利息をカットしてもらったり、返済期限を延長してもらったりすることで、返済計画を無理のないかたちに調整し、借金を返済していきます。
なお、任意整理は原則として、3年で返済できる支払い能力が必要です。
そのため、将来利息をカットしたり、月々の返済額が減ったとしても、3年程度で完済できないなら、任意整理は向いていないといえます。
ただし、任意整理は債権者との直接交渉であるため、債権者が認めれば、5年程度返済に時間をかけてもよいという契約に落ち着く場合もあります。
任意整理についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】任意整理とは?基本をわかりやすく解説
2.個人再生|裁判所から許可を得て、借金を減らしてもらう
個人再生は、裁判所を介して債務整理をする方法です。
再生計画を作成し、裁判所の認可を受けることで、借金額を5分の1〜10分の1程度に減額してもらえます。
大幅な減額となるため、相続してしまった借金が多額である場合も、返済できる可能性が高くなるでしょう。
任意整理と同様に、原則3年での返済を目指しますが、最長5年での分割返済が認められるケースもあります。
また、住宅ローン特則という制度を利用することで、持ち家を手放すことなく、借金を減額できるのもメリットです。
ただし、国が発行する機関紙である「官報」に氏名や住所が掲載されることには、注意しましょう。
個人再生についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】個人再生とは?基本をわかりやすく解説
3.自己破産|裁判所から許可を得て、借金を免除してもらう
自分の収入や資産では相続した借金を返せない場合、自己破産を検討します。
自己破産は、返済不能であることを裁判所に申立て、支払い義務を免除してもらう手続きです。
認められれば借金は原則、全額支払う必要がなくなります。
ただし、個人再生と同じく公的な手続きであるため、「官報」に氏名や住所が掲載されるほか、一定以上の価値ある財産が回収され、処分されます。
そして、処分された財産は、債権者への返済に充てられます。
なお、自己破産を申請したとしても、必ず借金が免除されるわけではないことに、注意しましょう。
自己破産についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】自己破産とは?基本をわかりやすく解説
親の借金を相続する際によくある質問
ここからは、親の借金の相続について、よくある質問に答えていきます。
親の借金の相続放棄は生前にできますか?
親の借金の相続放棄は生前におこなうことができません。
なぜなら、相続放棄は相続が発生して初めて効力を持つ行為であるからです。
このため、親が亡くなる前に相続放棄の意思を表明したとしても、法律上認められません。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
引用元:民法915条
したがって、生前に親の借金を整理したい場合には、債務整理を検討するなど借金の返済計画を見直すことを検討します。
亡くなった親の借金に時効はありますか?
亡くなった親の借金にも時効は存在します。
時効のカウントは最後に返済した日を起点として進行します。
具体的な時効期間は、以下のとおりです。
- 個人間の貸し借りによる借金:5年
- 商法上の借金(貸主または借主が商人の場合):5年
ただし、令和2年3月31日以前の貸し借りによる借金の時効期間は、10年です。
これらの期間が経過したうえで、時効援用という手続きをおこなう必要があります。
【関連記事】時効の援用とは?条件や手続きの流れを解説
親の借金に過払い金があった場合はどうなる?
親に借金があったとしても、過払い金が発生している場合は、お金が戻ってくる可能性があります。
過払い金とは、カード会社に支払った返済のうち、本来支払う必要がない金額のことです。
現在お金を貸す際には、利息制限法によって利率が制限されており、貸す金額に応じて15〜20%と決まっています。
しかし、以前は20%を超える利息を取っているカード会社が多くありました。
それらの会社は、改正前の出資法が定める上限金利29.2%を採用していたのです。
現在は法改正によって、出資法の上限金利も20%に引き下げられています。
旧出資法の金利が適用された借金の場合、適法な利率に基づいて借金を計算し直すと、支払い過ぎた利息が見つかる可能性があります。
このとき相続人には、過払い金として取り戻す権利があります。
過払い金を取り戻せる条件は、2010年6月17日以前に開始した借入であることと、最後に借入れや返済をした日から10年以内であること、さらに過払い金が請求できると知ってから5年以内です。
被相続人が、長年、借入と返済をくり返していた方であれば、過払い金が発生しているかもしれません。
亡くなった親に借金があっても、すぐに相続放棄を決めず、まずは過払い金がないか調査しましょう。
親の借金の連帯保証人になっている場合はどうなりますか?
親が借金をしていて、相続人である自分が連帯保証人となっていた場合は、相続放棄をしても連帯保証契約はなくなりません。
なぜなら、連帯保証契約は、お金を借りた方と保証人ではなく、お金を貸す債権者と保証人とが交わすものだからです。
本人が借りたお金を返せないときのために、代わりに返済を保証するのが連帯保証人です。
そのため、本人が亡くなった場合は、連帯保証人が返済します。
連帯債務を支払えない場合は、本記事で紹介した債務整理を検討しましょう。
親の借金を肩代わりしない方法はありますか?
親の借金を肩代わりしないためには、以下の3つの方法が有効です。
- 相続放棄
- 限定承認
- 団体信用生命保険の活用
相続放棄は全ての相続財産を引き継がない手続きです。
相続放棄をすることでプラスの資産やマイナスの負債を相続しないため、親の借金を肩代わりせずに済みます。
一方で、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
これは、借金はあるけど特定の財産を手放したくないときに有効です。
プラスの財産を確保しつつ、借金をプラスの財産で相殺することができるでしょう。
また、親の借金が住宅ローンのみであり、団体信用生命保険に加入していた場合、住宅ローンの残高が、完済されることがあります。
この保険は、住宅ローンの契約者が死亡したり高度障害を負った際に適用されるため、借金が相続人に引き継がれることがありません。
親が団信に加入していたかどうかを確認し、必要な書類を保険会社に提出し、手続きをおこないましょう。
さいごに|親の借金の相続で悩んだときは弁護士に相談を!
亡くなった親に多額の借金があることが発覚した場合、相続放棄すべきか迷う方は少なくありません。
相続放棄すべきか、ほかに方法がないか悩んだ際には、弁護士に相談するのがおすすめです。
相続問題に強い弁護士であれば、自身に最適な方法をアドバイスしてくれます。
納得のいく解決策が見つかるように、まずは無料相談を活用し弁護士に悩みを相談してみましょう。
相続の際に親の借金が見つかり、どうすれば借金を相続せずに済むかわからず悩んでいませんか。
結論からいうと、親の借金は相続放棄で回避できます。しかし、相続放棄は財産調査のうえで判断しないと損をする可能性もあるので、一度弁護士へ相談するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 相続放棄をすべきかどうか判断できる
- 相続放棄以外の方法に関してもアドバイスがもらえる
- 依頼した場合、借金を相続しないための手続きをサポートしてもらえる
ベンナビ相続では、相続放棄を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。