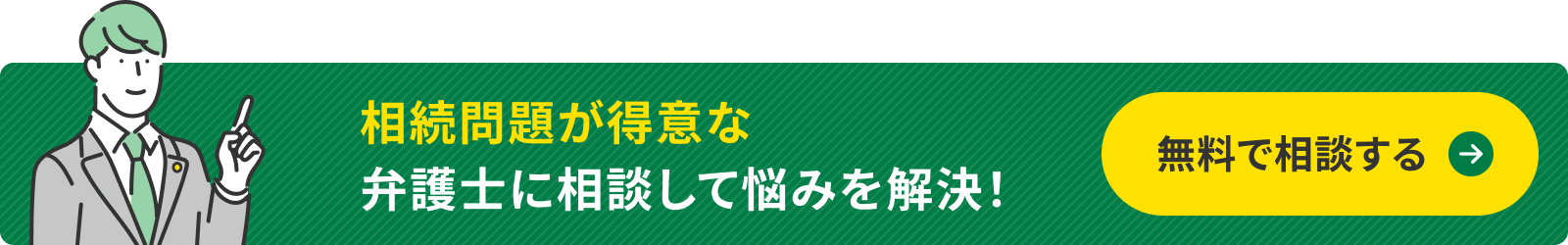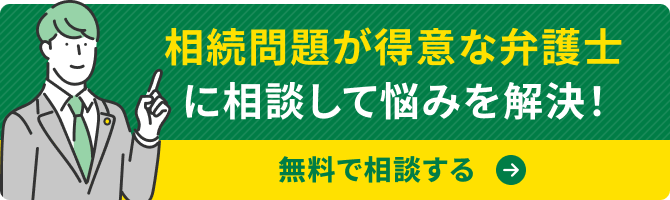相続が発生し遺産分割協議を始めたものの、被相続人の預貯金の遺産分割方法について疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
- 「預貯金はどのように分割すべき?」
- 「立て替えた葬儀費用分だけでも先に引き出してもいい?」
被相続人の預貯金は、以前は「可分債権」として遺産分割協議を経なくても、相続人であれば法定相続分に相当する金額を引き出せましたが、現在は遺産分割協議後でなければ引き出せません。
しかし、被相続人の葬儀や法要のために必要な費用を早く引き出せる預貯金の仮払い制度というものがあります。
本記事では、遺産分割における預貯金の分け方や、遺産分割前に預貯金を引き出す方法、預貯金を相続するまでの流れについて解説します。
これから預貯金の遺産分割をおこなうという方は、ぜひ参考にしてください。
遺産分割の対象に預金は含まれる
預貯金はほかの遺産と同じく、遺産分割協議のうえで相続すべき財産です。
以前は遺産分割の対象外となる「可分債権」とされ、法定相続分に相当する金額を各相続人が単独で受け取ることができました。
しかし、現在では遺産分割の対象となる財産として扱われ、遺産分割協議を経なければ受け取ることができません。
これは、平成28年に最高裁判所が預貯金を遺産分割の対象とする判決を下したことによるものです。
【参考元】平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件|平成28年12月19日 大法廷決定
このため、預貯金の相続人は原則として遺産分割協議を通じて、預貯金の分け方を調整する必要があるのです。
遺産分割における預貯金を分ける方法
遺産分割における預貯金の具体的な分け方について見ていきましょう。
預貯金の遺産分割では、以下のいずれかの方法で分けることが一般的です。
預金口座ごとに分割する
被相続人が複数の預金口座を持っていた場合の分割方法です。
各預金口座を相続人に割り当て、それぞれが口座名義を変更して相続します。
この方法は、特に遺産分割協議で決めた取り分と各口座の残高が一致している場合に適しています。
ただし、預金口座の残高が異なる場合には、不公平が生じやすく、相続トラブルの原因となる可能性があります。
そのため、預貯金以外の財産などを活用して、差額分を調整することが大切です。
預貯金を解約して分割する
預貯金を解約して分割する方法は、相続人のひとりが代表者として被相続人の預貯金口座を解約し、各相続人の預金口座に振り込むことで分割します。
たとえば、被相続人の預貯金口座に1,000万円があり、相続人Aと相続人Bがその預貯金を2分の1ずつ遺産分割するとします。
この場合、まずは相続人Aがこの預金口座を解約し、1,000万円を自身の口座に払い戻します。
そして、半分にあたる500万円を相続人Bの預金口座に振り込むことで分割を完了させます。
この方法は、遺産分割の割合を正確に反映できというメリットがあります。
ただし、手続きには相続人全員の同意書や必要書類をきちんと用意する必要があります。
代償分割をおこなう
代償分割とは、遺産分割をする際に、相続人のひとりが特定の財産を取得し、その差額に当たる金額を、ほかの相続人に支払うことで調整する方法です。
主に不動産の遺産分割で用いられますが、預貯金の遺産分割にも適用できます。
たとえば、被相続人の預貯金が3,000万円あり、相続人Aと相続人B、相続人Cがその預貯金をそれぞれ3分の1ずつ分割するとします。
この場合、まずは相続人Aが3,000万円全額を取得し、相続人Bと相続人Cにそれぞれ1,000万円ずつ現金を支払う形で調整します。
特に預貯金以外にも相続財産があり、不公平を解消したい場合に有効な方法です。
ただし、代償金を支払う相続人に十分な支払い能力が必要である点には、注意が必要です。
遺産分割によって預貯金が振り込まれるまでの流れ
相続発生から被相続人の預貯金が遺産として分割されるまでには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。
相続開始から、遺産である預貯金を各相続人が受け取るまでの流れを紹介します。
1.相続人と相続財産を確認する
はじめに、相続人と相続財産を確認します。
相続人については、被相続人の配偶者とそれ以外の法定相続人の範囲を明らかにします。
法定相続人の範囲は、以下のとおりです。
- 第一順位:被相続人の子ども
- 第二順位:被相続人の父母や祖父母
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹
順位が高いほど相続人として優先されます。
また、優先順位の相続人がいない場合には、次順位の方が相続人になります。
次に、相続財産を正確に把握するため、相続財産の調査をおこないます。
遺産分割の対象となる預貯金については、各金融機関に問い合わせて残高証明書を取得します。
また、通帳や取引明細なども確認し、把握できていない預貯金や未解約の定期預金がないか調べることも大切です。
遺言の有無についても合わせて確認するようにしましょう。
2.相続人全員で遺産分割協議をおこなう
預貯金口座の相続手続きをする際には、遺言書がない限り、遺産分割協議書の提示を求められます。
そのため、遺産分割協議を経て、遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。
遺産分割協議は、必ず相続人全員でおこないます。
ひとりでも欠けた状態で協議をしてしまうと、決まった分割内容があとで無効になる可能性があるためです。
しかし、遺産分割協議は必ずしも全員が一堂に会しておこなう必要はありません。
遠方に住んでいたり、病気などで移動が難しかったりして全員が集まれないなら、電話やメールで全員の合意を取り付けてもかまわないとされています。
また、相続人同士の仲が悪かったり、問題が起こったりして話がまとまらない場合は、早めに弁護士に相談するほうがよいでしょう。
弁護士が間に入ることで、早く合意にいたる可能性が高まるからです。
【関連記事】相続を弁護士に無料相談するには?注意点や司法書士・税理士との違いも解説
3.金融機関に提出する必要書類を集める
遺産分割の内容が定まったら、金融機関に提出するための書類を準備して、手続きを進めましょう。
なお、必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無や、各金融機関によって異なります。
それぞれの場合に必要となる主な書類は、以下のとおりです。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、以下の書類を準備しましょう。
- 遺言書
- 遺言の検認調書または検認済調書(公正証書遺言の場合は不要)
- 被相続人が死亡した旨を確認できる戸籍謄本、または除籍謄本
- 遺言執行者、または該当口座を相続する方の印鑑証明書
- (裁判所に遺言執行者として選任された場合)遺言執行者の選任審判謄本
遺言書はないが遺産分割協議書がある場合
遺言書が残されておらず、遺産分割協議によって遺産の分割方法を決定した場合は、主に次の書類が必要です。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本類
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑証明書
遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書がなく、法定相続分どおりに遺産を分割したために遺産分割協議書もない場合は、以下の書類を準備します。
- 各金融機関所定の書式
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本類
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑証明書
ただし、各金融機関所定の書式には相続人全員の署名・捺印が必要となるでしょう。
また、遺言書がなく、遺産分割協議をおこなったものの、協議がまとまらず家庭裁判所で解決した場合は、遺産分割協議書の代わりに以下の書類が必要です。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判事件となり、審判書に確定の旨の記載がない場合)
- 審判確定証明書
- 預金を相続する方の印鑑証明書
4.必要書類を提出し相続手続きをおこなう
必要書類が準備できたら、金融機関の窓口または指定された方法で相続手続きをおこないます。
必要書類を提出し、各相続人の口座への振り込みを依頼しましょう。
5.各相続人の口座に預貯金が振り込まれる
提出した書類に不備がなければ、数週間程度で各相続人の口座に分割された預貯金が振り込まれます。
ただし、書類の確認状況によってはさらに時間がかかる場合があります。
振り込みが確認できたら、預貯金の遺産分割手続きは終了です。
遺産分割前に預貯金を引き出す方法
「葬儀費用の立て替え分を早く返してほしい」「これまで被相続人名義の口座に保管されている預貯金で生活してきたため、引き出せなくて困っている」など、早急に払い戻してほしい事情がある場合には、仮払い制度を利用することで、遺産分割前でも預貯金を引き出せます。
預貯金の仮払い制度について詳しく知っておきましょう。
預貯金の仮払い制度
2019年7月1日より施行された改正相続法により、一定以下の金額であれば、相続人は、被相続人の預貯金口座から現金を引き出せるようになりました。
通常、被相続人が亡くなった旨を金融機関へ届け出ると、被相続人名義の口座は凍結されます。
そして、遺産分割協議後に相続手続きをしなければ、口座に残された現金を引き出せません。
しかし、仮払い制度を利用すれば、遺産分割前でも各相続人が現金を払い戻してもらえます。
この制度の利用には、以下のふたつの方法があります。
- 金融機関で直接払い戻しを求める方法
- 家庭裁判所の審判を得る方法
ただし、家庭裁判所の審判を得る方法が取れるのは、家庭裁判所で遺産分割調停や審判手続き中である場合に限られます。
また、どちらの方法で払い戻しを受けるとしても、多少の時間は要しますので注意しましょう。
【参考元】遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ|一般社団法人全国銀行協会
払い戻しの上限となる金額
払い戻しの上限金額は、選択する方法に応じて異なります。
家庭裁判所の審判を得る場合
家庭裁判所の審判による場合は、家庭裁判所が認めた金額であれば払い戻してもらえます。
具体的な金額は個々のケースに応じて異なります。
家庭裁判所が、仮払いが必要な事情を考慮し、ほかの相続人の利益を損なわない範囲で金額を決定するでしょう。
金融機関で直接払い戻しを求める場合
金融機関の場合、払い戻してもらえる金額の上限は、相続人の法定相続分に応じて異なります。
払い戻しの上限となる金額は、下記の計算式で算出します。
なお、金融機関一行あたりの払い戻し上限金額は、150万円です。
上記の計算式で算出した金額が150万円以上となっても、150万円までしか払い戻しはできません。
仮払い制度の申請に必要な書類
申請に必要な書類も、選択する方法に応じて異なります。
家庭裁判所の審判を得た場合
家庭裁判所の審判を得て申請する際は、以下の書類の提出が必要です。
- 審判書謄本
- 請求者の印鑑証明書
審判書謄本は、家庭裁判所で交付申請をして発行してもらいます。
交付申請書式は、下記のページからダウンロード可能です。
【参考元】家事事件の各種書類交付申請等 | 裁判所
金融機関で直接払い戻しを求める場合
金融機関に直接払い戻しを申請する場合は、下記の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本類
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 請求者の印鑑証明書
ただし、金融機関によっては必要な書類が異なることもあります。
事前に確認のうえ手続きを進めるほうがよいでしょう。
遺産分割で預貯金を相続するときの注意点
預貯金の相続手続きを進める際には注意点もあります。
困った事態に陥ったり、トラブルが起こったりするのを避けるためにも、ぜひ知っておきましょう。
口座の凍結前に預貯金を引き出さない
被相続人の死亡を届け出る前に預貯金を引き出してはいけません。
被相続人の遺産を勝手に使ったり、処分したりすれば「単純承認」をしたとみなされてしまうためです。
相続の方法には、以下の三つの方法があり、単純承認とはこのうちのひとつの方法です。
- 単純承認:プラスもマイナスも含めた全ての遺産を相続する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する
- 相続放棄:プラスもマイナスも含めた全ての遺産の相続を放棄する
単純承認をしたとみなされれば、ほかの相続方法を選択できません。
相続放棄や限定承認をすべき状況であっても、選択できずにあとから困る可能性もあります。
被相続人が亡くなったら、まずは必ず金融機関にその旨の届け出をおこない、口座が凍結する前に引き出さないように気を付けましょう。
遺産分割協議の内容は文書にして保管する
遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書に記載して残しておきましょう。
遺産分割協議だけでも十分に相続人同士のトラブルを防止するのに役立ちますが、可能であれば、話し合いの内容についても文書にしておくのがおすすめです。
誰がどのような理由を主張して、その遺産を相続することになったのかなど、話し合いの要点を文書で残しておけば、万が一相続に関するトラブルが起こった際の証拠になります。
文書の作成が大変であれば、話し合いを録音して保管しておくのも効果的です。
相続手続きは早めにおこなう
預貯金の相続手続きに期限はありませんが、可能な限り早めにおこなうのが望ましいところです。
特に相続税の納付が必要なケースでは、速やかに手続きすることをおすすめします。
というのも、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内におこなわなくてはならないからです。
相続税の納付までに金融機関での相続手続きが間に合わなければ、十分なお金が手元にないために大変な思いをすることもあるでしょう。
また、高齢であったり病気を患っていたりする相続人がいる場合も注意が必要です。
万が一、相続手続きが完了していないときに、ほかの相続人が亡くなってしまえば、その相続人の相続分についても、さらなる相続手続きが生じます。
非常に複雑で手間のかかる事態になりかねません。
そのため、預貯金の相続手続きには期限がないものの、できるだけ早期におこなうべきなのです。
まとめ
今回は遺産分割における預貯金の分け方や、遺産分割前の引き出し方法、相続するまでの手続きの流れについてご紹介しました。
預貯金は遺産分割の対象となる財産であり、相続人が勝手に引き出せるものではありません。
遺言書があるなら遺言書の内容どおりに、遺言書がないなら遺産分割協議を経てその分割方法を相続人全員で決定します。
思わぬトラブルを引き起こさないためにも、必ず流れに準じて相続手続きを進めましょう。
また、遺産分割や相続について不明点があったり、問題が起こったりしたら、相続問題に強い弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、問題が大きくならずに早期解決できる可能性が高まるからです。
初回無料で相談に応じてくれる法律事務所もありますので、気軽に利用してみるとよいでしょう。