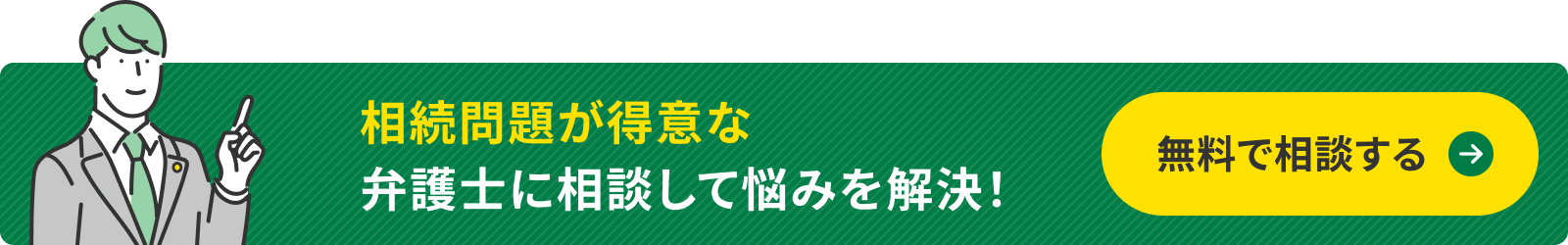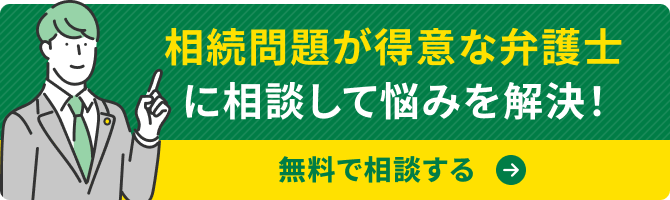遺産相続などの場面で、時効取得に関して以下のような疑問や不安がある方もいるでしょう。
- 「時効取得ってなに?」
- 「不動産を時効取得できる可能性があるが、要件や手続き方法がわからない」
- 「時効取得はどうしたら成立するのか知りたい」
時効取得が成立すると、不動産などの長年占有してきたものの所有権を取得できます。
ただし、時効取得の要件は複雑なうえにいくつかの注意点があり、単に長く占有していればよいというわけではありません。
本記事では、時効取得の成立要件や手続きの流れ、よくあるトラブルの対処法や時効取得をする際の注意点などについて解説します。
本記事を読むことで、時効取得の手続きを進めるためにどうするべきかが理解できます。
相続した土地の時効取得をしたいけど、自分のケースは時効取得できるのかどうかわからず、悩んでいませんか。
結論からいうと、時効取得できるかどうか判断できないときは、弁護士に相談することをおすすめします。
時効取得の要件は複雑な問題が絡むため、法的観点からのアドバイスを得ることが、問題解決につながるでしょう。
弁護士の無料相談を利用することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 自分の状況で不動産の時効取得の要件を満たしているのかがわかる
- 手続きを弁護士に依頼すべきか判断できる
- 時効取得で注意すべき点をアドバイスしてもらえる
当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
時効取得とは
時効取得とは、他人の物を一定期間占有した場合、要件を満たすことで時効により自分の物にできるという制度です。
民法では、時効取得について以下のように定められています。
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ここでは、時効取得という制度の目的や時効制度の基礎知識などを解説します。
時効には取得時効と消滅時効の2種類がある
時効とは「事実状態と法律関係を合わせるための制度」であり、以下の2種類に分類されます。
- 取得時効:ある状態が一定期間継続した場合、権利の取得が認められる制度
- 消滅時効:権利未行使の状態が一定期間継続した場合、権利の消滅が認められる制度
たとえば「境界線があいまいな土地を長期間使っていた」「無権原者から買い取った土地を長期間占有していた」というようなケースでは、時効取得が成立して所有権を得られる可能性があります。
時効取得が定められている理由
時効取得は、もともとの所有者にとっては酷な制度にも見えますが、他人の所有物を奪うことを認める制度ではありません。
時効取得は、主に以下のような事情から存在するといわれています。
- 長期間にわたって実質的に所有していた事実を尊重するため
- 「長期間にわたって権利を主張していない者を保護する価値はない」と考えられるため
- 所有権を主張するのが実質的に困難な状態を救済するため
時効取得できる権利・できない権利
時効取得は全ての権利が対象になるわけではありません。
以下では、時効取得できる権利・できない権利について解説します。
時効取得できる権利
時効取得できる権利は多岐にわたり、具体的には以下のような権利が挙げられます。
- 所有権:物を自由に使用・収益・処分できる権利
- 地上権:工作物(建物など)・竹木を所有するために他人の土地を使用する権利
- 地役権:自身が所有する土地の利便性を高めるために他人の土地を使用する権利
- 永小作権:耕作・牧畜のために、小作料を支払って他人の土地を使用する権利
- 賃借権:他人の物を有償で借り、使用・収益する権利
時効取得できない権利
一方、以下のような権利については時効取得が認められません。
- 留置権:関連する債権の弁済を受けるまで対象物を留置できる(返さずにおくことができる)権利
- 先取特権:対象財産の競売などにより、ほかの債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利
- 質権:債権の担保として受け取った物を占有し、弁済されない場合に売却して代金を弁済に充当できる権利
- 抵当権:被担保債権が弁済されない場合に、不動産を競売できる権利
そのほか、1回の行使で権利が消滅する債権・取消権・解除権なども時効取得の対象外です。
時効取得の要件
時効取得が認められるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 所有の意思をもって占有を開始したこと
- 平穏かつ公然と占有を開始したこと
- 一定期間占有していること
各要件のポイントを詳しく確認していきましょう。
1.所有の意思をもって占有を開始したこと
1つ目の要件は「それが自分のものである」という所有の意思をもって占有を開始したことです。
所有の意思をもっておこなう占有のことを「自主占有」、所有の意思がない占有は「他主占有」と呼び、自主占有と他主占有のどちらにあたるかは、占有取得原因事実(売買や賃借など)の性質に従い、外形的・客観的に判断されます。
たとえば、売買・贈与・交換などによって占有を開始した場合は、一般的にその物を所有する意思があると考えられるため自主占有にあたります。
一方、たとえばマンションの賃貸借によって占有を開始した場合は、他人から借りている状態に過ぎないため所有の意思を持たない他主占有にあたります。
いくら本人が所有しているつもりであっても、賃貸借関係にあることが契約上明らかなので自主占有にはあたりません。
もし「所有の意思をもって占有を開始した」といえるかどうか判断できない場合は、弁護士に相談してアドバイスを求めることをおすすめします。
2.平穏かつ公然と占有を開始したこと
時効取得するための2つ目の要件は「平穏かつ公然と占有を開始したこと」です。
平穏とは暴力的な手段を用いていないこと、公然とは実際の権利者に占有の事実を隠していないことを指します。
たとえば、暴行や脅迫によって所有者から占有を奪った場合は時効取得の対象外です。
また、所有者からの問い合わせに対して占有の事実を認めなかった場合は公然な占有とはいえません。
3.一定期間占有していること
時効取得が認められるための3つ目の要件は「一定期間占有していること」です。
途切れることなく継続して占有していなければならない、という点にも注意してください。
なお、時効取得の成立に必要な占有期間は状況によって異なります。
詳しくは後述しますが、善意無過失の場合は10年、悪意または過失がある場合は20年です。
取得時効の完成にかかる期間
ここでは、時効取得における占有期間の考え方を解説します。
状況によって占有期間は大きく異なるため、ポイントをしっかりと押さえておきましょう。
占有者が善意無過失の場合|10年
占有者が善意無過失の場合、時効取得の成立に必要な占有期間は10年です。
善意とは「占有物が他人の物だと知らなかったこと」、無過失とは「他人の物だと知らなかったことに関して注意義務違反がない状態」を指します。
過失の有無は、占有取得時の状況を総合的に考慮して判断されます。
たとえば、以下にあてはまる場合は、占有者側の過失が認められて10年間の占有による時効取得が成立しない可能性が高いです。
- 登記簿を調査しなかった
- 前主の説明を鵜呑みにして図面などを確認しなかった
- 取引の相手方の代理権に関して委任状などを確認しなかった
- 取引の相手方が制限行為能力者であることを確認しなかった など
占有者に悪意または過失がある場合|20年
占有者側に悪意または過失がある場合、時効取得の成立に必要な占有期間は20年です。
悪意とは「占有物が他人の物だと知っていたこと」、過失とは「他人の物だと知らなかったことに関して注意義務違反がある状態」を指します。
占有対象が農地の場合は原則として有過失となる
占有の対象が農地の場合、原則として有過失となるという点には注意しておきましょう。
農地を占有するには農業委員会の許可を得る必要があり、その過程で他人の物であるということが明らかになります。
他人の物であることを知らない場合は法的手続きを怠っているということになり、過失があると判断されてしまうのです。
つまり、農地の所有権を現時点で持っていないにもかかわらず占有している場合、特段の事情がない限り有過失と判断され、時効取得するためには20年以上の占有を要する可能性が高いです。
時効取得の具体例
ここでは、時効取得できる可能性があるケースとして代表的なものを3つ紹介します。
自分の場合は時効取得が可能かを判断する際の参考にしてください。
境界線があいまいな土地を長期間使っていた場合
境界線があいまいな土地を長期間使っていた場合は、境界部分の土地を時効取得できることがあります。
たとえば「隣地との境界線と思われる場所に塀を設置し、長い年月が経過している」というようなケースです。
この場合、要件を満たせば塀の敷地について時効取得が成立し、土地の境界線を有利な形で画定できる可能性があります。
登記されていない土地を相続し、長期間占有していた場合
2つ目は「被相続人が所有していた土地の登記が前主のままになっている状態で、その土地を相続した」というようなケースです。
この場合、相続人は登記簿上の所有者に対して、被相続人が土地を所有していた事実(売買契約に基づく所有権の取得など)と相続による所有権の取得を証明して所有権移転登記を求めるのが原則ですが、被相続人による所有の事実を証明するのが難しいこともあります。
もし時効取得の要件を満たしていれば、被相続人の所有権を証明することなく、相続人が自らの所有権を主張して所有権移転登記を請求することが可能です。
無権原者から買い取った土地を長期間占有していた場合
「無権原者(=所有者でない人)から買い取った土地を長い間占有していた」というような場合も時効取得できる可能性があります。
たとえば「本来の所有者はAで、BはAから土地を借りていただけにもかかわらずCに売却した」というケースで考えてみましょう。
この場合、本来であればBには土地の所有権がないため、仮にCが買い取っても所有権を取得することはできません。
しかし、Cは売買によって土地を占有したわけですから、所有の意思をもって占有を開始しています。
そのため、平穏・公然などの要件を満たし、かつ10年または20年の時効期間が経過すれば、Cはその土地を時効取得できます。
時効取得の手続きの流れ
ここでは、不動産を時効取得する際の基本的な手続きの流れを解説します。
1.土地の名義人を確認する
土地を時効取得する場合、名義人を確認して権利関係を明らかにしておく必要があります。
詳しくは登記簿謄本に記載されているので法務局で取得しましょう。
2.時効取得の要件を満たしているか確認する
「時効取得の要件」で解説した要件を満たしているかどうかの確認も必要です。
自分では正確に判断できない場合は、相続問題が得意な弁護士に相談しましょう。
事務所によっては初回相談無料のところもあるので、費用が気になる方も安心して利用できます。
3.所有者(登録名義人)に対して取得時効の援用をする
次に、所有者に対して取得時効の援用をおこないましょう。
援用とは、時効の完成による利益を享受する旨を所有者に伝えることです。
具体的な方法は決められていませんが、援用した事実を証拠として残すためにも、内容証明郵便で通知することをおすすめします。
必要に応じて所有権移転登記請求訴訟などを提起する
相手方が時効の援用に対して反論してきた場合の対処法としては、所有権移転登記請求訴訟などを提起することが考えられます。
この場合、裁判手続きを通じて取得時効の成否を争うことになります。
訴訟によって対象物の所有権が争われる場合は、裁判所に提出する書面(訴状・答弁書・準備書面など)によって時効を援用することも可能です。
4.所有権移転登記手続きをおこなう
時効取得が成立した場合は、速やかに所有権移転登記手続きを進めましょう。
時効完成後、売買などにより不動産を譲り受けた第三者が所有権移転登記を先に得ると、所有権を失ってしまうため注意してください。
なお、所有権移転登記手続では、当事者双方の意思を確認するために、権利を失う者(前所有者)と得る者(現所有者)が共同でおこなうのが原則とされています。
ただし、訴訟において登記手続を命じる旨の判決が下された場合は、現所有者単独での手続きも可能です。
時効取得でよくあるトラブルと対処法
ここでは、時効取得でよくあるトラブルと対処法について解説します。
占有期間中に所有者や占有者が変わった
「占有期間中に所有者や占有者が変わった」というようなケースでは、変わったタイミングが時効完成前か完成後かによって扱いが異なります。
このようなケースでは、権利関係が複雑になり当事者同士では解決が長引くおそれがあるため、相続問題が得意な弁護士にサポートしてもらいましょう。
相手が時効取得の手続きに応じてくれない
相手によっては、時効取得の手続きに協力してくれずに難航することもあります。
このようなケースでは、訴訟の提起・処分禁止の仮処分命令の申立てを検討しましょう。
処分禁止の仮処分命令がおこなわれた場合、相手は他者に不動産の売却・譲渡などができなくなります。
裁判では登記簿謄本や売買契約書などの証拠を用いて主張を展開することになりますが、ある程度の法律知識なども必要になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
時効取得を阻止された
時効については「時効の更新」「時効の完成猶予」などの制度があり、これらが適用された場合は時効の成立が長引きます。
たとえば「元の所有者側に所有権があることを認めた場合」や「占有が途切れた場合」などは時効の更新となり、振り出しに戻って一から時効期間が開始することになります。
これらの時効制度や時効成立のタイミングなどについて自力では判断が難しい場合も、相続トラブルに注力する弁護士に一度相談してみましょう。
不動産の時効取得をするなら弁護士に相談するのがおすすめ!
不動産の時効取得を検討しているなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
「時効取得の要件を満たしているかどうか」についてはさまざまな問題も絡むため、自分だけでは判断するのが難しい場合も少なくありません。
弁護士に時効取得が可能か適切に判断してもらい、今後の対応についてアドバイスを受けるとよいでしょう。
また、弁護士であれば時効取得で必要な手続きを一任でき、相手方との交渉や裁判手続きも任せられるため安心です。
なお、弁護士を探す際は「不動産などの相続トラブルの解決実績が豊富かどうか」を確認するようにしましょう。
十分な知識と経験のある弁護士であれば、個々の状況に合った最善の解決策を提案してくれるはずです。
全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ相続」では、時効取得に関する問題解決が得意な弁護士を地域別で探せます。
無料相談や電話相談などに対応している弁護士も多数登録されているので、ぜひ活用してください。
時効取得に関して知っておくべき注意点
ここでは、時効取得に関して知っておくべき注意点を解説します。
占有の事実と無過失は占有者側が立証する必要がある
訴訟で時効取得の成否を争う場合、占有者は以下の事実を立証しなければなりません。
- 占有開始時において無過失であったこと(10年間の時効取得を主張する場合)
- 占有開始時と現在の2点において占有していること
まず、占有期間10年での時効取得を主張する場合は、占有開始時における無過失を立証しなければなりません。
占有者が無過失を立証できない場合は、時効取得の成立に20年の占有期間が必要となるため注意してください。
また、占有開始の事実と10年または20年経過時における占有の事実も、占有者側が立証する責任を負います。
この2点における占有が立証できれば、その間は占有が継続されていたものと推定されます。
なお、所有の意思・平穏・公然・善意の要件については法律上推定されるため、否認する側が立証責任を負います。
したがって、時効取得を主張する側がこれらの要件を立証する必要はありません。
登録免許税や不動産取得税などの税金が課される
不動産を時効取得する際は、登録免許税や不動産取得税が課されます。
登録免許税は、不動産を登記する際にかかる税金のことです。
所有権移転登記をおこなう場合は、不動産の固定資産税評価額の2%にあたる登録免許税が課されます。
不動産取得税とは、有償・無償にかかわらず不動産を取得するだけで課せられる税金のことです。
不動産取得税の金額は、固定資産税評価額の4%(2024年3月31日までに時効取得した土地の場合は3%)となります。
不動産の価値によっては、時効取得することで大きな金銭的負担が生じる可能性もあるため注意しておきましょう。
不動産の課税価額に応じて所得税や住民税も課される
不動産を時効取得すると、不動産の評価額に応じて所得税や住民税などが課されます。
これは、時効取得によって経済的利益が生じたものとみなされるためです。
時効によって不動産を取得した年は、確定申告の手続きを忘れずにおこなうようにしましょう。
時効取得に関するよくある質問
最後に、時効取得に関するよくある質問について解説します。
同様の疑問を抱えている方はぜひ参考にしてみてください。
時効取得は難しい?
時効取得については、まず要件を満たしているかどうか確認する必要があるうえ、必要書類を集めたり訴訟などの対応が必要になったりすることもあります。
知識や経験のない素人では適切に対応できないおそれがあるため、ミスなく済ませたいのであれば弁護士などのサポートを受けたほうがよいでしょう。
時効取得にはどれくらいの期間がかかる?
時効取得の成立に必要な期間は状況によって異なり、占有者が善意無過失の場合は10年、悪意または過失がある場合は20年です。
占有の承継とはどのような制度?
占有の承継とは、物の占有状態を別の人物に引き継ぐことです。
たとえば「不動産Xを所有者でないAが5年間占有し、そのあとAから不動産Xを譲り受けたBが5年間占有した」とします。
この場合、Bだけの占有期間は5年間ですが、Aの占有期間と合わせて10年間の占有期間を主張することができます。
民法では、以下のように定められています。
(占有の承継)
第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ただし、占有期間を合算する場合は、前の占有者の瑕疵も引き継いでしまうという点には注意が必要です。
たとえ自分は善意無過失であっても、前の占有者に悪意や過失があった場合は、時効取得の成立に必要な占有期間が10年から20年に伸びてしまいます。
前の占有者に瑕疵がある場合などでは、自身の占有期間のみ主張したほうが有利なこともあるということを覚えておきましょう。
相手方が登記を備えていたらどうなる?
相手方が登記を備えていた場合、時効取得に基づく不動産の所有権移転登記手続を請求できるかどうかは、相手方の立場や登記を備えたタイミングなどによって異なります。
相手方が前の所有者だった場合は、登記を備えていたとしても、時効取得に基づく所有権移転登記手続が請求可能です。
また、相手方が前の所有者から目的物を譲り受けて登記を備えた場合でも、登記を備えたのが時効完成前であれば、時効取得に基づく所有権移転登記手続を請求できます。
一方、相手方が登記を備えたのが時効完成後である場合は、相手方が確定的に所有権を取得するため、所有権移転登記手続は請求できません。
不法占拠でも時効取得は成立する?
不法占拠の場合であっても、時効取得が成立する可能性はあります。
不法占拠かどうかにかかわらず、長期間にわたって占有してきたという事実は尊重されるべきと考えられるためです。
もちろん、時効取得を成立させるためには、上述した要件を全て満たしている必要があります。
不法占拠にあたって暴力的な行為に及んだり、所有者に占有していることを隠したりしている場合は、時効取得を主張することができません。
賃貸アパート・マンションは時効取得できる?
賃貸アパート・マンションを時効取得することはできません。
賃貸借契約は、あくまでも建物を借りるための契約です。
賃借人に所有の意思があるとは認められないため、これらの建物の時効取得は成立しません。
相続財産である不動産を占有した場合に時効取得は成立する?
ほかの相続人がいるケースにおいて、相続財産に含まれる不動産を占有した場合、時効取得は原則として成立しません。
被相続人が亡くなった時点で、不動産はほかの相続人との共有状態となります。
遺産分割協議によって所有者が決定しないまま相続人の1人がその不動産を占有しても、原則として時効取得は認められません。
その相続人はほかの相続人がいることを通常知っており、自己の共有持分権に基づき占有しているに過ぎないためです。
すなわち、所有の意思が認められないため時効取得は成立しません。
ただし、以下のようなケースでは、その相続人に所有の意思が認められて時効取得が成立する可能性があります。
- 「自分が単独で相続した」と信じて疑うことがない状態だった
- 不動産をその相続人だけで管理し、不動産による利益もその相続人が1人で得ていた
- 被相続人の死後、実質的にずっとその相続人が占有していた
- 不動産に関わる税金を、全てその相続人が支払っていた
- 不動産を占有していることについて、ほかの相続人が反対したり干渉したりすることがなかった など
土地や建物の抵当権はどのように扱われる?
時効取得が成立すると、土地や建物に設定されている抵当権は消滅します。
時効取得者は、対象物の完全な所有権を原始的に取得するためです。
さいごに|時効取得に関する悩みは弁護士に相談しよう
時効取得とは「所有者以外が不動産などを長期間にわたって占有した場合、要件を満たすと占有者が所有権を取得できる」という制度です。
ただし、不動産の時効取得は要件が難しく、専門家のアドバイスなしでは判断が難しいというケースも少なくありません。
要件を満たしていないにもかかわらず時効取得を主張すると、トラブルに発展する可能性もあります。
弁護士であれば、時効取得の要件を満たしているかを正確に判断してくれて、どのような証拠を集めればよいかなどのアドバイスを得ることも可能です。
なるべく早めに弁護士へ相談して、スムーズに手続きを進めましょう。