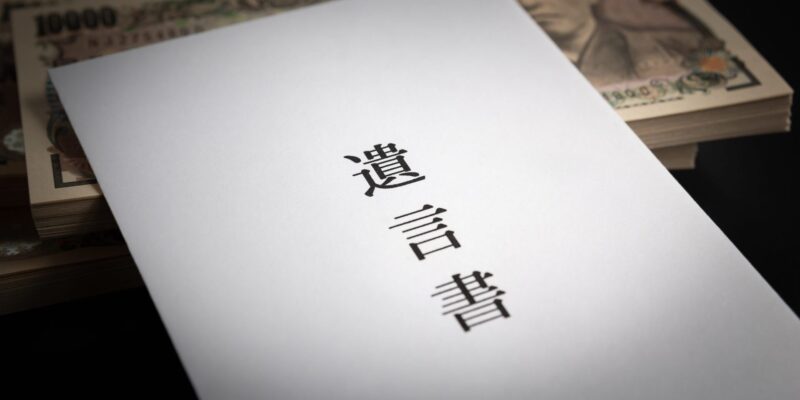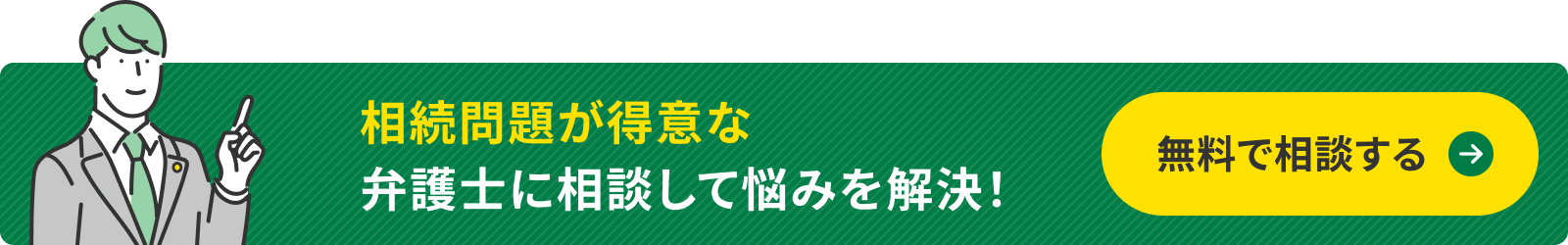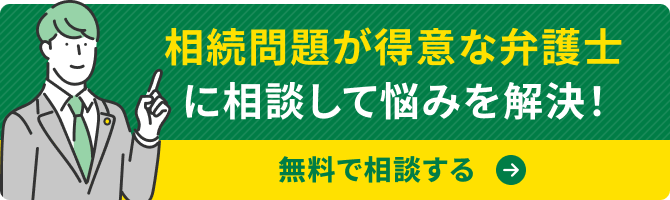- 「介護をしてくれた娘に全ての財産を相続させたい」
- 「長男には過去に裏切られた経験があるので遺産を渡したくない」
さまざまな事情があり、特定の人物に偏った遺産相続を希望する人も少なくありません。
しかし、各相続人には遺留分と呼ばれる最低限の取り分があります。
いくら被相続人が希望したところで、遺留分を侵害するような遺産相続をおこなうことは基本的に認められません。
そのため、特定の相続人に対して遺留分さえも渡したくないと考えているのであれば、特別な対応が必要です。
本記事では、特定の相続人に遺留分を渡したくないときにとるべき方法について解説します。
遺留分は非常に強い権利であるため、基本的に権利者の意思に反して奪うことは難しいです。
本記事では、遺留分を減らす方法についても紹介するので、参考にしてみてください。
自分の遺産を全て息子や娘に相続するために、別の相続人に遺留分を渡さない方法がないかと悩んでいるの方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、特定の相続人以外には遺留分を渡したくないなら、弁護士への相談をおすすめします。
なぜなら、遺留分を渡さないというのは、法的にかなり難易度が高いため、プロのサポートが必要になる可能性が高いからです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 遺産分を渡さないための方法を教えてもらえる
- 法的な観点から的確なアドバイスをもらえる
- 遺留分放棄の交渉についての注意点を教えてもらえる
- 遺留分を渡したくない相続人に対して、本気度が伝わる
当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
遺留分を渡さなくていいケースはあるが基本的には難しい
遺産相続において、遺留分を渡さなくていいケースは実際に存在します。
しかし、遺留分を渡さなくていいような状況を意図的に作り出すのは、簡単ではありません。
遺留分は法律で定められた権利であり、被相続人がいくら希望したところで、自由に奪うことはできないからです。
相続人自らが受け取りを拒否している場合や、そもそも相続人としての資格が認められない場合など、特定の条件下でのみ、遺留分を渡さなくて済む可能性があります。
遺留分を渡したくないときに取るべき5つの方法
以下の方法であれば、遺留分の分与を回避できる可能性があります。
- 相続人自身に遺留分を放棄してもらう
- 相続人自身に相続放棄してもらう
- 特定の相続人に対して相続人の廃除を申し立てる
- 相続欠格に該当するかどうかを確認する
- 遺言書に「遺留分を渡したくない」旨を記載しておく
いずれの方法も簡単ではありませんが、どうしても遺留分を渡したくない事情がある場合は試してみる価値があるでしょう。
1.相続人自身に遺留分を放棄してもらう
相続開始前に、相続人本人から家庭裁判所に遺留分放棄の申立てをしてもらうことができれば、確実に遺留分を渡さずに済みます。
ただし、遺留分の放棄が認められるには、主に以下の要件を満たしていなければなりません。
- 遺留分放棄が申立人の意思に基づいている
- 遺留分放棄が必要的かつ合理的である
- 放棄に見合う代償を獲得できているか
被相続人やほかの相続人からの圧力によって不本意に申立てをおこなう人も少なくないので、遺留分放棄の妥当性については裁判所で厳格に判断されます。
もちろん、生前における遺留分放棄の申立ては、相続人本人にしかできません。
遺留分を放棄してほしいのであれば、本人が自分の意思で申立てするように説得する必要があります。
2.相続人自身に相続放棄してもらう
遺留分を渡したくないときは、相続人自身に相続放棄してもらうのもひとつの方法といえます。
相続放棄とは、相続人として遺産を相続する権利を放棄する手続きです。
相続放棄した相続人は、はじめから相続権を失っている状態になるため、当然遺留分を受け取る権利も認められません。
しかし、一般的に相続放棄は、借金などのマイナスの財産が大きい場合に選択されます。
遺産相続によって相続人が得をするケースで、相続放棄してもらうことは難しいかもしれません。
3.特定の相続人に対して相続人の廃除を申し立てる
家庭裁判所に対する「相続人廃除」の申立てが認められれば、遺留分を含めた財産を渡さなくて済みます。
相続廃除とは、相続人としての資格を奪う手続きのことです。
相続廃除となった相続人は、遺産相続自体ができなくなるため、遺留分を渡す必要もありません。
ただし、相続廃除が認められるのは、以下のようなケースに該当しているときだけです。
- 特定の相続人から、被相続人に対する虐待があった
- 特定の相続人から、被相続人に対する重大な侮辱行為があった
- 特定の相続人に著しい非行があった
単に「気に食わない」「もともと性格が合わなかった」などという理由で、相続廃除が認められることはありません。
なお、相続廃除した人物に子どもがいる場合は、子どもに相続権が移る「代襲相続」が発生するため、少なくとも遺留分は渡すことになります。
4.相続欠格に該当するかどうかを確認する
遺産を手に入れるために悪質な行為をし、民法第891条に定められた相続欠格事由に該当すると、相続欠格が適用されます。
相続欠格とは、相続人の資格の喪失を意味し、同時に遺留分を請求する権利も失います。
相続欠格は法律で定められた制度で、被相続人の意思表示や特別な手続きは必要ありません。
ただし、相続欠格となるのは、相続人の廃除以上に限られたケースのみです。
- 被相続人やほかの相続人を殺害した、もしくは殺害しようとしたことで刑事罰を受けた
- 被相続人が殺されたことを知っていて告発・告訴しなかった
- 遺言を改ざん・破棄・隠ぺいした
- 詐欺や強迫によって遺言の取り消しや変更を妨害した
- 詐欺や強迫によって遺言の取り消しや変更をさせた
なお、相続欠格でも代襲相続は発生するため、子どもがいる場合は遺留分を受け取る権利も引き継がれます。
5.遺言書に「遺留分を渡したくない」旨を記載しておく
遺言書に「遺留分を渡したくない」旨を記載しておくのも、ひとつの方法です。
法的な効力は発生しませんが、強い意志をみせることはできるので、相続人が相続放棄などに踏み切ってくれるかもしれません。
生前の対策次第で遺留分を減らすこともできる
遺産相続において遺留分を渡さないことは高いハードルがあり、実現できる可能性は低いといえます。
しかし、生前の対策次第で遺留分を減らすことはできます。
主に3つの方法が考えられるので、詳しく見ていきましょう。
1.ほかの人物に生前贈与して遺産自体を減らす
各相続人の遺留分は、遺産総額によって決まります。
そのため、ほかの人物に生前贈与して遺産総額を減らせば、結果的に遺留分を減少させることが可能です。
ただし、以下の要件を満たす生前贈与は遺留分侵害額請求の対象となり、実質的に遺留分は変わらないことになるので注意してください。
- 相続開始前1年間で法定相続人以外に対しておこなわれた生前贈与
- 相続開始前10年以内に法定相続人に対しておこなわれた生前贈与
生前贈与による遺留分の減額を狙うのであれば、計画的に準備しておくことが大切です。
2.金融資産を生命保険に変えて遺産自体を減らす
遺留分を減らしたいのであれば、金融資産を生命保険に変えることも検討してみてください。
生命保険の保険金は受取人固有の財産であり、相続財産からは除かれます。
そのため、金融資産を生命保険に変えることで、遺産総額を減らし、遺留分も減少させることができるのです。
3.養子縁組で相続人の数を増やす
養子縁組で相続人の数を増やせば、遺留分を減少させることができます。
遺産相続において、養子は実子と同等の立場であり、遺留分を受け取る権利も有しています。
つまり、養子縁組により遺留分権利者が増えることになれば、一人当たりの遺留分が減少するわけです。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人だった場合、遺留分はそれぞれ4分の1ずつです。
しかし、養子が相続人に加わることで、実子と養子の遺留分は2等分され、8分の1ずつになります。
ほかの相続人から遺留分侵害額請求されたときの対処方法
ほかの相続人から遺留分侵害額請求されたときは、まず、請求してきた人物が遺留分権利者であるかどうかを確認しましょう。
遺留分権利者となる相続人は、主に配偶者・子・父母です。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けても、応じる必要はありません。
また、請求内容が正しいかどうかも必ずチェックしてください。
遺留分の計算は複雑になるケースも多いので、請求に対して安易に応じてはいけません。
自分で算出するのが難しい場合には、相続問題が得意な弁護士に相談してみましょう。
最後に|遺留分対策にお困りの方はぜひ弁護士に相談を
遺留分は遺言でも奪えない強い権利です。
そのなかで、特定の相続人に遺留分を渡さない方法としては、以下の5つが考えられます。
- 遺留分を放棄してもらう
- 相続放棄してもらう
- 相続人の廃除を申し立てる
- 相続欠格を適用する
- 遺言書を利用する
とはいえ、いずれの方法をとっても、遺留分を渡さないようにすることには高いハードルがあります。
強引に進めようとすると、余計なトラブルに発展する可能性もあるので十分注意しておきましょう。
遺留分を渡したく相続人がいるなど、遺留分の対策に困っているのなら、ぜひ弁護士に相談してください。
弁護士であれば、遺留分放棄についてだけでなく、その後の遺産分割や相続税の対応など、相続手続きに関することを全て任せられるでしょう。
自分の遺産を全て息子や娘に相続するために、別の相続人に遺留分を渡さない方法がないかと悩んでいるの方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、特定の相続人以外には遺留分を渡したくないなら、弁護士への相談をおすすめします。
なぜなら、遺留分を渡さないというのは、法的にかなり難易度が高いため、プロのサポートが必要になる可能性が高いからです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 遺産分を渡さないための方法を教えてもらえる
- 法的な観点から的確なアドバイスをもらえる
- 遺留分放棄の交渉についての注意点を教えてもらえる
- 遺留分を渡したくない相続人に対して、本気度が伝わる
当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。