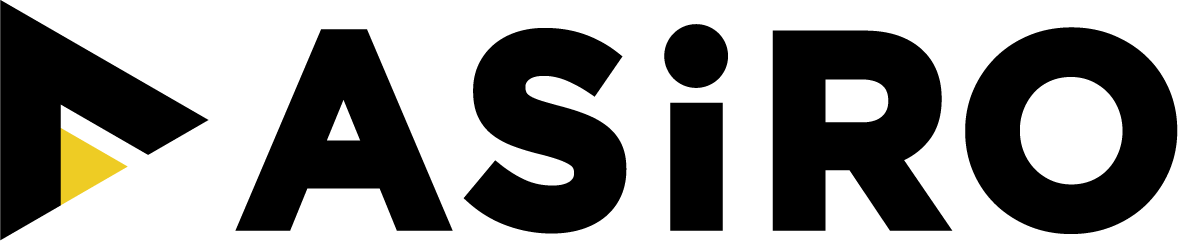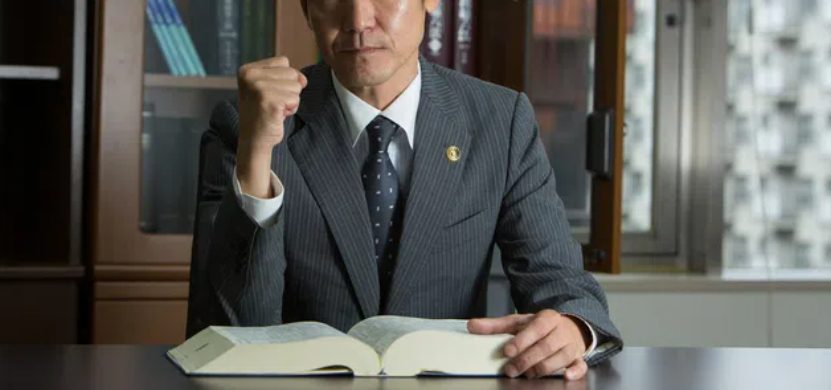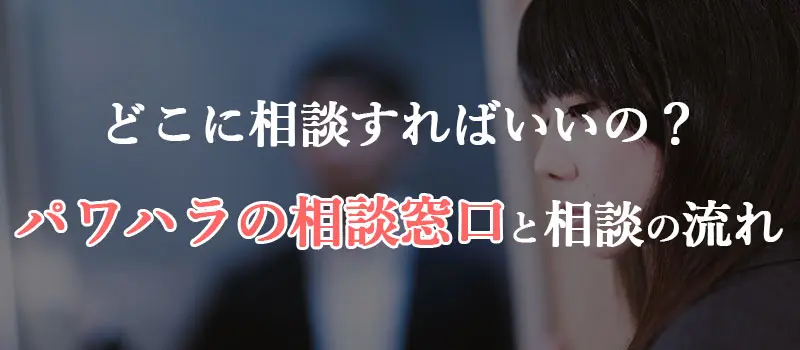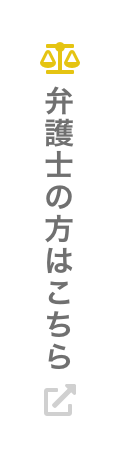職場で受けたパワハラは、退職後に訴えることが可能です。
精神的に苦痛を受けてうつ病などになると生活もままなりません。
泣き寝入りをしないためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、パワハラを弁護士に相談するメリットや相談後の流れ、パワハラで訴える際にかかる費用、慰謝料の相場などについて解説します。
職場で受けたパワハラ被害を、退職後に訴えたいと考える方はいるかもしれません。
しかし、退職後にパワハラ被害を訴えるとなると、退職前と比べ、パワハラの証拠が集めにくく請求が難しくなります。
そのため、パワハラ被害に対応する弁護士には、ハラスメントの解決実績が豊富にあるのに加え、お悩みの問題についてさまざまな方向性からアドバイスができる知識をもっていることが求められます。
以下リンクから、パワハラ被害を含めた労働問題の対応実績が豊富な法律事務所・弁護士を探してみましょう。
初回相談が無料の弁護士事務所も掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
パワハラ・セクハラについて弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
退職後でもパワハラは訴えることができる!ただし時効に注意
在籍時に受けたパワハラは、退職後に訴えることができます。
ひどいパワハラによってうつ病などになることもあるうえ、精神疾患は時間が経ってから発症することも少なくありません。
退職後であっても、労災で治療費の補償を受けられるケースもあります。
ただし、訴える際には時効に注意しましょう。
パワハラ被害に対し、民事裁判の「不法行為に基づく損害賠償請求」という訴えを適用する場合、時効は被害者が「損害および加害者を知ったときから3年以内、かつ不法行為の時から20年以内」とされています。
時効の期間は損害の内容によって異なる点にも注意が必要です。
「不法行為に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」という訴えを起こす場合は、「損害および加害者を知ったときから5年以内、かつ不法行為の時から20年以内」とされています。
【参考】法務省|2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります
退職後にパワハラを訴えたい場合は弁護士に相談するのがおすすめ
パワハラで会社や加害者を訴えたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
ここでは、弁護士に相談するメリットや相談・依頼後の流れなどについて見ていきましょう。
弁護士に相談するメリットは?
パワハラを弁護士に相談するメリットは、ハラスメントの代理交渉を行ってもらえる点です。
弁護士はハラスメントの「差止要求書」というものを作成し、会社と交渉します。
パワハラは、本人が会社に相談しても取り合ってもらえないというケースが少なくありません。
弁護士が介入することで、会社側も真剣に交渉に取り組むことが期待できます。
また、パワハラを行った相手と直接交渉するのは、精神的にも大きな負担となるでしょう。
交渉を弁護士に任せることで、負担が軽減できる点もメリットです。
交渉がスムーズにいかない場合は裁判になることもあるため、早い段階から裁判の実績がある弁護士に相談しておくと安心。
また、そもそも被害がハラスメントにあたるかの判断も難しいため、弁護士に相談して適切な対応を提案してもらうこともできます。
弁護士の中には、無料相談や電話相談を受け付けているところもあるので、一度相談してみるのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼してからの流れは?
ここでは、弁護士に相談のうえ、問題解決のサポートを依頼をした後の流れについて解説します。
弁護士を通して会社へ交渉する
まずは、弁護士を通して会社へ交渉します。
交渉のみで和解となれば、この時点で和解金が支払われる可能性も。
会社を訴えるとなればより費用もかかるので、和解できれば負担も少なくて済みます。
ただし、会社側が交渉に応じない、和解に至らないという場合は次のステップへ進むことが必要です。
労働審判手続きを申し立てる
交渉によって会社と和解ができなかった場合は、「労働審判手続き」を申し立てます。
労働審判手続きとは、パワハラや残業代未払いなどを含む労働問題について、労働審判委員会を通じて解決を目指す制度のことです。
平成18年から始まった制度で、労働審判員が審理を行います。
申し立て後、労働審判員が3日以内に審理して調停を試み、調停が成立しない場合は審判が下されるという流れです。
ただし、一般的な訴訟とは異なり、当事者が異議申し立てをした場合には審判は失効となり訴訟へと移ります。
審判の結果は裁判の和解と同等の効力があるため、当事者の異議申し立てがなく審判が確定した場合は、会社側が決定内容に応じなければ強制執行を申し立てることが可能です。
一般的な訴訟は解決までに1年近くかかることが多い一方、労働審判手続きは2か月程度で終了するケースが多く見られます。
解決しなければ裁判所に訴状を提出する
交渉や労働審判で解決しない場合は、裁判所へ訴状を提出し、民事訴訟へと進んで裁判を起こします。
民事訴訟は判決が出るまでに1年以上かかる場合もあり、その分費用がかさむ傾向にあります。
また、第一審の判決に納得できない時は控訴することも可能ですが、さらに判決までの期間が延びる点に注意しましょう。
長期戦になるとお金と労力がかかるため、その点をしっかりと理解しておく必要があります。
原則として、訴訟は訴える相手の現住所がある裁判所で行うとされていますが、なかには例外もあります。
不法行為に基づく損害賠償で訴えを起こすケースでは、実際に不法行為が行われた土地を管轄する裁判所へ訴状を出すことも可能です。
例えば、支店での勤務中にパワハラ被害を受けた場合、本社のある所在地の裁判所ではなく、支店所在地管轄の裁判所へ訴状を提出できます。
弁護士への相談や訴えるために必要な準備
ここでは、弁護士に相談する際や会社を訴える際に必要な準備について解説します。
証拠を集める
まずは、パワハラを受けたことを証明するために証拠を集める必要があります。
交渉や訴訟の際、証拠がないと慰謝料の請求が難しくなってしまうので、退職前に残しておいた証拠をできる限り集めましょう。
ボイスレコーダーによる録音やメールの文章は有効な証拠となり、スマートフォンで録音した音源も有効です。
パワハラが原因で病院にかかった場合は、医師に診断書を書いてもらいましょう。
うつ病などの精神疾患だけでなく、ストレスによる胃潰瘍など体の症状についても同様です。
他には、パワハラの状況を記した日記やメモ書き、理不尽な転勤や異動を命じられた際の通達、同僚の証言なども貴重な証拠となります。
メモ書きの場合は、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことを言われた(された)」「自分がその行為に対してどう思ったか」などを記録しておくと有利になるでしょう。
在籍中から遡って状況を時系列で経緯を整理する
パワハラを受けた会社に在籍していたときのことを思い出して、具体的な状況を時系列で整理することも必要です。
パワハラの状況を思い出すのは辛い作業ですが、弁護士や裁判所など第三者に状況を詳しく説明する必要があります。
在籍中にどのようなパワハラを受けたのか、退職に至るまでの経緯、退職後の生活に影響していることなどを整理してまとめておきましょう。
内容をわかりやすく簡潔にまとめ、なるべく感情は強く出さずに事実を伝えることを意識すると信憑性が高くなります。
被害を受けた人が、加害者やパワハラの様子などを具体的に立証できるかが重要です。
集めた証拠を活用しながら、時系列で状況整理することをおすすめします。
また、パワハラのトラウマで現在の生活がままならない、通院をしているなど、退職後に生じている不都合についてもしっかりと伝えましょう。
自分がどうしたいのか希望を整理する
弁護士へ相談する際には、自分がどうしたいのかも整理する必要があります。
交渉や訴訟となるとつい手段を優先して考えがちですが、まずは「自分がどうしたいのか」「状況がどのように変われば楽になるのか」を考えることが重要です。
自分の希望や目的が定まったら、それに向けた解決の具体的手段を考えることができます。
できれば和解で済ませたい、会社を訴えたいなど解決方法はさまざまです。
慰謝料はどれくらい取りたいかなどもあわせて考えておきましょう。
弁護士に相談することで、自分にとって最良の解決策を見つけることができます。
パワハラの被害を訴えるときにかかる費用

パワハラで訴訟を起こす際にかかる費用には主に、「弁護士費用」と「訴訟にかかる手数料」の2つがあります。
ここでは、それぞれについて解説します。
弁護士費用
弁護士費用には、相談料や着手金、成功報酬、実費などが含まれます。
相談料の相場は30分5,000円〜1万円程度とする法律事務所が多く、なかには相談無料とするところも少なくありません。
実際に会って相談するまで事務所や弁護士の対応はわからないので、相談無料のところを選ぶのもよいでしょう。
着手金とは実際に弁護士に依頼する時にかかる費用で、訴訟の勝ち負けにかかわらず支払うものです。
相場は訴訟請求額の8%程度ですが、事務所によっては着手金ゼロ円を謳っていたり、あらかじめ固定金額を設定したりしているところもあります。
成功報酬とは、訴訟に勝った際や相談者の満足のいく結果になった場合に支払う費用です。
相場は訴訟請求額の15〜20%程度。
その他には、手続きに必要となる切手代や印紙代などを含む実費、弁護士が移動する場合の交通費、宿泊費、日当なども必要です。
着手金ゼロ円であっても成功報酬が高く設定されている場合もあるので、トータルの費用を把握しておくことが重要です。
パワハラ問題解決のサポートを弁護士に依頼する費用の相場は、トータルで50〜100万円程度と考えておくといいでしょう。
訴訟にかかる手数料
訴訟を起こす場合は、裁判所に手数料を支払う必要があります。
手数料は損害賠償の請求額に応じて変わります。
訴訟額 | 手数料 |
| 100万円以内 | 訴訟額10万円ごとに+1,000円 |
| 100〜500万円 | 10,000円+100万円から訴訟額20万円ごとに2,000円ずつ追加 |
| 500〜1,000万円 | 30,000円+500万円から訴訟額50万円ごとに2,000円ずつ追加 |
| 1,000万円〜10億円 | 50,000円+1,00万円から訴訟額100万円ごとに3,000円ずつ追加 |
訴訟で600万円の損害賠償を請求する場合、手数料は30,000円+(2,000円×2)=34,000円となります。
裁判所のサイトには手数料が一覧になった早見表が掲載されているので、確認してみてください。
【参考】裁判所|手数料額早見表
パワハラに対して請求できる慰謝料の相場
パワハラに対して請求できる慰謝料の相場は、50〜100万円程度です。
パワハラに対する慰謝料は決して高いとはいえませんが、被害の内容や期間などによっても変動するため、あくまで目安として捉えておいてください。
〈実際に慰謝料が支払われた事例〉
消費者金融の従業員3名が上司からパワハラを受けたとして訴訟を起こした案件です。
パワハラの内容は、扇風機が不要な時期に風を当て続けたこと、殴打や蹴るなどの暴力行為、「給料をもらいながら仕事をしていませんでした」と理不尽な始末書を書かせたことなど。
裁判の結果、被害者の3名に対し60万円、40万円、10万円の慰謝料の支払いが命じられました。
パワハラにおける慰謝料の金額は、「加害者の立場」「被害の悪質性」「パワハラの期間」などの要素によっても変動します。
上司など職場の地位を利用して嫌がらせを行った、暴行や脅迫などの悪質行為があった、パワハラをどれくらいの期間受けたかなどもポイントとなります。
また、加害者の数やパワハラに対する会社の対応、パワハラによってうつ病になった、退職に追い込まれたなどの実害も争点となるでしょう。
【関連記事】パワハラの訴訟実例と勝訴・慰謝料請求する3つのポイント
まとめ
本記事では、以下の内容について解説しました。
- 退職後にパワハラで訴える場合は時効に注意が必要
- パワハラ問題は弁護士に相談するのがおすすめ
- パワハラで訴える際に必要な費用
- パワハラで請求できる慰謝料の相場
パワハラを受けた会社を退職した後でも、時効がきていなければ訴えることは可能です。
辞めた後も苦しんでいる、どうしても許せないという人は、これからの人生を明るく生きていくためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
職場で受けたパワハラ被害を、退職後に訴えたいと考える方はいるかもしれません。
しかし、退職後にパワハラ被害を訴えるとなると、退職前と比べ、パワハラの証拠が集めにくく請求が難しくなります。
そのため、パワハラ被害に対応する弁護士には、ハラスメントの解決実績が豊富にあるのに加え、お悩みの問題についてさまざまな方向性からアドバイスができる知識をもっていることが求められます。
以下リンクから、パワハラ被害を含めた労働問題の対応実績が豊富な法律事務所・弁護士を探してみましょう。
初回相談が無料の弁護士事務所も掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
パワハラ・セクハラについて弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |