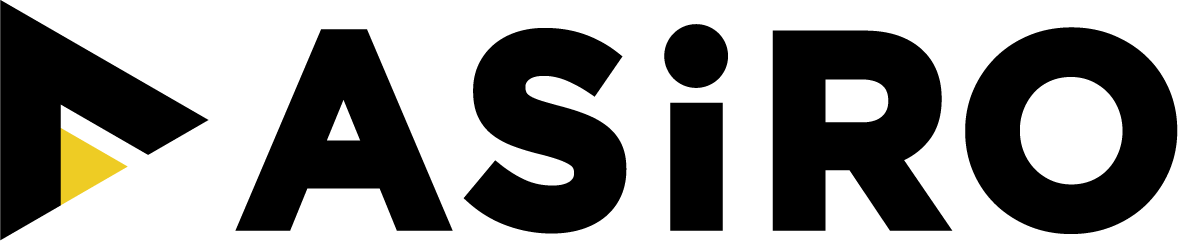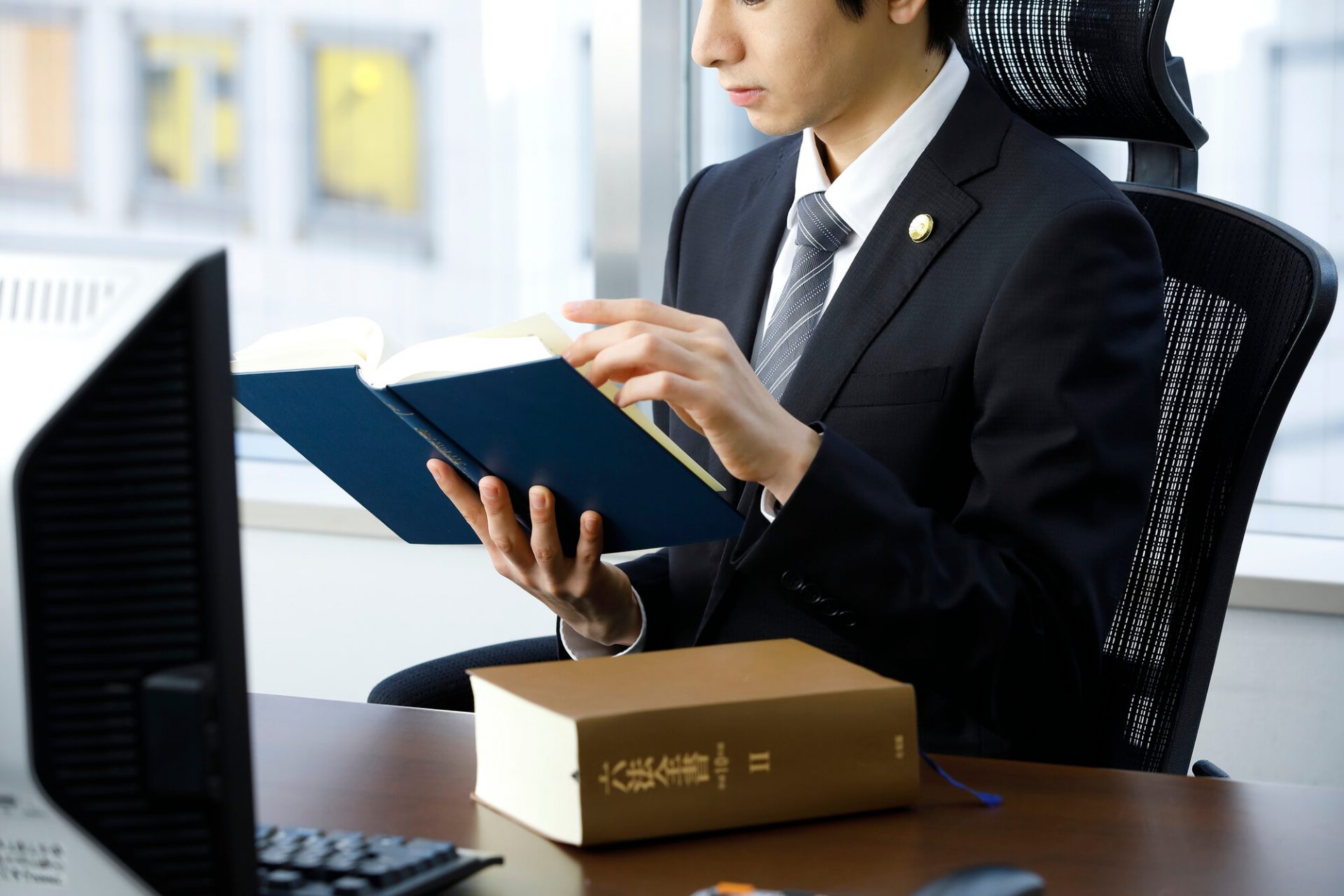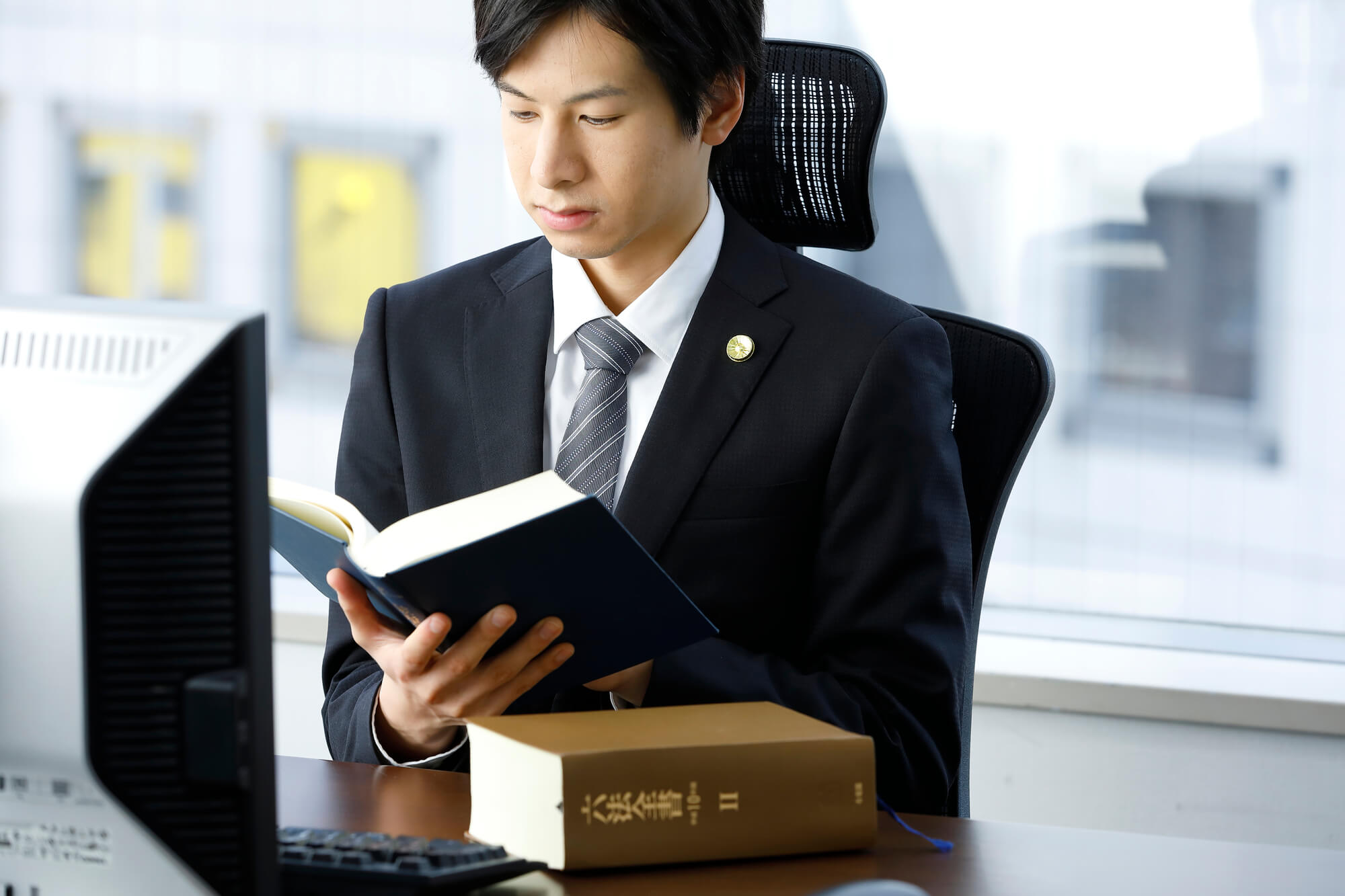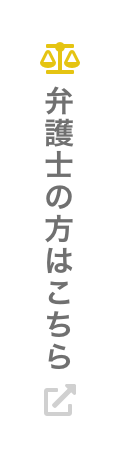労働問題のトラブルが当事者間で解決しない場合は、労働審判も選択肢に入れる必要があります。
しかし、そもそも労働審判とはなにか、どのようなメリットがあるのかなど、具体的なイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、労働審判の流れや期間、費用を徹底解説します。
労働審判を利用するにあたって知っておくべき注意点なども紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
労働審判は、原則として3回を期日としています。短い期間で自分の主張を認めてもらうには、申し立ての段階から十分な準備をして、充実した申し立て書と必要な証拠を裁判所に提出することが重要になってきます。
また相手の反論に対して論理的かつ客観的な証拠に基づいて回答する必要があるので、裁判所も弁護士に依頼する事を推奨しております。
【参考】労働審判手続 | 裁判所
弁護士なら、審判や訴訟だけではない解決策も豊富に持っているので、自分の悩みの解決に労働審判が適しているのかもわかります。
労働審判を検討中の方は、まずは下記から労働問題が得意な弁護士に相談してみることをおすすめします。
労働審判とは|労働審判委員会が労働問題の判断をする手続き
労働審判とは、労働審判委員会が労働問題の判断をおこなう手続きのことです。
労働者と会社の間に労働審判官1名と労働審判委員2名の3名で構成される労働審判委員会が介入し、双方の意見を聞きながら解決を図ります。
話し合いで問題が解決できた場合は調停が成立し、労働審判もそこで終了となります。
しかし、調停が不成立となった場合は、労働審判委員会が審判を下します。
なお、審判に対し2週間以内に異議申し立てがおこなわれると、通常の訴訟に移行してしまうことも覚えておきましょう。
労働審判の事件件数|2022年の新規受付数は3,208件
2022年における労働審判の新規受付数は3,208件にのぼります。
内訳としては、賃金手当などの金銭を目的とするものが約1,700件、解雇などの金銭を目的とする以外のものが約1,500件です。
労働トラブルは私生活にも大きな影響を与えるため、労働審判制度による迅速な問題解決を望む人が多いものと推察されます。
労働審判の終局区分|調停成立が2,272件で最も多い
労働審判の終局区分として最も多いのは調停成立で、その数2,272件におよびます。
2番目に多いのは労働委員会が審判を下す労働審判で544件、その次が取り下げで258件です。
労働審判を利用すれば、労働者と会社との和解によって問題を解決できる可能性が高いといえます。
労働審判の4つの特徴|ほかの労働トラブルの解決手段との違い
ここからは、労働審判の4つの特徴を解説します。
まずは、ほかの解決手段との違いを理解しておきましょう。
【労働トラブルを解決するための手段】
| 解決手段の種類 | 手続きの特徴 |
| 労働審判 | 裁判官と専門家の仲介のもと、原則3回以内の審理で話し合いによる解決を図り、最終的には審判が下される |
| 少額訴訟 | 原則1回の審理で判決が下される訴訟手続きで、60万円以下の支払いを求める場合にのみ利用可能 |
| 民事調停 | 調停主任(裁判官または調停官)と一般国民から選出された調停委員の立会いのもと、話し合いによる解決を図る |
| 民事訴訟 | 厳格な手続きのもとで互いの主張を出し合い、裁判官の判決によって解決を図る |
| 個別労働紛争解決制度(助言・指導、あっせん) | 弁護士や大学教授など、労働問題の専門家が公平・中立の立場で仲介し、具体的なあっせん案を提示 |
労働トラブルの内容によって、とるべき方法は異なります。
労働審判もあくまで選択肢のひとつであり、必ずしも労働審判による解決が正しいとは限りません。
原則として3回以内の期日で審理が終結する
原則3回以内の期日で審理が終結する点は、労働審判の大きな特徴といえるでしょう。
迅速に手続きを進めていくために、労働審判法では以下のように定められています。
(迅速な手続)
第十五条 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
引用元:労働審判法|e-Gov法令検索
通常の訴訟で争うと、審理を終えるまでに1年以上を要するケースもあります。
一方、労働審判は2ヵ月~3ヵ月程度で終結することが一般的です。
トラブルの内容によっても審理期間は変動しますが、1回目で終了することも珍しくありません。
早ければ1ヵ月程度、長くても6ヵ月程度とされており、迅速にトラブルの解決を図ることができます。
労働問題に精通する労働審判員が参加する
労働審判には、裁判官だけでなく、労働問題に精通している労働審判員が参加します。
これは、専門的な知識と経験によって、トラブルの迅速かつ適切な解決を図るためです。
具体的には、労働者や使用者の立場で労働紛争の処理に携わった経験を有する人物などが選ばれます。
労働審判員はあらかじめ最高裁判所が任命しており、個別の事案ごとに割り振りがおこなわれる仕組みです。
労働審判委員会とは口頭でやり取りする
労働審判における労働審判委員会とのやりとりは、口頭でおこなわれます。
通常の訴訟であれば、文書によって意見を主張するケースが一般的です。
しかし、労働審判では、審理の場で事前に提出した書類をもとに、労働審判委員会からの質問に答えるかたちで話し合いが進められる場合が多いです。
事情に応じた柔軟な審判がおこなわれる
事情に応じた柔軟な審判がおこなわれる点も、労働審判の特徴です。
労働審判では当事者間の権利関係などを踏まえ、問題解決に必要な事項を臨機応変に定めることが認められています。
そのため、主張が正しいかどうかの判断だけでなく、個別具体的な解決策を求めることも可能です。
たとえば、金銭の支払いに関しても、支払い方法や支払い期限の条件を細かく決めたうえで問題の解決を図れます。
労働審判の対象となる労働トラブルの事例と基礎知識
労働審判の対象となる労働トラブルの事例として、次のようなケースがあります。
- 残業代の未払い
- 不当解雇
- 労働災害
- ハラスメント
それぞれの事例を詳しく解説するので、ご自身の状況と一致するものはないかチェックしてみてください。
残業代の未払い
残業代の未払いは、労働審判の対象となる労働トラブルのひとつです。
残業代の未払いには労働時間が過少に計算されていたり、労働基準法から逸脱したルールで残業代が支給されていたりと、さまざまなケースが存在します。
そして、未払い分の支払いを求めたにもかかわらず、会社側が応じようとせず、トラブルに発展することも珍しくありません。
残業した事実を示せるタイムカードや違法な就業規定などの証拠があれば、労働審判によって残業代の支払い請求が認められる可能性は高いといえます。
不当解雇
不当解雇も、労働審判の対象となる労働トラブルのひとつです。
労働者の解雇に関しては、労働契約法で以下のように定められています。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法|e-Gov法令検索
会社都合で労働者を一方的に解雇することは、基本的に認められません。
しかし、中にはなにかしらの理由をつけて不当に解雇を迫ってくる会社も実在します。
不動解雇にあった場合は解雇自体を無効にし、復職や解雇期間中の賃金を求めるためにも、労働審判の活用を検討してみてください。
労働災害
労働審判の対象となる労働トラブルには、労働災害も挙げられるでしょう。
業務中や通勤中の事故などで傷病を負ったり、死亡したりした場合は労働災害として扱われます。
労働災害が認められると労災保険による給付を受けられますが、実際の損害に比べて補償額が十分ではないケースも少なくありません。
不足額に関しては会社側に対して請求するのが一般的ですが、請求に応じてもらえないこともあるでしょう。
その際も、労働審判を利用すれば損害賠償請求を迅速に進めることができます。
ハラスメント
職場でハラスメントの被害を受けた場合も、労働審判を利用できる可能性があります。
労働者をセクハラやパワハラ、モラハラなどから守ることは会社の義務です。
ハラスメントの事実がわかった時点で話し合いの場を設けたり、加害者の社員に処分を下したりといった対応が求められます。
しかし、被害を受けて対処を求めたにもかかわらず、会社に行動を起こしてもらえないケースも珍しくありません。
当事者間での解決が難しいと判断した場合は、労働審判で損害賠償請求などを進めることも検討しましょう。
労働者が労働審判を利用する3つのメリット
次に、労働審判を利用する3つのメリットを紹介します。
労働審判の基礎知識ともいえる内容なので、実際に利用する前にしっかりと把握しておきましょう。
少ない負担で労働トラブルを解決できる
労働審判を利用すれば、少ない負担で労働トラブルを解決できます。
労働審判の手数料は比較的安価であり、解決までの時間も短く済ませられることがほとんどです。
詳しくは後述しますが、労働審判にかかる手数料は通常の訴訟の半分以下に設定されています。
取り扱う内容によって金額は変動するものの、一般的には3万5,000円以内に収まるため、金銭的な負担も少なく済むでしょう。
また、労働審判でおこなわれる審理は、原則3回までです。
もちろん個々の事案によって差はありますが、3ヵ月程度あれば多くの問題は解決すると考えられます。
問題が長期化すると精神的な負担も無視できなくなるので、迅速な解決を期待できる点は労働審判に大きなメリットといえるでしょう。
労働審判委員会による客観的な判断が得られる
労働審判を利用するメリットのひとつが、労働審判委員会による客観的な判断が得られることです。
労働問題に関しては会社側と労働者側のそれぞれに言い分があるため、当事者間の話し合いでは解決できないケースも珍しくありません。
自己の利益を主張しあうなかで、さらなるトラブルに発展してしまうこともあるでしょう。
一方、労働審判では公平・中立の立場にある労働審判委員会が介入し、和解を進め、最終的に審判を下します。
当事者の主張を客観的に判断してもらえるため、会社側に明らかな違法行為がある場合は、労働者側に有利な結果を得られる可能性が高いといえるでしょう。
労働審判の内容次第では強制執行をおこなえる
労働審判の内容次第では、強制執行をおこなえることもメリットのひとつに挙げられるでしょう。
労働審判委員会が下す労働審判は、異議申し立てがなければ確定し、和解と同様の効力を持ちます。
よって、相手が審判に従わない場合は強制執行の手続きを選択することも可能です。
たとえば、未払い分の残業代を支払うよう命じられたにもかかわらず、会社側が応じようとしなければ預金口座の差し押さえなども実行できる可能性があります。
労働者が労働審判を利用する4つのデメリット
次に、労働審判を利用する4つのデメリットを解説します。
メリット・デメリットの両方を理解したうえで、労働審判に踏み切るかどうかを判断しましょう。
妥当ではない審判が出される可能性がある
労働審判を利用しても、妥当ではない審判が出される可能性はあるので注意が必要です。
労働審判は、一般的な訴訟と比べて手続きが簡略化されていることもあり、十分な検討がおこなわれないリスクをはらんでいます。
通常の裁判では、長期間にわたって互いの意見を主張し合うのが基本です。
証拠を集め、取捨選択する時間にも余裕があり、裁判所も主張や証拠が出そろったうえで慎重に判断していくことになります。
一方、労働審判では原則として1回目までに当事者の主張は全て出し尽くさなければなりません。
あとから主張したいことが見つかっても、手遅れになる可能性があります。
また、裁判所が各主張の適否を見極めるための時間も短いため、妥当とはいえない審判が下されることも想定されるでしょう。
労働基準法上の付加金が認められない可能性が高い
労働基準法上の付加金が認められにくいことも、労働審判を利用するデメリットのひとつです。
会社に対して未払いの賃金を請求する場合などは、本来支払われるべきだった金額に付加金を上乗せできます。
しかし、労働審判では通常の裁判と比べて、付加金の加算を認めない傾向にあるので注意が必要です。
付加金の加算によって、できるだけ多くの金額を請求したい場合は、労働審判ではなく通常の裁判で争うほうが望ましいといえます。
証人尋問などの複雑な手続きをおこなうことができない
労働審判では、証人尋問などの複雑な手続きをおこなうことはできません。
通常の裁判では、それぞれの主張を裏付けるために、当事者や関係者を呼んで尋問をおこないます。
一方、労働審判においては、証人尋問自体が禁止されているわけではないものの、迅速な問題解決のために実施されないケースがほとんどです。
労働審判委員会と当事者が直接会話し、審理を進めていきます。
また、労働審判では相手方に確認したいことがあっても、質問することは基本的に認められていません。
仮に質問の機会を与えられても限られた範囲にとどまるうえ、虚偽の主張に対する明確な罰則などもないので、相手が虚偽の内容を答える可能性もあります。
会社の経営者や役員などと直接顔を合わせることになる
労働審判では、会社の経営者や役員など、争う相手と直接顔を合わせることになります。
通常の裁判では尋問時を除いて、当事者の出席は強制されていません。
しかし、労働審判では、労働者側も会社側も出席するのが基本です。
呼出しを受けた事件の関係者が正当な理由なく出席を拒否すれば、過料に処されることもあります。
よって、特別な事情がない限り、争う立場にある相手方と直接顔を見合わせることになるため、大きな負担に感じる人も多いでしょう。
ただし、労働審判委員会が間に入ってくれるうえ、直接相手方と会話することは少ないので安心してください。
労働審判の申し立てから終局までの大まかな流れ
労働審判の申し立てから終局までの流れは、以下のとおりです。
- 労働審判の申し立て
- 委員会による期日の指定
- 会社による答弁書などの提出
- 労働審判期日における審理
- 調停成立または労働審判
それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
労働審判の申し立て
労働審判での問題解決を希望する際は、まず地方裁判所に対して申立書や証拠書類などを提出しなければなりません。
その後、申し立てに形式的な誤りや不備がなければ、裁判所に受理してもらえます。
なお、申し立てには数万円程度の手数料がかかる点に注意してください。
委員会による期日の指定
労働審判委員会は、申し立ての日から40日以内に第一回期日を指定します。
当事者双方には期日呼出状が送付され、特段の事情がない限りは指定された期日に出席しなければなりません。
また、会社側には期日呼出状とあわせて、申立人が裁判所に提出した申立書のコピーが渡されます。
会社による答弁書などの提出
会社側は、労働審判委員会が指定した期日までに、申立書に対する答弁書や証拠書類などを提出します。
労働審判では第一回期日までに出揃った書類をもとに、問題解決に向けたおおまかな方向性を決めるのが一般的です。
よって、会社にとって答弁書は、労働審判の行く末を左右する極めて重要な書類といっても過言ではありません。
労働審判期日における審理
あらかじめ労働審判委員会によって指定された期日になれば、審理がおこなわれます。
出席者は一般的に労働審判委員会の3名、申立人とその弁護士、相手方(会社の担当者)とその弁護士です。
労働審判における審理は1回~3回おこなわれるので、それぞれで話し合う内容などを詳しく見ていきましょう。
第一回期日
第一回目期日では申立書や答弁書の内容をもとに、労働審判委員会が事実関係を整理し、当事者双方への質問を進めていくケースが一般的です。
ただし、一方の質問内容を踏まえ、それに対する主張や反論をもう一方に求めることも少なくありません。
また、多くの場合は第一回期日において調停に向けた和解案が示されます。
第二回期日
多くの場合、第一回期日の2週間から1ヵ月後に、第二回期日が設定されます。
第二回期日では、和解案に対する双方の意見を確認し合うケースが多いといえるでしょう。
なお、第二回期日までに双方が納得する結論が出た場合、第三回期日は実施されません。
第三回期日
一般的には、第二回期日から1週間前後から1ヵ月後に、第三回期日が開催されます。
この段階に入ると、新たな主張がおこなわれたり、証拠が提出されたりすることは基本的にありません。
また、第二回期日で和解案が提示されている場合は、第三回期日中に双方が返答する必要があります。
調停成立または労働審判
第三回期日までに双方が和解案に合意すれば、調停が成立します。
労働委員会によって合意事項を記した調書がつくられ、当事者はその調書の内容に従って義務を履行していかなければなりません。
第三回期日を迎えてもなお意見が対立している場合は、調停が不成立となり、労働審判へと移行します。
労働審判とは、労働審判委員会によって最終的な解決案が提示されることを指し、裁判の判決と同様の効力を持つ点が特徴的です。
解決案が示された翌日から2週間以内に、当事者双方から異議申し立てがなければ労働審判の効力が確定します。
いずれか一方からでも異議申し立てがおこなわれると、自動的に民事訴訟へと移行するため、改めて訴訟手続きを進めていかなければなりません。
労働審判の費用|一般的には3万5,000円程度が目安になる
一般的に、労働審判の費用は3万5,000円程度が目安です。
具体的には、以下のような費用があげられます。
| 項目 | 内容 | 金額 |
| 印紙代 | 申し立てにかかる手数料 | ~2万5,000円程度 |
| 予納郵券代 | 裁判所から相手方への郵送費 | 〜4,000円程度 |
| その他実費 | 交通費・印刷代・郵送代など | 6,000円程度 |
労働審判に要する主な費用は、印紙代と予納郵券代です。
交通費や印刷代などの実費は、人によってはほとんどかからないこともあるでしょう。
まず、印紙代は労働審判での請求額によって、以下のとおり決められています。
| 請求額 | 印紙代 |
| 10万円以下 | 500円 |
| 20万円以下~100万円以下 | 1,000円~5,000円 (請求額が10万円増えるごとに印紙代も500円ずつ加算) |
| 160万円以下 | 6,500円 |
| 200万円以下 | 7,500円 |
| 300万円以下 | 1万円 |
| 400万円以下 | 1万2,500円 |
| 500万円以下 | 1万5,000円 |
| 600万円以下~1,000万円以下 | 1万7,000円~2万5,000円 (請求額が100万円増えるごとに印紙代も2,000円ずつ加算) |
予納郵券代は、裁判所によって金額が異なるため、裁判所へ事前に問い合わせておくと安心です。
なお、上記は個人で労働審判を申し立てる際の費用である点に注意してください。
弁護士にサポートを依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。
【参考元】手数料早見表|裁判所
労働審判で納得のいく結果に繋げるための5つのポイント
労働審判で納得のいく結果に繋げるためには、以下のポイントを意識することが大切です。
- 請求の正当性がわかる申立書を作成する
- 主張する事実を裏付ける証拠を収集する
- 会社の反論を予想し再反論を考えておく
- 妥協できる大まかな目安を決めておく
- 労働問題が得意な弁護士に相談する
では、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
請求の正当性がわかる申立書を作成する
労働審判で納得のいく結果に繋げるためにはまず、請求の正当性が伝わる申立書を作成しなければなりません。
労働審判では申立書を含め、第一回期日までに出揃った書類をもとに、最終的な着地点をおおまかに決定するためです。
申立書は法律の要件に従って、請求内容を記載していく必要があります。
よって、申立書の作成は弁護士に依頼するのが得策といえるでしょう。
弁護士であれば法的な観点に基づいて、説得力のある申立書を作成できるため、労働審判を有利に進められるはずです。
主張する事実を裏付ける証拠を収集する
主張する事実を裏付ける証拠の収集も欠かせません。
労働審判では、双方から提出された証拠をもとに事実関係を明らかにしていきます。
そのため、主張とは無関係の証拠をいくら持ち出しても、判断材料として認めてもらえない可能性があるので注意してください。
事実の裏付けに有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 就業規則
- 求人票
- 出勤簿・タイムカード
- 業務日誌
- 給与明細
- 解雇通知書・解雇理由書
揃えておくべき書類は、請求内容によって異なります。
ご自身で判断することが難しければ、弁護士に依頼することも検討してみてください。
なお、提出する証拠は書面上でリスト化し、労働審判委員会へ提出しなけばなりません。
会社の反論を予想し再反論を考えておく
労働審判で納得のいく結果を得るためには、会社の反論を予想し再反論を考えておくも大切です。
素早く論理的に再反論できれば、労働審判委員会に有利な心証を持ってもらえる可能性が高くなります。
申立書を作成する段階で、相手側からの反論内容もある程度予想できるはずです。
しかし、再反論は法的根拠に基づいておこなうことが重要になるため、個人の力で考えるのは難しいでしょう。
過去の事例などから相手方の反論を正確に予想し、適切な再反論を展開していくためには、弁護士のサポートが欠かせません。
妥協できる大まかな目安を決めておく
労働審判に臨む際は、あらかじめ妥協できる大まかな目安を決めておく必要があります。
もちろん、互いの意見の折り合いがつかないのであれば、最後まで争うこともひとつの方法です。
しかし、労働審判に判断を委ねた結果、労働者側に不利な条件が提示される可能性も否定できません。
こちらが納得できる労働審判が下されても、相手側から異議申し立てがあれば訴訟に移行し、問題が長期化してしまうリスクもあります。
労働審判では、調停での解決を目指すのが基本です。
ある程度の妥協点に達した場合は、早期に調停を決断することも選択肢に入れておきましょう。
労働問題が得意な弁護士に相談する
労働問題が得意な弁護士に相談することも、労働審判を有利に進めるためのポイントです。
弁護士を頼れば、以下のようなメリットを得られます。
【労働審判を利用するにあたり弁護士に相談するメリット】
- 労働審判で争うことの妥当性を判断してもらえる
- 法的に有効な書類の作成・収集を任せられる
- 審理での主張や受け答えをサポートしてもらえる
まず、弁護士に相談すれば、トラブルを解決する手段として労働審判が適しているかどうかを判断してもらえます。
トラブルの内容によっては、労働審判で早期解決を目指すのではなく、通常の裁判でじっくり争うほうが好ましいケースもあるでしょう。
弁護士なら個々の状況にあわせて、最善の方法を提案してくれるはずです。
また、法的に有効な書類の作成や収集を任せられる点もメリットといえるでしょう。
労働審判では、第一回期日までに提出する申立書や証拠書類が、最終結果を大きく左右します。
労働問題が得意な弁護士であれば、法的根拠に基づいて説得力のある申立書を作成し、それを裏付ける証拠書類も適切に取捨選択しながら揃えることが可能です。
さらに、弁護士に依頼すれば、審理での主張や受け答えもサポートしてもらえます。
労働審判委員会から次々と投げかけられる質問に対し、一般人が冷静に回答し続けることは困難でしょう。
そのほか、事実と異なる発言や自身が不利になる発言をしてしまう可能性も否定できません。
審理の場で弁護士が発言する機会は多くないものの、的確にフォローしてもらえる存在がいることは心強く感じられるでしょう。
労働問題について弁護士と無料で相談できる窓口4選
労働問題について弁護士と無料で相談できる主な窓口は、以下の4つです。
- ベンナビ労働問題
- 法テラス
- 弁護士会
- 各自治体の法律相談会
まずは無料相談の機会を活用して、信頼できる弁護士を探してみましょう。
ベンナビ労働問題|労働審判が得意な弁護士が見つかる
弁護士を探したいときは、「ベンナビ労働問題」の利用を検討してみてください。
ベンナビ労働問題なら、労働審判が得意な弁護士を全国から探せます。
地域や相談内容を絞って検索することもできるので、ご自身にぴったりの弁護士を見つけられるでしょう。
初回相談が無料の法律事務所も多数登録されているため、なるべく費用をかけず弁護士を探したい方には特におすすめです。
法テラス|資力基準などを満たせば無料で相談ができる
資力基準などを満たしている場合は、法テラスで無料相談を受けられます。
法テラスは、法的トラブルの解決を図るために設置された公的な法人です。
経済的に余裕がない方に対して、弁護士による無料相談の場を提供しています。
法テラスで無料相談を受けられるのは、1つの問題につき3回までです。
相談時間も1回30分程度に限られているので、事前に聞きたいことをまとめたうえで利用しましょう。
実際に相談する際は、最寄りの法テラスや弁護士の事務所を訪れるのが一般的です。
移動が難しければ、電話でも相談に応じてもらえる場合があります。
なお、法テラスの無料相談を利用するには収入が一定額以下であることなど、各種条件を満たしていなければなりません。
利用条件は細かく決められているため、法テラスの公式サイトで確認してみてください。
【参考元】無料の法律相談を受けたい|法テラス
弁護士会|労働者からの相談は初回無料であることが多い
地域によっては、弁護士会の無料相談も利用できるかもしれません。
全国には50ヵ所以上の弁護士会が存在し、複数の団体が労働トラブルに関する無料相談を受け付けています。
たとえば、東京の弁護士会が運営する法律相談センターでは、労働者に限り初回30分の無料相談が可能です。
最寄りの弁護士会は、日本弁護士連合会の公式サイトで調べられます。
各サイトには無料相談の有無が記載されていることもあるので、気になる方は利用条件とあわせて一度確認してみるとよいでしょう。
各自治体の法律相談会|地域の役所などで気軽に相談できる
自治体によっては、労働トラブルの無料相談会を実施しているケースもあるでしょう。
一般的には月に数回程度、対面や電話で弁護士に相談できる場が設けられます。
労働トラブルを含め、幅広い相談内容に対応していることが多いので、何から手をつければよいのかよくわからない方もまずは気軽に相談してみてください。
ただし、基本的に居住する市区町村以外の無料相談は利用できません。
利用回数や利用時間の上限も決められているため、詳細は各自治体の公式サイトなどで早めに確認しておきましょう。
労働審判を利用するにあたって知っておくべき注意点
ここからは、労働審判を利用する際の注意点を解説します。
あらかじめ注意点を押さえておくことで、問題が生じたときにも焦らず冷静に対応できるはずです。
使用者に異議の申し立てをされるリスクがある
労働審判では、会社側に異議の申し立てされるリスクがある点に注意してください。
第三回期日を迎えても労働者と会社の意見が折り合わない場合は、労働審判が下されます。
しかし、労働審判に不服がある場合、2週間以内であれば異議申し立てをおこなうことが可能です。
もし労働者側に有利な労働審判が下されたとしても、会社側からの異議申し立てによって労働審判は効力を失い、民事訴訟に移行してしまうことを覚えておきましょう。
複雑な事案は民事訴訟に移行する可能性がある
複雑な事案は、民事訴訟に移行して争わなければならない可能性もあります。
労働審判から民事訴訟へと移行するのは、主に以下の2つのケースです。
- 事案の性質上、労働審判での解決が適切ではないと労働委員会が判断したとき
- 労働審判に対して異議申し立てがおこなわれたとき
労働審判では原則3回の期日で問題の解決を図りますが、双方の対立が深刻な場合は和解が難しいこともあるでしょう。
民事訴訟への移行によって問題解決までの期間が長期化するリスクは、ある程度覚悟しておかなければなりません。
労働審判の対象にならない労働トラブルもある
そもそも抱えている労働トラブルが、労働審判の対象にならないケースもあります。
労働審判の対象となるのは、不当解雇や給料の未払いなど、個々の労働者と会社との間で生じたトラブルです。
たとえば、労働組合と会社との対立や、上司個人を対象とした事案などは労働審判で審理することは認められません。
また、労働審判の主たる目的は短期間での紛争解決なので、職場全体に関わるリストラ問題や就業規則の変更といった、解決に時間を要する事案も対象外となる可能性があります。
労働審判に関するよくある質問
最後に、労働審判に関するよくある質問を紹介します。
事前に疑問を解決しておけば手続きをスムーズに進められるので、ぜひ参考にしてみてください。
Q.労働審判が適しているのはどのようなケースか?
労働審判に適しているのは、基本的に短期間での解決が期待できる事案です。
具体的には、主に以下のようなケースが挙げられます。
- 解雇・賃金未払いなど早期解決しなければ生活に支障が生じるケース
- 明らかな法律違反など会社側の落ち度が比較的容易に立証できるケース
- 当事者間での話し合いに応じてもらえないケース
- 損害賠償など金銭での解決が見込めるケース
複雑な事案に関しては、通常の裁判で争ったほうが得策といえる場合があります。
そもそも労働審判を利用すべきかどうかは、弁護士に助言を求めながら慎重に判断しましょう。
Q.労働審判は自分でできるか?それとも弁護士に依頼すべきか?
労働審判の申し立て自体は、個人でもおこなうことができます。
しかし、労働トラブルは法的問題をともなうケースがほとんどです。
専門的な知識をもたない個人が一人で対応しようとしても、思うような結果は得られないかもしれません。
法的に有効な主張・立証をおこなうためには、労働問題を得意とする弁護士の協力は不可欠です。
弁護士に依頼すれば申立書の作成から、審理の場でのサポートまで安心して任せられるでしょう。
Q.万が一、労働審判で負けてしまった場合はどうすれば良いか?
労働審判の結果に不服がある場合、2週間以内であれば異議申し立てが可能です。
異議申し立てがおこなわれると自動的に民事訴訟に移行するため、再度会社側と争うことができます。
期限内に異議申し立てをおこなわなければ、労働審判の効力が確定してしまうので注意してください。
さいごに|労働トラブルを迅速に解決したいなら労働審判がおすすめ!
労働トラブルに悩んでいる方は、労働審判を利用して早期解決を図りましょう。
通常の裁判であれば1年以上の期間を要することも珍しくありませんが、労働裁判なら多くの場合、数ヵ月で問題は解決されます。
しかし、手続きを急ぐ場合でも、まずは弁護士に相談してみることが大切です。
自分だけで解決しようとすると、本来有利に進められるはずの事案でも最終的に負けてしまう可能性があります。
無料で弁護士に相談できる機会は多数あるので、有効に活用してみてください。