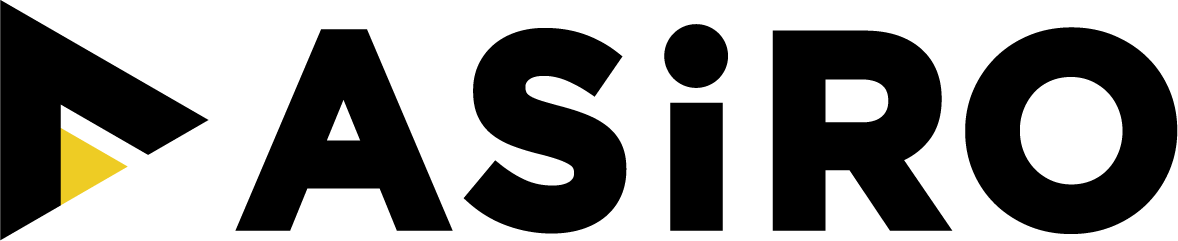遺産相続において不公平な遺言や贈与があって遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をおこなうことで、遺留分を取り戻すことができます。
しかし、遺産に不動産が含まれていた場合、不動産を取得した相手に対して遺留分侵害額請求はできるのでしょうか。
本記事では、遺産に不動産が含まれていた場合に遺留分侵害額請求はできるのか、またどのように請求したらよいのかについて解説します。
具体的な評価方法についても説明しますので、不動産が含まれる遺産について、遺留分侵害額請求を検討している方は、参考にしてみてください。
遺産分割について悩みを抱えている方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、下記の様なサポートを受けることができます。
- 遺留分侵害者との交渉の代理
- 自分の本来持っている遺留分の計算
- 調停・訴訟のときの代理人としての活動
ベンナビ相続には、相続問題が得意な弁護士のみ掲載しております。
さらに初回相談無料のところもありますので、まずは下記からお気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、相続において、法律で保障された最低限の取り分である「遺留分」が確保されなかった場合に、その不足分を請求できる権利を指します。
この権利を行使することで、遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く受け取った方から、その不足分を取り戻すことができます。
まずは、遺留分侵害額請求の詳細について詳しく見ていきましょう。
遺留分侵害額請求権には期限がある
遺留分侵害額請求権には、期限があります。
下記のいずれか早い時期に権利が消滅するため、注意する必要があります。
- 権利者が遺留分を侵害する遺言や贈与などがあったことを知ってから1年間権利を行使しなかったとき
- 相続開始から10年経過したとき
遺留分侵害額請求権を行使する方法
遺留分侵害額請求権の行使は相手方との話し合いから始まります。
当事者同士で話し合って解決できれば、それが最もスムーズな解決方法となるからです。
話し合いで合意できたら、合意書を作成し、遺留分を侵害した相当額を相手に支払ってもらいます。
一方、話し合いで合意できなかった場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申立てをおこないます。
そして、裁判所を通じて、遺留分の請求について解決を図ります。
もし調停でも解決できなかった場合には、訴訟になり、最終的な判断が裁判官に委ねられます。
話し合いで解決できなかった場合には、一連の手続きが複雑になってしまうため、弁護士に依頼することが一般的です。
遺留分減殺請求権との違い
遺留分侵害額請求権と似たような用語に「遺留分減殺請求権」があります。
この権利は、遺留分侵害額請求権が適用される前にあった遺留分を請求する手続きです。
遺留分減殺請求権では、遺留分の不足分について金銭ではなく、現物財産そのものの返還を求める手続きでした。
このため、遺留分の対象となる財産に不動産が含まれる場合、遺留分を侵害する贈与や遺贈が侵害の限度で失効するため、その不足分に応じて不動産の持分を取得することになります。
しかし、不動産の持分を与えることは、相続人同士で不動産を共有する複雑な状態となるため、管理や処分の際に問題となっていたのです。
こうした不都合を解消するため、2019年6月30日以降は民法改正により、金銭請求ができる遺留分侵害額請求権に変わったのです。
したがって、遺留分侵害額請求権は、財産の現物ではなく金銭を請求できるという点で、遺留分減殺請求権とは大きく異なります。
不動産が含まれる場合の遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求の詳細について理解したところで、遺産に不動産が含まれる場合の遺留分侵害額請求の流れについて見ていきましょう。
基本的には、以下のステップにしたがって、遺留分侵害額請求をおこないます。
- 遺留分を請求できる立場にあるか確認する
- 自分が相続する遺留分の割合を確認する
- 自分がもらえる遺留分額を計算する
- 侵害されている遺留分を計算する
- 遺留分侵害額請求をおこなう
はじめに、自分が遺留分を請求できる相続人であるかを確認します。
被相続人の兄弟姉妹である場合には、遺留分の請求はできません。
次に、自分が相続する遺留分の割合を確認します。
相続人の構成ごとに自分の遺留分が何分の1になるのか確かめましょう。
自分の遺留分の割合がわかったら、具体的な遺留分の金額を計算します。
遺留分額は、遺産の総額に対して、自分の遺留分割合をかけた金額で計算できます。
なお、遺産に不動産が含まれる場合には、以降で解説する評価方法によって、金額が異なります。
適切な評価方法を選択することが大切です。
遺留分額の計算が終わったら、自分の遺留分がどれくらい侵害されているか計算します。
最後に、時効の期限に注意して遺留分侵害額請求をおこないます。
不動産の評価方法は5つある
遺留分侵害額請求をおこなうためには、不動産の評価方法の種類を知ったうえで、適切なものを選択することが大切です。
なぜなら、どの評価方法を採用するかによって、不動産の評価額は大きく変わるからです。
ここでは、不動産を評価するための代表的な5つの方法を解説します。
1.路線価
路線価は国税庁が発表している不動産の評価基準のことです。
路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、これに土地の面積を乗じれば、「路線価による土地の評価金額」を算出できます。
市街地の路線ごとに価格が設定されており、贈与税額や相続税額を算出する場面で使用されます。
路線価による評価額は、あとに出てくる地価公示価格の8割前後です。
国税庁のホームページから確認でき、毎年夏頃にその年に用いる路線価が公表されます。
2.固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税などを算出する際に基準となる不動産の評価額です。
建物については、相続税や贈与税の評価の基準にもなります。
不動産のある市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書や、市区町村にある固定資産課税台帳、不動産のある都税事務所や市区町村で入手可能な固定資産税評価証明書から確認することができます。
3.実勢価格
実勢価格とは、不動産が市場で実際に取引された価格を指します。
市場での取引成立価格のため、実生活の取引でも参考になるでしょう。
不動産会社も、売り出し広告などはこの価格を参考にしています。
国土交通省のホームページにある「不動産取引価格情報検索」に過去の実勢価格が掲載されていますが、全ての取引を網羅したものではありません。
4.地価公示価格
地価公示価格とは、毎年3月に国土交通省が発表している地価の基準のことです。
1月1日時点での価格を指し、各地に設定された標準的な土地について1平方メートルあたりの価格で示されています。
不動産鑑定士がふたり以上で鑑定評価したものを土地鑑定委員会で審査をおこなって決定されます。
市場で取引される価格と近いため、不動産売買の際にも参考にできるものです。
国土交通省の「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」で確認できます。
5.不動産鑑定評価額
不動産鑑定評価額とは、国家資格を持つ不動産鑑定士が「不動産鑑定評価基準」に基づいて算出する不動産の評価方法です。
この評価方法は、公的な証拠力や信頼性が高く、遺留分や相続のトラブルにおいて不動産の評価額が争点となる場合に、評価額の根拠として利用されます。
ただし、この評価方法を依頼する際には、鑑定料として20万円〜100万円程度の費用が発生します。
そのため、依頼する際には費用に注意しましょう。
不動産の評価額が自分で計算できない場合の対処法
ここまで述べてきたとおり、不動産の評価額を出すのは難しいものです。
しかし、評価額がわからないと遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。
なぜなら、遺留分侵害額請求は、原則として金額を明示しておこなう必要があるからです。
このため、不動産の評価額を自分で計算することが難しい場合には、専門家に相談したほうが安心です。
弁護士に相談する
弁護士に相談をすると、法律面からアドバイスを受けられるうえに、交渉の席についてもらうことができます。
当事者同士の話し合いでは、お互いの主張がぶつかり合い、感情的になって決裂する可能性があります。
弁護士に相談すると、この場合の交渉をサポートしてもらえます。
また相続全般について不安なことがある場合においても、相続手続き全般を弁護士に任せられます。
まずは弁護士に相談をしてみましょう。
【関連記事】遺留分の無料相談窓口6選|弁護士・市役所・相談センターのどこに依頼すべきか解説
不動産鑑定士に相談する
評価方法や評価額の見解に相違があるときには、不動産鑑定士に相談をする方法も効果的です。
遺留分侵害額請求の話し合いをおこなううえで、不動産の計算方法の相違によって話がまとまらない場合があります。
不動産鑑定士は国家資格であり、第三者の立場から公平に不動産の評価をおこなうため、不動産の価格面でお互いが納得しやすくなるでしょう。
ただし、不動産鑑定士の算出した金額が、必ずしも当事者間で遺留分侵害額を計算するための基準額となるわけではない点については、注意する必要があります。
不動産の遺留分侵害額の請求権についてよくある質問
最後に、不動産の遺留分侵害額の請求権について、よくある質問を見ていきましょう。
遺留分を現金で支払えない場合はどうしたらよいですか?
不動産は、一般的に高額であるものの、遺留分は現金一括で支払わなければなりません。
そのため、すぐに用意できない場合には、相手方と交渉して支払期限を延長できないか、もしくは分割払いにできないか、などについて協議するとよいでしょう。
交渉した結果、双方が合意すれば柔軟な支払い方法を採用することができます。
また、話し合いで解決できなかった場合には、裁判所に対して支払期限の延長を求めることができます。
遺留分を現物の不動産で返してもらうことはできますか?
遺留分侵害額請求をした場合、原則として金銭で清算することが定められています。
そのため、遺留分を請求したとしても、不動産の一部を返してもらうことはできません。
ただし、当事者同士の話し合いによって双方が合意した場合には、例外的に不動産を取得することが可能です。
このため、もし現物の不動産を取得したい場合には、まずはその希望を相手方に伝えて、交渉を進めるとよいでしょう。
まとめ
遺留分とは、簡潔にいうと、被相続人が亡くなった際、一定の相続人が最低限取得できるものとして保障された相続財産の取得分のことです。
遺留分を侵害されていることが判明した場合は、遺留分侵害額請求権を行使できます。
ただし、対象となる財産の中に不動産が含まれているときには、適切な評価方法を用いて評価額を計算しなければなりません。
評価方法は大きく分けて5種類あり、どの方法を使用するかによって評価額が大きく変わってきます。
そのため、自身や家族だけで問題を解決するのが難しいケースもあるでしょう。
その場合には、弁護士に相談すると安心です。
法律事務所によっては無料相談や電話相談を設けていますので、自身の状況に合わせて活用してみてください。