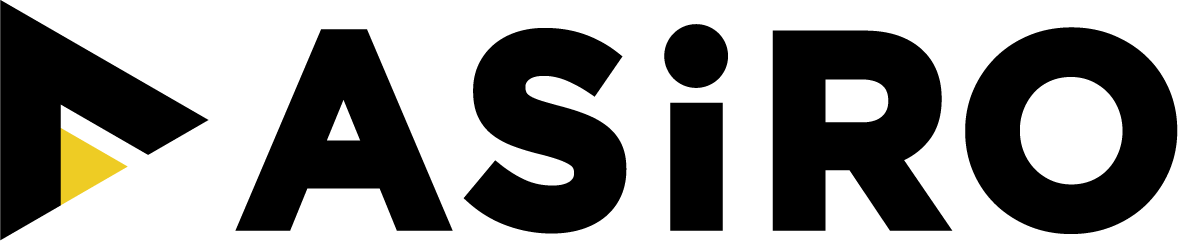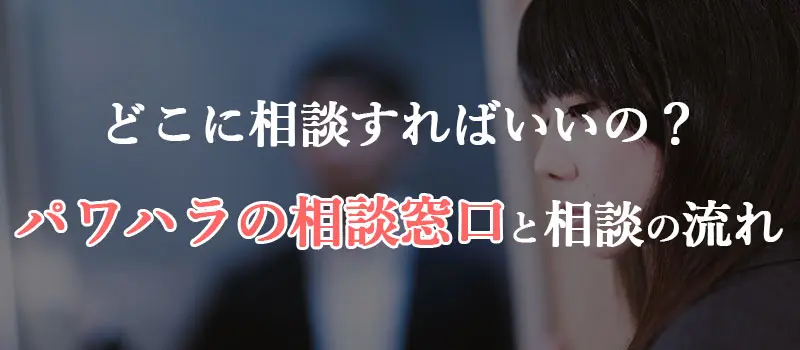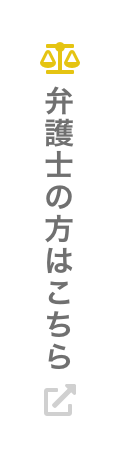会社でハラスメントに悩まされている方は、問題を解決するために相談窓口を探しましょう。
ハラスメントの相談窓口にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。
ご自身の悩みや希望に合わせて、適切な窓口を選んで相談してください。
本記事では、ハラスメント被害の相談窓口や各相談窓口のサポート内容を解説します。
ハラスメント問題を解決したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
職場でのハラスメント被害への対処法がわからず、困っていませんか?
結論からいうと、ハラスメントに関する相談は、会社・行政・弁護士などが受け付けています。
もし、加害者や会社に対して損害賠償請求したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- どのようなものが証拠になりうるか教えてもらえる
- 会社の対応が適切か判断してもらえる
- 依頼すれば、損害賠償請求の手続きを一任できる
- 依頼すれば、代理人として会社に配置転換や再発防止策を要請してもらえる
ベンナビ労働問題では、職場でのハラスメントの解決を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。
ハラスメントに関する社内の相談窓口2選
ハラスメントに関する社内の相談窓口には、主に次の2つがあります。
- 会社のハラスメント相談窓口
- 労働組合・ユニオン
会社のハラスメント相談窓口
会社のハラスメント相談窓口は、手軽に利用できることがメリットです。
社員が安全に働ける環境を提供するために、多くの企業ではハラスメントに関する相談窓口を設けています。
相談員は問題を解決するためのアドバイスを提供し、場合によっては社内の適切な部署に報告・対応を依頼します。
しかし、中には人事評価への影響や、周囲にバレてしまうことが不安な方もいるでしょう。
念のため、相談前には匿名性や守秘義務が守られているかについて、よく確認しておきましょう。
労働組合・ユニオン
労働組合またはユニオンに加入している場合は、相談窓口として利用できます。
労働組合やユニオンは労働者の権益を守る目的で活動しています。
ハラスメント問題についても、状況によっては労働組合が直接会社に交渉してくれることもあります。
ハラスメントに関する社外の相談窓口3選
ハラスメントに関する社外の相談窓口として、次の3つを紹介します。
- 総合労働相談コーナー
- 法テラス
- ベンナビ労働問題
総合労働相談コーナー|労働問題全般の相談ができる
総合労働相談コーナーは労働条件や労働環境、ハラスメント問題など労働問題全般に関する相談ができる窓口です。
労働問題に詳しい相談員が対応し、相談者のプライバシーを厳重に保護しながら状況に応じたアドバイスを面談や電話で提供してくれます。
いじめや嫌がらせ、パワハラなどハラスメント全般の労働問題も対象です。
また、労働基準法などの法的違反が疑われるケースには、労働基準監督署などの適切な行政機関に案件を引き継ぐ手続きもおこなっています。
法テラス|経済的に余裕がなくても弁護士と無料で相談できる
法テラスは法的問題を解決するための公的機関で、経済的に余裕がなくても弁護士に無料相談ができます。
ハラスメント被害は法的な問題に発展する可能性があるため、初期段階での弁護士への相談が有用です。
法テラスは収入・資産が一定額以下であるなど、一定の条件を満たせば無料で相談ができます。
また、実際に弁護士へ依頼する際には、弁護士費用の立替払い制度も利用可能です。
経済的な理由が原因で相談に不安を抱える方は、法テラスの利用を検討してみましょう。
ベンナビ労働問題|ハラスメント問題が得意な弁護士を探せる
ベンナビ労働問題では、ハラスメント問題が得意な弁護士を探せます。
検索条件で「ハラスメント」を指定することで、ハラスメント問題が得意な弁護士を簡単に絞り込めるでしょう。
「初回相談が無料」「電話相談可能」な弁護士も多数在籍しているので、ハラスメント問題に悩む方はベンナビ労働問題で弁護士を探してみてください。
ハラスメントの相談窓口を選ぶときのポイント
ハラスメントの相談窓口を選ぶときのポイントは、次のとおりです。
- 社内相談窓口か、社外相談窓口か
- 相談料などを支払う余裕があるか
- 損害賠償を請求するか
社内相談窓口か、社外相談窓口か
まずは、相談先を社内相談窓口と社外相談窓口のどちらにするかを決めましょう。
ハラスメントの問題に直面した場合は、まずは社内相談窓口への相談がおすすめです。
社内相談窓口は会社も問題を把握しやすいうえ、解決策を速やかに見つけ出せる可能性が高いでしょう。
また、パワハラ防止法が施行されたことで、企業はパワハラの知識を深めながら防止に努めることが義務化されました。
そのため、多くの企業が社内でのハラスメント問題に対する対策を強化しており、以前よりも社内相談窓口での相談がしやすいでしょう。
社内相談窓口で問題が解決できなかった場合は、社外相談窓口の利用を検討しましょう。
社外相談窓口では、第三者の観点からのアドバイスが受けられます。
また、弁護士に相談することで法的な解決方法を提案してもらえますし、実際の解決に向けた対応も弁護士に依頼できるため、より適切な解決が期待できるでしょう。
相談料などを支払う余裕があるか
あらかじめ、自身が相談料を支払う余裕があるかどうかを考慮することも重要です。
ハラスメントの相談窓口の利用料金は、有料の場合も無料の場合もあります。
公共機関や非営利団体が提供する相談窓口は、基本的に無料です。
たとえば、総合労働相談コーナーがおこなう労働委員会による個別労働紛争のあっせんは無料で提供されています。
無料相談窓口では、ハラスメント問題に詳しい専門家が無償で相談に乗ってくれますが、サービス内容や対応範囲が限定されている場合があるのであらかじめ相談できる内容を確認しておきましょう。
有料の窓口では、通常よりも詳細な相談や法的手続きの支援が期待できます。
費用がかかる分、専門的な知識に基づくアドバイスや、問題解決に向けた具体的な対応をしてもらえる場合が多いです。
損害賠償を請求するか
ハラスメントによって受けた損害に対して、損害賠償を請求するかどうかも考慮しましょう。
損害賠償請求をおこないたい場合は、弁護士への依頼がおすすめです。
労働委員会が提供する「個別労働紛争のあっせん」でも、損害賠償請求についての相談はできます。
しかし、弁護士に相談した方が、具体的な法的手段や訴訟に至る過程での戦略を詳細に説明してくれるため、有益な場合が多いです。
また、実際に損害賠償請求を行う際には、弁護士に手続きをそのまま依頼できる点もメリットといえます。
ハラスメントの相談窓口を利用するときの流れ
ハラスメントの相談窓口を利用するときの流れは、次のとおりです。
- 相談先を決めて、必要に応じて予約をする
- 相談窓口でハラスメントについて相談する
- 必要に応じてハラスメントの解決を依頼する
相談先を決めて、必要に応じて予約をする
まずは相談先を決めましょう。
社内の相談窓口、社外の公共相談窓口や弁護士など選択肢はさまざまです。
自身の状況や求めるサービス、費用に応じて最適な相談窓口を選びましょう。
相談窓口が決まったら、必要に応じて事前に予約をします。
相談窓口でハラスメントについて相談する
次に、相談窓口でハラスメントについて相談します。
ハラスメント問題に詳しい専門家に相談することで、自身に合った最も適切な対応策が把握できるでしょう。
問題に関する事実を全て正直に話すことで、具体的な解決策のアドバイスを受けやすくなります。
必要に応じてハラスメントの解決を依頼する
相談を終えたら、必要に応じてハラスメントの解決を依頼します。
たとえばハラスメントについて損害賠償を請求する場合は、弁護士に示談交渉や訴訟の提起を依頼する選択肢もあるでしょう。
具体的な解決策を実際の行動に移すためには、専門家への依頼がおすすめです。
ハラスメントについて相談する際に必要な準備
ここでは、ハラスメントについて相談する際に必要な準備について解説します。
- ハラスメントに関する出来事を整理しておく
- ハラスメントに関する証拠を集めておく
- 希望する解決内容を考えておく
ハラスメントに関する出来事を整理しておく
まず、相談前にはハラスメントに関する出来事を整理しておきましょう。
時系列や関係性、発生した状況を明確にしておくことが重要です。
- 時系列:いつ、どのような状況でハラスメントが発生したか
- 関係性:加害者との関係性や普段の関わり合いについて
- 発生状況:ハラスメントが発生した具体的な状況や場所
上記のポイントを箇条書きやメモにしておくと、相談時にも思い出しやすくなります。
相談がスムーズに進むだけでなく、解決に向けた具体的なステップも明確になるでしょう。
ハラスメントに関する証拠を集めておく
ハラスメントについて再発防止や損害賠償を求める際には、有力な証拠を揃えて提示することが大切です。
可能な限り、次のようなハラスメントに関する証拠を集めておくとよいでしょう。
- 文書やメール
- 音声・動画記録
- 目撃者の証言
- 当時のメモや日記
希望する解決内容を考えておく
自身が希望する解決方法を明確にしておくと、相談窓口での議論を効率的に進められます。
解決方法は職場環境の改善や損害賠償の請求などさまざまです。
あらかじめ希望する解決策を伝えておくことで、専門家から希望に沿った具体的なアドバイスを受けられるでしょう。
被害者ができるハラスメントへの対応方法・解決方法
被害者ができるハラスメントへの対応方法・解決方法は次のとおりです。
- 会社にサポートや懲戒処分の要請をする
- 加害者や会社に対して損害賠償請求をおこなう
- 犯罪に該当する場合は刑事告訴をおこなう
- 退職や転職を検討する
会社にサポートや懲戒処分の要請をする
ハラスメント被害から自身を守るために、会社にサポートや懲戒処分の要請をおこないます。
会社内のハラスメント対策窓口や人事部などに相談をして、具体的な対策を要望しましょう。
たとえば、座席の変更や部署移動などが挙げられます。
また、加害者への懲戒処分が実行されれば、今後のハラスメント再発抑止にも効果があるでしょう。
加害者や会社に対して損害賠償請求をおこなう
加害者や会社に対して損害賠償請求をおこなうことも検討しましょう。
損害賠償請求は法的な手続きを必要とするため、法律の専門家である弁護士への相談がおすすめです。
被害者は加害者と会社、どちらに対しても賠償を求められます。
たとえば、加害者が賠償能力に乏しい場合は会社に対しても賠償請求をおこなうとよいでしょう。
加害者本人に対する損害賠償請求
ハラスメントをした加害者は、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負います。
精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、休職による賃金の損失である休業損害も損害賠償の対象に含まれることがあります。
会社に対する損害賠償請求
ハラスメントの状況によっては、個人だけでなく会社も賠償責任を負うことがあります。
会社の損害賠償責任の根拠は次の2つです。
- 安全配慮義務違反
- 使用者責任
安全配慮義務違反とは、使用者が労働者の生命や身体などの安全を守るために必要な配慮をする義務に違反することです。
安全配慮義務を怠った結果として労働者がハラスメント被害を受けた場合は、会社も賠償責任を負います。
さらに、会社の従業員や役員が業務中にハラスメントをおこなった場合、会社も使用者責任により賠償責任を負うことがあります。
犯罪に該当する場合は刑事告訴をおこなう
ハラスメントの程度や状況によっては、刑事犯罪に該当する可能性があります。
もし、ハラスメント被害が犯罪に該当する場合は、刑事告訴を検討しましょう。
ハラスメントに関する主な犯罪は次のとおりです。
- 名誉毀損罪・侮辱罪(刑法第230条第1項・231条)
- 傷害罪・暴行罪(刑法第204条、第208条)
- 強要罪(刑法第223条第1項)
- 強制わいせつ罪(刑法第176条)
「公に怒鳴る」「侮蔑的なメールをほかの従業員にも送信する」などの行為は名誉毀損罪または侮辱罪に該当する可能性があります。
また、被害者に対して殴る、蹴る、物を投げるなどの暴力を振るう行為は暴行罪、暴力の結果として被害者がけがを負ったら傷害罪が成立する場合があります。
明らかに不必要な行為を脅迫や暴力で強制した場合は強要罪、セクハラによるわいせつな行為をおこなった場合、その態様によっては強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
犯罪に該当するハラスメント行為に遭遇した場合、被害者は警察署などに対する刑事告訴が可能です。
手続きの方法が不明な場合は、弁護士に相談して具体的なアドバイスを受けるとよいでしょう。
退職や転職を検討する
ハラスメント被害が続く場合は、新たな職場を探して退職することも選択肢のひとつです。
ハラスメントの加害者と顔を合わせたくない場合は、職場を変えることも有効でしょう。
法的には、退職日の2週間前までに退職届を提出すれば退職できます。
ハラスメント被害は弁護士に相談するのがおすすめ!
ハラスメント被害は弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談することのメリットは次のとおりです。
- 適切な法的アドバイスが受けられる
- 損害賠償請求の手続きを一任できる
- 悩みや疑問点をいつでも相談できる
- プライバシーが適切に守られている
- 社内窓口と異なり仕事に支障が出にくい
適切な法的アドバイスが受けられる
弁護士に相談することで、適切な法的アドバイスが受けられます。
弁護士は法律や判例、労働実務などの専門的な知識を持っているため、自身の状況に応じた解決策を提示してくれます。
損害賠償請求の手続きを一任できる
弁護士に依頼すれば、損害賠償請求の手続きを一任できます。
損害賠償請求は法的な手続きで、複雑なプロセスです。
専門的な知識がない状態で進めると、時間や手間がかかるほか、必要な対応に漏れが生じるおそれもあります。
弁護士に依頼すれば、損害賠償請求に関する書類の作成や証拠収集、交渉、訴訟の提起などを代わりにおこなってくれます。
手続きを代行してもらうことで、時間や手間だけでなく、精神的な負担も大きく減らせるでしょう。
また、被害者側の請求が認められる可能性も高まります。
悩みや疑問点をいつでも相談できる
弁護士に依頼することで、悩みや疑問点をいつでも相談できます。
たとえば、損害賠償請求をするためには具体的にどのような証拠が必要なのかを知りたい場面もあるでしょう。
弁護士は専門的な知識と経験を活かして、どのような文書や音声記録が証拠として有効かを明確にアドバイスしてくれます。
さらに、証拠を集めるときの注意すべきポイントなど、具体的な方法も提案してくれるでしょう。
そのほか、請求できる損害賠償の額や、成否の見通しなどについてもアドバイスを受けられます。
プライバシーが適切に守られている
弁護士は守秘義務があるため、プライバシーが適切に守られます。
ハラスメントはセンシティブな問題も含まれるため、プライバシーが守られていないと相談がしにくいでしょう。
弁護士に相談した内容は第三者に漏れることはないため、安心して全ての事情を話せます。
社内窓口と異なり仕事に支障が出にくい
弁護士への相談は社内窓口よりも仕事に支障が出にくいこともメリットです。
社内窓口での相談も基本的にはプライバシーが守られていますが、場合によっては人間関係や評価に影響を与えかねません。
社外の弁護士に相談することで、社内での自身の立場が脅かされるリスクを回避しながら、問題解決に向けてのアプローチをスムーズに進められます。
ハラスメント問題を弁護士に依頼する場合の費用相場
パワハラやセクハラなど、ハラスメント問題の着手金の相場は20万円~30万円程度です。
着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で支払う金額になります。
依頼が成功した際に支払う成功報酬金の相場は、加害者や会社から損害賠償金額の15~20%程度です。
ただし、損害賠償請求を行わない場合には、別の条件によって報酬金が発生することもあります。
弁護士によって費用が異なるため、依頼前によく確認しておきましょう。
【目的別】ハラスメントに関するそのほかの相談窓口5選
ハラスメントに関するそのほかの相談窓口としては、主に次の5つが挙げられます。
- 人権相談窓口
- ハラスメント悩み相談室
- 弁護士会
- こころの耳
- 労働基準監督署
人権相談窓口|ハラスメントなど人権問題全般に関する相談
人権相談窓口は、ハラスメントなどの人権問題全般を相談できます。
全ての相談は厳密に秘密が守られるうえ、相談料もかかりません。
相談を受け付けるのは、各地域の法務局の専門職員や人権擁護委員です。
人権問題に詳しい相談員に相談できるため、悩みに対する最適な解決策が期待できます。
また、相談方法は多様で電話、窓口、インターネットを通じた相談が可能です。
相談に対する具体的な対応としては、専門職員や人権擁護委員が状況を調査し、人権侵害が確認された場合は関係者と協力して適切な「救済措置」を取ります。
また、調査が終了しても必要に応じて後続のケアも提供されるため、安心して利用できるでしょう。
法務省による人権相談窓口は次のようなものもあります。
- みんなの人権110番
- 女性の人権ホットライン
- インターネット人権相談
- SNS(LINE)による人権相談
ハラスメント悩み相談室|労働者以外のハラスメント相談
「ハラスメント悩み相談室」では、カスタマーハラスメントや就活ハラスメントのような労働以外のハラスメント相談に応じています。
カスタマーハラスメントとは、顧客からの過度な要求や脅迫行為などを指します。
業務への不合理なストレスを感じると、心身に大きな負担になるでしょう。
就活ハラスメントは企業や採用担当者が応募者に対して不適切な行動をとることです。
優越的な立場を利用することで、応募者に対してセクハラやパワハラをするケースが該当します。
ハラスメント悩み相談室では、メール相談やSNS相談を24時間365日受け付けており、72時間以内に返信があります。
相談は無料なうえに匿名での相談もできるため、初めて相談をしたい方や忙しくて時間がない方、費用に余裕がない方でも利用しやすいでしょう。
弁護士会|弁護士への有料相談・弁護士の紹介
弁護士会では弁護士への有料相談ができるほか、ハラスメント問題に詳しい弁護士の紹介を受けられます。
弁護士会には専門的な相談ができる弁護士が多数在籍しているため、法的な手段を検討している場合には弁護士会への相談を検討しましょう。
こころの耳|メンタルヘルスに関する相談
「こころの耳」は、メンタルヘルスケアに関するさまざまな情報や相談窓口を提供しているメンタルヘルス・ポータルサイトです。
ハラスメント被害は精神にも大きなダメージを与えることがあるでしょう。
こころの耳には精神的な健康に関する悩みを解決するための情報や解決策が提供されています。
電話、SNS、メール相談も実施しており、ハラスメントに関してメンタル的な悩みを抱えている方に役立つ相談窓口です。
労働基準監督署|精神障害の労災申請手続き
労働基準監督署では、精神障害の労災の申請手続きがおこなえます。
ハラスメントによる精神的な障害が原因で仕事に復帰できなくなってしまった場合、労災(労働災害)が認定される可能性があります。
労働基準監督署では専門の相談員が必要な書類や手続きの流れについて詳しく説明してくれるため、手続きもスムーズに進められるでしょう。
さいごに|ハラスメント被害はひとりで抱え込まずに誰かに相談を!
ハラスメント被害はひとりで背負い込む問題ではありません。
ハラスメント被害を感じた瞬間から、重荷をひとりで抱え込まずに各相談窓口に相談するようにしましょう。
ハラスメント問題を相談するための窓口はさまざまあります。
相談窓口によって相談できる内容が異なるため、自身が抱えている悩みや求める解決策に合わせて選択しましょう。
法的なアドバイスを受けたい場合は、弁護士への相談がおすすめです。
一般的な相談窓口でもアドバイスを受けられますが、法的な観点からの助言や解決策を求める場合は限界があります。
とくに自身が受けたハラスメントが犯罪に該当するかの判断や損害賠償請求を求める場合は、弁護士からの専門的なアドバイスが必要になるでしょう。
弁護士のサポートを受けることが、ハラスメント問題の早期解決につながります。
参考:39のハラスメントをまとめてみた|企業にとってのリスクとアルハラを防ぐためのガイドラインもご紹介 | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE