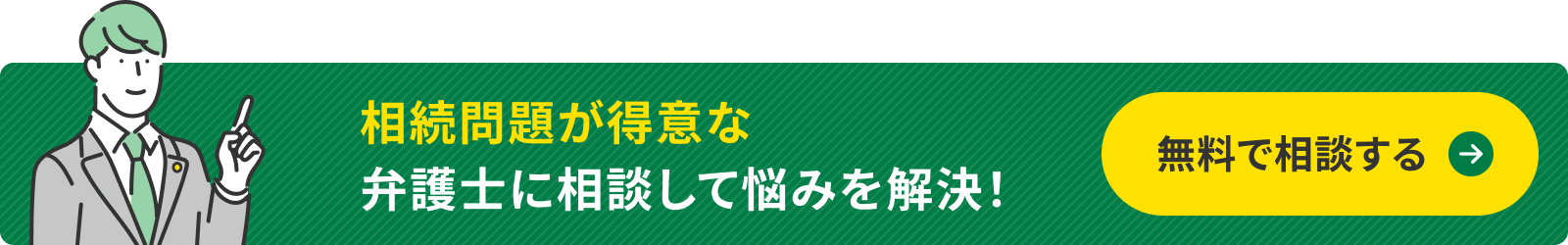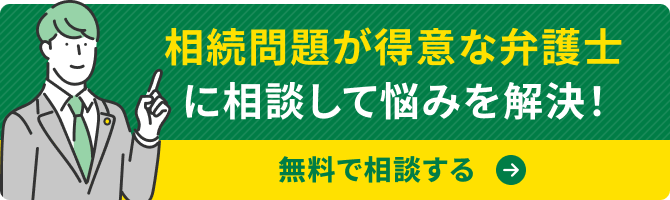親や兄弟などの身近な人が、認知症などによって成年後見制度を利用する必要が生じたという方もいるのではないでしょうか。
しかし、成年後見制度についてよくわからず、自分で手続きすることにも不安があるため、誰かに相談したいという方も少なくないでしょう。
成年後見制度について、専門家を頼りたいと考えるのは当然です。
ただし、相談窓口は数多くあるため、ご自身の状況や相談内容に合ったところを選ぶのがおすすめです。
本記事では、成年後見制度について無料相談できる専門家や具体的な無料相談窓口、依頼するときにかかる費用、成年後見制度について無料相談する際の注意点、成年後見制度を弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって、判断能力が不十分になった方を保護するための法的な制度です。
現在では、超高齢化社会の進展にともなって、認知症を理由に成年後見人を選任するケースが増えています。
ご本人の 判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。
成年後見制度では、本人の権利を守るために、家庭裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約手続きなどをおこないます。
成年後見制度を申し立てるには、必要書類を収集・作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
この申請手続きは複雑であるため、法律の専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
成年後見人を立てることは、判断能力に不十分な方が、法的な手続きをスムーズにおこなったり、ご自身の財産を守ったりするために、重要な役割を果たすのです。
成年後見制度について相談するなら誰がいい?
成年後見制度について相談できる専門家には、弁護士・社会福祉士・司法書士・行政書士などがいます。
いずれの専門家も成年後見制度に関する相談に対応できますが、法律の制限によって、対応できる業務の範囲が異なります。
そのため、相談先を選ぶ際には、ご自身の状況や目的に応じて、最適な専門家を選ぶことが重要です。
ここでは、各専門家が対応できる業務範囲などについてみていきます。
各専門家が対応できる業務の範囲
各専門家が対応できる業務の範囲は、以下のとおりです。
| 弁護士 | 司法書士 | 社会福祉士 | 行政書士 | |
|---|---|---|---|---|
| 必要書類の収集 | 〇 | 〇 | × | × |
| 必要書類の作成 | 〇 | 〇 | × | × |
| 申立て手続き | 〇 | △※ | × | × |
| 成年後見人への就任 | 〇 | 〇 | △ | △ |
※申立て手続きの代行のみ可能
成年後見制度の利用を検討している段階では、どの専門家にも相談可能です。
もっとも、成年後見の申立てをおこなうためには、家庭裁判所に申立てをおこない、裁判所との打ち合わせなどを必要とします。
そのため、裁判手続きに慣れている弁護士に相談をされるのが通常です。
なお、社会福祉士や行政書士は、成年後見の申立てに必要な書類の収集や作成、申立て手続きを代理でおこなうことはできません。
このため、成年後見制度の申立てを前提とした相談であれば、最初から弁護士または司法書士を相談先に選ぶことを検討したほうがよいでしょう。
成年後見人に選任された専門家の割合
成年後見を申し立てた際に、専門職の方が成年後見人に選任されることが多くあります。
その際に家庭裁判所から選任された成年後見人の専門家の割合は、以下のとおりです。
- 弁護士(26.8%)
- 司法書士(35.9%)
- 社会福祉士(18.4%)
- 行政書士(4.6%)
実際の選任割合では、司法書士が最も多く、次いで弁護士や社会福祉士、行政書士となっています。
成年後見人への就任する者は、裁判所が選任します。
簡潔な事案であれば、行政書士や司法書士といった弁護士以外の資格者が選任されることもありますが、複雑な事案であれば、弁護士が選任されることが通常です。
そのため、もし成年後見人申立てで悩まれておられるのであれば、ひとまずは一番難しい場合に備えて、弁護士に相談するのが無難でしょう。
成年後見について無料相談できる窓口10選
成年後見制度の利用を考えている場合、できる限り早い段階で専門家へ相談するのがおすすめです。
専門家であれば、ご自身の状況に合わせて最適な対応策を提示してくれるからです。
主な相談窓口には、以下のようなものがあります。
| 無料相談 | 相談できる時間 | おすすめの人 | |
|---|---|---|---|
| ベンナビ相続 | 30分程度 | 平日00:00~24:00 土日祝00:00~24:00 | 成年後見について相談したい全ての方 |
| 法テラス | 30分程度 | 相談先による | 経済的な余裕がない方 |
| 弁護士会 | 30分程度 | 相談先による | 弁護士に直接相談したい方 |
| 司法書士会 | 30分程度 | 相談先による | 司法書士に直接相談したい方 |
| 成年後見センター・リーガルサポート | 各支部や相談内容によって異なる | 平日14:00~17:00 | 司法書士に無料電話相談したい方 |
| コスモス成年後見サポートセンター | 30分程度 | 平日13:00~16:00 | 行政書士に相談したい方 |
| 権利擁護センターぱあとなあ | 各社会福祉士会によって異なる | 各社会福祉士会によって異なる | 社会福祉士に相談したい方 |
| 社会福祉協議会 | 30分程度 | 各自治体によって異なる | 社会福祉士などの専門家に相談したい方 |
| 各自治体の相談窓口 | 30分~1時間程度 | 各自治体によって異なる | お近くの窓口直接相談したい方 |
いくつかの無料相談窓口の特徴についてみていきましょう。
【おすすめ】ベンナビ相続|成年後見に注力している近くの弁護士を探せる
成年後見の専門家として信頼できる弁護士に相談したい場合は、「ベンナビ相続」がおすすめです。
ベンナビ相続では、お住まいの地域や相談したい内容を入力するだけで、成年後見に注力している法律事務所を探すことができます。
また、多くの法律事務所が「初回の面談相談料無料」を提供しており、まずは話を聞いてもらいたいという方にも安心して利用できます。
法テラス|経済的に余裕がなくても弁護士や司法書士に相談できる
法テラスでは、収入や資産が一定の基準以下の方に対して、弁護士による無料相談を提供しています。
ただし、無料相談は、1回30分程度を目安に同じ事案につき3回までという制約があります。
法テラスの無料相談は、電話で申込みが可能です。
また、弁護士に依頼する場合の費用を法テラスが立て替えてくれる「民事法律扶助」という制度もあります。
法テラスのサービスは、誰でも利用できるというわけではありませんが、経済的に余裕のない方に特におすすめです。
もっとも、弁護士には受任義務がありません。
法テラスを利用した場合、弁護士の報酬は低額となってしまいますので、引き受けてくれる弁護士が見つからないという可能性もあります。
もし弁護士で依頼できる先生が見つからなかった場合には、司法書士や行政書士などの他の専門職に依頼しましょう。
| 運営元 | 法務省所管 |
|---|---|
| 対象者 | 収入等が一定額以下であること、民事法律扶助の趣旨に適することの要件を満たす者 |
| 相談方法 | 直接面談、電話など |
| 相談時間(目安) | 30分程度 |
| 参考サイト | 日本司法支援センター| 法テラス |
弁護士会|成年後見センターなどで弁護士に相談できる
成年後見については、弁護士会の窓口で相談することもできます。
たとえば、第一東京弁護士会は、成年後見センター「しんらい」を設置しています。
また、弁護士会によっては無料の電話相談を実施しているところもあります。
相談時間は30分程度が目安となりますが、弁護士に直接相談したい方におすすめの相談窓口です。
| 運営元 | 弁護士会 |
|---|---|
| 対象者 | 相談希望者 |
| 相談方法 | 直接面談・電話など |
| 相談時間(目安) | 30分程度 |
| 参考サイト | 日本弁護士連合会|高齢者・障害者に関する法律相談窓口 |
司法書士会|司法書士総合相談センターで司法書士に相談できる
司法書士会は、司法書士が対応する相談窓口「司法書士総合相談センター」を設置しています。
この相談センターでは、様々な法律問題について、司法書士が相談対応してくれます。
また、法テラスと連携し、相談しやすい体制を整えています。
お住まいの都道府県にある相談センターで、面談や電話による無料相談が可能です。
| 運営元 | 司法書士会 |
|---|---|
| 対象者 | 相談希望者 |
| 相談方法 | 直接面談・電話など |
| 相談時間(目安) | 30分程度 |
| 参考サイト | 日本司法書士会連合会|司法書士総合相談センター一覧 |
権利擁護センターぱあとなあ(社会福祉士会)|社会福祉士に無料電話相談できる
権利擁護センター「ぱあとなあ」は、日本社会福祉士会が運営する、権利擁護に関する支援をおこなう専門機関です。
成年後見制度を含む、権利の保護や支援を必要とする方に対して、社会福祉士による無料相談を提供しています。
このセンターは、各都道府県に支部を設置しており、成年後見制度の利用について相談が可能です。
ただし、相談できる回数に制限がある場合もあるため、利用条件や詳細については、事前にお近くの社会福祉士会に問い合わせて確認してください。
| 運営元 | 日本社会福祉士会 |
|---|---|
| 対象者 | 相談希望者 |
| 相談方法 | 直接面談、電話など |
| 相談時間(目安) | 各社会福祉士会によって異なる |
| 参考サイト | 日本社会福祉士会|権利擁護センター「ぱあとなあ」 |
社会福祉協議会|弁護士や社会福祉士に相談できる
社会福祉協議会は、地域福祉の推進を目的とする公的機関です。
日本全国の都道府県や市区町村に設置されており、成年後見制度に関する情報の提供や相談に対応しています。
相談にあたるのは、社会福祉士のほか、社会福祉協議会から紹介された弁護士・司法書士などの専門家です。
成年後見制度に関する基本的な相談であれば、無料で受け付けていますが、具体的な内容やサービスの範囲は地域によって異なる場合があります。
社会福祉協議会への相談を検討している方は、お近くの社会福祉協議会に直接問い合わせてください。
| 運営元 | 社会福祉協議会 |
|---|---|
| 対象者 | 相談希望者 |
| 相談方法 | 直接面談、電話など |
| 相談時間(目安) | 30分程度 |
| 参考サイト | 社会福祉法人|全国社会福祉協議会 |
各自治体の相談窓口|相談員に無料相談できる
各自治体の相談窓口では、成年後見に関する無料相談を受け付けている場合があります。
相談には、自治体の相談員が対応するほか、自治体の要請により弁護士や司法書士などの専門家が対応するケースもあります。
ただし、相談内容は成年後見制度の基本的な説明や利用方法が中心であり、個別具体的なケースについて相談するのは難しいことが多いです。
また、自治体の相談員が、成年後見人の候補者になることはできません。
相談内容や相談可能な時間については、自治体ごとに異なります。
詳細については各自治体のホームページで確認してください。
成年後見制度について無料相談する際の注意点
成年後見制度について無料相談する際には、以下のような注意点について、十分に理解しておく必要があります。
- 相談時間や回数に制限がある
- 事前に予約する必要がある
- 依頼した場合には費用がかかる
相談時間や回数に制限がある
無料相談では、1回の相談が30分程度に限られる場合や、同じ事案についての相談が年に3回までとされる場合など、時間や回数に制限があることが一般的です。
そのため、無料相談を利用する際には、あらかじめ相談したい内容を整理し、優先順位の高い内容から、聞けるように準備しておくことが重要です。
事前に予約する必要がある
基本的に無料相談は、予約なしでは利用できません。
これは、無料相談が多くの方に利用されており、効率的な運営が求められているからです。
このため、無料相談を利用する際には、事前に予約することが必須となっています。
ただし、相談先によっては予約が集中し、空き時間が少ない場合もあります。
予定がわかり次第、なるべく早く予約を取るようにしましょう。
依頼した場合には費用がかかる
無料相談の結果、成年後見制度を利用することが決まった場合、必要書類の収集や作成、申立ての手続きの依頼には費用が発生します。
相談自体は無料でおこなえますが、実際に依頼したあとには費用が発生することついて理解しておきましょう。
成年後見について専門家に依頼するとかかる費用
成年後見について専門家に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
具体的な目安となる金額は、以下のとおりです。
弁護士に相談・依頼した場合の費用の目安
弁護士に相談・依頼した場合の費用の目安は、以下のとおりです。
| 費用項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 相談料 | 無料〜1万円/30分 |
| 申立ての代理 | 15万〜25万円 |
なお、相談料については、初回無料としている法律事務所も多くあります。
【関連記事】成年後見人の弁護士費用はどれくらい?報酬の相場や申立ての手続きについても解説
成年後見制度について弁護士に相談・依頼するメリット
成年後見制度を利用する際には、専門的な知識や経験をもつ弁護士に相談することが重要です。
弁護士は、成年後見制度の仕組みや手続きを詳しく説明するだけでなく、個別の事情に応じた最適な方法を提案してくれます。
また、弁護士のなかには自ら後見人となって支援してくれる場合もあります。
成年後見制度に関する専門家として、弁護士は信頼できるパートナーといえるでしょう。
成年後見制度を弁護士に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。
- 成年後見制度の利用についてアドバイスをもらえる
- 成年後見以外の制度について教えてくれる
- 必要書類の準備や手続きを任せられる
- 行政書士や司法書士とは違い、裁判手続きや複雑な遺産分割の事案への経験を有している
- 後見人候補者として指名できる
成年後見制度の利用についてアドバイスをもらえる
成年後見制度を利用すると、本人を保護・支援するための身上監護・財産管理がおこなわれます。
しかし、この制度にはいくつかのデメリットもあります。
たとえば、コストがかかることや、家族間のトラブルが起こる可能性があることなどです。
そのため、成年後見制度を利用するかどうかは慎重に考えなければなりません。
また、本人の判断能力の程度によっては成年後見制度を利用できない場合もあるでしょう。
こうした状況において、成年後見制度に詳しい弁護士に相談することで、本人や家族の状況に合った最適な方法を提案してもらえます。
必要書類の準備や手続きを任せられる
成年後見制度は、本人や配偶者、4親等内の親族などが申し立てることができます。
しかし、この制度を利用するには申立書などの必要書類を準備したり、家庭裁判所での面接を受けたりする手続きが必要です。
弁護士に依頼すると、このような書類作成などの煩雑な手続きを任せることができます。<?span>
後見人候補者として指名できる
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度のふたつの制度があります。
法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を決めますが、申立ての際に「後見人候補者」を指名できます。
そして、この候補者には、弁護士を選ぶことも可能です。
候補者である弁護士が後見人に選任されれば、後見開始後の財産管理をその弁護士に任せることができます。
成年後見の無料相談に関するよくある質問
最後に、成年後見の無料相談についてよくある質問をみていきましょう。
成年後見人になりたい場合、誰に相談すればよいですか?
成年後見人になりたい場合には、以下の相談窓口に相談することをおすすめします。
- 社会福祉協議会
- お住まいの自治体の相談窓口
- 弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家
なお、相談する際には、なぜ成年後見人になりたいのか、支援したい対象者の状況や必要なサポート内容について事前に整理しておきましょう。
また、上記のとおり、成年後見人に選任する者を選ぶのは裁判所です。
裁判所は、法的な専門家でもない一般の方を成年後見人に選任するのは決して多くはないということに留意しましょう。
成年後見人にかかる費用は無料ですか?
成年後見人にかかる費用は無料ではありません。
成年後見制度を利用する際には、申立て手続きにかかる裁判費用や、成年後見人に支払う報酬が必要です。
具体的には、家庭裁判所に提出する書類の作成費用や、申立て手続きの代行費用、成年後見人として選任された専門家への月額報酬などが発生します。
無料でできるのは、あくまでも制度を利用するための相談のみである点に注意しましょう。
また、無料相談も、あくまでも各専門職がサービスでおこなっているにすぎませんので、そこで悩みを全部解決しようとしたりするような使い方は適していません。
上記のように、成年後見の申立てをおこなうためには、裁判所に提出する資料をそろえたうえで、裁判所の担当者と調整をおこなう必要があります。
専門的な知識、経験を必要とする手続きであることに注意しましょう。
なお、法律事務所によっては、無料での相談を実施していない事務所もあります。
成年後見人の苦情やトラブルに関する相談窓口はどこですか?
成年後見人に対する苦情やトラブルがある場合、成年後見監督人が選任されていれば、まずは成年後見監督人に相談することが一般的です。
成年後見監督人は、家庭裁判所から選任され、成年後見人の事務を監督する役割を担っています。
もし、成年後見人が不正な行為や義務違反をした場合、成年後見監督人は家庭裁判所に対して、解任請求をおこなう権限があります。
そのため、まずは成年後見監督人に相談することが適切です。
もっとも、成年後見人がご本人や親族の思うとおりに行動しない、単に気に入らないというだけでは、成年後見人を解任する理由にはなりません。
また、成年後見人を解任するためには裁判所の判断が必要となります。
さいごに|成年後見についてお悩みの方は弁護士に相談を
成年後見制度を利用する際は、必要書類を準備したり、家庭裁判所への申立てをおこなったりする必要があります。
全ての手続きをご自身でおこなうのは難しいでしょう。
成年後見の専門家として信頼できる弁護士に相談したい場合は、「ベンナビ相続」が便利です。
ベンナビ相続では、住んでいる地域や相談したい内容を入力するだけで、成年後見に注力している法律事務所を探せます。
また、初回の相談料が無料の法律事務所も多数ありますので、「まずは話を聞いてもらいたい」という方にも最適です。
成年後見制度を利用することになった場合には、なるべく早く法律の専門家である弁護士に相談しましょう。