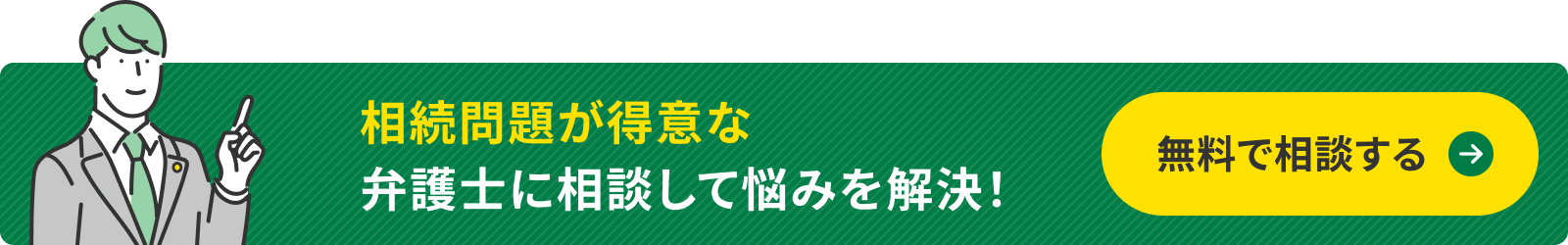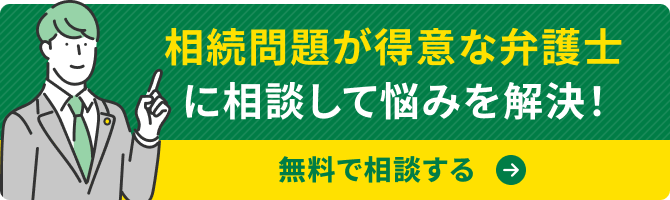遺言書は所定の要件を満たさないと無効になり、自分の想いを実現できない可能性があります。
また、遺言自体は問題なくても、親族が納得してくれなければ「遺留分の請求」といった形で争族に突入するリスクもあります。
トラブルなく遺言を残すためにも、まずは専門家などの無料相談を利用することをおすすめします。
本記事では、遺言書についての無料相談先を紹介します。
あわせて、相談時の流れや専門家ごとの特徴、無効となる遺言の特徴についても紹介するので参考にしてください。
遺言書の相談ができる専門家
遺言書について相談できる専門家は以下の4つです。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
それぞれ相談できる内容や依頼できる内容について特徴があります。
遺言書で作成したい内容や依頼したい作業によって利用すべき相談先が変わるので、自身の状況を整理しながら選びましょう。
弁護士|相続手続き全般・相続トラブルが不安な方
遺言・相続全般について相談したい方の中で、特に遺産や親族関係に悩んでいる方は弁護士への相談がおすすめです。
親族同士での争い防止はもちろん、必要に応じて司法書士や行政書士などの専門家を紹介してもらえるケースもあります。
「相続手続きについて全然わからない」という方はもちろん、「遺言書についてとりあえず聞きたい」という方などにも弁護士はおすすめです。
詳しくは「遺言書の無料相談ができる窓口6選」で後述しますが、弁護士は個別の事務所でも無料相談を実施しているところもあります。
相談したからといって契約を迫られるようなことはないため、まずは気軽に相談してみましょう。
司法書士|遺産に不動産が含まれる方
相続財産が主に不動産の方は司法書士への相談がおすすめです。
司法書士は不動産登記の手続きやその他法務についての知識を持つ専門家です。
相続において不動産はかなり大きな負担となります。
例えば、遺産分割の際、現金であればきれいに割ることができますが、不動産はそうはいきません。
不動産はその物件の所在地を管轄する法務局に登記されているため、相続割合を決めたあとは「相続登記」という名義変更をする必要があるのです。
司法書士は、土地などを持つ相談者から、遺言書の作成段階で相談を受けているケースが多く、争族にならないようにアドバイスをすることも得意としています。
例えば、100m四方の土地を2人で相続する場合、共有名義にしたり50mずつ分けて登記したりする方法があります。
いずれの場合でも、登記事項証明書や相続関係図といったさまざまな書類を入手・作成して申請する手間が発生します。
不動産登記は弁護士・司法書士しか対応できません。
しかし、弁護士はその性質上さまざまな分野を履修しているため、こうした登記手続きに精通しているとは限らないので、司法書士のような登記を得意とする専門家に依頼するのがベターなのです。
行政書士|遺言書作成のみサポートしてほしい方
行政書士にも、遺言書作成について相談・依頼可能です。
行政書士は公正証書遺言や車の登記など、都道府県・市区町村の役場に提出する書類の作成をおこなう専門家です。
行政書士なら、遺言執行者にも適しています。
遺言執行者とは、相続人が被相続人の要望どおりに財産の管理・譲渡をしているか見届けて、必要であれば実施をおこなう人のことです。
相続人も相続人の生活があるので、執行者を代行してくれる人がいるのは大変ありがたいものです。
なお、公正証書遺言や遺言執行者は弁護士でも対応可能です。
税理士|相続財産が多くて相続税が発生する方
相続には相続税の話がつきものです。
税理士は税金のプロフェッショナルであり、唯一税に関して相談できる専門家でもあるので、相続税の計算・書類作成から申告まで全てを実行できます。
相続は始まってしまうとさまざまな手続きが必要となり、相続人の生活を圧迫してしまいます。
税理士に依頼すれば、税金周りの手続きを全て代理で実施してもらえます。
2015年以降、基礎控除により「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」までの相続財産には相続税はかかりませんので、手続きが必要な方は一部だけと思われがちです。
しかし、持ち家や自動車、時計や貴金属といった宝飾品があると、基礎控除部分を超えてしまう可能性もゼロではありません。
なお、税理士の職務上、遺言書の内容自体の相談はできません。
しかし、相続税は誰が相続したかによって変動しますので、そうした内容については相談できます。
相談の仕方にややコツがいるので、事前に調べてから相談をするようにしましょう。
遺言書の無料相談ができる窓口6選
ここでは、遺言書に関する無料相談窓口について解説します。
1.法律事務所
弁護士との法律相談では、30分あたり5,000円程度の相談料がかかります。
しかし、法律事務所の中には「初回相談無料」のところもあります。
当社が運営する「ベンナビ相続」では、相続問題が得意な全国の弁護士を掲載しており、弁護士を探す際はおすすめです。
また、無料相談・電話相談・LINE予約・オンライン面談など、さまざまな相談方法に対応している弁護士も多数掲載しています。
弁護士探しについて以下のような悩みがある方は、ぜひ活用してみてください。
- 無料相談できる弁護士を探したい
- 家の近くで夜まで相談に乗ってくれる弁護士を探したい
- 電話で相談できる弁護士を探したい など
2.法テラス
法テラス(日本司法支援センター)とは、法務省によって設立された誰でも使える法律相談窓口です。
日本全国に窓口があり、民事法律扶助制度に基づいてあらゆる法律相談を受け付けています。
民事法律扶助制度とは、法テラスと契約する弁護士・司法書士との無料相談や、依頼費用の一時立て替えなどが利用できる制度です。
事例に応じて弁護士の紹介なども実施しており、遺言書の作成や財産目録の作成なども依頼可能です。
利用条件はありますが、月々最大1万円での分割支払いで返済していくことで、通常一括で支払う必要がある弁護士費用を分散させることが可能です。
また、通常の法律事務所では無料相談を初回のみに設定していますが、法テラスであれば最大3回まで無料で利用可能です。
ただし、利用条件が設けられていることと、担当してくれる弁護士が選べないなどのデメリットがあります。
【参考元】民事法律扶助業務|法テラス
3.弁護士会の法律相談窓口
各都道府県には、そこで活動する弁護士が加盟する弁護士会が存在します。
弁護士会では住民向けに無料法律相談窓口を設けているところがあり、日常生活や債務整理といったさまざまな法律相談を受け付けています。
弁護士会の法律相談窓口を利用するメリットとしては、誰でも無料で受けられることと、弁護士の紹介が受けられることです。
デメリットとしては、時間制限が厳しいことと、有料相談に移るとき弁護士を選べないことなどが挙げられます。
弁護士会は全弁護士が加盟している組織で、基本的に当番制なので、担当してくれる弁護士が相続問題や遺言書作成などに注力している保証はありません。
また、弁護士会の無料相談では多くの場合30分が上限であるため、事前に相談内容をまとめておかないと要件を話しただけで終了することも考えられます。
もし利用する場合は、事前に下書き程度は作っておくことをおすすめします。
4.市区町村役場の法律相談会
市区町村によっては、無料での法律相談会を実施しているところもあります。
家から近い場所で開催しているのであれば、利用を検討するのもよいでしょう。
ただし、場所によって相談の流れや対応内容などは異なるため、あらかじめホームページなどで詳細を確認しておく必要があります。
5.司法書士総合相談センター
司法書士会が運営する司法書士総合相談センターでは、遺言書作成などの相続に関する相談に対応しています。
基本的には相談料がかかりますが、なかには無料相談に対応しているところなどもあります。
ただし、必ずしも相続問題が得意な司法書士が対応するとはかぎらない、という点は注意が必要です。
6.行政書士会の無料相談会
行政書士が所属する行政書士会でも、相続などのさまざまな分野の法律トラブルに関する相談に対応しています。
地域によっては無料相談できるところもあり、基本的な遺言書の作成方法を知りたい場合などは利用するのもよいでしょう。
遺言書について専門家に相談・依頼するメリット
遺言書は自分で作成しても無効になる可能性があるばかりか、争族の種になったり、財産処分が適正におこなわれなかったりと、相続人の負担を増やす可能性もあります。
法律相談は無料でおこなっている窓口が増えているので、しっかり検討しましょう。
ここでは、遺言書について専門家に相談・依頼するメリットを2つ紹介します。
自分で遺言書作成すると無効になる可能性があるから
遺言書の方式は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つに分けることができます。
そして、自筆証書遺言を法的に成立させるためには、以下4つのルールを守っている必要があります。
- 全文(財産目録以外)を被相続人自身が作成していること
- 作成日が明確であること
- 署名があること
- 押印があること
このうち、よくあるミスがパソコンやワープロで作成してしまうことです。
内容自体は全て自分で考えて書いていたとしても、自筆証書遺言は「自筆」である必要があります。
また、作成日や署名を忘れてしまうこともあります。
なお、秘密証書遺言の場合は、パソコンやワープロで書かれていても問題ありません。
ただし、公証役場で1万1,000円の手数料が必要なほか、法的にふさわしいとされる証人2名を準備しなければなりません。
手間なくスムーズに有効な遺言書を作成できるから
専門家に依頼すると、手間をかけずに正しい遺言書を作成できます。
もし自筆証書遺言を作成するのであれば、以下のような書類が必要です。
- 被相続人の住民票
- 被相続人・相続人の戸籍謄本
- 受遺者の住民票
- 不動産等の登記謄本および固定資産評価証明書 など
なお、相続関係図は必ずしも必要ではありませんが、相続人の確定・相続割合の検討がスムーズに進むため、できれば準備しましょう。
被相続人との続柄によって法定相続割合や相続税は変わってきます。
遺言書の作成においては、相続登記や遺産分割協議書などの複雑な書類の準備が重要なポイントです。
そのため、自身では作成が不安な方も専門家に相談することをおすすめします。
遺言書について無料相談する際の流れ
弁護士などの専門家に遺言書の無料相談をする際の流れを解説します。
事前に用意したほうが良いこともあるので、しっかり準備して向かいましょう。
遺言書について無料相談する際の流れ
- 相談先を探して相談予約をする
- 打ち合わせをする
- 遺言書の原案を作成する
- 遺言書作成に必要な書類を収集する
- 作成した遺言書を保管する
1.相談先を探して相談予約をする
まずは無料相談を実施している法律事務所を選び、電話やメールで問い合わせをしましょう。
相談したい内容と都合の良い日程を伝え、専門家のスケジュールを押さえます。
所在地はなるべく自宅から通いやすいところが望ましいでしょう。
もし田舎で交通の便がよくない場合や、けがや病気で体調がすぐれず外出が難しい場合などは、出張やオンラインの相談を検討してください。
最近では出張してくれるところもありますし、Zoomなどのオンライン相談も可能な法律事務所も増えています。
ベンナビ相続なら、電話相談・出張相談・オンライン相談など、都合のよい条件で弁護士を検索可能です。
専門家選びでお悩みの方はぜひ利用してみてください。
2.打ち合わせをする
日程調整が完了したら打ち合わせをします。
基本的に無料相談では時間制限があるので、事前に相談内容や悩みについてしっかりまとめておきましょう。
まとめておくべきこととして、最低でも親族の状況や遺言で記したい内容などは整理しておきましょう。
すでに自分で書いた遺言書があるなら、それも用意しておきましょう。
打ち合わせの際には、専門家の観点から手直しできることや対応可能な部分などについて教えてもらえます。
同時に見積もりももらえるので、しっかりメモを残しておきましょう。
なお、できれば打ち合わせは複数の事務所とおこなったほうがよいです。
遺言書作成では実現したいことのズレがあってはならないため、担当の弁護士との相性の良さなども重要です。
比較対象を得るためにも、最低2人〜3人と打ち合わせするのがよいでしょう。
3.遺言書の原案を作成する
打ち合わせで出した要望やもらったアドバイスをもとに、遺言書の原案を作成していきます。
原案の作成では通常何往復もするものなので、納得いくまで作成・修正を繰り返しましょう。
なお、公正証書遺言の場合は自筆でなくても問題ありません。
パソコンやワープロでもOKですので、修正しやすい方法で作成しましょう。
相続させたい家財や物品などが決まっている場合、その旨はしっかり弁護士に伝え、原案にも盛り込んでおきましょう。
4.遺言書作成に必要な書類を収集する
遺言書作成を専門家に依頼する場合、必要書類の収集も依頼できます。
遺言書作成で必要となる書類は、役所などの複数の場所で取得しなければなりません。
面倒な場合は依頼してしまいましょう。
ただし、発行に手数料がかかるものや、本人でしか取得できない書類もあります。
弁護士に依頼する場合は、相談料に加えて実費も必要になるので注意しましょう。
必要となる主な書類と手数料は以下のとおりです。
| 相続人・被相続人の戸籍謄本 | 市区町村役場で入手(1通450円) |
|---|---|
| 住民票 | 市区町村役場で入手(1通300円) |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場で入手(1通350円~400円程度) |
| 資格証明書 | 法務局で入手(1通600円) |
| 不動産登記事項証明書 | 法務局で入手(1通600円) |
住民票は相続人以外に相続させる場合に必要になります。
また、資格証明書は法人に相続させたい場合に必要です。
どちらも相続人のみに相続させるなら必要ありません。
5.作成した遺言書を保管する
作成した遺言書はしっかり保管しておきましょう。
公正証書遺言の場合は公証役場に保管されるため、紛失のリスクはありません。
自筆証書遺言はしっかり自分で保管しなければなりません。
相続では、遺言書が見つからないというトラブルがよくあります。
明示しておく必要はありませんが、できるだけ見つけやすいところに保管しておくほうが、相続人の負担を軽減できます。
弁護士や司法書士といった専門家に預けておくという方法もあります。
遺言書作成を専門家に相談・依頼する場合の費用
弁護士などの専門家に自筆証書遺言のサポートや公正証書遺言の作成を依頼した場合の費用相場を解説していきます。
専門家ごとの費用相場
自筆証書遺言の作成に関する相談やサポートを依頼した際の費用相場は以下のとおりです。
| 専門家 | 費用目安 |
|---|---|
| 弁護士 | ・相談料:30分あたり5,000円程度(初回無料のケースあり) ・遺言書作成:10万円~20万円程度 ・遺言執行:費用や財産内容に応じて異なる 例)遺産額が1,500万円以下であれば報酬金は33万円(税込み) |
| 司法書士 | ・相談料:30分あたり5,000円程度 ・遺言書作成:7万円~15万円程度 ・遺言執行:25万円~30万円程度 |
| 行政書士 | ・相談料:30分あたり5,000円程度(初回無料のケースあり) ・遺言書作成:4万円~5万円程度 ・遺言執行:20万円~40万円程度 |
| 税理士 | ・相談料:30分あたり5,000円程度(初回無料のケースあり) ・遺言書作成:6万円~15万円程度 ・遺言執行:50万円程度 |
【関連記事】相続問題の弁護士費用はこれだけ!|相談料・着手金・報酬金の内訳と依頼内容別の相場を知ろう
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記に加えて以下のような費用もかかります。
公正役場への手数料
公証役場へ支払う手数料は、遺言書によって決定する遺産の相続額によって金額が変わります。
金額は公証人手数料令第9条別表により以下のように定められています。
| 遺産額 | 費用 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円+遺言加算1万1,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円+遺言加算1万1,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円+遺言加算1万1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万7,000円+遺言加算1万1,000円 |
| 1,000万を超え3,000万円以下 | 2万3,000円+遺言加算1万1,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 2万9,000円+遺言加算1万1,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円+遺言加算1万1,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円+5,000万円超過ごとに1万3,000円 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円+5,000万円超過ごとに1万1,000円 |
| 10億円を超える場合 | 24万9,000円+5,000万円超過ごとに8,000円 |
【参考元】Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?|日本公証人連合会
なお、公正証書遺言の場合、4枚(法務省令で定める横書きの公正証書は3枚)以上の原本を作成する場合、1枚あたり250円の手数料が発生します。
証人への報酬
公正証書遺言を作成するには、法が定める基準を満たした証人2名を準備する必要があります。
知人や友人に依頼する場合は不要ですが、弁護士や公証人の紹介などで証人を雇う場合には、1人につき1日あたり5,000円〜1万5,000円程度の費用がかかります。
まとめ|遺言書の悩みなら専門家との無料相談がおすすめ
遺言書にはさまざまな形式がありますが、素人が作成しようとすると法的要件を満たさないリスクがあったり、手間がかかったりなどのデメリットがあります。
専門家に依頼すれば費用はかかりますが、適切な形式の遺言書を手間なく作成してもらえます。
相続では、遺言書に端を発して争いになることもあり得ます。
相続人の負担を減らすという意味でも、遺言書作成する際は専門家に相談・依頼したほうが全体的なメリットは大きくなるでしょう。