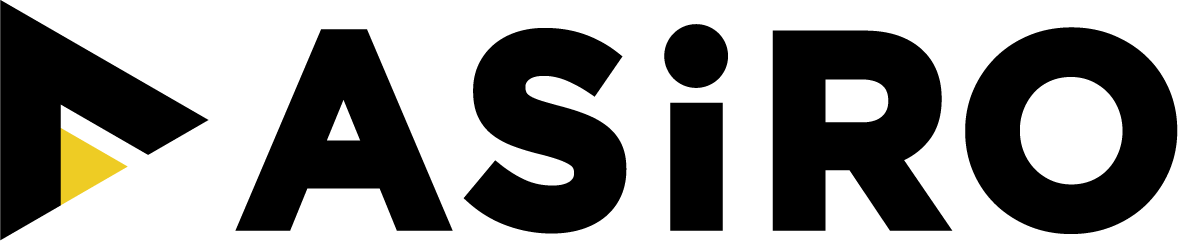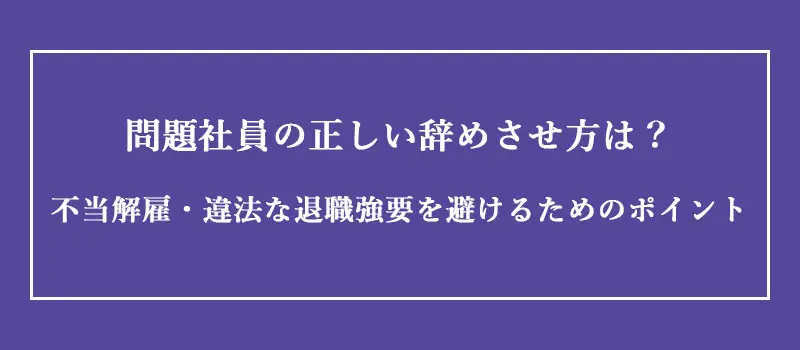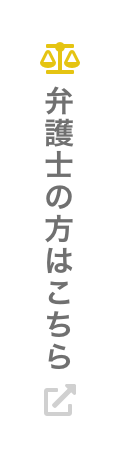会社が労働者を退職させたいと考える場合は、厳しい解雇規制を回避するため、解雇ではなく退職勧奨をおこなうことがあります。
退職勧奨に応じるかどうかは、労働者が任意に判断できます。
会社側の条件提示が適切でなければ、受け入れずに拒否して構いません。
その一方で、好ましい退職条件を提示され、退職後の生活についてもめどが立つ場合には、退職勧奨を受け入れることが有力な選択肢となります。
会社側の提案や態度などを見ながら、退職勧奨を受け入れるかどうか適切に判断しましょう。
本記事では、会社から退職勧奨を受けた労働者が知っておくべきことを解説します。
突然退職勧奨を受けてしまった方は、本記事を参考にしてください。
退職勧奨とは|解雇や退職強要との違い
「退職勧奨」とは、会社が労働者に対して退職を促すことをいいます。
日本の労働法に基づく厳しい解雇規制を回避するため、会社が労働者を退職させたい場合には、解雇ではなく退職勧奨が選択されるケースが多いです。
退職勧奨と解雇の違い
退職勧奨はあくまでも、労働者に対して自発的に退職を促すものです。
これに対して解雇の場合、会社が労働者を強制的に退職させます。
雇用契約を途中で打ち切って強制的に会社から追い出す解雇は、労働者にとって不利益の大きい処分です。
そのため、会社が労働者を適法に解雇するためには、厳しい要件を満たす必要があります。
特に「解雇権濫用の法理」では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効とされています(労働契約法16条)。
一方退職勧奨の場合、労働者は退職に同意しています。
そのため、解雇のような厳しい法規制を適用する必要がありません。
退職勧奨に応じての退職は、労働者が真に同意している限り、どのような理由であっても適法と認められます。
退職勧奨と退職強要の違い
退職勧奨によって労働者の同意を得たという体裁をとっていても、実際には会社が労働者に圧力をかけて、実質的に退職を強要したと評価されるようなケースがあります(=退職強要)。
たとえば、以下のような行為が退職強要の典型例です。
- 暴力・脅迫・ひどい侮辱などを用いて退職を迫る
- 複数人で圧迫面談をおこなって退職へのプレッシャーをかける
- 退職したくなるように全く仕事を与えない、または簡単すぎる仕事だけをひたすらおこなわせる など
退職勧奨を受けての退職に厳格な解雇規制が適用されないのは、労働者が真の意思によって退職に同意しているためです。
退職強要がおこなわれた結果の退職は、「労働者の真の意思による同意」という前提を欠いています。
そのため、解雇に準じて厳格な解雇規制が適用され、退職が無効となる可能性が高いです。
もし退職強要を受けた場合には、速やかに弁護士へご相談ください。
一般的な退職勧奨の流れ|3ステップ
退職勧奨は一般的に、以下のような流れでおこなわれます。
- 上司から呼び出され、退職してほしいと促される
- 退職条件について交渉する
- 会社に対して結論を伝える
1.上司から呼び出され、退職してほしいと促される
退職勧奨は、上司から個室などに呼び出されて、1対1で退職してほしい旨を伝える形でおこなわれることが多いです。
退職勧奨を受けたら、動揺する気持ちを抑えて冷静に対処しましょう。
会社の言うとおりに退職する義務はありませんし、会社の言い分を聞いてから適切に判断すればよいからです。
退職勧奨を受けた際には、退職届を書くように求められることがありますが、すぐに応じてはいけません。
必ず持ち帰って検討する旨を伝えましょう。
なお、退職勧奨をおこなう会社側の担当者が多人数であるケースや、密室に閉じ込められて長時間にわたり退職勧奨を受けるケースもあるようですが、いずれも不適切と考えられます。
このような退職勧奨は、実質的に退職を強要していると評価される可能性が高いです。
もし不適切な退職勧奨を受けたら、速やかに弁護士へ相談しましょう。
2.退職条件について交渉する
退職勧奨を受けて退職するかどうかは、退職条件の内容も踏まえて判断すべきです。
会社が提示する退職条件に納得できなければ、改善を求めて交渉しましょう。
交渉の対象になる退職条件の例としては、退職金の増額や有給休暇の買い取り、再就職先のあっせんなどが挙げられます。
納得できる退職条件の提示を受けられなければ、退職勧奨に応じてはいけません。
3.会社に対して結論を伝える
退職するかどうかを判断したら、その結論を会社に対して伝えます。
回答期限が設けられている場合には、その期限までに結論を伝えましょう。
退職する場合には、会社に対して退職届を提出するか、または会社との間で退職合意書を締結します。
退職勧奨を受けたときに確認・検討すべき3つのポイント
会社から退職勧奨を受けたら、主に以下の3点を確認・検討しましょう。
- 現在の会社における待遇や将来性などを確認・検討する
- 転職できるかどうかの見込みを検討する
- 会社が提示する退職条件を確認する
なお、退職勧奨が強制やパワハラに当たる場合は違法です。
不適切な形で退職勧奨を受けたら、速やかに弁護士へご相談ください。
現在の会社における待遇や将来性などを確認・検討する
退職するかどうかを検討する際には、まず現在の会社に残り続けたらどうなるかをシミュレーションしましょう。
現在の会社における待遇が十分であり、かつ将来にわたって待遇の改善が期待できる場合には、退職するとデメリットの方が大きいと考えられます。
この場合、退職勧奨を拒否する方向に傾くでしょう。
これに対して、待遇がそれほど良くなく、かつ将来的にも改善が期待できない場合には、現在の会社にこだわる必要はありません。
納得できる退職条件が提示されれば、退職を前向きに検討してもよいでしょう。
また、働きやすさの観点からも、現在の会社に残り続けるべきかどうかを検討しましょう。
残業が少なく時間の融通が利きやすいなど、働きやすい環境が整っている場合には、待遇が今一つでも現在の会社に残った方がよいかもしれません。
これに対して、残業が多すぎるなどの理由でワークライフバランスを確保しにくい場合には、退職して環境を変えることも有力な選択肢です。
働くことに対して何を求めるかは、人によって異なります。
ご自身の希望や家庭の状況などと照らし合わせて、現在の会社がよい環境なのか、それとも手放してよい環境なのかを適切に判断しましょう。
転職できるかどうかの見込みを検討する
現在の会社を退職したと仮定して、転職先がすぐ見つかるかどうかも考慮すべき重要なポイントです。
なかなか転職先が見つからないようであれば、安易に退職勧奨に応じるべきではありません。
たとえば転職エージェントに登録するか、または連絡をとり、自身の希望に合った求人情報が見つかるかどうかをチェックするとよいでしょう。
早期から転職の可能性を探れば、退職勧奨の交渉における方針を適切に定めることができます。
なお、転職活動に時間がかかりそうな場合は、退職勧奨への回答期限を後ろ倒しにしてもらったり、退職時期を遅めに設定したりすることが考えられます。
転職活動の状況を踏まえつつ、会社との間で適切に交渉しましょう。
会社が提示する退職条件を確認する
退職勧奨を受けて退職するかどうかは、労働者が自由に判断できます。
つまり、退職勧奨の交渉において、労働者は会社よりも有利な立場にあるということです。
労働者としては、会社が提示する退職条件に納得できなければ、退職勧奨に応じるべきではありません。
退職勧奨の際に会社が提示する退職条件が妥当であるかどうかは、弁護士のアドバイスを受けると適切に判断できます。
退職金の相場額などについても、弁護士に相談すれば過去事例などを踏まえたアドバイスを受けられます。
会社から退職条件の提示を受けたら、一度弁護士にご相談ください。
退職勧奨を受け入れて退職する場合の退職金相場
退職勧奨を受け入れて退職する場合は、通常の自己都合退職よりも退職金が増額されるケースが多いです。
具体的な退職金の額は、会社との労働者の間の交渉などによって決まります。
そのため一概に言えませんが、賃金の6か月分から1年分程度の退職金が支払われるケースが多いようです。
適正な退職金額は、勤続年数などの事情によっても変わります。
特に、長期間にわたって勤続した方が退職する際には、賃金の1年分を上回る退職金が支払われるケースも少なくありません。
弁護士のアドバイスを踏まえて、会社が提示する退職金の額が適切であるかどうかを確認しましょう。
退職勧奨を受け入れる場合と断る場合の伝え方
退職勧奨を受け入れる場合と断る場合のそれぞれについて、会社に対する伝え方を紹介します。
なお、退職勧奨を受けた場合の具体的な対応については、以下の記事も併せてご参照ください。
退職勧奨を受け入れる場合の伝え方
退職勧奨を受け入れる場合は、まずその旨を会社側に対して口頭で伝えましょう。
その際、前提となる退職条件についても確認しておきます。
その後、会社側に対して退職届を提出するか、または会社との間で退職合意書を締結します。
退職届を提出する場合は、会社に対して退職条件を記載した書面の交付を求めましょう。
口約束だけで退職条件を決めると、後で会社に前言撤回されてトラブルになるおそれがあるので注意が必要です。
退職条件を確約する書面の交付を受けるまでは、退職届を提出してはいけません。
まずは口頭での伝達を先行させ、会社との調整を経た後、正式に退職の意思を書面で会社に伝えましょう。
退職勧奨を断る場合の伝え方
退職勧奨を断る場合は、端的にその旨を会社に伝えれば足ります。
断ったことを明確化するため、書面を会社に対して交付しましょう。
退職勧奨を断ったにもかかわらず、なおもしつこく会社が退職を求めてくる場合には、違法な退職強要に当たる可能性があります。
その場合は、弁護士にご相談ください。
不本意に退職勧奨を受け入れてしまったらどうすべき?
不本意に退職勧奨を受け入れてしまっても、退職せずに済む道は残されています。
以下の対応を検討しましょう。
承諾の通知前|退職届の提出をやめる
会社に対して退職届を提出しておらず、退職合意書もまだ締結していない場合には、退職届の提出をとりやめましょう。
口頭では退職勧奨を受け入れる旨を伝えていても、退職届を提出しなければ、正式な意思表示がなかったものとして退職せずに済む可能性があります。
承諾の通知後|退職の取り消しを主張する
すでに会社に対して退職届を提出しており、または退職合意書を締結している場合には、退職の取り消しを主張しましょう。
退職の取り消しが認められるケースとしては、以下の例が挙げられます。
- 錯誤(民法95条)
重要な退職条件を勘違いしていた場合には、錯誤に基づく取り消しが認められる可能性があります。
ただし、その退職条件を前提として退職することを、会社に対して表示していたことが必要です。 - 詐欺(民法96条)
退職条件などにつき、会社に騙されて退職に同意した場合には、詐欺に基づく取り消しが認められます。 - 強迫(民法96条)
会社に脅されて退職に同意した場合には、強迫に基づく取り消しが認められます。
退職勧奨に関するQ&A
退職勧奨について、よくある質問と回答をまとめました。
- Q.退職勧奨を受けたら、退職したほうがよいのか?
- Q.退職勧奨によって退職する場合は会社都合退職?それとも自己都合退職?
- Q.退職勧奨を受けてから、実際に退職するまでの期間はどのくらい?
- Q.転職活動をする場合、退職理由をどのように説明したらよいのか?
- Q.「退職勧奨を拒否したら解雇する」と会社に言われたらどうすべき?
Q.退職勧奨を受けたら、退職したほうがよいのか?
退職勧奨を受けたとしても、退職した方がよいとは限りません。
退職勧奨に応じるかどうかは、退職した場合のメリットとデメリットを総合的に考慮して判断すべきです。
具体的には、現在の会社における待遇の良し悪しや将来性、転職活動の見通し、会社が提示する退職条件などが判断材料となります。
特に退職条件については、納得できなければ会社と交渉して改善を求めましょう。
Q.退職勧奨によって退職する場合は会社都合退職?それとも自己都合退職?
雇用保険の基本手当の受給との関係では、退職勧奨を受けて退職する場合は会社都合退職に当たります(=特定受給資格者)。
したがって、自己都合退職よりも有利な条件で雇用保険の基本手当を受給可能です。
退職勧奨を受けての退職であるにもかかわらず、会社が自己都合退職として書類を記載してしまった場合には、会社に対して修正を求めましょう。
会社が修正に応じない場合は、ハローワークに対して雇用保険の基本手当の受給を申請する際、退職勧奨がおこなわれたことを証拠資料を提示しながら説明しましょう。
Q.退職勧奨を受けてから、実際に退職するまでの期間はどのくらい?
退職勧奨を受けてから実際に退職するまでの期間は、会社と労働者の交渉によって決まるので一概に言えません。
早ければ数週間程度で退職するケースがありますが、数か月程度を経て退職するケースもあります。
なお、退職前に有給休暇を取得することは労働者の権利です。
有給休暇を取得する場合、退職日は原則として有給休暇をすべて消化した後の日付になります(ただし、有給休暇を買い取る代わりに退職日を前倒しするケースもあります)。
会社に有給休暇の取得を拒否されたら、弁護士または労働基準監督署に相談しましょう。
Q.転職活動をする場合、退職理由をどのように説明したらよいのか?
転職活動に当たって、前職の退職理由を詳しく説明する必要はありません。
「一身上の都合により退職した」「キャリアの方向性を変えるために退職した」など、嘘にならない範囲で適宜回答すれば大丈夫です。
Q.「退職勧奨を拒否したら解雇する」と会社に言われたらどうすべき?
違法な退職強要に当たる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
そのほかにも、会社が強引な手段で退職勧奨をおこなってくる場合には、弁護士を代理人として対応することをおすすめします。
さいごに|退職勧奨について疑問があるなら弁護士に相談するのがおすすめ
会社から退職勧奨を受けたときは、退職のメリットとデメリットを総合的に比較衡量して、退職勧奨を受け入れるかどうか適切に判断しましょう。
退職勧奨を受け入れるかどうかの判断に迷う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
ご自身の希望や家庭の状況などを踏まえつつ、法律・労働実務の観点から、何を考慮して検討すべきかについて有益なアドバイスをしてもらえるでしょう。
また、退職勧奨の方法が強引である場合などにも、弁護士に相談しましょう。
もし違法な退職強要に当たる場合には、弁護士が代理人として会社に立ち向かってくれます。
「ベンナビ労働問題」には、労働問題に精通した弁護士が多数登録されています。
相談内容や地域に応じて、スムーズに弁護士を検索可能です。
会社から退職勧奨を受けて、どのように対応すべきか悩んでいる方は、「ベンナビ労働問題」を通じて弁護士にご相談ください。