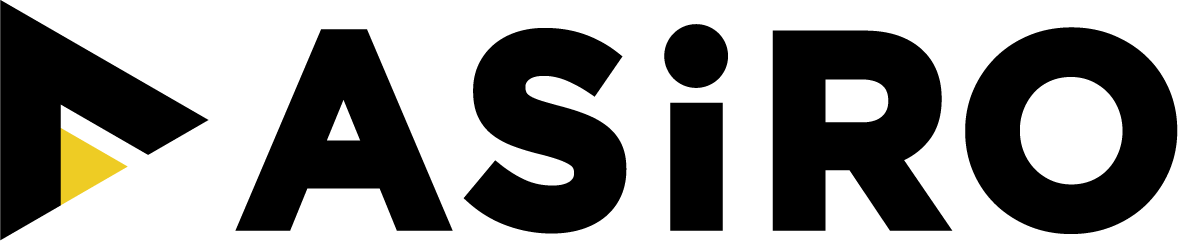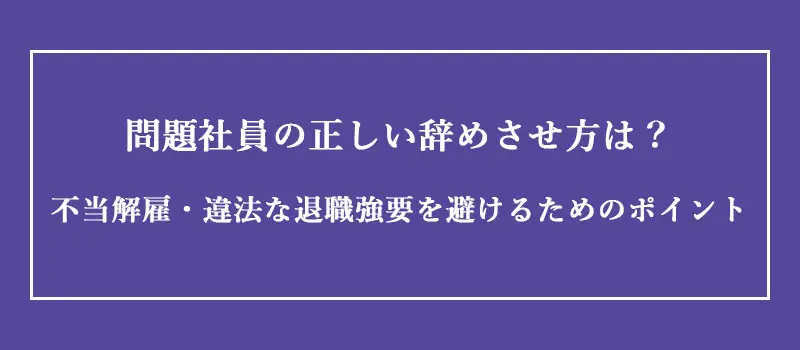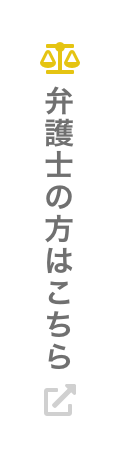- 「会社に長時間働かされているが、違法ではないか」
- 「残業代をきちんと支払ってもらっていない気がする」
- 「36協定とは、どんなものだろう」
長時間労働や残業代未払いなどの問題に悩み、調べていたところ36協定というものがあることを知った方もいるでしょう。
会社が従業員に時間外労働や休日出勤をさせる際は、36協定の締結が必要です。
本記事では、36協定とはなにかや36協定の詳細、36協定に関わるトラブル事例、会社が36協定に違反している場合の相談先について解説しています。
36協定とは|労働者に時間外労働をさせるために必要な協定
「36協定」とは、会社が従業員に時間外労働や休日労働をさせる際に必要な労使間の協定のことです。
36協定は、会社と労働者の過半数で組織される労働組合や労働者の過半数を代表する方との間で締結することが義務づけられています。
36協定を締結した場合、労働基準監督署への届出が必要です。
36(サブロク)協定という名称は、本協定の詳細が労働基準法第36条で定められていることに由来しています(正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」)。
36協定を締結せず労働者に時間外労働をさせると違法となる
労働基準法では、雇用主が労働者を働かせてよい時間の上限と休日について以下のように定めています。
- 法定労働時間
原則として1日に8時間・1週間で40時間を超えて働かせることはできない(労働基準法第32条1項) - 法定休日
最低でも週に1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない(労働基準法第35条1項)
ただし、会社の業務によっては法定労働時間内でしか働けなかったり、休日労働ができなかったりすると、成り立たないこともあります。
会社が法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせたりする必要がある場合に、36協定を締結することになるのです。
36協定における時間外労働と一緒に覚えておきたい「所定労働時間」とは
法定労働時間と混同しやすい言葉として、「所定労働時間」があげられます。
この2つは似ていますが、異なる内容を意味するので注意が必要です。
所定労働時間とは、会社が定めた労働時間を指します。
たとえば会社が就業規則などで定めた勤務時間が9時00分~17時30分(休憩1時間)なら、所定労働時間は以下のようになるのです。
- (17時30分-9時00分)-1時間=7.5時間
一方で残業代の対象となるのは、法定労働時間を超えて働いた分で、この時間のことを時間外労働といいます。
上の所定労働時間を例にとって、どういうことか考えてみましょう。
たとえばこの会社の従業員が18時まで働いたとします。
この場合、1日8時間働いた計算となり、所定労働時間より30分多く働いたことになりますが、この30分は残業代の対象となりません。
所定労働時間より長く働いたとはいえ、働いた時間が法定労働時間である8時間以内だからです。
次に、従業員が18時30分まで働いたとしましょう。
この場合の労働時間は1日8.5時間となり、法定労働時間より30分長く働いていることになります。
この30分が時間外労働という扱いになり、残業代支給の対象となるわけです。
所定労働時間を超えて働いたものの、法定労働時間内である時間を「法定内残業」とも呼びます。
上記18時まで働いた例でみると、所定労働時間を超えて働いたものの残業代の対象とならない30分が法定内残業です。
36協定による時間外労働・休日労働の上限時間
36協定を締結することによって、「時間外労働」や「休日労働」をさせることができるといっても、以下のとおり時間制限があります。
原則|月45時間、年360時間が上限
36協定で雇用主が労働者に求めることができる時間外労働・休日労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
臨時的で特別な事業がない限り、雇用主は労働者にこれ以上働かせることはできません。
特別条項の場合|原則以上の時間外労働が可能
以上が原則ですが、オプションとして特別条項を付けることで、上記の上限を超えて時間外労働をさせることができます。
特別条項が付いているかどうかで上限時間が変わるため、注意が必要です。
特別条項が付いた場合、雇用主は以下にあげるルールの範囲内で、労働者を働かせることができます。
- 1ヵ月の時間外労働と休日労働の上限は合計100時間未満
- 1年間の時間外労働の上限は720時間以内
- 1ヵ月45時間を超える時間外労働が認められるのは、1年間で6ヵ月(6回)以内
- 2~6ヵ月平均の上限は80時間以内
36協定の対象者|労働基準法上の労働者が対象
36協定は労働基準法36条に基づくので、対象となるのは労働基準法上の「労働者」(労働基準法第9条)です。
対象者|会社に使用されて、賃金を支払われる者
労働基準法上の「労働者」は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定められています(労働基準法第9条)。
使用されて賃金を支払われる者と定義されているので、雇用形態は問いません。
正社員ではない契約社員、パート、アルバイトなども「労働者」にあたります。
対象外|労働基準法上の労働者にあたらない者や18歳未満の労働者など
以下にあてはまる方は「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」という労働基準法上の労働者には該当しないため、36協定の対象外となります。
- 役員(労働者でなく労働基準法上の「使用者」に該当する)
- 派遣社員(派遣元の事業者と雇用関係にあるため、派遣先の「事業又は事務所に使用される者」ではない)
- 業務委託の方
- 業務請負の方
- 管理監督者(労働基準法第41条2号)
最後の管理監督者は注意が必要です。
管理職であれば管理監督者にあたるわけではありません。
管理職に当たるかどうかは、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。
- 職務の内容や権限などから見て経営者と一体的な立場にあるか
- 勤務態様が労働時間の管理になじまないものかどうか
- ほかの一般の労働者に比べて管理監督者にふさわしい待遇か
そのほかにも、36協定の対象とならないケースがあります。
- 18歳未満の者
- 育児や介護を理由とした請求がある場合
- 妊産婦から請求がある場合
18歳未満の方には時間外労働を命じることができません(労働基準法60条)。
また、未就学児を養育する労働者から育児を理由とした請求があったときは、月24時間・年150時間を超えて時間外労働をさせることはできません(育児介護休業法17条)。
要介護状態にある家族を介護する労働者から、介護を理由とした請求があったときも同じく、月24時間、年150時間を超えて時間外労働をさせることはできません(育児介護休業法18条)。
妊産婦から請求があったときも、時間外労働をさせることはできません(労働基準法66条2項)。
妊産婦とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性のことをいいます。
36協定の上限規制が猶予・除外となる業種・業務
以下にあげる業種・業務は、36協定の上限規制の適⽤が、2024年3月31日まで猶予されています。
建設事業
1つ目は、建設事業です。
2024年3月31日まで上限規制が適用されません。
2024年4月1日以降は、災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制が全て適用されます。
災害の復旧・復興の事業だけは特別であり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
ただし、年の上限「360時間、特別条項ありの場合は720時間」は適用されます。
自動車運転の業務
2つ目は、自動車運転の業務です。
2024年3月31日まで上限規制は適用されません。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
また、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとする規制は適用されません。
2024年4月1日以降は、特別条項付き36協定を締結すると年間の時間外労働の上限が年960時間に制限されます。
医師
3つ目は、医師です。
2024年3月31日まで上限規制は適用されません。
2024年4月1日以降は、以下のとおり分類され、医師ごとに異なる上限が適用されます
- 一般的な医師の時間外労働の上限水準(A水準:上限は年960時間、月100時間未満)
- 地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずA水準を超える場合の水準(B水準・連携B水準:上限は年1860時間、月100時間未満〔例外あり〕)
- 一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水準(C-1水準・C-2水準:上限は年1860時間、月100時間未満〔例外あり〕)
鹿児島県と沖縄県における砂糖製造業
4つ目は、⿅児島県および沖縄県における砂糖製造業です。
2024年3月31日までは、時間外労働と休⽇労働の合計について、⽉100時間未満、2〜6カ⽉平均80時間以内とする規制は適用されません。
2024年4月1日以降は上限規制が全て適用されます。
新技術・新商品等の研究開発業務
5つ目は、新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務です。
この業務については猶予されているのではありません。
36協定の上限規制の適用が「除外」されています(労働基準法36条11項)。
ただし、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が⽉100時間を超えた労働者がいた場合、医師の⾯接指導が義務づけられています。
これに違反すると罰則があります(労働安全衛生法66条の8の2)。
36協定に関するトラブル事例4選
36協定に関するよくあるトラブル事例を4つ紹介します。
1.そもそも会社が36協定を締結していなかった
1つ目は、そもそも会社が36協定を締結していなかったというケースです。
仮に会社と労働者との間で暗黙の了解などがあったとしても、36協定を締結して所轄の労働基準監督署長へ届出しなければなりません。
2.時間外労働が上限時間を超えてしまっている
36協定を締結・届出していたとしても、月45時間、年360時間という制限を超えてしまっているケースがあります。
特別条項つきの36協定であればこの制限を超えることもできますが、特別条項つきで認められている時間さえも超えているケースもあるのです。
3.特別な事情がないのに上限を超えてしまっている
前述したとおり、特別条項付きの36協定であれば月45時間、年360時間という制限を超えることが認められています。
ただし、以下のような臨時的な特別な事情がある場合に限られているのです。
- 大規模なクレーム
- 予算・決算業務
- ボーナス商戦による業務の繁忙化など
このような臨時的な特別な事情がないのに上限を超えて働かせているケースがあります。
4.サービス残業をするよう会社から命令されている
36協定で定められた上限時間を超えたくないばかりに、会社が労働者に対してサービス残業をするよう命じているケースがあります。
労働基準法に違反するだけでなく、残業代も請求できます。
36協定違反や残業代未払いなどに関する主な相談先
会社が36協定に違反しているかもしれない場合や、残業代未払いに関する主な相談先は以下の3つです。
労働条件相談ほっとライン|違法に残業させられている場合などに相談が可能
1つ目は、労働条件相談「ほっとライン」です。
この窓口では、違法に残業をさせられている場合や残業代未払いなどのトラブルについて電話で相談できます。
専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例をふまえた相談対応や各関係機関の紹介などをおこなってくれます。
誰でも無料で全国どこからでも利用できるのに加え、匿名での相談も可能です。
労働基準監督署|会社の36協定違反を通報できる
2つ目は、労働基準監督署に申告する方法です。
労働基準監督署とは、会社が法令を遵守しているかをチェックする機関で、全国に設置されています。
会社が36協定に違反していれば、労働基準法を違反していることにもなるので、労働基準監督署が会社に是正勧告をしてくれることが期待できます。
弁護士|36協定違反かどうかの判断などをしてもらえる
3つ目は、弁護士への相談です。
弁護士に相談することで、36協定に違反しているか正しく判断してくれるうえに、法的な観点から対処法をアドバイスしてくれます。
また弁護士に対応を依頼すれば、依頼者にかわり会社と直接交渉してもらうことも可能です。
会社は弁護士から通知が来るだけで態度を改め、依頼者の要求に応じる可能性も少なくありません。
いずれにしろ、弁護士に依頼することで、会社との交渉をスムーズにすすめられるでしょう。
全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ労働問題」には、36協定違反や残業代の未払いトラブルを含め労働問題の対応を得意とする弁護士が多数登録されています。
地域別や無料相談可否などの条件で希望にあう弁護士を簡単に探せるので是非活用ください。
36協定に関するよくある質問
ここからは、36協定に関するよくある質問を4つ紹介します。
Q.会社が36協定を締結しているかどうか確認する方法は?
会社が36協定を締結している場合、以下の方法で内容を確認できます。
- オフィスや工場などに掲示された労使協定の内容を確認する
- 従業員に配布された労使協定に関する書面を確認する
- 社内サイトなどにアップされた、労使協定の説明・ファイルを確認する
もし、これらの方法で確認できない場合、会社の人事担当者などに労使協定の提示先を確認しましょう。
たとえば書面を紛失していれば、会社に依頼することで再発行に応じてくれる筈です。
もし会社が提示を拒んだ場合、労働者に対する周知義務を怠っていることになります(労働基準法第106条1項)。
万が一、開示に応じてくれない場合は労働基準監督署や弁護士への相談を検討しましょう。
Q.会社が36協定を締結していなかった場合の残業代の扱いは?
会社が36協定を締結していなかったとしても、残業代を請求できます。
会社が36協定を締結せず残業(時間外労働)をさせていた場合は違法なので、会社側に法的なペナルティが科せられることにはなりますが、労働者が不利に扱われることはありません。
残業をした事実があれば残業代を請求できるのです。
Q.会社が36協定に違反した場合はどのような罰則を受けるのか?
36協定を締結していないにもかかわらず、会社が従業員に時間外労働・休日労働をさせた場合、会社は「6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科される可能性があります(労働基準法第119条1号)。
また、会社だけでなく、労務管理を担当する責任者などの上司が処罰の対象になることもあります(労働基準法第10条「使用者の定義」)。
さらに、労働基準監督署が会社を送検すると企業名が公表される可能性があります。
法律は、届出をせずに時間外労働を課している会社に厳しい姿勢をとっています。
Q.働き方改革関連法の施行に伴い36協定はどのように変わったか?
働き方改革関連法案の施行により、労働時間について下記の制限が加えられることとなりました。
- 特別条項付きの場合、月40時間の時間外労働を上回ることができるが、回数は年6回まで。
- 特別条項を締結していても、時間外労働は「年間720時間」「休日労働を含み、単月で100時間」「休日労働を含み、2ヵ月ないし6ヵ月平均で80時間」を超えることはできない
働き方改革関連法案が施行されるまでの「特別条項付き36協定」は、時間外労働の延長時間に上限がないことが問題視されていたため、この点が是正されました。
さいごに|会社の36協定違反は専門窓口に相談・通報しよう
36協定は、労働者に時間外労働や休日出勤を命じるのに必要な労使協定です。
会社が36協定を締結せずに時間外労働や休日出勤を命じている場合は違法となります。
また36協定の制限を超えて、時間外労働を強いているケースも違法です。
実際、会社が違法に時間外労働をさせているケースや、残業代を適切に支払っていないケースは少なくありません。
このようなケースでは、労働基準監督署に通報したり弁護士に相談したりといった対応を検討ください。
たとえば弁護士に相談すれば、法的な観点から有効なアドバイスをしてくれるでしょう。
弁護士に対応を依頼すれば、会社に是正するよう直接交渉してもらうことも可能です。
弁護士を探す際は、労働問題の対応を得意とする全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ労働問題」をおすすめします。
ベンナビ労働問題では、地域別や無料相談可否などの条件で希望にあう弁護士を簡単に検索可能です。
弁護士へ相談し、労働問題をなるべく早く解決しましょう。