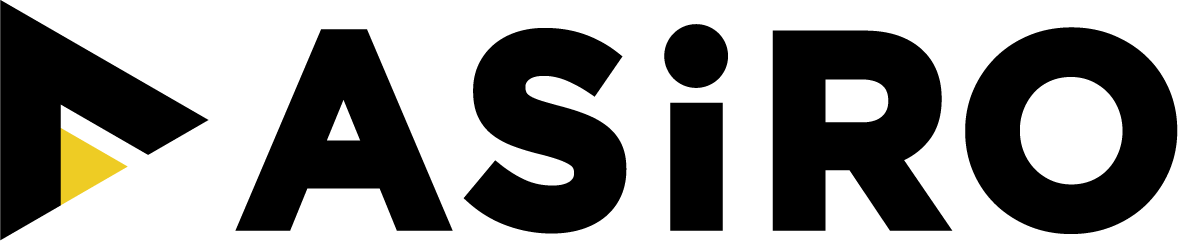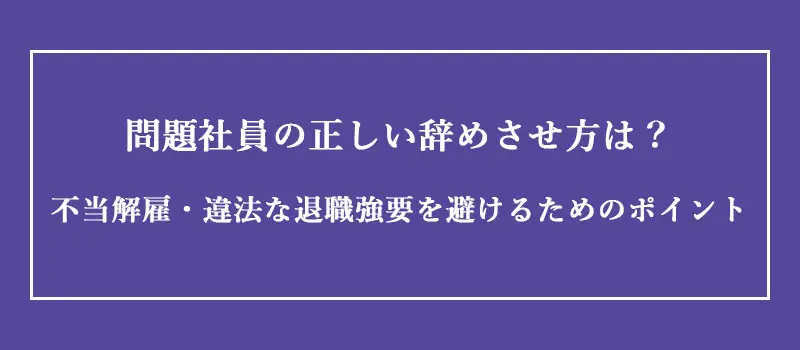自爆営業(じばくえいぎょう)とは、企業に務める従業員が、ノルマ達成などのために自社商品を購入することを言います。
なぜ自社の売上のために身銭を切ってまで商品を購入するような非合理なことをしてしまうのでしょうか?
今回は、自爆営業をしてしまう4つの理由と事例、問題点と対処法をお伝えします。
自爆営業をしてしまう4つの理由
まず、自爆営業をしてしまう理由をお伝えします。
ノルマが達成できないほどキツイから
自社の従業員に厳しいノルマを課し、達成できなければ自分で商品を購入させるのが自爆営業です。
成績が悪いと評価が下がったり、怒られたり、時にはクビになったりすることもあるかもしれません。
上からの指示がなくても、バレないように自分で商品を購入してしまう人もいるでしょう。
会社が儲けられないから
会社側がそもそも売れ行きが下火の商品にしがみつき、ニーズに合っていないようなノルマを課すこともあります。
本来ならば、売れる商品を開発したり既存商品のバージョンアップをしたり、ターゲットを変えたりと経営努力をする必要があります。
しかし、命令権限のある社員が昔の功績や自分の時代をベースに販売自体を考えることで、現在ではニーズのない商品を末端の社員が売らねばならず、売れない商品を売らされているのに尻拭いもさせられるようなことが起こり得ます。
社員を追い詰めていくような社風や仕組みがある
ノルマを達成できない場合に過度な叱責がある会社だと、社員は上司に相談しにくくなり、怒られるのを回避するために自分で商品を買ってしまいます。
いくら上が理不尽だろうが理にかなっていなかろうが、上に嫌われてしまうと給与や待遇が悪くなったり、クビにされたりする可能性もあるため、転職を考えていない人ほど泣き寝入りせざるを得なくなります。
自爆営業が蔓延する会社ではパワハラがまかり通っている可能性も
ノルマを達成できない分を自分のお金で買うような合理的ではない行為をするということは、会社でパワハラがまかり通っていて自爆営業をせざるを得なくなっている可能性があります。
仕事ができた上司の中に、自分ができたことを部下にも強要してくる人はいないでしょうか。
会社全体で売上が伸びない社員を追い詰めるような社風ができており、パワハラがまかり通っているような職場では、自爆営業をしてしまう社員がいるのも自然なことなのかもしれません。
自爆営業の事例
ここでは、自爆営業の事例をご紹介します。
事例1|年賀はがきの販売に厳しいノルマを課す事例
ノルマを達成できなかった郵便局員が、自分で年賀はがきを買い、金券ショップに売る場合があるようです。
スマートフォンが普及した現在では、毎年年賀はがきの販売数が落ちているのにも関わらず、販売ノルマは変わらないのだそうです。
売れなかった場合は、真冬の屋外に立たされて路上販売をさせられることもあるのだとか。
そこまでするぐらいだったら自分で買ってしまう人がいるのも頷けますね。
事例2|バスの手配に失敗して、遠足自体を中止に追い込もうとした事例
バスの手配を失敗したJTB中部多治見支店の男性社員が、自殺をほのめかす高校生のふりをした手紙を書き、高校に送り付けて遠足自体をなくそうとした事例です。
ミスで手配に失敗したと上司に報告できる社風がないために、言い出せず隠蔽工作に走った可能性があります。
隠蔽をした元社員がしたことは許されることではありませんが、上司に報告できないような社風があったことも見逃す訳にはいきません。
自爆営業の問題点
自爆営業には、具体的に次のような問題点があります。
違法
自爆営業は違法です。
給与の一部を商品で提供したと考える事もできるため、給料不払いにあたる可能性があります。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
引用元:労働基準法第24条1項
また、ノルマを達成できないからと、社員の意志に関係なく商品を購入させた人は、刑法第223条1項に抵触し、3年以下の懲役に処せられる可能性があります。
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
引用元:刑法第223条1項
会社の業績の悪さを社員が尻拭いすることになる
売れない商品を社員に売らせ、現実のニーズを反映していないノルマを課している場合は、会社の尻拭いを社員にさせていることになります。
昔売れた商品が今も売れるとは限りません。
あまりにも現実に即していない目標を掲げるような会社では、長く働きたくないものです。
一回買えば済むわけではない
一度、自爆営業をすれば済むわけではありません。
そもそもニーズのない商品を売っているのだとしたら、また同じように売れないものに厳しいノルマが課される可能性もあります。
自爆営業をしたとしても、達成できないノルマという目先の問題からは逃れられますが、ニーズのない商品を厳しいノルマでまた売らされる可能性があるという根本的な問題からは逃れられません。
クーリングオフできない
業者とその従業員の間でなされた契約はクーリングオフできません。
不要な商品を買ってしまっても返品ができないため、金券ショップで売るなどの対処法しかできなくなりますが、それでも全額が返ってくるわけではないので販売員が損をすることに変わりはありません。
自爆営業を強要されたときの対処法
ここまででお伝えしたように、自爆営業があるような会社ではパワハラがまかり通っていたり、商品のニーズがないために売上が伸びない事のしわ寄せを社員に押しつけたりする社風があるため、ひとりの力だけではなかなか解決できないかもしれません。
ここでは、自爆営業を強要させられた際の対処法をお伝えします。
証拠をとっておく
自爆営業を強要された証拠やパワハラの証拠をとっておきましょう。
ボイスレコーダーで相手の発言を録音するのもよいですし、ノートにボールペンで何月何日に誰に何と言われたのか、何をいくら買わされたのかを記入しておくとよいでしょう。
自分の主張を証明することを考えるのであれば、のちに証拠が必要になってきます。
転職する
売れない商品を売り続けて社員に尻拭いをさせる会社や、パワハラがまかり通っている会社からは転職するのもよいかもしれません。
終身雇用の時代は終わりましたから、社外でも市場価値のある人材になることを考えないまま過ごしてしまうと、将来どこにも行き場がないなんてことになりかねません。
労働基準監督署に相談する
労働基準法に反する行為があった場合は労働基準監督署に相談することで、企業に指導をしてもらえる場合があります。
ここにきて、先程お伝えした自爆営業をするようそそのかされたことを示す証拠が生きてきます。
労働基準監督署は相談を受けても、証拠が十分でなかったり、重要性が低かったりする場合は動いてくれません。
いつ誰に何をされてどうなったのかを記録してとっておきましょう。
弁護士に相談する
商品を買ってしまった金額があまりにも多い場合や、パワハラの慰謝料を請求したい場合は弁護士に依頼する選択肢もあります。
ベンナビ労働問題を使って、労働問題を解決した実績を持つ弁護士を探しましょう。
まとめ
もし会社がニーズのない商品を売り続けていて、なおかつ従業員のノルマが変わらないような職場では、自爆営業をせざるを得ない状況が続くことでしょう。
ただ、このような体制がある限り、一度自爆営業をすれば済むわけではなく、在籍している期間が長いほど従業員は金銭的に損をする可能性があります。
泣き寝入りするにせよ企業と戦うにせよ、証拠だけは取っておくようにしましょう。