「遺産分割」に関する記事一覧ページです。
換価分割は不動産など物理的に分けにくい遺産を売却して現金化し、その現金を公平に分ける方法。 ほかの分割方法と比べて公平性が高いのがメリットですが、不動産の売却に手間と時間がかかる点はデメリットです。 また換価分割をおこな...

被相続人である祖父母の子どもが生存している限り、孫に財産を相続させることはできません。 そのため、孫に財産分与をしたいのであれば、祖父母が元気なうちに遺言書の作成や贈与などの方法で孫に財産分与をおこなう準備をしなければな...

遺産分割調停はそれほど複雑な手続きでもないため、個人でも対応することができます。 とはいえ、ご自身が納得できる結果を得るためには、弁護士に依頼するのが賢明といえるでしょう。 実際、遺産分割調停事件は弁護士が介入しているケ...

相続手続きをおこなう方の中には、遺産分割に関わる手続きの期限について不安に思っている方もいるのではないでしょうか。 遺産分割に関わる手続きでは、期限が定められているものもあります。 期限を超過してしまうと、相続に関する重...
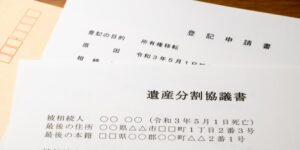
「父が亡くなったのに、相続人である息子に連絡がつかない」 「長年のあいだ行方不明で、生きているのかもわからない」 このように、相続人のなかに行方不明の者や音信不通者がいると、遺産分割協議ができません。 そのような場合には...
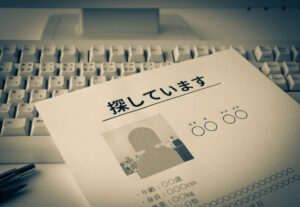
遺産相続で相続人たちの話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所にて遺産分割調停や遺産分割審判がおこなわれます。 遺産分割審判の結果には基本的に従う必要がありますが、その審判の内容に不服があるなら「即時抗告」を申し立てる...

「兄弟など相続人間で遺産を分割するが、遺産分割協議書の作り方が分からない」 「遺産分割協議書を作成する必要があるのだろうか」 「遺産分割協議書の書き方が間違っていないか不安だ。」 遺産分割協議をおこなう際は、遺産分割協議...
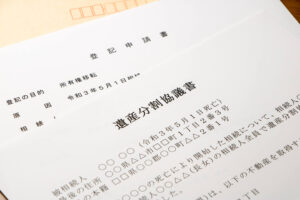
遺産分割とは、相続人全員の共有財産となった遺産を話し合いによって分割する手続きのことです。 遺産分割にはその手続きにおいて、さまざまな種類や方法がありますが、正しい手順を理解していれば、相続人自身でスムーズにおこなうこと...
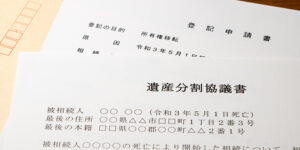
相続が発生し遺産分割協議を始めたものの、被相続人の預貯金の遺産分割方法について疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。 「預貯金はどのように分割すべき?」 「立て替えた葬儀費用分だけでも先に引き出してもいい?」 被相続人...

親族同士で遺産分割協議をおこなってきたものの、話がまとまらず、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。 しかし、以下のようなわからないことが多いために、準備を進められずお困りではないでし...
