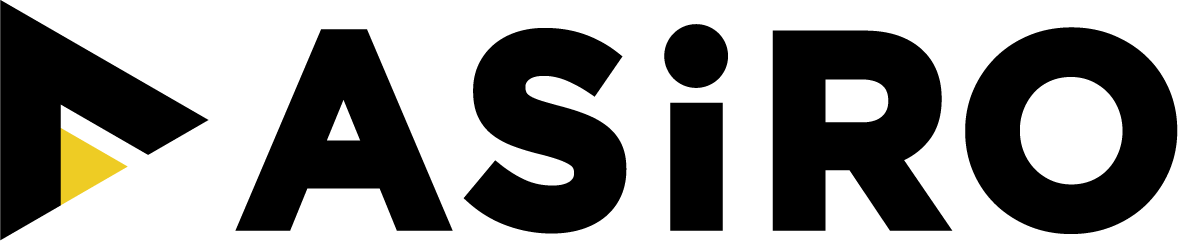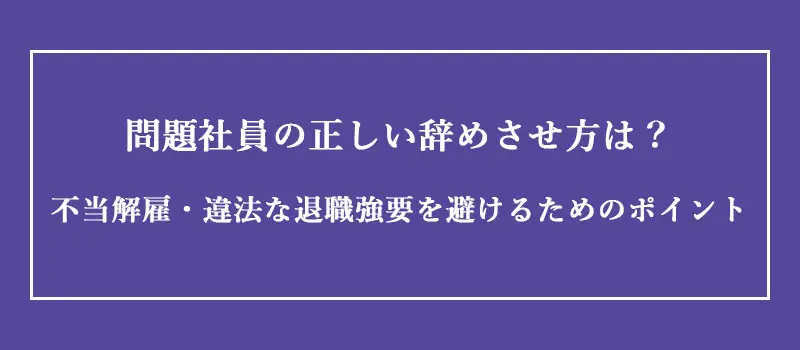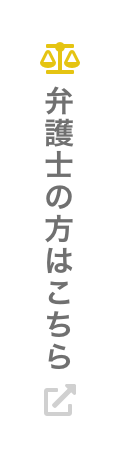労働基準監督署は、全ての労働者からの相談・申告を受け付けています。
この相談・申告をきっかけに、事業所に労働基準法違反などの事実があることが発覚すれば是正勧告などがおこなわれる場合があります。
そこで本記事では、労働基準監督署に相談できること、労働基準監督署では対応できない相談内容、労働基準監督署以外に労働者にとって役立つ相談窓口などについてわかりやすく解説します。
労働基準監督署とは?相談によって期待できること
従業員が働く中でトラブルに見舞われたとき、労働基準監督署への相談をすすめられることがあります。
まずは、労働基準監督署とはどのような機関なのかについて解説します。
労働基準監督署とは企業が労基法を守っているか監督する機関
労働基準監督署(労基署)とは、企業が労働関係に関する法令を遵守しているかを監督する機関です。
労働基準監督署がチェックする「労働関係に関する法令」には、以下のものが挙げられます。
たとえば、企業が従業員を働かせるときに、残業規制に違反していないか、給与の未払いが発生していないかなど、労働基準法を遵守しているかどうかをチェックします。
また、企業内に設置されている機械が労働安全衛生法で定められた基準を満たすかを検査したり、労災保険の支給が労働者災害補償保険法のルールや基準に従っているかを調査したりします。
また、労働基準監督署は、従業員側からの申告を受け付ける窓口としても機能しています。
各都道府県、全国で321署設置
労働基準監督署は、厚生労働省の第一線機関として企業をチェックし、そこで雇用される従業員の就労環境を安全なものにしています。
まず、厚生労働省の下には、都道府県労働局が47局設置されています。
そして、その下部組織として、全国321署と4つの支署があります。
各都道府県の比較的大きな都市に設置されているのが通常です。
厚生労働省のWebサイトで、ぜひ最寄りの労働基準監督署を探してみましょう。
労働基準監督署に相談をすれば労基法違反の是正が期待できる
会社側に労働基準法や労働安全衛生法違反となっているような状況がある場合、労働基準監督署から会社への是正勧告が期待できます。
具体的には、会社が従業員に残業代を支払っていない場合や、労働者死傷病報告を故意に提出しないことや虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出した場合(いわゆる労災隠し)などが挙げられます。
もし、企業が労働基準監督署からの是正勧告に応じない場合は、逮捕や差し押さえといった捜査がおこなわれ、その後刑罰が科されることもあります。
このことからも、労働基準監督署からの指導によって状況が改善するケースが多くあるようです。
労働者の味方になって解決してくれるわけではない
結果的に労働者の利益につながるようなケースがあるかもしれませんが、労働基準監督署はあくまでも会社等の事業所を監督する機関です。
そのため、労働者がどれだけ深刻なトラブルに関する相談をしたとしても、労働基準監督署が判断をしなければ企業へ働きかけてもらうことはできません。
また、労働基準法を違反していることを証明できる資料や証拠がなければ、より悪質性が高い事案を優先されてしまう可能性が高いでしょう。
労働基準監督署に相談できること
労働基準監督署に申告できる内容は多岐にわたります。
ここでは、労働基準監督署に相談できる内容の一例を紹介します。
1.残業代を支払ってもらえない
会社(使用者)は、労働者が所定労働時間を超えて働いた場合に残業代を支払わなければなりません。
また、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて働いた場合には、割増賃金を支払う必要があることが労働基準法で定められています(労働基準法第37条1項)。
それにもかかわらず、会社によってはタイムカードを前倒しで打刻させたり、労働基準法を都合よく解釈して残業代を支払わなかったりするという悪質なケースもあります。
ご自身の残業代が未払いになっている可能性があると疑われるような場合には、労働基準監督署へ一度相談することをおすすめします。
2.違法な長時間労働を強いられた
使用者が労働者を働かせることができるのは、原則として1日8時間・1週間40時間と決まっています(労働基準法第32条1項)。
ただし、労使協定(36協定)を締結することで、法定労働時間を超えて労働者を働かせることも可能です(労働基準法第36条1項)。
しかし、このような場合も36協定で定めた上限時間が適用され、法律上の上限規制を遵守する必要があります(同条3項~6項)。
つまり、これらの制限を超えて労働者を働かせることは、労働基準法違反となる可能性があります。
違法な長時間労働は、労働者の健康面にも大きな影響を及ぼすおそれがあるため、労働基準監督署へ相談するようにしましょう。
3.労働災害(労災)に遭った
労働災害(労災)とは、従業員・社員が労務に従事したことで被った負傷・疾病・死亡などのことをいいます。
労災の認定を受けると、会社が加入している労災保険から、認定等級に応じた保険給付を受けられます。
そして、労災保険給付の請求は労働基準監督署が実施しているので、以下のような労災隠しなどのトラブルが生じた時には、労働基準監督署に相談することで会社に対する是正勧告が期待できます。
- 「この会社には労災制度がない」と嘘をつかれて労災保険請求の手続きを進めてもらえない
- 「通勤中のけがは労災の対象外」と主張されて医療費などの自己負担を強要された
- 「アルバイト・非正規雇用では労災保険は利用できない」とごまかされたうえに、就労できないことを理由に自主退職を迫られた
- 長時間労働による過労死、ハラスメントによる精神疾患など、従業員が負った・病気・死亡と業務との因果関係を頑なに否定された
なお、労災に該当するかどうかは事案ごとの事情を踏まえて判断されます。
労災の具体的な適用条件や申請方法などについては、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】労災(労働災害)とは?適用条件・補償内容・申請方法の解説
労働基準監督署へ相談できないこと
労働基準監督署は、「企業活動が労働基準関係法などを遵守しておこなわれているのか」という観点から、会社などの事業所を監督・指導する機関です。
そのため、一例として以下のような事案は労働基準関係法違反に該当しないため、労働基準監督署では対応してもらえない可能性が高いでしょう。
- セクハラ、パワハラなど、ハラスメント被害に関すること
- 配置転換、部署異動など、正当な人事権の行使に関すること
- 懲戒処分に関すること
- 能力不足や経歴詐称など、従業員の個別的な事情を理由とする解雇処分に関すること
これらのトラブルについての救済を希望するなら、依頼者を守るために職責を果たしてくれる弁護士に相談することをおすすめします。
労働基準監督署へ相談する4つのメリット
ここでは、労働基準監督署へ相談するメリットを4点紹介します。
1.相談・申告は労働者であれば誰でも可能
自分が働いている事業所に労働基準法違反の事実がある場合、労働者には、その事実を労働基準監督署などの行政機関に申告する権利が認められています(労働基準法第104条第1項)。
なお、労働基準監督署では、労働者からの一般的な労働相談にも対応する窓口を設置しています。
どこかの企業に所属している労働者であれば、誰でも労働基準監督署の相談窓口を利用できるので、仕事や働き方などについて少しでも不安があるのなら、まずは労働基準監督署の窓口に連絡をしてみるのも選択肢のひとつでしょう。
2.トラブルが解決する可能性がある
労働基準法等の違反の状態が明らかになると、労働基準監督署が会社への是正勧告や指導をおこないます。
その結果、会社側の労働基準法等の違反によって従業員に生じていたトラブルが解決する可能性があるでしょう。
ただし、中には「残業代は払われるようになったものの、これまでの未払いの分については支払いがない」など、過去に被った損害は回復しない可能性も否定できません。
ご自身がそのようなケースに該当する場合は、弁護士に相談・依頼するようにしましょう。
3.匿名での相談・申告も認められている
「労働基準監督署に相談・申告したことが会社にバレそうで怖い」などの不安から、労働基準監督署への相談・申告をためらう方も少なくはないでしょう。
労働基準監督署では、匿名での相談・申告も受け付けています。
また、労働基準監督官には守秘義務が課されています(労働基準法第105条)。
ですから、労働者がもし実名で相談したとしても、使用者側に相談・申告の事実が漏れることはないでしょう。
4.相談したことを理由に会社が不利益な取り扱いをすることは違法とされている
労働基準法では、労働基準監督署を頼りたいと考えている労働者を守るために、以下のようなルールを定めています。
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索
中でも労働基準監督署への相談や申告を理由に労働者を解雇したり、降格・減給などの処分をおこなったりすることは明らかに違法です。
万が一、使用者から不当な処分を受けた場合には弁護士に相談して争うことも可能です。
恐れずに労働基準監督署への相談・申告をおこないましょう。
労働基準監督署へ相談する4つのデメリット
労働基準監督署は労働者に対して広く相談・申告を受け付けてくれる一方で、「企業側を監視する」という職責に担っている以上、状況次第では、従業員にとってメリットが生じないリスクもあります。
ここでは、労働基準監督署へ相談・申告するデメリットを4つ解説します。
1.証拠がないと対応してくれないことがある
労働基準監督署は、あくまでも独自の調査に基づいて、使用者に対する監視・監督をおこないます。
そのため、労働者側が労働基準法違反を確信していたとしても、労働基準監督署が動いてくれるとは限りません。
労働者が労働基準監督署に相談・申告をした際に、労働基準法違反を根拠付ける十分な証拠を提示できなければ、労働基準監督署が対応してくれないことがあります。
2.初動までに時間がかかるケースが多い
下表のとおり、労働基準監督署には年間100万件以上の相談が寄せられています。
年度 総合労働相談件数 民事上の個別労働紛争相談件数 平成25年度 1,050,042件 245,783件 平成26年度 1,033,047件 238,806件 平成27年度 1,034,936件 245,125件 平成28年度 1,130,741件 255,460件 平成29年度 1,104,758件 253,005件 平成30年度 1,117,983件 266,535件 令和元年度 1,188,340件 279,210件 令和2年度 1,290,782件 278,778件 令和3年度 1,242,579件 284,139件 令和4年度 1,248,368件 272,185件
ところが、労働基準監督官は全国に3,000人程度しかいません。
そのため、どうしても労働基準監督署では悪質な違反を優先的に対応する傾向にあるため、軽微なものについては後回しにされる傾向にあります。
3.会社に対して相談者の代理で交渉してくれるわけではない
労働基準監督署は、行政機関という立場で企業を監視する役割を担う組織でしかなく、個別の労働紛争を解決するものではありません。
つまり、違反状態を是正するために労働基準監督署が動いてくれたとしても、各従業員の残業代未払い請求や損害賠償請求、示談交渉などの法的措置については、労働基準監督署は一切代理してくれないということです。
以上を踏まえると、会社側の違反行為によって各従業員が被った損害などの回復を目指すなら、労働基準監督署ではなく弁護士に相談するべきだと考えられます。
4.会社に対して強制力のある命令ができるわけではない
ここまでに何度か触れてきましたが、労働基準監督署は個別の紛争を解決する機関ではありません。
そのため、会社に対して個人の不利益解消のために直接交渉をすることはありません。
もし、個別の紛争で受けた不利益を解消したいという場合には、労働局や弁護士への相談が有効です。
特に労働問題に強い弁護士へ依頼をすれば、労働審判や訴訟などの強制力をもった手段を取ることも可能です。
【関連記事】労働審判の流れを解説|労働審判を活用する際の手続きと解決フロー
労働基準監督署への相談方法
労働基準監督署への相談方法は、訪問・電話・メールの3種類です。
ここでは、それぞれの相談方法の特徴について解説します。
1.訪問して相談する
労働基準監督署は全国各地に設置されているので、ご自身の勤務先を管轄する労働基準監督署を検索して、直接訪問して相談しましょう。
担当職員に証拠書類を示しながら口頭でコミュニケーションを交わせるので、労働基準法違反などの実態を丁寧に伝えやすいでしょう。
管轄の労働基準監督署は、厚生労働省のWebサイト内「全国の労働基準監督署の所在案内」から検索できます。
労働基準監督署の開所時間は、通常平日8時30分~17時15分です。
ただし、労働基準監督署によって受付時間が異なる場合があるので、必ず事前に確認してください。
2.電話で相談する
電話での相談する場合、署内直通の電話番号にかけるという方法があります。
ただ、電話では労働基準監督署も証拠などを確認できないため、一般的なアドバイスに終始する可能性があります。
解決を求める場合は直接訪問したほうがよいでしょう。
そのため、電話での相談は、一般的な法律上のルールについて説明をもらえるなどにとどまる可能性があります。
より具体的な対応を期待するのであれば、労働基準監督署に直接訪問することをおすすめします。
メール窓口はあるが、あくまで情報提供にとどまる
厚生労働省では、メール窓口を設けています。
労働基準監督署の開所時間に訪問・電話するために仕事を休むのが難しいという方は、厚生労働省が設けている「労働基準関係情報メール窓口」で情報提供するのも選択肢のひとつです。
メールフォームには、以下の内容を入力する必要があります。
- 勤務している事業場の名称
- 勤務している事業場の住所
- 会社と送信者の関係
- 雇用形態
- 情報提供事項
- 情報提供があったことを事業場に通知することの可否(もちろん、個人情報は開示されません)
- 情報提供内容(2,000文字以内)
ただし、メール窓口でできるのは情報提供のみであり、具体的な相談やコミュニケーションがとれるわけではありません。
ご自身が被っている損害を通報するという役割は果たせるかもしれませんが、何らかの回答や対応を求めている場合は、別の方法での相談が適しているといえます。
労働基準監督署以外の相談先6選
職場におけるトラブルや労働環境の不満に対する相談窓口は、労働基準監督署だけではありません。
ここでは、労働基準監督署以外の相談先を6つ紹介します。
1.総合労働相談コーナー|どんな分野の労働問題も相談できる
総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局・全国の労働基準監督署内などの379ヵ所に設置されています。
総合労働相談コーナーでは、解雇、雇止め、配置転換、賃金の引き下げ、募集・採用に関するトラブル、いじめや嫌がらせ、各種ハラスメント問題、性的志向・性自認に関連する労働問題など、あらゆる労働問題に対応可能です。
「労働に関することでひとまず誰かに無料で相談したい」と考えているなら、まずは総合労働相談コーナーに問い合わせをするとよいでしょう。
総合労働相談センターは、専門の相談員が面談・電話で対応します。
予約不要、無料で相談可能なので、誰でも気軽に連絡できます。
さらに、総合労働相談コーナーでの相談の結果、踏み込んだ解決が必要であると判断された場合には、労働基準監督署に取り次いでくれたり、助言・指導・あっせんの制度(個別労働紛争解決制度)を案内してくれます。
総合労働相談コーナーの所在地については「総合労働相談コーナーのご案内」から確認してください。
【関連記事】総合労働相談コーナーとは|公的相談窓口の評判や活用法を解説
2.労働条件相談ほっとライン|平日22時まで、土日祝日に電話で相談できる
労働条件相談ほっとラインとは、違法な時間外労働・過重労働による健康被害・賃金未払いなど、労働基準関係法令に関する問題について、法令・裁判例を踏まえて対応してくれる電話相談窓口です。
専門の相談員が無料で相談に対応してくれるので、労働基準監督署の窓口などにいきなり訪問するのに抵抗がある方におすすめです。
- 電話番号:0120-811-610
- 受付時間:月曜日~金曜日:17時00分~22時00分 / 土日祝日:9時00分~21時00分
※年末年始(12月29日〜1月3日)はお休み
【関連記事】労働条件相談ほっとラインとは|相談できる内容と利用時の注意点を解説
3.労災保険相談ダイヤル|労災保険についてのあらゆる内容を相談できる
労災保険相談ダイヤルは、労災に関する相談に幅広く対応してくれる電話相談窓口です。
労災補償該当相談、労災請求手続きに関する相談、労働保険の加入・労働保険料納付に関する相談、アスベストなどによる労災に関する相談など、労働者・事業者それぞれの疑問に幅広く対応しています。
- 電話番号:0570-006031
- 受付時間:月曜日~金曜日8時30分~17時15分
4.こころの耳電話相談|過重労働による健康障害などについて相談できる
こころの耳電話相談は、メンタルヘルスの不調、ストレスチェック制度、過重労働による健康障害の防止対策などについて相談できる窓口です。
所定の訓練を受けた産業カウンセラーなどが、専門的な知見をもって以下の事項についてアドバイスをしてくれます。
- こころの悩み
- 職場の人間関係や仕事内容の悩み
- 長時間労働や過重労働による健康への影響について
- 事業場の健康管理システムの状況について
- ストレスチェックの結果について
- ストレスチェックの結果に基づいて医師の面接指導を受けるときの注意点などについて
- ストレスチェックをめぐる不利益取扱いについて
なお、こころの耳相談窓口では、病名の診断や治療方法、現在受診中の医療内容の是非のチェックなど、医療行為に関する相談には対応していません。
また、1回あたりの相談時間は最長20分です。
- 電話番号:0120-565-455
- 月曜日~金曜日:17時00分~22時00分
- 土日祝日:10時00分~16時00分
5.社会保険労務士(社労士)|労働問題解決のアドバイスをもらえる
社会保険労務士(社労士)は、労働問題・社会保険問題・年金問題に関する専門家です。
社会保険労務士の職務内容は、以下のとおりです。
- 書類等の作成代行
- 書類等の提出代行
- 個別労働関係紛争の解決手続き(調停、あっせんなど)の代理(特定社会保険労務士のみ)
- 労務管理や労働保険・社会保険に関する相談 など
たとえば、職場の労働実態に疑問を抱いたり、労災保険の認定について不満があるときには、社会保険労務士に相談するとスムーズでしょう。
また、会社側との間で調停・あっせんの必要に迫られたときには、依頼者に代わり交渉をおこなってくれます。
もっとも、社会保険労務士の助言やあっせんの代理で問題を解決しないケースもあるため、そのような場合は弁護士への依頼を検討しましょう。
6.弁護士|代理人として会社との交渉や裁判を任せられる
何かしらの労働問題に巻き込まれたときに最も頼りになるのが弁護士です。
法律のプロである弁護士に相談・依頼をすれば、以下のメリットが期待できます。
- 労働問題の種類に関係なく、全ての相談内容に対応してくれる
- 会社との示談交渉、調停、審判、民事訴訟など、全ての手続きを代理してくれる
- 労働者に弁護士が就任したことで会社側からの誠実な対応を引き出しやすくなる
- 会社側と争うときに必要な証拠の種類・収集方法について丁寧にアドバイスしてくれる
- 労使紛争で精神的・身体的に負担を感じている依頼者により沿って最適な解決策を提案してくれる
なお、弁護士によって注力する分野が異なるので、労使紛争について相談したいときには、必ず労働問題に力を入れている法律事務所を選ぶようにしてください。
また、弁護士ごとに費用設定が異なるので、委任契約を締結する前に、相談料・着手金・報酬金・支払い方法などについて確認しましょう。
ベンナビ労働問題では、労働問題に注力している法律事務所を多数掲載しています。
所在地や相談内容などから絞り込むことが可能なので、速やかに信頼できる弁護士まで問い合わせてください。
労働基準監督署への相談についてよくある質問
最後に、労働基準監督署への相談・申告についてよくある質問をQ&A形式で紹介します。
平日は仕事で夜遅くしか時間を取れず、相談に行けません
労働基準監督署の窓口対応時間は平日日中だけなので、有給休暇などを取得しない限り、労働基準監督署に直接訪問するのは難しいでしょう。
ただ、労働問題に関する相談窓口は労働基準監督署だけではありません。
労働条件相談ほっとラインなどでは、平日夜や土日でも回線が繋がっているので、労働問題に関する不安などを相談できるでしょう。
また、弁護士事務所の中には、土日祝日や平日夜に相談可能なところや、オンライン相談にも対応してくれるところも少なくありません。
労働基準監督署に限らず幅広い相談窓口を探せば必ず対応してくれるところは見つかるので、できるだけ早いタイミングで問い合わせをしてください。
労働基準監督署に相談したら会社にバレてしまいますか?
労働基準監督署には守秘義務が課されているので、労働基準監督署に相談・申告した事実がバレることはありません。
ただし、小規模な会社等では、労働基準監督署の指導などによって、結果的にバレてしまう可能性も否定できません。
万が一、相談したことが会社にバレてしまったときに備えて、匿名で労働基準監督署に相談・申告するのも選択肢のひとつでしょう。
いずれにしても、誰が労働基準監督署に相談したかといった事実が会社にバレる可能性は極めて低いので安心してください。
さいごに|労働基準監督署へ相談しても解決しない場合は弁護士へ
労働基準監督署に相談すれば、労働基準法違反となっている状態や損害が是正・改善される可能性があります。
ただし、労働基準監督署はあくまでも使用者を監督する機関のため、個々の労働者を直接的に救済するためのサポートは期待することができません。
もし、示談交渉や損害賠償請求などを検討しているのであれば、労働基準監督署ではなく弁護士へ相談することを強くおすすめします。
ベンナビ労働問題では、労使紛争の経験豊富な法律事務所を多数掲載しています。
この機会にぜひ、信頼できる弁護士まで相談してください。