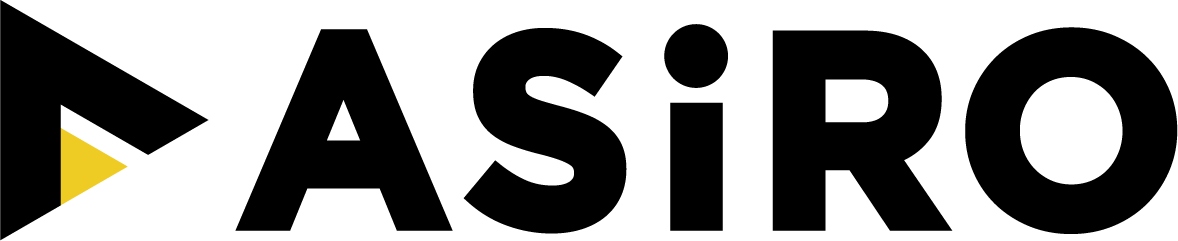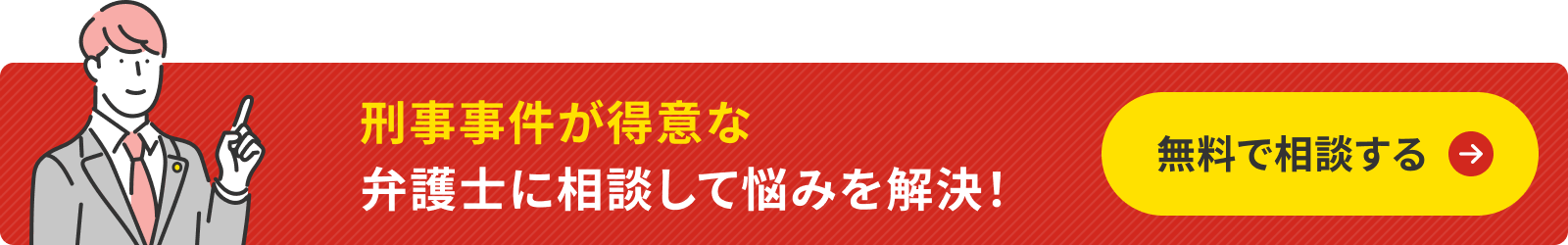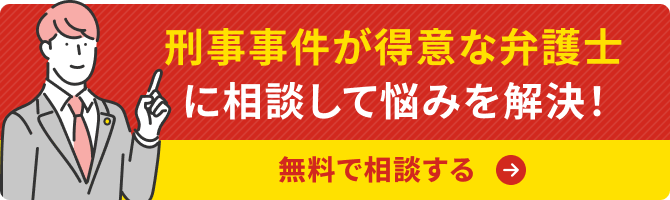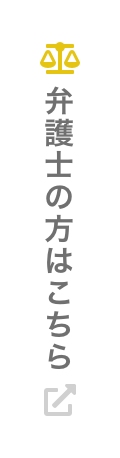飲酒運転をしてしまい、警察に逮捕されるのではないかと不安を抱えている方は多いでしょう。
また、すでに逮捕されてしまい今後どうなるのか心配な方もいるのではないでしょうか?
本記事では、飲酒運転の種類と定義、飲酒運転に対する刑罰の内容、飲酒運転で逮捕された場合の流れなどについて解説します。
飲酒運転に関するトラブルで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
「飲酒運転」の意味と基準
そもそも、飲酒運転とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか?
まずは、飲酒運転の意味と飲酒運転とみなされる基準について解説します。
一般的な意味と法律上の定義は異なる
「飲酒運転」とは、一般的にはお酒を飲んで自動車やバイクなどを運転する行為を指します。
一方、道路交通法上では「飲酒運転」という用語はなく、「酒気帯び運転等」という言葉の定義が示されています。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
酒気を帯びた状態とは、体内にアルコールを保有していることです。
ビール・日本酒・焼酎などのアルコール飲料に限らず、少しでもアルコールを含む飲料・料理・菓子類を口にして車を運転した場合、道路交通法上の酒気帯び運転に該当します。
摂取したアルコール量がわずかであっても酒気帯び運転として取り締まりの対象となるので、「少ししか飲んでいないから大丈夫」といって、運転してしまうと違法となります。
飲酒運転の種類と逮捕の基準
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。
それぞれの違いを確認しておきましょう。
酒気帯び運転
道路交通法では、酒気帯び運転を「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」の場合に罰金に処するとしています。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
「身体に政令で定める程度」は、道路交通法施行令で以下のとおり定められています。
- 血液1ミリリットルにつき3ミリグラム以上のアルコールを保有する状態
- 呼気1リットルにつき15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態
警察による飲酒検問や職務質問では呼気検査がおこなわれるため、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコール保有する状態が基本的な検挙基準となります。
血液中のアルコール量を検査されるのは、呼気検査を拒んだために裁判官の令状で強制採血されるケースに限られます。
酒酔い運転
酒酔い運転は、酒気帯び運転よりも悪質な状態です。
酒酔い運転は、道路交通法で「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と定義されています。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
しかし、酒酔い運転とされるアルコール量の基準については、道路交通法・道路交通法施行令のいずれにおいても明確に定められていません。
呼気検査で酒気帯び運転の基準値を超えるアルコールが検出されなくても、警察官が「正常な運転ができない状態」と判断すれば酒酔い運転として検挙されます。
酒酔い運転であるかどうかは、主に以下の基準をもとに判別されます。
- 顔面の紅潮や眼球の充血がないか
- 日時や場所などを正しく認識できているか
- 警察官の質問に対して正常に会話できているか
- ろれつが回っているか
- 片足立ち・直線歩行などは可能か
- 意識がしっかりしているか
飲酒運転で逮捕されると問われる法的な責任
飲酒運転で逮捕された場合、どのような法的責任を負うのでしょうか?
ここでは、飲酒運転で逮捕された場合に問われる法的責任について解説します。
刑事責任|刑罰を受ける
飲酒運転で逮捕されると、道路交通法に基づき処罰されます。
飲酒運転に対する刑罰は、以下のとおりです。
| 飲酒運転の種類 | 罰則 |
|---|---|
| 酒気帯び運転(道路交通法第117条の2の2第4号) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転(道路交通法第117条の2第1号) | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪が適用されればより厳罰に
危険運転致死傷罪が成立した場合、より重い処罰を受けることになります。
危険運転致死傷罪とは、故意に危険な運転をして人を死傷させる犯罪のことです。
危険運転には、主に以下のような行為が該当します。
- 飲酒運転
- 制御困難な高速度での走行
- 赤信号の無視
- あおり運転などの妨害行為
危険運転致死傷罪では20年以下の懲役に処せられるため、5年以下の酒酔い運転に比べるとはるかに厳しい処罰を受けることになります。
行政処分|運転免許上の処分を受ける
道路交通法違反により、所定の違反点数が加算されます。
違反点数が積み重なると、運転免許の停止や取り消しといった行政処分を受けることになります。
処分の内容は、飲酒運転の種類やアルコール量によって異なります。
| 飲酒運転の種類 | 呼気1リットル中のアルコール量 | 違反点数 | 行政処分 |
|---|---|---|---|
| 酒気帯び運転 | 0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 | 13点 | 免許の停止(前歴がある場合:免許の取り消し・欠格期間1年) |
| 酒気帯び運転 | 0.25ミリグラム以上 | 25点 | 免許の取り消し(欠格期間2年) |
| 酒酔い運転 | 35点 | 免許の取り消し(欠格期間3年) |
免許が取り消しされると、一定期間は運転免許を取得できません。
この期間を欠格期間といいます。
仕事や私生活で日常的に車を運転している場合、かなり不便を感じることになるでしょう。
民事責任|事故相手への賠償
飲酒運転をして事故を起こしてしまった場合、事故の相手への賠償責任も問われます。
相手車両の修理費、事故現場の壁や塀などの修繕費、相手のけがの治療費、慰謝料などを支払う必要があるので、金銭的な負担は大きいでしょう。
飲酒運転でも基準値以下なら「基本的には」逮捕されない
飲酒運転をした場合でも、呼気検査の結果アルコール量が基準値以下であれば、基本的に処罰は受けません。
しかし、処罰を受けないからといって「違反にならない」と考えるのは間違いです。
基本的には刑罰や行政処分は受けない
道路交通法上では、「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で運転した場合に刑罰に処するとされています。
そのため、定められた数値以上のアルコールが検出されなかった場合は、刑罰や行政処分を科せられることはありません。
しかし、基準値以下なら飲酒運転が許されるわけではない点は留意しておく必要があります。
道路交通法では「酒気を帯びて車両等を運転すること」を禁止しているので、アルコール量が基準値以下であっても違反であることには変わりありません。
継続した運転は認められない
警察による尋問や呼気検査で飲酒運転が発覚した場合、基準値以下であっても、そのあとに運転することはできません。
以下の対応が必要です。
- 酒気を帯びていない同乗者に運転を代わってもらう
- 近くの駐車場に車を置いて帰る
- レッカー業者や運転代行業者に依頼する
飲酒運転で逮捕される3つのケース
飲酒運転をしたからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。
それでは、飲酒運転を理由に逮捕されるのはどのようなケースなのでしょうか?
逮捕の目的……逃亡や証拠隠滅の防止
逮捕の目的は、被疑者の逃亡・罪証隠滅を防ぐ点にあるため、これらのおそれがあると判断される場合には、逮捕される可能性が高まります。
一方で、職務質問の際の態度が誠実であったり(運転免許証を素直に提示したり、事情聴取に応じる等)、定職や家庭があり、上司や家族が監督を誓約している等の事情に照らし、逃亡・証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕を免れる場合もあるでしょう。
逃亡・罪証隠滅の可能性があると判断されやすいケースとしては、たとえば次のような場合が挙げられます。
犯行態様が悪質と判断される場合
飲酒運転の態様が悪質である場合、重い刑罰を科されることが予想されるため、逃亡や罪証隠滅の可能性が高いと判断され、逮捕されやすいと考えられます。
たとえば、以下のような場合は悪質な犯行とみなされるでしょう。
- 蛇行運転をおこなう
- 基準値を大幅に超えるアルコールが検出される
- 飲酒検問を察して逃走の気配を見せる
- 常習性が高いと判断される(日ごろから飲酒運転に及んでいるとして警察にマークされているケース等)
交通事故を起こした場合
飲酒運転により交通事故を起こした場合は、単に酒気を帯びて運転行為に及んだケースより犯罪の結果が重大であり、相応の刑が科される可能性が高いため、逃亡・罪証隠滅の危険があると判断されやすいと考えられます。
なお、人身事故を起こした場合、道交法上の罪とは別に、過失運転致傷罪に問われることがあります。
この場合、被害者のけがが軽い場合は、最終的に刑が免除されることがありますが、だからといって直ちに逮捕を免れる訳ではないことには注意が必要です。
飲酒運転で逮捕された場合の刑事手続きの流れ
飲酒運転で逮捕された場合、窃盗、暴行、傷害などの事件と同様に刑事手続が進められます。
ここでは、刑事手続の大まかな流れについて解説します。
逮捕による身柄拘束
飲酒運転を理由に「逮捕する」と告げられた時点で、身柄を拘束されます。
逮捕後は警察署に連行されて取調べがされ、当日の行動、飲酒の状況、発覚前の経路、運転の目的などを聴取されます。
身柄拘束中は、警察署の留置場で過ごすこととなり、帰宅することはできません。
また、罪証隠滅や逃亡のおそれが高いと判断されるケースでは、弁護人以外の家族・友人等との接見(面会)の禁止を命じられることがあります(接見禁止)。
ただし、警察署での取調べには逮捕から48時間以内という時間制限があり、その間に検察官に送致するか釈放するかが判断されます。
事実を認めていたり、死傷者がいない等の事情から、身柄拘束を続ける必要性がないと判断される場合には、釈放されることもあるでしょう。
検察官への送致
48時間以内に釈放されず、事件の取扱いについて検察官の判断を仰ぐ必要があるとされた場合は、検察庁へ送致されます。
検察官のもとへ身柄を送致されたあとは再度取調べを受け、事件の経緯や犯行の理由などについて詳しく聴取されます。
検察官は、被疑者の身柄が送致されてから24時間以内に、裁判所に対して被疑者の身柄拘束を継続する処分(勾留)の請求をするか、被疑者を釈放するかを判断します。
勾留による身柄拘束
検察官が「さらに留置の必要がある」と判断した場合は、勾留請求がおこなわれます。
勾留請求は検察官が裁判官に対しておこなうもので、裁判官が請求を認めて勾留決定をくだすと、被疑者はそこから10日間身柄を拘束されることとなります。
また、裁判所は、検察官の請求に応じて、更に最大10日を限度に勾留期間を延長することができます。
つまり、被疑者は逮捕時から起算して最大で23日もの間身柄を拘束される可能性があるということです。
また、原則として、勾留期間中も家族等との面会は可能ですが、上述の接見禁止を命じられている場合には、弁護人以外との面会は禁じられます。
起訴・不起訴の判断
検察官が、被疑者に対して刑事罰を科す必要があると判断した場合には、当該被疑者は起訴されます。
起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を請求することです。
日本の刑事裁判における有罪率は99%といわれているので、起訴された時点でほぼ前科がつく可能性が極めて高いといわざるを得ません。
一方、不起訴処分とは刑事裁判を請求しないことを指します。
不起訴となれば、警察による捜査が終了し身柄も解放されます。
ただし、不起訴処分は必ずしも被疑者が無罪であることを意味するものではなく、飲酒運転がおこなわれたものの、初犯の事情に照らして刑事罰を以て望む必要がないために、公訴を提起しない処分が下される(起訴猶予処分)場合も含まれます。
こうした場合には、不起訴処分が下されても、飲酒運転をしたという事実は変わらないので、刑事処分とは別に、免許停止・取り消しなどの行政処分を受ける可能性もあります。
刑事裁判
起訴された場合は、刑事裁判にて判決が言い渡されます。
飲酒運転の場合、特に悪質な事件でない限りは略式手続によって審理されることが多いといわれます。
略式手続とは、法廷での裁判はおこなわず、検察官が提出した書面だけで審査を済ませる簡易的な裁判手続きのことを指します。
100万円以下の罰金または科料に相当する事件の場合に採用される方法なので、飲酒運転の多くは略式手続がおこなわれます。
略式手続を選択すると裁判で争うことができないため必ず有罪となりますが、判決が即日言い渡されるので身柄が早期に解放されます。
判決の内容に納得できない場合、14日以内であれば不服申し立てをすることが可能です。
不服申し立てをおこなった場合は正式裁判が開かれます。
【参考】略式裁判について|検察庁
在宅事件の場合
飲酒運転が発覚したものの逮捕されなかった場合や、逮捕後すぐに釈放された場合、事件記録のみが検察官に送致されることになります(いわゆる書類送検)。
この場合には身柄は拘束されず、書類や証拠資料のみが検察庁に送致されます。
書類送検のあと、通常の場合と同様に検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴された場合は刑事裁判に発展することがあるので、逮捕されなかったり釈放されたりした場合でも、刑罰に処せられる可能性があることは覚えておきましょう。
飲酒運転での逮捕がその後の人生に及ぼす影響
飲酒運転で逮捕された場合、仕事や私生活に大きな支障をきたすおそれがあります。
仕事を失う可能性もある
飲酒運転で逮捕されたり、飲酒運転で人を死傷させた場合は、解雇されて仕事を失う可能性があります。
また、車での移動が不可欠な仕事をしていて免許の停止や取り消しを受けた場合、業務に大きな支障をきたすおそれもあるでしょう。
家族が離れ離れになることも
飲酒運転により家族と暮らせなくなるおそれもあります。
これまでも、配偶者が飲酒運転で人を死亡させてしまった事実を受け入れられず、離婚に至った事例があります。
また、事故によって婚約を破棄される人や、家族が周囲から嫌がらせを受けないよう自ら離婚を選択する人もいます。
飲酒運転により、幸せな家庭生活を一瞬にして失う可能性があるといえるでしょう。
賠償金や見舞金の支払いで困窮するケースもある
任意保険に加入していなかった場合、事故相手への賠償金や見舞金を自分で支払う必要があります。
一定額までは自賠責保険会社によって補償されますが、超過した分は自己負担となります。
支払えないと、最悪の場合自己破産せざるを得なくなってしまうので、事故前のような生活を送ることはできなくなるでしょう。
悪質な交通事故の場合、破産したとしても損害賠償責任の免責を受けられないケースもあります。
賠償金を支払うために借金を背負い、一生をかけて罪を償う必要があります。
本人や家族にとって精神的に大きな負担となる
飲酒運転で交通事故を起こすと、本人や家族は精神的なショックを受けます。
交通事故で相手を死なせた場合は周囲から嫌がらせを受けることもあり、心理的なダメージは計り知れません。
最近ではネット上で実名、顔写真、住所などが公表されることもあるので、たとえ引っ越しても「事故の加害者」という目で見られるおそれがあります。
また、精神的なショックに耐えきれず自殺してしまう事例も多くあります。
一度の交通事故でその後の人生が台無しになってしまうということを、肝に銘じておく必要があるといえるでしょう。
飲酒運転での逮捕についてよくある質問と回答
ここからは、飲酒運転での逮捕に関連してよくある質問をまとめています。
飲酒運転について疑問が残っている方は参考にしてください。
飲酒運転で後日逮捕される可能性はありますか?
飲酒運転は呼気検査によって発覚することが多いので、現行犯逮捕される場合がほとんどです。
呼気検査の際に基準値以上のアルコールが検出されなければ現行犯逮捕はできないので、あとから逮捕されることは稀かもしれませんが、防犯カメラなどで飲酒の状況が記録されていた場合は、後日逮捕される可能性もあると考えられます。
飲酒運転の初犯でも逮捕されますか?
初犯でも逮捕される可能性が高いでしょう。
酒気帯び運転・酒酔い運転をした時点で道路交通法に違反します。
逮捕するかどうかの判断に際し、これまで何度検挙されたかは関係ありません。
警察の尋問や呼気検査の際に運転免許証や本人確認資料をしっかり提示する等して、逃亡や証拠隠滅の危険性がないと判断されれば、身柄を拘束されない在宅事件として扱われる可能性もあるでしょう。
飲酒運転の容疑をかけられたら弁護士に相談を
飲酒運転で逮捕されると最大23日間身柄を拘束されます。長期間にわたる身柄拘束から、強い孤独感にさいなまれるかもしれません。
また、交通事故を起こして人を死亡させた場合はその後の人生に大きな悪影響を及ぼし、仕事や家族を失うことにもつながりかねません。
仕事や私生活への影響を最大限抑えるためにも、早期に弁護士に相談・依頼しましょう。
弁護士に依頼すれば、早期の身柄解放を実現できたり、刑罰を軽くしたりすることができる場合があります。
容疑にかけられた時点で、飲酒運転をめぐるトラブルに詳しい弁護士を速やかに探して相談することをおすすめします。
さいごに
飲酒運転は、場合によっては人生を一変させます。
「少しだけだから大丈夫」と思って運転してしまうと、思いがけず人を死なせたり、けがをさせたりするおそれもあります。
加害者本人だけでなく、家族にも精神的なショックを与えることになるので、飲酒運転は絶対にしてはいけません。
もし、飲酒運転をしてしまい今後の対応に不安を抱えているなら、すぐに弁護士へ相談してください。
飲酒運転のトラブル解決が得意な弁護士に依頼すれば、早期の釈放や刑の減軽のためにさまざまなサポートを受けられます。
仕事や家族を守るためにも、迷わず弁護士に相談しましょう。