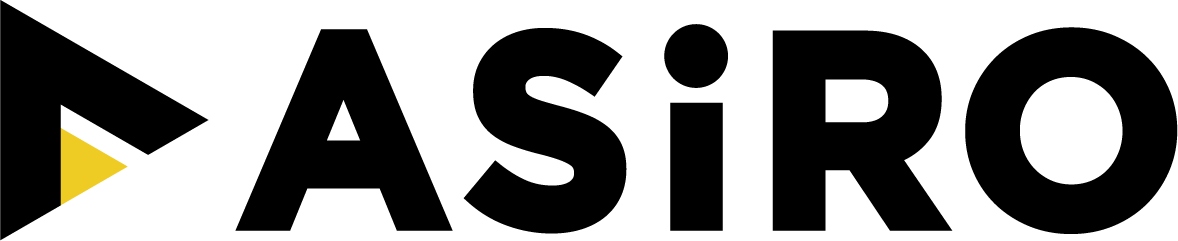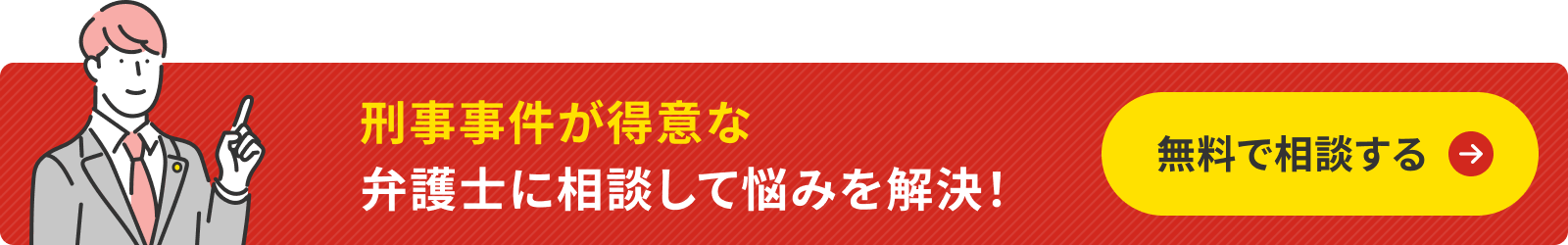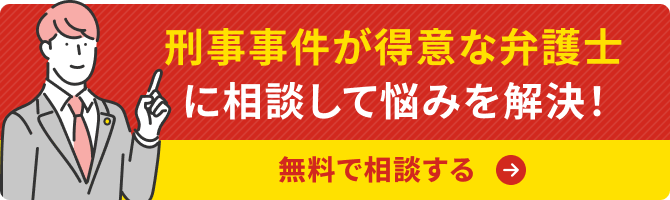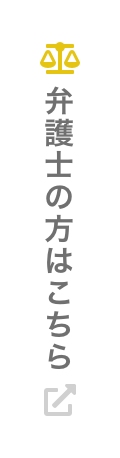- 「婚約をしていた相手から『だまされた』と言われて、被害届を出されたかもしれない…」
- 「以前交際していた婚約相手からお金を受け取ったけど、まさか詐欺になるとは思わなかった…」
このように、過去の言動や金銭のやりとりについて不安を感じ、「結婚詐欺をしてしまったかもしれない」と心配している方も多いのではないのでしょうか。
何気なくおこなっていた行為によって、知らず知らずのうちに結婚詐欺が成立してしまう可能性もあるため、正しい知識を持たずに対応を誤ると、逮捕や起訴といった事態に発展するおそれもあります。
本記事では、結婚詐欺の定義や刑罰や罰則の内容、逮捕される可能性が高いケース、被害届を出されたときにとるべき対応について解説します。
今後どのように行動すべきか正しく選択できるようになるためにも、ぜひ参考にしてください。
結婚詐欺とは?結婚を信じ込ませて金銭をだまし取る犯罪行為のこと
結婚詐欺とは、本当は結婚する意思がないにもかかわらず、あたかも結婚するかのように装って相手を信じ込ませ、信頼を利用して金銭や財産をだまし取る行為を指します。
たとえば、内心では結婚する気持ちがないのも関わらず、結婚式場の見学に同行する、相手の家族に挨拶する、新居を一緒に探すなど、結婚に向けた具体的な行動を見せて、相手方を結婚できるであろう錯誤に陥れ、「借金を返済してから結婚したい」などともっともらしい理由を伝えて金銭を要求し、相手からお金をだまし取るケースが代表的です。
結婚詐欺(詐欺罪)の要件
結婚詐欺は、刑法第246条の「詐欺罪」に該当して、逮捕・起訴される可能性があります。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
詐欺罪が成立するには、以下の4つ全ての要件を満たしている必要があります。
- 欺罔行為:相手をだますような嘘をつくこと
例:財物、財産上の利益を騙し取る故意で、結婚するつもりがないのに「結婚しよう」と持ちかける、実在しない借金を「返済したい」と訴えるなど。 - 錯誤:相手がその嘘を信じること
例:「結婚資金が必要」と言われて、「本気で結婚を考えているのだ」と誤解すること。 - 交付行為:だまされた相手が金品を渡すこと
例:預金口座にお金を振り込む、ローンの保証人になるなど。 - 財産移転:金品が加害者または第三者のもとへ移ること
例:振り込まれた金銭が加害者の口座に移されて使われる。
結婚詐欺(詐欺罪)の刑罰
詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です。
有罪判決が下されると刑務所に入るケースもあるので、重大な犯罪といえます。
なお、詐欺罪は未遂でも処罰の対象となります。
そのため、相手が金銭を支払わなくとも、嘘をついて金品をだまし取ろうとする行為を行った時点で詐欺罪の未遂が成立します。
交際相手に結婚詐欺を働いた場合に想定される2つのリスク
交際相手に対して結婚詐欺を働くと、主に以下の2つの重大なリスクが生じます。
- 警察に被害届を出される
- 返金や慰謝料を求められる
それぞれのリスクについて、詳しく見ていきましょう。
1.警察に被害届を出される
まず考えられるのは、被害者が警察に被害届を提出するリスクです。
被害届が出されると、警察は事件として捜査を開始し、証拠がそろえば詐欺罪として容疑者を逮捕する可能性もあります。
ただし、被害届を出されたからといって、すぐに逮捕されるとは限りません。
警察はまず、当事者間に実際に結婚の意思があったのか、相手をだます意図があったのかなど、詐欺罪の成立要件に該当する事実があるかを慎重に判断します。
そのため、初期段階では任意の事情聴取や電話での連絡といった対応から始まることが多いです。
しかし、同様の手口で複数の被害者が存在する場合や、不自然な事情が重なる場合には、本格的な捜査に発展し、逮捕される可能性が高まります。
2.返金や慰謝料を求められる
もう一つは、被害者から金銭の返還や慰謝料を請求されるリスクです。
民法第96条1項では、詐欺によってなされた契約や贈与などの意思表示は取り消せる旨が定められています。
そのため、詐欺によって得た金銭や財産については返還義務が生じます。
また、結婚詐欺によって精神的な苦痛を与えたと認められる場合には、民法第709条に基づき、不法行為として慰謝料を請求されることもあります。
結婚詐欺の容疑で逮捕される可能性が高い3つのケース
恋愛や金銭のトラブルは、私的な問題として処理されることもあります。
しかし、以下のようなケースでは、警察が詐欺罪として積極的に捜査・逮捕に踏み切る可能性が高くなります。
1.被害額が高額である場合
被害額が数十万円〜数百万円にのぼる場合、警察は深刻な事件と取り扱って捜査を進める傾向があります。
また、複数回にわたって金銭を受け取っていた場合は、被害が積み重ねられていると評価され、逮捕の可能性が高まります。
2.手口の悪質性が高い場合
複数の相手に対して結婚詐欺を繰り返していた場合は、常習的な詐欺や組織的な犯罪として扱われ、悪質と判断されやすくなります。
そのほか、存在しない親族トラブルや病気、借金などを理由に金銭を要求するなど、巧妙に相手を信じ込ませるような手口も悪質と判断されやすく、逮捕後の処分にも大きな影響を与える可能性があります。
3.詐欺の証拠がある場合
LINEやメールなどに「本当は結婚する気なんてなかった」といった内容のやりとりが残っていたり、第三者の証言によって詐欺の意図が明らかになったりした場合、それらが証拠として警察に提出されれば、逮捕につながる可能性が高まります。
結婚詐欺で警察に被害届を出された場合に取るべき行動
被害届が提出されたことがわかった場合、適切な対応を取ることで、逮捕や起訴の可能性を下げることができます。
ここでは、主な対応として以下2つを見ていきましょう。
- 刑事事件が得意な弁護士に相談する
- 被害者に謝罪をして示談を成立させる
1.刑事事件が得意な弁護士に相談する
まず最優先すべきなのは、刑事事件を得意とする弁護士への相談です。
被害届が提出されると、警察や検察が事実関係を調査し、必要に応じて事情聴取や証拠収集を進めます。
一連の捜査により犯罪の嫌疑が固まれば、警察は逮捕や勾留に乗り出す場合もあります。
そこで、経験豊富な弁護士にあらかじめ相談しておけば、現在の状況を整理したうえで、今後の見通しや、起訴・不起訴の判断に影響するポイントについても丁寧に説明してくれるはずです。
また、取り調べにはどう対応すればよいかといった具体的なアドバイスも受けられます。
2.被害者に謝罪をして示談を成立させる
被害届が提出されたあとであっても、示談が成立すれば、逮捕や起訴を避けられる可能性があります。
示談とは、加害者と被害者の間で、損害賠償や謝罪の方法などについて合意し、事件を円満に解決することを目的とした合意のことです。
検察が事件を起訴するかどうかを判断する際、被害者の処罰感情や被害の回復状況も重要な要素とします。
そのため、あらかじめ示談を成立させておくことは、不起訴処分や処分の軽減につながる大きなポイントになるのです。
ただし、加害者本人が直接謝罪や示談を申し出ることは慎重におこなうべきです。
なぜなら、被害者の感情を逆なでするおそれがあるだけでなく、態度によっては謝罪や返金の意思が「脅迫」と受け取られてしまうリスクもあるからです。
そのため、示談交渉は必ず弁護士を通じておこなうようにしましょう。
弁護士が第三者として中立的かつ法的な立場で関与することで、より安全かつ円滑に話を進められます。
さいごに|結婚を信じ込ませて金銭をだまし取れば結婚詐欺になる!
本記事では、結婚詐欺についてわかりやすく解説しました。
結婚を信じ込ませて金銭を受け取る行為は、状況によっては詐欺罪に該当する可能性があります。
相手が警察に被害届を提出すれば、捜査が進み、結婚詐欺と認定されれば、10年以下の懲役という重い刑罰が科されることもあります。
決して軽く考えてよい問題ではありません。
実刑判決や前科を避けるためには、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談すれば、現状の整理や今後の見通し、逮捕・起訴を避けるための具体的な対応、被害者との示談交渉の支援など、専門的なサポートを受けることができます。
「ベンナビ刑事事件」を利用すれば、詐欺事件を得意とする弁護士を地域に応じて簡単に検索できます。
できるだけ早めに弁護士のサポートを受けるためにも、ぜひご利用ください。