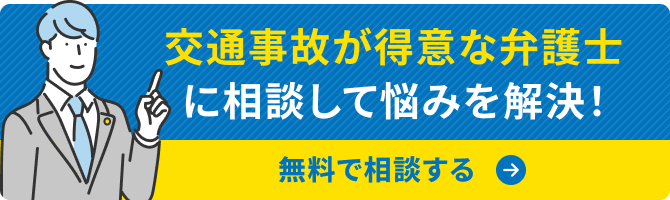- 「もらい事故ではどこまで費用を請求できるのか」
- 「全損の買い替え手続きはどのように進めればよいのか」
自分にはまったく過失がない「もらい事故」で車が全損し、買い替えを余儀なくされるケースは決して珍しくありません。
実際、もらい事故に遭ってしまい、車の買い替え費用や手続きに関して、大きな不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、もらい事故によって車が全損となった場合に請求できる「買い替え費用」について、具体的な計算方法・請求方法や見落としがちな注意点をわかりやすく解説します。
買い替え費用を適切に受け取るためのコツも紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
もらい事故で車が全損した場合は買い替え費用を請求できる!
交通事故における「もらい事故」とは、信号待ちで停車中に後方から追突されたケースなど、被害者に過失がまったくない事故を指します。
もらい事故で車が「全損」扱いとなった場合、被害者は加害者に対して買い替え費用を請求できるのが基本です。
民法第709条では、加害者は被害者に生じた損害を賠償する義務があるとされています。
修理不能で「物理的全損」になった場合や、修理費用が車両時価を大きく上回り、「経済的全損」になった場合は、買い替えに必要な費用の一部または全部を賠償請求することが可能です。
車が全損した場合に請求できる買い替え費用の計算方法・計算手順
もらい事故で車が全損となった場合に請求できる金額は、単純に新車の購入費全額ではありません。
請求金額の上限は、事故当時の車の「時価相当額」を基準にして合理的に決められます。
ここでは、買い替え費用の算定方法を3つのステップに分けて解説します。
1.「車両時価額-車両売却代」で買い替え差額を計算する
まずは、事故に遭った車の「時価額」を調べます。
車両時価額は事故直前の中古市場における価格であり、年式・走行距離・装備・状態などから算定されます。
保険会社は「レッドブック」などを用いて評価しますが、実際の市場価格と乖離があることもあるため注意が必要です。
次に、事故車を処分することで得られる「売却代」を差し引きます。
※ただし、保険会社や担当者によっては、車両の売却代を差し引かないこともあります。
たとえ全損であっても、部品取りや鉄くずとしての価値が残ることがあるためです。
したがって、以下の式で「買い替え差額」が算出されます。
たとえば、時価が100万円、事故車の売却代が10万円であれば、差額は90万円となります。
2.「(1)の買い替え差額+諸費用」で買い替え費用を計算する
次に、上記で求めた買い替え差額に、「買い替えにかかる諸費用」を加え、買い替え費用の総額を求めましょう。
以下は、もらい事故で請求可能とされる代表的な諸費用です。
【全損時に請求できる買い替え諸費用の例】
- 廃車手続費用
- 自動車リサイクル料金
- 車庫証明の申請費用
- 車庫証明手続代行費
- 登録手続代行費
- 納車費用
- 消費税相当額
- 自動車税環境性能割
上記の諸費用は、事故がなければ発生しなかった支出であるため、賠償の対象となります。
見積書などに細かく記載して積算することが大切です。
3.「(2)の買い替え費用×過失割合」で実際の賠償額を計算する
最後に、買い替え費用の総額に「過失割合」を掛けた金額が、実際に加害者側から支払われる賠償額です。
一連の計算式をまとめると以下のようになります。
とはいえ、もらい事故の場合は、被害者に過失が一切ない「10対0」となるのが基本です。
そのため、被害者の過失割合は100%、つまり「1」で計算し、買い替え差額に諸費用を加えた金額をそのまま請求することになるでしょう。
ただし、相手の保険会社が「被害者にも注意義務違反があった」として、過失割合を9対1や8対2と主張してくるケースもあります。
また、過失割合に争いがあるにもかかわらず、被害者が十分に反論できず、やむなく減額に応じてしまうケースも少なくありません。
たとえば、買い替え差額が90万円、諸費用が15万円で買い替えに合計105万円かかる場合でも、過失割合が1割認定されれば、最終的な賠償額は105万円 × 0.9 = 94万5,000円です。
※このほか、加害者車両の損害のうち、過失割合分を負担しなければならない場合もあります。
過失割合が1割違うだけで、賠償額には大きな差が生じます。
納得できない主張をされた場合には、交通事故問題が得意な弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
車が全損した場合に相手方に買い替え費用を請求する流れ|4ステップ
もらい事故で車が全損となった場合、被害者は加害者に対して買い替え費用を請求することができます。
ここでは、請求の流れを4つのステップに分けて解説します。
1.警察と自分の保険会社に連絡をする
まずは警察に連絡して、交通事故証明書を取得します。
交通事故証明書は、事故の詳細を示す書類です。
交通事故が起きたことを警察に報告していれば、作成されているはずなので、事故処理担当の窓口に問い合わせてください。
また、自分の保険会社にも連絡を入れておきましょう。
過失割合10:0のもらい事故では、保険会社に損害賠償請求の手続きを依頼することはできません。
しかし、車両保険や弁護士費用特約など、自分の契約内容によっては何かしらの補償を受けられる可能性があります。
2.車両時価や諸費用の見積もりを取る
次に、車両時価や諸費用の見積もりを取りましょう。
損害賠償請求する際には、積算根拠としてディーラーや販売店などの見積もりを提示する必要があります。
ただし、車両時価額は中古車価格情報専門誌のレッドブックを参考にするケースが一般的ですが、市場での取引価格より低く見積もられていることも多いです。
そのため、オークションサイトなどでの情報収集し、実際の取引価格で損害賠償を算定するのもひとつの方法といえます。
3.加害者や相手方保険会社と交渉する
資料がそろったら、加害者が加入している保険会社との示談交渉を開始します。
まずは、相手方の保険会社から損害賠償額を提示されるケースが一般的です。
保険会社は、車両時価や諸費用の金額、過失割合の妥当性などを検討し、賠償額の提示をおこないます。
提示内容に納得がいかない場合は、見積書や市場価格の証拠を示しながら粘り強く交渉しましょう。
4.示談がまとまれば賠償金が振り込まれる
交渉の末、賠償額に合意できた場合は、示談書を取り交わします。
そして、示談書に記載された期日までに、保険会社から賠償金が振り込まれます。
なお、示談成立後は、基本的にやり直しがききません。
少しでも不安や疑問がある場合は、示談書に署名する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
もらい事故で全損した場合の買い替え費用を適切に受け取るための4つのコツ
もらい事故では、原則として買い替え費用を全額請求できますが、実際の交渉では、想定よりも低い賠償額を提示されることも少なくありません。
適正な金額をしっかり受け取るためには、いくつかの工夫が必要です。
ここでは、買い替え費用を適切に受け取るためのポイントを紹介します。
1.車両時価を正確に算定してもらう
もらい事故で全損になった車の買い替え費用を適切に受け取るためには、まず「車両時価」を正確に算定してもらうことが極めて重要です。
なぜなら、買い替え費用の基準となるのは「事故当時の車の時価」であり、この金額が過小評価されてしまうと、請求できる総額そのものが低く抑えられてしまうからです。
実際、車両時価は「レッドブック」などを参考にすることが多いですが、実際の市場価格より低めに算出される可能性もあります。
たとえば、同じ年式・同じグレードの中古車が市場で80万円で販売されているにもかかわらず、車両時価が50万円で算定されることもあり得るのです。
この場合、被害者がそのまま示談に応じてしまえば、30万円分損することになります。
そのため、自ら中古車販売サイトなどで相場を調べ、その価格帯を提示資料として保険会社に提出するのが効果的です。
なお、中古車市場価格が不明な古い車両に関しては、新車価格の10%が車両価額の目安になります。
2.買い替え諸費用を漏れなく請求する
買い替え費用を適切に受け取るためには、本体価格だけでなく、発生した諸費用をもれなく請求することが大切です。
車の買い替えにあたっては、単に車両代金を支払うだけでなく、廃車手続費用や車庫証明の取得費、登録費用、納車費用、リサイクル料金、自動車税の環境性能割といった、さまざまな付随費用が発生します。
買い替え諸費用も事故がなければ必要のなかった支出なので、「損害」として賠償の対象に含めることができます。
請求にあたっては、各費目を具体的に区分し、見積書や領収書といった書類をきちんと保管・提出することが不可欠です。
3.過失割合に納得がいかない場合は争う
もらい事故で全損となった場合、被害者には原則として過失がないとされるため、過失割合は「10対0」となるのが基本です。
しかし、実際の示談交渉では、相手の保険会社から「9対1」や「8対2」といった不利な過失割合を提示されることがあります。
過失割合に納得できない場合は、そのまま受け入れず、争うように姿勢を持ちましょう。
保険会社が過失割合でゴネてくるのは、自社の支払額を少しでも抑えるためです。
被害者に1割の過失が認定されれば、たとえば100万円の請求が90万円に減額されることになります。
ほんのわずかな過失でも、最終的な支払額には大きな差が生じるため、過失割合の判断は交渉における極めて重要なポイントです。
たとえば、信号待ちで停車中の車に追突された場合でも、「停車位置が不適切だった」などと保険会社側が主張してくることがあります。
しかし、ドライブレコーダー映像や警察の事故証明、目撃証言などの客観的な証拠があれば、保険会社の主張が不当であることを証明できる可能性があります。
4.交通事故問題が得意な弁護士に相談する
もらい事故で車が全損となった場合の示談交渉に不安があるときは、交通事故問題が得意な弁護士に早めに相談することをおすすめします。
過失割合10:0の交通事故では、自身が加入する保険会社に示談交渉を任せることができません。
そのため、自分自身で相手方の保険会社と交渉を進める必要がありますが、交渉経験や専門知識を持たずに対応すると、十分な補償を受け取れないおそれがあります。
その点、弁護士に相談すれば、請求の漏れがないか、主張すべきポイントが適切に伝わっているかを確認してもらえるほか、相手方との示談交渉を一任することも可能です。
弁護士の介入によって、必ずしも損害賠償が増額されるとは限りません。
ただし、見落としがちな諸費用や不当な過失割合といった問題に対して、的確なアドバイスが得られるという点で、専門家の助言を受ける意義は大きいでしょう。
不当な条件で示談を終えてしまわないためにも、早い段階で弁護士に相談しておくと安心です。
もらい事故で車が全損した場合に買い替え費用を請求する際の3つの注意点
ここでは、買い替え費用の請求にあたって気をつけるべきポイントを3つに絞って解説します。
1.新車の購入代金を100%受け取れるとは限らない
もらい事故で車が全損となり、新たに車を買い替える必要が生じた場合、多くの人が「新車を買うのだから、その費用は全額補償されるだろう」と考えがちです。
しかし、実際には新車の購入代金全てを受け取れるとは限りません。
交通事故の損害賠償は、あくまでも事故前の状態に戻すことを目的とした「原状回復」が原則です。
そのため、加害者側が賠償責任を負う範囲は、事故当時の被害車両の「時価相当額」と、買い替えに伴って発生した合理的な諸費用に限定されます。
「新しい車を手に入れる費用」ではなく、「壊された車を同等の状態に戻すための費用」に相当する分だけが、損害賠償として認められるのです。
この点を理解せずに新車購入の全額を請求してしまうと、「過大請求」と判断されて交渉がこじれるおそれもあるため注意が必要です。
2.加害者が特定できない場合は請求するのが難しくなる
もらい事故で車が全損となった場合でも、加害者が特定されていない状態では、賠償請求の手続きを進められません。
たとえば、当て逃げやひき逃げといったケースでは、加害者の氏名・住所・加入保険などがわからないので、交渉すべき相手そのものが存在しない状況に陥ってしまいます。
加害者がわからない場合にやるべきことは、警察に被害届を提出することです。
そして、ドライブレコーダー映像や目撃者の証言など、少しでも手がかりとなる情報を提出し、警察による加害者特定をサポートしましょう。
当面は自己資金や車両保険で買い替え費用を捻出し、加害者が見つかれば、示談交渉で損害賠償を請求してください。
3.事故発生から3年経過すると賠償金を請求できなくなる
交通事故による損害賠償請求には「時効」が定められており、永続的に請求できるわけではありません。
民法上、物損事故における損害賠償の時効期間は、原則として「損害および加害者を知った日から3年」です。
事故から3年以上が経過してしまうと、たとえ損害が回復していなくても、損害賠償を請求する権利そのものが消滅します。
特に注意すべきは、示談交渉が長引いているケースや、事故直後に「相手保険会社からの連絡を待っているだけ」の状態が続いているケースです。
上記のような状況でも、時効は進行しており、何の措置も講じなければ突然「時効成立」で請求できなくなるリスクがあります。
なお、時効は完成を猶予させたり、更新してリセットさせたりすることも可能です。
たとえば、相手方が当事者間での協議に合意すれば時効の成立が1年間猶予され、訴訟を起こせば時効がリセットされます。
時効が近づいている場合は、一刻も早く弁護士に相談し、効果的な対処法をアドバイスしてもらうことが大切です。
さいごに|買い替え費用の請求ルールを知って適切な賠償金を受け取ろう
もらい事故で車が全損となった場合、突然の出費と不安に直面することになります。
しかし、正しい知識と手順を踏めば、適切な買い替え費用を受け取ることが可能です。
ただし、新車購入費の全額が補償されるわけではなく、時効により損害賠償請求権が消滅するリスクもあります。
泣き寝入りせず、適切な補償を受けるためにも、事実関係を丁寧に整理し、準備を整えて交渉に臨みましょう。
少しでも不安に感じることがあれば、一人で抱え込まず、弁護士に相談することをおすすめします。