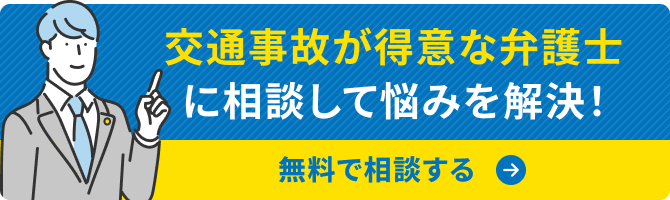- 「通勤中に事故に遭ってしまったけれど、これって労災保険の対象になるの?」
- 「自動車保険と労災保険、どちらを使うべき?」
通勤途中に事故に遭ってしまい、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
通勤途中の事故は「通勤災害」として労災保険の対象になる可能性がありますが、その適用には一定の条件があります。
また、すでに自動車保険に加入している場合、「どちらを優先して使うべきか」「併用は可能か」といった使い分けも重要です。
本記事では、通勤途中の事故における労災保険の適用条件や、自動車保険との違い・使い分けについてわかりやすく解説します。
事故後の対応で迷わないためにも、ぜひ参考にしてください。
通勤途中の事故には原則として労災保険を適用できる!
通勤途中での交通事故には原則として労災保険の適用が可能です。
そもそも労災保険とは、業務中や通勤中に起きた病気やけが、死亡事故が発生した場合に事故によって生じた労働者の損害を補償する制度です。
労災保険は労働者が必ず加入している保険で、ほかの社会保険と異なり、労災保険の保険料はその全額を事業主が負担する点に特徴があります。
そして、通勤途中に自動車事故に巻き込まれてけがをしたケースや業務中に移動している際にけがをしたケース、機械に手を挟まれて骨折したケースなども労災保険の対象となるのが通常です。
なお、業務中ではなく、通勤途中の事故やけがのことを「通勤災害」と呼びます。
通勤途中の事故で労災がおりるケース・おりないケース
通勤災害は原則として労災保険の適用対象ですが、全てのケースで労災が認められるわけではありません。
状況によっては、労災が「おりるケース」と「おりないケース」があるため、注意が必要です。
それぞれのケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。
労災がおりるケース
通勤災害として労災保険が適用されるためには、「通勤途中での事故」であることが前提になります。
つまり、事故が発生した当日に出勤予定があった、または実際に勤務していたことが必要です。
さらに、事故が起きた移動の内容や方法も重要です。
以下のようなケースで、かつ移動が合理的なルート・手段でおこなわれていた場合は、通勤災害として認められる可能性があります。
| 住居と就業場所の往復 | 自宅から職場、あるいは職場から自宅へ向かう途中の事故は、典型的な通勤災害に該当します。 ここでいう「住居」とは、実際に生活している場所を指し、住民票のある場所とは必ずしも一致しなくても問題ありません。 また「就業場所」とは、仕事を始めたり終えたりする場所のことで、通常は会社や営業所などを指します。 |
| 複数の仕事場を移動しているケース | たとえば建設業やサービス業などで、1日に複数の現場を回る場合、ひとつ目の職場から次の職場へ向かう途中の移動も「通勤」とみなされることがあります。 このような移動中の事故も、労災保険の対象となる可能性があります。 |
| 転勤のための引っ越しで移動しているケース | 会社命令による転勤にともない、引っ越し先へ移動している最中に事故に遭った場合も、通勤災害として扱われることがあります。 引っ越し自体が就業上の必要性に基づく移動と判断されるためです。 |
このように、「いつ・どこへ・どのように」移動していたのかが、通勤災害かどうかの判断ポイントとなります。
労災がおりないケース
通勤途中の事故であっても、全てが通勤災害として労災保険の対象になるわけではありません。
移動の目的やルートから逸脱している場合などは、労災として認められないこともあります。
とくに、以下のようなケースには注意が必要です。
| 仕事帰りに飲食店に立ち寄ったケース | 帰宅途中に飲食や買いもののため、通勤とは関係のないお店へ立ち寄った場合は「通勤経路からの逸脱」と見なされることがあります。 このようなケースでは、通勤災害として認められない可能性が高くなります。 |
| 休日に事故に遭ったケース | 原則として、通勤災害が認められるのは「勤務がある日」に限定されます。 したがって、就業予定のない休日に発生した事故については、通勤災害には該当しません。 |
| 私物を取りに戻ったケース | 職場に忘れたものを取りに戻る途中の事故については、その忘れものが「業務に関連するもの」かどうかが判断のポイントになります。 仕事で使う資料や機材などであれば通勤災害と認められる可能性がありますが、業務とは無関係の私物の場合は、補償の対象外となることが多いです。 |
| 会社に届出ている通勤経路から大幅に外れているケース | あらかじめ会社に届け出ている通勤経路から大幅に逸脱していた場合も、労災の対象にならない可能性があります。 寄り道の理由や経路の合理性が問われるため、正当な理由がなければ通勤災害と認められないことがあります。 |
通勤途中の事故に対する労災保険の補償内容
通勤災害に対する労災保険の補償内容は、大きく以下の7つにわかれます。
| 補償項目 | 補償内容 |
| 療養補償給付 | 療養補償給付とは、けがの治療のために必要な費用を補償するものです。 具体的には、以下の様な費用が支給されます。 ●診察費 ●薬代 ●治療費 ●入院費や看護費 ●救急車やタクシーによる移送費 ●治療用装具費(コルセットなどの費用) |
| 休業補償給付 | 休業補償給付とは、労災事故により仕事ができなかった場合に、得られるはずだった収入を補償するものです。 休業補償給付で支給される額は、平均賃金の6割となっており、これに併せて、休業特別支給金から2割が支給され、合計8割が支給されます。 なお、休業補償給付は自賠責保険で請求する休業損害とは以下の点が異なるので注意しましょう。 ●対象期間が労災保険の場合は休業開始の4日目から支給開始となるのに対し、自賠責保険の場合は交通事故が原因で休業した期間全てが対象になる。 ●休業補償は、給与基礎日額(事故前3ヵ月の1日あたりの平均給与)×60%×休業日数で計算されるのに対し、休業損害は、1日あたりの基礎収入額×休業日数で計算されます。 ●ボーナス(賞与)や有給休暇の取扱いは、休業補償では、休業特別給付金(給与基礎日額の20%を加算)が支給されるのに対し、休業損害は、休業により賞与の減額があった場合や、治療を目的に有給休暇を消化した場合にはその分の請求が可能となっています。 |
| 傷病補償年金 | 休業期間が1年6ヵ月以上になると、労働監督署署長の職権で休業補償給付から傷病補償年金に切り替わるケースがあります。 ただし、けがや疾病が傷害等級に該当しない場合には引き続き、休業補償給付を受けることになります。傷害等級ごとの傷病補償年金の額は、以下のとおりです。 ●傷病等級1級:平均賃金の313日分 ●傷病等級2級:平均賃金の277日分 ●傷病等級3級:平均賃金の245日分 休業補償では平均賃金の60%が支給されていたため、傷病補償年金の方が支給額が多くなるケースが多く見られます。 |
| 障害補償給付 | 障害補償給付は、けがや病気の治療が終わっても障害が残ってしまった場合に支給されます。 障害補償給付を受けるためには後遺障害等級認定を受ける必要があり、後遺障害等級に応じて金額や支給の種類が変わります。 ●年金形式:等級1級~7級 ●一時金形式:等級8級~14級 |
| 介護保障給付 | 傷病補償年金と障害補償給付を受ける権利がある場合には介護補償給付が労災保険から支給されます。 介護がどの程度必要かや、介護に当たる人が親族や友人、知人なのかによっても支給額が異なります。 ●常時介護が必要な場合:月額70,790円~165,150円 ●随時介護が必要な場合:月額35,400円~82,580円 |
| 遺族補償給付 | 労災事故により労働者が死亡した場合、以下の人へ遺族補償給付が支給されます。 配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 以上の関係者は遺族補償給付の対象となります。遺族補償給付が受けられるかに当たっては、その関係者が被害者の収入で生計を立てていたかが判断要素となります。 そのための判断基準のひとつとして被害者と同居していたかどうかが大きな考慮要素となります。 したがって、子どもが近所に住んでいて頻繁に会っていたが、同居はしていなかったというケースでは支給の対象外とされる可能性があります。 |
| 葬祭料 | 葬祭料は、被害者が死亡し葬祭をする際に、葬祭をおこなう人(喪主など)に支給されます。 葬祭料は以下のもののうち、高い方が支給されます。 ●31万5,000円+被害者の事故前における平均賃金の30日分 ●被害者の事故前における平均賃金の60日分 |
通勤途中の事故は労災保険と自動車保険(自賠責保険・任意保険)のどちらを選ぶべき?
ここまで、通勤途中の事故が「通勤災害」として労災保険の対象になることを紹介してきました。
では実際に事故が起きた場合、労災保険と自動車保険(自賠責保険や任意保険)のどちらを利用すべきなのでしょうか?
それぞれの特徴や補償内容の違いをふまえて、わかりやすく解説します。
【前提】労災保険と自動車保険は併用できるが二重取り部分は支給調整される
前提として、労災保険と自動車保険は併用可能ですが、補償の内容が一部重複するため、重複する部分は二重取りできないように支給調整がされる仕組みになっています。
労災保険と自動車保険とで重複する補償は以下のものがあります。
- 治療費
- 休業に対する補償
- 後遺障害に対する補償
- 介護が必要になった場合の補償
- 葬儀費用
- 遺族への補償
以上の補償については二重取りにならないように支給調整がなされることを覚えておきましょう。
労災保険を先に請求したほうがよいケース
労災保険を先に請求したほうがよいケースとしては以下のケースが挙げられます。
- 被害者の過失割合が大きい場合
- 加害者が不明な場合や無保険の場合
- 治療が長引きそうな場合
- 治療費の先払いを避けたいとき
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
被害者の過失割合が大きい場合
交通事故において被害者の過失割合のほうが大きい場合、労災保険から先に請求したほうがよいでしょう。
なぜなら、自動車保険では被害者と加害者の過失割合に応じて保険金を減額したり増額したりする仕組みになっており、被害者の過失割合のほうが大きい場合には保険金の額が大幅に減額される可能性があるからです。
一方、労災保険は過失割合の大きさや有無によって補償額が変わるといったことはありません。
そのため、労災保険から先に請求することで、補償額の減額を防ぐことができるのです。
加害者が不明な場合や無保険の場合
加害者がいる事故は、労災保険の制度上「第三者行為災害」と呼ばれます。
第三者行為災害では、被害にあった労働者は労災保険による補償を受けられるだけでなく、加害者(第三者)に対して損害賠償を請求する権利も持つことになります。
ただし、加害者がひき逃げで特定できない場合や、任意保険・自賠責保険のいずれにも加入していない無保険者だった場合は、加害者側からの補償が受けられません。
このようなケースでは、労災保険を先に活用することで、治療費や休業補償などを早期に受け取れる可能性があります。
つまり、加害者が特定できない・補償を受けられない状況では、労災保険の申請を優先するのが安心といえるのです。
治療が長引きそうな場合
治療や通院が長期にわたる可能性がある場合は、労災保険を優先して請求することをおすすめします。
というのも、自賠責保険には支払い限度額があるためです。
たとえば、交通事故でけがを負った場合、自賠責保険から支払われる傷害の補償は最大120万円までと定められています。
そのため、治療費や通院費、休業による損失額がこの上限を超えてしまうと、超過分は被害者自身が負担しなければならない可能性があるのです。
一方で、労災保険の「療養補償給付」には上限がなく、治療が長引いても原則として必要な費用を継続的にカバーしてもらえます。
安心して治療を受けるためにも、補償の充実した労災保険を活用することが重要です。
治療費の先払いを避けたいとき
治療費の先払いを避けたいときも労災保険を利用することをおすすめします。
労災によるけがで、労災保険の指定医療機関で治療を受けた場合は、「現物給付」として扱われるため、治療費を自己負担する必要はありません。
つまり、病院での支払いを求められることなく、そのまま治療を受けられるということです。
治療費をいったん自分で立て替えるのが難しい方や、先にお金を支払いたくない場合は、労災保険を利用するのが安心です。
自動車保険を先に請求したほうがよいケース
反対に、以下のようなケースでは、自動車保険を先に利用するのがよいでしょう。
- 仮渡金を受け取りたいとき
- 慰謝料を早く受け取りたいとき
- 自賠責の保険金請求権の時効期間が経過しそうなとき
それぞれのケースについて、詳しく解説します。
仮渡金を受け取りたいとき
自賠責保険には「仮渡金(かりわたしきん)」という制度があり、一定の条件を満たすと、あらかじめ定められた金額を迅速に受け取ることができます。
たとえば、交通事故で被害者が死亡した場合は290万円、けがをした場合にはその程度に応じて、40万円・20万円・5万円のいずれかが支給されます。
この仮渡金制度は、被害者が早期に生活費や治療費の一部をまかなえるように設けられた仕組みですが、労災保険には同様の制度はありません。
そのため、「すぐにまとまったお金が必要」という場合には、自賠責保険を先に請求したほうがよいでしょう。
慰謝料を早く受け取りたいとき
労災保険では、治療費や休業補償などは対象となりますが、「慰謝料」は補償の対象外です。
一方、自動車保険(自賠責保険や任意保険)では、交通事故によるけがや後遺障害によって生じた精神的苦痛に対して、慰謝料が支払われる仕組みがあります。
そのため、慰謝料の補償を早く受けたい場合には、労災保険よりも自動車保険を先に請求することを検討するとよいでしょう。
自賠責の保険金請求権の時効期間が経過しそうなとき
自賠責保険の保険金請求権の時効期間は、被害者が交通事故による損害および加害車両の運行共用車を知ったときから3年とされています。
一方、労災保険給付の時効期間は5年とされているため、原則として自賠責保険の時効のほうが先に到来します。
そのため、自賠責保険の時効期間が迫っている場合には、先に自賠責保険を請求するようにしましょう。
交通事故で労災を使わないほうがよいケースはある?
労災保険が使えるケースで「労災保険を使わないほうがよい」というケースはありません。
労災保険を使うことは、労働者に認められた権利なので、使えるときは使うようにしましょう。
ただし、以下のようなケースでは労災が使えない場合もあるので注意が必要です。
- 業務外の移動中に交通事故に遭った場合
- 故意に交通事故を発生させた場合
- 通勤経路として合理的な経路・手段から外れた場所で交通事故に遭った場合
- 被害者が労災保険の対象である労働者に該当しない場合
- 労災の申請期限を過ぎている場合
労災が使えるかどうかわからない場合は、社内の担当者に確認するほか、弁護士などの専門家に相談することも検討してください。
通勤途中の事故で労災保険を適用する際の注意点
通勤途中の事故に労災保険を適用する際には以下の点に注意しましょう。
労災給付を受ける場合は健康保険を利用できない
労災によるけがや病気については、原則として健康保険を使うことができません。
ただし、労災病院や労災保険の指定医療機関で治療を受ける場合は、窓口で「療養給付たる療養の給付請求書」を提出することで、治療費の全額が労災保険から支払われます。
そのため、自己負担は発生しません。
一方で、労災保険の指定外の医療機関で受診すると、健康保険も使えず、治療費を全額自己負担しなければならないことになります。
思わぬ高額負担となる可能性があるため、労災によるけがの治療は、できるだけ指定医療機関で受けるようにしましょう。
示談成立後は原則として労災保険を適用できない
交通事故の相手方と示談が成立した場合、その後は原則として労災保険の給付を受けることができなくなる点に注意が必要です。
ここでいう「示談」とは、交通事故によって発生した損害について、被害者と加害者が話し合いによって賠償額を決め、その金額で最終的な解決とする合意のことを指します。
一度示談が成立すると、それ以上の損害賠償請求は原則としてできなくなります。
そのため、仮に示談後に症状が悪化して追加の治療費がかかった場合でも、示談金以上の補償を受けることはできません。
このようなリスクを避けるためにも、示談に応じるタイミングは慎重に判断することが大切です。
とくに、今後の治療や後遺症の可能性がある場合には、示談前に専門家へ相談しておくと安心です。
労災保険は給付内容ごとに時効が設定されている
労災保険には給付内容ごとに時効が設定されています。
時効期間を経過すると給付を受けられなくなってしまうため、必ず時効前に手続きをおこなうようにしましょう。
各給付内容ごとの時効期間は以下のとおりです。
- 療養給付:療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
- 休業給付:賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
- 障害給付:傷病が治癒した日の翌日から5年
通勤途中の事故で労災保険を適用する際に必要な手続き
通勤中の事故について労災保険を適用する際には、以下のような手続きが必要になります。
- 労働者が雇用主に対し労働災害が発生した旨を報告する
- 雇用主は必要書類をそろえて労働基準監督署に提出する
- 労働基準監督署が調査・審査をおこなう
- 保険金の給付が決定されると給付がなされる
申請手続は原則として労働者本人がおこなうことになっていますが、本人による申請・手続きが困難な場合には雇用主が申請手続を補助することが義務付けられているため、手続きを雇用主が代行することも可能です。
なお、労災申請で必要な書類は、請求する給付ごとに異なり、所定の様式は労働基準監督署のホームページでダウンロード可能です。
さいごに|通勤途中の事故に関して迷ったときは弁護士に相談を
通勤途中の交通事故で、労災保険を優先すべきか、自動車保険を先に使うべきかは、事故の状況や補償内容によって異なります。
そのため、被害者ご自身だけで判断するのが難しいケースも少なくありません。
とくに、加害者との過失割合や、示談の可否といったポイントは、過去の判例や法的知識が必要になるため、個人では判断がつかないことが多いでしょう。
こうした場面では、早い段階で弁護士に相談するのが安心です。
交通事故に強い弁護士であれば、あなたの状況に合った最適な補償の受け方や進め方をアドバイスしてくれるはずです。
迷ったときは、一人で抱え込まず専門家の力を借りてみましょう。