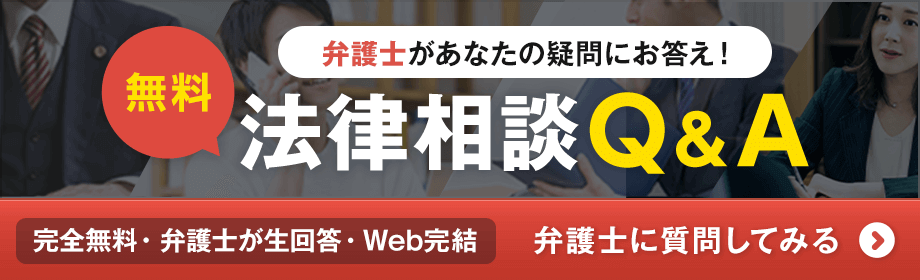交通事故で休業した場合に受け取れるものとしては、休業損害や休業補償などがあります。
休業損害が加害者側の保険会社から支払われるのに対し、休業補償は労災保険から支払われます。
また、それぞれ計算方法が異なるほか、休業補償については受給条件なども定められています。
ミスなくスムーズに事故対応を済ませるためにも、休業損害と休業補償の特徴や違いについて正しく理解しておきましょう。
本記事では、交通事故の休業損害・休業補償の定義や計算方法、もらうまでの流れなどを解説します。
交通事故の休業損害(休業補償)とは?
まずは、休業損害と休業補償がどのようなものなのかを解説します。
休業損害は損害賠償金の1つ
休業損害とは損害賠償金のひとつで、人身事故のケガによって収入の減額が発生した場合に請求できます。
交通事故における損害には積極損害・消極損害・慰謝料・物的損害などがあり、休業損害は消極損害に属します。
休業補償は労災保険の給付金の1つ
休業補償とは、労災保険の給付金のひとつです。
通勤中や業務中などに起きた交通事故の場合、休業補償も請求できる可能性があります。
休業損害との大きな違いは、休業補償では「業務に関する事故を対象としている」という点です。
たとえば「客先をまわる際に営業車で交通事故を起こした」「高所作業中に転落した」「通勤・帰宅の途中にけがをした」というようなケースでは、休業補償の対象となります。
交通事故の休業損害の対象・計算方法
交通事故の休業損害は、休業日数・職業・前年の収入状況などのさまざまな要素をもとに算定されます
ここでは、休業損害の計算方法について解説します。
休業損害の算定基準
休業損害では以下のような3種類の算定基準があり、それぞれ計算方法が異なります。
- 自賠責基準:自賠責保険が用いる計算基準で、最も低額になりやすい
- 任意保険基準:各任意保険会社が用いる計算基準で、自賠責基準よりも高額になりやすい
- 弁護士基準:弁護士や裁判所が用いる計算基準で、最も高額になりやすい
各算定基準の計算方法は以下のとおりです。
自賠責基準|自賠責保険が用いる基準
自賠責基準の場合、以下のような式で計算します。
- 休業損害=1日あたり6,100円×休業日数
ただし、会社側が発行した休業損害証明書などの立証資料によって1日あたりの収入額がこれを超えることが明らかであれば、1日あたり1万9,000円を上限に引き上げられます。
この計算式では請求者の職業などを考慮しないため、計算結果と実際の減収分との間に大きな差が生じてしまう可能性があります。
なお、自賠責保険では、治療費や慰謝料などを含めた傷害に対する賠償額の上限が120万円に定められています。
入院が長引いて治療費が高額になったりした場合は、自賠責保険からは減収分を満額得られない可能性があります。
任意保険基準|任意保険会社が用いる基準
任意保険基準については、保険会社によって計算方法が異なるうえ公開されていません。
具体的な計算式は不明ですが、自賠責基準と同額かやや高額程度になるのが一般的です。
弁護士基準|弁護士が用いる基準
弁護士基準の場合、以下のような式で計算します。
- 休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
弁護士基準では実際の収入状況などをもとに算定されるため、自賠責基準などに比べて高額な金額を受け取れる可能性があります。
基礎収入の求め方
弁護士基準の場合、基本的に1日あたりの基礎収入は「事故前3ヵ月分の給与額÷90日」で求めます。
ただし、被害者の職業によっては異なる場合もあり、詳しくは「【職業別】休業損害の計算方法」で後述します。
休業日数の考え方
休業日数は「けがが完治または症状固定となるまでの間に治療で仕事を休んだ日数」が対象となります。
病院に行くために有給を使ったり仕事を早退したりした場合も、休業日数に含まれます。
休業損害の計算方法
各計算基準での休業損害の計算方法をまとめると、以下のとおりです。
- 自賠責基準:1日あたり6,100円×休業日数
- 任意保険基準:不明
- 弁護士基準:1日あたりの基礎収入×休業日数
【職業別】休業損害の計算方法
弁護士基準を用いる場合、休業損害の計算方法は職業などによって異なります。
以下では職業ごとの計算方法を解説します。
給与所得者・サラリーマンの場合
会社から給料をもらっている給与所得者・サラリーマンの場合は、収入額が明確なので計算も簡単です。
- 休業損害=事故前3ヵ月分の給与額÷稼働日数×休業日数
事故前3ヵ月分の給与額は、会社に「休業損害証明書」を作成してもらって証明することになります。
保険会社側が用意した様式を利用するのが一般的ですが、会社側が独自に作成した証明書が交付されることもあり、必要事項がしっかりと記載されているかのチェックが大切です。
なお、休業損害証明書とあわせて源泉徴収票や所得証明書・課税証明書の提出を求められることもあるため、臨機応変に対応しましょう。
自営業者の場合
個人商店の経営者やフリーランスなどの自営業者は、事故前1年間の所得額を基準として1日あたりの基礎収入を算出します。
- 休業損害=事故前1年間の合計所得額÷365日×休業日数
所得額を証明するために、確定申告書の控えや課税証明書などの提出を求められるのが一般的です。
確定申告をしていない場合や、過少申告などで所得額が実収入額を反映していない場合などは、銀行口座の取引明細・帳簿類などで丁寧に証明する必要があります。
専業主婦・専業主夫の場合
専業主婦・専業主夫といった家事労働者でも、休業損害の請求が可能です。
この場合は実収入が存在しないため、性別・年齢に応じた「賃金センサス」の平均給与額を参考にします。
- 休業損害=賃金センサスを参考とした平均年収÷365日×家事労働ができなかった日数
なお、兼業主婦・兼業主夫の場合は、実際の収入額と賃金センサスを参考とした平均給与額のいずれか高いほうを用いるのが一般的です。
また、具体的な証拠によって兼業の状況を明らかにできる場合は、実態に即した計算も可能です。
アルバイト・パート従業員の場合
アルバイト・パート従業員などの非正規雇用の場合でも、サラリーマンと同じように休業損害の請求が可能です。
- 休業損害=事故前3ヵ月分の給与額÷稼働日数×休業日数
ただし、シフト制で勤務するアルバイト・パート従業員の場合は、勤務日数が一定でなかったりして、月ごとの収入にばらつきが生じやすくなります。
このようなケースでは、90日で割るのではなく実際の稼働日数で割って日額を算出することもあります。
無職の場合
原則として、失業中の無職者では休業損害の請求は認められません。
ただし「すでに就職先が決まっていた」「一定期間をおいて就職する蓋然性が高かった」といった事情があれば、内定先の給与額や賃金センサスを参考とした休業損害の請求が認められる可能性があります。
【就職先が決まっていた場合】
- 休業損害=内定先の3ヵ月の給与合計額÷90日×休業日数
【就職する蓋然性が高かった場合】
- 休業損害=賃金センサスを参考とした平均年収÷365日×休業日数
学生の場合
学生も収入がない立場なので、基本的には休業損害の請求は認められません。
ただし、アルバイトで働いていた場合や、すでに就職先が決まっていた場合などは、休業損害を請求できる可能性があります。
【アルバイトで働いていた場合】
- 休業損害=事故前3ヵ月分の給与額÷90日×休業日数
【就職先が決まっていた場合】
- ①休業損害=内定先の3ヵ月の給与合計額÷90日×休業日数
- ②休業損害=賃金センサスを参考とした平均年収÷365日×休業日数
※①・②のいずれかが適用
たとえば「すでに就職先が決まっており、大学を卒業する前のタイミングで交通事故に遭って就職が遅れた」といったようなケースでは、就職が遅れた期間を休業日数として考えることになるでしょう。
交通事故の休業補償の対象・計算方法
休業補償の場合、休業損害とは計算方法が異なるほか、受給条件なども定められています。
ここでは、交通事故の休業補償について解説します。
休業補償の受給条件
休業補償を受け取るためには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
- 業務または通勤による負傷や疾病の療養中であること
- 休業によって賃金が発生していないこと
- 労働できる状態ではないこと
休業損害ではけがの治療で有給を使った場合も休業日数に含めて請求できますが、休業補償の場合は請求対象外となります。
なお、休業の初日から3日間までを「待機期間」といい、この間の休業補償は受け取れません。
この3日間については、事業主から労働基準法にもとづく休業補償が支払われます。
休業補償の計算方法
休業補償の場合、以下のような式で算出します。
- 休業補償(給付)=給付基礎日額の60%×対象日数
給付基礎日額については「事故前3ヵ月間の給与総額÷90日」または「事故前1年間の給与総額÷365日」で算出します。
また、休業補償特別支援金として給付基礎日額の20%×対象日数も支払われます。
交通事故の休業損害のもらい方
ここでは、交通事故での休業損害の請求手続きについて解説します。
休業損害をもらうまでの流れ
休業損害のもらい方としては「毎月もらう方法」と「示談成立時にまとめてもらう方法」の2通りがあります。
それぞれの主な流れは以下のとおりです。
【毎月請求する場合】
- 加害者側の任意保険会社に必要書類を提出する
- 加害者側の任意保険会社が手続きをおこなったのち、休業損害が支払われる
【示談交渉にて請求する場合】
- 加害者側の任意保険会社に必要書類を提出する
- 休業損害を含む示談金額が提示されて示談交渉をおこなう
- 示談成立後にまとめて支払われる
休業損害を請求する際の必要書類
休業損害を請求する際の必要書類は、被害者の職業などによって以下のように異なります。
- 給与所得者の場合:休業損害証明書・事故前年分の源泉徴収票
- 自営業者の場合:確定申告書の控え
- 専業主婦・専業主夫の場合:家族分の記載がある住民票・源泉徴収票・休業損害証明書(兼業主婦・兼業主夫の場合)
- アルバイト・パートの場合:休業損害証明書・事故前年分の源泉徴収票
- 無職の場合:求職活動していたことを証明する書面・内定通知書
- 学生の場合:源泉徴収票・内定通知書・就労時期が遅れたことを証明する書面
交通事故で休業損害の請求を弁護士に依頼するメリット
加害者側の保険会社が提示する休業損害の金額に納得できない場合や、自力での請求手続きが不安な場合などは、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。
休業損害の増額が期待できる
相手保険会社が提示する休業損害の金額は、基本的に自賠責基準または任意保険基準を用いて算出されています。
弁護士に依頼すれば、最も高額になりやすい弁護士基準を用いて請求対応を進めてくれます。
これまで休業損害の増額交渉を渋っていた保険会社でも、弁護士が請求することで対応が変わって応じてくれることもあります。
元気に仕事をしていたときと同等の休業損害を得られれば、安心して治療にも専念できるでしょう。
職業に応じた証拠の収集を任せられる
実際の収入額を基準に休業損害を請求するためには、事故前の収入額や稼働状況などを客観的に証明する資料・証拠を提示しなくてはなりません。
交通事故トラブルや労務関係に詳しくない素人がこれらの資料・証拠を集めるのは容易ではないでしょう。
突然の交通事故に巻き込まれて、精神的苦痛を受けながら治療に取り組んでいるような状況であればなおさらです。
請求のために必要な資料・証拠の収集は、弁護士に任せるのが最善でしょう。
休業損害の請求トラブルについて解決実績が豊富な弁護士であれば「どのような資料が有効なのか」「どのような証拠を用意するべきなのか」などのノウハウも持っており、的確に動いてくれます。
保険会社との交渉・やり取りを一任できる
休業損害は、示談をまとめる前段階からでも請求可能です。
治療期間が長引けば保険会社とのやり取りの回数も多くなり、わずらわしさを感じることになるでしょう。
また、まだ治療が必要で休業もやむを得ない状況なのに、保険会社が「そろそろ治療費を打ち切りにしたい」などと打診してくることもあります。
個人で対応しても真摯な対応が期待できない場合は、弁護士に一任しましょう。
弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りのわずらわしさから解放されるだけでなく、保険会社に交渉の主導権を握られるリスクも回避できるでしょう。
交通事故の休業損害を弁護士に依頼する流れ
休業損害などの請求対応を弁護士に依頼する場合、基本的には以下のような流れで手続きが進行します。
- 弁護士を探す
- 相談予約をして法律相談をおこなう
- 弁護士と契約を結ぶ
- 弁護士が加害者側と交渉をおこなう
- 示談成立して休業損害などが支払われる
なお、弁護士に法律相談する際は「相談料」、請求対応を依頼する際は「着手金」、示談成立した際は「成功報酬」などの弁護士費用が発生します。
弁護士費用は依頼先事務所によってもバラつきがあるため、具体的な金額などを知りたい方は直接事務所に確認してください。
交通事故の休業損害について弁護士を探す際のポイント
休業損害に関するトラブルを納得のいく形で解決するには、弁護士のサポートが欠かせません。
ただし「弁護士なら誰でもよい」というわけではなく、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談する
休業損害の請求などを依頼する際は、交通事故トラブルの解決に力を注いでいる実績豊富な弁護士を選ぶ必要があります。
弁護士には「借金問題の解決に注力している」「刑事事件に注力している」「労働問題・離婚問題・知的財産問題に注力している」など、それぞれ得意としている分野があります。
全ての弁護士が交通事故トラブルの解決を得意としているわけではないため、弁護士選びを間違えると期待した結果が得られないおそれがあるのです。
休業損害などの事故後対応が得意な弁護士の探し方
休業損害のトラブル解決が得意な弁護士を探す際は、交通事故トラブルに特化した弁護士ポータルサイトを活用するのがおすすめです。
当社が運営する「ベンナビ交通事故」では、お住まいの地域・相談内容を選択するだけで、付近で対応可能な弁護士を一括検索できます。
休業損害などのトラブル解決に力を注いでいる弁護士を検索できるだけでなく、初回相談無料・夜間や休日の相談可能・着手金0円プランあり、などの細かい条件検索も可能です。
交通事故の休業損害に関するよくある質問
ここでは、交通事故の休業損害に関するよくある質問について解説します。
休業損害はいつもらえる?いつまでもらえる?
交通事故の休業損害については「毎月もらう」「示談成立時にまとめてもらう」のどちらかを選択して受け取ることになります。
休業損害をもらえる期間は「けがが完治または症状固定となるまで」が原則です。
交通事故の休業補償は1日いくら?
交通事故の休業補償は「給付基礎日額の60%×休業日数」で算出します。
給付基礎日額については「事故前3ヵ月間の給与総額÷90日」または「事故前1年間の給与総額÷365日」で計算します。
また、休業補償特別支援金として給付基礎日額の20%×対象日数も支払われます。
休業損害を受け取る際に税金はかかる?
休業損害などの損害賠償金は非課税所得であり、課税されません(所得税法第9条1項18号)。
有給休暇を使っても休業損害は請求できる?
けがの治療のために有給休暇を使った場合も、休業日数に含まれます。
ただし、自己判断で有給休暇を使って自宅療養した場合や、弁護士に相談するために有給休暇を使った場合などは対象外になる可能性があります。
休業損害の請求に時効はある?
交通事故の損害賠償請求権の時効期間は5年であり、時効成立したものについては請求できなくなります(民法第724条の2)。
事故後に退職した場合も休業損害は認められる?
「交通事故のけがが原因で仕事が続けられなくなり退職した」というようなケースでは、退職後も休業損害を一定期間受け取れることもあります。
ただし、そのためには交通事故と退職の因果関係を証明する必要があります。
「どのような仕事内容だったのか」「自己都合退職か会社都合退職か」「再就職は可能か」など、さまざまな点を考慮したうえで判断されるため、詳しくは交通事故トラブルが得意な弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
まとめ
交通事故で休業した場合は休業損害や休業補償などを請求できます。
被害者の収入によって金額は変わり、休業損害についてはどの計算基準が適用されるのかによっても大きく変動します。
十分な金額の補償を得るためには、休業損害の請求などの交通事故トラブルが得意な弁護士によるサポートが必須です。
相手方との交渉が難航している方や、自力での請求対応が不安な方などは「ベンナビ交通事故」で事故対応をサポートしてくれる心強い弁護士を探しましょう。