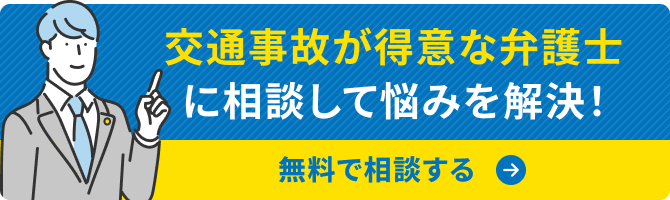突然の交通事故に巻き込まれた際、多くの被害者が戸惑うのが「保険会社とのやり取り」です。
とくに、自分が被害者であるにもかかわらず、加害者側の保険会社から連絡が来て、治療費や示談の話を進められるという状況に、違和感や不安を覚える方も少なくありません。
- 「相手の保険会社からの連絡がない」
- 「治療費の支払いが突然打ち切られた」
- 「示談金額があまりに低い」
このようなトラブルに直面したとき、どのように対処すればよいのでしょうか。
本記事では、被害者の立場で押さえておくべき「交通事故後の保険会社対応」について、トラブル事例や相談先も含めてわかりやすく解説します。
弁護士に相談すべきタイミングや相談方法についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
交通事故の被害者は加害者側の保険会社とやり取りをすることが多い
交通事故に遭った際、被害者が交渉する相手は、加害者本人ではなく、加害者側の「保険会社」であることがほとんどです。
その背景には、日本における自動車保険の高い加入率があります。
2023年度の統計によると、約88.7%のドライバーが任意保険または共済に加入しており、事故の多くは任意保険を通じて処理されています。
多くの保険会社では、事故対応の一環として「示談代行サービス」を提供しており、被害者との損害賠償交渉や治療費の支払いを加害者に代わっておこないます。
たとえば、事故直後に加害者が自分の保険会社へ連絡すると、その保険会社の担当者が被害者に連絡し、通院・修理・示談交渉などを引き継ぐ仕組みです。
これにより、当事者間での感情的なやり取りを避け、円滑な解決が図られます。
ただし、加害者が任意保険に加入していないケースや、被害者に過失がゼロの「もらい事故」では示談代行が使えないため、被害者自身が交渉するか、弁護士の力を借りる必要があります。
交通事故の被害者が加害者側の保険会社とやり取りをするタイミング
保険会社とのやり取りは、事故直後から示談交渉に至るまで、以下の3つの段階に分けられます。
それぞれのタイミングで、どのような連絡や確認があるのかを見ていきましょう。
1.事故直後|今後の流れなどの説明を受ける
交通事故が発生し、加害者が自身の保険会社に事故の報告をすると、通常は加害者側の保険会社から被害者に連絡が入ります。
保険会社の担当者からは、「このたびは事故に遭われて大変でしたね」といったお見舞いの言葉とともに、今後の補償の流れや必要な手続きについての説明がなされるのが通常です。
連絡の際に案内される内容は、事故の内容や被害状況に応じて異なりますが、一般的には以下のような確認事項や説明がおこなわれます。
| 項目 | 内容の概要 |
| 事故状況の確認 | 発生日時、場所、事故の経緯などの事実確認 |
| けがの状態の確認 | 傷害の部位や程度、通院の必要性、症状の経過などの把握 |
| 就労への影響の確認 | 仕事を休んでいるかどうか、収入への影響の有無、休業補償に関する情報の確認 |
| 通院先・立替金の確認 | 通院先の医療機関名や治療費を一時的に立て替えているかなどの情報 |
| 一括払に関する意思確認 | 自賠責保険からの支払い分を含めて保険会社がまとめて支払う「一括払」の希望有無 |
| 医療機関への直接支払いに関する確認 | 治療費を保険会社が医療機関に直接支払うか、被害者が立て替えるかの取り決め |
| 必要書類の案内と返送依頼 | 賠償手続きに必要な書類の説明と提出のお願い |
| 今後の連絡タイミングに関する調整 | 被害者の都合に配慮した連絡時間帯や頻度などのすり合わせ |
これらの内容は、一度にまとめて説明される場合もあれば、何度かに分けて連絡されることもあります。
また、必要書類として保険会社から郵送されるものもいくつかあります。
| 書類名 | 目的・用途 |
| 同意書 | 医療機関等から診療情報を取得するため、被害者の個人情報を取り扱うことへの同意書 |
| 口座確認書類 | 保険会社から被害者へ賠償金を振り込むための口座情報を記載する書類 |
| 入院・通院交通費明細書 | 通院や入退院にかかった交通費を補償するために使う申告用の明細記入用紙 |
これらの書類は、損害賠償の対象となる範囲を明確にするために必要です。
提出が遅れると支払いも遅れてしまうおそれがあるため、不明点があれば遠慮なく保険会社の担当者に確認しましょう。
このように、事故直後の連絡は「今後の補償方針の共有」「手続きの流れの説明」「必要書類の案内」といった初期対応を目的としており、まだ示談交渉には入りません。
被害者にとっては、事故後の見通しを立てるための重要なタイミングでもあるため、連絡内容は必ずメモを残すなどして記録しておくことをおすすめします。
2.治療中|通院や治療の状況などを確認される
治療が始まると、加害者側の保険会社の担当者から、被害者の通院状況や症状の経過について定期的に連絡が入るようになります。
これは、治療が必要かつ適切な内容でおこなわれているかを確認し、保険会社として支払いを継続するかどうかを判断するためのものです。
保険会社からの連絡では、通院の頻度や医師の診断内容、仕事への影響などが尋ねられることが一般的です。
聞かれた内容にはできるだけ正確に答え、日々の通院状況や症状の変化についてはメモを取っておくと、後の交渉や証拠として役立ちます。
3.完治後|示談の案内や話し合いがおこなわれる
交通事故によるけがが完治した、または「症状固定」と診断された段階で、相手の保険会社から示談交渉の連絡が入ります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医学的に判断される状態のことです。
示談では、治療費や休業損害、慰謝料などを合算した金額が提示され、内容に納得すれば署名・押印して合意となります。
ただし、交通事故の損害が確定してからでなければ示談は始められません。
後遺症が残っている場合には、後遺障害等級の認定結果が出てから交渉に進むのが通常です。
示談交渉が始まったら、送付された書類の内容をよく確認し、不明点があれば保険会社に問い合わせをしましょう。
内容に納得できない場合は、自動車事故の保険会社対応に詳しい弁護士への相談も選択肢となります。
交通事故で加害者側の保険会社とやり取りをする際に多いトラブル4選
加害者側の保険会社とのやり取りの中では、被害者が不安やストレスを感じるトラブルも少なくありません。
ここではとくによくある4つのケースと、その対処法を解説します。
1.相手方の保険会社から連絡が来ない
交通事故のあと、加害者側の保険会社から被害者に連絡があるのが通常の流れですが、なかには「いつまで経っても連絡が来ない」というケースがあります。
これは、加害者が保険会社に事故を報告していない場合や、そもそも任意保険に加入していない場合、あるいは保険会社側の対応が遅れているケースなど、いくつかの理由が考えられます。
このような状況では、加害者に直接連絡を取り、保険会社に報告したかどうか、どこの保険会社と契約しているのかを確認してみるとよいでしょう。
加害者が保険会社に連絡していなければ、当然保険会社からも連絡はありませんし、未加入であれば自賠責保険や直接請求といった別の手段を検討する必要が出てきます。
また、自分が加入している自動車保険の内容を確認し、人身傷害補償保険などが付帯している場合には、そちらから補償を受けられる可能性もあります。
加害者の保険会社がわかっている場合には、被害者から直接連絡を入れて、事故の受付状況や担当部署の確認をすることも可能です。
加害者の連絡先等が分からない場合には、事故証明書を取得することで、加害者の氏名・住所・電話番号・自賠責保険会社などを確認することができます。
2.完治前に治療費の打ち切りを迫られる
通院を続けていると、ある時点で保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。
これは、保険会社が社内基準に基づいて「この程度のけがなら〇ヵ月で治るはず」と判断し、それを超えた場合に支払いを止めようとする対応です。
しかし、治療を続けるべきかどうかを判断するのは医師であり、保険会社ではありません。
主治医が治療継続を勧めているのであれば、その指示に従いましょう。
以下は、保険会社から打ち切りを打診されたときの典型的なやり取りと、その対応例です。
| 保険会社の言い分 | 被害者側の対応 |
| もう治療は必要ないのでは? | 医師に継続の必要性を確認する |
| 支払いは○日で終わります | 必要な治療なら自費で続けて記録を残す |
| 打ち切り後の費用は補償できません | 後日、示談時に請求できる可能性あり |
治療費を一時的に立て替える必要があっても、医師の診断書や領収書があれば、後日の示談交渉で補償対象となるケースもあります。
そのため、通院の記録や費用の証明書類は必ず保管しておきましょう。
3.わかりにくいなど不親切な対応をされる
保険会社の担当者とやり取りをしている中で、説明が不十分だったり、態度が高圧的だったりといった不親切な対応にストレスを感じる被害者は少なくありません。
このような場合、まずは感情的にならず、冷静に「改善してほしい点」を具体的に伝えることが重要です。
それでも対応が変わらない場合は、保険会社のカスタマーサポートや「お客様相談室」などの苦情受付窓口へ連絡してみましょう。
その際には、これまでのやり取りの内容や日時、担当者の氏名などを整理して伝えると、スムーズに対応してもらえる可能性が高まります。
4.相場よりも低い保険金の額を提示される
加害者側の任意保険会社が提示してくる示談金額は、慰謝料・治療費・休業損害などを合算した金額です。
しかし、保険会社による示談金額は、任意保険基準で計算されていることが多く、裁判所基準より低いことが一般的です。
そもそも交通事故の示談金の決定基準には、以下3つがあります。
| 基準名 | 内容・特徴 | 金額の傾向 |
| 自賠責基準 | 強制保険(自賠責)により最低限の補償をおこなう | 低い |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定している | 中間 |
| 裁判所基準 | 裁判所や弁護士が過去の判例をもとに算定する | 高い |
提示された金額がこのうちのどの基準によって計算されたものかは、保険会社からの説明だけではわからないこともあります。
そのため、少しでも金額に疑問があればその場で署名せず、「検討したい」と伝えて保留にしましょう。
判断材料として、インターネット上にある慰謝料計算機を活用するのもひとつの方法です。
通院日数やけがの程度を入力すれば、おおよその相場を把握することができます。
ただし、実際に増額交渉を進めるには、法律や過去の裁判例などに基づいた客観的な根拠が求められます。
保険会社に対して説得力のある主張をするためには、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談するのが安心です。
交通事故で加害者側の保険会社とのやり取りに不満があるときの対処法
加害者側の保険会社とのやり取りで不満や不安を感じた場合、被害者が一人で抱え込む必要はありません。
状況に応じて適切な窓口や専門家を活用することで、対応が改善されたり、補償内容が見直されることもあります。
ここでは代表的な3つの対処方法を紹介します。
1.保険会社の苦情窓口に相談する
まず試してみたいのが、保険会社が設けている「お客様相談室」や「苦情受付窓口」への相談です。
対応に問題があると感じた場合は、具体的にどのような点が不満かを整理し、担当者名や対応日などとあわせて伝えるとスムーズです。
保険会社としても企業イメージへの配慮から、真摯に対応してくれる可能性が高まります。
主要な保険会社の苦情受付先は、各社の公式サイトに記載されています。
電話やWebフォームで簡単に問い合わせできる体制が整っているため、まずは一度相談してみるとよいでしょう。
【主な任意保険会社ごとの苦情窓口】
| 任意保険会社 | 苦情窓口 |
| 東京海上日動 | お客様相談センター 0120-071-281 平日:9:00〜18:00/土日祝:9:00〜17:00 (年末年始除く) |
| 損保ジャパン | お客さま相談室 0120-668-292 平日:9:00〜17:00 (12/31〜1/3休業) |
| あいおいニッセイ同和損保 | ご不満・ご要望のお申出窓口 0120-721-101 平日:9:00〜17:00 (土日祝・年末年始除く) |
| 三井住友海上 | 保険金支払相談デスク 0120-288-861 平日:9:00〜17:00 (土日祝・年末年始除く) |
2.そんぽADRセンターに相談する
保険会社に直接苦情を申し立てても解決しない場合は、第三者機関に相談することも有効な手段です。
たとえば、日本損害保険協会が運営する「そんぽADRセンター」は、損保会社とのトラブルを中立的な立場で調整・解決するための無料相談窓口です。
相談を受けたセンターは、必要に応じて保険会社へ是正の申し入れをおこない、問題解決に向けた調整をおこなってくれます。
また、「交通事故紛争処理センター」のように、示談あっせんや裁定をおこなう機関も存在します。
過失割合や賠償額で揉めている場合は、こうした機関を活用することで、公平な判断を得られる可能性が高まります。
【参考元】相談対応、苦情・紛争の解決(そんぽADRセンター)|日本損害保険協会
3.交通事故と取り扱う弁護士に相談する
根本的な解決を目指すなら、やはり交通事故案件に精通した弁護士に相談するのが最も確実です。
弁護士が交渉に介入することで、相手保険会社の対応が変わり、示談金額が大幅に増額されるケースも少なくありません。
また、法律の専門家が間に入ることで、被害者自身の負担も大きく軽減されます。
示談交渉が難航している、または保険会社からの提示額が明らかに低いと感じた場合には、一度弁護士の意見を聞いてみる価値は十分にあります。
さいごに|示談交渉を取り扱う弁護士は「ベンナビ交通事故」で簡単に探せる
交通事故のあと、相手の保険会社とのやり取りに不安を感じたり、保険会社の対応に納得できない場面は少なくありません。
保険会社は交通事故対応に慣れている一方で、被害者にとっては初めての経験であることが多く、示談金額や手続きの流れに疑問を抱くこともあるでしょう。
そんなときは、「ベンナビ交通事故」を使えば、示談交渉に注力する弁護士を簡単に探すことができます。
地域や相談内容に応じて検索でき、保険会社との交渉や慰謝料の増額請求など、自動車事故に関する保険会社対応をサポートしてくれる弁護士が多数掲載されています。
交通事故で適正な補償を受けたいと考えるなら、泣き寝入りせず、示談成立前に一度相談してみることが大切です。