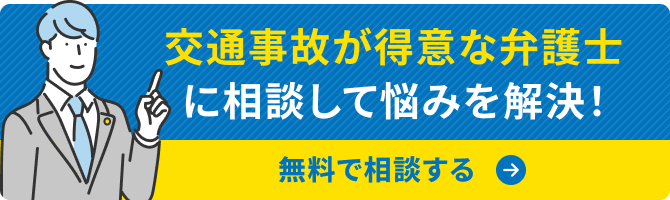自転車事故に遭ったとき、警察を呼ぶべきかどうかで迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
実際、自動車との接触事故であれば迷わず警察に通報する方が多い一方で、自転車との事故では「そこまで大ごとにする必要はないのでは」と判断してしまうこともあります。
しかし、たとえ相手が自転車であっても、事故の被害にあったのであれば、警察への通報を過度にためらうべきではありません。
その場でのやりとりだけで済ませてしまうと、あとになって保険金が受け取れなかったりするなど、不利益を受けるケースも少なくないので注意しましょう。
本記事では、自転車事故の被害者であっても警察を呼ぶべき理由と、警察に通報したあとの具体的な流れ、そして通報以外に被害者がおこなうべき対応を解説します。
自転車と歩行者の事故や、自転車同士の事故で不安を感じている方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。
自転車事故の被害であっても警察を呼ぶ必要がある!
自転車事故の被害にあったときは、警察を呼ぶことが望ましいといえます。
加害者が自転車であっても、事故に変わりはありません。
道路交通法では、自転車も軽車両に分類されており、自転車を含む車両等の運転者は事故を起こした際は警察への報告義務があると定められています。
また、被害者であっても、警察に通報しなければ「交通事故証明書」が発行されず、保険金の請求や損害賠償手続きが進められなくなるおそれがあります。
たとえば、その場で加害者と話し合いをして解決としたケースで、あとから痛みが出た場合、加害者と連絡が取れないと証拠不十分によって補償を受けられなくなる可能性があるのです。
このようなトラブルを防ぐためにも、自転車事故にあったら、警察へ通報することを心がけましょう。
自転車事故で警察を呼んでからの基本的な流れ|4ステップ
警察へ通報したあとは、自転車事故の内容や被害の程度に応じて、一定の手続きが進められます。
ここでは、被害者が知っておきたい基本的な流れを4つのステップに分けて解説します。
1.病院を受診する
自転車事故にあった直後は痛みが軽いと感じても、必ず病院を受診しましょう。
病院を受診するタイミングは、事故当日か、遅くとも2日~3日以内が望ましいとされています。
とくに、骨折や内臓の損傷などはすぐに症状が出ず、あとから悪化することもあるため、早期に適切な診断と治療を受けることが後遺症のリスクを軽減することにもつながります。
なお、受診が遅れるとけがと事故との因果関係が証明しづらくなり、賠償金の請求が難しくなるおそれもあります。
病院でかかる初診料や検査費、通院時の交通費などは、相手に請求できることが多いため、費用を理由に受診をためらう必要はありません。
事故後は無理をせず、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
2.人身事故に変更する
交通事故は「人がけがをしたかどうか」によって物損事故と人身事故に分けられます。
けがをしているのに物損事故のままでは、実況見分がされないなど、被害者にとって不利になるおそれがあります。
そのため、事故後に痛みが出た場合は、人身事故への切り替えも検討しましょう。
まずは整形外科などで診察を受けて診断書を取得し、その後、加害者側と被害者側の保険会社に連絡して切り替える旨を伝えます。
診断書が完成したら警察署に提出し、正式に人身事故として扱ってもらう手続きをおこなってください。
なお、一般的には事故から10日以内であれば人身事故への切り替えが受理されやすく、1ヵ月以上経過すると難しくなる傾向があるため、早めに変更を申し出ましょう。
3.実況見分に立ち会う
人身事故として扱われると、警察によって実況見分が実施されます。
実況見分とは、警察が事故現場に出向き、事故当時の状況を再現しながら記録をとる手続きです。
被害者と加害者の双方が立ち会い、当日の動きや位置関係について説明を求められるのが一般的です。
実況見分では、接触の位置、道路の状況、ブレーキをかけたタイミングなど、事故の客観的な要素が記録されます。
これらは「実況見分調書」としてまとめられ、過失割合や損害賠償の判断において重要な証拠となります。
立ち合いの際には、なるべく正確な記憶にもとづいて状況を説明し、事実と異なる点があればその場で伝えましょう。
4.必要に応じて刑事告訴をおこなう
事故の状況や加害者の態度によっては、刑事責任を問うために告訴を検討することも可能です。
自転車事故でけがを負った場合、加害者には過失傷害罪や重過失傷害罪が適用される可能性があります。
なかでも過失傷害罪は親告罪とされており、被害者が処罰を望む意思を警察に伝えなければ、加害者が刑事処分を受けることはありません。
告訴を希望する場合は、警察署でその意思を伝えると、告訴調書を作成してもらう流れになります。
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヵ月以内という期間制限があるため、迷っている場合でも早めの判断が求められます。
なお、告訴によって直接的な金銭的メリットが生まれるわけではありません。
加害者に対して強い処罰感情がある場合や、再発を防ぎたいと考えている場合には、選択肢のひとつとして検討してもよいでしょう。
「警察を呼ぶ」以外に自転車事故の被害者がとるべき4つの対応
自転車事故に遭った際、警察への通報は最優先にすべきですが、それ以外にも被害者自身で心がけておきたいことがあります。
後の示談や損害賠償請求を円滑に進めるために、事故直後から以下の4点を意識して行動しましょう。
1.加害者と連絡先などを交換する
事故が発生したら、まず加害者の情報を正確に確認しておきましょう。
氏名・住所・電話番号のほか、自転車保険に加入しているかどうかも確認しておくと安心です。
可能であれば、運転免許証や保険証券など、本人確認ができるものを見せてもらい、スマートフォンで撮影しておくと証拠になります。
もし事故直後に加害者の情報を十分に控えないまま別れ、そのまま連絡が取れなくなってしまうと、示談交渉や保険請求が難しくなってしまうおそれがあります。
警察が到着すれば身元確認をおこなってくれますが、通報前の段階では被害者自身で情報を押さえておくと安心です。
加害者とのトラブルを避けるために無理をする必要はありませんが、コミュニケーションがとれるのであれば「あとで確認すればいい」と思わず、その場ですぐに行動に移すようにしましょう。
2.事故現場などの写真を撮っておく
事故直後には、現場の状況をできるだけ詳しく写真に残しておくことが重要です。
時間が経つと、現場の状態は変わってしまい、事故の証拠が失われてしまう可能性があります。
たとえば、ぶつかった自転車の損傷箇所、破損した衣類やカバン、現場の道路状況、周囲の建物や標識などを記録しておきましょう。
接触のあった位置関係がわかるように、広い範囲からスマホなどで撮影するのも効果的です。
これらの写真は、事故の証拠として保険会社への提出や、示談交渉、裁判になった場合にも役立ちます。
事故の全体像を第三者に伝えるための材料として、できる限り多く、かつ正確に記録しておくことが大切です。
3.自分が利用できる保険を確認する
自転車事故の被害にあった場合でも、自分が加入している保険で補償を受けられることがあります。
事故後は早めに保険証券を確認し、必要に応じて保険会社に問い合わせておきましょう。
たとえば傷害保険に加入している場合、入院や通院、手術などが補償の対象です。
個人契約だけでなく、家族傷害保険や学校・職場を通じて加入している保険が使えることもあります。
また、任意自動車保険に付帯された人身傷害保険が、自転車や歩行中の事故に適用されるケースや、通勤中や業務中の事故で労災認定を受けられる場合もあります。
他方で、通勤中や業務中の事故でなければ、健康保険を使って治療を受けることも可能です。
その際は「第三者行為による傷病届」ほか、「傷病届」「負傷原因報告書」「事故発生状況報告書」などといった書類の提出が必要です。
【自転車事故の被害者が利用できる保険の例】
- 傷害保険
- 人身傷害保険
- 労災保険・健康保険
4.交通事故を取り扱う弁護士に相談する
自転車事故にあったあと、加害者とのやり取りや示談交渉に不安を感じる場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談しましょう。
とくに、けがが残った場合や損害賠償に納得できないときは、法律の専門家の力を借りることで状況が大きく変わる可能性があります。
まず、弁護士に依頼すれば、加害者やその保険会社との示談交渉を全て任せることが可能です。
当事者同士で交渉をおこなうと、感情的になったり、話が進まなかったりすることもありますが、弁護士を通せば冷静かつ法的に適切に対応してもらえるでしょう。
また、損害賠償の金額についても、弁護士が関係法令や過去の判例をもとに適正な金額を算出してくれます。
慰謝料や治療費、休業損害、逸失利益など、補償されるべき費用が抜け落ちることなく整理されるため、相手方に不当に低い金額を提示されても正当に反論が可能です。
さらに、示談がまとまらないときには裁判で損害賠償を請求することも視野に入ります。
弁護士がいれば、裁判所とのやり取りや証拠の準備を任せることができるため、加害者が交渉に応じないようなケースでも泣き寝入りせずに済むでしょう。
さいごに|自転車事故の被害に遭ったときも必ず警察を呼ぼう!
自転車事故は、被害が軽いと感じた場合でも、あとから症状が悪化したり、相手との示談でトラブルになったりする可能性があります。
そうした事態を避けるためにも、事故に遭ったら必ず警察に通報し、事故の記録を残しておくことが重要です。
通報をおこなえば、交通事故証明書や実況見分調書といった客観的な証拠が得られ、保険の利用や損害賠償請求の場面でも安心して対応できます。
さらに、事故直後の対応として、加害者の情報の確認や現場写真の保存、自身の保険の確認、弁護士への相談なども早めに進めておきましょう。
不安や迷いがあるときは、一人で抱え込まず、専門機関や弁護士などに相談することも大切です。
ぜひ本記事を参考にして、事故に遭った際の対応に役立ててください。