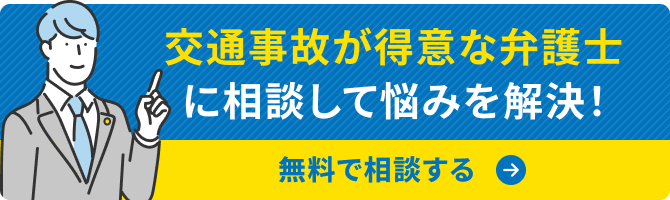- 「交通事故に遭ったけど、軽傷だから診断書は出さなくていいでしょ?」
- 「継承なのにわざわざ病院に行って事故の診断書を出すのが面倒…」
このように交通事故についての診断書を出すべきかどうかで悩んでいる方や「出さなくてもいいや」と考えている方は少なくないのではないでしょうか。
実は、交通事故でけがを負った場合、診断書を出す・出さないでその後の補償内容は大きく変わります。
そのため、正しい知識を押さえて、必ず診断を出すことが大切です。
本記事では、交通事故の診断書を出すべき理由や診断書を出さないことのデメリットを詳しく解説します。
診断書を出すべきか迷ってしまいがちなケースについても紹介するので、ぜひ今後の対応の参考にしてください。
交通事故でけがをしたら診断書は出すべき!出さない3つのリスク
結論からお伝えすると、交通事故が原因でけがをした場合は、できるだけ診断書を出すことをお勧めします。
交通事故に巻き込まれてけがをしたのに診断書を出さないままだと、以下のデメリットが生じてしまいます。
- 人身事故として扱われずに物損事故として処理される
- 交通事故の被害実態に応じた適切な賠償金を受け取ることができないリスクが生じる
- 交通事故に関する客観的証拠が不足して示談交渉が難航するリスクが生じる
それぞれのデメリットについて、詳しく解説します。
1.人身事故として扱ってもらえない
交通事故でけがを負った場合でも、診断書を出さなければ、警察から人身事故として処理してもらえません。
つまり、物損事故として扱われてしまうということです。
そして、物損事故として処理されると、慰謝料や治療費などを請求するのが難しくなるリスクが出てきます。
もちろん、交通事故現場にかけつけた警察官が目で見てすぐにわかるほどのけがを負っている状況なら、診断書がなくても人身事故として処理してもらえることもあるでしょう。
しかし、むちうちや軽度の打撲など、外観だけではわかりにくいけがを負った場合には、診断書がなければ人身事故として扱われにくいのが実情です。
2.十分な示談金が受け取れなくなる
交通事故で損害が生じた場合には、加害者に対して損害賠償請求することが通常です。
たとえば、けがをして通院・入院をすると、治療費、入院費用、検査費用、通院交通費、装具購入費、休業損害などの損害項目が発生するため、これらの費用を加害者に請求することになります。
また、人身事故の場合には精神的損害が生じたと考えられるので慰謝料も請求することになります。
さらに、後遺症が残った場合には、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料なども請求します。
ところが、診断書を提出していないと、これらの費用が交通事故によって生じたと証明できないリスクが出てきます。
その結果、事故相手に対して請求できる賠償項目が物損分だけに限定されかねません。
そうなると、本来事故相手に請求できたはずの賠償金を受け取ることができず、泣き寝入りを強いられかねないでしょう。
3.証拠が不足して示談交渉で不利になる
交通事故でけがを負った場合、人身事故として警察に届け出ることで、以下のような情報が記載された「実況見分調書」を作成してもらえます。
- 実況見分の日時・場所
- 立会人の氏名・年齢・住所・職業
- 実況見分時の天候
- 路面や道路の状況(舗装の有無、勾配、障害物など)
- 衝突時の痕跡(ブレーキ痕、破片の散乱など)
- 車両の損傷状況
- 当時の走行速度や信号の色、ブレーキをかけた位置など事故発生時の状況
この調書は、事故の状況を客観的に記録した非常に重要な資料です。
しかし、診断書を提出せず物損事故として処理されると、実況見分調書は作成されません。
そもそも、器物損壊罪は「故意」による行為のみが処罰対象となっており、「過失」による物損事故は刑事事件として扱われないためです。
そして、実況見分調書がなければ、相手方から一方的な主張をされても、反証できる客観的な根拠が乏しくなってしまいます。
結果として、事故の実態に基づいた過失割合の認定が難しくなり、示談交渉でも不利な立場に立たされるおそれがあるでしょう。
交通事故の被害に遭った際に診断書を出すか出さないか迷ってしまうケース
交通事故でけがをした場合、適切な形で事後処理をするために、速やかに診断書を出す必要があります。
ところが、実際の交通事故の場面では、診断書を出すか出さないかを迷ってしまう人が少なくありません。
ここでは、診断書を出すか出さないかを迷ってしまうことが多いケースを具体的に紹介します。
1.事故直後は痛みなどを感じていない場合
事故直後に痛みなどを感じていない場合、診断書を出すか出さないか迷ってしまう人も少なくありません。
事故直後は緊張状態・興奮状態にあるうえ、筋肉や神経などの損傷はすぐに症状として現れないこともあります。
そのため、そもそも病院を受診しなかったり、診断書を受け取っても提出しないままにしたりするケースが数多く見受けられます。
しかし、事故から数日経過して痛みが表れる事例は多く、はじめは軽微な自覚症状だったとしても、今後悪化していく可能性は十分あります。
交通事故の被害に遭ったときは迷わず病院を受診し、診断書が出された場合は必ず提出するようにしてください。
2.加害者側から診断書を出さないよう頼まれた場合
診断書を出すべきかどうかで迷うケースとして、加害者側から「十分な解決金を支払うから、その代わりに診断書を出さないでほしい」などと依頼されるパターンもあります。
加害者としては、交通事故トラブルが深刻化するのをおそれて、このような依頼をしてくるのです。
しかし、このような打診をされたとしても、診断書を提出することにためらわないでください。
というのも、「交通事故によってけがを負った」という客観的な証拠がなければ、あとから適切な補償を受けられなくなる可能性があるからです。
また、そもそも事故現場では「十分な解決金を支払う」と話していた加害者が約束を守ってくれる確証もありません。
3.面倒ごとに巻き込まれたくないと感じている場合
病院に行ったり関係各所に提出したりするのが面倒だと感じて、診断書を出すのをためらってしまうケースもあるでしょう。
実際、診断書を出すと人身事故として処理されるため、各種明細書を整理・管理したり、警察の実況見分への立ち会いを求められたりします。
また、自身の過失が大きい場合には、診断書を出すことで自身が交通違反によるペナルティーを受けるリスクも否定できません。
しかし、事故に対する適切な補償を得られないリスクを考慮すると、これらの手間やペナルティーを理由に躊躇するのは避けるべきでしょう。
交通事故の被害者が診断書を出すのは簡単!種類と提出先を確認しておこう
交通事故でけがや後遺症を負った場合には、関係各所に診断書を提出したうえで、各種手続きを進める必要があります。
ここでは、交通事故の被害者が提出するべき以下4つの診断書の内容と提出先を整理します。
- 通常の診断書(警察提出用診断書)
- 自賠責診断書
- 後遺障害診断書
- 労災保険診断書
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1.通常の診断書(警察提出用診断書)|人身事故に切り替えるために警察に提出する
交通事故でけがをした場合、警察に人身事故として処理してもらうために診断書を提出しなければなりません。
警察提出用診断書は、通院をしている病院で発行することができ、病名・症状・治療経過・治療期間・回復見込みなどの諸情報が記載されています。
警察に診断書を提出する期限は特に決まっていません。
ただし、交通事故発生日から診断書を提出するまでの期間が空いてしまうと、交通事故との間の因果関係に疑問が生じて診断書を受理してもらえないリスクが生じます。
そのため、遅くても交通事故発生日から10日以内には診断書を提出するようにしてください。
なお、警察に提出する診断書は原本です。
コピーは認められないので注意しましょう。
また、病院によって異なりますが、診断書を発行する際には5,000円前後の費用がかかります。
診断書の発行費用も加害者側に請求できるので、必ず明細書を保管しておきましょう。
さらに、最初は物損事故として処理された事案でも、あとから診断書を提出することで人身事故に切り替えることが可能です。
2.自賠責診断書|被害者請求の際に加害者側の自賠責保険会社に提出する
自賠責診断書とは、交通事故で負傷をした被害者が自賠責保険から治療費・慰謝料などを受け取るための「被害者請求」をする際に必要な書類のことです。
自賠責診断書は主治医が作成し、1ヵ月の間に実施された治療内容や検査結果が記載されます。
なお、自賠責診断書の作成期間は2週間程度は要します。
医師に作成を依頼してすぐその場で受け取ることができるものではないので、時間の余裕をもって医師に作成を依頼してください。
3.後遺障害診断書|後遺障害等級認定申請をする際に保険会社に提出する
後遺障害診断書とは、交通事故で負ったけがが完治しなかった場合に、後遺障害認定申請をする目的で作成される書類のことです。
交通事故で後遺症が残った場合には、事故前と比べて労働能力が減少したり喪失したりすることで収入が減少する可能性があります。
このような減収分は後遺障害逸失利益として加害者側に請求可能です。
また、後遺症を負ったことで精神的苦痛が発生していると考えられるので、後遺障害慰謝料も受け取ることができます。
ただし、後遺症が残っているからといって、それだけで後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料を受け取れるわけではありません。
これらの賠償項目に対する補償を受け取るには、後遺障害認定申請を受けたうえで、後遺症の程度に応じて適切な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
後遺障害診断書は、後遺症の程度や内容を審査する際に利用される重要な書面なので、必ず後遺障害診断書の作成経験豊富な医師に作成を依頼してください。
4.労災保険診断書|通勤途中や勤務中の事故の場合は勤務先などに提出する
労災保険診断書は、労働者が業務中または通勤中に負傷したときに、労災保険の申請をする目的で作成される書類のことです。
通勤途中や仕事中に交通事故に巻き込まれてけがをした場合には、労災保険から以下の給付を受けることができます。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 傷病補償年金
- 障害補償給付
- 介護補償給付
- 遺族補償給付
- 葬祭料
なお、どの給付を受けるかによって必要な診断書の種類は異なるので、勤務先の総務課や労働基準監督署に確認しましょう。
交通事故の診断書を出すか出さないか迷ったら弁護士に相談してみよう
交通事故の診断書を出すか出さないかで迷ったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。
というのも、交通事故トラブルに巻き込まれたときに弁護士に相談すれば、以下のメリットを得られるからです。
- 交通事故後に病院を受診するタイミングについてアドバイスをもらえる
- 交通事故でけがをしたのに診断書を出さないままだとどのようなデメリットが生じるか解説してくれる
- 医療機関で受けるべき治療内容や検査項目についてアドバイスをしてくれる
- 自賠責診断書や後遺障害診断書に記載するべき内容を指示してくれる
- 過失割合や賠償範囲・賠償額について加害者側と揉めたときに、示談交渉を代理してくれる
- 任意保険基準や自賠責基準ではなく、弁護士基準で慰謝料額を算定できるので、加害者側から受け取ることができる示談金の増額を期待できる
- 加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしても、診断書などの客観的証拠を活用しながら、安心して通院を継続できる状況を作り出してくれる
- 示談交渉が決裂したとしても、民事調停・民事裁判の手続きを代理してスムーズに進めてくれる など
加害者側の保険会社は交通事故実務のプロです。
相手方の言いなりになっていると、本来請求できたはずの賠償額を受け取ることができず、泣き寝入りを強いられかねません。
そのため、交通事故に巻き込まれた場合には、一度は交通事故対応を取り扱う弁護士の話を聞いてみるとよいでしょう。
なお、弁護士に相談すると、事務所にもよりますが概ね30分あたり5,500円〜11,000円(税込)の相談料が発生する点に注意が必要です。
ただし、被害者が加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には自動車保険から弁護士費用を支出してもらえます。
また、初回の相談料無料のサービスを提供している法律事務所であれば、相談料の負担なしで弁護士からアドバイスをもらうことができます。
さいごに|交通事故でけがを負った場合は必ず診断書を出すことが重要!
本記事では、交通事故でけがをしたときに、診断書を出すべきかどうかについて詳しく解説しました。
どれだけ軽微な交通事故であったとしても、けがをした以上は、必ず診断書を出してください。
人身事故として処理されることによって、初めて治療費や休業損害、慰謝料などを請求できるからです。
なお、ベンナビ交通事故では、交通事故対応を取り扱う弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回の相談料無料などのサービス面から24時間無料で弁護士を検索できるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合せください。