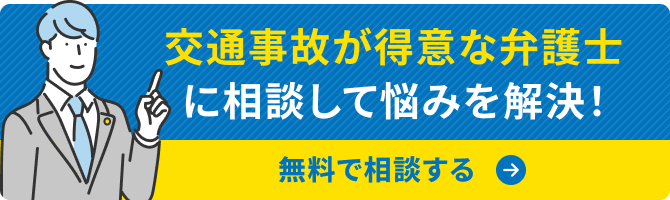交通事故に巻き込まれた結果、顔面を打ちつけてしまって歯を欠損・喪失することがあります。
歯を欠損・喪失すると元には戻りませんし、口の咀嚼・言語機能に後遺症が残るケースも存在します。
このような後遺症が残ったときには、後遺障害等級認定申請をしたうえで、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
ただし、交通事故で後遺症が残ったからといって、常に後遺障害等級認定申請が通るとは限りません。
希望通りの後遺障害等級認定を受けるには、治療段階から丁寧に医師とコミュニケーションをとり、ポイントを押さえた後遺障害診断書を準備する必要があります。
そこで本記事では、交通事故で歯を欠損・喪失等したときの後遺障害について徹底的に解説します。
慰謝料額の目安や請求の流れ、請求時のポイントなども紹介するので、ぜひ参考してください。
交通事故による歯のけがと後遺障害等級認定
まずは、交通事故で歯を怪我したときにどのような後遺障害等級認定を受けることができるのかについて解説します。
1.後遺障害等級認定をされる症状と等級
歯の怪我が対象になる後遺障害等級認定は以下のとおりです。
| 等級 | 症状 |
|---|---|
| 第10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
【参考】「後遺障害等級表|国土交通省
ここからわかるように、歯科補綴(しかほてつ)を加えた本数によって後遺障害の等級が判断されます。
2.「歯科補綴」とは?認定を受けられる歯の症状について
後遺障害等級認定の対象になる歯の怪我は、正式には「歯牙障害」と呼ばれます。
歯牙障害とは、「所定の本数の歯に歯科補綴を加えた状態」のことです。
まず、歯科補綴とは「失われたり、大きく損傷したりした歯に対する治療方法」を意味します。
たとえば、クラウン、ブリッジ、インプラント、入れ歯などの施術方法が挙げられます。
- クラウン:虫歯・破損した歯を保護して機能を回復するために使われる被せ物のこと。金属、セラミック、レジンなどの素材がある。
- ブリッジ:喪失した歯を補うために隣接する健康な歯に人工歯を固定する施術方法のこと。
- インプラント:顎骨に人工歯根を埋め込んで、上にクラウンを装着する施術方法のこと。
- 入れ歯:全部または一部を喪失した箇所に装着する取り外し式の人工歯のこと。
次に、「現実に歯を喪失した状態」には、事故の衝撃で歯が無くなった場合だけではなく、抜歯をせざるを得ない場合も含まれます。
「著しく欠損した状態」は、歯肉から露出している歯冠部の体積3/4以上を欠損した状態のことです。
このような歯牙障害に対して、歯科補綴を加えた本数を基準に後遺障害の等級が認定されます。
なお、実際に歯科補綴をおこなう前の状態であったとしても、「現実に歯を喪失または著しく欠損した」といえる状態なら、後遺障害等級認定の算定基準に含まれます。
3.認定の対象にならない歯の状態
後遺障害等級認定の対象になるのは「永久歯」です。
乳歯・三大臼歯や、交通事故よりも前に喪失または著しく欠損していた歯、交通事故前からC4の状態まで虫歯が進行していた歯は含まれません。
また、有床義歯・架橋義歯の支台冠、鈎の装着歯、ポスト・インレーをおこなった歯なども補綴歯数からは除外されます。
なお、喪失・欠損数と義歯数が異なる場合、後遺障害等級認定の際の基準になるのは「喪失・欠損した歯の数」です。
義歯の数ではないので注意が必要です。
4.けがをした歯が2本以下でも対象になることもある
歯牙障害が後遺障害等級の対象になるには、原則として「3歯以上に対し歯科補綴を加えた」状態でなければいけません。
ただし、欠損した歯が2本の場合であったとしても、ブリッジ治療をするときには、例外的に後遺障害等級の対象になります。
なぜなら、ブリッジ治療をするには、欠損した歯の横の健康な歯も削る必要があるからです。
そのため、欠損した歯とブリッジをかけた歯の合計数が3本以上になる場合には、後遺障害等級認定の対象になります。
歯のけがで請求できる後遺障害慰謝料
歯牙障害が後遺障害等級認定の対象になったときには、以下の後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
| 等級 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 10級4号 | 550万円 |
| 11級4号 | 420万円 |
| 12級3号 | 290万円 |
| 13級5号 | 180万円 |
| 14級2号 | 110万円 |
【参考】後遺障害等級表|国土交通省
どの等級に該当するかによって後遺障害慰謝料の金額は全く異なります。
負傷の程度に応じた慰謝料額を受け取るために、交通事故後は速やかに病院を受診して適切な治療を受けましょう。
歯のけがと併発する可能性があるそのほかの後遺障害と等級
交通事故で歯に怪我をしたときには、歯牙障害以外の後遺症が併発する可能性があります。
ここでは、咀嚼機能と言語機能の後遺障害について解説します。
咀嚼機能の後遺障害
咀嚼機能の後遺障害とは、交通事故が原因で食べ物を噛んだり飲み込んだりするのに支障が生じる状態のことです。
交通事故で頭部に強い衝撃を加えられると、顎を骨折・脱臼することがあります。
咀嚼機能障害は、このような顎部分への衝撃が原因で起こることが多いです。
咀嚼機能障害を発症すると、言語障害、嚥下障害、開口障害、味覚障害などを伴うこともあります。
言語機能の後遺障害
言語機能の後遺障害とは、言葉を発することに支障が生じる状態のことです。
交通事故時の衝撃で舌を強く噛んでしまったり、反回神経麻痺や高次脳機能障害を負ったりしたときに言語障害が残る可能性があります。
咀嚼・言語機能の後遺障害等級認定と症状
咀嚼機能障害や言語機能障害の後遺障害等級認定の基準・症状は以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 症状 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの下記両方の症状がある 【咀嚼】流動食しか摂取できない 【言語機能】口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音※のうち3種以上の発音ができない/td> |
| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 下記のうちどちらかの症状がある 【咀嚼】流動食しか摂取できない 【言語機能】口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音のうち3種以上の発音ができない |
| 4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 下記両方の症状がある 【咀嚼】お粥と同程度のものしか食べられない 【言語機能】口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音のうち2種以上の発音ができない |
| 6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 下記のうちどちらかの症状がある 【咀嚼】お粥と同程度のものしか食べられない 【言語機能】口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音のうち2種以上の発音ができない |
| 9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 下記両方の症状がある 【咀嚼】咀嚼できない固形物があるか、十分に咀嚼できないものがありそれが医学的に確認できる状態 【言語機能】口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音のうち1種以上の発音ができない |
| 10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 下記のうちどちらかの症状がある 【咀嚼】咀嚼できない固形物があるか、十分に咀嚼できないものがありそれが医学的に確認できる状態 【言語機能】口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音のうち1種以上の発音ができない |
【参考】後遺障害等級表|国土交通省
上記表内の言語機能を確認するための発音には、それぞれ以下が用いられます。
| 口唇音 | ま行,ぱ行,ば行,わ行,ふ |
|---|---|
| 歯舌音 | な行,た行,だ行,ら行,さ行,しゅ,し,ざ行,じゅ |
| 口蓋音 | か行,が行,や行,ひ,にゅ,ぎゅ,ん |
| 喉頭音 | は行 |
なお、咀嚼機能障害・言語機能障害で後遺障害等級認定を受けるのは難しいといわれています。
なぜなら、咀嚼機能障害・言語機能障害は他覚的所見を得にくい性質の障害であり、満足のいく後遺障害診断書を用意するのが大変だからです。
そのため、交通事故が原因で咀嚼機能障害・言語機能障害が生じたときには、治療段階から後遺障害実務に詳しい弁護士に相談をし、どのような後遺障害診断書を作成してもらうべきかについてアドバイスをもらうことをおすすめします。
咀嚼・言語機能の後遺障害等級と慰謝料額
咀嚼機能障害や言語機能障害の後遺障害等級別の慰謝料額は以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 1級2号 | 2,800万円 |
| 3級2号 | 1,990万円 |
| 4級2号 | 1,670万円 |
| 6級2号 | 1,180万円 |
| 9級6号 | 690万円 |
| 10級3号 | 550万円 |
【参考】後遺障害等級表|国土交通省
なお、ここに記載した慰謝料額は「弁護士基準」を前提としたものです。
弁護士基準(裁判基準)とは、交通事故の慰謝料額を算出する基準のひとつです。
過去の裁判例・判例を蓄積したうえで基準額が決定されており、任意保険基準・自賠責基準よりも高額な点が特徴です。
加害者側と示談交渉をする際、相手方の保険会社は「任意保険基準」を使って低額の慰謝料額条件を提示してくることが多いでしょう。
そのため、交通事故が原因で後遺症が残った被害者は、「弁護士基準」で高額の慰謝料額を算出するために、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
口の後遺障害がある場合の逸失利益は認められないことが多い
交通事故の被害に遭ったときには、損害賠償項目のひとつに「逸失利益」が計上されるのが一般的です。
逸失利益とは、「交通事故に遭わなければ得られたはずの収入(交通事故によって得ることができなくなった収入)」を意味します。
たとえば、現場作業員として働いていた被害者が、交通事故により歩行が困難になるほどの重篤な後遺症を負って仕事を辞めざるを得なくなったときには、「現場作業員として将来働き続けた場合に得られた収入」が逸失利益と扱われて、損害賠償請求に含めることができます。
しかし、交通事故で歯牙障害を負ったケースでは、後遺障害慰謝料は請求できたとしても、逸失利益に関する損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
なぜなら、歯牙障害は労働能力の喪失・低下とはほぼ無関係であると判断されることが多いからです。
労働能力が低下する原因となったのであれば逸失利益が認められる
歯牙障害・言語障害などが労働能力の低下・喪失に影響していると考えられるケースであれば、逸失利益が認められる可能性はあります。
たとえば、学校教員として働いていた被害者が、交通事故のせいで重篤な言語障害を負った場合、教壇に立って従来通りに授業をすることができなくなってしまいます。
また、プロスポーツ選手として活躍していた被害者の場合、比較的軽微な歯牙障害を負ったとしても、労働能力の大幅な低下につながるといえるでしょう。
労働能力の低下・喪失は、被害者の現在の職業・収入・経歴・転職可能性・障害の程度など、個別具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。
歯牙障害などが原因で仕事に影響が出たと主張をしたいときには、交通事故トラブルに強い弁護士に相談・依頼しましょう。
逸失利益は認められなくても、慰謝料が増額する要因になることがある
歯牙障害・言語障害などが残ったとしても、特別な要因がなければ逸失利益の請求は認められません。
その一方で、歯牙障害や言語障害などについては、日常生活に生じる不具合が大きく、被害者は心に大きな傷を負っていると考えられます。
このような事情を総合的に考慮した結果、交通事故で歯牙障害や言語障害が残った事案では、逸失利益は認められなくても、他の後遺症・怪我と比べて慰謝料が増額される傾向が強いです。
歯のけがで後遺障害等級申請をする流れ
歯や咀嚼機能・言語機能に後遺症が残ったときには、後遺障害等級申請をする必要があります。
歯牙障害について後遺障害等級申請をするときの流れは、以下のとおりです。
- 症状固定後、歯科医に後遺障害診断書を作成してもらう
- 保険会社に必要書類を提出する
それぞれについて、以下で詳しく解説します。
1.症状固定後、歯科医に後遺障害診断書を作成してもらう
交通事故で歯を負傷したときには、事故の後、できるだけ早いタイミングで歯医者を受診してください。
その後、歯科医によって「症状固定」の判断が下されるまで、担当医の指示通りに治療を継続しましょう。
通院をスタートするタイミングが遅いと、歯の怪我や各種障害と交通事故の因果関係を証明するのが難しくなります。
また、歯科医の指示を破って途中で通院をやめると、適切な後遺障害等級認定を受けられなくなる可能性があります。
症状固定の判断が下されたら、歯科医に後遺障害診断書の作成を依頼してください。
ただし、後遺障害診断書の作成に慣れていない歯科医では、後遺障害等級認定申請に必要な項目が抜け落ちた診断書を作成してしまうリスクがあります。
歯牙障害について後遺障害等級認定申請を検討しているのなら、事前に後遺障害実務に詳しい弁護士に相談をして、診断書に記載するべき項目についてアドバイスをもらいましょう。
2.保険会社に必要書類を提出する
後遺障害診断書の準備が整ったら、後遺障害等級申請をおこないます。
後遺障害等級申請の方法は以下2つです。
- 事前認定:相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を送付する簡便な方法
- 被害者請求:被害者本人が直接自賠責保険に後遺障害診断書などの必要書類を送付する複雑な方法
事前認定・被害者請求のどちらが適しているかは事案によって異なります。
歯牙障害などの治療・リハビリなどに専念しており被害者本人で手続き選択を判断する余裕がないのなら、後遺障害申請手続き自体を弁護士に任せてしまうのがスムーズでしょう。
後遺障害等級認定申請をするなら弁護士に相談・依頼することが推奨される理由
後遺障害等級認定申請をするときには、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
ここでは、後遺障害等級認定申請について弁護士を頼るべき理由を解説します。
自分でするより慰謝料の増額が期待できる
歯牙障害の後遺障害等級認定申請を弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料の増額を期待できます。
なぜなら、弁護士が介入することによって、任意保険基準ではなく弁護士基準で慰謝料額を算出できるからです。
とくに、歯牙障害などの症状が重篤なケースほど、任意保険基準と弁護士基準の差額は大きくなります。
交通事故で重い後遺症が残った事案では、必ず弁護士の力を借りるようにしてください。
手続きや保険会社とのやりとりを任せられる
弁護士に依頼をすれば、後遺障害等級認定申請だけではなく、加害者側との示談交渉や民事訴訟などの各種手続きを全て代理でおこなってもらえます。
歯牙障害などの後遺症を負ったケースでは、被害者本人は治療やリハビリをする必要があり、交通事故後の各種手続きに対応する余裕はないはずです。
弁護士に依頼をすれば、被害者本人の手続き負担を大幅に軽減されるので、日常生活に復帰することに専念できるでしょう。
また、加害者側の保険会社は、早期の治療打ち切りや被害者側に不利な示談条件を提案してくることが多いです。
法律に詳しくない被害者本人では、加害者側の任意保険会社に言いくるめられて、不利な示談条件での合意を強いられかねません。
少しでも被害者にとって有利な解決に至るには、弁護士のサポートは不可欠だと考えられます。
適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まる
弁護士に依頼をすれば、被害者が負った後遺症に合った後遺障害等級認定を受けやすくなります。
適切な後遺障害等級認定を受けるには、審査時に必要な項目について十分に記載されている後遺障害診断書が不可欠です。
しかし、後遺障害等級認定実務に詳しくない歯科医にあたってしまうと、不十分な内容の後遺障害診断書が出されるリスクが生じます。
これでは、被害実態に応じた後遺障害等級認定を受けることができません。
後遺障害等級認定の実務に詳しい弁護士に依頼すれば、歯科医に直接コンタクトをとって後遺障害診断書に記載するべき項目を指摘するなど、適切な後遺障害等級認定を受けられるようにサポートしてくれるでしょう。
歯の後遺障害等級認定を適切に受けるためのポイント
ここでは、歯牙障害について適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイントを2つ解説します。
歯科医に診察してもらう
交通事故に巻き込まれたときには、歯以外にもさまざまな怪我を負い、整形外科などを受診する場合も少なくありません。
ただし、歯牙障害についての後遺障害等級認定申請を検討しているなら、整形外科だけで済ませるのではなく、必ず歯科医の診断も受けてください。
歯科医でなければ歯牙障害について適切な診断結果を下すことはできないからです。
歯科用の後遺障害診断書作成を依頼する
後遺障害の種別によって後遺障害診断書に記載するべき項目は異なります。
歯牙障害について後遺障害等級認定申請を検討している場合には、「歯科用の後遺障害診断書」を作成してもらってください。
歯の後遺障害等級認定についてよくある質問
さいごに、歯牙障害の後遺障害等級認定についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
差し歯や入れ歯などで補綴されなかった場合はどうなりますか?
歯牙障害に関する後遺障害等級認定申請は「後遺障害等級認定表所定の歯の本数に『歯科補綴』を加えたとき」に受けることができます。
歯科補綴には、クラウン、ブリッジ、インプラント、入れ歯などの施術方法が含まれます。
そのため、差し歯・入れ歯による処置であったとしても、原則として3本以上の歯を現実に喪失または著しく欠損したときには、後遺障害等級認定の対象と扱われるでしょう。
既存障害があった場合、歯の後遺障害等級認定はどうなりますか?
交通事故に巻き込まれる前から歯科補綴を加えた歯がある被害者が、交通事故によってさらに歯科補綴を受ける必要に迫られた「加重障害」の事例では、交通事故前から補綴されていた歯の本数も後遺障害等級認定の判断の際に考慮されます。
たとえば、交通事故前に5本の歯を欠損しており、交通事故によってさらに3本の歯の補綴を要するケースでは、「8本」を基準に後遺障害等級が決まります。
ただし、後遺障害慰謝料額を算出する際には、「『後遺障害第12級第3号の290万円(8本分)』から『既存障害の後遺障害第13級第5号の180万円(5本分)』を減額した金額を目安にする」というのが実務の運用です。
交通事故前から歯牙障害を負っていたときには後遺障害慰謝料の算定方法が複雑になるので、必ず後遺障害等級申請実務に詳しい弁護士へ相談をしてください。
さいごに|歯の後遺障害で等級認定申請するなら早めに弁護士へ相談を
交通事故に巻き込まれて歯牙障害が残ったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談をしてください。
後遺障害等級認定申請が通りやすくなるだけではなく、加害者側との示談交渉を有利に進めやすくなるなどのメリットを得られるでしょう。
ベンナビ交通事故では、さまざまな後遺症を負って不安・疑問を抱えている被害者のサポートを得意とする弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から、24時間無料で専門家をWeb検索できるので、信用できる弁護士を見つけてお気軽にお問い合わせください。