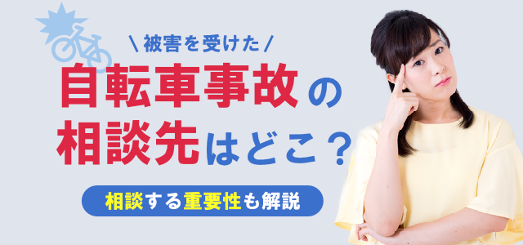自転車乗車中の事故は自動車事故よりも軽微に考えられることが多いですが、死者数は2021年~2023年まで毎年300人以上にものぼるなど、非常に怖い事故です。
また、自転車事故の対応には、「自賠責保険の加入義務がない」「過失割合で争いになりやすい」「保険会社ではなく当事者自身で交渉する必要がある」など、複雑な問題が山積みです。
これらの問題を自分ひとりで解決するのは困難ですので、まずは信頼できる相談先を見つけなければなりません。
本記事では、自転車事故に関するおすすめの相談先を紹介します。
自転車事故を相談する重要性についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

無料相談できる弁護士一覧
自転車事故に遭ったときの相談窓口
まずは、自転車事故に遭ったときの相談窓口を6つ紹介します。
それぞれに利用条件や相談できる内容が異なるため、状況に応じて適切に使い分けるようにしましょう。
1.法律事務所|個別のサポートを受けたい場合

個別のサポートを受けたい場合は、法律事務所の弁護士に直接相談するのがおすすめです。
弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロです。
依頼者が少しでも有利になるように、個々の状況に合わせた最善の解決策を提案してくれます。
相談した流れでそのまま委任契約を結べば、すみやかに示談交渉や後遺障害等級認定の手続きなどを進めてくれるはずです。
ベンナビ交通事故を使えば、交通事故問題を得意とし、自身が希望する条件を満たす弁護士を効率的に探し出せるので、うまく活用してみてください。
2.法テラス|経済的に余裕がない場合

法テラスは、法律問題の解決支援を目的に設置されている公的機関です。
経済的に余裕がなく、弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラスに相談してみましょう。
民事法律扶助制度を設けており、一定の収入・資産基準を満たしている方であれば、3回まで弁護士に無料で相談することができます。
また、弁護士に事件処理を依頼する場合には、弁護士費用を立替えてもらうことも可能です。
収入・資産基準は家族の人数や居住地ごとに細かく決められているので、気になる方は一度公式サイトをチェックしてみてください。
【参照元】弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ|法テラス
3.各自治体の相談窓口|身近な施設で相談したい場合
自治体によっては、交通事故の相談窓口を設けていたり、弁護士との無料相談会を実施していたりすることがあります。
身近な施設で相談したい方には、各自治体の相談窓口がおすすめです。
多くの場合は役所などの公共施設で相談できるので、アクセスしやすい点が大きなメリットといえるでしょう。
ただし、相談できるのは基本的に地域住民だけです。
そのほか、相談回数・時間や予約の有無など利用条件は自治体ごとに異なるので、早めに下調べをしておくようにしてください。
自転車ADRセンター|裁判ではない方法で第三者に仲介してもらいたい場合

自転車ADRセンターは、自転車事故に関する紛争を解決・予防することを目的とした調停機関です。
裁判ではない方法で第三者に仲介してもらいたい場合は、自転車ADRセンターに相談してみるとよいでしょう。
3名の調停委員が当事者から話を聞き、双方が納得できるかたちでの和解を目指します。
「妥協するつもりはないけれど、裁判まではしなくない」と考えている方には、特におすすめの相談先といえるでしょう。
ただし、自転車ADRセンターの調停委員はあくまでも中立的な立場で関与するため、必ずしも相談者の味方になってくれるとは限りません。
和解が成立した場合には、手数料が発生する点にも注意が必要です。
交通事故紛争処理センター|加害者が自動車の場合

交通事故紛争処理センターは、自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決を中立公正な立場で支援する公益財団法人です。
加害者が自動車の場合は、交通事故紛争処理センターも利用できます。
交通事故の損害賠償問題を得意とする弁護士が中立的な立場で介入してくれるうえ、依頼費用もかかりません。
話し合いでの解決が難しい場合には、有識者による審査がおこなわれ、「裁定案」と呼ばれる結論が出されます。
なお、裁定案に対する保険会社の異議申立ては認められていないため、被害者が同意すれば、裁定案どおりに示談が成立することになります。
被害者が裁定案に同意しない場合は、裁判での解決を目指すことになるでしょう。
日弁連交通事故相談センター|無料で法律相談がしたい場合

日弁連交通事故相談センターでは、自動車による交通事故問題に関する電話相談・面談相談・示談あっせんに対応しています。
無料で法律相談がしたい場合は、日弁連交通事故相談センターを利用してみるのもひとつの方法です。
電話相談は10分程度なので、細かな相談が必要な場合は、最寄りの相談所で面談相談をおこなってください。
面談相談であれば、30分5回まで対応してもらえます。

無料相談できる弁護士一覧
自転車事故は専門機関に相談するべき理由性
自転車が絡む交通事故は、「自動車対自動車」の事故や「人対自動車」の事故とは少し性質が異なり、事故処理や損害賠償についても手続きの流れが変わります。
そのため、自転車事故を起こしたときは、できるだけ専門機関に相談することをおすすめします。
ここでは、自転車事故の厄介な点を中心に、その特徴を4つ紹介します。
1.十分な補償を受けられない可能性が高い
自転車事故では、十分な補償を受けられない傾向があります。
自動車やバイクの事故とは異なり、自転車事故には自賠責保険が適用されません。
また、近年では自転車用の任意保険も登場し、大都市を中心に加入を義務化する自治体も増えつつあります。
しかし、全体としてはまだまだ数が少なく、都市部以外の地域ではほとんど普及していないのが現状です。
加入が義務化されていない自治体では、自転車に乗っている人の大半は無保険であると考えなければなりません。
つまり、事故の加害者が自転車に乗っていた場合は、保険のサポートを得られないのです。
その結果、被害者は十分な額の損害賠償金を受け取れない可能性があります。
被害者が自転車に乗っていた場合も、人身傷害保険などによる補償を受けられず、過失割合によっては大きく損をすることになりかねません。
2.後遺障害の等級認定機関がない
後遺障害の等級認定機関がないことも、自転車事故を専門家に相談するべき理由のひとつです。
事故後に後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求するために、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
自動車事故では、自賠責保険会社が等級認定の該当性を判断しますが、自転車事故には等級認定機関が存在しません。
そのため、以下のような対応が必要になります。
- 加害者の自転車保険会社に認定してもらう
- 被害者の人身傷害保険・労災保険に認定してもらう
- 裁判で適切な後遺障害等級を判断してもらう
どの方法を選択すべきなのかは人それぞれ異なるので、まずは弁護士に相談することが大切です。
3.当事者が直接交渉する必要がある
多くの自転車事故では、当事者が直接交渉しなければなりません。
自動車事故の場合は、加入している任意保険会社の担当者が示談交渉をおこなってくれる場合も多いです。
しかし、自転車に乗っている人は無保険であるケースが多く、事故を起こしても保険会社を頼れません。
とくに人対自転車や自転車対自転車の事故だと、どちらも保険会社が交渉を代理してくれない場合が多くなるので、専門知識のない当事者同士で示談交渉を進めることになります。
相手が話し合いから逃げ続ければ、損害賠償請求などの手続きも難航し、裁判に進まざるをえないこともあるでしょう。
また、被害者側が自転車で加害者側が車の場合、加害者側は任意保険会社の担当者が出てくるのに対し、被害者は自分で交渉しなければなりません。
そのまま交渉に臨むと相手のペースに飲まれてしまう可能性が高いため、何かしらの対策を立てる必要があります。
4.過失割合で争いになりやすい
自転車同士の事故に関しては、過失割合を決める指標の類型化が進んでおらず、過失割合を巡って争いになりやすい傾向にあります。
当事者同士が直接示談交渉をおこなうような場合には、建設的な話し合いが成立しないかもしれません。
自動車事故における損害賠償請求のポイント
最後に、自転車事故における損害賠償請求のポイントを見ていきましょう。
損害項目に漏れがないようにする
自転車事故で損害賠償請求をおこなうときは、損害項目に漏れがないように注意してください。
自転車事故で請求できる可能性があるのは、主に以下のような費用です。
- 治療費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 介護費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
実際に請求できる項目は、けがの程度や後遺症の有無などによって異なります。
また、請求費用もそれぞれ細かく算定しなければならないため、適切な損害賠償を受け取るためには弁護士のサポートが必要不可欠です。
滞納や踏み倒しのリスクに備えておく
自転車事故の損害賠償請求においては、滞納や踏み倒しのリスクに備えることが一層重要になります。
自転車事故では加害者が保険に入っておらず、損害賠償の支払いに耐えられない可能性が高いためです。
自転車事故であっても、数百万円~数千万円の損害賠償が発生することは少なくありません。
そのなかで、保険が使えず、全て自費で支払わなければならない状況に陥ると、滞納や踏み倒しを選択する人も出てきます。
そのため、相手方の資力に応じて損害賠償額を減額したり、分割払いを認めたりするなど、遅滞なく支払いを受けられるような工夫を講じることが大切です。
また、示談書を強制執行承諾文言付き公正証書で作成し、滞納や踏み倒しがあった場合には、すみやかに強制執行に移れる体制をとっておくのもよいでしょう。
自転車事故の相談先に迷ったときはどうすればいい?
それでは実際のところ、自転車事故に遭ったときはどこに相談するといいのでしょうか。
総合的に見ると、やはり弁護士が一番おすすめです。
弁護士に相談すれば、被害者・加害者に関わらず、依頼者の絶対的な味方として、迅速にトラブルを解決してくれます。
交通事故問題に関しては、相談料が無料とされているケースや、完全成功報酬型の料金体系がとられているケースも多いので、費用面が気になる方でも相談しやすいはずです。
しかし、事故から時間が経てば経つほど、弁護士が介入できる余地は小さくなります。
そのため、自転車事故を起こした場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを求めることが大切です。
自動車保険の弁護士費用特約は自転車事故に使える?
自転車事故を起こし、弁護士への相談を検討しているなかで、「弁護士費用特約」が適用されるかどうかが気になっている方もいるでしょう。
弁護士費用特約とは、一定額の弁護士費用を保険会社が負担してくれるサービスのことです。
一般的には、自動車保険に加入する際にオプションとして付帯するかどうかを選ぶことができます。
原則として、弁護士費用特約を適用するには、加害者か被害者のどちらかが自動車に乗っている必要があります。
そのため、人対自転車や自転車対自転車の事故には適用できない点に注意してください。
ただし、日常生活での事故も補償対象とした特約を付帯させている場合は、自動車やバイクが絡まない自転車事故にも適用できます。
費用負担を大幅に軽減できるので、弁護士へ相談する前に自分の加入状況をしっかりチェックしておきましょう。
まとめ
自転車保険への加入を義務付ける自治体が増えていることで改善の傾向が見られるとはいえ、自転車事故は自動車事故に比べて対応が難しいのが実情です。
だからこそ、自転車事故の当事者になったときは、すみやかに専門家・専門機関のサポートを得ることが大切です。
適切な窓口に相談して最大限の損害賠償金を勝ち取り、1日も早い解決を目指しましょう。

無料相談できる弁護士一覧