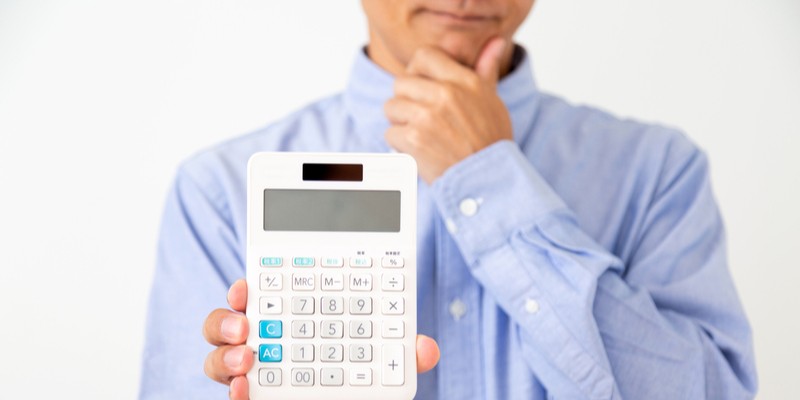交通事故紛争処理センターは、交通事故の相手方と賠償額について争いが生じたときに利用できる裁判外紛争解決機関(ADR機関)です。
加害者側の保険会社の主張内容に納得できないなど、示談交渉がうまく進んでいない場合に、交通事故紛争処理センターに相談することで、弁護士などのサポートを受けながら、話し合いを進めることができます。
本記事では、以下の5点についてわかりやすく解説します。
- 交通事故紛争処理センターとは
- 交通事故紛争センターで受けられる主なサービス
- 交通事故紛争処理センターを利用するメリット・デメリット
- 交通事故紛争処理センターに相談する際の流れ
- 交通事故紛争処理センター以外の相談窓口
交通事故紛争処理センターとは
公益財団法人交通事故紛争処理センターとは、交通事故の示談交渉が紛糾している場合に、被害者と加害者側の間に中立的な立場で立ち、解決をサポートしてくれる機関です。
交通事故紛争処理センターでは、担当弁護士による和解のあっせんや専用の審査手続きを無料で提供しています。
交通事故が発生した場合、修理費や治療費などの損害額や過失割合などについて、加害者側と見解が衝突するケースが少なくありません。
本来であれば、民事訴訟によって損害額や賠償責任の範囲について裁判所の判断を仰ぐことになりますが、訴訟手続きなどに慣れていない被害者にとって、精神的・肉体的にも経済的にも大きな負担になるのは否めません。
交通事故紛争処理センターでは、被害者を救済するために、裁判よりも簡単で負担のかからない手続きによって交通事故をめぐる問題の早期解決を目指しています。
交通事故紛争処理センターで受けられる主なサービス
交通事故紛争処理センターが提供する主なサービスは、以下の3つに大別されます。
- 法律相談
- 和解あっせん
- 審査
法律相談|和解あっせんを前提とした相談ができる
交通事故紛争処理センターでは、和解あっせんを前提とした法律相談を無料で受けることができます。
たとえば、相談担当弁護士との面談では、提出した資料と当事者の意見を前提として、生じる可能性がある法律問題や争点が整理されたり、想定される落としどころなどについてアドバイスを求めたりできます。
法律相談の結果、当事者が和解あっせんを希望したり、担当弁護士が和解あっせんの必要性があると判断したりしたときは、和解あっせんの段階に進みます。
一方、法律相談を受けた結果、相手方の主張を全面的に受け入れて良いと判断できたときや、そもそも和解になじまない事案では、別の司法手続きを提案されたり、弁護士会などより適切な相談機関を紹介されたりします。
和解あっせん|弁護士を交えた話し合いができる
交通事故紛争処理センターの法律相談を受けたあとは、和解あっせん手続きで問題解決をはかることになります。
和解あっせんでは、被害者と加害者側の保険会社などが出席したうえで、担当弁護士が中立的な立場で双方の意見を聴取し、争点や賠償額などをまとめて和解案を提示します。
双方が和解案に合意をしたときには、担当弁護士立会のもとで示談書、もしくは免責証書を作成し手続きが終了となります。
審査|審査会による裁定がおこなわれる
和解あっせん手続きで合意に至らなかった場合、和解が成立しなかったことを通知されてから14日以内に当事者が申立てをすることで、審査会による審査手続きを利用できます。
審査会は当事者間で交渉するものではありません。
審査会が被害者・加害者の意見や証拠を確認したうえで、紛争の結論(裁定)を下します。
保険会社は審査会の裁定を尊重するルールなので、被害者(申立人)が裁定の内容に同意すれば和解が成立します。
一方、被害者が裁定の内容に同意しない場合、交通事故紛争処理センターの手続きは終了し、民事訴訟などで解決の糸口を探ることになります。
交通事故紛争処理センターを利用する4つのメリット
交通事故に巻き込まれたときに、交通事故紛争処理センターを利用することには、以下の4つのメリットがあります。
- 中立的な立場のサポートを受けることができる
- あっせんによる和解成立が期待できる
- 少ない来訪回数で、交通事故トラブルの和解を目指せる
- 交通事故トラブルについての法律相談などを全て無料で利用できる
1.保険金を多く獲得できる可能性が高くなる
交通事故紛争処理センターを利用すれば、中立的な立場で担当弁護士からのサポートを受けられます。
たとえば、交通事故に巻き込まれたとき、加害者側の保険会社は少しでも低い金額で保険金の見積もりを提示してくるケースは少なくありません。
加害者側の保険会社と納得のいく金額で示談することは簡単ではないのです。
交通事故紛争処理センターに相談すると、専門知識が豊富な担当弁護士が、公正な立場で双方の仲介をおこなってくれます。
そのため、保険会社から提示された条件を鵜呑みにしなくてよく、適切な金額を獲得できる可能性は高くなるのです。
ただし、交通事故紛争処理センターはあくまでも中立的な立場で紛争解決のサポートを提供する機関です。
ですので、相談者の利益を最大化するためのアドバイスまでは期待できません。
有利な主張を展開したい場合には、自分自身で弁護士を選任したうえで示談交渉を進めるほうが適切です。
2.あっせんによる和解成立が期待できる
交通事故紛争処理センターに相談すれば、交通事故の賠償責任をめぐるトラブルを「あっせん」によって解決できます。
ここでいう「あっせん」とは、交通事故紛争処理センターが中立的な立場で和解案を作成・提案することで解決を目指す裁判外の手続きです。
民事訴訟を提起すると、通常1年~2年の時間をかけて、複数回の口頭弁論がおこなわれます。
しかし、交通事故紛争処理センターによるあっせんであれば、数ヵ月程度で和解が成立する可能性が高いです。
実際、2023年に交通事故紛争処理センターに寄せられた相談では、あっせんによる終了件数4,700件のうち、4,112件で和解が成立しています。
【参考元】「2023年度 取扱事案分類」交通事故紛争処理センター
3.来訪回数が少なくても和解を目指せる
交通事故紛争処理センターの和解あっせん手続きを利用すれば、少ない来訪回数での示談成立を期待できます。
一般的なあっせん手続きでは、交通事故の資料などを提出したうえで、当事者双方の意見を聴取しながら和解条件を探ります。
そのため、相手方の主張内容を確認して反論をしたい場合、期日に来訪して再度主張を展開しなければいけません。
一方、交通事故紛争処理センターの和解あっせんでは、担当弁護士が双方の意見を都度整理して妥協点を上手く探ってくれるので、来訪回数が増えることは避けられるのです。
実際、2023年度に交通事故紛争処理センターが取り扱った事件のデータをみると、以下のとおり約4割が2回以内の来訪で、8割以上が4回以内の来訪で和解成立に至っています。
【和解成立に至るまでの来訪回数(和解成立件数:4,522件)】
来訪回数 件数 割合 1回 590件 13.0% 2回 1,529件 33.8% 3回 1,098件 24.3% 4回 567件 12.5% 5回 324件 7.2% 6回 180件 40% 7回 113件 2.5% 8回以上 121件 2.7%
4.法律相談など全て無料で利用できる
交通事故紛争処理センターの法律相談や和解あっせん手続きは、全て無料で利用できます。
ただし、医療関係書類の取付け費用・交通費・資料作成費・通信費・当事者が自主的に選任した弁護士への依頼料などは、当事者負担になるので注意してください。
交通事故紛争処理センターを利用する4つのデメリット
交通事故紛争処理センターを利用することには、メリットばかりではなく、以下の4つのデメリットがあります。
- 保険会社との交渉段階にならないと、利用できない
- 交通事故の種類によっては、利用できない
- 必ずしも示談金を満額得られるわけではない
- 被害者自身が相談・あっせんに対応する必要がある
1.保険会社との交渉段階にならないと相談できない
交通事故紛争処理センターは、「自動車事故の示談交渉が難航したケースを早期解決に導くこと」を目標にする組織です。
交通事故発生直後などで示談交渉が開始されていない段階では、交通事故紛争処理センターに連絡をしても対応してもらえません。
2.交通事故の種類によっては利用できない
交通事故紛争処理センターでは、全ての交通事故について取り扱ってくれるわけではありません。
なぜなら、交通事故紛争処理センターは基本的に、自動車事故の被害者と加害者側の保険会社・共済組合間の示談をめぐる紛争の解決を目的とする機関であるからです。
このため、交通事故の種類によっては、交通事故紛争処理センターを利用できない場合があります。
たとえば、以下のような交通事故の事案では、交通事故紛争処理センターを利用できません。
- 自動車・原動機付自転車ではない交通事故(自転車同士または自転車と歩行者の事故)
- 被害者と被害者が加入している保険会社間の紛争
- 自賠責保険後遺障害の等級認定や後遺障害の有無についての紛争
- 相手方の保険会社が不明の紛争など
ただし、原則として受け付けていない事案でも加害者が同意することで利用できる場合もあります。
たとえば、相手方が任意保険に加入していない場合や、加入していたとしても被害者の直接請求に関する取り決めが約款に規定されていない場合などです。
どのような場合に例外として認められるのかわからない場合には、交通事故紛争処理センターに直接確認してみるとよいでしょう。
3.必ずしも示談金を満額得られるわけではない
交通事故紛争処理センターを利用すれば、交通事故に詳しい弁護士の法的知見を活用した紛争解決を期待できます。
しかし、担当弁護士はあくまでも中立・公平な立場で和解案を作成する立場にあります。
すなわち、交通事故紛争処理センターの法律相談や和解あっせんでは、被害者側の利益を最大化するために担当弁護士が力を発揮してくれるわけではないということです。
そのため、場合によっては被害者側の主張が認められず、相手方保険会社の主張が全面的に採用されることもあり得ます。
自分が希望する示談金を受け取りたい場合には、ご自身で弁護士を選任して、最初から民事訴訟を提起するほうがよいケースも少なくありません。
4.被害者自身が相談・あっせんに対応する必要がある
交通事故紛争処理センターでの法律相談やあっせん手続きは、被害者自身が平日の日中に直接センターに出向いておこなう必要があります。
また、手続きに必要な書類についても被害者自身が用意しなければなりません。
平日に仕事があり、スケジュールを合わせることや出向くことが難しい場合もあるでしょう。
交通事故紛争処理センターを利用する際の流れ
交通事故紛争処理センターを利用する際の流れは、以下のとおりです。
- 交通事故紛争処理センターの支部・相談室に電話予約をする
- 紛争処理センターから利用申込書や利用規定を受け取る
- 予約当日に紛争処理センターで担当弁護士と面談する
- 必要であれば和解あっせん手続きを申し立てる
- 和解が成立しなかったときは審査会による裁定を求める
1.管轄の紛争処理センターに電話予約をする
交通事故紛争処理センターの利用を希望するときには、電話による事前予約が必須です。
申立人の住所地、もしくは事故地の最寄りの紛争処理センターまでお問い合わせください。
センター 連絡先 札幌支部 011-281-3241 仙台支部 022-263-7231 東京本部 03-3346-1756 さいたま相談室 048-650-5271 名古屋支部 052-581-9491 静岡相談室 054-255-5528 金沢相談室 076-234-6650 大阪相談室 06-6227-0277 広島支部 082-249-5421 高松支部 087-822-5005 福岡支部 092-721-0881 引用元:センター所在地一覧
なお、予約の受付は、月曜日~金曜日(祝祭日と12月29日~1月3日を除く)の午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)となっています。
2.紛争処理センターから利用申込書・利用規定を受け取る
電話予約で法律相談の日程が’決まったら、紛争処理センターから「利用申込書」と「利用規定」を受け取ります。
利用申込書と利用規定には、法律相談当日に持参する必要書類に関する説明が記載されています。
法律相談当日までに必要書類を提出できるように用意しましょう。
なお、相談時に持参するべき主な資料・書類には、以下のようなものがあります。
物損事故・人身事故(けが、死亡、後遺障害)によって必要となる資料・書類は異なるので、事前に交通事故紛争処理センターまで確認するようにしてください。
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで入手)
- 事故発生状況報告書(道路の形状、標識の位置、自動車の進行方向などを簡単に記載)
- 相手方の情報(氏名、自動車保険の会社名・担当者名、代理人弁護士の氏名・連絡先など)
- 保険会社や加害者側が提示した賠償金提示明細書など
- 診断書、診療報酬明細書、施術証明書
- 後遺障害診断書、後遺障害等級の認定結果及び理由が書かれている書面
- 治療費・証明書費用・通院交通費・家政婦や介護者などに要した費用・葬儀関係費用の明細書や領収書
- 休業損害証明書(源泉徴収票、確定申告書控え、納税証明など)
- 死亡診断書、死体検案書
- 戸籍謄本(除籍謄本)
- 修理費の請求書、修理工場の見積書、損傷箇所の写真
- 車両仮修理・引揚げ・牽引・運搬・代車・代替車両購入費・登記費用の請求書、領収書
- 車両の評価額を裏付ける資料
- 車両の所有権を確認する資料(自動車検査証など)
3.紛争処理センターで弁護士と相談する
電話予約をした日時に交通事故紛争処理センターを訪れ、担当弁護士に交通事故の詳細と自分の考えを説明します。
担当弁護士との相談は、基本的に和解あっせんを目的におこなわれるものですが、明らかに申立人の主張が通らないようなケースでは、法律問題などについて解説を受けるのみで終了し、和解あっせんに至らずに終わることもあります。
4.担当弁護士に和解あっせんを要請する
法律相談のあと、和解あっせん手続きに移行します。
通常は、第2回期日以降から相手方が参加して当事者双方の意見が聴取されます。
しかし、物損事故について代理人弁護士が和解あっせんを申し立てているのであれば、紛争の早期解決が望ましいことから第1回期日から相手方の出席が求められることが多いです。
この場合には、申立人が相手方に交通事故紛争処理センターでの和解あっせん期日を伝え、出席を依頼する必要があります。
5.和解が成立しない場合は審査を申し立てる
和解あっせんで示談成立に至らないときには、調停不調の通知から14日以内に申立てがあった場合に限り、審査会における審査を求めることができます。
審査会の裁定に申立人が同意した場合は、相手方の保険会社は審査会の裁定を尊重することになっているので、示談が成立して手続きが終了します。
反対に審査会の裁定に不同意の回答をしたとき(回答期限までに返答をしなかったとき)には、交通事故紛争処理センター以外で話し合いを継続するか、民事訴訟を提起して解決を目指すことになります。
交通事故紛争処理センターを利用した方の体験談・実際の声
交通事故紛争処理センターを利用した方の体験談と実際の声を紹介します。
損害賠償金が15万円程度増額した
昨年の交通事故。
紛争処理センターに相談したら賠償額が15万円くらいアップした。
無料だったし、担当してくれた弁護士さんはこちらの味方をしてくれた。
保険会社の言いなりになったら損するよ。— KSK (@KSK_FX_) July 1, 2023
状況次第では、保険会社が提示した賠償額が覆ることも少なくありません。
そもそも、保険会社は交通事故当事者ではない第三者ですが、「加害者側の代理人」という立場から、少しでも賠償額を引き下げようとしてくるものです。
賠償額や修理箇所などについて少しでも納得できない点があるなら、交通事故紛争処理センターの利用を検討してください。
被害者側の主張が全面的に通った
#損保ジャパン 損保ジャパンとの話し合いがつかないので交通事故紛争処理センターへ持ち込みました。100%こちらの言い分が通りました。https://t.co/d1gdK4p6Ay
— 田舎道_Tyrell (@inakamichi2010) July 27, 2023
保険会社側は交通事故の発生状況を詳細にチェックして賠償額を提示するわけではなく、当事者から事故状況についてある程度の聞き取りをしたうえで、テンプレートどおりに賠償額を決定するのが一般的です。
そのため、事故当時の個別具体的な状況や、過失の有無・割合などが見落とされているケースも少なくありません。
交通事故紛争処理センターに相談をすれば、法律のプロである弁護士の判断で、事故当時の過失状況などが詳細に確認されることになります。
場合によっては、被害者側の主張が全面的に通ることもあり得るわけです。
交通事故紛争処理センター以外の相談窓口3選
交通事故に巻き込まれたとき、交通事故紛争処理センターだけではなく、以下の相談窓口を利用することを検討できます。
- 日弁連交通事故相談センター
- 自賠責保険・共済紛争処理機構
- 法律事務所
1.日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会が運営する公益財団法人で、交通事故をめぐる法律問題全てを相談できます。
同一交通事故について原則5回まで無料相談を受け付けてくれるうえに、示談あっせんや審査事業もおこなっています。
示談交渉が開始してから相談が可能な交通事故紛争処理センターと違って、事故発生直後からアドバイスを求められる点が、大きなメリットといえるでしょう。
2.自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険・自賠責共済の保険金・共済金・損害賠償額・後遺障害の等級認定制度についての紛争を対象とする組織です。
同じく交通事故を対象とする組織ですが、交通事故紛争処理センターと自賠責保険・共済紛争処理機構では取り扱う範囲が全く異なる点に注意してください。
3.法律事務所
法律事務所に相談・依頼することは、交通事故に強い弁護士から直接支援を受けることを意味します。
一方、交通事故紛争処理センターはあくまでも中立的な立場で被害者をサポートする機関です。
そのため、慰謝料の増額など被害者の利益の最大化したい場合には、法律事務所に個別相談するほうが適しているでしょう。
また、弁護士に依頼すると、納得のいく慰謝料を得られる可能性が高まるだけではなく、書類作成などの手続き面でもサポートを受けられます。
なお、気になる弁護士費用についてですが、ご自身が加入している保険会社に弁護士費用特約が付いている場合、自己負担は不要となるケースがあります。
多くの保険では、弁護士費用特約の上限を300万円程度に設定しています。
また、家族が加入している保険に特約が付いている場合でも、利用できる場合があります。
さいごに|交通事故のお悩みはひとりで抱えず弁護士に相談する
交通事故は人生で何回も巻き込まれるものではありません。
慣れない保険会社との対応に不安を感じたり、多少の不満は我慢したほうがよいのではないかと思い込む方も少なくないでしょう。
加害者側の保険会社はあくまでも「加害者の代理人」として賠償額を提示しているに過ぎず、保険会社の主張を受け入れるだけだと、受け取ることができたはずのお金を受け取れない、ということになりかねません。
交通事故紛争処理センターに連絡をすれば無料で担当弁護士のアドバイスを受けられます。
また、示談条件について疑問や不満がある場合は、和解あっせんや審査の手続きを利用することも可能です。
被害者側の意見が全面的に採用される確証はありませんが、法律相談を受けるだけでも、悩みや不安が軽減される可能性があります。
無料で気軽に利用することもできるので、興味のある方は交通事故紛争処理センターに相談を申し込んでみてはいかがでしょうか。