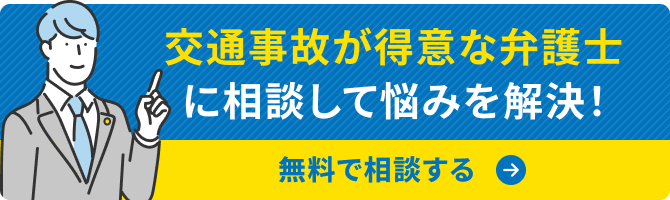交通事故によるけがで仕事や家事ができなくなってしまった場合、加害者側に休業損害を請求することができます。
仕事や家事ができなくなると生活に大きく影響するため、できるだけ多くの金額を請求したいと思う方は多いでしょう。
しかし、「休業損害額はどのように計算すればよいのか」「休業損害をもらうためには何から始めればよいのか」と、悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
本記事では、休業損害とは何か、休業損害の計算方法、請求方法などについて解説します。
休業損害をこれから請求しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
休業損害とは交通事故のけがで仕事を休んだ際に失った収入のこと
休業損害とは、交通事故によるけがが原因で休業ないし不十分な稼働を余儀なくされたことで失った収入のことをいいます。
交通事故に遭い、仕事を休んだり遅刻や早退をしたりした場合、加害者側に休業損害分の支払を請求することができます。
なお、請求できる金額は、職業、休業前の収入、休業期間、休業中の通院日数などによって異なります。
また、会社員だけでなく専業主婦・主夫の場合でも、けがによって家事ができなくなってしまった場合も補償を請求することが可能です。
さらには、失業中の方や学生の場合であっても、状況によっては、休業損害の請求が可能です。
休業損害で用いられる三つの算定基準
休業損害の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
どの算定基準を用いるかによって、休業損害の金額が大きく変わることを覚えておきましょう。
自賠責基準|1日あたり原則6,100円となる
自賠責基準は、加害者側が加入している自賠責保険会社に休業損害を請求する際に用いられる算定基準です。
自賠責保険は、被害者に対して最低限の補償を支払うことを目的としているため、三つの基準のなかで金額が最も低いとされています。
自賠責基準を使用する場合は、1日あたりの損害額を原則6,100円として計算します。
ただし、休業前の収入が明らかに6,100円を超えていると証明できる場合は、1日あたり1万9,000円を上限として休業損害を請求することが可能です。
任意保険基準|任意保険会社によって異なる
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社に対して休業損害を請求する際に使用する算定基準です。
任意保険基準の具体的な限度額や休業の上限日数は保険会社ごとに独自に定められており、公表はされておりません。
一般的には自賠責基準と同額や、やや高い程度とされています。
弁護士基準|事故前の収入を基準にする
弁護士基準とは、弁護士及び裁判所が休業損害を計算する際に用いる算定基準です。
三つの基準のなかで、休業損害の金額が最も高くなります。
つまり、弁護士に加害者側の任意保険会社との示談交渉を依頼すれば、休業損害の賠償額を増やすことができます。
休業損害額の計算式は、以下のとおりです。
- 1日あたりの基礎収入×認定休業日数
「1日あたりの基礎収入」は、交通事故に遭う前の収入を基に計算される金額のことで、被害者の職業により算出方法が異なります。
また、「認定休業日数」とは、入院や通院のために仕事を休んだ日数のことです。
なお、有給休暇を使って休んだ場合でも、休業日数に含めることができます。
1日あたりの基礎収入と休業損害算出方法
休業損害は、1日あたりの損害額を基に算出されますが、被害者の職業によって計算方法が異なります。
ここからは、休業損害の日額の算出方法を、給与所得者、自営業・個人事業主、会社役員、専業主婦・主夫の職業別で解説します。
また、無職・失業中の場合も解説します。
給与所得者の場合|事故前3ヵ月分の給与額を基準にする
被害者が、会社員やアルバイトなどの給与所得者の場合は、以下のような計算式を適用して休業損害を算出します。
- 断続的に欠勤している場合:(事故前3ヵ月分の給与額÷出勤日数)×休業日数
- ある程度連続して欠勤している場合:(事故前3ヵ月分の給与額÷90日)×休業日数
ただし、「事故前3ヵ月分の給与額」は、税金や社会保険料などが控除される前のいわゆる額面での金額です。
手取額ではないので、給与明細を確認する際に間違えないよう注意しましょう。
なお、産休・育休明けで直近3ヵ月の正確な給与額を算出できない場合は、産休・育休に入る前の年収を基に休業損害を計算します。
また、交通事故によるけがが原因でボーナスや手当が減少したり、昇給が遅れたりした場合も、休業損害として請求できることがあります。
自営業・個人事業主の場合|前年の所得金額を基準にする
被害者が自営業者や個人事業主の場合は、主に以下の計算式で算出します。
- (事故前年の所得金額+固定経費)×寄与率÷365日×休業日数
「事故前年の所得金額」は、前年度の確定申告書で確認しましょう。
青色申告者の場合は「前年度の確定申告所得額+青色申告控除額」、白色申告者の場合は「前年度の確定申告所得額+専従者控除額」が「事故前年の所得金額」となります。
「寄与率」とは、親族などが事業をサポートしていた場合に、自営業者本人の稼働による利益の度合いを示すものです。
完全に自分一人で事業をおこなっているのであれば、稼働率は100%で計算します。
会社役員の場合|役員報酬の労務対価部分を基準にする
会社役員の場合は、以下の計算式で算出します。
- 1日あたりの労働対価(役員報酬-利益配当分)×休業日数
基礎収入は、労働によって発生する報酬分の金額のみ含まれます。
役員報酬のうち利益配当は労働の対価ではないため、基礎収入には算入できません。
専業主婦・主夫の場合|賃金センサスを基準にする
専業主婦・主夫の場合は、以下の計算式で請求額を求めます。
- 女性労働者の全年齢平均賃金額から算出した基礎収入額の日額×休業日数
「女性労働者の前年齢平均賃金額」は、賃金センサスを基に算出します。
なお、主夫の場合も女性の平均賃金を使って計算するケースが一般的です。
無職・失業中の場合|失業前の収入や賃金センサスなどを基準にする
無職や失業中の場合は、以下の条件に該当すれば休業損害を請求できます。
- 求職活動中で、交通事故前後に内定をもらっていた場合
- 年齢、能力、本人の意欲などから、事故がなければ当然就労していたと考えられる場合
上記の条件に該当する場合は、以下のように損害額を計算することが可能です。
- 求職活動中で、交通事故前後に内定をもらっていた場合:賃金センサスまたは就職予定先の給与推定額に基づいて算出
- 年齢、能力、本人の意欲などから、事故がなければ当然就労していたと考えられる場合:賃金センサスまたは失業前の収入額に基づいて算出
基礎収入の立証に必要な書類
休業損害を請求する際には、算定に用いた基礎収入に間違いがないことを立証しなければなりません。
立証方法は個々のケースごとに異なりますが、例えば、以下のような書類を用意する必要があります。
- 源泉徴収票
- 給与明細書
- 休業損害証明書
- 賞与減額証明書
- 昇給・昇格の遅延に関する社内規定・陳述書
基礎収入の立証ができなければ、十分に休業損害を補償してもらえない可能性があります。
どの書類が必要なのか判断できない場合には、弁護士に相談してみてください。
休業日数の数え方
休業損害を計算する際に用いる休業日数とは、具体的にどの期間を指すのでしょうか。
ここからは、休業日数の数え方について解説します。
休業損害の対象日|入通院のために休業した日数が対象
基本的には、入院や通院のために休業した日数が休業日として認められます。
半休や早退など全日休業していない場合でも、休んだ時間分を休業日に算入することが可能です。
自営業者や専業主婦・主夫など、いつ休業したかの記録がない場合は、病院で発行される診療報酬明細書や診断書を基に休んだ日数を証明できます。
また、入院や通院だけでなく、リハビリで休んだ場合も休業日に含めることが可能です。
休業損害の対象期間|完治・症状固定した日までが対象
休業損害の対象となるのは、事故に遭った日から、けがが完治または症状固定した日までの休業日です。
症状固定とは、今後治療を続けても症状がよくならないと医師が判断した状態のことです。
ただし、症状固定後もリハビリを続ける場合、例外的に休業損害の補償を引き続き受けられることがあります。
症状固定したあとの補償は、休業損害ではなく「逸失利益」として請求するケースが一般的です。
逸失利益とは、後遺障害が被害者に残り、労働能力が減少するために、将来的に発生するはずであった収入の減少をいいます。
症状固定の状態になると、仕事の能率やスキルの低下により事故前よりも収入が下がってしまう可能性があるので、仕事に支障が出るほどの症状が残った場合は逸失利益を請求しましょう。
こんなとき休業損害はどうなる?
休業損害を受け取るのが初めての場合、わからないことが多く、戸惑ってしまう方は多いでしょう。
ここからは、会社員など給与所得者が迷うことが多い4つケースと、正しい対処法を解説します。
1.通院のために有給休暇を利用した場合
有給休暇を使った場合でも、休業損害を請求できます。
有給休暇は労働者の権利であるうえ、事故に遭わなければ有給休暇を消化する必要はなかったはずです。
交通事故によって有給休暇を使わざるを得なくなったこと自体が損害ととらえられるため、現実に収入が減っていなくても、休業損害の請求は可能です。
有給休暇日も休業日数にカウントされるので、有給休暇を使ったからといって休業損害が少なくなることはありません。
2.賞与を減額された場合
交通事故によるけがが原因で賞与を減額された場合も、加害者に減額分を請求できることがあります。
ただし、請求する場合は「賞与減額証明書」によって、具体的にいくら減収したのかを証明しなければなりません。
賞与減額証明書は、任意保険会社に問い合わせれば郵送してもらえるので、届いたら勤務先に記入してもらいましょう。
また、会社が賞与を計算する際に使う基準である「賞与支給規定」があると、減収を証明しやすくなります。
賞与を算出するための計算式や基準がきちんと決められていれば、それらに従って計算することで、どのくらい減収したのかを正確に把握できるためです。
賞与を減額された場合は、賞与減額証明書と賞与支給規定の2つを用意しておきましょう。
3.事故による休業が原因で退職した場合
交通事故によるけがで仕事を辞めてしまった場合は、退職に対する補償を請求することが可能な場合もあります。
交通事故にあわなければ退職する必要がなかったはずなので、退職によって収入が失われてしまったことは交通事故による損害といえます。
交通事故によって退職を余儀なくされたことを証明すれば、休業損害を受け取れる可能性があるので、勤務先に退職証明書を作成してもらいましょう。
退職の原因が交通事故であることが証明できれば、再就職までの必要やむを得ない期間に限り、休業損害を受け取れます。
4.事故による休業が原因で昇給できなかった場合
交通事故によって昇給や昇格ができなかった場合も、休業損害を請求できます。
交通事故がなければ今より多くの給料をもらえていたはずなので、交通事故による損害として支払いを求めることが可能です。
請求する際は、「昇給予定があったこと」「昇級できなかったことでどのくらいの損害を被ったのか」を会社に証明してもらう必要があります。
昇級できなかった原因が交通事故であることと具体的な損害額を立証できれば、休業損害として認められる可能性が高いでしょう。
まとめ|休業損害についてわからないことは弁護士に相談しよう
休業損害は、職業、事故前の収入、休業日数などを考慮して損害額を算定します。
しかし、休業損害の日額や休業日数を自分で正確に算出するのは簡単ではありません。
休業損害を請求するための手続きも複雑なため、書類の提出に時間がかかってしまい、休業損害を受け取れる時期が遅れてしまう可能性もあります。
休業損害の計算方法や手続きについて不安があるなら、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
休業損害請求に強い弁護士に相談・依頼をすれば適切な金額を算定してもらえるうえ、自分で交渉するよりも多くの休業損害を請求できるでしょう。
また、示談交渉は弁護士に代行してもらえるので、交通事故の問題をスムーズに解決できます。
休業損害をできるだけ多く受け取りたい方や、休業損害の手続きを自分でできるか心配な方は、弁護士に一度相談してみましょう。