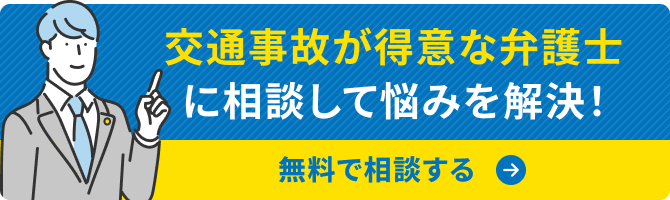交通事故で負ったけがが完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請することにより、後遺症の程度に見合った等級が認定される可能性があります。
しかし、申請しても非該当になったり、本来よりも低い等級に認定されたりするケースも珍しくありません。
事故で痛い思いをした上に損をしないためには、弁護士に依頼して適切な後遺障害等級に認定してもらうことが重要です。
本記事では、交通事故の後遺障害について、弁護士に相談するメリットやデメリット、弁護士の選び方について紹介します。
交通事故における後遺障害等級認定とは?
事故の被害者において、後遺障害が残存した場合は、相手方保険会社より、被害者の精神的損害に対して賠償がなされます。
そこで、後遺障害の程度を算定するために、後遺障害等級の認定をおこないます。
具体的には、交通事故によるけがが原因で機能障害・神経症状などが残り、労働能力の低下などが生じている場合に認定されるものです。
等級は障害の程度に応じて、非該当の場合を除き、1級~14級に分類されています。
では、なぜ後遺障害等級の認定を受けることが重要なのか、また、どのような手続が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
後遺障害等級によって損害賠償額は大きく変わる
後遺障害等級によって、損害賠償額は大きく変わります。
後遺障害等級認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料・後遺障害による逸失利益を請求できるからです。
また、等級が高くなるほど、請求できる金額も高くなっていきます。
そのため、後遺障害が残った場合にできるだけ多くの損害賠償を請求するためには、適切な後遺障害等級認定を受けることが必要不可欠です。
等級認定の結果次第で、損害賠償額が数百万円以上変わってくるケースも少なくありません。
後遺障害等級認定の申請方法は2種類ある
後遺障害等級認定の申請方法は、以下の2種類から選択できます。
- 事前認定:加害者の任意保険会社に申請手続を任せる方法
- 被害者請求:書類作成・収集などの申請手続を全て自分で行なう方法
どちらの方法でも加害者の自賠責保険に対して申請し、損害保険料率算出機構による調査がおこなわれる点は変わりありません。
しかし、それぞれの申請方法には以下のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 事前認定 | 任意保険会社に後遺障害診断書を提出するだけで手続きが終わる | 任意保険会社が等級認定に向けて尽力してくれるとは限らない |
| 被害者請求 | ・自由に資料を追加できるので適切な等級認定を受けやすい ・等級認定された場合は示談前に自賠責保険金を受け取れる | ・資料作成・収集の手間がかかる ・法律や医学の専門知識がないと対応が難しい |
少しでも等級認定の可能性を高めたいのであれば被害者請求で申請することをおすすめします。
後遺障害等級認定の手続きを自力で進めることは難しい
後遺障害等級認定は、損害賠償額を大きく左右する要素です。
そのため、少しでも適切な等級を受けられるように、被害者請求での手続きが望ましいといえるでしょう。
しかし、被害者請求では症状を正確に把握し、どの等級に該当するのかを見極めて主張する必要があります。
高度な専門知識が求められるので、自力での対応は現実的ではありません。
また、作成・収集しなければならない書類も、以下のように多岐にわたります。
- 保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
- 診療報酬明細書
- 医師の診断書
- 休業損害を証明する書類
- 印鑑証明書
- MRIやCTなどの検査結果
十分な知識がないなかで無理やり手続きを進めても、主張どおりの等級認定を受けるのは難しいでしょう。
被害者請求を選択するのであれば、交通事故問題を得意とする弁護士のサポートが必要不可欠といえます。
交通事故の後遺障害について弁護士へ相談するメリット
交通事故で後遺症が残った場合、交通事故問題に注力する弁護士への相談にはさまざまなメリットがあります。
ここでは、具体的なメリットを5つ紹介します。
1.被害者請求の対応を代理してもらえる
後遺障害等級認定の申請には、保険会社がおこなう事前認定と被害者がおこなう被害者請求の2つの方法があります。
被害者請求では資料を自由に提出できるため、適切な後遺障害等級の獲得に向けて自分が主導できる点で有利な方法です。
ただし、被害者請求では、認定のポイントを踏まえた医師の診断書や申請書類の作成、症状を証明するための他覚的所見が必要になります。
資料の作成・収取には交通事故に関する法律知識や医学的な知見が求められるため、自分でおこなうのは現実的ではありません。
しかし、後遺障害等級認定の実績豊富な弁護士に依頼すれば、全ての作業を一任できるので、依頼者は負担なく適切な後遺障害等級を獲得できるでしょう。
2.後遺障害診断書の作成に関して医師に意見してもらえる
弁護士に相談するメリットのひとつは、後遺障害診断書の作成に関して医師に意見してもらえることです。
後遺障害診断書は担当医が作成してもらう書類であり、記載内容次第で後遺障害等級認定の結果が大きく変わります。
しかし、自身の担当医が必ずしも後遺障害等級認定に有利な診断書を作成してくれるとは限りません。
そこで、後遺障害診断書の書き方について、弁護士から医師に対して意見してもらうことが重要になってきます。
医師と弁護士の両方の視点を取り入れた後遺障害診断書があれば、適切な等級認定を受けられる可能性は格段に高まるでしょう。
3.適切な通院期間・頻度のアドバイスを受けられる
適切な通院期間・頻度のアドバイスを受けられることも、弁護士に相談するメリットのひとつです。
後遺障害等級認定の審査においては、通院期間・頻度も重要視されます。
例えば、重傷を負っているにもかかわらず、ほとんど通院していない状況では、「後遺障害が残るほどのけがではなかった」と判断されるかもしれません。
反対に、必要以上に通院していた場合は、等級認定を受けることが目的だったと捉えられ、審査で不利になる可能性があります。
もちろん通院期間・頻度は医師の指示に従うことが原則ですが、後遺障害等級認定を見据えている場合には、弁護士からも助言を受けるようにしてください。
4.後遺障害等級の認定結果に対する異議申立てをサポートしてもらえる
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級の認定結果に対する異議申立てをサポートしてもらえます。
異議申立て自体は個人でも進められますが、不足している要素を分析し、認定結果を覆すだけの資料を準備することは簡単ではありません。
無駄な時間を費やすことにもなりかねないので、異議申立ては弁護士に任せるのが賢明な判断といえます。
保険会社への異議申立てが上手くいかない場合も、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請をおこなったり、裁判所に訴訟を提起したりと、さまざまなアプローチ方法を提案してくれるはずです。
5.交通事故の損害賠償金を増額できる可能性がある
後遺障害に関して弁護士に相談すれば、交通事故の損害賠償金を増額できる可能性があります。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを算出する際には、3つの算定基準が使用されます。
- 自賠責基準:最低限の補償を目的とした基準。そのため、最も低額になる。
- 任意保険基準:各保険会社が独自に定めている基準。自賠責基準と同額かやや高い程度。
- 弁護士基準:過去の裁判例に基づく基準。最も高額になる。
例えば、自賠責基準と弁護士基準で算出した場合の、後遺障害慰謝料はそれぞれ以下のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
| 第2級 | 998万円 | 2,370万円 |
| 第3級 | 861万円 | 1,990万円 |
| 第4級 | 737万円 | 1,670万円 |
| 第5級 | 618万円 | 1,400万円 |
| 第6級 | 512万円 | 1,180万円 |
| 第7級 | 419万円 | 1,000万円 |
| 第8級 | 331万円 | 830万円 |
| 第9級 | 249万円 | 690万円 |
| 第10級 | 190万円 | 550万円 |
| 第11級 | 136万円 | 420万円 |
| 第12級 | 94万円 | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 110万円 |
最大で1500万円以上の差があり、最も低い14級でも、自賠責基準と弁護士基準では70万円以上の増額が見込めます。
後遺障害逸失利益に関しても、どの算定基準を用いるかによって、最終的に受け取れる金額は大きく変わってきます。
なお、弁護士基準での算定は自力でおこなうこともできますが、計算式が複雑になったり、相手側の保険会社が受け入れなかったりするケースもあるので、弁護士に依頼するのが一般的です。
交通事故の後遺障害について弁護士に依頼するデメリットは弁護士費用がかかること
弁護士に依頼すると適切な後遺障害等級を獲得し損害賠償を増額できる可能性が高いため、後悔するようなデメリットはありません。
強いてデメリットを挙げるとするのであれば、弁護士費用がかかることです。
弁護士に被害者請求の手続きや示談交渉などを依頼する場合、弁護士費用の相場は以下のようになります。
【着手金あり】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 相談料 | 5,000円~1万円/30分 ※無料の事務所あり |
| 着手金 | 経済的利益の額が300万円以下:経済的利益の8% 300万円を超え3000万円以下:5%+9万円 |
| 成功報酬 | 経済的利益の額が300万円以下:経済的利益の16% 300万円を超え3000万円以下:10%+18万円 |
| 実費 | 出張費や収入印紙などにより増減 |
【着手金なし】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 相談料 | 5,000円~1万円/30分 ※無料の事務所あり |
| 着手金 | 0円 |
| 成功報酬 | 経済的利益の額が300万円以下:経済的利益の16%+10万円~20万円 300万円を超え3000万円以下:10%+28万円~38万円 |
| 実費 | 出張費や収入印紙などにより増減 |
弁護士費用の料金形態は法律事務所ごとに違い、着手金がない事務所では成功報酬が高めに設定されているケースがほとんどです。
そのため、着手金がないからといって、必ずしも弁護士費用が安くなるわけではありません。
弁護士費用が不安な方は、まず自分が加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付帯しているかを確認してみてください。
付帯していれば、弁護士費用を300万円程度まで補償してもらえるため、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。
また、弁護士費用は獲得した損害賠償金から支払うことができるため、極軽微な事故でなければ不安に思う必要はないといえるでしょう。
交通事故の後遺障害に強い弁護士の選び方
希望通りの内容で保険会社との示談を成立させるには、後遺障害に強い弁護士を選ぶことが重要です。
ここでは、後遺障害に強い弁護士の選び方のコツを5つ紹介します。
1.返信や連絡が早く面談までの予約がスムーズにおこなえる
弁護士選びにおいては、返信や連絡が早く、面談までの予約がスムーズにおこなえるかどうかが重要です。
弁護士へ相談する場合、電話やメールなどで面談日程を決めることになりますが、中には返信や対応が遅い弁護士もいます。
対応が遅い弁護士に依頼してしまうと、手続きや交渉がスムーズに進まず不安になりますし、なかなか解決しないことにストレスを感じてしまうでしょう。
当日中は難しくても、翌日や翌々日までには対応してくれる弁護士をおすすめします。
2.後遺障害の解決実績が豊富である
一概に弁護士といっても得意分野が異なるため、後遺障害の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。
交通事故に注力し、豊富な解決実績をもつ弁護士であれば、後遺障害等級認定や示談交渉などに関するノウハウが蓄積されているはずので、スムーズな問題解決が期待できます。
ただし、交通事故の解決実績が多くても、後遺障害等級1級と14級では対応に違いが生じることもあります。
そのため、自分と同じようなけが、もしくは高い等級の解決実績を持っている弁護士を選ぶことがポイントです。
3.医学の知見が豊富・提携している協力医がいる
医学の知見が豊富で、協力医がいる弁護士を選ぶことも重要です。
後遺障害等級認定の手続きでは、法律の知識だけでなく、医学の知識も求められます。
また、医師が作成する後遺障害診断書がカギとなるため、医師と弁護士との連携も欠かせません。
医学分野の解決実績や協力医などはホームページなどで公開している法律事務所も多いので、相談する前に一度確認しておくようにしましょう。
4.話を丁寧に聞き依頼人へ寄り添ってくれる
自分の納得できる示談を目指すには、話を丁寧に聞き、依頼人へ寄り添ってくれる弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士によってはあまり話を聞いてくれず、弁護士自身が良いと考えている解決策を説明もなく押しつけてくる可能性もあります。
身勝手な弁護士に依頼してしまうと、自分が希望していた結末にならないおそれがあるため、無料相談の機会を利用してしっかり話を聞いてくれるかを確認しましょう。
5.弁護士費用や支払い方法について明確な説明がある
弁護士に相談・依頼する際には、実際に弁護士費用がどの程度かかるのかをしっかり確認しておくことが重要です。
ほとんどの法律事務所では、費用や支払い方法について事前に説明があります。
一方で、料金体系を確認してもあいまいな返事しかもらえない場合は、あとから費用トラブルが発生する可能性があるため依頼は避けたほうがよいでしょう。
また、交通事故の成功報酬は経済的利益の何%と定めているケースがほとんどです。
ただし、何を経済的利益とするかは法律事務所によって異なるので、事前に確認しておくことが重要です。
「ベンナビ交通事故」に掲載している弁護士の解決事例
「ベンナビ交通事故」は、交通事故問題を得意とする弁護士が多数掲載されているポータルサイトです。
ここでは、ベンナビ交通事故に掲載されている弁護士の解決事例を一部紹介します。
解決事例1|非該当から14級を獲得し、損害賠償220万円増額に成功した事例
| 被害者 | 40代男性 |
|---|---|
| 事故状況 | 車対車 |
| 受傷部位 | むちうち(頸椎捻挫) |
| 後遺障害等級:依頼前→依頼後 | 非該当→14級9号 |
| 慰謝料:依頼前→依頼後 | 約110万円→約330万円 |
| 増額 | 約220万円 |
症状固定後も首の痛みが消えなかったものの、事前認定では非該当とされてしまい後遺症に対する慰謝料をもらえなかったため、弁護士へ相談した事例です。
弁護士は受任後、医師と面談をおこない必要書類を揃えて、非該当だったことへの異議申立てをおこない、14級9号の獲得に成功。
その上で、保険会社と交渉をおこない当初の110万円の約3倍である330万円での示談成立を実現しました。
交通事故によくあるむちうちは、外傷として残らないため痛みが続いていても非該当になるケースがほとんどです。
早い段階で弁護士に相談しておくことで、スムーズに後遺障害等級を獲得できるでしょう。
解決事例2|14級から併合11級を獲得し、損害賠償を540万円増額できた事例
| 被害者 | 50代男性 |
|---|---|
| 事故状況 | 車対車 |
| 受傷部位 | 第5頸椎椎体骨折など |
| 後遺障害等級:依頼前→依頼後 | 14級→併合11級 |
| 増額 | 約130万円 |
後遺障害等級14級に認定されたものの想定より低く、納得がいかなかったため、ベンナビ交通事故に掲載中の弁護士と契約した事例です。
より重篤な状況があると異議申立てをおこなったところ、複数の後遺障害が認められ、併合11級を獲得しました。
その結果、裁判を経て、既払金を除き1000万円以上の損害認定を受けることに成功しています。
解決事例3|後遺障害等級1級の事故で損害賠償8000万円の増額に成功した事例
| 被害者 | 70代女性 |
|---|---|
| 事故状況 | 車対人 |
| 受傷部位 | 頭部 |
| 後遺障害等級:依頼前→依頼後 | 1級1号 |
| 慰謝料:依頼前→依頼後 | 約3700万円→約1億1700万円 |
| 増額 | 約8000万円 |
事故により被害者の意識が戻らず、後遺障害等級1級と判断された事故で、示談金が適正なのか疑問をもった後見人が弁護士に相談した事例です。
被害者の将来的な介護費用や過失割合などが争点になると想定し事前準備を進めたことで、裁判では長く争わずに被害者側の主張を認める和解を成立させることができました。
損害賠償額が高くなるほど、示談で話がまとまらず裁判に発展する可能性もあります。
早い段階で弁護士に依頼すれば、十分な準備期間を設けて裁判に臨めるため、早期和解につながります。
なお、ほかの解決事例について知りたい方は【交通事故の解決事例】をご覧ください。
後遺障害について弁護士相談する際によくある質問
初めての弁護士相談に不安を抱える方は少なくありません。
ここでは、相談する際によくある質問をまとめたので、参考にしてみてください。
後遺障害に関して弁護士に相談・依頼するタイミングは?
後遺障害に関して弁護士に相談・依頼するタイミングは、できるだけ早いほうが望ましいといえるでしょう。
適切な後遺障害認定を受けるためには、通院中から準備を進めなければなりません。
どの程度通院し、どのような検査を受けるのかなど、そのときどきの対応次第で、等級認定の結果は大きく変わります。
対応が遅れると、交通事故との関連性が薄れてしまい、手遅れになる可能性も否定できません。
そのため、できるだけ早い段階で弁護士のアドバイスを受けておくことが重要です。
後遺障害等級認定を受けられるまでの期間は?
後遺障害等級認定を受けられるまでの期間は、申請してから1ヵ月~2ヵ月程度を目安としておきましょう。
| 損害調査所要日数 | 割合 |
|---|---|
| 30日以内 | 73.7% |
| 31日~60日 | 14.0% |
| 61日~90日 | 6.7% |
| 90日超 | 5.6% |
【参考元】2023年度自動車保険の概況|損害保険料率算出機構
ただし、事前認定の場合は任意保険会社の手続きが遅れ、認定までの期間が長引くケースもあります。
少しでも早く等級認定を受けたいのであれば、弁護士に依頼し、被害者請求で手続きを進めるようにしましょう。
まとめ|交通事故の後遺障害に関することは弁護士に相談を!
後遺障害等級は等級がひとつ上がるだけでも、損害賠償金が大きく変わります。
後悔しない結果を目指すのであれば、まず弁護士に相談するようにしてください。
ただし、弁護士・法律事務所によって、得意分野や実績、料金体系などに違いがあります。
そのため、無料相談の機会などを活用しながら、しっかりと比較検討し、自分に合った相談先をみつけることが大切です。