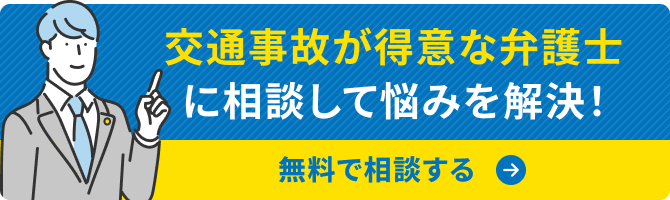交通事故にあってむちうちになってしまったら、相手にそれなりの慰謝料を支払ってほしいものです。
しかし、実際どのくらいの慰謝料を請求できるものなのかわからない方が多いのではないでしょうか?
できるだけ多くの慰謝料を受け取るためには、何をすべきなのかも気になるでしょう。
本記事では、交通事故でむちうちになったときに請求できる慰謝料の相場や計算方法、しっかり受け取るためのポイントなどについて解説します。
交通事故によるむちうちで悩んでいて、慰謝料の相場を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
交通事故のむちうちで請求できる慰謝料とその相場
交通事故でむちうちになった場合、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」を慰謝料として、請求できる場合があります。
まずは、これらふたつの慰謝料と、それぞれの相場について解説します。
入通院慰謝料
むちうちになってしまった場合、入通院慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料とは、けがや入院・通院などをおこなうことによる肉体的・精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
入通院慰謝料の相場は、事故後から症状固定までの入院・通院期間に基づいて、以下のように定められています。
なお、任意保険基準は、保険会社が独自に定めており一般に公表されていないため、ここでは推定値となっています。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 8.6万円 | 12.6万円程度 | 19万円 |
| 2ヵ月間 | 17.2万円 | 25.2万円程度 | 36万円 |
| 3ヵ月間 | 25.8万円 | 37.8万円程度 | 53万円 |
| 4ヵ月間 | 34.4万円 | 47.8万円程度 | 67万円 |
| 5ヵ月間 | 43万円 | 56.8万円程度 | 79万円 |
| 6ヵ月間 | 51.6万円 | 64.2万円程度 | 89万円 |
※自賠責基準は、月の通院日数を10日間で計算
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害等級に認定された場合に請求できる慰謝料です。
後遺障害には1級~14級までの等級が用意されており、認定された等級によって慰謝料額が大きく異なります。
むちうちの場合に該当する後遺障害等級は、12級13号または14級9号であり、請求できる後遺障害慰謝料の相場は、それぞれ以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準(裁判基準) |
|---|---|---|---|
| 12級13号 | 93万円 | 100万円程度 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
どちらの等級に認定されるかは、むちうちの症状によって決まります。
一般的には、以下の症状のときに等級が認定されます。
- 14級9号:局部に神経症状を残すもの
- 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
交通事故のむちうちで慰謝料を決める基準と計算方法
交通事故のむちうちで請求できる慰謝料の算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。
- 自賠責基準:自賠責保険から慰謝料を支払う場合に使用される基準で、被害者に対して最低限の保証をおこなうことを目的としています。
- 任意保険基準:加害者側の任意保険会社が、被害者側に対して提示する基準で、自賠責基準よりやや高い金額になります。
- 弁護士基準:弁護士や裁判所が計算する際に使用する基準です。慰謝料の算定基準のなかで最も高額で、自賠責基準に比べて2倍~3倍高くなります。
各基準を用いた場合の入通院慰謝料の計算方法は、以下のとおりです。
自賠責基準による計算方法
自賠責基準の計算方法は、次のようになります。
対象日数は、以下のいずれか少ないほうとなります。
- 治療期間(病院に通っていた期間)
- 実際に通院した日数×2
たとえば、治療期間が3ヵ月、実際に通院した日数が40日だった場合、1ヵ月あたり30日として計算するため、治療期間は90日、実際に通院した日数×2は80日となります。
そのため、この場合の対象日数はより短い80日となります。
この結果、本ケースで請求できる入通院慰謝料は、4,300円×80日=34.4万円です。
また、慰謝料の上限金額は通院にかかる交通費、治療費、休業損害などと合わせて120万円までとなります。
なお、過失割合が7割以上の場合は日額が低くなってしまうので注意してください。
任意保険基準による計算方法
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に運用している基準であるため、計算方法が異なります。
また、その計算方法は公開されていません。
しかし、過去には統一された任意保険基準が公開されています。
そのときの入通院慰謝料は、以下のとおりです。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 |
| 1月 | 12.6 | 37.8 | 63.0 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 173.9 |
| 2月 | 25.2 | 50.4 | 73.0 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.5 | 162.6 | 171.4 | 176.4 |
| 3月 | 37.8 | 60.4 | 82.0 | 102.0 | 118.5 | 133.5 | 146.3 | 157.6 | 166.4 | 173.9 | 178.9 |
| 4月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 | 161.3 | 168.9 | 176.4 | 181.4 |
| 5月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 | 163.8 | 171.4 | 178.9 | 183.9 |
| 6月 | 64.2 | 83.2 | 102.0 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 185.4 |
| 7月 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.3 | 136.7 | 149.9 | 160.1 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 188.9 |
| 8月 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.4 |
| 9月 | 82.0 | 99.6 | 116.0 | 131.1 | 143.7 | 154.9 | 165.1 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 193.9 |
| 10月 | 87.0 | 103.4 | 118.5 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.6 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.4 |
※単位:万円
弁護士基準による計算方法
弁護士基準で慰謝料を計算するときには、以下の算定表を使用します。
この算定表は、過去の判例を基に設定された、いわゆる「赤い本」に基づいて計算されています。
重傷用と軽傷用のふたつに分けられていますが、むちうちの場合は基本的に軽傷用を参照してください。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
交通事故のむちうちで後遺障害の認定を受けた場合
むちうちが交通事故による後遺障害と認定されると、慰謝料を含めた賠償金をより多く受け取ることができます。
慰謝料金額を大きく左右するものなので、相応の慰謝料を請求したいなら後遺障害等級認定についてしっかりと知っておくことが必要です。
ここからは、後遺障害等級認定について詳しく解説します。
後遺障害慰謝料の相場
交通事故のむちうちで後遺障害の認定を受けた場合、該当する後遺障害等級は12級13号または14級9号となります。
各等級の後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準(裁判基準) |
|---|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 100万円程度 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
慰謝料額については、14級9号よりも12級13号のほうが高くなります。
また、後遺障害等級が同じであっても、実際に受け取れる慰謝料額は算定に使われる基準によって異なります。
後遺障害等級における認定基準の違い
後遺障害等級における各認定基準の違いは、以下のとおりです。
- 14級9号:局部に神経症状を残すもの
- 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号であれば、負傷した部位に痛みや痺れなどの神経症状が一貫して残っている場合に認定されます。
症状の原因が不明であったとしても、自覚症状を示す資料を提出することで認定される可能性が高いです。
一方、12級13号であれば、神経症状が一貫して残っていることに加えて、症状の原因が医学的にきちんと証明できることが求められます。
たとえば、画像検査(レントゲン写真・MRI写真・CT画像など)で症状の原因が明確に指摘できなければなりません。
このように、むちうちにおける後遺障害等級の認定基準は、14級9号が痛みや痺れなどの自覚症状が認定判断の中心です。
それに対して、12級13号は画像診断などの結果で、症状の原因が証明されることが求められます。
このため、認定されるためのハードルが高くなっています。
認定されると逸失利益を請求できる
後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。
後遺障害慰謝料は、すでに説明したとおり、認定された等級に応じて支払われる慰謝料のことです。
後遺障害等級は1級~14級の14段階に分かれており、上位の等級ほど多くの慰謝料を請求することができます。
一方、逸失利益とは、後遺障害で仕事の能率やスキルが低下したことにより、将来受け取れるはずだった収入の減少分を補償するものです。
被害者の職業、収入、後遺障害等級、年齢などによって金額が変わります。
交通事故のむちうちで後遺障害の認定を受ける方法
それでは、交通事故のむちうちで後遺障害の認定を受けるための方法について見ていきましょう。
ここでは、後遺障害等級認定を受けるための条件と、認定を受けるまでの一般的な流れを解説します。
むちうちで後遺障害等級認定を受けるための要素
後遺障害等級認定を受けるには、以下の5つの要素が挙げられます。
①症状が他覚的に表れていること
後遺障害等級認定における審査では、提出した書類を基に症状の有無や程度を判断します。
主に、以下の検査結果を参考に、症状がどの程度のものなのかをチェックされます。
- 画像検査:レントゲン写真、MRI写真、CT画像など
- 神経学的検査:患部やその周辺に刺激を与えて痛みを感じるかをみる検査。
スパーリンクテスト、深部腱反射テスト、筋萎縮検査、知覚検査などの方法が用いられる。
上記の検査の結果を基に、該当する等級があるか、あるとしたらどの等級に該当するかが判断されます。
該当する等級がなかった場合は等級認定されず、後遺障害慰謝料や逸失利益などは受け取れなくなります。
後遺障害等級認定を受けるために必要な検査は決められているので、全てを検査できているかについては、弁護士に相談するとよいでしょう。
②事故発生直後から継続して一貫した症状があること
事故直後からずっと同じ症状が続いていなければ、後遺障害等級に認定されるのは難しいです。
事故から時間がかなり経ってから症状が出始めた場合、途中で症状が変わった場合、天気によって症状にばらつきがある場合などは、交通事故との関連性が立証できず、後遺障害と認めるほどではないと判断されてしまいます。
症状が続いているか、一貫しているかは、主に医師が作成する後遺障害診断書から判断されます。
後遺障害診断書の内容は、後遺障害等級認定されるための重要な書類なので、提出前に念入りにチェックしましょう。
③労働能力に影響を与えていること
後遺障害によって仕事に悪影響が出ているかどうかも、後遺障害等級認定を受けるうえで重要なポイントです。
後遺障害により仕事の能率が下がったことで、昇給・昇格の機会を失った、収入が下がった、業務範囲が狭くなった、などの不利益を被っている場合は、そのことをしっかりと主張しましょう。
④後遺障害等級の認定基準を満たしている
後遺障害等級は、1級~14級の14段階に分けられています。
それぞれの等級には認定基準があり、後遺障害診断書や検査資料などを基に、認定基準を満たしているかどうかが判断されます。
そのため、認定基準を満たしていることがわかる書類を提出することが大切です。
⑤治療期間が適切であること
治療期間が短いと、後遺障害等級に認定されない可能性があるので注意してください。
具体的には治療期間が半年以上でないと、後遺障害等級に該当しないと判断される可能性が高いです。
ただし、足や腕を切断せざるを得ない場合など明らかに生活に支障をきたすレベルの後遺障害がある場合は、治療期間が短くても等級認定される可能性があります。
むちうちで後遺障害認定を受けるまでの流れ
ここからは、後遺障害認定の一般的な流れについて解説します。
医師から症状固定の診断を受ける
これ以上治療をしても完治しない状態のことを症状固定といいます。
つまり、症状が後遺症として残ってしまうということです。
医師に症状固定と診断されたら、それ以降は保険会社から治療費や休業損害が支払われなくなります。
症状固定後の補償や、後遺症が残ったことによる慰謝料を請求するためには、後遺障害等級に認定される必要があるので、そのための手続きを進めましょう。
後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害等級認定の申請に向け、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害等級の認定審査では、後遺障害診断書の内容を基にどの等級がふさわしいかが決まります。
書類に不備があったり、等級認定されるための十分な根拠が記載されていなかったりすると等級認定されない可能性があるので注意しましょう。
後遺障害診断書を作成してもらったら、正しい内容や症状の詳細が書かれているかチェックしてください。
「相応の等級に認定されて、納得できる慰謝料を支払ってほしい」と考えているなら、弁護士に後遺障害診断書の内容をチェックしてもらうのがおすすめです。
「法的に十分な根拠が揃っているか」という観点で確認してもらえるので、自分でチェックするよりも等級認定される可能性が高くなります。
必要書類を揃えて保険会社に提出する
後遺障害等級認定の申請に必要な書類を揃えましょう。
必要書類は、加害者側の自賠責保険会社から取り寄せられるものと、病院や役所などで自分で集めるものとがあります。
- 支払請求書
- 事故発生状況報告書
- 人身事故証明書入手不能理由書(※物損事故として届け出ている場合)
- 診断書
- 後遺障害診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 施術証明書・施術費明細書(※整骨院に通った場合)
- 委任状(※申請を弁護士など第三者に任せる場合)
- 看護料領収書・付添看護自認書(※看護・介護が生じた場合)
- 休業損害証明書(※事故が理由で休業した場合)
- 交通事故証明書
- 被害者の印鑑証明書
- 委任者の印鑑証明書(※申請を弁護士など第三者に任せる場合)
- 住民票または戸籍抄本(※申請者が未成年の場合や、主婦として休業損害を請求する場合)
- 後遺症の詳細がわかる資料
- 自動車検査証、標識交付証明書または軽自動車届出済証(※原付自転車または軽自動車(二輪)、車検対象者でない場合)
- 確定申告書や所得証明書(※治療のために休業した場合)
後遺障害診断書や各種検査資料など必要書類が揃ったら、相手方の自賠責保険会社に書類を提出し、後遺障害等級認定の申請をおこないます。
なお、上記のように書類を全て自分で用意する申請方法を「被害者請求」といいますが、「事前認定」という方法でおこなうことも可能です。
事前認定の場合、後遺障害診断書のみ加害者側の保険会社に提出すれば、残りの書類は全て保険会社がまとめて準備してくれます。
手間がかからないのがメリットですが、ほとんどの書類の準備を加害者側の保険会社に任せてしまうので、書類の不備があっても気づけないのがネックです。
加害者側の保険会社は治療費や慰謝料を支払う立場であることから、被害者側に有利な資料を積極的に集めてくれるとは限りません。
書類に不備や不足があると、思ったとおりの等級が認定されず、納得できる慰謝料を受け取れない可能性があります。
その点、被害者請求は書類を全て自分で用意するので、万全な状態で審査を受けられるわけです。
書類集めの手間や時間はかかりますが、相応の慰謝料を請求したいなら被害者請求がおすすめです。
損害保険料率算出機構による審査がおこなわれる
提出した書類を基に、損害保険料率算出機構にて審査がおこなわれます。
書類の内容から、後遺障害等級に該当するか、該当する場合はどの等級に該当するかが判断されます。
通知結果を基に示談交渉する
審査開始から1ヵ月~3ヵ月ほどで結果が通知されます。
通知内容を確認し、問題がなければ相手方の保険会社との示談交渉を始めましょう。
示談交渉では、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できます。
相応の賠償金を受け取れるよう、可能であれば弁護士に依頼しましょう。
認定結果に不服があれば異議を申し立てる
後遺障害等級の認定結果に納得がいかなければ、自賠責保険会社へ異議申立てをおこなうことも可能です。
しかし、合理的な根拠がなければ再審査してもらえない可能性があるので、異議申立てをおこなう場合は、新たな医学的根拠を提示する必要があります。
認定結果に不服がある場合は、異議申立てをするべきかどうか、医師や弁護士に相談するとよいでしょう。
交通事故のむちうちで適切な慰謝料を受け取るポイント
交通事故のむちうちで適切な慰謝料を受け取るためには、どのような点に気を付ければよいのでしょうか?
ここからは、慰謝料請求の際の注意点について解説します。
慰謝料の請求や示談交渉は治療が終了してからおこなう
慰謝料の請求や示談交渉は、医師から完治または症状固定と診断されてからおこないましょう。
入通院慰謝料は、治療期間や通院日数が多いほど高額になります。
治療がまだ終わっていない段階で交渉を始めてしまうと治療期間が短くなり、受け取れる慰謝料が少なくなってしまうので注意しましょう。
保険会社からの治療費打ち切りには応じない
保険会社から治療費支払いの打ち切りをほのめかされても鵜呑みにしてはいけません。
保険会社は慰謝料を抑えるため、早期に支払いを打ち切ろうとしてきます。
しかし、症状が完治または症状固定したかどうかは医師が判断することです。
治療をやめてしまうと、その分の慰謝料が減ってしまうので気をつけましょう。
治療をやめる時期については保険会社のいうことには応じず、医師としっかり相談して決めてください。
接骨院や整骨院での治療は医師の許可を取る
接骨院や整骨院でむちうちの治療を受ける場合、必ず医師の許可をとりましょう。
医師の許可がないまま、医療機関以外で治療を始めてしまうと、「治療は本当に必要だったのか?」と疑われる可能性があります。
治療の必要性が疑われてしまうと、慰謝料を受け取れない恐れがあるので注意する必要があります。
一方、事前に医師の許可を受けていれば「接骨院や整骨院での治療がむちうちの症状改善に必要なものである」と医師が認めていることになります。
相応の治療費や慰謝料を受け取りたいなら、医師の同意や許可を得てから接骨院や整骨院に通うことを忘れないようにしましょう。
過失割合が適切かどうか見極める
慰謝料は、過失割合によって金額が大きく変わるので注意しましょう。
示談交渉では、相手方の保険会社が被害者側に高めの過失割合を提示してくることがありますが、安易に受け入れてはいけません。
自賠責基準では、被害者の過失割合が7割を超えると慰謝料が減額されます。
過失割合が不当に高いと、受け取れる慰謝料が減って損をしてしまうので、必ず提示された過失割合が適正かどうか見極めるようにしてください。
交通事故のむちうちで慰謝料以外に請求できる賠償金
交通事故でむちうちになってしまったら、慰謝料以外にもさまざまな賠償金を請求できます。
ここからは、むちうちで請求できる賠償金について解説します。
治療費
むちうちの治療に伴って支払った以下の費用を、損害賠償として請求できます。
- 文書料:診断書や通院証明書などの書類の作成にかかる手数料
- 診断書発行費:診断書の発行にかかる費用
- 通院交通費:通院にかかるバス代、電車賃、ガソリン代など
- 付添看護費:専門のヘルパーや家族に看護をしてもらった場合にかかる費用
- 入院雑費:入院時の洗面具、衣類、寝具、新聞などの購入費用
治療にかかった費用をしっかり請求できるよう、レシートや領収書は大切に保管しておきましょう。
休業損害
むちうちで仕事を休んだことにより受け取れなかった収入分を請求できます。
会社員だけでなく、専業主婦(夫)やアルバイトをしている学生でも請求することが可能です。
休業損害は、自賠責基準では原則として以下の計算式で算出されます。
ただし、1日あたりの収入が6,100円を明らかに超える場合は、休業前の実際の収入を基に算出することもあります。
休業損害は弁護士に依頼すれば増額も可能なので、収入の減少分をしっかり補填したい場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
逸失利益
逸失利益とは、事故がなければ将来受け取れるはずだった収入のことです。
後遺障害が残ってしまった場合、事故前に比べて仕事の効率が落ちてしまい収入が減ってしまう可能性があります。
逸失利益を賠償してもらうことで、将来にわたる収入の減少分を補うことができます。
逸失利益は、以下の計算式で求められます。
基礎収入には、政府が毎年実施している平均賃金の統計(賃金構造基本統計調査)、いわゆる「賃金センサス」が用いられます。
また、労働能力喪失率は認定された等級に応じて、喪失期間に対応するライプニッツ係数は被害者の年齢に応じて決められています。
また、追突事故などで車が損壊した場合も修理費を逸失利益に含めて請求できます。
【参考元】
政府統計の総合窓口|賃金構造基本統計調査
国土交通省|労働能力喪失率表
国土交通省|就労可能年数とライプニッツ係数表
相手方が提示する慰謝料が安い場合の対処法
相手方の保険会社から提示された慰謝料が低いと感じた場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士は、弁護士基準(裁判基準)という算定基準を使って慰謝料金額を計算します。
弁護士基準は、慰謝料の算定基準のなかで最も金額が高いので、弁護士に依頼することで慰謝料を増額できる可能性が高くなります。
加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を一定額まで負担せずに済みます。
「適切な慰謝料を請求したい」「もっと多くの慰謝料を支払ってほしい」と考えている方は、弁護士に一度相談してみましょう。
交通事故のむちうちで慰謝料が増額した事例
ここでは、「ベンナビ交通事故」に掲載している解決事例のなかから、賠償金を増額できたケースを紹介します。
非該当から14級を獲得し、損害賠償を約3倍まで増額できたケース
被害者は乗用車を運転していて信号待ち中に、後続乗用車に追突され、これによって、頸椎捻挫や腰椎捻挫、いわゆるむちうちの傷害を負いました。
当初、自賠責から後遺障害非該当とされ、後遺症以外に対する慰謝料が請求できない状況でした。
しかし、弁護士が介入して医師と相談し、必要書類を揃えたうえで、自賠責への異議申立てをおこなったことで、14級が認定されました。
結果として、慰謝料額は当初の提示額から約3倍の220万円の増額となりました。
当初後遺症認定が14級とされたが、異議を申立て併合11級が認定された事案
被害者は幹線道路を直進中に、交差点で反対車線から右折してきた車両と衝突し、後遺障害14級と認定されました。
しかし、等級認定が極めて低いと感じて弁護士に依頼をしたことで、後遺障害の等級認定が11級となり、裁判を経て既払金を除いて1000万円以上の障害認定を受けました。
このように、弁護士に依頼をすることで、多くの金額を回収できる場合もあります。
【参考元】交通事故の解決事例 | ベンナビ交通事故
まずは、交通事故の慰謝料請求が得意な弁護士に相談してみましょう。
交通事故でむちうちになった場合に弁護士に依頼するメリット
交通事故でむちうちになった場合に、弁護士に依頼することには、以下の3つのメリットがあります。
弁護士基準で慰謝料を算出してもらえる
弁護士基準を使って慰謝料を算出してもらえるので、自力で示談交渉するよりも慰謝料が高額になるでしょう。
弁護士基準なら、自賠責基準や任意保険基準の2倍~3倍の金額を請求できるとされています。
慰謝料の大幅増額を狙えるので、相応の慰謝料を請求したいと考えている方は弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士費用がかからない可能性がある
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用がかからない可能性があります。
弁護士費用特約では、弁護士への相談料を10万円まで、依頼にかかる費用を300万円まで保険会社が代わりに負担してくれます。
弁護士に依頼すると高額な費用がかかるため、相談できずにいる方も多いでしょう。
その場合、まずは加入している自動車保険に弁護士費用特約がついているかチェックし、付帯していれば利用するのがおすすめです。
また、自分が加入していなくても、家族の自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、利用できる可能性があります。
適正な過失割合を判断してもらえる
相手方の保険会社から提示された過失割合が適正かどうかを判断してもらえるのも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。
慰謝料の金額は過失割合によって決まるため、被害者に過失割合がついてしまうとその分受け取れる慰謝料が少なくなります。
このため、保険会社は被害者の過失割合を高めに提示して、支払う慰謝料を抑えようとします。
しかし、示談交渉を初めておこなう方にとって、提示された過失割合が適正なのかどうか判断するのは難しいところです。
弁護士であれば、事故の状況を考慮したうえでどの程度の過失割合が適切なのか判断でき、その根拠を論理的に説明できます。
当初提示された過失割合が不当だった場合、弁護士が交渉することで正しい過失割合に訂正してもらえる可能性があるのです。
まとめ|交通事故によるむちうちの慰謝料請求は弁護士に相談
交通事故によるむちうちの慰謝料請求では、保険会社への対応、後遺障害等級認定の申請、示談交渉など、やるべきことが非常に多くあります。
しかし、どれも相応の知識が必要なので、自力で円滑に進めるのはかなり難しいでしょう。
交通事故後の総合的なサポートを受けたい方や、示談交渉を成功させて適切な慰謝料を受け取りたいと考えている方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の申請のサポート、示談交渉の代行などを任せられます。
また、法律の専門家である弁護士に一任すれば、納得できる慰謝料を支払ってもらえる可能性が高くなるでしょう。
交通事故後の対応や慰謝料請求について少しでも不安があるなら、「ベンナビ交通事故」を利用して、ぜひ弁護士に相談してみてください。