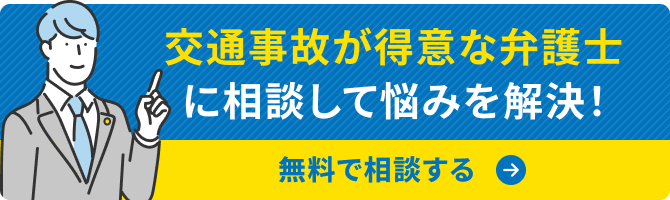交通事故に遭ったとき、「相手からの慰謝料はいくら支払われるのだろう」と心配になることでしょう。
慰謝料とは、交通事故に遭ったときに被害者が被った精神的苦痛を填補する目的で相手方保険会社や加害者から支払われる「謝罪金」のようなものです。
本来、慰謝料額は被害者が負った精神的苦痛の大きさを考慮して決めるものですが、交通事故においてはある程度決まった基準にしたがって支払われます。
「実際の交通事故で被害者が慰謝料をいくらもらったのか」なども知ることで、自分の場合の慰謝料額の目安をつかむことにもつながるでしょう。
本記事では、交通事故の慰謝料相場や実際の獲得事例、慰謝料増額のポイントなどを解説します。
交通事故の慰謝料の種類と相場
交通事故の慰謝料には以下のような3種類の算出方法があり、どの計算方法を参考にするかによって金額が異なります。
| 自賠責基準 | 自賠責保険で用いられる計算基準で、最も低額となる |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が定める計算基準で、中間の金額になりやすい |
| 弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる計算基準で、最も高額になりやすい |
基本的に自賠責保険のみ加入している場合は自賠責基準、任意保険に加入している場合は任意保険基準、弁護士に対応を依頼する場合は弁護士基準が適用されます。
また、交通事故の慰謝料は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類あり、被害状況に応じて請求できるものが異なります。
ここでは、計算基準ごとの各慰謝料の目安などを解説します。
入通院慰謝料|入通院した場合に請求可能
入通院慰謝料とは、交通事故によって通院・入院した場合に請求できる慰謝料です。
通院した場合・入院した場合の慰謝料の目安はそれぞれ以下のとおりです。
通院した場合
まず、通院のみのケースをみていきましょう。
なお、1ヵ月ごとの通院日数は10日と仮定して計算しています。
| 通院期間 | 自賠責基準 (※1) | 任意保険基準 (推定) | 弁護士基準 (※2) |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月間 | 8万6,000円 (8万4,000円) | 12万6,000円 | 28万円 (19万円) |
| 2ヵ月間 | 17万2,000円 (16万8,000円) | 25万2,000円 | 52万円 (36万円) |
| 3ヵ月間 | 25万8,000円 (25万2,000円) | 37万8,000円 | 73万円 (53万円) |
| 4ヵ月間 | 34万4,000円 (33万6,000円) | 47万8,000円 | 90万円 (67 万円) |
| 5ヵ月間 | 43万円 (42万円) | 56万8,000円 | 105万円 (79万円) |
| 6ヵ月間 | 51万6,000円 (50万4,000円) | 64万2,000円 | 116万円 (89万円) |
※1:()内は2020年3月31日以前に起きた事故の慰謝料です。
※2:()内はむちうち症などの他覚的所見がない負傷での慰謝料です。
入院した場合
次に、入院した場合をみてみましょう。
| 入院期間 | 自賠責基準 (※1) | 任意保険基準 (推定) | 弁護士基準 (※2) |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月間 | 12万9,000円 (12万6,000円) | 25万2,000円 | 53万円 (35万円) |
| 2ヵ月間 | 25万8,000円 (25万2,000円) | 50万4,000円 | 101万円 (66万円) |
| 3ヵ月間 | 38万7,000円 (37万8,000円) | 75万6,000円 | 145万円 (92万円) |
| 4ヵ月間 | 51万6,000円 (50万4,000円) | 95万8,000円 | 184万円 (116 万円) |
| 5ヵ月間 | 64万5,000円 (63万円) | 104万7,000円 | 217万円 (135万円) |
| 6ヵ月間 | 77万4,000円 (75万6,000円) | 113万4,000円 | 244万円 (152万円) |
※1:()内は2020年3月31日以前に起きた事故の慰謝料です。
※2:()内はむちうち症などの他覚的所見がない負傷での慰謝料です。
後遺障害慰謝料|後遺障害が残った場合に請求可能
後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺症が残って等級認定された場合に請求できる慰謝料です。
後遺障害は、症状の重さなどによって1級から14級までの等級に分けられています。
以下のとおり、第1級に近づくほど症状が重く、慰謝料も高額になります。
| 等級 | 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) | 任意保険基準 (推定) | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 1,600万円程度 | 2,800万円 |
| 第2級 | 998万円 (958万円) | 1,300万円程度 | 2,370万円 |
| 第3級 | 861万円 (829万円) | 1,100万円程度 | 1,990万円 |
| 第4級 | 737万円 (712万円) | 900万円程度 | 1,670万円 |
| 第5級 | 618万円 (599万円) | 750万円程度 | 1,400万円 |
| 第6級 | 512万円 (498万円) | 600万円程度 | 1,180万円 |
| 第7級 | 419万円 (409万円) | 500万円程度 | 1,000万円 |
| 第8級 | 331万円 (324万円) | 400万円程度 | 830万円 |
| 第9級 | 249万円 (245万円) | 300万円程度 | 690万円 |
| 第10級 | 190万円 (187万円) | 200万円程度 | 550万円 |
| 第11級 | 136万円 (135万円) | 150万円程度 | 420万円 |
| 第12級 | 94万円 (93万円) | 100万円程度 | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
死亡慰謝料|被害者が死亡した場合に請求可能
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料です。
まず、自賠責基準の場合は以下のように算出します。
| 請求する要項 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 死者本人に対する慰謝料 | 400万円 (2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円) |
| 死亡者に扶養されていた場合(※) | 200万円 |
| 慰謝料を請求する遺族が1人の場合 | 550万円 |
| 慰謝料を請求する遺族が2人の場合 | 650万円 |
| 慰謝料を請求する遺族が3人の場合 | 750万円 |
※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。
(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)
次に、任意保険基準・弁護士基準の相場は以下のとおりです。
| 死亡者の立場 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 1,500万円~2,000万円 | 2,800万円 |
| 配偶者・母親 | 1,500万円~2,000万円 | 2,500万円 |
| 上記以外 | 1,200万円~1,500万円 | 2,000万円~2,500万円 |
※死亡者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した額
このように、交通事故の被害状況や適用される計算基準などによって、慰謝料額には大きな差があります。
弁護士に慰謝料請求を依頼して弁護士基準が適用されることで、当初の提示額から2倍以上増額できる場合もあります。
交通事故の慰謝料はいくらもらった?5つの事例を解説
ここでは、当社が運営する「ベンナビ交通事故」に掲載している弁護士の解決事例を紹介します。
1.パートを辞めた直後の専業主婦が約100万円獲得できたケース
被害者は主婦で、まだ主治医からは「治療を続けたほうがよい」と勧められていたにもかかわらず、相手保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けてしまったという事例です。
このケースでは、依頼者本人も治療の継続を希望しており、弁護士が間に入ることになりました。
依頼を受けた弁護士が主治医の意見を基に相手保険会社と交渉をしたところ、3ヵ月の治療継続が認められました。
当時の被害者はパートを辞めたばかりでしたが、主婦の休業損害(主婦休損)なども認められて50万円ほどの慰謝料増額もでき、約100万円の損害賠償金を獲得しました。
2.自転車事故で骨折して約150万円獲得できたケース
交差点で自転車同士が衝突事故を起こしたという事例です。
この事例では、加害者側が自分の非を認めずに「被害者側に過失がある」と主張を続けていました。
そこで、依頼を受けた弁護士が間に入り、刑事記録を取り寄せて事故現場に足を運ぶなどして事故状況を調査して交渉しました。
その結果、最終的には当初の3倍を超える金額で解決でき、慰謝料を含めて約150万円の賠償金を獲得しました。
骨折の場合、後遺障害が認められて慰謝料が高額になる可能性があります。
例えば「骨折で後遺障害等級の申請をしたところ後遺障害10級が認定され、最終的に2,600万円以上の賠償金が支払われた」というようなケースもあります。
3.むちうちで後遺障害14級が認定されて約400万円獲得できたケース
被害者が運転中に信号待ちをしていたところ、前方不注意の乗用車に追突されてしまったという事例です。
被害者は、事故発生直後から整形外科に3日に1回の頻度で通院していましたが、まだ首と腰に痛みがあるにもかかわらず、相手保険会社から治療費打ち切りの打診を受けてしまいました。
そこで、依頼を受けた弁護士が間に入り、まずは後遺障害等級認定の申請をしました。
後遺障害等級の認定を受けるうえで被害者に必要な検査方法などを伝え、適切な書類を渡して主治医に記載してもらうことで、被害者は後遺障害等級14級9号の認定を受け、併合14級が認められました。
その結果、当初保険会社が提示した慰謝料額から6.5倍以上の増額に成功し、慰謝料を含めて約400万円の賠償金を獲得しました。
4.被害者が死亡して約2,500万円獲得できたケース
被害者が歩道を歩いている際、駐車場からバック走行してきた車両に轢かれて亡くなったという事例です。
この事例では、被害者遺族が事故直後から弁護士に依頼し、弁護士によって損害賠償請求に関するアドバイスやサポートなどがおこなわれました。
依頼を受けた弁護士が相手保険会社とやり取りをした結果、弁護士基準での慰謝料請求なども認められ、最終的には慰謝料を含めて約2,500万円の賠償金を獲得しました。
5.高次脳機能障害で後遺障害2級が認定されて約5,000万円獲得できたケース
被害者が横断歩道を歩行中、右折してきた加害者の車両と衝突したという事例です。
この事例では、交通事故によって被害者が高次脳機能障害を負い、後遺障害3級の認定を受けていました。
しかし、依頼を受けた弁護士が新たな証拠などを準備して異議申立てをおこなったことで、異議が認められて2級に上がりました。
その後、相手保険会社との交渉などを進めた結果、当初の提示額は約600万円でしたが、最終的には慰謝料を含めて約5,000万円の賠償金を獲得しました。
交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料請求のポイント
けがが軽傷で済んだとしても、交通事故で被害を受けた事実は変わらないため、慰謝料が支払われるケースもあります。
以下では、交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料相場や、請求する際の注意点などについて解説します。
軽傷を負った場合の慰謝料相場
交通事故のけがが軽傷でも、慰謝料をもらえるケースはあります。
金額の目安としては以下のとおりです。
| 症状の程度 | 慰謝料相場 |
|---|---|
| 完治まで1週間程度の軽傷 | 5万円程度 |
| 完治まで1ヵ月~3ヵ月程度の捻挫 | 1ヵ月程度の通院の場合:19万円程度 3ヵ月程度の通院の場合:50万円程度 |
| 完治まで2週間~1ヵ月程度の打撲 | 2週間程度の通院の場合:10万円程度 1ヵ月程度の通院の場合:19万円程度 |
慰謝料請求する際の注意点
たとえけがの程度が軽い場合でも、必ず事故後は警察を呼びましょう。
交通事故が起きた際は通報するのが道路交通法上の義務であり、交通事故とけがの関係性を裏付ける証拠なども残しておく必要があるからです。
なお、実際のけがの重さに見合わない額の慰謝料請求は避けるべきでしょう。
軽い打撲程度であるにもかかわらず50万円請求したりすると、加害者との金銭トラブルに発展するかもしれません。
慰謝料は交通事故による精神的苦痛などに対して支払われるものであり、その金額はけがの深刻さに比例します。
すぐに治って傷も残らない程度のけがであれば、あまり多くの慰謝料獲得は期待できないでしょう。
交通事故で慰謝料を増額するためのポイント
交通事故で慰謝料請求をする場合には、交通事故の証拠を記録して相手の主張には簡単に応じないようにしましょう。
以下では、交通事故での慰謝料を増額するために気を付けるべきポイントを5つ解説します。
1.事故後はすみやかに医師の診断を受ける
交通事故でけがを負ったら、けがの程度に関係なくすぐに病院で医師の診断を受けましょう。
軽傷だからといって診断を受けないと、「交通事故で負ったけがではない」などと相手保険会社から言われる可能性があります。
また、交通事故から受診までに期間が空いてしまうと、慰謝料だけでなく治療費の請求なども難しくなります。
なお、むちうちなどの症状が出ている場合には、整骨院ではなく必ず整形外科の病院を受診しましょう。
後遺障害等級認定を申請する場合、整骨院ではなく医師の診断や診療経過が重要となります。
整骨院に通った方の中には、むちうちの症状があるにもかかわらず、後遺障害等級の認定を受けられずに慰謝料の額が大幅に下がってしまったケースもあります。
たとえ軽傷の場合でもすぐに医師の診断を受けて、むちうちなどの症状がある場合は整骨院ではなく整形外科を受診しましょう。
2.相手方が提示する示談内容には安易に応じない
交通事故で一度示談に応じてしまうと、基本的にあとから追加で賠償金を請求したりすることはできなくなります。
したがって、相手方の提示内容に納得できない場合や、後遺障害等級認定の申請手続きをおこなう場合などは、相手方から示談を急かされたりしても安易に応じないようにしましょう。
3.治療費打ち切りを告げられても自己判断で治療を止めない
なかには、けがの治療を続けている最中に、相手保険会社から治療費の打ち切りを打診される場合もあります。
しかし、まだ痛みなどが残っているのであれば、自己判断で治療を止めたりするのは避けましょう。
相手保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合には、まず主治医に治療を継続するべきか相談しましょう。
そのうえで「まだ治療を継続するべき」という判断がなされた場合には治療を続け、相手保険会社とのやり取りについては弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
4.被害者請求で後遺障害等級認定の申請をする
後遺障害等級認定の申請方法は、以下の2つがあります。
| 事前認定 | 相手保険会社に手続きを一任する方法 |
|---|---|
| 被害者請求 | 被害者自身が手続きをおこなう方法 |
事前認定では、相手保険会社が主体となって書類などを集めますが、等級認定のために積極的に対応してくれるわけではありません。
一方、被害者請求であれば必要だと思う書類を一通り集めたうえで申請できます。
「事前認定では非該当と判断されたが、自分で書類を集めて再度申請したら等級認定された」というようなケースもあります。
5.弁護士に示談交渉を依頼する
交通事故で納得のいく金額を受け取るためには、ある程度の法律知識や交渉経験などが必要になります。
弁護士であれば依頼者の代理人として対応してくれて、知識やノウハウなどを活かしてスムーズな示談成立や慰謝料の増額などが望めます。
また、後遺障害の被害者請求などの事故後手続きも一任でき、交通事故被害者にとって心強い味方になるでしょう。
交通事故で慰謝料請求するなら弁護士がおすすめ
交通事故の被害者になった場合は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
ここでは、交通事故トラブルを弁護士に相談・依頼するメリットを4つ紹介します。
1.交通事故後の適切な対応方法をアドバイスしてくれる
弁護士に相談すると、けがの通院中などでも状況に適したアドバイスが受けられます。
例えば「週にどれくらい病院に通ったらよいのか」「整骨院は利用するべきなのか」など、事故後はさまざまな疑問が湧くでしょう。
弁護士にアドバイスしてもらうことで、適切に事故後対応を進めることができます。
2.症状に適した後遺障害等級の獲得が望める
弁護士であれば、後遺障害申請の手続きを一任することができます。
特にむちうちのようなレントゲンにも写らないけがの場合、後遺障害として等級認定を受けるのは難易度が高いでしょう。
弁護士に依頼すれば、後遺障害認定を受けるためにどのような資料が必要か判断して集めてくれて、場合によっては主治医に対して後遺障害診断書の修正や書き直しなどを求めてくれることもあります。
このような弁護士によるサポートを受けることで、症状に適した後遺障害等級の獲得が望めます。
3.有利な過失割合での示談成立が期待できる
交通事故の場合、当事者双方の過失割合について揉めるケースもあります。
過失割合については過去の裁判例なども参考にしたうえで、基本的には話し合いによって決定します。
自身の過失割合が大きいほど獲得できる損害賠償額は減ってしまうため、安易に妥協せずに話し合いを進める必要があります。
弁護士であれば過失割合の交渉対応なども依頼でき、相手方の主張する過失割合が妥当ではない場合は、裁判例などをもとに的確に主張してくれます。
なかには、当初は相手保険会社が「被害者側にも過失がある」と主張していたところ、弁護士が間に入ったことで過失割合が10対0になったという事例などもあります。
4.正確な損害賠償額を算定してくれる
基本的に示談成立後の内容変更は認められないため、損害賠償請求する際は請求漏れなどがないように注意する必要があります。
交通事故の加害者に請求できる項目は被害状況によって異なり、一例としては慰謝料・治療費・入院雑費・休業損害・後遺障害逸失利益などがあります。
弁護士であれば、被害者がどのような損害を負ったのか正確に算定してくれて、安心して請求対応を進めることができます。
まとめ|交通事故で慰謝料請求する際は弁護士に相談を
交通事故における慰謝料は、修理代金や治療費などのように客観的な資料に基づいて算出されるものではないため、場合によっては相手保険会社と揉める可能性があります。
相手方の提示内容に少しでも疑問を感じている場合や、自力での事故対応に不安を感じている場合などは、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
当社が運営する「ベンナビ交通事故」では、交通事故対応が得意な全国の弁護士を掲載しており、慰謝料増額や早期解決に向けた的確なサポートが望めます。
初回相談無料の法律事務所もあり、とりあえず相談だけしてみるということも可能ですので、まずは気軽に利用してみましょう。