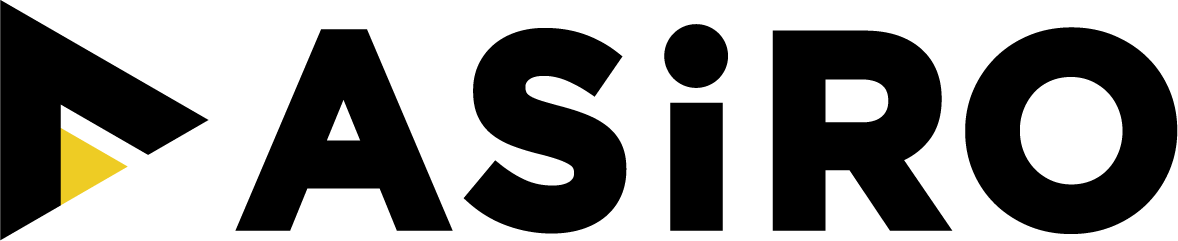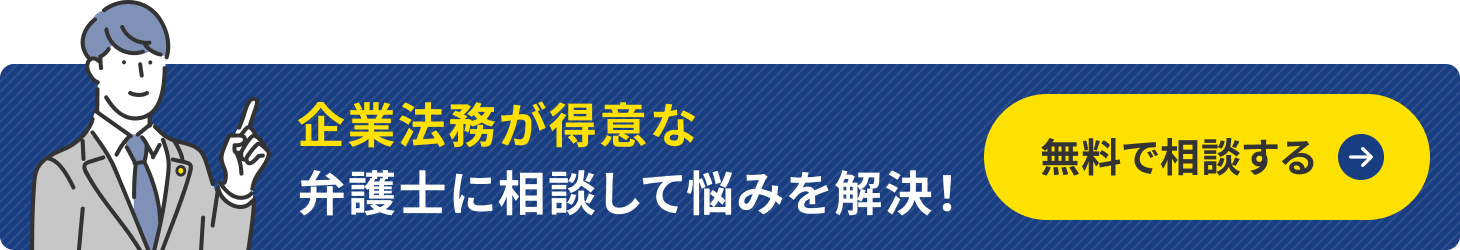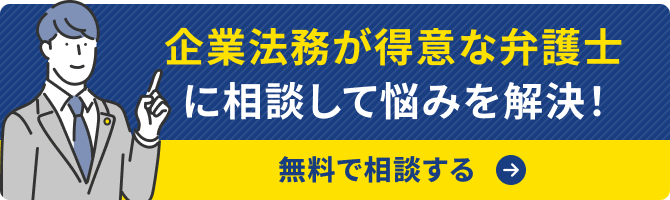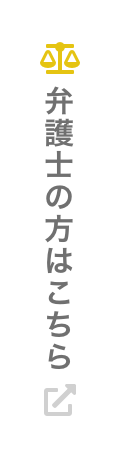毎年のように行われる法改正に対応するだけでなく、社内の人事制度を変更するにあたって、就業規則の内容を見直す必要が生じることはあるでしょう。
就業規則の内容はそこで働く従業員が従うべき義務ばかりを定めたものではなく、従業員の権利についても定められています。
そのようなものを会社の一存で変更することはできるのでしょうか。
変更できるのであれば、どれだけ従業員に不利益な内容に変更されても許されるのでしょうか。
この記事では就業規則を変更する上での手順や注意点について解説します。
企業法務について弁護士を探す 電話相談・オンライン相談可・初回面談無料 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
就業規則を変更するための手順

就業規則を変更する前に、まずは法的に可能かどうかについて確認してみましょう。
労働契約法9条では、以下のように定められています。
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
と記されており、労働者と合意がなされないまま、会社が就業規則を変更することを禁じています。
労働者と合意しているのであれば、就業規則を変更することができます。
この点について、労働契約法10条では、以下のように定められています。
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
つまり、就業規則を変更する上では、
- 変更後の就業規則を周知すること
- 内容が合理的であること
上記の2つの要件を満たす必要があるということになります。
では、改めて変更の手順を確認してみましょう。
上述した労働契約法の要件も踏まえると、変更するためには以下の手順を経る必要があります(※法改正に対応するためであれば、必ずしも下記の手順に従う必要はありません)。
①変更点を社内で決定し、就業規則へ反映する
まずは就業規則のどの部分を変更するのか取りまとめます。
この段階で「何の必要性があって変更するのか?」を整理しておくとよいでしょう。
変更が認められるためには、合理的であることを要します。
単に「人件費をカットしたいから」「来期の業績見通しが悪そうだから」というだけでは合理性があるとはいえないため注意が必要です。
変更する部分が決まったら、実際に新しい条文案へ変更内容を反映します。
②変更届を作成する
変更した就業規則を届出る際には、どこを変更したのか明確に示すために変更届を就業規則と併せて提出することになります。
決まったフォーマットはありませんが、従業員に説明するためにも変更前と変更後の条文を対比できる表を作成しておくとスムーズです。
厚労省のサイトからは以下のような様式が公開されています。
【就業規則変更届のリンクはこちら】
③意見書を作成する
届出時には変更届に加え、新たに作成する時と同様に意見書の添付が必要になります。
労働者の過半数を代表する者から変更点について意見を聴取し、それを書面にまとめます。
なお、変更に際して同意を得る必要はありませんが、不利益に労働条件を変更する場合はこのタイミングで変更点について説明し、同意を得ておいたほうがよいでしょう。
この点については詳しく後述します。
意見書の内容は意見を聴取した日付、過半数代表者の意見、過半数代表者の署名捺印が1枚にまとまっていれば十分です。
変更届と同様、決まったフォーマットはありませんが、厚労省のサイトからは以下の様式をダウンロードすることが可能です。
【意見書のリンクはこちら】
④労働基準監督署へ届け出る
変更した就業規則を、変更届と意見書を添えて所轄労働基準監督署へ届け出ます。
形式が整っていれば、明らかな法違反がない限り就業規則は問題なく受理されます。
変更内容が合理的かどうかの判断は労働基準監督署が行うわけではありません。
あくまでも労働契約法は「民事的なルール」について定められたものであるからです。
就業規則の内容が労働基準法で定められる基準に達していない場合、その場で受理されないことも考えられますが、労働契約法に罰則はないため労働契約法の定めを理由として就業規則が受理されない、内容を変更させられるというようなことはありません。
⑤変更した就業規則を社内で周知する
最後に、変更し終えた就業規則を社内で周知します。
上記のプロセスに沿って変更を進めていれば問題ありませんが、最終的にどこをどう変更したのかがわかるように変更届と変更後の就業規則を併せて周知したほうが、変更点がスムーズに周知されるでしょう。
周知をする上では必ずしも労働基準監督署に届け出た就業規則を周知する必要はないので、④と⑤は順序が逆になっても差し支えありません。
変更は事業場ごとに必要

自社に事務所や支店が複数ある場合には「その場所ごと」に変更手続きを行う必要があります。
ただし、内容が同一であれば本社で一括届出をすることもできます。
全社で同じ内容の就業規則にする必要はないため、本社では変更するけれども支店では変更しない、もしくは別の内容に変更することも可能です。
就業規則変更に関する判例
ここでは、法令以外に就業規則の変更に関する判例についてもメジャーな論点を押さえておきましょう。
秋北バス事件
会社が就業規則を変更して定年制度を改正した際、それまで定年制の適用のなかった原告がその対象となったため、解雇通知の無効を訴えた事件です。
最高裁は、「新たな就業規則の作成又は変更によって労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」と判示しています。
つまり、変更した就業規則が合理的な内容であれば、その内容に同意しない労働者がいたとしても新たな就業規則の適用を免れることはできないということです。
| 裁判年月日 昭和43年12月25日 裁判所名 最高裁大法廷 裁判区分 判決 事件番号 昭40(オ)145号 事件名 就業規則の改正無効確認請求事件 〔秋北バス事件・上告審〕 裁判結果 上告棄却 文献番号 1968WLJPCA12250014 |
大曲市農業協同組合事件
農協の合併により新たな就業規則が作成されたものの、内容のうち退職金規定が合併前の農協で定められていたものよりも不利益な内容とされたことを受け、退職金の差額支払いを求めて提訴した事件です。
最高裁は、結論としては退職金規定の変更は有効であると判示したものの、「就業規則の内容が合理的なものと認められるためには、その就業規則の作成又は変更が、その必要性と内容の両面から見て、それによって従業員に及ぶ不利益の程度を考慮しても、なお法的規範性を是認できるだけの合理性が必要である」と述べており、就業規則の内容だけでなく変更の必要性についても合理性が求められるとしています。
| 裁判年月日 昭和63年 2月16日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決 事件番号 昭60(オ)104号 事件名 退職金請求事件 〔大曲市農業協同組合事件・上告審〕 裁判結果 破棄自判 文献番号 1988WLJPCA02161050 |
実際に変更する場合の注意点
上述した内容を踏まえ、実際に就業規則を変更する場合の注意点を確認しましょう。
就業規則の内容を労働者の有利に変更するのか、労働者の不利に変更するのかで大きく異なります。
労働者の有利に変更する場合
有利に変更する上では法律上特にハードルとなる問題はありません。
ただし注意すべきなのは、一度有利に変更してしまえば簡単には元に戻せないということです。
有利に変更する具体的な事例としては、退職金制度や新たな手当の導入などが考えられます。
先を見据えてその制度の導入に無理がないかどうかを考えた上で検討するとよいでしょう。
労働者の不利に変更する場合
一方、労働者にとって不利な内容に変更する場合は、労働契約法が要請する「合理性」のハードルを越えなければなりません。
先に述べた通り、労働契約法に反したとして労働基準監督署から指導を受けることはありませんが、労働者とトラブルになり訴訟に発展した際、変更した就業規則の合理性が認められなければ、変更後の就業規則は無効とされ、遡って従前の就業規則で定めた内容を保証しなければなりません。
何をもって合理的と判断するかは個別事例で判断されることになるため、一概に基準を示すことは難しいですが、労働者が変更後の就業規則について合意しているのであれば、そもそも法的な合理性が問題になることはありません。
必要なことは、労働者への納得のいく説明となるでしょう。
まずは上述した変更プロセスを経ることが求められますが、過半数代表者が意見書に就業規則の変更について同意したからといって、必ずしも全労働者が同意しているとは限らないことに注意が必要です。
実務上の留意点としては、個別の従業員に対して就業規則を変更する必要性、受ける不利益の程度、代替措置などを説明した上で、可能であれば全員から就業規則の変更に同意する旨を書面で受理しておくとよいでしょう。
必要に応じて、変更の経緯や変更後の就業規則に合理性があるかどうか、弁護士や社会保険労務士などの専門家の判断を仰ぐことも検討しましょう。
まとめ
以上、就業規則を変更する上での注意点について解説しました。
就業規則は後で変更することは可能ですが、原則として合理的な理由なしに労働者にとって不利な内容に変更することはできません。
就業規則は会社が自由に変更できるものではないということがわかりました。
やむを得ず変更する場合は、上述の注意点や判例などを参考に、従業員とトラブルにならないよう厳格なプロセスを経た上で変更するとよいでしょう。
企業法務について弁護士を探す 電話相談・オンライン相談可・初回面談無料 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |