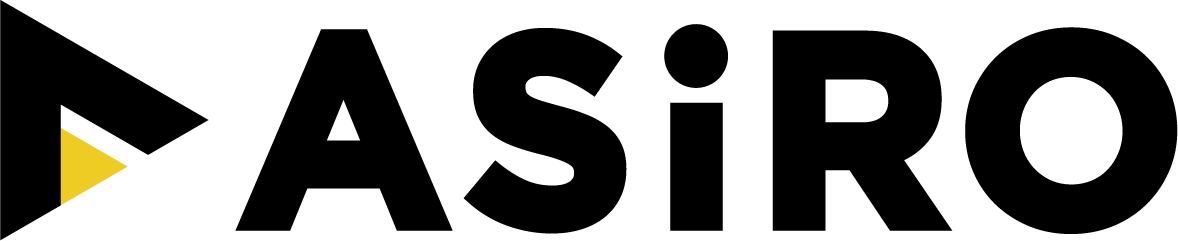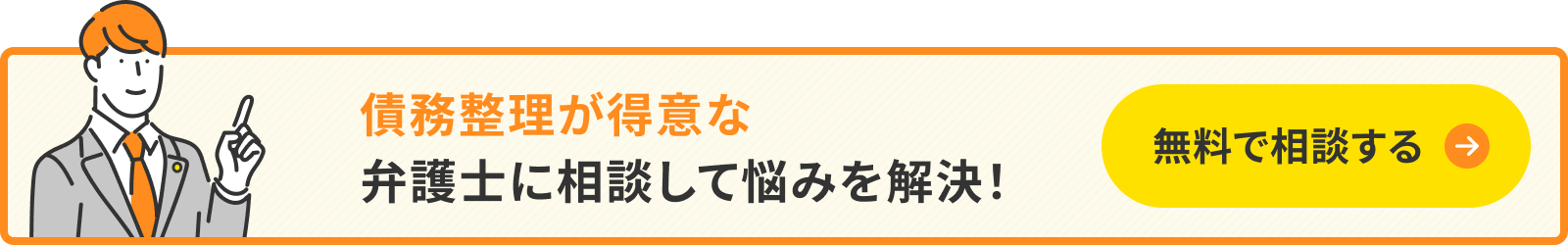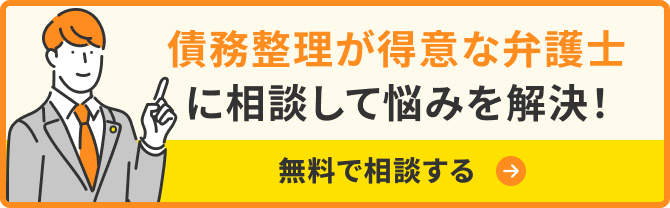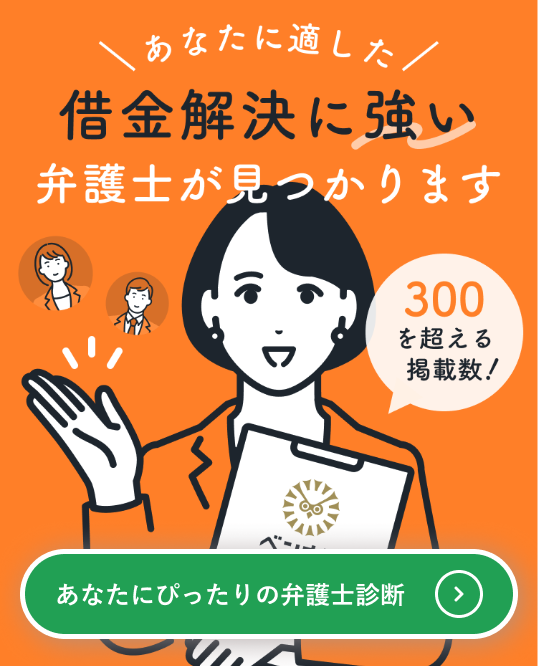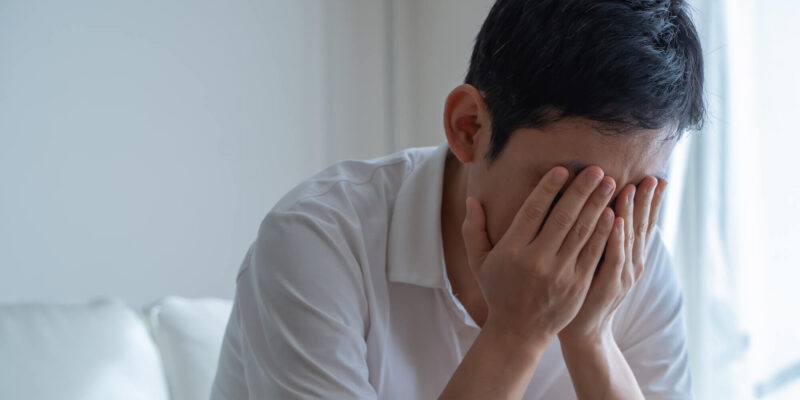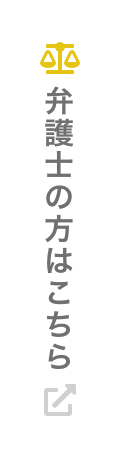- 経済状況が苦しく、家賃を支払えない……
- このまま支払えない状態が続けば、強制退去させられてしまうのだろうか?
不安な気持ちで過ごしている方もいるかもしれません。
しかし、結論からいうと家賃を1ヵ月滞納しただけで強制退去させられることはありません。
大家(オーナー)が強制退去に向けて行動を始めるのは、おおむね2ヵ月以上の滞納があり、かつ信頼関係が壊れてしまってからです。
また、実際に強制退去に至るまでには、明け渡し請求訴訟などの法的手続きを経る必要があります。
とはいえ、いずれ強制退去をさせられる可能性はありますし、ほかにもリスクがあるため、早めに対策を講じたほうがよいでしょう。
本記事では、家賃滞納で強制退去となる条件や、強制退去までの流れを紹介するほか、強制退去を回避するための方法などについて解説します。
家賃滞納が続くと、遅延損害金が発生する・連帯保証人に支払督促・給料や家財などの財産を差し押さえられるなどのリスクがあります。
そのため、借金を抱えて家賃を支払えない方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが望めるからです。
- あなたの状況に適した借金の解決策をアドバイスしてくれる
- 債務整理の手続きを代わりにおこなってくれる
- 大家や管理会社と代わりに交渉してくれる など
家賃を滞納し続けていても状況の改善は見込めません。
初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずは無料相談してみて今後どのような対応を取るべきかアドバイスをもらいましょう。

無料相談できる弁護士一覧
家賃滞納で強制退去になる条件
家賃を滞納したからといって、直ちに強制退去させられるわけではありません。
多くの場合、大家(オーナー)が強制退去に向けて行動を開始する前には、以下の4つの条件を満たすことが必要です。
1.2ヵ月以上の家賃滞納が続いていること
賃貸借契約書には通常、違約による解除条項が定められています。
契約解除の条件としては、一定期間の家賃滞納が続いていることであり、過去の判例に基づいて、2ヵ月以上の滞納を目安としていることが多いでしょう。
この背景には、敷金や礼金を支払う物件では、1ヵ月程度の滞納であれば大家(オーナー)が実質的に受ける損害が軽微と判断されることなどが挙げられます。
2.内容証明郵便で定められた期間を過ぎている
内容証明郵便とは、大家(オーナー)が借主に対して家賃滞納の支払いについて公式に請求するためのものです。
この郵便は、家賃滞納から一定の期間が経過したあとに送付される書類であり、通常は支払い期限が明記されています。
もし、この記載されている期間を過ぎても支払いがなければ、滞納している事実が明確になるとともに、契約解除や法的手続きの際の証拠として機能します。
3.支払いの意思がないとみなされる
借主が滞納家賃の支払い請求を無視したり、対応や連絡を全くおこなわない場合、支払い意思がないとみなされる可能性が高くなります。
支払いの意思がないとみなされると、大家(オーナー)が賃貸者契約の解除を進める正当な理由になり得ます。
4.貸主・借主間の信頼関係が喪失している
通常、大家(オーナー)が借主との賃貸借契約を一方的に解除することは認められていません。
そして、賃貸借契約の解除が有効であると認められるケースは、貸主と借主間の信頼関係が破壊されていると判断された場合に限られます。
また、多くの判例においては、3ヵ月以上の家賃滞納がある場合に、信頼関係が破壊されたとみなされることが多いとされています。
強制退去までは「裁判」が必須
家賃滞納で強制退去となるまでには、必ず裁判を経る必要があります。
これは、大家(オーナー)が借主に対して、一方的に退去を命じることができないからです。
裁判所では、家賃滞納の期間や、支払い意思の有無、そして貸主と借主の信頼関係が破壊されているかどうかなどを総合的に判断します。
その結果、裁判所が賃貸借契約の解除を認めた場合、借主に建物の明け渡し命令が下されるのです。
そして、それでも自主的に退去しない場合、最終的に強制退去が実施されることになります。
家賃滞納から強制退去に至るまでには、このような裁判によるプロセスがあることを覚えておきましょう。
家賃滞納から強制退去までの流れ
自身の今の状況を知るためにも、強制退去に至るまでの流れを知っておくことが有効です。
ここでは、家賃滞納から強制退去に至るまでの一般的な流れを紹介します。
1.大家(オーナー)から督促を受ける|滞納から1ヵ月以内
家賃を滞納すると、通常1ヵ月以内に大家(オーナー)から督促があるでしょう。
督促の方法は、最初は電話による場合がほとんどです。
2回~3回程度、電話での督促を受けても応じなければ、今度は督促状として書面で請求されます。
保証会社の場合はより厳しく督促を受ける
保証会社を利用している場合は、連帯保証人を立てている場合よりも厳しく督促を受けることになるでしょう。
電話や書面による督促の頻度は増え、自宅に訪問されて支払いを求められることもあるため注意が必要です。
2.連帯保証人へ督促される|滞納から1ヵ月〜2ヵ月程度
1ヵ月〜2ヵ月程度滞納してしまうと、連帯保証人へ督促されてしまいます。
連帯保証人への督促も電話や書面などで連絡されることが一般的です。
また、大家(オーナー)が法的手続きに則って強制退去を進めようとしている場合は、内容証明郵便で届く場合もあります。
3.内容証明郵便が届く|2ヵ月~3ヵ月程度
大家(オーナー)が法的手続きに則って強制退去を進めようとしている場合、督促状が内容証明郵便として送付される場合があります。
内容証明郵便には、差出日や文書の内容を法的に証明する力があり、督促をおこなっていることを正式に記録する方法として用いられます。
また、裁判においても証拠書類として認められるため、大家(オーナー)が強制退去という法的手続きを進めるうえで重要な役割を果たします。
4.契約解除通知が届く|滞納から3ヵ月〜6ヵ月程度
3ヵ月〜6ヵ月程度滞納してしまうと、次に契約解除通知が届きます。
契約解除通知とは、過去に締結した契約を解除する旨を通知するための書面です。
相手の意思表示という意味合いではありますが、解除事由があれば、契約解除が成立します。
家賃滞納をしている場合、それが解除事由となるため、この書面の到達によって賃貸借契約は解除とされます。
5.裁判所に明け渡し請求訴訟を起こされる|滞納から3ヵ月〜6ヵ月程度
契約解除通知によって契約が解除となれば、賃貸人は賃借人に対して、建物の明け渡し請求訴訟をおこなえる権利が発生します。
そのため、裁判所を通じた法的手段へと移行します。
大家(オーナー)は、裁判所に明け渡し請求訴訟を提起するでしょう。
また、建物の明け渡しだけでなく、滞納している家賃や遅延損害金の支払いも同時に求められる場合があります。
6.強制執行(強制退去)を命じられる|強制執行の申立てから1ヵ月~2ヵ月程度
大家(オーナー)が勝訴すれば強制執行が可能となります。
大家(オーナー)が強制執行を申し立てた場合、裁判所の執行官が強制執行(強制退去)をおこないます。
強制執行が申し立てられた場合、明け渡しの催告を経ます。
そして、催告後も占有を継続した場合には、明け渡しの断行として強制退去をさせられてしまうでしょう。
家賃滞納から強制退去させられたその後
家賃滞納による強制退去をさせられたあとは、住む家がなくなるだけではなく、さまざまな問題に直面します。
家賃滞納から強制退去させられたあと、どうなるのかについて見ていきましょう。
荷物が一定期間保管される
裁判所の執行官により運び出された荷物は、指定の場所に一定期間保管されます。(民事執行法第42条)
保管期間については法律で明確に規定されていませんが、通常は1ヵ月程度が目安となります。
この保管期間を過ぎても、賃借人が荷物を引き取りに来ない場合、裁判所や執行官の判断に基づいて、荷物が売却または破棄される可能性があります。
滞納家賃や強制執行の費用を請求される
続いて、滞納した家賃や強制執行の際にかかった費用について請求されます。
滞納した家賃については、遅延損害金と合わせて請求されることが多く、通常は賃貸借契約書に記載された利率で計算されます。
また、契約書に利率の記載がない場合には、法定利率(年14.6%が上限)が適用され、その範囲内で大家(オーナー)が自由に決めます。
一方、強制執行の費用については、部屋の広さや荷物の量によって変わってくるものの、おおむね以下の金額となります。
- 解錠技術者費用:1回約2万円~
- 荷物の運搬費用:ワンルームの場合で約10万円~
- 廃棄処分費用:約2万円~4万円
退去後に、これらの費用が追い打ちをかける形で請求されることになります。
給料などの財産が差し押さえられる
滞納家賃や強制執行の費用が支払えない場合には、その費用を回収するために給料などの財産が差し押さえられる可能性があります。
最低限の生活を保障するため、差し押さえ可能な金額には、法的な上限が定められています。
具体的には、手取り額の4分の1または手取り額が33万円を超える部分のいずれか低いほうです。
また、給料以外にも預貯金や自動車、不動産などの財産がある場合には、同様に差し押さえの対象となるでしょう。
次の家が借りにくくなる
滞納情報が信用情報機関に登録されることで、次の家が借りにくくなる可能性があります。
これは特に部屋を借りる際に保証会社を利用した場合に滞納情報が共有されることが多いためです。
その結果、次の部屋を借りる際の入居審査で不利に働き、物件の選択肢を狭めることになります。
なお、家賃滞納の情報は一般的に5年〜10年ほど記録として残ります。
そして、この記録は、次の家が借りにくくなるだけではなく、クレジットカードが発行できないなど生活自体に悪影響を及ぼす結果となる可能性があります。
家賃滞納者による強制退去を回避するための6つの方法
強制退去をさせられるのは、できるだけ避けたいものです。
ここでは、家賃を滞納してしまった方が強制退去を回避するための6つの方法を紹介します。
1.大家(オーナー)や管理会社に家賃の相談をする
まずは、大家(オーナー)や管理会社に家賃を支払えない旨を相談してみましょう。
強制退去の条件のひとつである、大家(オーナー)との信頼関係を維持するためにも、家賃を支払う意思を示すことが大切です。
家賃の支払いを待ってもらっても全額を用意できそうにない場合は、分割払いの相談をしたり、少額でも支払ったりするなど、信頼関係を維持するよう努めましょう。
2.家族など第三者からお金を借りる
第三者からお金を借りて、家賃を支払うのもひとつの方法です。
借りる相手は、家族などの身近な人がもっとも無難といえるでしょう。
友人などに借りると、あとになってトラブルになる可能性もあるため、避けるのが賢明です。
消費者金融から借りる方法もありますが、金利が高く、返済に苦労するリスクがあります。
消費者金融を検討する場合は、短期で返済できる場合に限ったほうがよいでしょう。
3.住居確保給付金制度を利用する
離職や廃業によって家賃を支払えないのであれば、住居確保給付金制度を利用できる可能性があります。
この制度は、以下の要件を満たす場合に、各自治体が定める額を上限として、家賃を原則3ヵ月間、状況に応じては最大9ヵ月分支給してもらえる制度です。
- 主たる生計維持者が離職・廃業してから2年以内である、または自身の責任や都合以外の原因で、離職・廃業と同程度まで収入が減少している
- 直近の世帯収入の合計が、基準額と家賃の合計額を超えていない(基準額とは、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1を指す)
- 世帯の預貯金合計額が、基準額の6ヵ月分を超えていない、かつ100万円を超えていない
- ハローワークなどに求職の申し込みをするなど、誠実かつ熱心に求職活動をおこなっている。自営業者の場合は事業再生のための活動でもよいこともある
各市区町村役場の福祉課で相談できるので、要件に当てはまる方は問い合わせてみるとよいでしょう。
4.失業手当や傷病手当を受け取る
予期せぬことが原因で、突然収入が断たれた場合は、国などから手当を受け取れる可能性があります。
たとえば、勤めていた会社が倒産したり、突然解雇されたりした場合は失業手当が受給できます。
支給が開始されるのは、7日間の待機期間後であるため、早めに手続きをおこなったほうがよいでしょう。
また、病気やけがで仕事を休まざるをえなくなった場合は、傷病手当金を受け取れる可能性があります。
なお、受給するには、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 業務外に原因のある病気やけがの療養のための休業であること
- 仕事に就けない状態であること
- 連続して3日間仕事を休まざるをえず、4日目以降も休職を余儀なくされていること
- 休業期間中の給与の支払いがないこと
受給要件を満たす場合は、全国健康保険協会に申請しましょう。
【参考元】
基本手当について|ハローワークインターネットサービス
病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
5.生活保護制度の利用を検討する
あらゆる努力をしても困窮状態から抜け出せない場合は、生活保護制度を利用するのもよいでしょう。
生活保護制度とは、困窮の度合いに応じて必要な保護を受けながら、自立へ向けて支援してもらえる制度です。
生活保護を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 生活のために利用していない土地や家屋などの資産を処分したり、預貯金を充当したりしても生活費が不足する
- 病気やけがなどの理由で働けない
- 給付金を受けられるほかの制度で利用できるものがなく、年金ももらえない
- 援助してくれる親族などの身内がいない
- 上記を満たし、月収が最低生活費を下回っている
生活保護を受けると、貯金や借金ができず、車の所持ができません。
そのため、申請する際には、これらのデメリットもよく検討しましょう。
6.弁護士に債務整理の相談をする
家賃にかぎらず、借金問題で苦しんでいるなら、弁護士に相談してみるのもおすすめです。
なぜなら、自身の状況に合った債務整理の方法を提案してくれるからです。
債務整理をすれば、無理なく返済できるようになったり、債務がなくなる可能性があります。
また、弁護士に依頼した場合は、債権者からの督促も止まるでしょう。
加えて、家賃トラブルの解決を依頼すれば、裁判手続きだけでなく、大家(オーナー)との交渉も代わりにおこなってもらえます。
これにより、精神的な負担が大きく軽減します。
なお、「相談に行きたくても、弁護士費用が心配……」という方もいるかもしれませんが、経済的に苦しい方でも弁護士に依頼する方法はあります。
その方法とは、法テラスの民事法律扶助制度を活用したり、分割払いに対応している法律事務所を探すというものです。
「ベンナビ債務整理」では、債務整理に強に強い弁護士を多数掲載しています。
また、「分割・後払い可能」「相談料無料」など、条件を絞ったうえで、法律事務所を探すことも可能です。
家賃が支払えなくて困っているなら、ぜひ「ベンナビ債務整理」を利用して、弁護士へ気軽に相談してください。
家賃滞納で債務整理した場合に起こること
家賃を滞納している場合、債務整理をするかどうかはよく検討したうえで決めたほうがよいでしょう。
なぜなら、メリットがある反面、デメリットも大きいからです。
ここでは、家賃滞納で債務整理した場合に起こることについて、紹介します。
1.滞納家賃の減額・免除ができる
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。
そして、どの方法を選択するかによって、滞納した家賃が減額されるのか、免除されるのかが異なります。
債務整理の方法と、それぞれの方法を選択した場合の影響は、以下のとおりです。
- 任意整理:場合によっては利息をカットしたうえで、残りの債務を3年〜5年かけて返済していく方法です。家賃滞納分は3年~5年(36回〜60回)で分割し、毎月無理のない範囲で返済していくことになります。
- 個人再生:裁判所の許可を得ることで、最大90%の債務を減らせる手続きです。裁判所が許可した返済計画に基づいて返済を進め、原則3年〜5年かけて返済します。
- 自己破産:裁判所に申立てをおこなって、免責決定を受けることで、全ての債務が免除されます。滞納していた家賃も全て免除されます。
2.立ち退きを要求される可能性が高まる
家賃を滞納している状態で債務整理をおこなえば、大家(オーナー)から立ち退きを要求される可能性が高まります。
なぜなら、入居者が債務整理をおこなうことで、大家(オーナー)は家賃をきちんと回収できなくなるからです。
これは大家(オーナー)にとって、損失でしかありません。
また、債務整理をおこなうことで信頼関係が破綻したとみなされるため、強制退去を求める要件を満たすことにもつながります。
滞納していた家賃の支払いを免れることができても、部屋から退去せざるをえないでしょう。
3.連帯保証人に対して家賃を請求される
債務整理をすると、連帯保証人に対して滞納家賃の一括請求をされてしまう可能性が高まります。
また、滞納家賃に遅延損害金が加算されるため、大きな金額になるケースもあります。
債務整理をおこなう場合は、連帯保証人にあらかじめ事情を説明しておきましょう。
また、連帯保証人に迷惑をかけたくなければ、滞納分の家賃を支払ったうえで、債務整理をするしかありません。
家賃滞納をした際の強制退去以外のリスク
家賃を滞納すると、強制退去させられる以外に、どのような不利益があるのでしょうか。
ここでは、家賃滞納によって起こり得るリスクについて説明します。
ブラックリストに記載される
連帯保証人を立てるのではなく、保証会社を利用して賃貸契約を締結した方の場合、家賃を滞納することで、ブラックリストに記載されます。
これは、信用情報に事故情報が登録されることを意味します。
信用情報とは、クレジットカードやローンの支払い状況などの取引情報のことです。
家賃を滞納して事故情報が記録されれば、返済能力に問題があるとして、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを申し込んだりする際に審査に落ちる可能性が高くなります。
また、返済状況によっては、利用中のクレジットカードが使えなくなることもあるでしょう。
事故情報は約5年間登録されます。
そのため、この期間は、クレジットカードの利用やローン契約ができなくなるため、注意しましょう。
遅延損害金が発生する
遅延損害金とは約束の期日までに支払いをしなかった場合に発生する、損害賠償金のことです。
その金額は、賃貸契約書に明記されていなければ、3%の法定利率で計算されます。
支払いの遅れた日数分が発生するため、長く滞納するほど遅延損害金の金額は高くなるでしょう。
家賃を支払うことさえ厳しい方にとって、これは、大きな負担となりかねません。
家賃を滞納してしまった場合は、できるだけ早めに対処するのが望ましいでしょう。
家賃滞納による強制退去についてよくある質問
家賃を支払えなくても、できるだけ強制退去は避けたいものです。
ほかにも「こんな場合はどうなるの?」「強制退去になるの?」などという疑問がある方もいるでしょう。
ここでは、家賃滞納と強制退去について、よくある質問とその回答について紹介します。
違法な取立てを受けている場合はどうなりますか?
違法な取立てなど、大家(オーナー)が法律に違反する行為をおこなっている場合、強制退去は認められません。
したがって、入居者が退去する必要もありません。
以下のような行為は、違法行為に該当する可能性が高いため、強制退去は認められないでしょう。
- 入居者の許可なく、勝手に部屋に入る
- 脅迫まがいの取立てをおこなう
- 勝手に部屋の鍵を交換する
- 入居者の荷物を勝手に家の外に出す
- 退去を強要する
大家(オーナー)がこのような違法行為をおこなった場合、直ちに立ち退く必要はありません。
またトラブルに発展しそうな場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
滞納分の家賃に敷金を充ててもらうことはできますか?
滞納した家賃に敷金を充当してもらうことはできません。
なぜなら、敷金を大家(オーナー)に預ける目的は、原則として退去時の原状回復に充てるためのものだからです。
入居者はその使途を決めることができないため、当然のことながら、滞納分の家賃に充てることはできません。
強制退去をさせられる条件は何ですか?
強制退去が認められるかどうかは、滞納した回数ではありません。
基本的には、以下の条件を満たすかどうかによります。
- 2ヵ月以上の家賃滞納が続いている
- 大家(オーナー)との信頼関係が破綻している
2回家賃を滞納したことがあっても、いずれも短期間で支払いをし、滞納が続いていないのであれば、退去させられることはありません。
また、過去に滞納をしたことがあっても、督促に応じて支払ってきたのであれば、オーナーとの信頼関係は維持できていると判断され、強制退去が認められる理由には当たりません。
強制退去になる前に夜逃げした場合、時効はありますか?
家賃にも消滅時効があり、その期限は5年と定められています。
しかし、大家(オーナー)から滞納家賃の支払いを求める訴訟を起こされれば、時効は中断します。
その場合の時効は、判決が下されてから10年です。
家賃の支払いが1ヵ月遅れたら退去させられますか?
家賃の支払いが1ヵ月遅れただけで、すぐに退去させられることはありません。
なぜなら、退去を強制するためには、貸主と借主の間にある信頼関係が破壊されていることを裁判所が認める必要があるからです。
家賃の支払いが1ヵ月遅れただけでは、信頼関係が破壊されたとみなされる可能性は低く、退去を強制されることは通常ありません。
さいごに|家賃が支払えない場合は弁護士に相談を
家賃を滞納しても、直ちに強制退去させられるわけではありません。
強制退去が認められるのは、2ヵ月以上の家賃滞納が続き、なおかつ大家(オーナー)との信頼関係が壊れていると判断される場合に限られます。
そのため、簡単に退去させられることはないでしょう。
しかし、だからといって、いつまでも支払わないわけにはいきません。
家賃を滞納すると、強制退去以外にもさまざまなリスクがあるからです。
どうしても家賃を支払えそうにない場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、強制退去を回避できるよう、相談者にとってベストな方法を提案してくれます。
したがって、精神的負担が、少しは軽減するはずです。
まずは無料相談を活用し、弁護士に相談してみましょう。

無料相談できる弁護士一覧