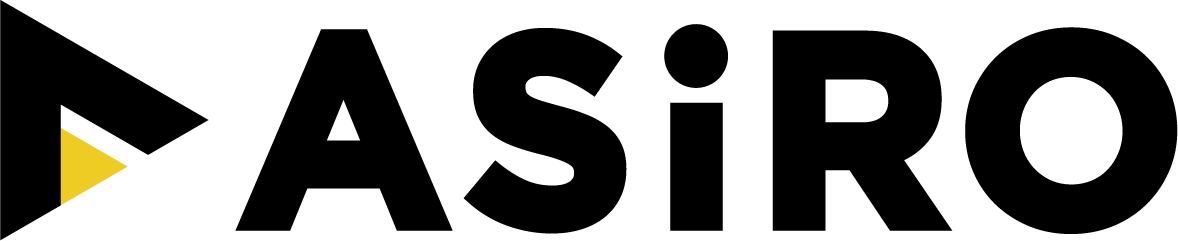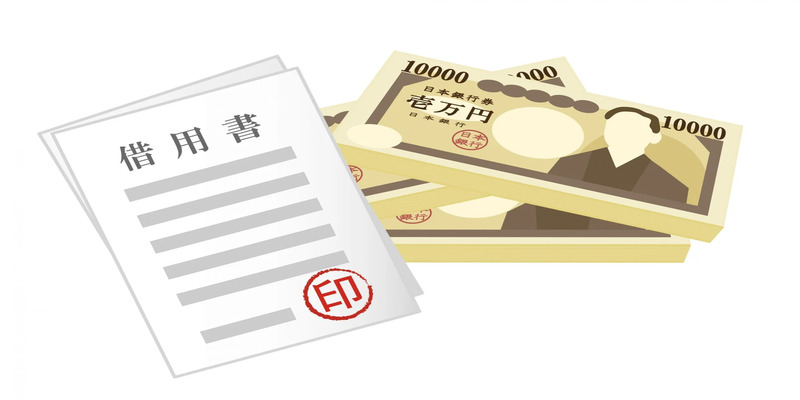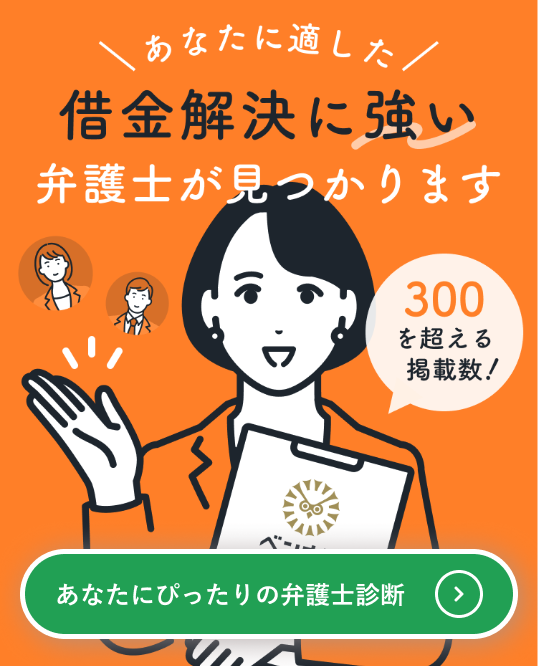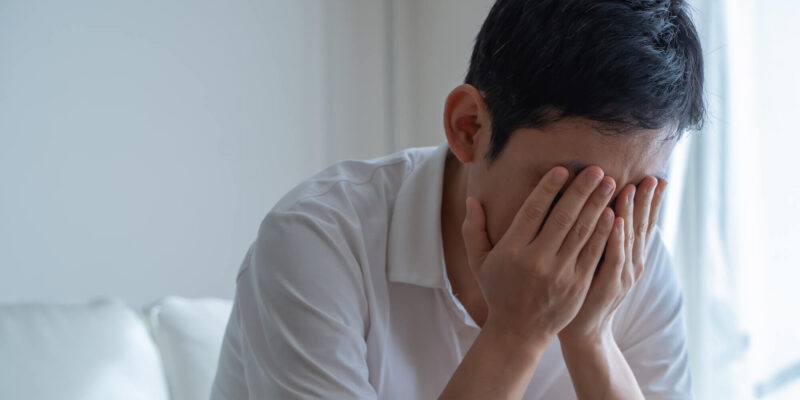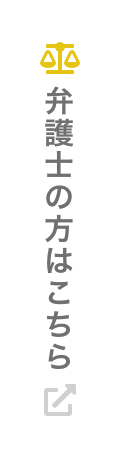借金には消滅時効が定められており、一定期間経って時効が成立すれば返済義務がなくなります。
しかし、時効の成立にはいくつかのルールがあり、場合によっては自分が知らない間に時効期間が延長(更新)されてしまうこともあるのです。
本記事では、借金の時効について知りたい方に向けて、消滅時効が成立する要件や注意点、借金の時効以外に検討すべき借金問題の解決方法などについて解説します。
借金トラブルを解決するための参考にしてください。
| ※2020年4月1日に改正民法が施行され、時効期間、時効の更新、時効の完成猶予など、時効に関する条文も多く見直しがされました。本記事では、改正民法の内容に基づいて借金の消滅時効について解説しています。 |
借金の時効援用には注意が必要です。
時効の更新というルールがあり、裁判上の請求で判決が出た場合や強制執行などが実行された場合、権利の承認があった場合には時効がリセットされます。
したがって、たとえ借りたときから5年や10年が経っていたとしても、必ず時効が成立しているとはいえないのです。
また時効の援用に失敗すると、多額の返済が求められる可能性もあります。
時効援用を検討中の方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
下記のようなメリットがあります。
- 借金問題の最善の解決策を知れる
- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる
- 弁護士に依頼すべきか判断できる など
初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。
後払い/分割払い対応可能な弁護士事務所も多数掲載!

無料相談できる弁護士一覧
借金の消滅時効とは
借金などの債務には、「消滅時効」という時効が存在します。
この消滅時効には「更新」や「完成猶予」といったルールがあり、さまざまな事由で時効期間が延長されたり、時効成立が先送りされたりします。
まずは借金の時効の概要として、消滅時効の定義と時効期間、時効の起算点について解説します。
そもそも消滅時効とは
消滅時効とは、債権者が一定期間権利を行使しなかった場合に、その権利(債権)が消滅するという法律上の制度です。
消滅時効の対象としては「債権」と「債権・所有権以外の財産権」の2つがあります。
詳細については民法166条で規定されており、消滅時効のカウントは、権利行使ができる時点や、権利行使ができると認識した時点によって異なります。
カウントが始まると、一定の期間が経過したあとに、消滅時効が成立します。
借金の時効期間
借金の時効期間については、2020年4月1日の民法改正後、以下のようなルールが適用されています。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
以前であれば、借金の時効期間は借入先によって異なっており、「業者から借りた場合は5年」「個人から借りた場合は10年」と定められていました。
しかし、民法改正により、個人から借りた借金についても「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年」という時効期間が導入されました。
このため、借金の時効期間は、借入先にかかわらず「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年」または「権利を行使できるときから10年」と定められています。
借金の時効の起算点
借金の時効の起算点とは、消滅時効のカウントが始まる時点を指します。
そして、借金の時効の起算点は、借金の返済期日と定められています。
例えば、借金の返済期日が令和6年10月31日と設定されていた場合、令和6年10月31日が時効の起算点となります(なお、期間は令和6年11月1日から計算します(民法第140条))。
この日付を基準として、5年または10年の時効期間が経過することで、消滅時効が成立します。
借金の時効が成立するための要件
時効期間が経過するのを待っているだけでは、借金の時効は成立しません。
なぜなら、時効の成立には、ほかにも満たすべきいくつかの要件があるからです。
ここでは、借金の時効が成立するための要件について確認していきます。
時効に必要な期間を経過している
すでに述べたとおり、借金の時効が成立するためには、必要な時効期間が経過している必要があります。
通常であれば、債権者が権利を行使できることを知った時点から5年、または権利を行使できる時点から10年経過していることが、時効の成立には欠かせません。
時効が更新されていない
時効が更新されていないことについても、時効が成立するためには大切です。
なぜなら、時効が更新されていた場合、経過していた時効期間が再びゼロからのカウントとなるからです。
時効の更新には、大きく分けて3つのパターンがあります。
- 裁判上の請求により判決が確定した場合
- 強制執行などが実行された場合
- 権利の承認がなされた場合
裁判上の請求により判決が確定した場合
時効の更新事由の1つ目が、民事訴訟にて判決が確定した場合や、和解で終了した場合などです。
民法第147条2項では、確定判決または確定判決と同等の効力を有するものによって権利が確定したときには、時効は訴訟や調停などが終了してから新たに進行を始めると規定されています。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
強制執行などが実行された場合
時効の更新事由の2つ目が、強制執行や担保権などが実行された場合です。
民法第148条2項では、強制執行などの事由が終了したときから新たに時効の進行を始めると規定されています。
強制執行とは、国が強制的に債務者の財産を押さえて、債権の回収をはかる手続きのことをいいます。
財産の差し押さえなどがあった場合にも時効が更新されるのです。
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
権利の承認がなされた場合
時効の更新事由の3つ目が、権利の承認がされた場合です。
民法第152条では、時効は、権利の承認があったときは、そのときから新たに進行を始めると規定されています。
権利の承認とは、時効期間の満了までに、債務者が債権者に対して権利の存在を認めることを意味します。
例えば、借金の一部を返済した場合や、「借金を支払います」と認めた場合のほか、減額や支払い猶予に関する交渉をした場合なども権利の承認に該当し、時効が更新されるのです。
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
これらいずれかのパターンに当てはまると、時効が成立しません。
そのため、時効が更新されていないか、確認する必要があるでしょう。
時効の完成が猶予されていない
時効の完成猶予とは、時効が完成しないように時効期間のカウントを一時的にストップ(猶予)させる仕組みのことです。
例えば、裁判上の請求や強制執行などに関する条文には、「裁判上の請求が終了するまでの間は、時効は完成しない」などと規定されています。
この仕組みは、2020年の民法改正によって導入されたもので、以下のような事由において、時効の完成が猶予される期間が定められています。
| 完成猶予事由 | 猶予期間 | 条文 |
|---|---|---|
| 裁判上の請求など | その事由が終了するまで (取り下げなどから6ヵ月) | 民法第147条 |
| 強制執行など | その事由が終了するまで (取り下げなどから6ヵ月) | 民法第148条 |
| 仮差し押さえ、仮処分など | その事由が終了してから6ヵ月 | 民法第149条 |
| 催告 | 催告から6ヵ月 | 民法第150条 |
| 天災などで裁判上の請求が不可 | 障害が消えてから3ヵ月 | 民法第161条 |
本来であれば、時効期間が経過していると思っても、完成猶予事由に該当する場合、時効期間が猶予されることになります。
したがって、時効の完成が猶予されていないか確認することが、時効の成立には必要です。
時効の援用をおこなっている
これまで説明した時効が成立する要件を満たしていたとしても、借金の返済義務が自動的になくなるわけではありません。
なぜなら、消滅時効が完成したことを最後に債権者に対して主張しなければならないからです。
民法第145条では「当事者が援用をしなければ、裁判所は時効による裁判をすることができない」と規定しています。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
そのため、時効を成立させるためには、このような時効の援用をおこなっている必要があるのです。
借金の時効を主張するときに注意すべきこと
借金の時効成立を主張する際は、以下の点に注意する必要があります。
それぞれについて詳しく確認しましょう。
- 借金の時効が成立する可能性は低い
- 時効が完成したあとに債務を承認する行為
- 消滅時効の援用に失敗すると多額の返済が求められる可能性もある
- 時効を援用しても事故情報が残る場合がある
借金の時効が成立する可能性は低い
借金の時効を成立させるには、「債権者が権利を行使できると知ったときから5年間行使しないとき」または「権利を行使できるときから10年間行使しないとき」のいずれかに該当している必要があります。
しかし、時効の更新により、裁判上の請求で判決が出た場合・強制執行などが実行された場合・権利の承認があった場合などは、時効がリセットされます。
そのため、そもそも時効の成立を達成すること自体が難しく、借金を放置して時効になる可能性は低いといえるでしょう。
債権名義が取られている場合は特に注意
借金の時効期間は前述のとおりですが、債権者が債務名義を取得している場合には時効期間が長くなります。
民法第169条では「確定判決や確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期限は10年とする」と規定されています。
つまり、確定判決・和解調書・調停調書・仮執行宣言付き支払い督促といった債務名義を取得された場合は、その後10年間はいつでも財産の差し押さえが可能な状態になってしまうということです。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
時効が完成したあとに債務を承認する行為
時効が完成したとしても、借金の一部を返済したり、借金の存在を認めるような発言をすると、債務を承認する行為に該当します。
こうなると、完成した時効を債権者に主張する「時効の援用」ができなくなります。
その結果、たとえ時効が完成していたとしても、消滅時効を理由に借金の返済義務をのがれることが難しくなるでしょう。
したがって、時効が完成している場合には、借金の返済を請求されたとしても、その債務を認めるような行為は避けなければなりません。
時効の援用に失敗すると多額の返済が求められる可能性もある
消滅時効の援用をする際、誤って債務の存在を承認してしまうケースもあります。
その場合には、通常の返済金額に加えて、遅延損害金も付加されて請求されることになります。
借入額によって変動しますが、借入額が100万円以上の場合遅延損害金の上限利率は年21.9%と定められています(利息制限法)。
そのため、例えば100万円の借金がある場合には、1年間で21万9,000円の遅延損害金が発生することになるのです。
また、たとえ分割払いで契約していても、一括払いで請求されるおそれもあります。
借金の額にもよりますが、多額の返済を求められる可能性があることに注意しましょう。
時効を援用しても事故情報が残る場合がある
借金の時効を主張したとしても、信用情報機関の対応や基準によっては、事故情報が一定期間残り続けることがあります。
そのため、時効を援用したとしても、新たにローンを組んだり、クレジットカードを発行したりすることが、引き続き難しい場合があるのです。
通常、長期間にわたる借金の滞納は、5年程度ブラックリストに登録されるようです。
このため、時効を援用したからといって、すぐに事故情報が抹消されるとは限らないことに注意する必要があるでしょう。
借金の時効以外に検討すべき解決方法
借金の時効成立が期待できない場合は、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理を検討しましょう。
債務整理が成功すれば、借金の減額・免除や返済期間そのものを延長できます。
多重債務や収入減少などで借金返済が苦しい方は、以下の債務整理の方法が特に有効です。
任意整理
任意整理とは、返済額の減額や支払い期間の猶予獲得などを目指して、金融機関などの債権者と直接交渉する手続きのことです。
ほかの債務整理に比べて、迅速な解決が目指せることや、身近な人に気付かれにくいことがメリットです。
ただし、債務者が債権者と直接交渉するのは難しいため、弁護士に交渉対応を依頼するのが一般的でしょう。
個人再生
個人再生とは、借金の大幅な減額を目指して、裁判所に申し立てる手続きのことです。
「借金総額が5,000万円未満であること」「継続的な収入が見込めること」などの利用条件はありますが、最大で返済額を10分の1まで減らすことができます。
また、持ち家などの財産を手元に残せる可能性が高いこともメリットです。
自己破産
自己破産とは、全ての借金の免除を目指して、裁判所に申し立てる手続きのことです。
「一定の財産の処分が必要」「官報に掲載される」などのデメリットはありますが、借金の返済義務がなくなるため、人生の再スタートを切れるという大きなメリットがあります。
なお、自己破産が認められないケースもあるので、注意が必要です。
さいごに|借金に悩んでいるなら弁護士に依頼するのがおすすめ
借金の消滅時効は、判決などが確定した場合・強制執行が実行された場合・権利が承認された場合など、さまざまな事由によって延長されます。
そのため、借金の時効が成立する可能性は低く、自分ではすでに時効が成立していると思っていても「実はまだ成立していなかった」ということもあります。
時効が成立しているかどうかを知ったうえで、問題解決に向けて動きたいのであれば、弁護士に依頼するのがおすすめです。
ベンナビ債務整理では「都道府県」と「相談内容」を選択するだけで、相談可能な法律事務所を一括検索できます。
まずは、ベンナビ債務整理から初回無料相談に対応している法律事務所を見つけて、話を聞いてみるとよいでしょう。
借金の時効援用には注意が必要です。
時効の更新というルールがあり、裁判上の請求で判決が出た場合や強制執行などが実行された場合、権利の承認があった場合には時効がリセットされます。
したがって、たとえ借りたときから5年や10年が経っていたとしても、必ず時効が成立しているとはいえないのです。
また時効の援用に失敗すると、多額の返済が求められる可能性もあります。
時効援用を検討中の方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
下記のようなメリットがあります。
- 借金問題の最善の解決策を知れる
- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる
- 弁護士に依頼すべきか判断できる など
初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。
後払い/分割払い対応可能な弁護士事務所も多数掲載!

無料相談できる弁護士一覧