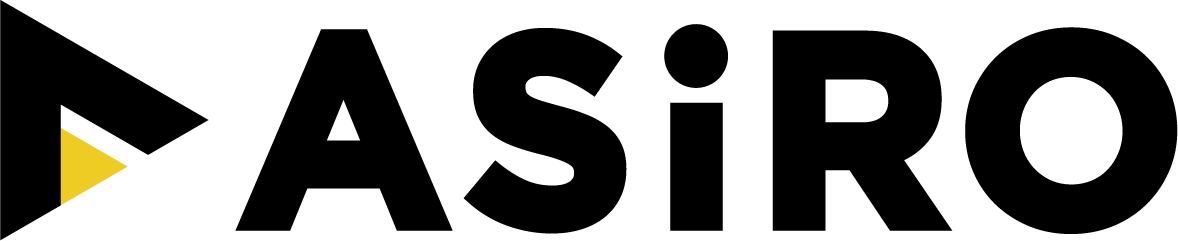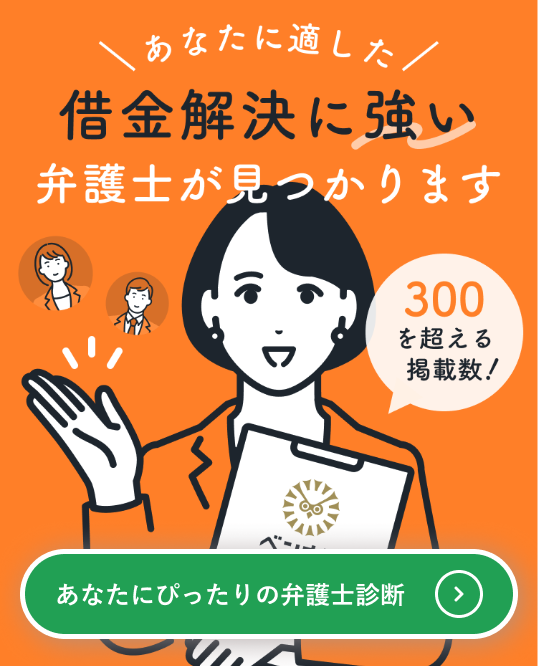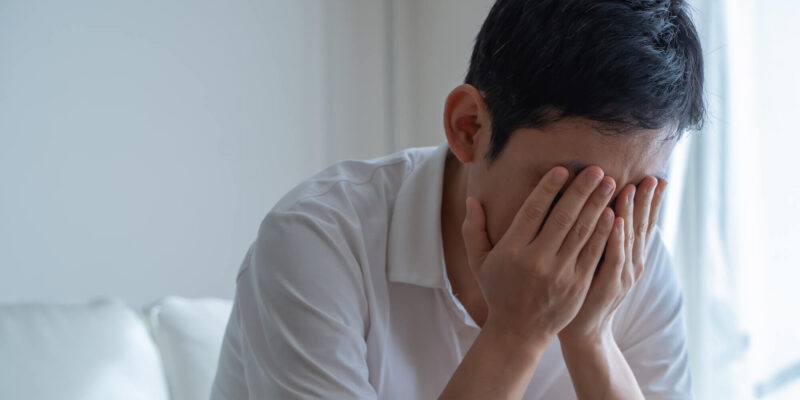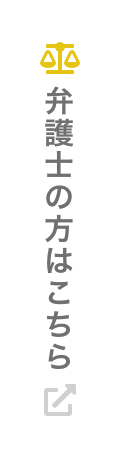「連帯保証人」や「保証人」などの言葉を聞いたことがあっても、どのような違いがあるのかわからない方も多いでしょう。
また、主債務者が債務を返済できなくなった場合、連帯保証人・保証人にどのような影響があるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、連帯保証人と保証人の違い、主債務者が債務整理をした場合の影響について解説します。
両者の違いについて詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
連帯保証人と保証人の3つの違い
連帯保証人と保証人の違いは、主に3つあります。
| 連帯保証人 | 保証人 | |
| 催告の抗弁権 | なし | あり |
| 検索の抗弁権 | なし | あり |
| 分別の利益 | なし | あり |
それぞれの違いについて、以下で詳しく解説します。
1.催告の抗弁権の有無|先に主債務者へ請求するよう求められるか否か
催告の抗弁権とは、債権者が債務の返済を求めてきたときに、主債務者に請求するよう主張できる権利のことです。
保証人には催告の抗弁権があるので、債権者がいきなり返済を請求してきたら「先に主債務者に請求してください」と求めることができるのです。
しかし、催告の抗弁権がない連帯保証人は、返済を求められたら拒否することはできません。
2.検索の抗弁権の有無|先に主債務者の財産を差し押さえるよう求められるか否か
検索の抗弁権は、返済できるほどの財産があるにもかかわらず、主債務者が支払いを拒否したときに、主債務者の財産を差し押さえるよう主張できる権利です。
主債務者が返済を拒否すると保証人や連帯保証人に返済の請求がされますが、保証人には検索の抗弁権があるため、主債務者の財産の差し押さえを求め、返済を免れることができます。
一方、連帯保証人には検索の抗弁権がないので、たとえ主債務者に十分な財産があったとしても、請求に応じなければなりません。
3.分別の利益の有無|主債務者の債務を、他保証人と分担できるか否か
分別の利益とは、保証人が複数人いる場合に、保証人の数で割った金額のみを返済すればよいことを指します。
たとえば、借金額が500万円で保証人が5人の場合、保証人は1人あたり100万円を返済すれば問題ありません。
しかし、連帯保証人の場合は分別の利益がないため、全員が500万円の返済義務を負います。
連帯保証人が複数人いても、全員が借金の全額を返済しなければならないのです。
2020年の民法改正で連帯保証人も極度額の設定が可能に!
連帯保証人は保証人に比べて重い責任が課され、ある日突然高額な借金を負うことにもなりかねません。
そこで、2020年の民法改正により、根保証契約において個人の連帯保証人に極度額(返済限度額)が設けられることになりました。
根保証契約とは、継続的に発生する不特定の債務を保証する契約のことです。
契約時点ではどのくらいの債務が発生するかわからない場合に、将来発生する債務もまとめて保証するケースを指します。
根保証契約は契約時点で債務額が確定しないため、連帯保証人が想像以上に高額な債務を背負うおそれがあります。
そこで、契約時に極度額を定めることで、連帯保証人のリスクや責任を軽減することとしたのです。
この改正により、連帯保証人は借金全額ではなく、契約時に取り決めた極度額を返済すればよいことになりました。
契約書などに「極度額は◯◯万円」と明記しなければ、その根保証契約は無効となるので注意しましょう。
債務者が債務整理をした場合の連帯保証人や保証人の違い
借金を返済できなくなった場合、主債務者は債務整理によって借金問題の解決を図ることがあります。
債務整理には以下の3つがあります。
- 自己破産:借金を免除してもらう
- 個人再生:借金の一部を免除して残額の支払いを猶予してもらう
- 任意整理:借金の毎月の返済額を減らす
債務整理をおこなった場合、主債務者の借金の一部または全額が免除されることになりますが、保証人や連帯保証人にはどのような影響があるのでしょうか。
ここでは、主債務者が債務整理をおこなった場合の、連帯保証人や保証人への影響について解説します。
主債務者が債務整理をしたときの保証人・連帯保証人に対する影響は原則変わらない
主債務者が債務整理をすると、免除された借金を保証人や連帯保証人が代わりに返済することになります。
主債務者の借金が免除されたからといって、保証人・連帯保証人の返済義務がなくなるわけではないので注意しましょう。
保証人・連帯保証人のいずれも支払い義務を負うので、影響は原則同じであるといえます。
ほかにも保証人がいる場合、返済しなければならない額には差が出る
保証人が複数人いる場合、保証人と連帯保証人とでは支払額に差が出る可能性があります。
保証人には分別の利益があるため、借金額を保証人の数で割った金額のみを返済すれば問題ありません。
しかし、連帯保証人の場合は分別の利益がないので、保証人が何人いても全員が借金の全額を支払う必要があります。
そのため、保証人が複数人いる場合は、連帯保証人のほうが保証人よりも返済額が大きくなってしまうでしょう。
債務整理と連帯保証人、保証人への影響
ここでは、自己破産・個人再生・任意整理のそれぞれのケースにおける、保証人・連帯保証人への影響を確認しましょう。
自己破産をした場合|債権者から一括請求を受ける
主債務者が自己破産をした場合、借金の全額を保証人・連帯保証人が肩代わりしなければなりません。
支払いは、原則として一括でおこなう必要があります。
分割払いを交渉することも可能ですが、認められる可能性は低いでしょう。
返済が難しい場合は、保証人・連帯保証人自身も債務整理を検討する必要があります。
個人再生をした場合|債権者から一括請求を受ける
主債務者が個人再生をおこなった場合、減額された分を保証人・連帯保証人が代わりに返済する必要があります。
たとえば、個人再生によって300万円の借金が50万円に減額された場合、減額分の250万円を保証人・連帯保証人が肩代わりしなければなりません。
保証人には分別の利益があるため、保証人の数で按分した金額のみ支払えば問題ありませんが、連帯保証人には分別の利益が認められないため、全員が減額分の全額を返済する義務があります。
任意整理をした場合|迷惑をかけずに済むケースも
任意整理は、債務整理のなかで保証人・連帯保証人への影響が最も小さいといえます。
任意整理では、任意整理をする借金・しない借金を個別に選ぶことが可能です。
そのため、保証人がついていない借金のみを任意整理すれば、保証人が代わりに返済義務を負うことはありません。
仮に保証人つきの借金を任意整理したとしても、保証人・連帯保証人は分割で返済できる可能性があります。
自己破産や個人再生の場合は、保証人は原則一括で返済する必要がありますが、任意整理なら分割払いに応じてもらえる可能性が比較的高いのです。
保証人・連帯保証人への影響をできる限り少なくしたいなら、任意整理を検討しましょう。
保証人や連帯保証人から外れることはできる?
保証人・連帯保証人から外れることは原則できません。
保証契約は保証人・連帯保証人と債権者との契約なので、債権者の合意がなければ一方的に解除することはできないのです。
ただし、以下のケースに該当する場合は解除できることがあります。
- 無断で保証人・連帯保証人にされた
- 代わりの連帯保証人や担保を準備できる
- 残りの借金額が少ない
- 借金の時効が成立している
- 債権者から解除の同意がある
上記のケースに該当するかわからない場合や、保証人から外れる方法を知りたい場合は、弁護士に相談しましょう。
連帯保証人についてよくある質問
ここからは、連帯保証人についてよくある質問をまとめています。
似たような疑問をお持ちの方は、ここで解消しておきましょう。
債権者から債務者のかわりに請求された場合、連帯保証人は支払い拒否できませんか?
連帯保証人が返済の請求を受けた場合、支払いを拒否することはできません。
連帯保証人には催告の抗弁権がないため「主債務者に請求してください」と主張することができないのです。
ただし、例外として主債務者に騙されて連帯保証人になった場合や、無断で連帯保証契約を結ばれた場合は、支払いを拒否することができます。
連帯保証契約は、連帯保証人と債権者の合意があってはじめて成立するので、連帯保証人の同意がない状態で交わした契約は無効です。
同意なく連帯保証契約を結ばれ、支払いを請求されたら「私は同意していません」と契約の効力がないことを主張しましょう。
この場合、多くのケースで裁判に発展するので、身に覚えのない連帯保証契約で支払いを請求されたらまずは弁護士に相談するのがおすすめです。
勝手に連帯保証人にさせられたらどうしたらよいですか?
無断で連帯保証人にさせられた場合、その保証契約は無効になるので、支払いに応じる必要はありません。
返済を請求されたら、契約が無効であることを債権者に主張しましょう。
契約が無効であることを証明する方法は、以下の2つです。
- 債権者に内容証明郵便を送る
契約締結の経緯をまったく知らない旨を記載した書面を債権者に送付します。
その後の対応は、債権者の返答をみて検討しましょう。
- 訴訟提起されることを見越して反論材料を集める
債権者が訴訟提起してきた場合に適切に対応できるよう、契約が無効であることを証明する資料をできる限り収集しておきましょう。
上記の方法で対処することで、契約の無効を証明でき、返済義務を逃れられる可能性があります。
ただし、勝手に連帯保証人にされたとしても「表見代理」が成立する場合は、支払いに応じなければなりません。
表見代理とは、債権者が連帯保証人の同意があると信じても仕方がない理由がある場合に成立する制度です。
表見代理が成立した場合、たとえ勝手に連帯保証人にさせられた場合でも、返済の義務を負うことになります。
自分のケースで表見代理が成立するのか、契約の無効を主張できるのかについて、一般の方が自分で判断するのは難しいので、まず弁護士に相談しましょう。
連帯保証人になってはいけませんか?
連帯保証人には大きなリスクが伴うので、慎重に検討しましょう。
連帯保証人は、保証人のように催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益などが認められていません。
主債務者が債務を返済できなくなった場合、真っ先に連帯保証人に請求がなされ、借金の全額を支払う義務を負います。
契約によっては、借金の元金だけでなく、利息や違約金、遅延損害金などの支払いも求められることがあり、思いがけず高額な債務を背負うことにもなりかねません。
「連帯保証人になってほしい」と頼まれた場合は、上記のリスクを考慮して判断しましょう。
さいごに|保証人・連帯保証人が関わる債務整理については弁護士へ相談を!
主債務者が債務を返済できず債務整理をおこなった場合、保証人・連帯保証人は借金の全額または一部を肩代わりしなければなりません。
借金が高額な場合、保証人・連帯保証人の生活に大きな悪影響を及ぼすおそれがあるでしょう。
保証人・連帯保証人が関わる債務整理をおこなう場合、まずは弁護士に相談してください。
弁護士に相談すれば、保証人・連帯保証人への影響を最低限に抑える方法を一緒に検討することができます。
適切な方法で借金問題を解決するためにも、弁護士の力を借りましょう。